事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁)
2.2.第三者機関等の関与に関する基本的考え方
|
【考え方等】
a. 基本的事項に、事業者が項目及び手法の選定に当たっては、必要に応じ専門家等の助言を受けながら客観的かつ科学的な検討を行う必要があることを示している。環境影響評価の内容を受けて実施する事後調査・再評価においても、専門家等で構成される第三機関等の関与のもとで実施することが適切と考えられる(「図2 第三者機関等の関与の考え方」の(1)を参照)。
b. 地方公共団体等の助言・指導のもとで、事業者が第三者機関等を組織し、費用負担を含めて運営する。当該機関は、第三者的な立場で事後調査・再評価に関する協議を行うものとする。
c. 事業者が行った事後調査・再評価の結果を踏まえて、予測・評価内容が妥当であったか、対象項目・調査手法の選定から予測・評価に至るまでの過程が適正に実施されたかどうかを、技術的、総合的に評価することが第三者機関等の役割である。また、第三者機関等は、その協議内容等について社会に向けた説明を行うとともに、協議を踏まえて環境保全の観点から事業者を助言・指導することが望ましい。
d. 第三者機関等において、予測・評価、事後調査に係る技術事項についてより専門的な検討を行うために、必要に応じて研究者・技術者等で構成する作業部会を組織することも想定される。
e. 事後調査及び再評価の実施にあたっては、事業者が、第三者機関等、地方公共団体、民間調査機関(環境コンサルタント)等と密接にコミュニケーションを図りながら進めることが適切と考えられる。さらに、より適切な社会的合意形成を図るためには、事業者がより広い利害関係者(事業者、地方公共団体、専門家、住民、環境NGO等)でラウンドテーブルを構成し、協議する等の取り組みが期待される。また、事後調査結果等をより効果的に(広範囲かつ短時間に)周知する観点からも、ラウンドテーブルにおいて一括して説明することは有効な手段の一つと考えられる(「図2 第三者機関等の関与の考え方」の(2)を参照)。
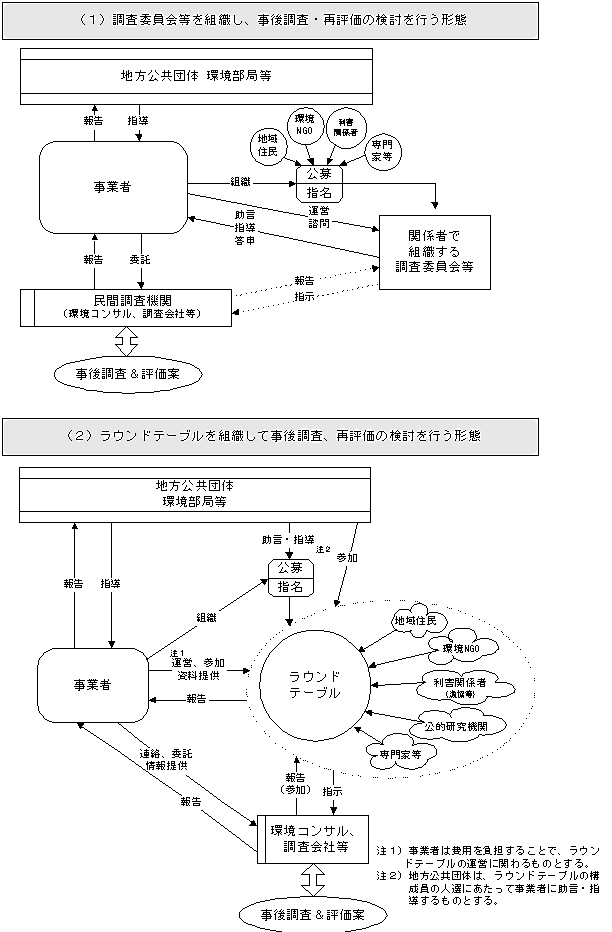
図2 第三者機関等の関与の考え方