事後調査・再評価(レビュー)マニュアル(平成11年3月 環境庁)
2.事後調査、再評価(レビュー)の基本的な考え方
2.1.事後調査・再評価の定義~
| (1) |
「事後調査」とは、当該事業の環境影響評価に係る選定項目としたもののうち、予測の不確実性が大きい場合、若しくは効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講じる場合等において、事業者が工事中及び供用後の環境の状態を把握する調査をいう。なお、事後調査結果から対象事業に起因する環境影響が明らかになった場合の対応の方針を事業者が予め示すことが重要である。 |
| (2) | 「再評価(レビュー)」とは、予測の不確実性の大きい事業等について、事業の進捗の段階に応じて得られた新たな事後調査結果等を用いて影響の再予測を行い、予測・評価結果が妥当な内容であったか、項目選定から予測・評価に至るまでの過程が適切であったかどうか、さらに、講じた環境保全措置が適切かつ十分であったかどうかについて事業者が検証を行う取り組みをいう。 |
【考え方等】
(1)事後調査の考え方
a. 基本的事項(平成9年環境庁告示第87号)において、「(環境影響評価の)選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査」として規定しており、事後調査によって、事業の実施に伴う環境の変化を事業者が適切に把握することを求めている。
b. 環境への影響の重大性の判断については、事業者がアセス手続きにおける住民等の意見を勘案し責任をもって行うべき事項である。
c. 「確実性をもって」、「影響はない(少ない)」との評価により、事後調査の対象としなかった項目についても、環境保全措置によって問題を軽減している場合等には、事業者は必要に応じて継続的な監視(モニタリング)調査を検討する必要がある。調査の方法としては、事業者の調査を基本とするが、国及び地方公共団体等のモニタリングデータ等が利用可能な場合には、これらを適切に活用するものとする。
d. 基本的事項において「事後調査の結果により著しい環境影響が明らかとなった場合等の対応の方針、・・・を明らかにすること」を規定していることから、環境影響の内容及びその程度(例えば、汚濁拡散防止膜が適切に設置されていないために、水質汚濁の範囲が拡大する)に応じた措置を講じる必要がある。したがって、事業者は環境影響が著しい場合の対応を事前に検討しておくとともに、係る事態が判明した場合には地方公共団体等と相談しながら迅速に対応することが求められる。
(2)再評価(レビュー)の考え方
a. 「再評価」は、後述するように、基本として事業者が行う。したがって、事後調査により把握される工事中及び供用後の環境の状況をもとに、「当該事業に関してなされた予測・評価内容が妥当なものか、調査項目・手法等の選定から予測・評価に至る過程が適切であったか、さらに講じた環境保全措置が適切かつ十分であったか等を適切な時期に再予測し、検証すること」が第一の目的であり、事業者はこの結果に基づいて必要な措置を講じなければならない。また、事業者は、事後調査の結果だけでなく、予測・評価あるいは環境保全措置に関する技術情報等についても適切な形で公表する必要がある。
b. 予測手法に限界がある場合、地形変化が大きい等予測の前提条件の設定に不確実性が大きい場合等においては、これまでにも環境庁長官意見として、事後の再評価を求めている事例が多い。特に、事後において、予測・評価の前提条件(例えば下水処理場の整備やバイパスの整備等)が大きく変わっている場合(例えばこれらの整備が遅れている)には、事業者は、前提条件を現実に合わせて変更し、再予測(再現計算)を実施する必要がある。この再予測結果と事後調査結果とを比較し、当該事業の影響を検討することが適切と考えられる。
c. 「予測・評価内容のみならず、環境影響評価過程全体が適切になされたかどうかを事後に判断する」ということも再評価の役割と考えられる。しかしこれは、事業者の責務というよりはむしろ環境影響評価法の適切な運用の観点から、環境庁や地方公共団体環境部局が事業者の実施した再評価結果を包含する形で取り組むことが適切であり、一種の監査に相当する業務として行政が行う再評価となる。「事後調査」から「再評価」に至る過程は下図のとおりである。
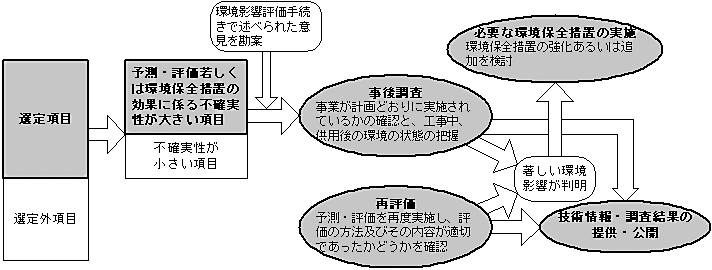
図1 事後調査から再評価に至る過程