平成13年度 第1回水環境分科会
資料2-6
1-2-4 地下水等のケーススタディⅡ(面整備事業)
1) 地域概況調査
地域概況調査によって把握される,ケーススタディ地域の概況や特性について,次のように想定した。
(1) 自然的状況
[1] 地形・地質の状況
造成地周辺は,丘陵の斜面部にあたり,地盤標高は40~100mを示す。
地層構成は表 1.25のような状況にあり,洪積層の砂泥互層のうち,洪積砂質土層(および挟在する砂礫層)が地下水帯水層となっていると考えられる。
表 1.25 事業対象地の地質層序表
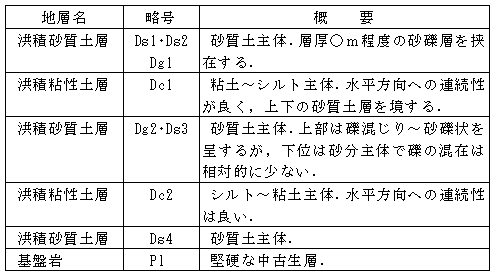
[2] 河川等の状況
事業計画地を含む丘陵一帯には,明瞭な谷地形は認められず,河川・沢は確認されない。
また,計画地西端部から約300m西方にあたる丘陵斜面の末端部には小規模な谷地形が認められ,合計で400~500・min程度の湧水量を有する湧水群が存在する。
[3] 土壌・地盤の状況
事業地周辺では,土壌汚染や地盤沈下は確認されていない。また,急傾斜地や地すべり防止区域は設定されていない。
[4] 地下水の状況
(地下水帯水層)
地形・地質状況から,地下水帯水層は洪積砂質土層と想定される。
(地下水位)
Ds1~Ds2・Dg1層の地下水:GL-5~10m(不圧地下水)
Ds3~Ds4・Dg2層の地下水:GL-5~10m(被圧地下水)
(地下水流動)
各層とも,全体として東から西に向かって傾斜する分布を示し,地下水はこれらの帯水層を流動することから,大局的には東→西方向の地下水流動が想定される。
なお,丘陵斜面の末端付近に小規模な谷地形があり,湧水が認められることから,この湧水に向かっての地下水流動も想定される。
(地下水の水質)
△△湧水群については,○○市環境課において飲料水項目の水質分析が実施されているが,一般細菌数および大腸菌群の項目について「飲用不適」との結果が得られている。
[5] 降水・蒸発散の状況
事業地周辺における平年降水量は1,500mmであり,ソーンスウェイトの式から求めた年間の蒸発散量は700mmである。したがって,事業地周辺に対する年間の実効雨量は 1,500-700=800mm となる(気象庁○○アメダス観測所の日降水量・日平均気温観測値過去20年分の収集・整理による)。
[6] その他
事業地一帯は雑木林であり,地下水や地表水と密接に関係する水生動植物等は確認されない。
ただし,丘陵末端部の湧水群付近とその流出水路一帯には,かつて水生動植物の生育が確認されたとの資料がある。
(2) 社会的状況
[1] 人口・産業の状況
事業地周辺は,人口○○万人の都市郊外部にあたり,近年,都市のベッドタウンとして開発が進められている。
事業地を含む丘陵一帯は未開発であるが,今後,本事業のような開発計画が進められることが考えられる。丘陵と接する沖積低地部は水田地帯であり,一部には小規模な集落が点在する状況にある。
[2] 土地利用の状況
事業計画地を含む丘陵一帯は,広葉樹・針葉樹が雑多に生育する雑木林である。
また,丘陵と接する沖積低地部は,一部に点在する集落付近を除いて,主に水田として利用されている。
[3] 地下水・地表水の利用状況
地元○○市における資料から,下記の状況を把握した。
生活用水)
近年の都市化に伴って上水道が整備されたが,それ以前に戸別に利用されていた井戸水源が数ヶ所に残存している。
その他)
工業用水,農業用水等の許認可を伴う利用は確認されていない。
なお,事業計画地西方の湧水群は「△△湧水群」として近隣地域で広く知られており,過去には周辺の生活用水源としても利用されていた経緯がある。現在は,親水公園として整備されているほか,農業用水(水田灌漑用水)の水源の一つとしても利用されている。
[4] 影響を受けやすい施設等の状況
既存資料に基づき,上水道・工業用水道等の水源井戸の有無について確認を行なったが,事業地近傍2km以内の範囲には,これらの水源は確認されなかった。
また,地下水・地表水に大きく依存する水生動植物や湿地等の分布がA湧水近傍に確認されたが,貴重種の生育は確認されなかった。
[5] 法令・基準の状況
事業区間周辺においては,特定の条例等の対象範囲は設定されておらず,水循環に係わる諸事項については,法令による環境基準(「地下水の水質汚濁に係る環境基準」,「排水基準」等)が適用される。
[6] その他
事業地周辺においては,既設の地下構造物や開発事業等,現時点で周辺の水循環に影響を与えているような施設・状況は確認されない。
2) 事業特性の設定(事業特性の把握)
(事業概要)
丘陵斜面を改変し,宅地を造成する。
造成範囲は,東西方向700m・南北方向1,000m の長方形の範囲であり,宅地および道路,緑地(公園)等として整備される。
なお,事業計画における面積比から,地表浸透量が現状の約43%に減少すると想定される。
(工事計画)
造成に際しては,重機による掘削,土工のほか,場合によって局所的な地盤改良工の実施が想定される。
3) 環境影響評価項目の選定
対象事業による地下水への影響を想定する際に,影響要因と環境要素との関係をわかりやすく示すため,マトリクスだけではなく,下記に示すような影響の伝達経路(影響フロー)も考慮に入れ,検討を行なった。
造成地の存在・供用および造成工事に係わる影響フローを図 1.35に,またこれらの影響マトリクスを表 1.26に,それぞれ示した。
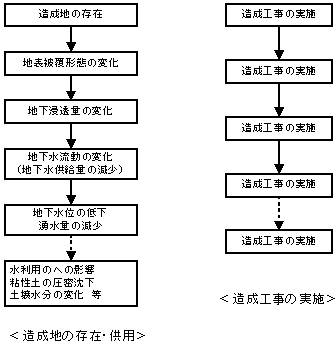
図 1.35 対象事業に係わる環境影響フロー
表 1.26 対象事業に係る影響マトリクス
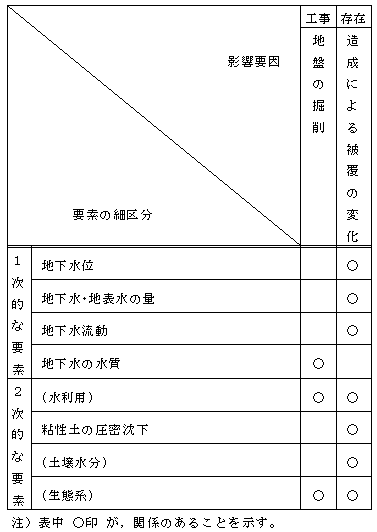
工事による影響については,地盤の掘削に伴う汚濁物質の発生が想定され,これによって地下水水質が変化する可能性があることから,これを環境要素として選定した。
また,造成後の存在・供用による影響については,被覆形態の変化に起因する浸透量の減少が想定され,これによって地下水流動の変化が生じ,湧水量の減少や地下水位の低下が生じる可能性があることから,これを環境要素として選定した。
4) 調査・予測手法の検討
(1) 調査・予測手法の検討の流れ
調査・予測手法の検討の流れを図 1.36~図 1.37に示す。
これらの検討にあたっては,先に整理した環境影響フローを踏まえるとともに,事業特性や地域特性,事業の実施による影響要因と環境要素に予想される影響について充分に留意し,適切な予測手法・調査手法の選定を行なうこととした。
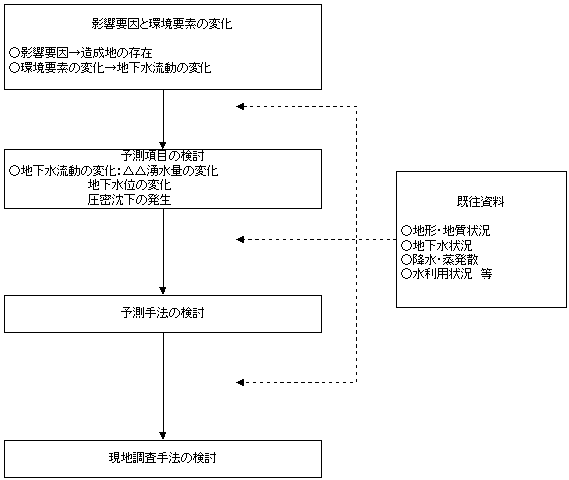
図 1.36 調査・予測手法の検討の流れ(造成地の存在)
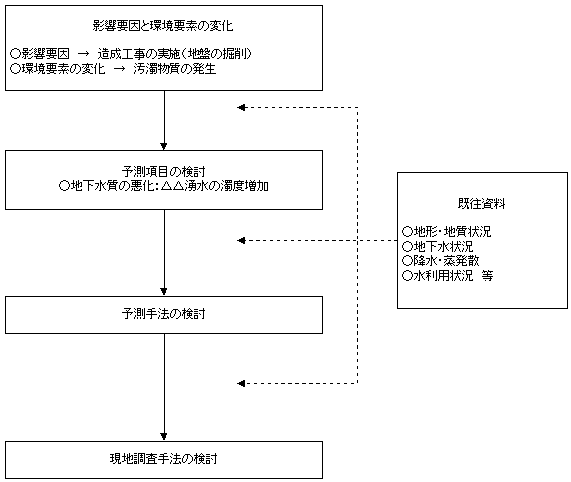
図 1.37 調査・予測手法の検討の流れ(造成工事の実施)
(2) 予測手法の検討
造成地の存在及び造成工事の実施による影響予測手法の検討内容について,表 1.27(PDFファイル7k)と表1.28(PDFファイル5k)に示す。
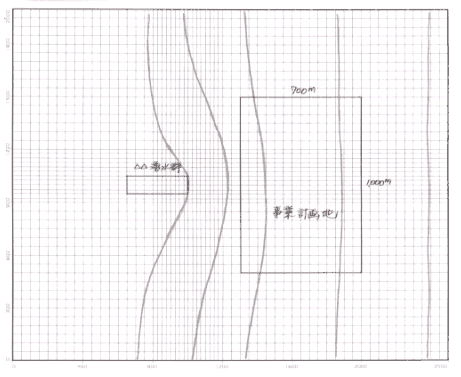
図 1.38 差分法による三次元解析の計算領域図
(3) 現地調査手法の検討
予測手法の検討の結果,予測手法として三次元解析を選定したことから,特に地質や地下水の状況について,より詳細な情報の入手が必要と判断された。
これに基づいて,表 1.29(PDFファイル25k)の通り,現地調査手法の検討を行なった。
(4) 調査結果・予測結果の概要
[1] 現地調査結果の概要
現地調査結果の概要を表 1.30(PDFファイル128k)に示す。
[2] 予測結果の概要
予測結果の概要を表 1.31~表 1.32(PDFファイル217k)に示す。
5) 評価の考え方
(1) 造成地の存在
回避・低減に係わる評価は,事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮を明らかにし,評価するものであり,造成地の形状や造成敷地内における回避・低減施設(例えば浸透施設)等について,複数案の比較検討結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討し,評価を行なう。
基準又は目標との整合に係わる評価の観点からは,地下水流動や湧水量・地下水位等について具体的な環境基準等は設定されていないため,周辺における水利用等に対する影響や既存構造物に対する影響等の観点から評価を行なう必要がある。
(2) 造成工事の実施
回避・低減に係わる評価は,事業者による環境影響の回避・低減への努力や配慮を明らかにし,評価するものであり,選定された工法や使用機械,影響防止対策等の工事計画において,複数案の比較検討結果や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討し,評価を行なう。
基準又は目標との整合に係わる評価の観点からは,ここで想定される濁り等の汚濁物質に関する具体的な環境基準は設定されていないため,周辺における水利用等に対する影響の観点から評価を行なう必要がある。