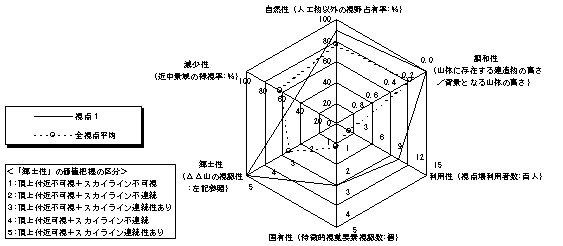平成13年度 第1回総合小委員会
III 調 査
III-1 眺望景観の把握
1.眺望景観の状態の把握
・図III-1に示すような作業を行い、調査・予測・評価の対象とする眺望景観を特定した。
|
図III-1 調査・予測・評価の対象とする眺望景観の特定に係る作業結果
・調査・予測・評価の対象として特定された眺望景観の状態の把握結果は、以下に整理するとおりである。
| № | [1] | 視点名称 | ○○ヶ丘 |
| <事業実施区域方向の現況写真> |
平成○年□月×日撮影 |
||
 |
|||
図III-2 眺望景観の状態把握結果
|
利用の状態 |
利用者数 |
不詳(統計データなし)。なお、利用者属性を考慮すれば、○○ヶ丘周辺*人口の1,031人(H.8.10)が視点の利用者数であると 考えられる。なお、○○ヶ丘は現段階において分譲・入居が概ね完了していることから、今後の利用者数(人口)増加は少ないと考え得る。 *:○○ヶ丘の含まれる○○町、○○ヶ丘二丁目の合計人口 |
|||||||
利用者属性 |
視点は団地内道路上であり、通過交通が生じないことから、利用の大半は団地内住民であり、外来利用者はほとんどないと考えられる。 |
||||||||
利用形態 |
日常的な風景観賞、あるいは道路通行者の通過型風景探勝。 |
||||||||
眺望の状態 |
眺望対象+
60°円錐(*)内の視野構成 |
△△山、○○山周辺の稜線、△△川沿いの水田 |
|||||||
空域 |
42% |
水域 |
0% |
||||||
樹林域 |
13% |
落葉広葉樹林、スギ人工林、竹林等 |
人工緑地 |
17% |
法面緑化地、民家の庭園木 |
||||
農地 |
18% |
主に水田 |
人工物 |
10% |
家屋、変電所、鉄道敷、鉄塔 |
||||
うち、近中景域の緑視率 |
46% |
||||||||
眺望方向・視野角 |
NNE-SSEの方位に約160゜の眺望が開け、そのほぼ中央に主眺望対象となる△△山方面の稜線が展開する。また、事業実施区域はENE-SSEの方位にわたって視認され、△△山方面と重複する。 |
||||||||
景観構成 |
近景 |
△△川沿いの谷戸地に形成された水田や小集落への俯瞰景とその背後の落葉広葉樹林に被われた低い斜面が主体となる。 |
|||||||
中景 |
事業実施区域一帯の樹林に被われた丘陵地が主体となり、視点からのスカイラインの一部を構成している。 |
||||||||
遠景 |
主眺望対象となる△△山方面稜線が主体となり、中景域を構成する稜線から連続するスカイラインを構成している。 |
||||||||
視認性解析 |
○○山~△△山方面稜線にかけて、あるいは事業実施区域北部稜線一帯、視点近傍の△△川及びその右岸斜面にまとまりのある可視領域が見られる。一方、事業実施区域南西部を中心とする一帯の可視頻度は低い傾向にある。なお、解析結果では北西方向にまとまりのある可視領域が広がるが、実際には視点付近の既存樹木や微地形により視認されることはない。 |
||||||||
*:60°円錐」について:人間が特定の対象を静止して眺める場合の視野は、通常60°の円錐にほぼ等しいとされる。
(参考:「新体系土木工学 59 土木景観計画」(1982 篠原修))
図III-3 眺望景観の状態把握結果(つづき)
2.眺望景観の価値の把握
・事業実施区域及びその周辺の特性をふまえ、重要性が高いと思われる眺望景観の認識項目を抽出し、各認識項目に対応する眺望景観の価値の状態を以下に示した。
№ |
[1] |
視点名称 | ○○ヶ丘 | ||||
 |
|||||||
| 認識項目 | 指標 | 指標値 | |||||
人工物以外の視野占有率(眺望方向を中心とする60°円錐内の全視野-当該視野内の人工物(%)) |
90% |
||||||
調和性 |
山体に存在する建造物の高さ/背景となる山体の高さ |
山体に建造物は存在しない(0.00) |
|||||
利用性 |
居住者人口+日最大来訪者数 |
1,031人 |
|||||
固有性 |
特徴的な視覚的要素の数 |
水田、○○山、△△山(計3) |
|||||
郷土性 |
地域のシンボルとして認識されている△△山の視認性 |
・ ・ |
山頂付近が視認できる:○ スカイラインの連続性がある:○ |
||||
近~中景域における斜面緑地の緑視率 (眺望方向を中心とする60°円錐内) |
46% |
||||||
|
|
|||||||
図III-4 眺望景観の価値の把握結果
III-2 囲繞景観の把握
1.景観区の区分
・事業実施区域及びその周辺の小水系・標高・傾斜区分、地形・地質調査の結果から得られた地形分類等の地形的要素と、植物調査の結果から得られた植生区分等の地被的要素、さらには視認性解析や現地踏査による目視観察結果等の情報を組み合わせ、景観的均質性や一体性を目安として、下図の通り景観区の区分を行った。
|
2-25図のみ |
図III-5 景観区の区分結果(例)
2.囲繞景観の状態の把握
・各景観区ごとの囲繞景観の「場の状態」「利用の状態」「眺めの状態」はそれぞれ下図の通りである。
|
2-28図のみ |
図III-6 囲繞景観の状態(場の状態)
|
2-28図のみ |
図III-7 囲繞景観の状態(利用の状態)
|
2-30図のみ |
図III-8 囲繞景観の状態(眺めの状態)
3.囲繞景観の価値の把握
・被験者を用いた計量心理学的手法(SD法)による実験結果と高い相関性が認められた囲繞景観の価値の認識項目に関する指標として、現地調査等に基づく妥当性の確認を行った上で表III-1に示す具体的指標を選定した。
・また、その指標に基づく価値把握の結果を以下の図III-9~9及び表III-2に示す。
表III-1 囲繞景観の価値の認識項目に関する指標の抽出結果
| 価値軸 | 重要性の高さが認められた認識項目 | 具体的指標 |
| 普遍価値 | 自然性 | 景観区内の平均樹高の高さ |
| 快適性 | 景観区内の植生単位の林床植生の粗密度 | |
| 固有価値 | 歴史性 | 景観区内の史跡の分布箇所数 |
| 郷土性 | 景観区内の地域住民に好まれる景観資源の分布箇所数 |
|
2-36 |
図III-9 囲繞景観の価値把握結果(普遍価値)
|
2-36 |
図III-10 囲繞景観の価値把握結果(固有価値)
表III-2 囲繞景観の価値把握結果の一覧
| 景観区№及び名称 |
普遍価値 | 固有価値 | ||||||||||||||||
| 自然性 | 快適性 | 歴史性 | 郷土性 | |||||||||||||||
| 植生単位の 平均樹高の構成 |
植生単位の 林床植生の粗密度 |
史跡分布数 |
ヒアリング調査で 抽出された景観要素数 |
|||||||||||||||
| ランク(*1)別 構成比(%) |
得 点 (*3) |
ランク(*2)別 構成比(%) |
得 点(*3) |
分布数 | 内 訳 |
要素数 | 具体名称 |
|||||||||||
| 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | |||||||||
| 尾根区 | 1 | 北部稜線コナラ林区 | 11 | 35 | 54 | 0 | 0 | 357 | 0 | 35 | 11 | 54 | 0 | 281 | 0 | 0 | ||
| 2 | 中部稜線植林区 | 50 | 1 | 45 | 0 | 4 | 392 | 0 | 0 | 53 | 45 | 1 | 252 | 0 | 0 | |||
| 3 | ××川上流区 | 84 | 5 | 11 | 0 | 0 | 472 | 0 | 2 | 89 | 9 | 0 | 293 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中部斜面混交林区 | 45 | 17 | 21 | 0 | 16 | 377 | 0 | 5 | 76 | 17 | 2 | 285 | 0 | 0 | |||
| 5 | 集落南部植林区 | 52 | 14 | 30 | 0 | 4 | 411 | 0 | 5 | 69 | 24 | 2 | 277 | 1 | 古墳 | 0 | ||
| 6 | 集落北部混交林区 | 21 | 45 | 32 | 2 | 0 | 384 | 0 | 18 | 78 | 3 | 0 | 314 | 2 | 窯跡 | 0 | ||
| 7 |
砂礫層アカマツ林区 |
10 |
7 |
82 |
0 |
0 |
326 |
5 |
12 |
83 |
0 |
0 |
321 |
11 |
窯跡(10) 城跡(1) |
0 |
||
| 8 | 造成跡草地区 | 0 | 7 | 20 | 56 | 17 | 216 | 2 | 18 | 32 | 47 | 1 | 273 | 0 | 0 | |||
| 9 | 上流植林区 | 7 | 20 | 67 | 2 | 5 | 323 | 0 | 14 | 35 | 49 | 2 | 262 | 2 | 窯跡(2) | 0 | ||
| 10 |
中流コナラ林区 |
8 |
41 |
48 |
0 |
3 |
350 |
0 |
44 |
53 |
1 |
2 |
340 |
2 |
窯跡(1) 古墳(1) |
0 |
||
| 11 | 下流マツ・コナラ林区 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 350 | 0 | 29 | 62 | 9 | 0 | 320 | 2 | 古墳(2) | 0 | ||
| 谷区 | 12 | □□川下流区 | 1 | 66 | 10 | 5 | 18 | 327 | 10 | 9 | 75 | 3 | 4 | 319 | 0 | 0 | ||
| 13 | □□川下流支沢区 | 3 | 8 | 81 | 5 | 2 | 306 | 1 | 45 | 51 | 2 | 0 | 346 | 2 | 窯跡 | 0 | ||
| 14 | ○○川合流区 | 3 | 34 | 15 | 24 | 24 | 266 | 0 | 24 | 51 | 11 | 14 | 285 | 0 | 0 | |||
| 15 | □□川中流区 | 18 | 52 | 8 | 2 | 20 | 346 | 5 | 3 | 88 | 0 | 4 | 306 | 0 | 0 | |||
| 16 | □□川中上流支沢区 | 0 | 35 | 59 | 6 | 0 | 330 | 0 | 24 | 72 | 3 | 0 | 321 | 0 | 0 | |||
| 17 | □□川中流集落口区 | 23 | 54 | 13 | 1 | 10 | 378 | 0 | 0 | 80 | 10 | 9 | 272 | 0 | 0 | |||
| 18 | 林道○□線植林区 | 78 | 10 | 6 | 1 | 4 | 457 | 0 | 2 | 89 | 6 | 4 | 288 | 0 | 0 | |||
| 19 |
○○集落地区 |
20 |
29 |
15 |
7 |
29 |
304 |
16 |
18 |
42 |
16 |
8 |
317 |
1 |
窯跡 |
7 |
○○集落、集落内の水田、集落内の民家、集落背後の二次林、神社、石仏、弘法堂 | |
| 20 | ××方面歩道区 | 0 | 82 | 12 | 3 | 3 | 372 | 0 | 18 | 77 | 3 | 1 | 313 | 0 | 0 | |||
| 21 | ○○川下流区 | 14 | 77 | 0 | 0 | 9 | 388 | 0 | 4 | 92 | 1 | 2 | 299 | 0 | 2 | ○○川の渓谷景観、滝 | ||
| 22 | ○○池区 | 16 | 52 | 2 | 7 | 22 | 333 | 20 | 9 | 69 | 1 | 2 | 345 | 0 | 2 | ○○池、池畔の落葉樹林 | ||
| 23 | ○○川中流区 | 33 | 24 | 32 | 5 | 6 | 373 | 0 | 8 | 57 | 31 | 4 | 268 | 2 | 窯跡 | 2 | ○○川の渓谷景観、集落跡 | |
| 24 | ○○川上流区 | 46 | 26 | 16 | 6 | 6 | 399 | 0 | 6 | 70 | 21 | 3 | 279 | 0 | 0 | |||
| 25 | ○○川上流支沢区 | 59 | 17 | 24 | 0 | 1 | 433 | 0 | 2 | 73 | 24 | 1 | 276 | 0 | 0 | |||
| 26 | ○○川最上流区 | 57 | 9 | 8 | 15 | 12 | 384 | 0 | 15 | 69 | 11 | 5 | 294 | 3 | 窯跡 | 0 | ||
| 27 | ○○川谷頭斜面区 | 19 | 1 | 67 | 13 | 0 | 326 | 0 | 13 | 20 | 67 | 0 | 245 | 0 | 0 | |||
| 28 | ××川中流植林区 | 84 | 2 | 0 | 9 | 6 | 450 | 0 | 11 | 84 | 0 | 6 | 299 | 0 | 0 | |||
| 29 | ××川上流区 | 67 | 33 | 0 | 0 | 0 | 467 | 0 | 33 | 67 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | |||
ランク |
*1:植生単位の平均樹高 |
*2:植生単位の林床植生の粗密度 |
5 |
20m~ |
低木層が未発達または刈払われている、開放水面、自然草地、耕作地 |
4 |
15~19m |
低木層は未発達であるが常緑樹が多い |
3 |
10~14m |
低木層がやや繁茂している |
2 |
5~ 9m |
低木層が繁茂している、草丈の高い草地 |
1 |
0~ 4m |
造成裸地、人工草地 |
*3:Σ(ランクの数値×各ランクの構成比)