平成14年度第1回検討会
資料 5
1章
2-2 騒音・振動・低周波音
「1 総論」においては、騒音分野の環境影響評価を進めるに当たっての主に環境保全措置・評価・事後調査の進め方についての基本的な考え方について示した。
ケーススタディでは、環境影響評価における様々なケースを想定し、環境保全措置の検討の考え方や事後調査の方法等について検討し、明らかにした。
なお、このケーススタディは現実の情報によるものではなく、あくまでも環境影響評価を行う上で考え方を整理するために想定した一例であり、必ずしもここで示す手法のみを推奨するものではない。
【ケーススタディ1】環境保全方針の設定
【ケーススタディ2】環境の状態が既に悪化している場合の環境保全措置
【ケーススタディ3】複数の環境保全措置の検討
【ケーススタディ4】効果に係る知見が明らかでない環境保全措置の実施と事後調査
【ケーススタディ5】予測の不確実性を見込んだ環境保全措置の強化
【ケーススタディ6】事後調査結果のフィードバック
【ケーススタディ1】環境保全方針の設定
●テーマ
環境保全方針の設定は、環境への配慮をどのような視点で実施するのかを明らかにするために行うものであり、事業特性や地域特性を勘案して適切に設定する必要がある。
ここでは、地下鉄事業における鉄道振動に対する環境保全方針の設定の例を示す。
●鉄道振動に係る環境保全方針の設定例
A市(都市部)に計画された地下鉄の建設事業において、計画路線が住居等に近接することから環境保全方針を以下の点に留意して設定した。
[1]特に配慮すべき対象
A市のうち、住宅等が密集するB地区及び将来住宅団地の立地が予想されるCニュータウン計画予定地を特に配慮すべき地域とする。
[2]目標値の設定
振動に係わる基準は設定されていないため、A市の環境保全計画で振動の指標とされている「気象庁震度階の震度1」に相当する振動レベルとして65dBを環境保全目標値として設定した。原則として住居等でこの目標値を下回るように配慮する。
[3]配慮した地域特性及び事業特性並びに環境保全方針
| 地域特性及び事業特性 | 環境保全方針 |
|
○ 地域特性 (土地利用状況) ・特に静穏を要する施設の存在 ・緩衝地帯の有無 |
・B地区については、住宅が密集しているため目標値を達成することとするが、公園や道路等に利用されており、将来住居等の立地が考えられにくい地域については目標値は適用しない。 ・ニュータウン計画予定地については、将来住宅団地の立地が予想されるが、今後の土地利用も明らかになっていないため、原則として目標値を達成することとする。 |
|
(環境の状況) ・地盤の状況 |
・地盤が軟弱な地域においては、影響が著しくなる可能性を考慮し、実行可能な対策があれば検討する。 |
|
○事業特性 ・開業後に軌道構造の変更等の対応が困難 |
・目標値を下回っている場合においても、予測の不確実性を勘案して実行可能な範囲で最大限保全措置の実施を検討する。 |
【ケーススタディ2】環境の状態が既に悪化している場合の環境保全措置
●テーマ
都市部の幹線道路の沿道では、騒音に係る環境基準を現状で超過しており、環境の状態が既に悪化していると考えられる場合がある。しかし、事業を実施するうえで、工事用車両及び関連車両の走行ルートとしてそのような道路を選定した場合の環境保全措置の考え方の例を示す。
●騒音に係る環境基準を超過している道路を工事用車両が走行する場合の環境保全措置の検討例
工事用車両走行ルートである国道○○号は、現況で環境基準(昼間○dB)を上回っており、既に環境の状態が悪化しているものと考えられる。この場合、事業者による環境保全措置により、環境基準を達成することは不可能であり、工事用車両の走行による騒音の影響を極力回避・低減するように以下の措置を講じることとする。
|
・工事用車両の走行は、朝・夕の渋滞時を極力避け、円滑な交通流の確保に努める。 ・工事用車両には極力最新規制適合車を採用するとともに、車両の整備・点検を励し、騒音の発生源対策に努める。 ・事業実施段階の詳細な工事計画の策定にあたっては、工事用車両の走行の効率化に努めるとともに、事後調査を実施する。 |
また、当該地域の環境管理計画によると、中・長期的には、防音対策、低騒音舗装の敷設等、事業者以外による環境保全措置が行われる可能性があることから、そのような措置の実施が検討される場合には、事業者として実行可能な範囲内で最大限の協力を行うこととする。
【ケーススタディ3】複数の環境保全措置の検討
●テーマ
騒音分野における環境保全措置は伝搬経路対策、発生源対策が基本となる。また、実施者の立場で分類すると、事業者が実施する対策と事業者以外の者が主に実施する対策に分類される。
環境保全措置が複数存在する場合、効果の確実性や実施主体等を総合的に勘案して、各環境保全措置の採用を検討することになる。
●新幹線鉄道騒音に係る複数の環境保全措置の検討例
採用する環境保全措置は、事業者により実行可能な範囲での対策を第一とし、防音壁の設置、普通スラブ(防振用)の採用、車両及び軌道の維持・管理等の配慮を行うこととした。更に、必要に応じて防音壁の嵩上げ、軌道構造の変更を行うこととした。
これらの環境保全措置と併せて、関係機関に対する協力要請を行うことにより沿線の影響に配慮した土地利用対策の促進に努める。
表 新幹線鉄道騒音に係る環境保全措置の検討例
| 区分 | 環境保全措置 | 効 果 | 実施主体 |
| 発生源対策 | 普通スラブ(防振用)の採用 | 発生する騒音を低減する軌道 | 事業者 |
|
軌道構造の変更 (普通スラブ(防振用) →弾性枕木直結軌道) |
防音効果のある軌道構造 | 事業者 | |
| 車両及び軌道の維持・管理 | 適正な条件での運行 | 事業者 | |
| 伝搬経路対策 | 防音壁の設置 | 回折減衰による騒音低減 | 事業者 |
| 防音壁の嵩上げ | 回折減衰量の増加 | 事業者 | |
| 土地利用対策 |
新幹線計画と整合した公共施設(道路、公園、緑地等)を沿線に配置するよう関係機関に協力を要請し、距離減衰による騒音の低減を図る |
事業者以外 |
【ケーススタディ4】効果に係る知見が明らかでない環境保全措置の実施と事後調査
●テーマ
効果に係る知見が明らかな環境保全措置だけでは十分に環境影響を回避・低減できない場合、効果に係る知見が明らかでない環境保全措置を実施する場合がある。
ここでは、高速道路の新設事業において、並行する既存道路の影響が著しく、道路沿道における騒音に係る環境基準が達成できない場合を例として挙げる。
●高速道路の新設事業における、効果に係る知見が明らかでない環境保全措置(二層式排水性舗装)の検討例
事業者により実行可能な範囲での保全措置の検討
速道路の建設後、防音壁の設置の保全措置を実施しても、○○地区は道路に面する地域の環境基準(60dB)を6dB超過すると予測された。保全措置の強化(防音壁の嵩上げ)はその効果が非常に小さいため実施しないこととし、既存道路への対策を検討することとした。
表1 効果に係る知見が明らかな保全措置による検討
| 区 分 | 保全措置の内容 |
騒音レベル予測結果 |
環境基準 |
保全措置の強化とその効果 (実施前)→(実施後) |
|
| 高速道路 | 防音壁の設置(3m) | 59 dB | 66 dB | 60 dB |
防音壁の嵩上げ 66dB → 66dB |
| 既存道路 | (なし) | 65 dB |
(なし) |
||
効果に係る知見が明らかでない保全措置の検討
高速道路への保全措置の実施が効果的でないことが明らかになり、並行する既存道路への保全措置について低騒音舗装と二層式排水性舗装の比較検討を行った。その結果、二層式排水性舗装を実施することとしたが、二層式排水性舗装の騒音低減効果には不確実性があるため、事後調査を実施する。
表2 効果に係る知見が明らかでない保全措置の検討
| 区 分 |
保全措置の内容とその効果 (実施前)→(実施後) |
検討結果 |
| 既存道路 |
低騒音舗装の設置 66dB → 64dB |
低騒音舗装は減音効果が明らかになっているが、その効果は2dBと小さい。 一方、二層式排水性舗装は未だ実験段階の環境保全措置ではあるが、実験結果による効果は5dBと非常に大きいことから、実施を検討し、不確実性を補うために事後調査を実施する。 |
|
二層式排水性舗装の設置 66dB → 61dB |
事後調査の結果、予定した騒音低減効果が得られずに環境影響が著しいことが明らかになった場合等には、環境保全措置を二層式排水性舗装から低騒音舗装等への変更について検討する。
【ケーススタディ5】予測の不確実性を見込んだ環境保全措置の強化
●テーマ
環境影響の回避・低減を図るために環境保全措置を実施し、基準・目標を達成することが予測結果から確認されたれものの、予測の不確実性を見込んで環境保全措置を強化する必要がある場合が考えられる。地下鉄事業における鉄道振動の事例を示す。
●鉄道振動について、予測の不確実性と事業特性を勘案して、環境保全措置を強化した事例
予測の不確実性を見込んだ環境保全措置の強化の例
A鉄道株式会社地下鉄○号線の環境保全措置(鉄道振動)を検討する際に、予測の不確実性を勘案して以下の環境保全方針を設定した。
<環境保全方針>
○環境保全目標値を60dBに設定
○事業実施後に軌道構造の変更による対策が困難であるため、目標を下回っていても実行可能な範囲で最大限の対策を行う。
<予測の結果と保全措置の検討>
4地点について予測を行った。その結果3地点について環境保全目標値である60dBを下回ったが、事業者の実行可能な環境保全措置として防振枕木の敷設を実施し、振動レベルの低減を図った。
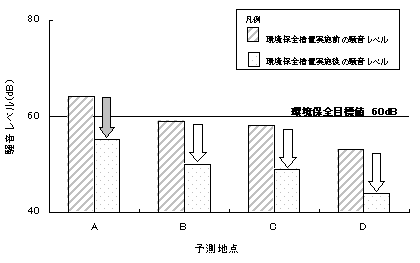
図 予測結果(保全前→保全後)
【ケーススタディ6】事後調査結果のフィードバック
●テーマ
事後調査は予測の不確実性を補う等の観点から実施し、環境影響が著しいことが明らかとなった場合には、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施するものである。道路事業における事例を示す。
●幹線道路の供用後に事後調査を実施して環境保全措置を強化した例
環境影響評価段階での環境保全措置の内容
A市~B市にかけて建設されたC道路は、日交通量が約11,000台の幹線道路であり、遮音壁の設置による環境保全措置を実施した。
遮音壁の高さは環境基準を達成できるように、将来交通量に基づき算出し、供用開始後に1.5mとした。
事後調査の方法
遮音壁の高さ検討に用いた将来交通量は、周辺の開発や道路ネットワークの整備等、様々な不確定要因があり、不確実性があると考えられるため、事後調査を実施した。
事後調査の項目:道路交通騒音レベル、交通量
事後調査の方法:予測地点において現地調査を実施する。
事後調査の時期:供用開始後、1,5年目の2回とし、5年目以降については、 地方公共団体が実施する環境モニタリングを活用する。
事後調査の結果の検討
供用開始後に事後調査を2度実施し、2回目の事後調査結果で環境保全目標である環境基準60dBを超過したため、環境保全措置を強化することとした。
| 調査時期 |
道路交通騒音 レベル(dB) |
交通量(台/日) | 検討結果 | |||
| 調査結果 | 予測値 | 調査結果 | 予測値 | 概要 | 実施した保全措置 | |
| 1年目 | 68~69 | 69 | 6,000 | 7,000 |
交通量が予測値よりも下回っており、環境基準(70dB)も達成している。 |
- |
| 5年目 | 72~74 | 70 | 15,000 | 11,000 |
騒音レベルは環境基準(70dB)を上回った。交通量が予測値を大幅に超過していることが原因と考えられる。 |
・遮音壁の嵩上げ (1.5m→3.0m) ・低騒音舗装の敷設 ・新型遮音壁の設置 |