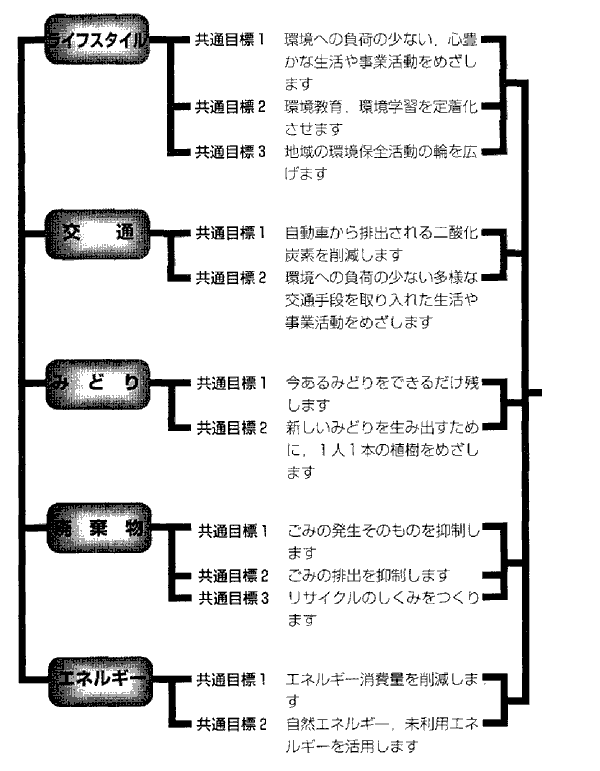平成13年度第1回環境負荷分科会
資料-2
2-3-1 温室効果ガス
1)環境影響要因の抽出
本事業における温室効果ガス等に関する環境影響要因としては、事業計画にもとづいて以下の項目を抽出する。
(1)活動の種類による区分
[1] 工場の操業
[2] 建築物(照明・空調等)の利用
[3] 産業廃棄物の焼却
(2)温室効果ガスの種類による区分
[1]二酸化炭素について
・燃料の消費
・他人から供給される電気の使用
・産業廃棄物の焼却(焼却対象物の排出として)[2]メタン
・ガス機関またはガソリン機関(定置式)における燃料の使用
・産業廃棄物の焼却(焼却対象物の排出として)[3]一酸化二窒素
・ガス機関またはガソリン機関(定置式)における燃料の使用
・一般廃棄物の焼却(焼却対象物の排出として)
2)調査
(1)地域における温室効果ガスの排出状況
K市においては温室効果ガスのうち二酸化炭素の排出量が把握されており、1980年から1995年における経年変化は図-1に示すとおりであり、我が国全体の約2%になっている。
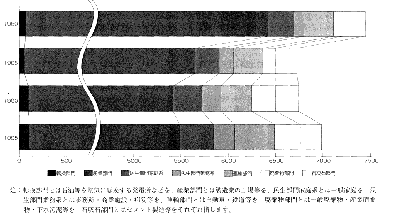
図-1 K市での二酸化炭素排出量の状況
また、産業活動や市民生活がこれまでの傾向のまま続くと仮定して予測した将来での二酸化炭素排出量は図-2のとおり推移すると考えられる。
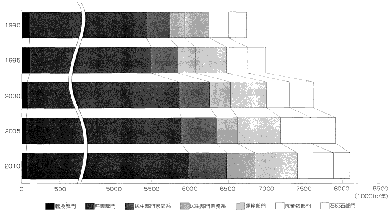
図-2 K市での二酸化炭素排出量の将来予測(現状での傾向が続くとした場合)
(2)地域での温室効果ガスの削減計画等
[1]目標値(ケース・スタディとして設定)
K市においては、地球温暖化防止施策を中心とした「地球環境保全のための行動計画」が定められている。ここでは、KOP3で合意した我が国での二酸化炭素削減量である1990年レベルに対し-6%を2008~2012年の間に達成することを目標としている。
[2]主要施策
a.視点とテーマ
【3つの視点・・・日常生活や事業活動の見直しのキーワード】
循 環 … 地球の環境には限りがあることを常に考え,不用物の再利用や自然への還元を常に心がける。 共 生 … 人間も生態系の一員であり,人間だけでは生存できないことを認識し,すべての生物の生命を大切にする。 抑 制 … どん欲は結局人間社会を破壊することを自覚し,量の拡大ではなく質の充実を図るとともに,自然や文化を愛し,心豊かに生きる。 そして,地球温暖化防止をはじめとする地球環境保全のために,取り組むべき5つのテーマを設定します。
【5つのテーマ・・・取組が必要な分野とその理由】
ライフスタイル … 環境への負荷の大きい現在の社会経済システムは,私たち一人ひとりのものの考え方や行動,事業を行う姿勢などに支えられています。 交通 … 日本が排出する二酸化炭素のうち約19%が運輸に伴うもので,さらにそのうちの85%以上がマイカーや貨物自動車から排出されています。 みどり … みどりは酸素を供給し,二酸化炭素を吸収・固定する機能とともに,私たちが心豊かな生活を送るために欠かせない要素です。 廃棄物 … 大量生産を基盤とした社会経済システムは,大量の廃棄物を排出し,その焼却による二酸化炭素の排出やダイオキシンの発生などの問題に結びついています。 エネルギー … エネルギーは,日常生活や事業活動に不可欠なものですが,石油や石炭などを燃焼させることにより,大量の二酸化炭素などが排出されています。
b.テーマ別行動計画
3)予測・評価及び環境保全措置
(1)温室効果ガス等の排出量の推計(ベースラインにおける推計)
[1]温室効果ガス排出量の推計方法
温室効果ガス排出量の計算は下記図書に示されている方法及び原単位を用いて行う(詳細は「技術シート 温室効果ガス-○」参照)ものとする。
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 平成11年8月 環境庁地球環境部
温室効果ガスは表-2に示した使用量を用いて(1)、(2)式により推計する。
各温室効果ガスの排出量=Σ(各活動の活動量×排出係数)・・・・・ (1)
温室効果ガスの総排出量=Σ(各温室効果ガスの排出量×地球温暖化係数) ・・・・・(2)
ここで、排出係数を表-1に、地球温暖化係数を表-2に示す。
表-1 温室効果ガスの排出係数
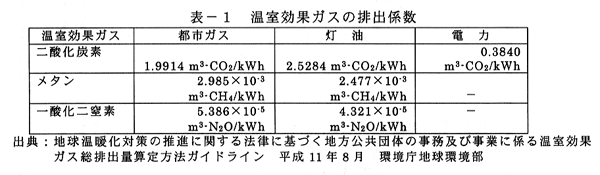
表-2 地球温暖化係数
| 温室効果ガス | 地球温暖化係数 |
| 二酸化炭素 |
1
|
| メタン |
21
|
| 一酸化二窒素 |
310
|
出典:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務
及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン
平成11年8月 環境庁地球環境部
また、ベースラインにおける温暖化ガス排出量の算定としては、事業計画に盛り込まれている各種削減対策がない場合を想定して、電力・燃料についてはその需要量から、廃棄物焼却について、焼却による排出のみを算定対象とした。
[2]工場の操業及び建築物(事務所等)の利用による活動量の推計
必要な情報は燃料・電力等の使用量である。
主要機械については駆動出力が事業計画で示されているため、(3)、(4)式で算出した。
・工場設備の電力使用量
個別主要機械の電力量(kWh)=個別主要機械の駆動出力(kW)×工場の稼働時間(hr)×負荷率(80%と仮定した。) ・・・・・(3)
全体での電力使用量(kWh)=Σ個別主要機械の電力使用量(kWh)+その他補機等の電力使用量(kWh) *1・・・・・
(4)
*1:既存の施設の実績を参考として主要機器の25%とした。
表-1の原単位にもとづいて算定された工場・事務所の電力・燃料使用量は表-4のとおりである。
[3]建築物の利用(照明・空調等)に伴う活動量
照明・空調等の動力用の電力・燃料等は事業計画では示されていないため、(5)式で算定した。
・事務所・工場での照明等の動力での電力使用量
電力使用量(kWh)=事務所・工場の延べ床面積(m2)×延べ床当りの原単位 (kWh/m2) ・・・・・(5)
工場における電力・燃料等の使用量の原単位は「平成10年度 建築物エネルギー消費量調査報告書 (社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会」での工場での平均値(異常値カット)を採用し、表-3のとおりとする。
表-3 建築物の電力・燃料消費原単位
| エネルギー種類 |
単位
|
数値
|
| 都市ガス |
m3/m2
|
2.79
|
| 灯油 |
l/m2
|
5.01
|
| 電力 |
kWh/m2
|
218
|
出典:平成10年度 建築物エネルギー消費量調査報告書
(社)日本ビルエネルギー総合管理技術協会
表-1の原単位にもとづいて算定された工場・事務所の電力・燃料使用量は表-4のとおりである。
表-4 工場・事務所の操業に係るエネルギー消費等(活動量)
|
企業団地進出企業
|
業種
|
建築設備動力等
|
工場設備動力等
|
||||
|
都市ガス (m3/年)
|
灯油
(l/年) |
電力
(kWh/年) |
都市ガス (m3/年)
|
灯油 (l/年)
|
電力
(kWh/年) |
||
|
A
|
製紙G
|
47,915
|
86,042
|
3,743,932
|
0
|
2,369,101
|
38,588,160
|
|
B
|
鋼材溶接
|
4,698
|
8,437
|
367,112
|
0
|
0
|
29,120
|
|
C
|
倉庫
|
402
|
721
|
31,392
|
0
|
0
|
0
|
|
D
|
鋼材溶接
|
2,983
|
5,356
|
233,042
|
0
|
0
|
165,776
|
|
E
|
配管加工
|
2,235
|
4,013
|
174,618
|
0
|
0
|
917,280
|
|
F
|
鋳造
|
2,394
|
4,299
|
187,044
|
480,100
|
0
|
775,632
|
|
G
|
めっき
|
901
|
1,618
|
70,414
|
2,400
|
0
|
342,264
|
|
H
|
めっき
|
5,156
|
9,258
|
402,864
|
96,000
|
0
|
810,264
|
|
I
|
板金
|
2,623
|
4,709
|
204,920
|
0
|
0
|
325,520
|
|
合 計 |
69,306
|
124,453
|
5,415,338
|
578,500
|
2,369,101
|
41,954,016
|
|
[4]産業廃棄物の焼却に伴う活動量の推計
産業廃棄物の焼却に係わる活動量としては、焼却炉機器の動力については1)で算定しているので、処理ごみ量、そのうちのプラスチックごみ量(二酸化炭素についてはプラスチックのみが算定対象であるため。)、助燃料(灯油)の種類と量の3項目である。これらは、事業計画にもとづいて表-5のとおり設定されている。
表-5 産業廃棄物焼却に関する活動量
|
処理ごみ量
|
灯油使用量
|
||
|
全体量 (t/年)
|
内訳
|
(l/年)
|
|
|
紙くず相当 (t/年)
|
汚泥相当 (t/年)
|
||
|
60,000
|
47,000
|
13,000
|
600,000
|
[5]温室効果ガス排出量の推計
前述した算定方法により求めた温室効果ガスの排出量は表-6に示す。二酸化炭素排出量で約27.3千t-CO2/年で、温室効果ガス総排出量で約30.0t-CO2/年となっている。二酸化炭素排出量で比較すると、この量はK市全体(約25.6百万t-CO2/年(1995年))の約1%に当たる量である。
表-6 温室効果ガス排出量推定結果(ベースライン)
| 区分 |
企業団地進出企業
|
業種
|
温室効果ガス排出量
|
|||
|
二酸化炭素
(kg-CO2/年) |
メタン
(kg-CH4/年) |
一酸化二窒素
(kg-N2O/年) |
総排出量
(kg-CO2/年) |
|||
|
工場・事務所の建築設備 |
A
|
製紙G
|
1,750,636.7
|
356.2
|
6.3
|
1,761,493
|
|
B
|
鋼材溶接
|
171,659.0
|
34.9
|
0.6
|
172,724
|
|
|
C
|
倉庫
|
14,678.7
|
3.0
|
0.1
|
14,770
|
|
|
D
|
鋼材溶接
|
108,968.8
|
22.2
|
0.4
|
109,645
|
|
|
E
|
配管加工
|
81,650.2
|
16.6
|
0.3
|
82,157
|
|
|
F
|
鋳造
|
87,460.5
|
17.8
|
0.3
|
88,003
|
|
|
G
|
めっき
|
32,925.1
|
6.7
|
0.1
|
33,129
|
|
|
H
|
めっき
|
188,376.4
|
38.3
|
0.7
|
189,545
|
|
|
I
|
板金
|
95,819.2
|
19.5
|
0.3
|
96,413
|
|
|
計
|
2,532,174.5
|
515.2
|
9.1
|
2,547,878
|
||
| 工場の操業に伴う排出量 |
A
|
製紙G
|
20,807,888.7
|
5,868.3
|
102.4
|
20,986,330
|
|
B
|
鋼材溶接
|
11,182.1
|
0.0
|
0.0
|
11,182
|
|
|
C
|
倉庫
|
0.0
|
0.0
|
0.0
|
0
|
|
|
D
|
鋼材溶接
|
63,658.0
|
0.0
|
0.0
|
63,658
|
|
|
E
|
配管加工
|
352,235.5
|
0.0
|
0.0
|
352,236
|
|
|
F
|
鋳造
|
1,253,913.8
|
1,433.1
|
25.9
|
1,297,757
|
|
|
G
|
めっき
|
136,208.7
|
7.2
|
0.1
|
136,428
|
|
|
H
|
めっき
|
502,315.8
|
286.6
|
5.2
|
511,083
|
|
|
I
|
板金
|
124,999.7
|
0.0
|
0.0
|
125,000
|
|
|
計
|
23,252,402.3
|
7,595.1
|
133.5
|
23,483,673
|
||
| 廃棄物焼却による排出量 |
1,517,040.0
|
2,201.2
|
7,825.2
|
3,997,872
|
||
| 合 計 |
27,301,617
|
10,311
|
7,968
|
30,029,423
|
||
(2)温室効果ガス削減対策及びその効果
[1]温室効果ガス削減対策
本事業における温室効果ガスの排出量削減対策として計画している内容を表-7に示す。
なお、これらの対策は事業の趣旨(ゼロエミッション工業団地というコンセプト)から既に事業計画に盛り込まれた内容であり、対策実施についての事業者間の合意も有り確実な実施が可能である。
| 対策の名称 | 対策の実施者 | 対策の内容 | 対策の効果 |
| コージェネレーション | 製紙業グループ | 製糸業グループで利用する全電力を発電できる施設を設け。その廃熱を製紙業者や他の事業者に供給する。 熱供給を受ける各工場は燃料による空調の全部と電力による空調の一部をこの熱供給で代替する。 | 発電効率32%、熱供給28%として総合熱効率60%の施設として建築動力分の燃料を削減する。 |
| 廃棄物焼却廃熱の供給 | 同上 | 焼却廃熱を製紙業のうち抄紙生産工程用の蒸気として供給する。 | 供給熱量5,271,240Mcal分の灯油消費を削減することができる。 |
| 都市ガスの利用 | 全事業者 | 燃料としては比較的二酸化炭素排出係数の低い都市ガスを使用して、灯油との石油の使用を行わない。 | 実質的にはコージェネレーションの燃料にのみ効果がある。ベースラインからの比較には考慮しない。 |
[2]削減対策の効果
ア.コージェネレーション 製紙業グループの供用設備としてコージェネレーション設備を設置する。設備の諸元は次のとおりである。
・機関:ガスタービン
・燃料:都市ガス 最大1,250 m3/h
・発電端出力 最大 4,610 kW
この発電によって製紙業グループで消費するすべての電力を供給する。 発電廃熱は熱供給としてすべての工場に供給を行う。これによって90%以上の熱(冷熱を含む。)の供給が行うことができる。削減の対象となるのは、都市ガス、灯油のすべてと電力のうち空調用動力分の全体の50%程度である。
イ.廃棄物焼却炉廃熱の供給
焼却廃熱を製紙業のうち抄紙生産工程用の蒸気として供給する。これによって製紙業の工場設備で計上されている灯油の全量を削減することができる。
ウ.削減量 削減対策による削減量を表-7に示す。削減量は約8.1千t/年で削減率は約26%となっている。
表-7 環境保全措置による温室効果ガス削減量
| 二酸化炭素 (kg-CO2/年) |
メタン (kg-CH4/年) |
一酸化二窒素 (kg-N2O/年) |
温室効果ガス 総排出量 (kg-CO2/年) |
|
| コジェネレーション |
-2,649,519
|
24,693
|
451
|
-1,892,358
|
| 廃棄物焼却廃熱供給 |
-5,990,035
|
-6,134
|
-107
|
-6,176,549
|
| 合計 |
-8,639,554
|
18,559
|
344
|
-8,068,907
|
4)評価
評価の視点を以下に述べる。
(1)ベースラインからの削減量
○実行可能な範囲において回避・低減がなされているか。
[1] コージェネレーション
コージェネレーションによる熱電供給→熱については自工場内だけではなく工業団地内全事業所に供給することで有効な対策となっている。→工業団地とした意義がある。
[2] 廃棄物焼却廃熱の供給
多量の蒸気を利用する工程への蒸気供給を目的として自区内で焼却炉を設置した。
[3] 都市ガスの利用
都市ガスは灯油等石油に比してやや効果であるが、二酸化炭素排出係数が小さいため採用している。
(2)対策実施の実現性と効果の確実性
○実施は確実か、効果は確実か。
[1] 対策は既に計画に盛り込まれ、実施者が確定している。
[2] 装置としては効果が確実である。
[3] 製紙業の操業の状況が不安定になると全体として数値が変動する余地がある。
(3)削減計画との整合性
○地域の削減計画と正号がとれているか。
全体で約14%の削減となっており、K市の削減目標に貢献できる。