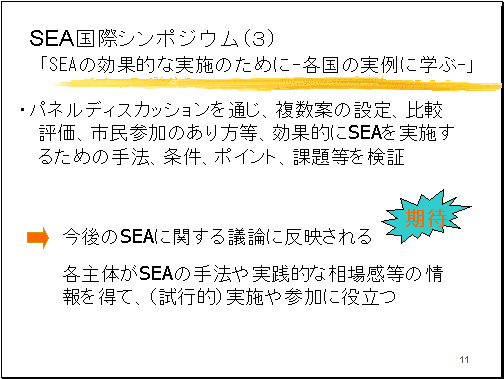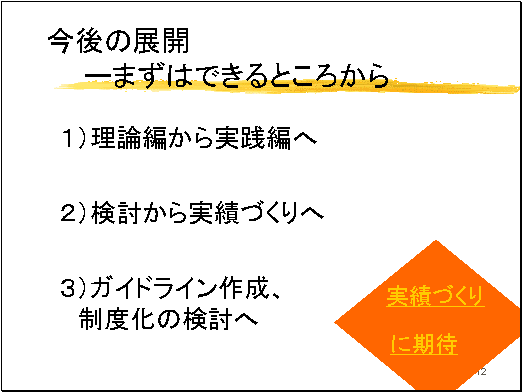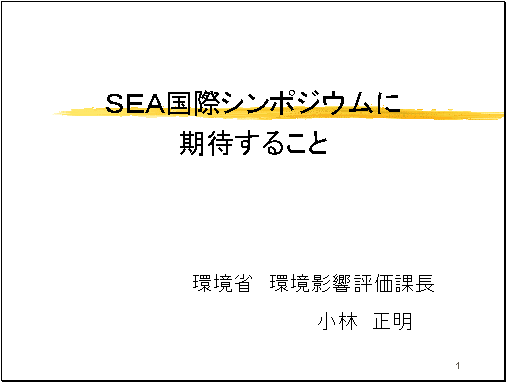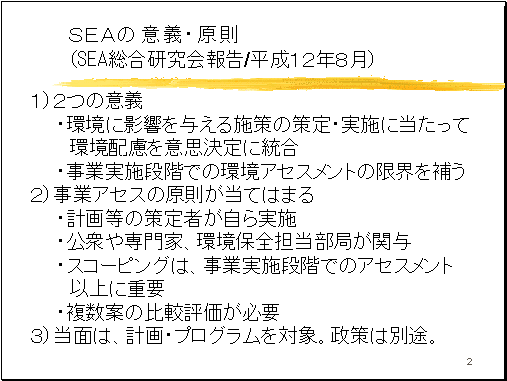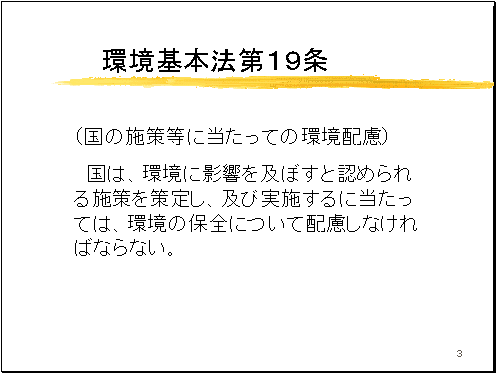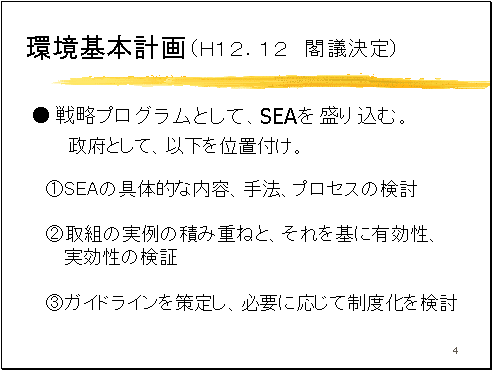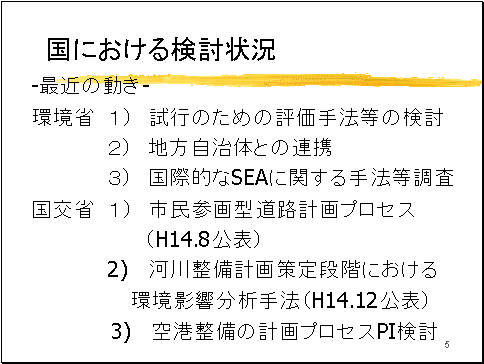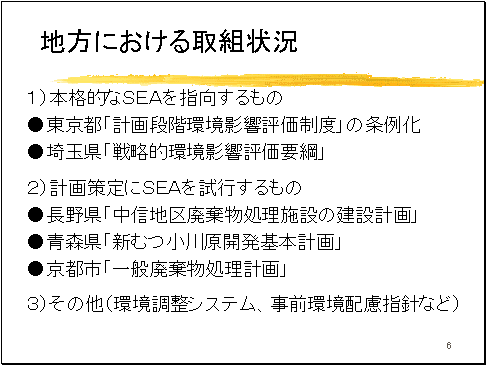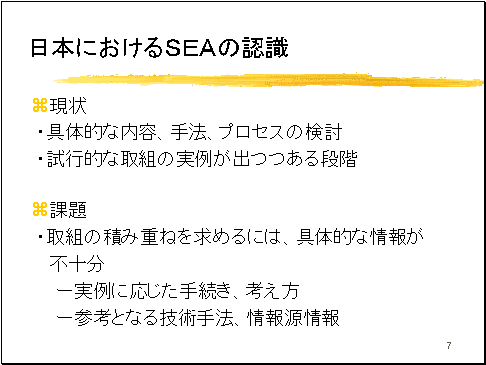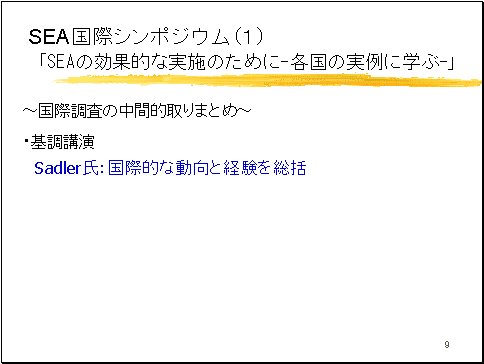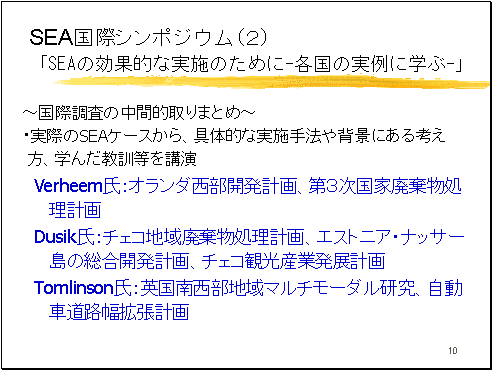|
「スライド1」皆様、おはようございます。環境省の環境影響評価課長の小林でございます。今日のシンポジウムの主旨・目的につきましては、ただ今私共の炭谷局長からお話しを申し上げたところでございます。そこで、改めまして、わが国でこれまでこの戦略的な環境アセスメントに対してどのような取り組みをしてきたのか、あるいは今どんな位置付けになっているのか、こういった事を整理致しまして、また、今日のシンポジウムの狙いや期待などについてもお話できればと思います。この戦略的環境アセスメントにつきましては、環境影響評価法の施行以来、いろいろ勉強を重ねているところであります。その意義やどういった考え方でやっていくのかなどについては、早速この後サドラーさんから最近のいろいろな考え方の動向やポイントなども含めて有益なお話があるだろうと期待しておりますが、環境省で研究してきた成果を若干ご披露しておきます。
「スライド2」この戦略的環境アセスメントの意義はどこにあるのか、一つは環境に影響を与えるような政策がいろいろ策定され実施されていくわけですが、そこに環境配慮をいかに組み込むか、意思決定の中に環境配慮を統合していくというのが第一の目的です。こういったことが持続可能な発展につながっていくというものだろうと思います。もう一つは、現実的な問題と致しまして、我が国でも既に環境影響評価法に基づき事業段階の環境アセスメントをやっておりますが、これにはまだいろいろ限界があります。例えば、タイミングが遅きに失する面があるとか単一の事業単位でしか考えにくいとか指摘があるところでございます。二番目に、戦略的環境アセスメントは、どんな考え方で進めていくのか、従来の我々の議論の整理の中で、事業の段階でやっている今の環境アセスメント、この原則で当てはまるものは多いのではないかと考えております。例えば、誰がやるのかという点については、計画を策定する人がやる、つまり一番良く分っている人がやるというのが原則です。しかしながら、一般の公衆の方、幅広い専門家、環境保全を担当しているセクション、こういったところが関与していくことによって適切な形でやっていくというところ、これは事業段階の環境アセスメントと同じ原則であろうと思います。その下にありますようなスコーピングあるいは複数の比較検討、これは事業段階の環境アセスメントでも重要でございますが、おそらく戦略的環境アセスメントにおいてはもっと重要な、あるいは幅広い役割を果たすというような考え方であります。三番目に、戦略的環境アセスメント自体はポリシーレベルからプログラムや計画のレベルまで幅広いところをカバーしているわけでありますが、我が国としては当面は計画やプログラムを念頭におきながら検討を進めていこうとしているところであります。
「スライド3」この法的な位置付けでありますが、環境基本法の十九条に「国は政策を策定しあるいは実施するにあたっては環境保全に配慮しなくてはならない」といった基本方針は既に位置付けられております。そういう意味で、戦略的環境アセスメントというのは、それを如何に具体化していくかという課題であろうと思っています。また、考え様によりましては、既にいろいろな計画を策定する段階で環境配慮というものは現実には行われているケースが多いわけでありますが、これをどうシステムとしてやっていくのか、あるいは社会が認めるような形でやっていくのかこういう課題ではないかと考えているところであります。
「スライド4」具体的には、国が閣議決定いたしました環境基本計画というものがございます。その中で、戦略的環境アセスメントの導入に取り組んでいくという事は既に政府として位置付けしているところであります。具体的な課題としては一体どのような内容・手法・プロセスでやっていくのか、特に取り組みの実例を重ねてその有効性・実効性を検証して、その上に立ってガイドラインを作成し制度化を考えていくというような道筋を描いているわけであります。
「スライド5」我が国で取り組んできている検討の状況でありますが、環境省としてはもうそろそろ実施段階であるという事を踏まえまして、具体的にこれを試していく場合にどんなやり方でやればいいのか、より実践的な手法を示していきたいということで、先程局長の方からもご披露いたしましたが、特に廃棄物処理計画などを具体的に想い描きながら手法の検討を進めているところであります。また、ちょっと後でもご紹介いたしますが、地方公共団体でもいろいろな形で取り組みが進んできております。地方公共団体と連携をしていく、あるいはバックアップをして行くというような事も我々の重要な仕事ではないかと思っております。また、国際的な動向にも視野を広げ、あるいはいろいろな情報交換をしていく、まさに今日のシンポジウムがそういうことでありますが、こういったことにも力を入れていきたいと思っています。政府部内でも、他の省でもいろいろな取り組みがされております。例えば、国土交通省におかれては、昨年いろいろな成果を提起されておりまして、道路の分野では市民が参加して早い段階から情報を提供し意見を貰いながらやっていくという方法が提示されておりますし、河川の整備計画につきましてはかなり本格的な戦略的環境アセスメントの手法の提示が行われております。これをこれから試していく段階だと伺っているところであります。これ以外にも、他の役所でも戦略的環境アセスメントについての検討を始めている役所は順次出てきていると思っております。
「スライド6」次に地方公共団体の取り組みでありますが、ご承知のように昨年、東京都と埼玉県で既に条例あるいは要綱というような形で制度化されております。また、具体的なプロジェクトあるいは計画について戦略的環境アセスメントをやろうという所も幾つか有りまして、こういった動きは順次広がってきていると思います。こういった各地での力強い動きと合わせて我々も進めて行ければと思っているところであります。
「スライド7」今、我が国で取り組み検討している状況を改めて整理してみますと、だんだんいろいろな分野での取り組みが進んできているというような事から、具体的にどんな方法でやったら良いのか、どういう計画を捉えてやったら良いのか、プロセスについてもどんな形でやったら良いのかというような事が模索され、検討されている段階だと思います。具体的な取り組みの事例も出てきておりますので、そういうものを比較検討して議論が出来る段階に至っていると思っております。逆に、課題と致しましては、まだまだ実践的にやっていく上で環境面の情報が不足しているとか、あるいはどんな技術的な手法があるのかというような悩みがあるという声は良く聞くところでございます。また、事業段階の環境アセスメントも制度的に行われておりますので、具体的にどんな手続きでやるのかということについていろいろお悩みがあるというようなお話も伺うところでございます。こういった課題に答えていかなければいけないということでございます。
「スライド8」そこで、先程も申し上げました国際調査についてちょっとご披露したいと思います。実は、今日のシンポジウムもこの調査の延長線上と申しますか、この途中段階で開催しているものでございます。ご承知のように、今、欧米では非常に活発な取り組みがされております。そこで、国際的に手続きの面あるいは技術の面でどんな考え方でこの戦略的環境アセスメントが進められているのか、従来もいろいろな考え方が披露されておりますが、今回、この環境省の国際調査では、特にケーススタディを通じて、参考になる具体的な事例あるいは技術事項を集約してご披露していきたいという事を考えております。四人の専門家の方々にそれぞれ役割分担をして頂きまして、かなり幅広い分野の計画について、今、調査を進めてきて、かなりまとまってきている段階でございます。例えば、廃棄物処理計画、これは国家レベルの計画あるいは地域レベルの計画について調査をしておりますし、あるいは資源利用の計画ですとか、土地開発計画、水供給、エネルギー、あるいは交通、こういう様々な分野のケースをやっております。
「スライド9」具体的にはサドラーさんに全体をコーディネイトしていただきながら、あとの三人の専門家の方々にそれぞれ数プロジェクトの調査をお願いしているという事でございます。今日のシンポジウムは、その中からそれぞれ代表的な概ね二つぐらいのケースをある観点から取り出して頂きましてご披露していただくという企画でございます。まず、サドラーさんは、この分野の第一人者でございまして、言わば世界の理論的な指導者といっても過言ではないと思いますが、今、国際的にどんな事が検討されどういうところを目指しているのか、また戦略的環境アセスメントを効果的に行っていく場合のポイントは何なのか、こんな事をお話いただこうと思っております。
「スライド10」それに続きましてフェルヒュームさん、デューシックさん、トムリンソンさん、この三人はそれぞれの分野あるいは国でまさに第一線で活躍されている専門家の方々でございまして、この方々に具体的な手法、あるいはその計画とかSEAの取り組みの背景にある考え方、あるいはそこから学べる教訓などをご披露いただこうということでございまして、そこに有るような幾つかの計画を取り上げて、今日、ご披露いただこうと考えているところでございます。地域の開発の計画、観光の発展計画、マルチモーダルの研究、いずれも興味深いテーマ、あるいは分野であると思っております。
「スライド11」そして、こういったを受けまして、午後、時間的には三時過ぎからになろうかと思いますが、これらの海外の専門家の方に我が国の専門家の先生、浅野先生、原科先生、田中先生というような我が国の代表的な専門家にもお加わりいただきまして、パネルディスカッションを通じて、今、我々がSEAを進めていく上で気になっている点を掘り下げて議論いただければと思います。その中では複数案の設定・比較・評価の問題、市民参加の問題、具体的な手法の問題、こういった事が議論されると期待しているところでございます。こういった事を通じまして、まさにこれから我々が具体的に取り組んでいく上でのいろいろなヒント、あるいはここを取り掛かりにして、我々が発想を広げて取り組んでいく、こういった手掛かりになればと期待しているところでございます。
「スライド12」いよいよ、この戦略的環境アセスメントも理論的な段階から具体的に実践していく段階、検討の段階から実績を作っていく段階、こういうところに来ていると思います。是非、皆様のご協力を得て、様々な取り組みの検討を進め、これが我が国での効果的な実施、あるいは制度、こういうものに繋がっていけばと思っております。以上、簡単に今日の狙いなどをご紹介申し上げました。ご静聴有難うございました。 |