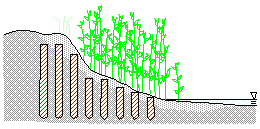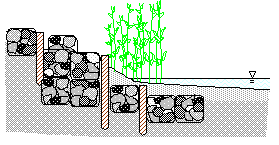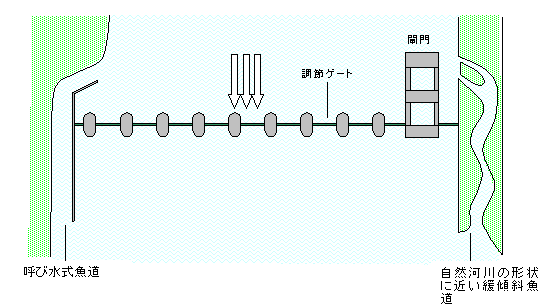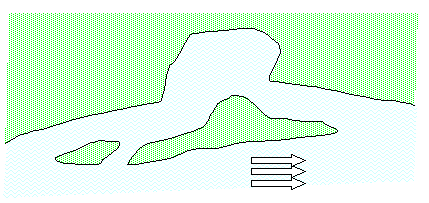生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会報告書
生物の多様性分野の環境影響評価技術(III) 生態系アセスメントの進め方について(平成13年9月)
2 陸水域生態系 ―河口堰新築事業を例として―
対象とする地域と事業の想定は以下のとおりとした。
●本州太平洋岸中部の河川における河口堰(調査・予測ケーススタディ:図I-2-1 参照)
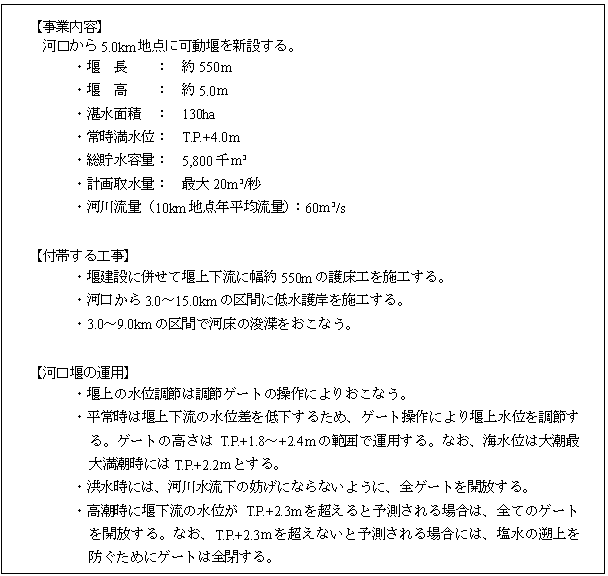
●基本条件
・河口堰に付帯する施設(照明など)による環境影響はないものとする。
・建設資材などからの溶出(例えばコンクリートあく)などによる環境影響はないものとする。
事業実施区域は、本州太平洋岸中部の大河川に位置し、河口域には干潟が存在する。下流部には潮汐によって海水が遡上し、大潮時には緩混合、小潮時には塩水楔となって汽水域を形成する。汽水域の河岸にはヨシ原が広がり、低水路内にはヤマトシジミを主とする汽水性の底生動物群集および汽水・沿岸性魚介類が生息している。また、河川にはアユを主とする回遊性魚類の遡上および降下がみられる。
以上のように事業実施区域およびその周辺は「河川下流域における汽水域の生態系」と位置づけられ、さらに重要な機能として、[1]動物の移動経路、[2]水質浄化機能、[3]動物の生息場所の形成(隠れ場、採食場、育成場、繁殖場など)、[4]物質生産機能が挙げられる。
本事業によって種々の環境影響が予測されるが、上記のような現況を踏まえると「汽水域生態系および重要な機能の保全」を環境保全上の基本的な考え方とし、環境保全措置を検討した。
生態系の環境影響評価は、事業実施により影響を受けやすいと推定される注目種・群集を選定し、それらへの影響の程度を評価対象とした。
事業実施区域およびその周辺は、本報告書第I部第2章の調査・予測ケーススタディで示したとおり汽水域から淡水域にわたる多様な環境が混在し、基盤環境やそこに生息する生物により5つの類型に区分された。重要な類型区分およびそこで形成される食物連鎖構造を踏まえ、類型区分ごとに注目種・群集を選定した結果、アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類に代表される移行帯(ヨシ帯など)への依存度が高い生物群集、ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集、マハゼに代表される汽水性魚介類およびイサザアミに代表される汽水域に特有な餌生物、トビハゼなどに代表される干潟生物、底生動物や魚類の捕食者である魚類、鳥類であった。重要な機能は、地域概況調査、水域の類型区分、重要な類型区分および対象となる生態系の構造と機能を勘案した結果、動物の移動経路、水質浄化機能、動物の生息場所の形成(隠れ場、採食場、育成場、繁殖場など)、物質生産機能であった。
調査・予測ケーススタディでは、これらの生態系や先に示した生態系のもつ重要な機能を指標する種を注目種・群集として選定し、事業による影響の有無や程度を検討した。選定された注目種を表II-3-1に示す。
環境保全措置のケーススタディにおいては上記の結果を受け、注目種または機能を有する場所(面積)を保全するための措置(環境保全措置)について検討をおこなう。なお、本ケーススタディでは選定された注目種の一部を対象とした。
調査・予測ケーススタディでの検討結果に基づく事業による注目種および重要な機能への影響予測結果を表II-3-2に示す。このように事業により生態系へ影響をおよぼすおそれがあると予測されたことから、環境保全措置ケーススタディにおいては、これらを対象として検討をおこなう。
表II-3-1 注目種の選定結果
|
選定の 観点 |
選定理由 |
||
|
ヨ シ |
典型性 |
・調査の結果、類型区分I~IIに共通して分布していた。 ・重要な機能(水質浄化機能および動物の生息場所の形成)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
コアマモ |
典型性 |
・調査の結果、生育面積は狭く、類型区分Iの一部に分布していた。 ・重要な機能(水質浄化機能、生息場所の形成)を指標する。 ・事業に伴う影響が生じる可能性がある。 |
|
|
エドガワミズゴマツボ |
特殊性 |
・調査の結果、干潟でのみ生息が確認された。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
ホソウミニナ |
特殊性 |
・調査の結果、干潟でのみ生息が確認された。 ・事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
ヤマトシジミ |
典型性 |
・調査の結果、汽水域に広く生息し、生息量も多いことが確認された。 ・調査の結果、本種の生息は、底質、水深、塩分などに支配されていることが示唆され、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 ・重要な機能(水質浄化機能)を指標する。 |
|
|
オキシジミ |
典型性 |
・調査の結果、類型区分IIに生息し、生息密度も高かった。 ・ヤマトシジミと同様に、重要な機能(水質浄化機能)を指標する。 |
|
|
イサザアミ |
典型性 |
・調査の結果、春季から夏季に汽水域における生息量がかなり多いと推定された。 ・重要な機能(物質生産機能)を指標する。 ・汽水域への依存度が高いものと推定され、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
モクズガニ |
典型性 |
・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域には小型個体が多い結果が得られ、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
アシハラガニ |
典型性 |
・重要な機能(連続性:河川から陸上)を指標する。 ・調査の結果、移行帯(水際)への依存度が高い結果が得られたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
ヒメカゲロウ |
典型性 |
調査の結果、類型区分IIに生息量が多かった。 |
|
|
ア ユ |
典型性 |
・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域を幼稚魚の遡上経路および仔魚の流下経路として利用していることが確認された。 ・本種は人為的な放流が盛んに行われているため、注目種として適切ではないが、遡上幼稚魚および流下仔魚は河川の分断、取水および流下所要時間の延長などの影響を強く受けると考えられる。 |
|
|
フナ類 |
典型性 |
・調査の結果、類型区分IIで生息量が多かった。 ・本種は止水性(流れの緩やかな場所を好む)のため、湛水区域の出現により増加する可能性が高い。 |
|
|
マハゼ |
典型性 |
調査の結果、類型区分Iには生息量がかなり多く、特に春季には河口干潟での生息量が多いものと推定された。 |
|
|
トビハゼ |
特殊性 |
調査の結果、干潟でのみ生息が確認され、生息量も少ないものと推定されたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
|
小卵型カジカ |
典型性 |
・重要な機能(連続性)を指標する。 ・調査の結果、対象地域を稚魚の遡上経路および仔魚の流下経路として利用していることが確認された。 ・遡上稚魚および流下仔魚は河川の分断、取水および流下所要時間の延長などの影響を強く受けると考えられる。 |
|
|
カワウ |
上位性 |
調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |
|
|
コサギ |
上位性 |
調査の結果、干潟やワンドを主要な採食場にしているものと推定された。 |
|
|
ミサゴ |
上位性 |
調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |
|
|
コチドリ |
特殊性 |
調査の結果、干潟を主要な採食場にしているものと推定された。 |
|
|
キアシシギ |
特殊性 |
調査の結果、干潟を主要な採食場にしているものと推定された。 |
|
|
コアジサシ |
上位性 |
調査の結果、海域~類型区分IIまでを広く採食場にしているものと推定された。 |
|
|
オオヨシキリ |
典型性 |
調査の結果、繁殖場としてヨシ帯を利用しており、ヨシ帯への依存度が高いものと推定されたため、事業に伴う影響が生じる可能性が高い。 |
|
表II-3-2 事業が各類型区分の注目種および重要な機能などに及ぼす影響の概要
|
主な環境変化 |
注目種および重要な機能などへの主な影響 |
該当する類型区分 |
||||
|
II-2 |
II-1 |
I-3 |
I-2 |
I-1 |
||
|
移行帯の消失 汽水域の減少 DO濃度の低下 底質の変化(細粒化など) 水域の富栄養化 干潟の消失 取水の発生 流速の低下 既存河床の消失 連続性の分断 湛水区域の出現 |
アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類に代表される移行帯(ヨシ帯など)への依存度が高い生物群集の減少。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集の減少。 |
○ |
○ |
○ |
|||
|
マハゼに代表される汽水性魚介類およびイサザアミに代表される汽水性餌生物の減少。 |
○ |
○ |
||||
|
トビハゼなどに代表される干潟生物の減少。 |
○ |
○ |
||||
|
底生動物および魚類の減少による捕食者(魚類、鳥類)の餌環境の悪化 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
オオクチバスおよびブルーギルといった魚食性魚類の増加に伴う生態系への影響。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
||
|
移動経路の分断(動物の遡上および降下阻害、移行帯の消失、取水口への迷入、流下時間の延長):アユや小卵型カジカなどのように主な生息場所を河川上流~中流域における生物種の減少を招くことにより、上流域、中流域の生態系への影響といった広範囲な影響が生じる可能性がある。 |
||||||
|
水質浄化機能の低下(ろ過食性底生動物の減少、干潟の減少、水生植物帯の減少):懸濁有機物および栄養塩類の海域への負荷量の増加などにより、海域における生息環境や生態系にまで影響を及ぼす可能性がある。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
動物の生息場所(生息場所、隠れ場、採食場、育成場、繁殖場など)の減少(ヨシ帯、ワンドおよび干潟などの減少):汽水域・干潟などを育成場とする動物(一時的に汽水域や干潟を生息場所として利用する)の減少を招くことにより、影響は汽水域に止まらず、海域における生態系にまで影響を及ぼす可能性がある。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|
|
物質生産機能の低下(イサザアミなどの汽水域に特有な餌生物の減少):汽水域・干潟などを育成場とする動物(一時的に汽水域や干潟を生息場所として利用する)の減少を招くことにより、影響は汽水域に止まらず、海域における生態系にまで影響を及ぼす可能性がある。 |
○ |
○ |
||||
「1)環境保全措置立案の観点」で述べた基本的な考え方や調査・予測結果を踏まえ、環境保全措置の対象と目標を表II-3-3に示すように設定した。
環境保全の基本的な考え方は「河川下流域における汽水域の生態系および重要な機能の保全」である。この考え方や調査・予測結果を踏まえて事業による影響を受けやすいと推定された注目種や重要な機能を環境保全措置の対象とし、環境保全措置の目標をそれぞれに対して設定した。
表II-3-3 環境保全措置の対象と目標
|
環境保全措置の対象 |
環境保全措置の目標 |
|
|
基盤環境 |
ヨシ帯などの移行帯(アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類に代表される移行帯に依存度が高い生物群集の生息場所)。 |
・水生植物帯(ヨシ帯など)の構成種および生育面積の確保。 ・アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類の種および個体数の維持。 |
|
干潟(トビハゼに代表される干潟生物群集の生息場所)。 |
トビハゼの生息個体密度の維持。 |
|
|
注目種および群集 |
ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集。 |
ヤマトシジミの平均生息密度の維持。 |
|
マハゼに代表される汽水性魚介類およびイサザアミに代表される汽水性餌生物の減少。 |
汽水性魚介類の個体数の維持。 |
|
|
取水口へ迷入する水生生物。特に遊泳力が弱い幼生や仔魚。 |
・アユ仔稚魚の迷入量の低減。 ・稚魚~成魚の迷入の回避または低減。 |
|
|
生態系の有する重要な機能 |
動物の移動経路(連続性) |
・移行帯の地形、構成材および面積の確保。 ・アユなどの回遊性種の遡上、降下量の維持。 ・流下仔アユの流下時間延長の回避または 低減。 |
| 水質浄化機能 |
・干潟面積の確保。 ・ヤマトシジミに代表されるろ過食者の平均生息密度の維持。 |
|
|
生息場所の形成 |
干潟、ワンド、水生植物帯および移行帯などの構成材、面積および生物群集(種構成・個体数)の維持。 |
|
|
物質生産機能 |
汽水性魚介類の個体数の維持。 |
|
|
その他 |
オオクチバスおよびブルーギルなどの止水環境を好む捕食者の増加によって影響を受ける生物群集。 |
止水性捕食者の個体数増加の抑制。 |
[1]環境保全措置の内容
表II-3-3に示した環境保全措置の目標に対して、影響を回避または低減する具体的な措置を検討した(表II-3-4参照)。
表II-3-4 回避または低減措置案の内容(例)
|
環境保全措置の目標 |
環境保全措置(回避または低減措置) |
対象とする類型区分 |
|||||||||
|
II-2 |
II-1 |
I-3 |
I-2 |
I-1 |
|||||||
|
水生植物帯(ヨシ帯など)の構成種および生育面積の確保。アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類の種および個体数の維持。移行帯の地形、構成材および面積の確保。 |
湛水区域の出現および低水護岸によって減少が予測されるヨシ帯を中心とする水生植物帯に対して回避または低減措置([1]自然復元型工法を用いた低水護岸)を検討する。 |
○ |
○ |
○ |
○ |
○ |
|||||
|
湛水区域の出現によって減少が予測されるヨシ帯を中心とする水生植物帯に対して回避または低減措置([2]湛水区域面積の5%の減少)を検討する。 |
○ |
○ |
|||||||||
|
ヤマトシジミの平均生息密度の維持。 |
・堰上の淡水化によって消失する生息場所に対して回避または低減措置([3]堰ゲート操作による汽水環境の維持)を検討する。
・堰下の生息環境に対して回避または低減措置([4]堰ゲート操作および曝気などによる底質および水環境におけるDO濃度の維持)を検討する。
|
○ |
○ |
||||||||
|
アユ仔稚魚の迷入量の低減。稚魚~成魚の迷入の回避または低減。 |
迷入によって減少が予測される魚介類に対して回避または低減措置([5]計画取水量の5%の減少および[6]仔魚~成魚に対する迷入防止対策)を検討する。また、迷入した仔魚に対して回避または低減措置([7]回収・帰還装置による本川への帰還)。 |
○ |
|||||||||
|
アユなどの回遊性種の遡上、降下量の維持。 |
堰の存在によって減少が予測されるアユなどの回遊性種に対して回避または低減措置([8]魚道の設置による連続性の確保)を検討する。 |
||||||||||
|
流下仔アユの流下時間延長の回避または低減。 |
湛水区域の出現によって流下時間の延長が予測される流下仔アユに対して回避または低減措置([2]湛水区域面積の5%の減少および[9]魚道および澪筋の施工による流下時間の維持)を検討する。 |
||||||||||
|
汽水性魚介類の個体数の維持。 |
・堰上の淡水化によって消失する生息場所に対して回避または低減措置([3]堰ゲート操作による汽水環境の維持)を検討する。 ・堰下の生息環境に対して回避または低減措置([4]堰ゲート操作および曝気などによる底質およびDO濃度の維持)を検討する。 |
○ |
○ |
||||||||
|
トビハゼの生息個体密度の維持。 |
-(回避および有効な低減措置はない) |
○ |
|||||||||
|
干潟面積の確保。ヤマトシジミに代表されるろ過食者の平均生息密度の維持。 |
-(回避および有効な低減措置はない) |
○ |
|||||||||
|
止水性捕食者の個体数増加の抑制。 |
-(回避および有効な低減措置はない) |
○ |
○ |
||||||||
【立地・配置または規模・構造の配慮】
(ⅰ)湛水区域面積の5%の減少(類型区分I-2)
|
期待する効果:水生植物帯の保全および移行帯への依存度が高い生物群集の生息場所の保全 |
|
ゲート操作によって堰上の水位を低下し、湛水区域の計画面積を5%減少させる。 |
【留意点】 適切なモニタリングおよび環境保全措置としての評価を実施し、運用面などの見直しをおこなう。 |
(ⅱ)計画取水量の5%の減少(類型区分I-2)
|
期待する効果:アユ仔稚魚および稚魚~成魚の迷入量の低減。 |
|
計画取水量を5%減少し、取水口に向かう流速を低下させ、その影響範囲を減少させる。 |
|
【留意点】 適切なモニタリングによって環境保全措置の効果を確認し、運用面などの見直しをおこなう。 |
【施設・設備などの配慮】
(ⅲ)自然復元型工法を用いた低水護岸(類型区分I-1~3およびII-1~2)
|
期待する効果:水生植物帯の保全および移行帯への依存度が高い生物群集の生息場所の保全 |
|
|
(類型区分I-1~3)
|
(類型区分II-1~2)
|
【留意点】 ・類型区分II-1~2は現状では流水環境にあり、河岸は砂礫で構成されるため、水際は砂礫や自然石などを用いて多孔質環境を維持し、緩傾斜構造とする。 ・類型区分I-1~3の河岸は現状では砂泥で構成されるため、水際には砂泥を用いるものとし、緩傾斜構造とする。 ・両類型区分ともに移行帯は既存植生を維持するように配慮する。 ・アシハラガニなどのカニ類および両生類には表土に孔を掘って生息するものが多いため、移行帯は既存の土質を維持するように配慮する。 ・継続的なモニタリングを実施し、順応的管理をおこなう。 |
|
(ⅳ)迷入防止対策(類型区分I-2)
|
期待する効果:仔魚~成魚における迷入の影響の回避または低減 |
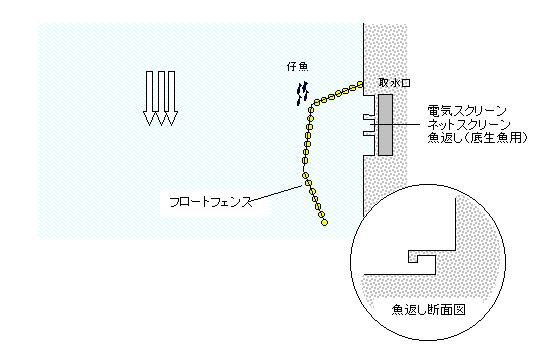 |
【留意点】 ・自力帰還が可能な遊泳魚(遊泳力のある稚魚~成魚)の迷入は、ネットスクリーンおよび電気スクリーンで防ぐ。 ・底生魚の迷入は魚返しで防ぐ。 ・フロートフェンスには非透水性の素材を用い、流下仔魚の迷入を防ぐ。取水口周辺に仔魚が出現する期間に運用する。 ・取水口の位置は、仔魚が流下する層をできるだけ避ける。 ・ネットスクリーンおよびフロートフェンスによる事業への影響(取水量への影響)に留意する。 ・継続的なモニタリングを実施し、順応的管理をおこなう。 |
(ⅴ)回収・帰還装置による本川への帰還(類型区分I-2)
|
期待する効果:仔魚の取水口への迷入に伴う減少の回避または低減 |
・取水口に迷入した仔魚を沈砂池内において集魚灯によって誘導し、フィッシュポンプなどを用いて回収して帰還水路を経て本川(取水口下流)へ帰還させる。 |
|
【留意点】 ・事業への影響(取水量への影響)に留意する。 ・継続的なモニタリングを実施し、順応的管理をおこなう。 |
(ⅵ)魚道の設置による連続性の確保
|
期待する効果:回遊性生物の遡上・降下阻害の回避または低減 |
|
|
【留意点】 ・魚道には多くの種類があり、目的に応じて選定するが、できるだけ堤体が遡上・降下の阻害にならないように留意する。 ・河川を移動する生物には、遊泳力の強弱および種々の生活型(遊泳性、底生性など)が存在するため、魚道利用が想定される生物種を整理し、その生活型および遡上能力を取りまとめた上で適切な魚道種類を選定し、設計をおこなう必要がある。 ・ここでは、主として遊泳魚用として右岸に呼び水式魚道、左岸には底生魚に効果が高い「自然河川の形状に近い緩傾斜魚道」を施工する例を示した。 ・継続的なモニタリングを実施し、順応的管理をおこなう。例えば、高い魚道機能を発揮できるように魚道流量の調節をおこなうとともに、堆砂による魚道機能の低下などに留意する。 |
(ⅶ)魚道および澪筋の施工による流下時間の維持
|
期待する効果:流下仔魚の流下時間延長の回避または低減 |
・湛水区域内に河床の掘削などによって澪筋をつくり、魚道に接続する流心を創出する。これによって湛水区域の上流端から魚道に向かう流線が発生し、流下仔魚をこの流線に乗せて湛水区域を流下させる。 |
|
【留意点】 ・事業への影響(取水量への影響)に留意する。 ・継続的なモニタリングを実施し、順応的管理をおこなう。 |
【管理・運用の配慮】
(ⅷ)堰ゲート操作による汽水環境の維持(類型区分I-1~2)
|
期待する効果:汽水性生物の生息場所の減少の回避または低減 |
|
・上げ潮時~満潮時にゲートを開け、堰上への海水遡上を可能とする。 ・堰下流域に対しては、維持流量を設定する。 |
【留意点】 ・事業への影響(塩害の発生)に留意する。 ・ゲート操作による手法は大きな効果は期待できないため、適切なモニタリングおよび環境保全措置としての評価を実施し、運用面などの見直しをおこなう。 |
(ⅸ)ゲート操作および曝気などによる底質および水環境におけるDO濃度の維持(類型区分I-1~2)
|
期待する効果:汽水性底生生物の生息場所の環境悪化の回避または低減 |
|
・定期的に(流量が豊富な時期)堰ゲートを開放し、堆積物をフラッシュアウトする。 ・高水温期に底層における曝気をおこなう。 |
【留意点】 ・フラッシュアウトによる濁りの発生。 ・曝気装置の効果がおよぶ範囲が狭いと考えられるため、適切なモニタリングおよび環境保全措置としての評価を実施し、手法などの見直しをおこなう。 |
[2]環境保全措置の妥当性の検証
環境保全措置案による影響の回避または低減措置の効果の検討結果は表II-3-5に示すとおりであるが、以下に示す理由から、環境保全措置(ⅰ)および(ⅱ)は採用しなかった。
・湛水区域面積の減少は、主として移行帯への影響の回避または低減に効果があるこ とを想定したが、検討の結果、5%の減少で得られる効果はわずかであると判断され た。
・計画取水量の減少は、主として汽水域の減少や重要な機能(動物の移動経路)への 影響の回避または低減に効果があることを想定したが、検討の結果、5%の減少では 得られる効果はわずかであり、取水量の減少に伴う事業への影響がより大きいと判 断された。
なお、本ケーススタディでは、事業計画の軽微な変更(湛水区域面積および計画取水量の5%の減少)を回避または低減措置の一つとしたが、効果の評価結果によっては、事業計画の変更(例えば、既存干潟への影響を回避するために堰の施工位置を変更するなど)も環境保全措置として検討する必要が生じる場合もある。
表II-3-5 環境保全措置の対象などへの回避または低減措置の効果の検討結果
|
環境保全措置の目標 |
【環境保全措置】 (ⅲ)~(ⅸ)の環境保全措置を講じる。 |
【参 考】 左記の環境保全措置に(ⅰ)および(ⅱ)を加える。 |
|
水生植物帯(ヨシ帯など)の構成種および生育面積の確保。 |
既往事例によれば、自然復元型工法を用いた低水護岸により、影響はほぼ回避される。
|
湛水区域面積の減少による効果はわずかである。
|
|
アシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類の種および個体数の維持。移行帯の地形、構成材および面積の確保。 |
既往事例によれば、自然復元型工法を用いた低水護岸により、影響はほぼ回避される。
|
湛水区域面積の減少による効果はわずかである。
|
|
ヤマトシジミの平均生息密度の維持。 |
既往事例によれば、堰ゲート操作および曝気装置による回避または低減措置の効果はわずかである。 |
-(湛水区域面積および計画取水量の5%の減少は回避または低減措置とはならない) |
|
アユ仔稚魚の迷入量の低減。稚魚~成魚の迷入の回避または低減。 |
既往事例によれば、取水口への迷入防止対策および回収・帰還装置により、影響はある程度回避される。 |
計画取水量の減少による効果はわずかである。 |
|
アユなどの回遊性種の遡上、降下量の維持。 |
既往事例によれば、魚道の設置により、影響はある程度回避される。 |
-(湛水区域面積および計画取水量の5%の減少は回避または低減措置とはならない) |
|
流下仔アユの流下時間延長の回避または低減。 |
粒子追跡シミュレーションにより、3倍の延長が想定される影響が1.5倍に低減される。 |
計画取水量の減少による効果はわずかである。 |
|
汽水性魚介類の個体数の維持。 |
既往事例によれば、堰ゲート操作および曝気装置による回避または低減措置の効果はわずかである。 |
計画取水量の減少による効果はわずかである。 |
|
トビハゼの生息個体密度の維持。 |
回避および有効な低減措置はない。 |
-(湛水区域面積および計画取水量の5%の減少は回避または低減措置とはならない) |
|
干潟面積の確保。ヤマトシジミに代表されるろ過食者の平均生息密度の維持。 |
回避および有効な低減措置はない。 |
-(湛水区域面積および計画取水量の5%の減少は回避または低減措置とはならない) |
|
止水性捕食者の個体数増加の抑制。 |
回避および有効な低減措置はない。 |
湛水区域面積の減少による効果はわずかである。 |
[1]環境保全措置の内容
上述の回避または低減措置においては、主としてヤマトシジミを主体とする汽水性動物群集への影響、トビハゼの現存量および干潟への影響に対して有効な環境保全措置を講じることができないものと判断された。したがって、これらに対しての代償措置を検討した。
代償措置として、環境保全措置の目標であるヤマトシジミやトビハゼの生息個体密度を保つことができる場所の造成、消失する干潟と同等程度の機能(水質浄化機能:濾過食者の生息密度の維持、その他干潟生物の生息場としての機能など)を持つ干潟の造成が必要であると判断できた。
以上より、環境保全措置の内容としては、ワンド状水路および人工干潟の造成により、ヤマトシジミを主体とする汽水性動物群集への影響、トビハゼ現存量および干潟への影響の緩和を図るものとした。なお、造成する人工干潟については、その地盤高や勾配、粒度組成などは既存の干潟を参考とし、また、最新の研究結果などを踏まえて計画することが重要である。
代償措置案の内容を表II-3-6に示した。
表II-3-6 代償措置案の内容(例)
|
環境保全措置の目標 |
環境保全措置(代償措置) |
対象とする類型区分 |
||||
|
II-2 |
II-1 |
I-3 |
I-2 |
I-1 |
||
|
ヤマトシジミ平均生息密度の維持。 |
消失が予測される生息場所に対して代償措置(代替生息場所:ワンド状水路)を検討する。 |
○ |
○ |
|||
|
トビハゼの生息個体密度の維持。 |
消失が予測される干潟に対して代償措置(人工干潟の造成)を検討する。 |
○ |
||||
|
干潟面積の確保。ヤマトシジミに代表される濾過食者の平均生息密度の維持。 |
消失が予測される干潟に対して代償措置(人工干潟の造成)を検討する。 |
○ |
||||
(ⅰ)ワンド状水路の造成(類型区分I-1~2)
|
期待する効果:汽水性生物の生息場所消失の影響緩和 |
|
|
【留意点】 ・河口堰下流の高水敷に造成する。 ・水路は蛇行させ、延長を長くとり、上流端および下流端を本川と接続することにより、淡水の流下および塩水の遡上を可能とする。 ・水路内の滞留を防ぐため、本川との接続箇所を複数設ける。 ・水路の底質は、ヤマトシジミの生息に適したもの(現状におけるヤマトシジミの生息場所の底質)とする(泥分30%以下)。 ・ヤマトシジミはT.P.-3m以浅に生息するため、水路の最大水深は3m以浅とする。 ・既存の高水敷を改変するため、この影響を十分に検討する必要がある。 ・継続的なモニタリングによって環境保全措置としての効果を確認しつつ、順応的管理をおこなう。 |
(ⅱ)人工干潟の造成(類型区分I-2)
|
期待する効果:トビハゼの生息地、干潟面積の減少および干潟の水質浄化機能の低下の影響緩和 |
|
・事業によって消失する干潟に対し、同質の人工干潟を堰下流汽水域に造成する。 |
【留意点】 ・人工干潟の造成面積は40,000㎡とし、既存干潟の消失面積と同じとする。 ・既存干潟の環境特性を十分に把握し、その特性を再現できるように留意することで、既存干潟に生息するトビハゼを主とする生物群集および水質浄化機能への影響を緩和する。 ・既存河床が消失するため、この影響を十分に検討する必要がある。 ・人工干潟の効果には不確実性が高いため、継続的なモニタリングを実施して順応的管理をおこなう。 |
[2]環境保全措置の妥当性の検証
今回のケースでは、ワンド状水路および人工干潟の造成を代償措置として採用したが、ワンド状水路の造成および人工干潟の造成は、いずれも新たな環境を創出し、既存の高水敷および河床の消失や改変を招くため、これらの代償措置による影響を十分に考慮する必要がある。これらの代償措置の効果・影響を以下に示す。
・ワンド状水路の造成によって高水敷の植生および生物群集の減少を招くが、水路の 造成によって得られる汽水性生物の生息場所および移行帯の創出効果がより大きい と考えられ、また、その移行帯には失われる植生および生物群集の一部が復元され るものと考えられる。
・人工干潟の造成面積は、消失する既存干潟の面積と同じ40,000㎡とする。造成場所 については、既存の生態系に大きな影響を及ぼすことがなく、かつ、造成した人工 干潟が安定するような場所を選定する。また、造成に際しては、既存干潟の環境特 性を十分に把握し、その特性を再現できるように留意することで、既存干潟に生息 するトビハゼを主とする干潟生物群集および水質浄化機能への影響の緩和を図る。
・人工干潟の造成によって既存の河床が一部消失し、ここに生息する生物群集の減少 を招くが、人工干潟の縁辺部から河床に連続する部分にこれらの生物群集の生息場 所の創出が期待できるものと考えられる。
・人工干潟およびワンド状水路の効果と影響には不確実性が伴うため、継続的なモニ タリングを実施して順応的管理*をおこなう必要がある。
*順応的管理では地域の開発や生態系管理を実験とみなす。計画を仮説として、モニタリングによって仮説の検証をおこない、その結果を見ながら新たな仮説を立てて、より良い方法を模索する。また、広く利害関係を持つ人々の間での合意を図るシステムを作ることが重視される。代償措置により生じる生態系の変化を完全に予測することは困難なため、今回のケースではこの考え方を適用することとした。新しい知見が得られた場合には柔軟に管理指針を変更し、多様な分野の研究者の議論を踏まえ、望ましい管理の方針・手法・計画を検討する。
環境保全措置の実施案は表II-3-7に示すとおりである。
表II-3-7 環境保全措置の実施案
|
措置の分類 |
回避または低減措置 |
代償措置 |
|
内 容 |
[1]自然復元型工法を用いた低水護岸による底質および地形の維持。 [2]堰ゲート操作による汽水環境の維持。 [3]堰ゲート操作および曝気などによる底質およびDO濃度の維持。 [4]仔魚~成魚に対する迷入防止対策。 [5]回収・帰還装置による本川への帰還。 [6]魚道の設置による連続性の確保。 [7]魚道および澪筋の施工による流下時間の維持。 |
[1]ワンド状水路の造成。 [2]人工干潟の造成。 |
|
実施方法
|
上記回避または低減措置の実施計画の作成および実施。 |
人工干潟の造成計画の立案および実施。 |
|
実施主体 |
事業者 |
事業者 |
|
効果と措置の不確実性の程度
|
[1]低水護岸設置面積のうち○%の地形が維持され、移行帯に生息・生育する種はほぼ保全される。 [2]ゲート操作による汽水環境維持の効果はわずかである。 [3]ゲート操作による底質維持の効果はわずかである。DO濃度は局所的に○mg/lの上昇が見込まれる。 [4]迷入防止対策により、迷入個体の○%が回避される。 [5]回収・帰還装置により、迷入個体の○%を帰還させることができる。 [6]少なくとも、遊泳性魚類の多くは魚道を利用する。 [7]流下時間の延長は○%に抑えることができる。 なお、定量的な効果予測が困難な事項も含まれるため、不確実性が大きい。 |
[1]ヤマトシジミに代表される汽水性底生動物群集の生息地が○m2が創出される。 [2]人工干潟として○m2が新たに創出される。 ワンド状水路および人工干潟の造成による効果は不確実性が大きい。 |
|
措置の実施に伴い生じる恐れのある環境影響 (新たに生じる影響) |
特になし。
|
ワンド状水路および人工干潟の造成区域に存在する植生、生物群集の消失。 |
|
措置を講じるにもかかわらず存在する環境影響(残る影響) |
定量的な効果予測は困難であるが、上記の回避または低減措置によって環境保全措置の目標を100%達成することはできない。 |
人工干潟の効果には不確定要素が多いため、継続的なモニタリングを実施して順応的管理をおこなう。 |
事業に伴う堰の存在、供用、河床の改変および干潟の消失などにより、各類型区分における生態系への予測および生態系が有する重要な機能(動物の生息場所の形成、水質浄化機能、移動経路および物質生産機能)への影響が予測されたため、湛水区域面積および計画取水量の5%の減少、自然復元型工法を用いた低水護岸、堰ゲート操作による汽水環境の維持、ゲート操作および曝気などによる底質および水環境におけるDO濃度の維持、迷入防止対策、回収帰還装置によるアユ仔魚の本川への帰還、魚道の設置による連続性の確保、魚道および澪筋の施工による流下時間の維持を環境保全措置として検討した。
検討の結果、回避または低減措置については、その効果の定量的な予測は困難であったが、既往事例に基づき、水生植物帯(ヨシ帯など)への影響(減少)およびアシハラガニ、オオヨシキリおよび両生類の種および個体数への影響はほぼ回避できるものと判断した。同様にアユ仔稚魚の迷入および稚魚~成魚の迷入、アユなどの回遊性種の遡上・降下量への影響(減少)、流下仔アユの流下時間延長においてもある程度の回避ができるものと判断した。また、湛水区域面積および計画取水量の5%の減少については、これにより得られる効果はわずかであり、取水量の減少に伴う事業への影響がより大きいと判断したために採用しなかった。
トビハゼの現存量への影響(減少)、干潟面積の減少およびそれに伴う水質浄化機能の低下に有効な回避または低減措置を講じることは困難と判断した。
したがって、トビハゼの現存量の減少、干潟面積の減少およびそれに伴う水質浄化機能の低下に対しては、ワンド状人工水路および人工干潟の造成を代償措置として講じることとし、回避または低減措置と併せて環境保全措置とした。
代償措置に関しては、ワンド状水路の造成によって高水敷の植生および生物群集の減少を招くが、水路の造成によって得られる汽水性生物の生息場所および移行帯の創出効果がより大きいと考えられ、また、その移行帯には失われる植生および生物群集の一部が復元されると考えられることから代償措置として採用した。
人工干潟については、造成面積を既存干潟の消失面積と同じとし、既存の生態系へ大きな影響を及ぼさず、かつ、人工干潟が安定するような場所に造成するものとした。また、既存干潟の環境特性を十分に把握することにより、既存干潟に生息するトビハゼを主とする干潟生物群集および水質浄化機能への影響の緩和を図るものとした。さらに、人工干潟の造成によって既存の河床が一部消失し、ここに生息する生物群集の減少を招くが、人工干潟の縁辺部から河床に連続する部分にこれらの生物群集の生息場所の創出が期待できるものと判断した。
なお、ワンド状水路および人工干潟の効果と影響には多くの不確実性が伴うため、継続的なモニタリングを実施して順応的管理をおこなう。
また、止水性捕食者については、湛水区域が出現する限りその個体数の増加を抑制することは困難である。これらの種のみを駆除するには多大な費用と労力が必要なうえ、効果に関する不確実性が大きい。したがって、先に示した水生植物帯の面積確保などの措置を講じて在来種の増加、保全を図り、事後モニタリングにより監視を続ける必要がある。
今回の環境保全措置は、その効果が定量的に予測できないものが大半のため、不確実性が大きい。したがって、適切なモニタリングをおこなって調査結果を整理、考察し、消失する汽水域や干潟が有する機能などを十分に検討し、順応的管理をおこなうことが重要であるとともに、将来における事業計画に結び付けるべくデータの蓄積に努めることも必要である。
事後調査の実施案は表II-3-8に示すとおりである。
表II-3-8 事後調査の実施案
|
回避または低減 |
代 償 |
||
|
環境保全措置の内容 |
|
|
|
|
調査項目および調査内容 |
調査地域内の状況 ・低水護岸における生物の生息状況。 ・堰上流域における塩分の分布。 ・堰上下流域における底質およびDO分布。 ・取水口における迷入量。 ・仔魚類の回収帰還装置による帰還率。 ・魚道の利用状況および遡上率。 ・堰上流域における流速分布。 ・湛水区域内の魚類相。 |
造成したワンド状水路および人工干潟とその周辺 ・物理・化学的項目 (水深、地盤高、勾配、水質、底質、流動) ・生物および機能に関する項目 (植生、底生生物、魚介類、干潟の水質浄化能力) |
|
|
調査範囲 |
対象範囲全域 |
造成したワンド状水路および人工干潟とその周辺 |
|
|
調査実施時期と期間
|
・各項目ともに四季調査を原則とするが、対象とする生物の出現時期などにより、増減する。 ・調査期間はいずれも○年間とする。 |
・各項目ともに四季調査とする。 ・調査期間は、ワンド状水路および人工干潟の効果が確認できるまでの期間とする。 |
|
|
調査方法 |
アセス実施段階における現地調査方法に準ずる。 |
||
|
調査結果の取り扱い |
調査結果の公開およびインターネットによる公表。 |
||
|
不測の場合の対処方法 |
不測の事態に陥った原因を調査し、事業が原因と判断される場合には、その影響を回避または低減(場合によっては代償)する環境保全措置を計画、実施する。 |
||
|
実施体制 |
事業者 |
事業者 |
|
事後調査報告例は表II-3-9に示すとおりである。
表II-3-9(1) 事後調査報告(堰供用後○年目)例
|
環境保全措置の内容 |
|
|||
|
調査項目 |
低水護岸における生物の生息状況 |
堰上流域における塩分の分布 |
堰上下流域における底質およびDO分布 |
取水口における迷入量 |
|
効果の確認 |
・低水護岸周辺にはヨシを主体とする植物群落が確認され、その範囲は○㎡であり、事業前の○%であった。 ・低水護岸周辺には両生類およびアシハラガニの生息が確認され、確認された種には事業前との差は認められない。また、アシハラガニおよびオオヨシキリの確認個体数は事業前の○%であった。 |
ゲート操作時には堰上に汽水環境の存在が確認され、その範囲は○mであり、事業前の汽水域の範囲の○%であった。 |
・堰上下流域にはシルト質の堆積が確認され、CODは2.5~6mg/g、強熱減量は15~17%であり、事業前よりも上昇した。 ・曝気装置周辺のDOは8~10mg/Lであり、その範囲は装置から約10mであった。 |
・取水口への仔アユ迷入量は日当たり○~○万尾であり、全流下量に対する比率は○%であった。 ・稚魚~成魚の迷入については、成魚の迷入は確認されなかった。また、オイカワ、ヨシノボリ類などの小型個体が日当たり○~○尾迷入していることが確認された。 |
|
追加措置 |
特になし。 |
特になし。 |
・シルト質の堆積が確認されたため、ゲート操作の頻度を上げることを検討する。 ・曝気装置の効果がおよぶ範囲が狭いため、装置の増設を検討する。 |
特になし。 |
|
今後の対応 |
特になし。 |
特になし。 |
特になし。 |
最新の迷入防止装置が開発される都度、追加施工を検討する。 |
|
今後の事後調査計画 |
- |
- |
追加措置に応じたモニタリングを計画、実施する。 |
迷入防止装置を追加する場合には、それに応じたモニタリングを計画、実施する。 |
表II-3-9(2) 事後調査報告(堰供用後○年目)例
|
環境保全措置の内容 |
|
||
|
調査項目 |
仔魚類の回収帰還装置による帰還率 |
魚道の利用状況および遡上率 |
堰上流域における流速分布 |
|
効果の確認 |
回収帰還装置による仔アユの帰還率は○~○%であった。 |
・魚道は遊泳魚~底生魚および大型魚~小型魚までに利用されていることが確認された。 ・ヨシノボリ類、アユおよび小卵型カジカに標識放流をおこなった結果、魚道遡上率は○~○%であった。 |
堰上の澪筋における流速は○~○cmであり、湛水区域の平均流速の○倍であった。 |
|
追加措置 |
特になし。 |
特になし。 |
特になし。 |
|
今後の対応 |
特になし。 |
最新の魚道が開発される都度、魚道の改善を検討する。 |
特になし。 |
|
今後の事後調査計画 |
- |
魚道の改善をおこなう場合には、それに応じたモニタリングを計画、実施する。 |
- |
表II-3-9(3) 事後調査報告(堰供用後○年目)例
|
環境保全措置の内容 |
|
|
|
調査項目 |
水深、地盤高、勾配、水質、底質、流動 |
植生、底生生物、魚介類、干潟の水質浄化能力 |
|
効果の確認 |
・ワンド状水路の水深は○~○mであり、造成当時との変化はほとんどなかった。 ・人工干潟の地盤高はT.P.○~○mであり、勾配も含めて事業前の既存干潟と同程度であった。 ・ワンド状水路の水質、底質は事業前の汽水環境がほぼ再現されていた。 ・人工干潟の底質は、事業前の既存干潟とほぼ同様であった。 ・ワンド状水路における流速は○~○cm/sであり、本川の河岸部よりも小さかった。 |
・ワンド状水路内には、ヤマトシジミが○個体/㎡の密度で生息していることが確認され、この密度は事業前の高密度分布域のそれと同程度であった。また、汽水性底生動物も事業前と同程度の密度で生息していることが確認された。 ・人工干潟には、事業前の既存干潟と同様の底生動物が確認された。また、その生息密度も同様であったが、トビハゼの生息は確認されなかった。 ・人工干潟を利用するシギ・チドリ類の数および種には事業前と大きな差はみられなかった。 ・人工干潟における水質浄化能力を測定した結果、単位面積当たりの浄化能力は事業前の既存干潟と同程度であった。 |
|
追加措置 |
特になし。 |
特になし。 |
|
今後の対応と事後調査計画 |
人工干潟の安定性には検討の余地があること、また、トビハゼの生息が確認されなかったことから、学識経験者による検討会を設置し、今後の追加措置を念頭においた人工干潟造成(消失した干潟と同質)の検討およびそれに応じた今後の事後調査計画の見直しをおこなう。 |
|