廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方(平成13年9月)
廃棄物分野における戦略的環境アセスメントの考え方TOPへ戻る
第2章 廃棄物分野におけるSEAの考え方
1、計画等の策定プロセスとSEAの関係と手続きの基本的考え方
計画等の策定という最終的な意思決定は、その策定プロセスの中で、経済性、地域性、技術的可能性などの要素に、適切な環境配慮がなされるようSEAの結果を反映しつつ、総合的に判断されるものである。
SEAの実施主体は、廃棄物処理に関する計画等の策定主体である都道府県や市町村である。
SEAにおいては、スコーピング、調査・予測・評価の実施、評価文書の公開、住民・専門家等や環境影響評価担当行政機関からの意見聴取、複数案の比較検討等が実施される。SEAの手続きを具体的に考えるに当たっては、計画等の策定プロセス自体の手続きと調整を図りつつ、柔軟に対応すればよいと考える。
1) 廃棄物分野における計画等の策定プロセスとSEAの関係
計画やプログラムの策定は、そのプロセスの中で、経済性、地域性、技術的可能性などが幅広く検討され、進められているが、そこに、SEAの結果を反映し、適切な環境配慮を組み込むことが重要である。この際、計画等の策定という最終的な意思決定は、環境面だけでなくこれらを総合的に判断して行われるものである。
廃棄物分野の計画等策定プロセスとSEAの関係は、図-2.1に示すとおりである。SEAは、計画等の策定プロセスに並行して、計画等による環境への影響を調査・予測・評価するものであり、計画等策定プロセスとは独立した手続きとして実施されることが基本である。
2) 手続きの基本的考え方
(1) SEAの実施主体
SEAの実施主体は、廃棄物処理に関する計画等の策定主体である都道府県や市町村である。
(2) 必要な手続き
SEAにおいては、スコーピング、調査・予測・評価の実施、評価文書の公開、住民・専門家等や環境影響評価担当行政機関からの意見聴取、複数案の比較検討等が実施される。
スコーピングは、SEAの検討範囲を明確にするとともに、調査・予測・評価の項目や手法を検討・設定するものであり、評価文書を公表してから調査・予測等の不足を指摘され、手戻りとなる事態を防ぐために重要な手続きである。
その後、調査・予測・評価を実施し、計画等による環境影響について複数案を比較評価し、また、それぞれの複数案の環境配慮事項を明らかにすることとなる。
また、住民・専門家等や環境影響評価担当行政機関が広範に保有している環境情報(住民等の思い描く環境の将来像等を含む)を十分収集し、環境配慮を適切に行うためには、調査・予測・評価の結果を評価文書としてとりまとめ、公表し、住民・専門家等や環境影響評価担当行政機関の意見を聴取することが必要である。
これらの手続きを具体的に考えるに当たっては、計画等の策定プロセス自体の手続きと調整を図りつつ、柔軟に対応すればよいと考える。
例えば、審議会への諮問・答申など計画等の策定プロセス自体の手続き等とSEAの手続きが効率よく進められるよう、計画等の策定プロセスにおけるパブリックコメント等の手続きと並行して意見聴取を行うなどの工夫も考えうる。
なお、スコーピングについては、必ずしも環境影響評価法の公告・縦覧、意見書の提出という形式にとらわれる必要はなく、公開・意見聴取の方法としてインターネットや電子メールを活用したり、住民・専門家等の代表から意見を聴取する方法等も検討する余地がある。
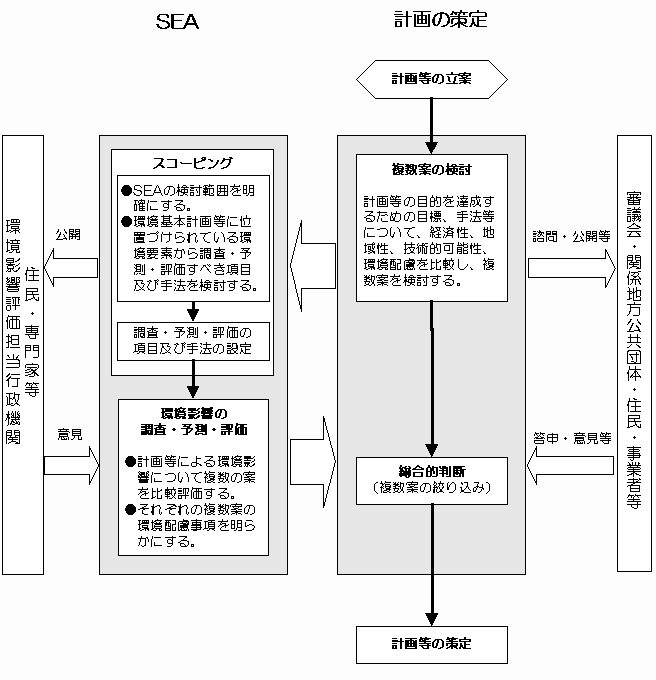
図-2.1:廃棄物分野の計画等の策定とSEAの関係
2、スコーピング
スコーピングは検討範囲を明確にする上で重要であり、実行可能な範囲をカバーした上で環境保全上重要な複数案を検討することが必要である。
また、環境基本法で扱われている環境要素の中から、スコーピング手続を通じて計画等の内容や地域特性に応じて論点を絞り込み、メリハリの効いた調査・予測・評価を行うことが必要である。
SEAは、意思決定の自由度・抽象度が高く、幅広い実行可能な選択肢が存在する段階で、環境の観点も踏まえて望ましい案を選択するための手続きであり、複数案の比較検討を行うことが必要である。また、複数案は、実行可能な範囲内をカバーした上で、環境保全上の観点から特に重要な案について検討することが必要である。
廃棄物分野の計画等といっても、内容は様々であり、また、地域の状況に応じて前提となる制約条件も多様であるため、複数案の設定は、個々の計画等ごとに検討がなされることになる。
なお、立地選定については、環境影響評価法の検討過程において、立地決定の以前に立地に係る複数案を含めて公表して議論を行うことに関して、我が国の場合、環境影響以外の利害関係を含んだ議論をより際だった形で誘発するおそれや事業内容によって地域間の対立を生じ、混乱を発生させる恐れがあるという指摘がなされている。しかし一方で、近年の情報公開法の制定、パブリックコメント制度の導入、政策評価の導入などにおいて、透明性の向上・アカウンタビリティの確保の動きが見られるほか、廃棄物処理法に基づき策定された基本方針において、「国民の環境に関する意識の高揚等に対応して、廃棄物の処理体制の確保に当たっては、施策の安全性等に関する情報公開を一層進め、地域住民の理解を深めていくことが必要である。」と位置づけられている。参考資料1-3に示すように、実際に立地に係る複数案を含めて公表し、議論が行われている案件も見られる。このような事例を積み重ねることなどにより、指摘された懸念を払拭するよう努めることが必要であると考えられる。また、既に施設の用地を確保しており予定地以外に確保できる用地がないなどの前提条件から、計画等の策定上、立地の複数案を検討する余地がない場合は、立地の複数案に係るSEAは必須ではなく、そのような事情を明らかにしつつ立地以外の複数案を比較することが考えられる。
また、具体的な環境保全努力を計画等に位置づける場合には、これを複数案に盛り込み、その効果を比較評価することも考えられる。
2) 調査・予測・評価の項目及び手法の選定
SEAでは、スコーピング手続を通じて、環境基本法で取り扱われている環境要素を対象に調査・予測・評価の項目(以下、「評価項目」という)を絞り込むことになる。計画等の性格から、予測評価が困難であったり、事業実施段階での検討に譲るべきものがあることなどに留意しつつ、計画等の決定内容に影響を与えうる重要な環境項目を選定し、それを適切にとらえるための手法を明らかにする必要がある。
例えば、都道府県全域の廃棄物処理のあり方を計画内容とする都道府県廃棄物処理計画のような場合は、計画の内容の性格から処理施設ごとの環境影響の予測をすることは困難であり、むしろ都道府県全体のマクロな視点に立って広域的・累積的な影響をトータルにみることがSEAで求められていると考える。その際、図-2.2に示すように、地球環境、大気・水等、物質循環、自然環境というように環境要素を大括りに捉え、それぞれ代表的な評価項目について調査・予測・評価を行うという方法もありうる。
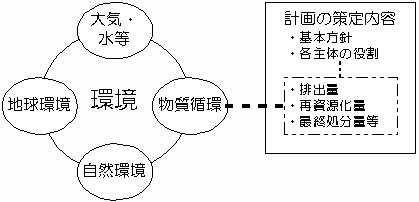
図-2.2:廃棄物分野におけるSEAの検討範囲
ここで、「物質循環」の評価としては、計画等によって廃棄物の排出量が十分抑制されるか、再資源化が十分なされるかについて検討することとし、排出量等を評価項目と考えることができる。
しかしながら、これらは計画等の目標そのものとして検討されることから、SEAにおける検討の重複を避けるため、SEAの前提条件として取り扱うことも考えられる。この場合、SEAでは、排出量等の目標が盛り込まれた計画等の案について、例えば地球環境等の別個の視点から環境配慮が十分であるかどうか評価することとなる。ただし、このような整理をする場合でも、「物質循環」に係る評価項目として、排出量等ではなく、天然資源の消費量の削減等を立てて、SEAで検討することは可能と考える。
3、環境影響の調査・予測・評価
スコーピングにより決定された評価項目及び手法に基づき、環境影響の調査・予測・評価を行う。計画等の諸元や前提条件の不確実性に応じた手法を用いることが重要である。また、複数案の比較検討、システム全体のトータルな視点での評価などが重要である。
1)調査について
廃棄物分野のSEAにおいては、計画等の内容がもたらす環境影響そのものの調査よりも、その前提となる予測の対象となる施策の技術的な特性や予測のための原単位等を把握するための調査が重要となる場合がある。また、循環資源の再資源化のプロセスにおいて発生する環境負荷の算定では、詳細な調査が必要となると考えられる。
また、計画等によっては、策定する内容からして詳細な現地調査を網羅的に行う必要がない場合もある。基本的には地域の環境状況を示す既存の環境情報を収集・整理し、効果的に活用することが重要である。なお、既存の環境情報では不明ないし不確実な点がある場合には、必要に応じ的を絞って現地調査等で補完することは必要である。
個別の一般廃棄物処理施設整備計画の構想段階で相当程度熟度が高まっている段階での意思決定に対するSEAでは、より詳細な調査を実施することができると考えられる。
2) 予測手法について
廃棄物分野のSEAにおいて、処理施設の規模等事業の詳細な諸元が不明な場合には、シミュレーションにより汚染濃度を精密に予測することが困難であり、また、そのような精緻な予測は、複数案について意味のある比較が行われるという観点からは必ずしも必要がない。このような場合には、環境の負荷の総量を大づかみに把握することにより、環境影響の程度の違いを明らかにするなどの手法が用いられることも考えられる。
また、定量的な予測が困難な場合は、定性的な予測(例:影響のある・なし、現況からの変化の程度等を明らかにする)を行うことも、意味があると考えられる。
3) 予測の不確実性
人口や産業活動等の予測の前提となっている諸条件には、諸制度の整備や技術進歩などにより将来的な動向が左右されるため、不確実性を含んでいる。また、予測手法についても、不確実性を含むものである。
予測・評価の記述にあたっては、その不確実性について言及するとともに、単一の前提条件、予測手法による単一の結果に固執することなく、必要な場合には不確実性を見込んで、複数のシナリオを設定し、幅をもった予測を行うなどの工夫を行うことが考えられる。
4) 評価の視点
(1) 複数案の比較検討SEAでは、複数案について比較評価を行うことが必要である。ただし、必ずしもSEAで1つの案に絞り込む必要はなく、いくつかの案の環境保全上のメリット・デメリットの比較を行い、案の選択は、計画等の策定プロセスの総合的な判断に委ねることも考えられる。
(2) 環境の改善効果も含めたトータルな視点からの評価
SEAでは、個々の施設ごとでは評価することが困難な、広域的、累積的な影響を考慮して、廃棄物処理システム全体のトータルな環境負荷の低減を評価することが重要である。
(3) 環境要素間のトレードオフ関係を評価する視点
複数案を比較するにあたっては、個々の環境要素をそれぞれ別個にチェックして判断するだけではなく、環境要素間のトレードオフ関係について評価する視点が重要である。
例えば、焼却量を増やす場合には、最終処分量を減らすことができるが、二酸化炭素やダイオキシン類の排出に対する対策が必要となることから、総合的に判断をしてどのような評価をしていくかを検討する。
このようなトレードオフ関係を評価するためには、複数案と評価項目の組み合わせからなるマトリックス(各案の得失の一覧表)に整理することも有用である。
(4) 評価軸の重要性
上述のように、廃棄物分野のSEAでは、単に環境要素ごとに予測評価をするだけではなく、環境要素間のトレードオフを含めて廃棄物処理システムのトータルな環境負荷の低減を図る必要がある。この際、どのようなシステムが望ましいかを判断するに当たっては、地域における環境保全のあり方について、価値判断の評価軸があることが望ましい。例えば、地域の環境基本計画や環境管理計画などがあれば、それを評価軸とすることが考えられる。
5) 評価のベースライン
事業実施段階の環境アセスメント制度では、事業が実施されなかった場合の環境の状態の推移等を評価のベースラインとして明らかにしている。
SEAにおいても同様に、計画等に基づく事業が行われなかった場合の環境の状態の推移等を評価のベースラインとして明らかにし、複数案と比較することが必要である。
この際、都道府県の廃棄物処理計画のようなケースでは、仮に既存の処理のあり方をそのまま続けた場合の目標年次における環境負荷の予測と、複数案のシナリオに沿った場合のそれとを比較するということが考えられる。
しかしながら、廃棄物分野では諸制度の整備や技術進歩等の変化が急であることを考慮すると、既存の処理のあり方を踏襲したとしても、従来のトレンドが単純に延長されるとはいえず、ベースラインも、さらに精緻な議論をして、仮定に基づき幅をもたせるなどの工夫をすることが考えられる。