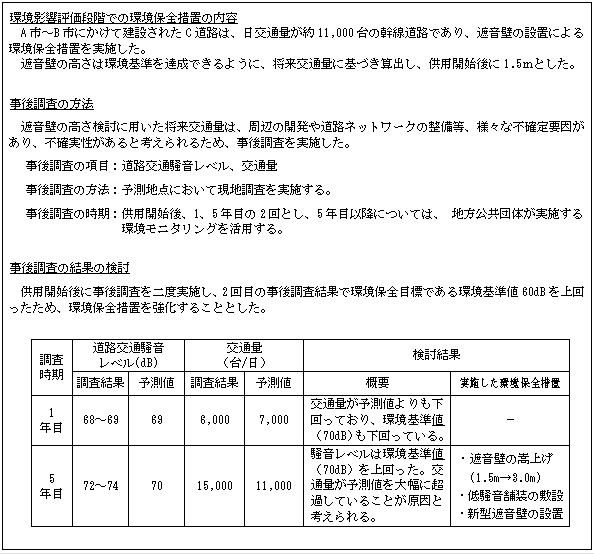大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会報告書
大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)<環境保全措置・評価・事後調査の進め方>(平成14年10月)
大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(III)TOPへ戻る
2-2 騒音・振動・低周波音
「1 総論」においては、騒音分野の環境影響評価を進めるに当たっての主に環境保全措置・評価・事後調査の進め方についての基本的な考え方について示した。
ケーススタディでは、環境影響評価における様々なケースを想定し、環境保全措置の検討の考え方や事後調査の方法等について検討し、明らかにした。
なお、このケーススタディは現実の情報によるものではなく、あくまでも環境影響評価を行う上で考え方を整理するために想定した一例であり、必ずしもここで示す手法のみを推奨するものではない。
【ケーススタディ1】保全方針の設定
【ケーススタディ2】環境の状態が既に悪化している場合の環境保全措置
【ケーススタディ3】複数の環境保全措置の検討
【ケーススタディ4】効果に係る知見が不十分な環境保全措置の実施と事後調査
【ケーススタディ5】予測の不確実性を見込んだ環境保全措置の強化
【ケーススタディ6】事後調査結果のフィードバック
【ケーススタディ1】保全方針の設定
●テーマ
保全方針の設定は、環境への配慮をどのような視点で実施するのかを明らかにするために行うものであり、事業特性や地域特性を勘案して適切に設定する必要がある。
ここでは、地下鉄事業における鉄道振動に対する保全方針の設定の例を示す。
●鉄道振動に係る保全方針の設定例
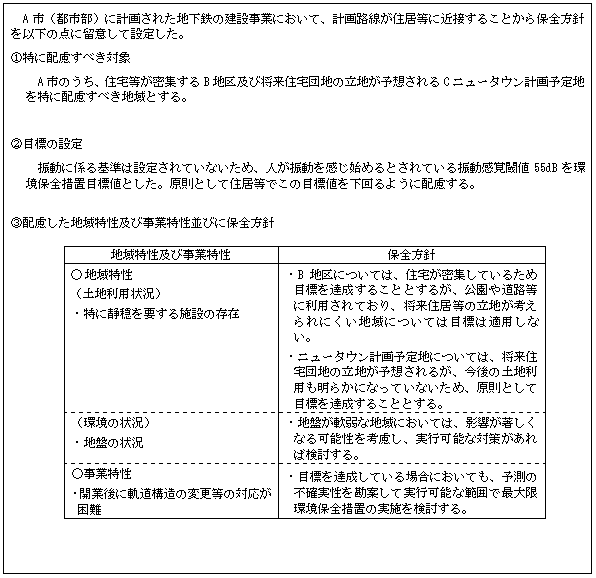
【ケーススタディ2】環境の状態が既に悪化している場合の環境保全措置
●テーマ
都市部の幹線道路の沿道では、騒音に係る環境基準値を現状で上回っており、環境の状態が既に悪化していると考えられる場合がある。事業を実施するうえで、工事用車両及び関連車両の走行ルートとしてそのような道路を選定した場合の環境保全措置の考え方の例を示す。
●騒音に係る環境基準値を上回っている道路を工事用車両が走行する場合の環境保全措置の検討例
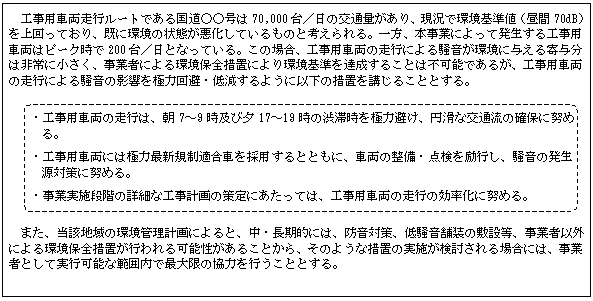
【ケーススタディ3】複数の環境保全措置の検討
●テーマ
騒音分野における環境保全措置は、伝搬経路対策及び発生源対策が基本となる。また、実施者の立場では、事業者が実施する対策と事業者以外の者が主に実施する対策に分類される。
環境保全措置が複数存在する場合、効果の確実性や実施主体等を総合的に勘案して、各環境保全措置の採用を検討することになる。
●新幹線鉄道騒音に係る複数の環境保全措置の検討例
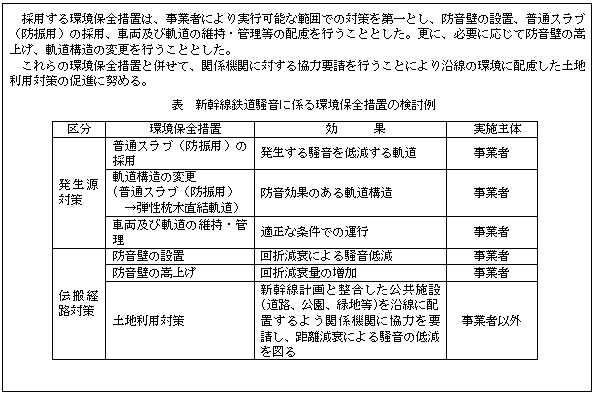
【ケーススタディ4】効果に係る知見が不十分な環境保全措置の実施と事後調査
●テーマ
効果に係る知見が明らかな環境保全措置だけでは十分に環境影響を回避・低減できない場合、効果に係る知見が不十分な環境保全措置を実施することがある。
ここでは、高速道路の新設事業において、並行する既存道路の影響が著しく、道路沿道における騒音に係る環境基準が達成できない場合を例として挙げる。
●高速道路の新設事業における、効果に係る知見が不十分な環境保全措置(二層式排水性舗装)の検討例
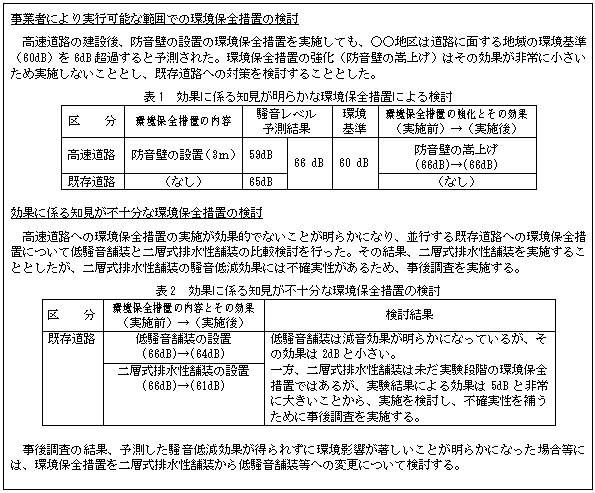
【ケーススタディ5】予測の不確実性を見込んだ環境保全措置の強化
●テーマ
環境影響の回避・低減を図るために環境保全措置を実施し、基準・目標を達成することが予測結果から確認されたものの、予測の不確実性を見込んで環境保全措置を強化する必要がある場合が考えられる。地下鉄事業における鉄道振動の事例を示す。
●鉄道振動について、予測の不確実性と事業特性を勘案して、環境保全措置を強化した事例
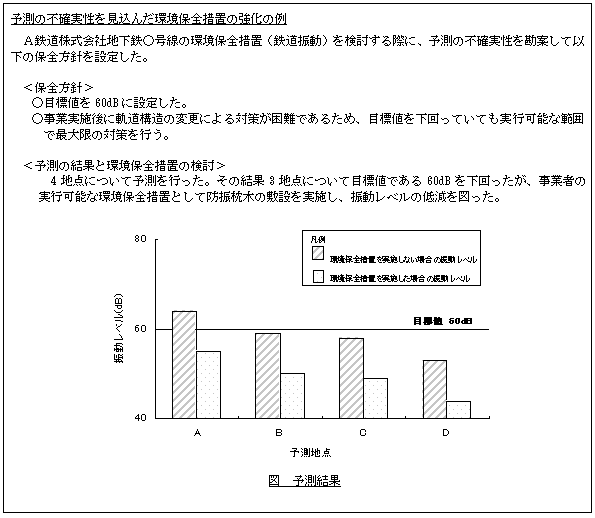
【ケーススタディ6】事後調査結果のフィードバック
●テーマ
事後調査は予測の不確実性を補う等の観点から実施し、環境影響が著しいことが明らかとなった場合には、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施するものである。道路事業における事例を示す。
●幹線道路の供用後に事後調査を実施して環境保全措置を強化した例