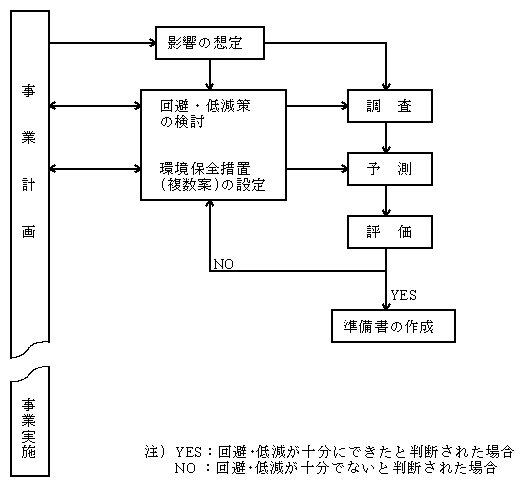生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)
第1章 総論
1-1 海域生態系の特徴
海域、特に沖合では主に植物プランクトンが基礎生産を担うことから、樹木等の大型植物が基礎生産を担う陸域の生態系に比べると、系の回転速度(生産速度/生物量)が一般に大きい。また、陸域では大型植物を食物連鎖の出発点とする腐食連鎖(detritus
foodchain)が卓越するが、海域では生食連鎖(grazing foodchain)のウェイトが大きいことも特徴のひとつである。ただし、海藻の生産の寄与の大きいごく沿岸では陸域に類似の特徴を示す。さらに、基礎生産者である植物プランクトンや主に一次消費者である動物プランクトンは、海の流れとともに常に移動し、それに伴って多くの生物も移動する上、海生生物には成長の過程で生活型(浮遊・遊泳・底生・付着など)や食性を変化させるものが多い。
一口で言えば、海域生態系は変化の大きなフローの生態系、陸域生態系は安定した植物群落に支えられたストックの生態系といえよう。
一方、海域生態系のもうひとつの特徴として、海域には陸域のような長期的に安定した植物群落がないため、動物の分布が海底の基質の状態(基質の固さなど)や外海と内湾といった物理化学的な環境要素に大きく規定されることがあげられる。
海域生態系の環境影響評価にあたってはこのような特性に配慮して、次のことに留意することが重要と考えられる。
- 対象海域の地形と海底の基質
- 生物の生活史と成長や季節による移動
- 捕食、被食の関係
- 物質循環やエネルギーフロー
1-2 注目種(群集)と機能
海域生態系はきわめて多くの環境要素と生物が複雑に関連して構成されている。また、海の流れや生物の移動に伴って流動的に変化しやすいものでもある。このような生態系について、事業による環境影響評価を行うためには生態系の構造を十分に調査する必要がある。しかしながら、生態系のすべてを調査し理解するには多大な労力と時間を要する上、現在の科学的知見では十分に把握しきれていないことが多い。したがって、生態系の調査・予測・評価手法の検討にあたっては上位性・典型性・特殊性の視点から注目種(群集)を選定し、それらに対する調査・予測の結果を通じて生態系に対する環境影響評価を行う方法について検討することとした(基本的事項で例示された方法)。
注目種(群集)を通じた環境影響評価では事業影響による注目種(群集)の変化が重要であり、選定した注目種(群集)の変化や存続の可否を予測することによって、海域生態系全体への影響を予測・評価することとなる。その際には、注目種(群集)の変化や存続の可否だけでなく、注目種(群集)の変化に伴う他の生物種(群集)の変化にも配慮して予測を行う必要がある。
また、海域には生物生産や水質浄化など重要な機能があり、それらの機能は生態系の健全性と密接に関連している。海域生態系の評価にあたっては対象海域の生態系が有する機能を把握し、重要な機能については調査・予測・評価を行う必要があり、その方法について併せて検討することとした。
これらの注目種(群集)や生態系の機能への影響を検討するためには、昨年度の報告書で述べたように、まず、スコーピングの段階で、当該海域における海底の基質や生物などから海域の類型区分を行い、その上で事業による影響要因も踏まえて、重要な類型を選定するとともに評価の対象とすべき注目種(群集)と重要な機能を選定することが必要となる。
1―3 現況と予測・評価
海域生態系の環境影響評価にあたっては、現況(現在の環境と生態系の状態)を知り、影響要因との関係から予測・評価を行うこととなる。ここで問題となるのが、どのような状態を現況とするかである。わが国の沿岸にはほとんどくまなく人為的影響が及んでおり、当該事業による環境影響との複合的影響が発生することも考えられる。また、過去からの開発等により、自然環境が既に大きく変化している場合もある。
このような場合、事業特性や地域特性に応じて、周辺の環境影響要因との複合や過去からの環境変化とその影響要因にも配慮して環境影響評価の実施段階の調査を行い、その結果を踏まえて現況を認識し、当該事業にかかわらない将来の環境の変化なども予想しながら予測・評価にあたる必要がある。
1-4 調査・予測・評価のあり方
環境影響評価とは事業者が事業の実施による環境影響について自ら適正に調査・予測・評価を行い、その結果に基づいて環境保全措置を検討することなどにより、その事業計画を環境保全上より望ましいものとしていく仕組みである。アセスメントの最終的な目的は評価であることから、何を評価すべきかという視点を明確にして調査・予測・評価を進めることが重要である。したがって、まず、スコーピング段階で調査・予測・評価手法を選定する際に、地域の環境特性、地域のニーズ、事業特性等から保全上重要な環境要素は何か、どのような影響が問題になるのか、保全対策の基本的な方向性はどうあるべきかなどについて検討した結果を十分踏まえて、まず第一に「生態系」項目で重点を置いて評価すべき影響の内容を設定する。次にその評価を行うために適切な予測手法、そして、その予測に必要な調査項目及び調査手法を決定するというプロセスで検討する必要がある。そして、環境影響評価の実施段階の調査等で得られた情報を基に項目・手法を柔軟に見直しながら、設定した目的とシナリオに沿って調査・予測・評価を進めていくことが必要である。
このように、海域生態系の調査・予測・評価にあたっては、生態系の現況と事業による環境影響を十分に把握・検討した結果、どのような点に重点を置いたのか、どのように考えて予測・評価を行ったのかなど、単に環境影響評価の結果を述べるだけでなく、結果を導いたプロセスと事業者としての見解を準備書等において述べることが特に重要である。この点は、従来の目標達成型の環境影響評価とは大きく異なる。また、より良い合意形成のためには、アセスメントのそれぞれの段階でその時点の計画熟度を踏まえた事業計画の内容(必要性、効果、計画策定の経過等も含む)や環境保全・環境の創出に向けての方針について、事業者の考え方を十分説明していくことも大切である。
さらに、調査・予測・評価の内容を適切なものとしていくために有識者や委員会などから適切な助言や指導を得ること、影響評価の過程をわかりやすく述べた準備書・評価書を創意工夫することなどの努力も望まれる。
1-5 海域生態系と他の環境影響評価項目との関係
「植物」「動物」「地形・地質」「水環境」「大気環境」など、他の環境影響評価項目で対象とする環境要素はそれぞれ「生態系」を構成する要素でもある。このため、スコーピング段階と同様に、生態系の調査・予測・評価に際しても、それらの関連する他の項目と情報を共有し、環境影響評価の実施段階の調査・予測作業についても十分な連携を図りながら進めることが必要である。
例えば、海域生態系では、流れ、地形変化、水質、底質などの環境要素の変化予測や物質循環の機能に関する検討などは内容的に「水環境」項目における作業と関連が深く、対象案件の特性に応じて、双方の分野における調査・予測の作業を統合して検討することも必要である。
なお、注目種(群集)を通じて生態系への環境影響を評価するアプローチと動物・植物項目については共通する調査項目等が多く、調査を一体的に行うことが重要である。その一方で、動物・植物項目においては学術上もしくは希少性の観点から重要な種(群集)の存続が主な評価項目になり、調査内容も限定され、詳細で精度の高いものが要求されるのに対して、生態系項目では注目種を通して生態系全体への影響を把握することを目的としており、評価の視点や調査・予測内容に違いが生じることに留意する必要がある。
スコーピング(環境影響評価の計画段階)から環境影響評価の実施段階への手順はおおよそ図II-1-1に示したフローのように進められる。スコーピングでは、事業計画のなるべく早い段階で、必要な情報を収集・整理し、適切な調査・予測・評価の手法を検討して方法書を作成することが望ましい。
方法書に対する国民や地方公共団体の意見を踏まえて、事業者が検討した項目・手法を柔軟に見直して、その案件に最もふさわしい実施方法を選定した上で、調査・予測・評価に入っていくことが重要である。
さらに、環境影響評価の実施段階で得られる情報によって項目・手法の見直しを加え、より詳細な実施方法を練りながら調査・予測・評価を進めていく必要がある。この見直しの経緯及び理由と最終的に選定した項目・手法については準備書において記載し、改めて意見を聴く必要がある。なお、図II-1-1に示した各項目の検討に際しては環境保全措置との関係にも十分配慮することが必要である
図II-1-1 スコーピング段階から実施段階への手順
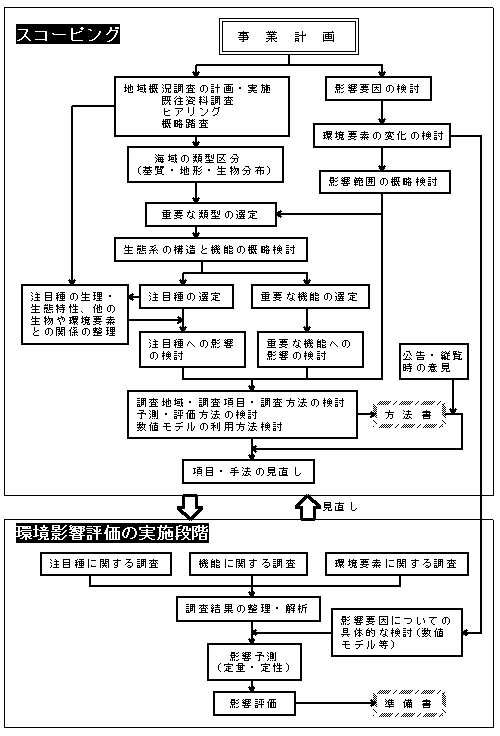
ここでは前項で示した手順に沿って、まず、スコーピング段階の手法に関して、 昨年度の中間報告書では十分に述べていない考え方や留意点を再整理して示した上で(3-1~3-6)、環境影響評価の実施段階の調査・予測手法に関して、作業の進め方、実施上の留意点、調査・予測内容を準備書等へ記載する上での留意点などを述べる(3-7~3-9)。
地域概況調査は事業特性や地域の環境特性を把握して、適切な環境影響評価のための調査項目、調査手法、予測手法を検討するために極めて重要な基礎調査である。単純に地域に関連する情報収集・整理を行うのではなく、事業影響の検討結果とも並行して検討し、必要に応じて調査をフィードバックさせつつ進行させなくてはならない。また、情報収集を行う過程において、対象範囲や対象期間などについても柔軟に変更、追加することが必要である。
調査は当該海域の生態系に関する様々な既存資料の収集・整理、有識者や現地の情報に詳しい人などへのヒアリング及び概略踏査によって行う(生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書(平成11年6月),p.111~112参照)。既存資料の収集にあたっては、行政関係の資料だけでなく、学術論文や民間団体による資料なども収集することが必要である。
主な調査項目は地形・基質の分布、海象条件、気象条件、水質・底質の現況、生物の分布状況、主要な生物の生理・生態特性、注目すべき環境、生態系の特徴などであり、事業による影響が想定される範囲より広めの海域を対象として実施する。
調査にあたって、当該海域で進められている他の事業や過去に行われた大規模な事業などの影響により、環境と海域生態系に大きな時間的空間的変化が生じた場合は、当該事業の影響評価を行う上で重要な参考となるので、それらの情報についても極力収集することが望ましい。
得られた情報については可能な範囲でその位置や分布等を適切な縮尺の図面で示し、事業実施区域との位置的な関係を明らかにする。また、出典を必ず明記する。
なお、公告・縦覧にあたって、保護を必要とする希少な動植物の生息に関する情報を示す場合には必要に応じて生息場所等の詳細を示さないなど、記載方法に配慮することも必要である。
当該海域における海底の基質や生物などから類型区分を行い、生態系の概要を把握した後に重要な類型や生態系への影響を検討する(生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書(平成11年6月),p.112~116参照)。その際には、従来のマトリックスによる検討だけでなく、事業による影響が類型や注目種あるいは生態系の機能などにどのように伝わっていくかを影響フロー図に示して検討することが重要であると考えられる。その理由はネットワーク的関係を持っている影響要因と環境要素や生物との関係をわかりやすく示すことができるからである。また、マトリックスでは表現しにくい影響の伝播経路を示すこともできる。ただし、作成したフロー図にもれがないように、従来のマトリックスも作成して、お互いにチェックすることも必要であろう。なお、この影響の整理の段階では、類型への影響の整理とともに注目種の選定や重要な機能の選定も同時に進行しているため、それらとの整合を図りながら作業を進める必要がある。
影響フロー図と影響マトリックスはおおよそ図II-1-2のように考えられる。これらは、類型への影響についても、注目種や生態系の重要な機能への影響についても、基本的には同様な形で用いられる。参考として、既存資料から引用した影響フロー図の一例を図II-1-3に示す。
このような手段で影響の検討結果を整理し、事業者が事業による影響をどのように捉えているかをわかりやすく示すことが望まれる。また、図II-1-4のように影響の伝播経路や位置的関係などを図解的にわかりやすく示すことも一般の理解を得るために有効な手法である。
なお、影響フロー図や影響マトリックスなどは様々なものを作ることができる。フロー図のボックスの配置や線の引き方も作り手の考え方によって異なる。したがって、例示したものが標準的であるということではない。
図II-1-2 影響フロー図と影響マトリックスの例
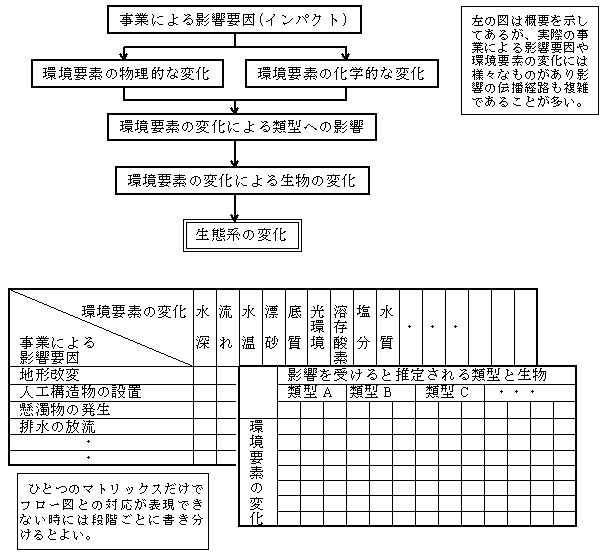
重要な類型の選定にあたっては、次の点に留意して調査・予測・評価の対象とすべき類型を選定する。
| [1] | 事業により、一部または全部が消失することとなる(または他の類型に置き換わる)類型(埋立・干拓など)。 |
| [2] | 事業による影響が及ぶと想定される範囲(影響予想地域)に含まれる類型の内、次のもの。 |
| ⅰ)当該海域の生態系を特徴付ける類型。 | |
| ⅱ)生物生産や浄化などの重要な機能を有する類型。 | |
| ⅲ)特殊な環境に依存する生物がみられる類型。 | |
| [3] | 影響範囲外の類型でも(例えば当該海域で成長した魚が海域外の別の類型で産卵するというように)、影響範囲内の類型と密接な関係があると考えられるものについては、評価の際に配慮する。多くの底生動物のように幼生プランクトンとして移動し、他の海域と密接な関係を有するものについても同様である。 |
評価対象とする海域生態系の構造は海域の類型区分図を基に、類型内の生物と環境要素の関係、生物間の関係、類型間の関係などから検討する。その際、生物の海底基質や海底の空間構造(砂泥底・岩礁・藻場など)への依存性、生物間の食物連鎖関係、生物の生活史などに配慮することが重要である。
海域生態系の機能については様々なものがあるが、類型別に重要と考えられる機能を参考として表II-1-1に示した。しかしながら、海域生態系が有する機能のすべてを調査し、予測・評価することは、現実的には困難である。実際には、当該海域において重要であると認識される機能を選定して、調査・予測・評価を行うこととなる。生態系の機能の検討にあたっては事業による影響の内容、対象海域の生態系の現状、対象海域の自然的・社会的な地域特性などを考慮して検討し、評価対象として選定した理由を明示する。
なお、海域生態系が有する機能の重要性を検討する際には、次の点に留意することが必要と考えられる。
| [1] | 人為的影響によってある機能が損なわれることで、海域生態系の健全性に影響を及ぼすおそれがある場合には、その機能は重要である。 |
| [2] | 海域生態系はフローの生態系であり、そこでは物質循環の機能が特に重要である。 |
| [3] | 生物資源の生産機能、生物多様性の維持機能など、生物的な機能については、その機能を担う生物種(群集)についての調査・予測を主体として評価できるようにする。 |
表II-1-1 海域の類型区分と生態系の機能
類型区分
生態系の機能 |
海水域 | 汽水域 | |||||||||||||||||||||||||||
| 潮間帯 | 潮下帯 | 潮間帯 | 潮下帯 | ||||||||||||||||||||||||||
| 砂浜 | 礫浜 | 磯 (岩) 浜 |
貝殻礁 | 干潟 | 海草藻場 | サンゴ礁 | マ ン グ ロ - ブ 林 |
砂泥底域 | 礫底域 | 岩礁域 | 貝殻礁 | 海草藻場 | 海藻藻場 | サンゴ礁 | 貝床 | 砂浜 | 貝殻礁 | 干潟 | 海草藻場 | マ ン グ ロ - ブ 林 |
ヨシ原 | 砂泥底域 | 礫底域 | 岩礁域 | 貝殻礁 | 海草藻場 | 貝床 | ||
| 生物的な機能 | 生物資源(水産、薬品等)の生産 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 生物多様性の維持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 遺伝子情報の維持 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
| 有機物生産機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 「場」としての機能 | 産卵場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||
| 避難(隠れ)場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 育成場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 索餌場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 河川への遡上の場 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 環境形成・維持の機能 | 酸素の供給 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||
| CO2の固定 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||
| 礁の造成 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||||||||
| 物質循環機能 | 水質・底質の浄化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 緩衝的機能 | 汚染物質の捕捉 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||||
| 消波機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 堆積促進機能 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
注:○印は一般的に重要と考えられる機能のあることを示す。
注目種は重要と考えられる類型に生息し、事業による影響を受けやすいと考えられる様々な生物から、上位性・典型性・特殊性の視点並びに生物の生活型や食性などの視点から、当該海域の生態系と事業による生態系の変化をより良く表現できるような生物種(群集)を選定することが必要である。選定した注目種についてはどのような評価を行うかも踏まえながらその選定理由を明示する。
なお、生活型や食性が同じような種(群集)をあまり多く選定すると、調査・予測・評価の作業が煩雑になることも考えられる。事業による影響要因に対して同じような反応を示すと思われる種(群集)が多くいる場合には、その中から代表的なものを選定することが効率的であると考えられる。
また、注目種の選定はその後の調査・予測・評価に大きく影響してくるので、当該海域の生態系に詳しい学識経験者、現地の有識者等の意見を十分に取り入れて行うことが望ましい。
注目種を選定する際の留意点を整理すると次のように考えられる。
| [1] | ある注目種(群集)を選定し調査することで、注目種を取り巻く他の生物や環境要素及び生態系の地域的特性がよりよく把握できること。 |
| [2] | 当該類型に比較的多くの個体数が長期間にわたって分布する生物であること。または、回遊などで定期的にみられる生物であること。 →環境に対応した注目種の分布の違い(環境に対する反応)を読み取りやすい、調査データをとりやすい、調査時期によるデータのバラツキが小さい等の利点がある。 |
| [3] | 生理・生態の既往知見が得られている、または調査によって知見を得やすいこと。 →環境変化による注目種の変化を予測しやすい、モニタリングがしやすい。 |
| [4] | 餌(被食-捕食)に視点を当て、調査結果から食物連鎖関係の検討ができること。 |
調査・予測地域の設定にあたっては、生物の生活史と環境要素の分布及びそれらの季節的変化などに十分配慮して検討する。特に、生物は産卵・育成など生活史の各段階で生息場所や餌料などを変化させることが多いので、その全体が把握できるような調査・予測地域を検討する。なお、広範囲に移動する(回遊や渡り)生物については、詳細な現地調査の範囲と既往資料などによる広域調査の範囲を分けて検討することも効率的である。
(1)直接的な影響範囲の推定
調査及び予測・評価の計画を検討する際には、まず、事業による直接的な影響要因の質と影響の時空間的な広がりを概略推定する必要がある。
この時点で既に数値実験(シミュレーション)や模型実験が行われており、影響範囲についてのデータがある場合にはそれを参考として調査及び予測・評価の検討を行うこととなる。しかし、この段階で事前の予測が行われていない場合には既往の事例を参考としたり、簡単な机上計算などから影響範囲を概略設定することとなる。
なお、影響要因が時間的にどのくらいの期間影響を及ぼすかについても概略予測する。
(2)間接的な影響範囲の推定
事業によるわずかな濁りの発生が海藻の生産力を少しずつ減少させ、ひいては藻場の衰退を招くというように、事業影響によってもたらされる生態系のわずかな変化が蓄積されて、あるとき大きな変化をもたらすといったことが想定される。また、微量物質の生物濃縮のように、生物の捕食・被食関係や移動などに伴い、小規模な生態系の変化が時とともに広範囲な生態系に影響を及ぼす可能性もある。影響範囲の概略検討にあたっては時間的な影響要因の蓄積や生物の移動に伴う影響についてもできるだけ考慮すべきである。
(3)調査・予測地域の設定
海域生態系の調査・予測を行う際、従来は予想される直接的な影響の範囲を考慮し、影響範囲の2~3倍の海域を目安として調査・予測の対象海域を設定していた。また、行政的な区分(県境・漁業権区域など)や地形などが考慮されることもあった。
海域生態系への影響予測・評価を行う場合、影響要因の伝わり方や生態系の広がりを十分考慮して調査・予測地域を設定する必要がある。しかしながら、生物の移動や微弱な影響の蓄積などを突き詰めて考えると、調査・予測の範囲は地球規模に広がってしまうこともありうる。実際には、科学的・社会的にみて大方の合意が得られる範囲を設定して調査・予測をすることになると考えられる。
調査・予測地域の設定にあたっては次の事項に留意する。
| [1] | 範囲内に次の区域を含むこと。 |
| ⅰ)埋立による海面の消失など直接的な影響のある区域。 | |
| ⅱ)潮流の変化や濁りの拡散など環境要素の変化が、スコーピング時点の影響予測結果や他地点の事例などから予測される区域。 | |
| [2] | 注目種の生活範囲を考慮すること。当該海域の複数の類型で生活史を完結する注目種がある場合はできるだけその類型すべてを対象範囲とする。 |
| [3] | 渡り鳥や回遊魚のように、ある期間に当該海域を利用し、それ以外は調査の困難な注目種については、注目種がその期間に生活している場所を対象範囲とする。また、環境の消失に伴い注目種が移動して生息する可能性のある場所も対象範囲とする。ただし、当該海域の類型がある生物にとって著しく重要な役割を持っている場合(例えばある魚類の産卵場が対象海域の特定の場所に限られ、そこでの影響がその魚類資源を決定的に左右するような場合)には事業実施区域の周辺海域だけでなくその生物の分布域全体を調査・予測地域として設定する。この場合、事業予定地周辺の詳細な調査・予測範囲と既往資料などによる広域の調査・予測範囲を分け、作業にメリハリをつけることも必要である。 既往資料等による広域調査、現地調査、予測の対象地域の大きさは次のように考えられる。 既往資料等による広域調査地域>予測地域≧現地調査地域 |
| [4] | 影響範囲外にあると推定される同様の類型については影響範囲内の類型の対照となるものとして捉え、後に実施する事後調査の対象として調査範囲に含める(ただし、影響範囲の外側で影響範囲の周辺に該当する類型がある場合)。 |
(1)調査・予測・評価項目の検討
生態系への影響評価のための調査は主に「注目種に関する調査」と「生態系の重要な機能」に関する調査である。
調査項目の検討にあたっては注目種及び重要な機能に及ぼすと想定される影響を検討することから始まる。そのためには、前述のように注目種及び重要な機能に及ぼすと想定される影響のフロー図を基に検討することが良いと考えられる。
調査・予測・評価の項目はフロー図に示した多くの項目の中からその重要性を検討して選定することとなる。
調査・予測の項目や手法はフロー図により検討して重要とした項目と流れについてその実態を調べ、事業による影響要因が時間的空間的にどのようにそれらに作用するかを評価できるように設定することとなる。
現在の科学的知見ではすべての項目と流れを定量的に調査・予測することは困難であり、理論的には可能な調査でも長年月を要するため現実的でないものもある。
調査・予測の項目や手法の設定にあたっては、実際に調べられること、既往の知見等から推定することを分けて検討せざるを得ない。しかしながら、生態系の保全という目標に対して、できる限り科学的・定量的に行うという姿勢が重要なことはいうまでもない。
重要なことは、生態系の評価にあたって、影響評価を行う当事者がどのような視点で問題を検討し、どのような目的を持って調査・予測の手法を選定して実施したのかが明確に示されることである。調査・予測の項目や手法を選定した理由についてはなるべくわかりやすく明示することも必要である。
(2)注目種からみた生態系への影響に関する調査
生態系に関する調査は事業による注目種(群集)や生態系の機能などの変化を予測するための調査である。したがって、環境要素の変化が生物にどのような変化を及ぼすかということをできるだけ定量的に予測するための情報を得ることが調査の目的となる。
前出の事業による影響が注目種に及ぼす影響フローには現時点で考えられる影響をほぼ網羅的に示すこととなる。しかしながら、現在の科学的知見ではそのフローに示された項目と影響の流れのすべてを定量的に把握することは難しい場合が多いと考えられる。実際には、その時点で活用し得る科学的知見や生態系項目についてどの程度重点を置いて環境影響評価を行うべきかの検討を踏まえて、フロー図に示した影響の検討結果を基に、重要と考えられる部分について調査・予測・評価することとなろう。したがって、どの部分を重点的に評価すべきかをよく検討し、その選定理由を明確にすることが特に重要である。
重点的に評価すべき項目が選定されたら、その予測のために必要となる調査・予測項目と手法の検討を行う。この場合、調査・予測の流れは図II-1-5のフローのようになると考えられる。また、検討の際に重要と考えられる視点は、次のとおりである。
| [1] | 事業の影響によって当該海域の注目種の生息状況にどの程度影響が生じるか。 |
| [2] | 事業実施に伴う環境要素(地形や水質・底質など)の変化がどの程度注目種に影響を及ぼすか。 |
| [3] | 注目種個体群への影響が生じた場合、他の生物(生態系)にどのような影響を及ぼすか。 |
これらのことを十分に検討し、調査計画を立てることとなるが、その際には、注目種の生活史に配慮することが重要である。生物はその生活史に応じて生息場所や餌料など選好する環境を変化させることが多い。したがって、調査地点・時期・期間・回数などは注目種や注目種と深い関わりを持つ種の生活史を極力把握できるように設定する。特に、種によっては生活史のごく一時期のみにある場を利用したり、ごく小規模な場を失うことにより生存が危ぶまれるようなものもあることから、そのような時期や場を見落とすことなく把握できるように設定することが必要である。
なお、具体的な調査手法の検討に際しては、既存の参考図書(「沿岸環境調査マニュアル(日本海洋学会)」、「漁場環境影響評価技術指針(日本水産資源保護協会)」など)も参考として、適切な調査計画を立案する。
図II-1-5 注目種に関する調査から予測の流れ
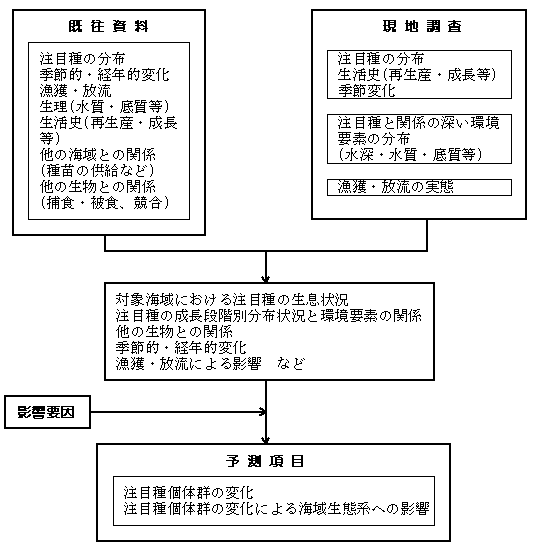
(3)生態系の機能に及ぼす影響に関する調査
生態系の機能に及ぼす影響についても注目種と同様に影響フロー図に基づいて調査項目を検討することとなる。影響フローには現時点で考えられる影響をほぼ網羅的に示すこととなるが、現在の科学的知見では、すべての項目と影響の流れを定量的に調査し、予測することは難しい場合が多いと考えられる。実際には、海域生態系の有する機能の仕組みを簡略化することで数値計算を可能にした数値モデルによる予測が用いられることが多い。数値モデルによる予測を行う場合は、予測する項目に適した予測範囲・計算条件・パラメータなどを十分検討し、必要なデータが的確に得られるように調査計画を立てる。一方、数値モデルによって予測できる機能は今のところ生物生産、物質循環、浄化量などに限られており、他の多くの機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって調査・予測をすることとなる。その場合でも予測結果の根拠や予測に用いたデータが極力定量的に示せるような調査計画を立てる。
(1)影響予測の基本的な考え方
予測の段階には大きく分けて次のようなケースがあると考えられる。
| [1] | 物理的・化学的影響の程度や時間的空間的な広がりが明確でなく、環境への影響が定性的にのみ予想される場合。生態系への影響予測も定性的・傾向的にしかできない。 |
| [2] | 物理的・化学的影響の程度や時間的空間的な広がりは、かなり正確に予測できるが、影響を受ける側(主に生物)の反応は定量的に予測できない場合。現実的にはこのようなケースが多い。 |
| [3] | 物理的・化学的影響の程度が極端に大きく、生物の生息に明らかな障害となるため、予測も明確にできる場合(埋立による死亡・逃避など)。 |
環境影響の予測を行う際にはこのそれぞれに応じて適切な手法で行うこととなるが、基本的に必要なこととして次のことがあげられる。
| [1] | 生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのか、どの生物を対象とするのかを対象として選定した理由とともに明確にする。 |
| [2] | 科学的・技術的に可能な範囲で、できる限り定量的な予測を行う。特に、物理的・化学的影響の程度については、時間的空間的に定量的な予測を行うようにする。 |
| [3] | 生態系を構成する生物については定量的な予測の難しいことが多いが、必要に応じて定量化・モデル化を試みる。また、定量化が困難な場合でも、生物の生理的・生態的特性を十分に検討し、感覚的な予測ではなく、データに基づいた客観的な予測を行う。 |
| [4] | 生態系の機能については機能の仕組みを簡略化して数値計算を可能にしたモデルが開発されているものもある(基礎生産や物質循環など)。それらのモデルを利用する場合には必要なパラメータを得て予測を行う必要がある。モデルが開発されていないものについては機能の仕組みを十分に検討し、調べられることは調べた上で予測を行う。 |
| [5] | 環境条件の変化による基礎生産速度の変化測定実験、生物の行動変化測定実験(忌避物質への反応など)など、実験的手法を用いることが予測の手段として効果的な場合がある。必要に応じて実施可能な実験的手法の検討も行う。 |
| [6] | 結果の記載にあたっては図表を添付するなど、わかりやすい説明をするとともに、結果を出したプロセスの明示、予測の前提条件、パラメータ設定の根拠、データやモデルの精度と不確実性などについての説明も行う。 |
(2)影響要因の具体的な検討
事業による影響要因の検討にあたっては前に述べたように影響フローを作成して行うのが良いと考えられる。影響フローには想定される影響要因についてできるだけ詳しく記載し、もれのないように配慮する。次に予測すべき影響要因の絞り込みを行うこととなるが、絞り込みにあたっては当該海域における生態系の特性、地域のニーズ、事業特性などを勘案し、何を評価すべきかという視点を明確にして行うことが重要である。
事業の影響要因による物理・化学的環境要素の変化についてはできる限り定量的な予測を行う。予測手法としては一般に数値モデルによる予測手法が用いられるが、簡易式による計算や既存事例による予測で十分定量的で正確な予測ができる場合には数値モデルを用いなくてもよい。
定量的な予測が可能な物理化学的環境要素の種類と予測モデルの概要については、生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書(平成11年6月,p.126参照)に示したように、波浪・流れ・熱拡散・水質(SS,
COD, DO, N, P等)などについては定量的な予測が可能である。
数値モデルや簡易式による計算で予測を行う場合には現況のデータやモデルのパラメータを現地調査、実験的手法及び既存資料などによって取得し実施することとなる。その際には、できるだけ代表性のあるデータを取得することや正確な現況再現を行い、モデルとパラメータの妥当性を確認することなどが重要である。また、数値モデルによる予測を行う場合には予測する将来条件の検討も十分に行い、事業による影響が正確に反映されるようにパラメータを設定することも重要である。
生態系に影響を及ぼす流れ、水質等の環境要素の変化について特定され予測されたら、その環境要素の変化がどの程度の範囲に広がるか、影響の程度(強さ)はどのくらいか、影響はどのくらい持続するかなどについて整理する。その際には、予測の条件やパラメータなどの適切さと予測結果の妥当性などについてわかりやすく説明する必要がある。
(3)注目種からみた生態系への影響予測
注目種からみた生態系への影響予測はまず事業の影響要因による物理化学的な環境要素の変化が注目種にどのような変化をもたらすかを予測することから始まる。しかしながら、生物の生理・生態と環境要素の関係は十分に解明されているとはいえず、環境要素の変化に対して起こりうる生物の変化を定量的に予測するのは影響が著しい(影響によって生物が死んでしまうような)場合を除くと困難なことが多い。さらに、環境要素の変化が注目種に及ぼす影響の程度も生物の成長や生活史の段階によって変化するのが一般的である。したがって、注目種からみた影響予測も不確実性が伴い、かつ定性的にならざるを得ない場合が少なくない。実際には、注目種の生理・生態特性の既存知見と分布状況などの現地調査結果から影響を推定することとなろう。その際には、注目種の生理・生態特性やハビタットの利用状況が地域によって異なることがあることにも留意する必要がある。なお、基礎生産と濁りの関係や生物の生息と塩分変化のように、実験的手法や詳細な現地調査によって注目種の生理・生態特性と環境要素との関係を知ることができる場合もあり、できる範囲内で極力正確な情報を得て、定量化・モデル化を試みる姿勢が望まれる。
注目種の生息状況の変化から注目種個体群への影響が予測できたら、注目種同士や注目種を取り巻く主要な生物間の関係をみて、注目種の変化がどのように他の生物に関係し、影響が伝播するかについても検討する。注目種との関係が強く、注目種の変化が他の生物にも大きく影響を及ぼす場合には、その生物についての予測・評価も必要になる。
(4)生態系の機能に及ぼす影響予測
生態系の機能には様々な環境要素と生物が複雑に関係しており、多くの機能については特段の確立された予測手法があるわけでない。比較的定量的に予測できる項目としては基礎生産や物質循環、あるいは生物(サンゴ礁等)による消浪機能などに関するものがあり、いくつかの数値モデルが開発・利用されているので、必要に応じて適切なモデルを選定して利用することとなる。場合によっては簡易な計算や既往事例などから予測することもできよう。また、生物(藻場等)による汚濁物質の捕捉や堆積促進機能など、実測からかなりの知見が得られると考えられるものもある。それら以外の機能については評価の重要性に応じて実施可能な手法を講じて予測することとなろう。
(5)モデルによる予測結果の妥当性の検討
モデルによる予測結果については予測モデルの条件設定や現況の再現性などの妥当性について十分に検討する必要がある。
そのためには、第一に現地調査データや既往知見に基づき、シミュレーションによる現況再現性を検証し、モデルの精度や設定した計算条件が適切であったかどうかを検討する。現況から大きくかけ離れたり、既往知見からみて特異な結果となった場合には計算条件を吟味するなどして原因を追求し、条件を変更するなど改善を図る。
さらに、シミュレーションでは絶えず変化する実際の海域ではなく、一定期間の平均状態や代表的状態を対象とすることが多いため、特に生物の生息環境や生物生産に重要な関わりを持つような短期的な変動が考えられる場合にはそれらを別途検討したり、平均状態としての予測結果に変動の幅を考慮することも必要となる。
予測にあたってはモデルの前提条件が海域における現象の中でどのように位置付けられるのかを明確にし、短期的な変動が著しい場合には可能な限りそれらについても検討することが望ましい。また、定量的な検討が難しい場合には予測結果の評価に変動要素の可能性を考慮することも必要である。
環境影響評価は複数の事業計画案や複数の環境保全措置(影響の回避・最小化などの効果)の検討を踏まえて行うこととなる。したがって、スコーピング段階で、複数の事業計画案や環境保全措置について検討されている場合には、複数の事業計画案の影響や環境保全措置(例えば事業予定地の変更など)による効果を予測するための情報収集も折り込んで調査・予測・評価を計画することが必要である。また、調査・予測・評価は一連の作業フローの中で行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討あるいは事業計画へのフィードバックが繰り返されることとなる。
予測・評価の実施段階では複数の事業計画案や環境保全措置のケースごとに予測・評価を行い、必要とあれば方法書に記載しなかった新たな調査・予測手法を取り入れるなど、柔軟な対応が望まれる。新たな調査・予測手法を取り入れた場合には準備書にその検討過程について記載することも必要である。
予測・評価の結果を準備書に記載する際には影響の予測結果、複数の環境保全措置の効果比較、最も影響が少ないと予測される事業計画などに対する事業者の見解や判断を整理して述べることとなる。
調査・予測・評価と環境保全措置の関係は、図II-1-6に示したようになる。
図II-1-6 調査・予測・評価と環境保全措置の関係