生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)
2 ケーススタディ -里山地域を例として-
《スコーピング》
面開発事業による生態系への影響を把握するために、事業により生じる「影響要因」及び、そこから生じる「環境要素の変化」についてマトリックスによる整理を行った(表I-2-1)。
影響要因は様々あるが、特に造成工事による植生・地形の改変は植生の変化や地形の変化、さらに、大気環境、水環境、土壌環境、生物群集などの環境要素の変化を引き起こすと想定された。
なお、事業実施区域内の改変区域の地形や植生は造成工事による直接的な影響を受けるとともに、事業実施区域及びその周囲については土砂の流出や地下水位の変化等による影響が生じると想定された。
表I-2-1 ケーススタディにおける影響要因と環境要素の変化とのマトリックス
| 環境要素 | 影響要因 | 工事の実施段階 | 存在 | 供用 | |||||||||
| 生態系へ影響を 与える環境要素の変化 | 造成工事 | 森林の伐採 | 機械の稼働 | 車両の通行 | 照明の設置 | 人の侵入 | 植生の改変 | 地形の改変 | 工作物の存在 | 道路の存在 | 自動車の走行 | 人の侵入 | |
| 大気環境 | 大気汚染物質の発生 | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 騒音の発生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 振動の発生 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 微気象の変化 | ○ | ○ | |||||||||||
| 水環境 | 水の濁りの発生 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 水量の変化 | ○ | ○ | |||||||||||
| 地下水位の変化 | ○ | ○ | |||||||||||
| 土壌環境他 | 地形の変化 | ○ | ○ | ||||||||||
| 表層の浸食、土壌の流出 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 土砂の流入・堆積 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 土壌の乾燥化 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 生物群集 | 植生の変化 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 森林・草地の消失・減少 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 生息場所の分断 | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 生物種の死滅・逃避 | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
| 移入種等の侵入 | ○ | ||||||||||||
| 踏圧の発生 | ○ | ○ | |||||||||||
| 盗掘、捕獲、殺傷 | ○ | ||||||||||||
| 餌付け | ○ | ||||||||||||
| その他 | 日照量の増加 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 夜間の光条件の変化 | ○ | ||||||||||||
事業の対象となる地域の生態系について地域概況調査を実施し、全国的な視点及び広域的な視点からの位置づけを把握した上で、事業実施区域及び周辺地域における環境の類型区分等の作業により地域特性の把握を行った。
(1)地域概況調査
前年度報告書の作業内容に従って地域の概況を把握するため、既存資料調査及び専門家等へのヒアリングを行った。調査した情報は、「植物」「動物」「地形・地質」等を中心とした他項目と共通した、生態系に関する基礎的な情報についてである。
概略踏査は、(4)の類型区分図の区分ごとや、さらに主な植生ごとに、「環境要素概略調査票」を基に調査を行い、現況の把握を行った(表I-2-2)。この調査票は、対象とした地域の生態系を概略把握するために、植生、地形・地質、土壌、水環境、人為的な管理状況、動植物の重要な生息場所などの状況を現地で記入するためのものである。その結果、概略踏査により様々な情報が得られたが、特に、既存の植生図では把握されない様々な小規模の植生や動植物の豊かなため池等が確認された。
(2)全国的な生態系区分における位置づけ
前年度報告書の作業内容に従って、全国的な視点で対象地域の生態系がどのように位置づけられるか検討を行った(前年度報告書図2-5,2-6)。
対象地域は環境庁による生態系の国土区分(試案)では「本州中部太平洋側区域」に属している。生物群集タイプは、A:区域の生物学的特性を示す生態系においては「照葉樹林生物群集」、C:伝統的な土地利用により形成された注目すべき二次的自然の観点からはすべての生物群集タイプが存在している。これにより、本地域は、照葉樹林及び、里山に代表される二次的自然に注目して調査・予測・評価を行うことが重要であることが把握された。
(3)広域的な環境特性の把握
対象地域の広域的な環境特性を把握するために広域図の作成を行った(図I-2-3)。これは広域的なレベルでの地形、植生、水系等の状況を概観するものであり、特に、対象地域の生態系が周辺地域に比較しどのような自然的特性を有しているか、周辺と連続性があるのかなどの点について把握を行った。なお、広域的に捉えることが可能な動物等の分布状況についてもこのレベルで整理する。
対象範囲としては地形、水系、植生等の資料により広域的なレベルで環境特性が把握される範囲とした。その際、植生や動植物の分布などの他、人為的環境(都市の広がりなど)についても考慮した。
事業実施区域は低地~台地~丘陵地へとつながる地形の入り組んだ部分に位置し、谷戸の環境が多くみられる。また、この地形は事業実施区域から南方の丘陵地、山地へとつながっていて、周囲をふたつの河川に囲まれている。丘陵地の植生はスギ・ヒノキ植林やクヌギ-コナラ群集が優占し、谷戸の部分は水田や休耕田となっている。
(4)陸域の類型区分
事業実施区域及びその周辺での生態系の概略を把握するために既存の主題図を用いてオーバーレイを行い、類型の抽出を行った。
類型区分の対象とする範囲は事業実施区域及びその周辺を含む環境の特性を把握できる範囲とし、また調査地域を設定するための資料とすることも念頭において設定した。
オーバーレイに用いた主題図としては生態系の特性を捉える上で重要な地形分類図、表層地質図、土壌分類図及び植生図を選定した(表I-2-3)。その際、表層地質、地形、土壌の分布は相関が高かったため、単位の抽出にあたっては地形を代表させて扱うこととし、地形と植生の組み合わせにより環境の類型区分を行った。植生図、動植物種の主要な生息環境の概略を検討するため、既存の植生図の凡例を相観により統合した。抽出された類型により類型区分図(縮尺1/5万)を作成した(図I-2-4)。
事業実施区域において広い面積を占める類型は丘陵地‐落葉広葉樹林(48.6ha,36.0%)、高位台地‐落葉広葉樹林(24.3ha,18.0%)、丘陵地‐スギ・ヒノキ林(23.7ha,17.6%)、高位台地‐スギ・ヒノキ林(15.2ha, 11.2%)、高位台地‐常緑広葉樹林(12.6ha, 9.4%)であった。これらの類型は相互に入り組んだ形状で隣接し、モザイク状をなしている。丘陵地‐落葉広葉樹林及び丘陵地‐スギ・ヒノキ林の土壌は主に褐色森林土壌であり、一部、黒ボク土壌により占められている(表I-2-5)。また、地質は下総層群より成っている。高位台地‐落葉広葉樹林、スギ・ヒノキ林、常緑広葉樹林ではローム層が厚く覆った上に、黒ボク土壌が発達している。また、事業実施区域の北側には、面積的には大きくないが、河岸段丘‐水田(4.4ha,
3.2%)の類型が出現した。本類型は沖積層の堆積する河岸段丘から谷戸部に広がり、土壌はグライ土壌または灰色低地土壌となっていた。
表I-2-3 類型区分に用いた資料
種別 |
縮尺 |
備考 |
表層地質図(○○年) |
1/5万 |
既存資料 |
地形分類図(〃) |
||
土壌分類図(〃) |
||
植生図(〃) |
1/2.5万 |
表I-2-4 事業実施区域内に含まれる各類型区分の面積
類型区分 |
事業実施区域 |
丘陵地-落葉広葉樹林 |
48.6(36.0) |
丘陵地-スギ・ヒノキ林 |
23.7(17.6) |
丘陵地・高位台地-畑地 |
5.2(3.9) |
高位台地-常緑広葉樹林 |
12.6(9.4) |
高位台地-落葉広葉樹林 |
24.3(18.0) |
高位台地-スギ・ヒノキ林 |
15.2(11.2) |
河岸段丘-水田 |
4.4(3.2) |
草地 |
1.0(0.7) |
住宅地・市街地・砂取場 |
0.1(0.0) |
総計 |
135.0(100.0) |
| 表中の数値は面積(ha)、ただし括弧内は各類型の割合(%)を示す |
表I-2-5 基盤環境と植生の対応関係
| 類型区分単位 | 地質 | 地形 | 土壌 | 主な植生 |
丘陵地-落葉広葉樹林 |
下総層群 |
丘陵地 人工改変 |
褐色森林土壌(A~E)・黒ボク土壌 |
落葉広葉樹林 |
丘陵地-スギ・ヒノキ林 |
スギ・ヒノキ林 |
|||
丘陵地・高位台地-畑地
|
ローム層 |
高位台地 |
黒ボク土壌 |
畑地 |
下総層群 |
丘陵地 |
褐色森林土壌(A~E)・黒ボク土壌 |
||
高位台地-常緑広葉樹林 |
ローム層 |
高位台地 |
黒ボク土壌 |
常緑広葉樹林 |
高位台地-落葉広葉樹林 |
落葉広葉樹林 |
|||
高位台地-スギ・ヒノキ林 |
スギ・ヒノキ林 |
|||
河岸段丘-水田 |
沖積層 |
河岸段丘 |
グライ土壌・ 灰色低地土壌 |
水田 |
草地 |
ローム層 |
高位台地 |
黒ボク土壌 |
草地 |
下総層群 |
丘陵地 |
褐色森林土壌(A~E)・黒ボク土壌 |
||
住宅地・市街地・砂取場 |
- |
人工改変地 |
- |
住宅地・市街地・砂取場 |
人工草地 |
人工草地(シバ草地) |
(1)評価する上で重要な類型の検討・選定
生態系への影響を捉えるにあたり、「2-1」で整理した「影響要因」が具体的に「2-2(4)」の「陸域の類型区分」により把握された類型やさらに地域概況調査で明らかとなった環境に対してどのような影響を与えるのか、を検討した。検討にあたっては「2-1」により想定されたものの内、特にそれぞれの類型等に関連する主要な環境要素の変化を取り上げ、マトリックスに整理した(表I-2-6)。
事業の影響要因の中でも、地形の変化、植生の変化等の直接改変による環境の変化が大きく、これらの変化に伴い、土砂の流入・堆積、土壌の乾燥化、地下水位の低下などの変化が予想された。これらの環境要素の変化はその種類によって様々な類型及び環境に影響を与えると想定された。
また、道路により高位台地-落葉広葉樹林、丘陵地-落葉広葉樹林、丘陵地-スギ・ヒノキ林での森林間の分断及び丘陵地-落葉広葉樹林と水田との分断が、造成工事により大気汚染物質の発生や騒音・振動の発生が予想された。
このような結果から、事業の影響要因及びそれに伴う環境要素の変化が生態系に影響を及ぼすおそれのある類型等は、表I-2-6のように整理された。影響の及ぶ面積・規模、影響の内容等から特に重要な影響として以下のものがあげられた。
| ・ | 各類型や重要な環境の消失・減少(表I-2-4の面積の大きい類型及び重要な環境) |
| ・ | 生息場所の分断 |
| ・ | 地形の改変及び森林等の消失による土壌環境及び水環境の変化 |
(2)対象とする生態系の構造・機能の概略検討
(1)で事業による対象地域の類型等に関する影響が把握された。ここでは、これらの各類型へ及ぼす影響が生態系の構造・機能にどのような影響を及ぼし、特に生物群集の視点からはどのような影響に着目していくべきかを把握するために、以下のような作業を、前年度報告書に示されたモデル的な手順(前年度報告書図2-8参照)に従って実施した。
これにより、生態系の環境影響評価にあたり、生物群集への影響の観点からどのような側面への影響の評価に重点を置くべきかを検討した。
1)生態的特性表の作成
生態系における種・群集の機能的な役割や種間の関係などについて基本的な内容を理解するために、対象地域にみられる生物相のうち生態系を捉える際に重要となる主要な動物、植物、植物群落の種・群集を対象として、それぞれ主に既存資料を参考にして生態学的知見についてとりまとめた(例として、動物:表I-2-7、植物:表I-2-8)。
2)主要な生息環境-生物種・群集表の作成(表I-2-9)
対象地域の生物の多様性を理解するため、どのような生息場所があり、そこにどのような生物相がみられるかを把握するため、既存資料調査や概略踏査等の結果を踏まえ、類型区分やそこに含まれる植生ごとに、生物群集の整理を行った。
表I-2-6 ケーススタディにおける環境要素の変化・類型マトリックス
環境要素の変化
類型及び重要な環境 |
大気環境 | 水環境 | 土壌環境他 | 生物群集 | その他 | |||||||||||||
| 大気汚染物質の発生 | 騒音の発生 | 振動の発生 | 微気象の変化 | 水の濁りの発生 | 水量の変化 | 地下水位の低下 | 地形の変化 | 表層の浸食 、土壌の流出 |
土砂の流入 ・堆積 |
土壌の乾燥化 | 植生の変化 | 森林 ・草地の消失 ・減少 |
生息場所の分断 | 生物種の死滅 ・逃避 |
移入種等の侵入 | 日照量の増加 | 夜間の光条件の変化 | |
| 丘陵地-落葉広葉樹林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丘陵地-スギ・ヒノキ林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 丘陵地・高位台地-畑地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||||
| 高位台地-常緑広葉樹林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 高位台地-落葉広葉樹林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||
| 高位台地-スギ・ヒノキ林 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
| 河岸段丘-水田 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| 草地 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||||
| 住宅地・市街地・砂取場 | ○ | |||||||||||||||||
| ヤブコウジ-スダジイ群集 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||||
| ハンノキ群落 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| カサスゲ群落 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||
| ススキ群落 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 放棄水田雑草群落 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
| ため池 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||||||||
表I-2-7 動物種の生態的特性表
種 名 |
生 活 史 | 種間の関係 | 生活形 | |||
| [1]生息場所の利用様式(定住性・繁殖・産卵等の時期や日周活動等) | [2]生息場所の利用内容 (生息場所の利用内容及び生息場所の環境要素) |
[3]生活圏の空間的広がり(行動圏) | [4]食性 | [5]捕食者他 | [6]採食ギルド区分 | |
| ニホンリス | 周年定着 5~8月(繁殖期) |
樹林 移動のための森林の連続性 が重要 |
10~30ha | ナラ類、クルミ類などの堅果、昆虫類 | オオタカ | 森林・高木層・ 種子食 |
| フクロウ | 周年定着 3~6月(繁殖期) |
樹洞(繁殖) | 数km2 | 主にネズミ類、モグラ、小・中型鳥類 | なし | 森林・林内空 間・肉食 |
| ヤマガラ | 周年定着 4~7月(繁殖期) |
広葉樹林 樹洞(繁殖) |
数ha | 主に昆虫類・広葉樹の堅果、針葉樹種子 | アオダイショウ | 森林・高木層雑食 |
| アオゲラ | 周年定着 4~7月(繁殖期) |
広葉樹林 大径木(繁殖) |
不明 | 甲虫類の幼虫・アリ類 果実 |
オオタカ | 森林・幹・昆虫食 |
| イシガメ | 周年定着 5~7月(交尾・産卵) |
池沼・水田 春~秋には水田で生活し冬 には数百m離れた池沼で越 冬する例が知られる。 |
~1km (移動距離) |
魚類・昆虫類・甲殻類・貝類・水草・カエル | イタチ、サギ類 | 池沼・水中・雑 食 |
| シュレーゲルアオガエル | 周年定着 5~7月(産卵期) |
水田・池沼(繁殖) 広葉樹林(非繁殖期) |
不明 | 昆虫類・クモ類 | ヘビ゙類(シマヘビ゙・ヤマカガシ) 鳥類(サシバ・カラス類) | 森林・低木層・昆虫食 |
| ホトケドジョウ | 周年定着 3~6月(産卵期) |
水田・湧水等の流水のある 浅い砂礫底または砂泥底 | 不明 | 底生動物、浮遊動物 | サギ類、カワセミ、オニヤンマ | 水田・水中・底生動物食 |
| オオムラサキ | 周年定着 6~7月(成虫期) 幼虫で越冬 |
広葉樹林 まとまった規模の林が必要 |
不明 | エノキ・エゾノキ(幼虫) コナラ・クヌギの樹液 (成虫) |
小鳥類 | 森林・高木層・葉食 |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
※本表は主要な種を対象とし、既存文献・概略踏査等により作成する。
表I-2-8 動物種の生態的特性表
種名 |
科名 |
生活形* |
分布域 |
生育場所 |
備考 |
| カンアオイ | ウマノスズクサ科 | 常緑多年草(G) | 丘陵地 | 常緑樹林内 | |
| ニリンソウ | キンポウゲ科 | 多年草(G) | 低地~山地 | 落葉樹林内 | |
| ヤマザクラ | バラ科 | 夏緑高木(MM) | 低地~山地 | 落葉樹林内 | |
| ウメガサソウ | イチヤクソウ科 | 多年草(Ch) | 低地 | 常緑樹林内 | 乾性立地に生育 |
| ヒルムシロ | ヒルムシロ科 | 多年草(HH) | 低地 | 池沼 | |
| オモダカ | オモダカ科 | 多年草(HH) | 低地 | 水田 | |
| ミズオオバコ | トチカガミ科 | 多年草(H) | 低地 | 池沼、水田 | |
| カタクリ | ユリ科 | 多年草(G) | 低地~山地 | 落葉樹林内 | 湿潤な斜面下部に生育 |
| キンラン | ラン科 | 多年草(G) | 低地~山地 | 落葉樹林内 | |
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
*( )内はラウンケアの休眠型区分 |
※本表は主要な種を対象とし、既存文献・概略踏査等により作成する。 |
表I-2-9 主要な生息環境-生物種・群集表
| 類型区分 | 地形 | 相観 | 植生 | 植物 | 哺乳類 | 鳥類 | 爬虫類・両生類 | 魚類 | 昆虫類 | その他 |
| 丘陵地-落葉広葉樹林 | 丘陵地 | 落葉広葉樹林 | クヌギ-コナラ群集 | コナラ、クヌギ、クリ、ヤマザクラ、ヤマコウバシ、ヒメウズ,ニリンソウ、キンラン、ササバギンラン、フタリシズカ、カタクリ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ | コジュケイ、キジバト、アオゲラ、コゲラ、ヒヨドリ、エナガ、ヤマガラ、シジュウカラ、メジロ、カケス | ジムグリ | ヒグラシ、クロナガオサムシ、アオバセセリ、オオムラサキ、イチモンジチョウ、コシロシタバ | ||
| 竹林 | 竹林(モウソウチク・マダケなど) | モウソウチク、マダケ、シュロ、チャノキ、シロダモ、ヤブガラシ、ミツバアケビ | オナガ | ゴイシシジミ、ベニカミキリ | ||||||
| 低木林(乾性) | 伐跡群落 | アカメガシワ、ミズキ、ヤマグワ、ニワトコ、ハゼ、ケヤキ、ムクノキ、アズマネザサ、カラスザンショウ、イヌビワ | モズ、ウグイス、ジョウビタキ、ホオジロ | 訪花性昆虫類 | ||||||
| 丘陵地-スギ・ヒノキ植林 | 丘陵地 | 常緑針葉樹植林 | スギ・ヒノキ林 | スギ、ヒノキ、アオキ、シロダモ、アラカシ、リョウメンシダ、イズセンリョウ、コバノカナワラビ、ミヤマカンスゲ、イワガネソウ | ヒミズ、ノウサギ、ニホンリス、ムササビ、アカネズミ、ヒメネズミ、タヌキ、イタチ、アブラコウモリ | アオジ、カケス | ||||
| 丘陵地・高位台地-畑地 | 丘陵地・高位台地 | 果樹園他 | 落葉果樹園 | ジョウビタキ | ||||||
| 苗圃 | クワ | クワカミキリ、キボシカミキリ | ||||||||
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・… |
| 河岸段丘-水田 | 河岸段丘 | 落葉広葉樹林 | ハンノキ群落 | ハンノキ、ミゾソバ、ヨシ、セリ、ハンゲショウ、イボタノキ、ヨシ、カサスゲ | アブラコウモリ、ノウサギ、カヤネズミ、タヌキ、イタチ | コサギ、セグロセキレイ | ||||
| 低木林(湿性) | メダケ群落 | メダケ | ||||||||
| 草地(湿性) | 放棄水田雑草群落 | ヨシ、ミゾソバ、チゴザサ、セリ、ガマ、イ、タコノアシ、チョウジタデ、コブナグサ、チゴザサ、アシボソ | ヤマカガシ、クサガメ、トウキョウサンショウウオ、シュレーゲルアオガエル | ホトケドジョウ、ドジョウ、メダカ | アオゴミムシなどの地表性甲虫類、ゲンゴロウ類・ミズカマキリなどの水生昆虫類 | |||||
| 水田雑草群落 | キカシグサ、アゼトウガラシ、ウリクサ、トキンソウ、ウリカワ、オモダカ,ヒデリコ、ウキクサ、イチョウウキゴケ、オオアカウキクサ、タガラシ、スズメノテッポウ、タネツケバナ、ムツオレグサ | オオシオカラトンボ、オニヤンマ、ヘイケボタル | ||||||||
| ミズオオバコ群落 | ミズオオバコ、ヒルムシロ | イトトンボ類、ゲンゴロウ類 | ||||||||
| カサスゲ群落 | カサスゲ、ハンゲショウ、アオミズ、クサヨシ、ミゾソバ | オオネクイハムシ | ||||||||
| 開放水域 | 開放水域(ため池・河川) | ヒシ、ヒルムシロ、ミズオオバコ、ミズヒキモ、クロモ、マツモ | カイツブリ、カルガモ、カワセミ | ウシガエル、クサガメ | ゲンゴロウブナ、ブラックバス、ブルーギル | 水生昆虫類、ギンヤンマ | ヌカエビ、アメリカザリガニ | |||
| ・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・ |
・ ・ ・… |
※本図は主要な食物連鎖につて既存資料を主に作成した。 |
3)食物網の模式図の作成(図I-2-5)
食物連鎖は捕食・被食などの生物相互の関係を把握する上で重要であり、上位性の視点からの注目種の選定にも有効である。そのため、対象地域における食物網の概要について主に既存の知見から想定した。この際、食物連鎖が対象地域のどの類型を主体として成立しているかも想定した。
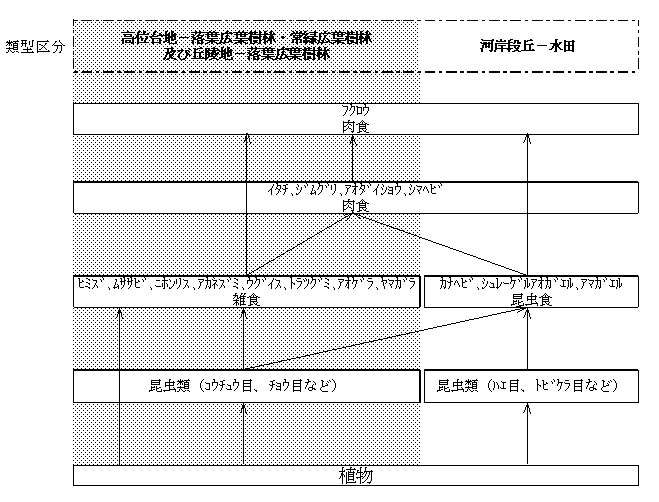
図I-2-5 食物網の模式図
4)基盤環境と生物群集に関する模式図の作成(図I-2-6)
対象地域の生態系の概要をとりまとめる上で、模式図を用いて表現することは広く一般から意見を得るためにも効果的な手法である。1)~3)の結果から、対象地域に典型的な基盤環境、植生及び動植物種についての模式図を作成した。
(3)重点をおいて評価すべき生態系への影響の整理
対象地域では様々な類型が把握されたが、対象地域において面積割合が大きく典型的な高位台地-落葉広葉樹林(主にクヌギ-コナラ群集)、丘陵地-落葉広葉樹林及び高位台地-常緑広葉樹林(ヤブコウジ-スダジイイ群集、シイ-カシ萌芽林)は森林の階層構造が発達し、人為的管理のなされた二次林や自然性の高い森林を主な生息場所とする動植物種が多いため、対象地域の生物の多様性を維持する上で重要と考えられた(表I-2-9)。また、クヌギ-コナラ群集内でも下草刈りなどの人為的な管理がされている場所とそうでない場所があり、林床植生などの生物相に違いがみられた。
河岸段丘-水田の類型内にみられる水田、放棄水田やため池などにはカエル類などの両生類、トンボ類などの昆虫類、ミゾソバ、ヨシなどが生息できるような水辺環境が存在し、多くの動植物種が生息していると考えられた。また、概略踏査の際には放棄水田やため池の岸の一部分においてミズオオバコの生育が確認され、このような場所は水位変動による影響を受けやすい陸域と水域の移行帯への影響を予測する上で重要と考えられた。
高位台地-落葉広葉樹林においては現地踏査の際、斜面下部の湿潤な立地において春植物が多く生育している場所が確認された。このような特殊な環境の存在により維持される種及び生息場所は地域の生物の多様性を保全する上で重要であると考えられた。
以上が対象地域の谷戸を含む里山環境を特徴づける類型や環境であり、これらは対象地域の生態系の重要な要素であると考えられた。
対象地域は様々な環境がモザイク状をなしており、特にクヌギ-コナラ群集などの森林と水田、放棄水田との移行帯部分では多様な動植物種が確認された。また、対象地域では行動圏の広いタヌキなどの哺乳類、鳥類やシュレーゲルアオガエルなどの複合した環境を利用する動物種も確認され、これらのモザイク状の環境に代表される生態系の水平構造は対象地域の生態系を考える上で重要であると考えられた。
さらに、対象地域における食物網の検討からは(図I-2-5)、高位台地-落葉広葉樹林、丘陵地-落葉広葉樹林、水田に生息する動植物種により支えられる栄養段階の上位に位置する種として、フクロウ、イタチ、ジムグリなどが把握された。こうした種は行動圏が広い種が多く、複数の類型にまたがる広域的なスケールでの環境の変化を指標するものとして重要であると考えられた。
以上の結果及びこれまでの影響要因及び環境要素の変化を踏まえ、生態系への影響の伝搬経路を影響フロー図に整理した(図I-2-7)。その結果、生物群集への影響の観点からは「森林の生物群集の変化」「水田・湿地の生物群集の変化消失」などの影響が予測された。
このように生態系への様々な影響が想定されたが、以下、本ケーススタディでは主として面的な環境の消失・変化と環境の分断による「森林の生物の生息環境の変化・消失」「水田・湿地の生物の生息環境の変化・消失」「生物の移動の阻害」が生態系へ及ぼす影響を対象として作業を進めた。なお、実際の環境影響評価では、影響フローにより整理された様々な影響について考慮していくことが必要である。
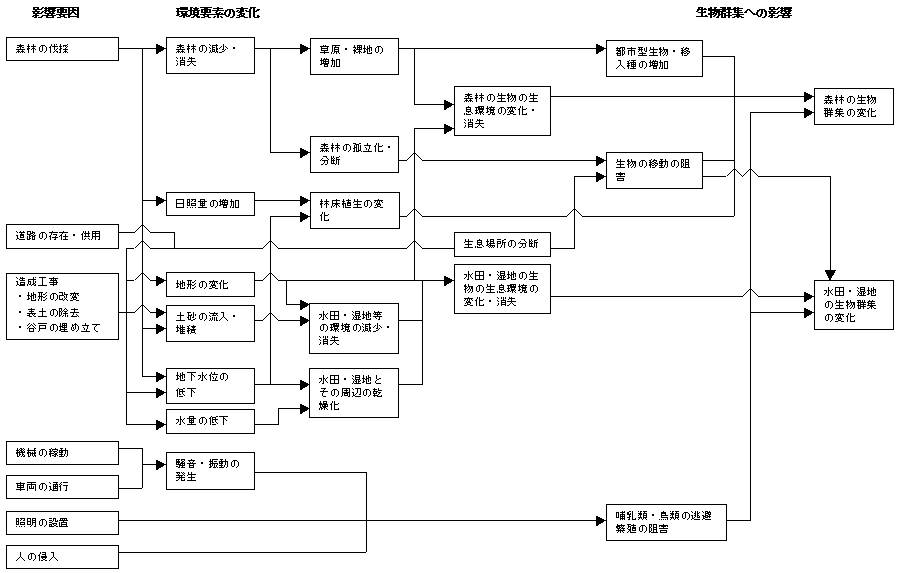
図I-2-7影響のフロー
(4)注目種・群集の抽出
(1)(2)(3)の結果を踏まえ、生態系への影響を把握するために適切な注目種・群集を抽出した。
具体的には、対象地域の生態系への影響を捉える上で重要と考えられる以下の生物種・群集に着目した。
| [1] | 対象地域において影響を受ける面積が大きく、地域の種多様性を維持する上で重要と考えられる高位台地-落葉広葉樹林、丘陵地-落葉広葉樹林及び高位台地-常緑広葉樹林を代表する生物種・群集 |
| [2] | 面積的には小さくても、その環境に依存する種がみられる河岸段丘-水田を代表する生物種・群集 |
| [3] | 本地域の栄養段階の上位に位置する種 |
| [4] | 複合した環境を必要とする生物種・群集 |
| [5] | 斜面下部の湿潤な立地の存在を必要とする生物種・群集 |
そして、それらに該当する生物種・群集の中から、生態的知見が多く、調査が比較的行いやすいもの、事業の影響を指標しやすいと考えられる種を抽出した。表I-2-10に選定された注目種・群集とその選定理由を示した。
表I-2-10 注目種・群集の一覧
選定種 |
観点 |
選定理由 |
| フクロウ* | 上位性 | 行動圏が広く、森林を繁殖・休息の場、狩り場として幅広く利用すると同時に、草原や畑地も狩場として利用するため、ランドスケープレベルでの植生改変、土地利用改変による影響を予測するのに適している。森林生態系の栄養段階の上位に位置する種で、繁殖可能な場所が限定されていること(樹洞のある大径木)、狩りや休息のために高樹齢で林内に空間がある高木林が必要なことから、森林の改変に敏感な種類である。里山に普通に生息する種で、調査は比較的行いやすい。 |
| タヌキ | 典型性 | 対象地域の様々な環境を利用し、かつ、雑食性であるため、森林の伐採、土地利用の変化、構造物の設置などの複合的な影響を予測するのに適している。また、森林の伐採などで環境が分断されると影響を受ける種である。 |
| ムササビ | 典型性 | 森林の連続性を必要とする種なので、森林の伐採などの分断による影響を予測するのに適している。大径木を休息や繁殖に利用するため、森林の伐採等による影響も受けやすい。 |
| ヤマガラ* | 典型性 | 繁殖のために小樹洞、採食のためには昆虫類や木本の種子など、森林の多様な資源を利用する森林性の種なので、里山の森林生態系に典型的な種として、影響を把握するのに適している。また、ヤマガラには森林が連続して存在することが必要なため、森林の断片化などの影響を受けやすく、森林の断片化による影響を把握するためにも適している。里山に普通に生息する鳥類で、個体数や採食行動の調査などの生態調査が比較的行いやすい。 |
| シュレーゲルアオガエル* | 典型性 | 本種は谷戸の水域と森林域とが連続した環境を必要とするため、森林や水田・湿地等の減少・消失及び、道路建設による水環境と森林環境の分断による影響を予測するのに適している。本種は繁殖期には水域に依存し、非繁殖期には森林域への依存度が高いため、水域及び森林域が隣接していることが重要である。 |
| オオムラサキ | 典型性 | 事業による落葉広葉樹林の伐採等の要因により、こうした環境に依存する生物群集に対する影響が想定された。こうした影響を予測するために本種を選定した。本種はクヌギ・コナラ林を中心とした落葉広葉樹二次林に生息し、成虫は樹液を餌とし、幼虫は谷戸周辺の斜面下部のエノキでみられ、特に適度に管理されたクヌギ・コナラ林の多様な生物群集を代表する種である。 |
| クヌギ-コナラ群集 | 典型性 | 事業実施区域内で多くの面積を占める植生であり、里山に特有の動植物相を支える上で重要な生息環境をつくりだす群落である。群落構造や林床植生の状況により、生息する動植物種が異なるため、事業による群落構造や林床植生の変化が動植物相に与える影響を予測するのに適している。 |
| カタクリ* | 特殊性 | 本種の良好な生育には水分条件が重要であるため、谷戸における水環境の変化を予測するのに適している。分布南限付近にあたる事業対象地域において本種は高位台地-落葉広葉樹林の類型の中でも特に、明るい林床で、斜面下部の凹状地や沖積錘等の水分条件の豊かな立地にのみ生育している。このような特殊な環境の存在は本地域の種多様性を維持する上で重要であり、本種の保全を考えることは同様の立地に生育する多くの種の保全につながる。 |
| ミズオオバコ | 特殊性 | 水位の変動する水辺に生育するため、水位変動による影響を予測するのに適している。また、水辺の植生や地形の改変による影響を受けやすいため、移行帯に対する影響を予測することができる。ため池や水田周辺のごく限られた場所にのみ生育している。 |
*印は今回報告書において、注目種・群集の調査・予測手法を示したもの |
(5)調査・予測・評価手法の選定
調査・予測・評価手法の選定に際してはこれまでの作業結果を踏まえて検討した手法を方法書にとりまとめるとともに、公告・縦覧時の方法書に対する意見を適切に反映させ、方法書に記述した手法を見直す必要がある。手法の選定に際しては地域特性を考慮し、対象地域の生態系に対する影響を捉える上で最も適切な方法を選定する。
本ケーススタディで検討した手法については2-4、2-5の環境影響評価の実施段階の調査・予測についての解説の中で併せて示した。
(6)調査地域の設定
1)調査地域
事業実施区域は丘陵地~台地部にあり、谷や尾根が連続し、谷戸が入り組んだ環境となっている。そのため、改変区域及び2-1で整理した事業の影響の範囲を想定した。そして、事業実施区域での影響をその地域で評価するためのまとまりとして、それを含む形で尾根や谷などの地形的な要素を重視して設定した(図I-2-8)。
2)注目種・群集の調査対象地域
注目種・群集の調査対象地域は、上記の「調査地域」を基本として、行動圏の大きさ、生活史、個体群の分布、など個別の種の生態的特性に応じてそれぞれ適宜設定した(2-5注目種・群集の調査参照)。