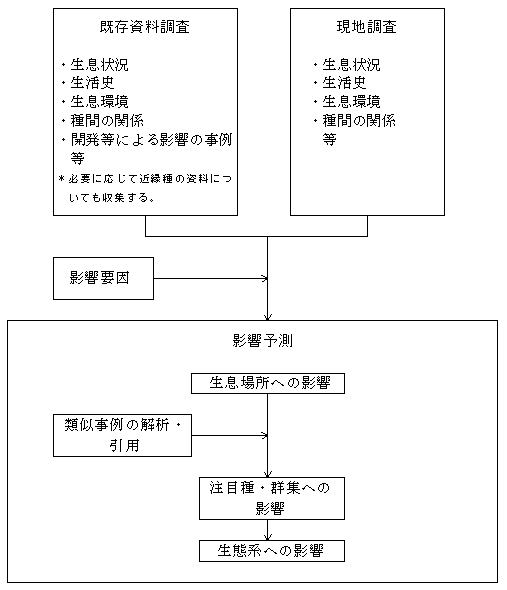生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)
3 陸域生態系の環境影響評価の手法
昨年度の報告書では前項2で示した手順の内、スコーピングについての作業の進め方についてとりまとめた。ここでは、スコーピングの検討を受けて、環境影響評価の実施段階の調査・予測手法に関して作業の進め方、実施上の留意点、調査・予測の内容を準備書等へ記載する上での留意点などを以下に述べる(3-3~3-5)。ただし、昨年度の中間報告書にはスコーピングにおいて事業の影響 要因が生態系へ与える影響を整理する方法や調査地域を設定する際の考え方について十分に述べられていなかったため、それらについても併せて示す(3-1~3-2)。
地形・植生の改変などの行為や施設の存在などの生態系に影響を与える「影響要因」を、事業特性を踏まえて想定する必要がある。そして、これらの影響要因が地形・地質、水環境などの基盤環境や植生に及ぼす影響等の「環境要素の変化」を検討する。次に、陸域の類型区分により把握された各類型への影響の程度なども踏まえ、これらの「環境要素の変化」やそこから派生する影響を通じて、生態系にどのような影響が及ぶ可能性があるかを把握することが重要である。
その際、影響要因及びそこから派生する影響を通じた生態系への影響については事業による影響の時間的な変化や長期における累積的な影響などの「時間的な側面」を捉えていくことが重要である。
また、従来の表やマトリックスによる項目の整理、項目間の関連等の検討だけでなく、事業が環境の類型や生物種・群集にどのような過程をへて影響を与えるかを影響フロー図に示して検討することが重要である。それは、ネットワーク的関係を持っている影響要因と環境要素や生物との関係をわかりやすく示すことができ、マトリックスでは表現しにくい影響の伝播経路を示すこともできるからである。ただし、作成したフロー図はもれがないように、従来のマトリックスも同時に作成して相互にチェックすることが必要である。
特に、陸域生態系に与える影響の検討の際に重要なことは、垂直的には植物群落の階層構造が発達し、水平的には様々な環境がモザイク状になっている場合が多いことである。そのため、対象地域への影響の整理にあたっては生態系の垂直・水平構造への影響を把握することが大切であり、階層構造の変化や複数の類型にまたがる広域的なスケールでの影響、隣接する類型間での影響、ひとつの類型内での影響といった空間的に異なるスケールでの影響を適切に捉えていくことも重要である。
なお、事業ごとの技術指針においては標準的な影響要因が示されているが、これを参考にしつつも、これにこだわらず生態系やそれぞれを構成する環境要素に対する影響を捉える観点から、幅広く抽出することが必要である。
以下に、影響要因と環境要素の変化のマトリックス(表I-1-1)、環境要素の変化と類型とのマトリックス(表I-1-2)、影響フロー図(図I-1-4)についての例を示す。このような手段で影響の検討結果を整理し、事業者が事業による影響をどのように捉えているかをわかりやすく示すことが必要である。なお、マトリックスや影響フロー図は、ここに示した方法以外にも様々なものを作ることができ、フロー図の線の引き方も作り手の考え方によって異なる。したがって、例示したものが標準的であるということではない。
表I-1-1 影響要因と環境要素の変化とのマトリックスの例(面整備)
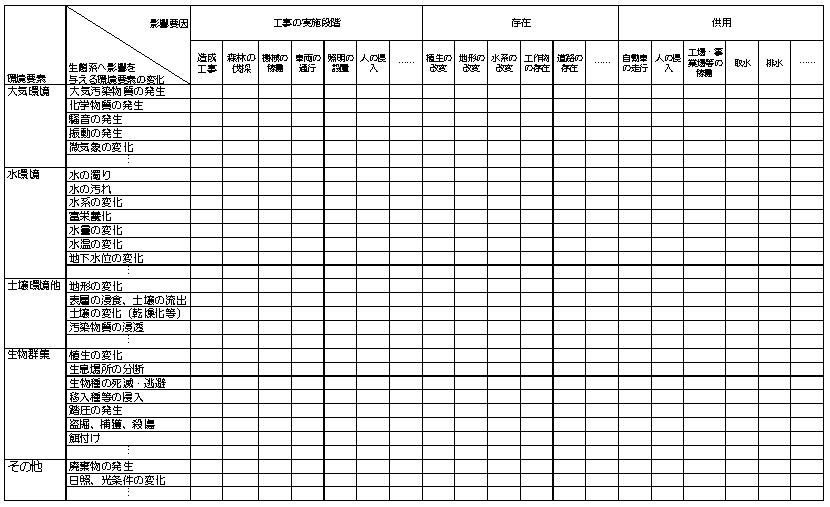
表I-1-2 環境要素の変化と類型のマトリックスの例
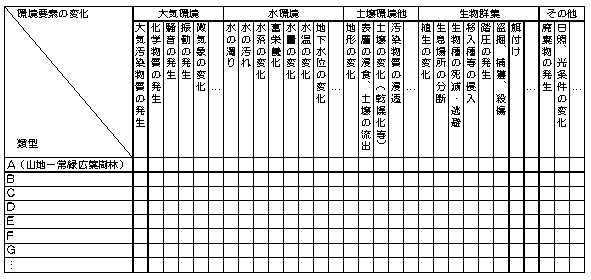
図I-1-4 影響フロー図の例
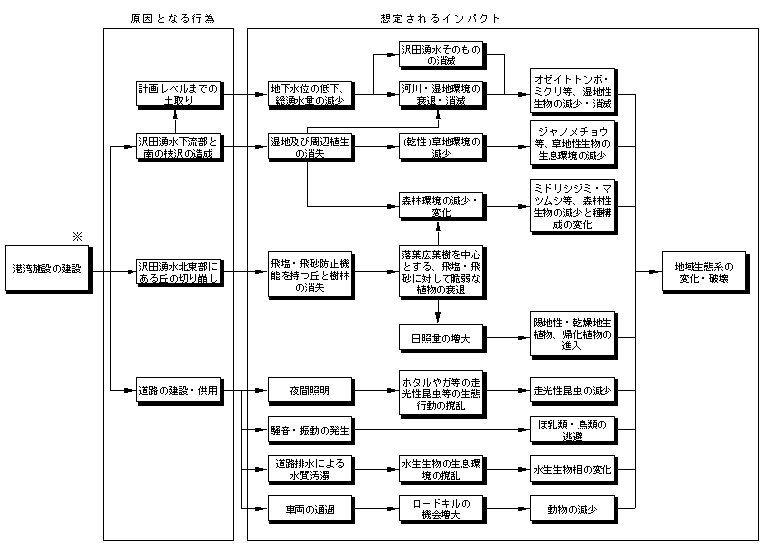
※陸域の丘陵地に改変が及ぶ事業内容である。 日置ほか(1998)(一部改)
調査地域については環境影響評価の段階や調査対象により、以下に示す[1]~[3]の捉え方で設定することができる。特に環境影響評価の実施段階での調査地域にあたる[2]及び[3]では事業による直接・間接的な影響の範囲と程度、地形・地質、水系、植生等から把握される生態系のつながり、生物種・群集の特性を考慮することが重要である。また、影響の評価や回避・低減等の環境保全措置の検討が適切に行えるという視点も大切であり、個別の事業ごとに適切な調査地域を設定することが必要である。なお、これらの範囲は、実施段階の現地調査等の結果を踏まえ適宜見直していくことも重要である。さらに影響範囲外にあると推定される同様の環境についても対照とする地域としてとらえ、後に実施する事後調査もおいても必要と考えられる場合には調査範囲に含める。
- [1]事業実施区域とその周辺の広域的な概況把握を行う範囲
- 事業実施区域の、広域から見た自然的特性や生物種の分布特性などについて把握するため、スコーピングの際に地域特性の把握を行う範囲として設定する。範囲の設定には主に地形・地質、水系、植生、土地利用などを考慮することが重要である。
- [2]調査地域
- 基盤環境、植生、動植物相に関する情報を主に現地調査により収集・整理する範囲は、事業実施区域とその周辺部とする。
調査地域の設定に際しては影響要因と影響の時空間的な広がりを概略推定する必要がある。そして、事業による直接的及び間接的な影響が生ずる可能性があると推定される区域を含み、事業の影響を評価するために必要な範囲とする。範囲の設定には、集水域などの地形単位(谷や尾根で区別される範囲等)や植生・土地利用等のまとまりを考慮することが重要である。
なお、事業計画は着工までに変更される可能性もあり、それを念頭においてあらかじめ変更の可能性のある範囲を調査地域に含めておく必要がある。これは環境影響評価法施行令第9条、第13条において事業によっては関係の規定があるので留意する。 - [3]注目種・群集の調査対象地域
- 注目種・群集への影響を把握する範囲として設定する。これは、注目種・群集が事業の影響を受ける可能性がある場所及び、注目種・群集への影響を当該地域で評価するために必要な周辺の範囲も含む。
注目種・群集の生態、行動圏の大きさ、生活史を完結するための生活空間の広がり、個体群の広がりなども考慮する。場合によっては当該地域にみられる個体群全体が含まれる地理的範囲などを対象として調査することも必要である。また、渡りをする鳥類など季節的に長距離移動を行う生物種については、生活史の完結する範囲をすべて現地調査範囲とすることは現実的ではないため、既存資料などを用いて情報を補完して影響を検討する。なお、調査対象地域の範囲の設定には植生や地形など注目種・群集の分布を規定する環境要因を考慮することが大切である。
(1)調査・予測・評価項目の検討
「1」に示した基本的な考え方に従い、本報告書では陸域生態系の影響評価のための調査・予測手法として、「基盤環境と生物群集の関係に着目した調査・予測」及び「注目種・群集に関する調査・予測」の手法について提示する。これらは主として生物種・群集とその基盤となっている環境要素に着目して、生態系への影響を捉えることを目的としている。生態系の影響評価内容としては、その他にも大気・水質浄化機能、二酸化炭素固定化機能など生態系の様々な機能への影響もあり、それらの機能への影響についても環境影響評価の中で必要に応じて調査・予測を行う必要がある。
「基盤環境と生物群集の関係に着目した調査・予測」では基盤環境と生物群集の関係について調査し、対象地域の生態系の垂直・水平構造の概要を把握した上で事業がそれらに及ぼす影響を予測することにより、生態系への影響を捉える。また、ここで把握される基盤環境と生物群集の関係は、注目種・群集の見直しや調査・予測などにも活用することができる。
「注目種・群集に関する調査・予測」では上位性・典型性・特殊性の視点から生態系を特徴づける生物種・群集に着目し、事業による環境の変化が注目種・群集へ及ぼす影響をより詳細に調査・予測することを通じて、生態系への影響を捉えていくこととなる。
そして、これらふたつの方法による調査・予測を相互に関連づけながら実施し、両者の結果を合わせて生態系への影響を予測評価するものである。
調査・予測の項目や手法は「3-1」で示した生態系への影響内容の整理結果を踏まえ、重要と考えられた項目についてその現況を調べ、事業による影響要因が時間的・空間的にどのようにそれらに作用するかを予測評価できるように選定することとなる。
現在の科学的知見では生態系への影響として想定されるすべての項目を調査・予測することは困難であり、理論的には可能な調査でも長い年月を要するため現実的でないものもある。しかしながら生態系の保全という目標に対して、できる限り科学的・定量的に行うという姿勢が重要なことはいうまでもない。
重要なことは、生態系の評価にあたって影響評価を行う当事者がどのような視点で問題を検討し、どのような目的を持って調査・予測の項目・手法を選定して実施したのかが明確に示されることである。調査・予測の項目や手法を選定した理由については、なるべくわかりやすく明示することが必要である。
(2)基盤環境と生物群集の関係の調査
特定の注目種・群集に関する詳細な調査を行う前に基盤環境と生物群集の関係について概括的に幅広く調査することにより、生態系の垂直・水平構造を把握する。このためには、基盤環境、植生、動植物種の関係を把握することを念頭に、「地形・地質」「植物」「動物」等の他項目と連携した現地調査及び既存資料調査を行うことが有効であると考えられる(図I-1-5)。調査は、既存資料と現地調査により各種の基盤環境、植物群落、動植物相、動植物種に関する情報を収集し、その関係を整理する(表I-1-3)。
また、表I-1-3の項目以外にも、対象地域の環境特性を捉える上で重要な項目については必要に応じて調査することが大切である(表I-1-4)。
基盤環境、植生、動植物種等の情報を整理する際には、他項目における調査により作成した植生図、地形分類図、土壌図等の主題図により詳細類型区分図を作成し、詳細類型区分を要素間の関係を整理するための単位とすることが有効と考えられる。(表I-1-5)
図I-1-5 基盤環境と生物群集の関係の調査から予測の流れ
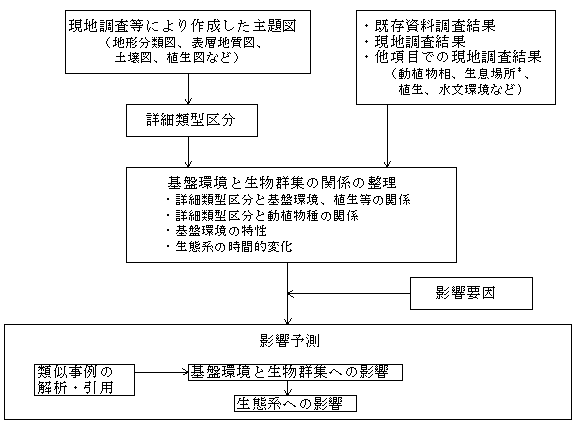
表I-1-3 基盤環境と生物群集について調査する情報(例)
| 調査対象 | 調査項目 |
|---|---|
| 動植物種 | 動植物相、分布、生息場所、生活史と生息場所の関係など |
| 植物群落 | 分布、階層構造、林床の状況、管理との関係
各群落の成立する基盤環境の特徴、光環境など |
| 地形 | 地形分類とその分布状況(小地形、微地形程度)、斜面方位、谷密度など |
| 表層地質 | 表層地質分類とその分布状況(既存資料、他項目での調査資料がある場合には基盤地質についても把握する) |
| 土壌 | 土壌分類とその分布状況 |
| 大気環境 | 温度、湿度、大気質など |
| 水環境 | 水系の位置、流域の範囲、地下水位、水質、水温の状況など |
*本報告書では動物の生息場所及び植物の生育場所をも含めて、「生息場所」と表現することとした。
表I-1-4 環境タイプ別に調査対象として考えられる項目(例)
| 丘陵地・台地 |
|---|
|
| 海岸 |
|
表I-1-5 詳細類型区分に用いる情報(例)
| 地形分類図 | 現地調査・航空写真判読等により作成したもの(小地形、微地形単位程度) | 縮尺 1/2,500~10,000 程度 |
| 表層地質図 | 〃 | |
| 水系図 | 〃 | |
| 植生図 | 現地調査・航空写真判読等により作成した詳細な植生図 | |
| 流域区分図 | 事業による基盤環境の変化を把握するために適切なスケールのもの |
○基盤環境と生物群集の関係についての調査にあたってのポイント
| [1] | 対象地域の生態系の特性や事業の特性を踏まえ、その垂直・水平構造への影響を把握するために必要な情報の項目について、実際の環境影響評価の案件ごとに検討する必要がある。 |
| [2] | 詳細類型区分を単位とした生物群集の整理を行う際には、「植物」「動物」項目における動植物相の調査結果が有効に活用できるよう工夫することが必要である。また、動植物相の調査結果を詳細類型区分単位の抽出、見直しに反映させることが必要である。 ここで、動植物相について把握・整理を行う生物群は、スコ-ピングでの検討結果から、対象地域の生態系の特性や事業の特性に応じて生態系の変化を検討するために必要と考えられる主要な生物群を対象とすれば良い。 |
| [3] | 基盤環境と生物群集の関係の整理を行う際には生物の生活史を考慮することが重要である。例として、動物ではその場所が繁殖場所かどうか等は重要な視点である。このような生物の生活史と利用する生息環境との関係を整理するにあたっては既存資料調査や現地調査により十分に情報を収集することも大切である。 |
| [4] | 植物群落は基盤環境の変化や人為的要因などに影響を受けて常に変化し、その変化は生物の生息場所に影響を与える。このため、基盤環境の変化が生物群集に与える影響を整理するには植物群落の時間的な変化とその要因を把握する必要がある。現地調査結果のみによっては植生の変化傾向など調査に長期間を要する情報は得られないため、既存文献から得られる情報を十分活用する必要がある。 |
| [5] | 基盤環境を捉える際にはその目的に合ったスケール・分類を工夫する必要がある。例えば、地形分類には形状、成因、地史、地形の安定性等異なるレベルでの区分方法があるが、広域において地域の特徴を捉える場合には大起伏山地、小起伏山地等、形状による分類が有効となる。種レベルでの生息場所の特徴を捉える際には斜面の凹凸など地形の安定性を反映させた分類方法が有効となる。 |
| [6] | 湿地や石灰岩の露岩地など対象地域の生態系を捉える上で小規模であっても重要な環境が見落とされないよう注意する。このような環境を抽出するためには地域のモザイク性を十分捉えることができるスケールで調査・整理を行う必要がある。 |
○詳細類型区分についてのポイント
スコーピング段階で作成した類型区分が既存資料を基に作成されるものであるのに対し、詳細類型区分は現地調査結果に基づき、現況に即して作成されるものである。詳細類型区分は適切な要素により捉えられた環境の重ね合わせにより抽出する。重ね合わせる環境要素としては地形・地質や動植物項目において作成された主題図を利用することも考えられる。抽出された単位は、煩雑なものとならないよう、環境要素の対応関係に基づいて整理する。
なお、詳細類型区分の単位の抽出においては上記[6]で示したように、小規模であっても重要な環境が見落とされることのないように注意する。これらの要素は小規模な要素は点情報として把握することも考えられる。同様に、類型間にみられる移行帯についても生態系を捉える上で重要であり、線情報として整理することなど見落とされないように注意する必要がある。
詳細類型区分に際しては生物群集の生息場所を把握するために適切な区分となるよう区分単位を考慮する必要がある。例えば、鳥類と昆虫類とでは行動圏の大きさや、生息場所の環境の質が異なるため、環境との関係を捉えるための情報や空間のスケールは異なってくる。そのため、詳細類型区分の単位が様々な生物との関係に対応できるものとなるよう階層性を持たせるなどの工夫をする必要がある。
この詳細類型区分は現地調査と並行して適宜修正され、現地調査結果を踏まえて最終的なものに仕上げられる。
(3)注目種・群集の調査
注目種・群集に関する調査は事業による生息場所の変化が注目種・群集へ及ぼす影響を予測するために情報を得ることが目的となる。その流れを図I-1-6に示す。
事業が注目種・群集に及ぼす影響は非常に多岐にわたり、また、複数の影響要因が複合して注目種・群集に影響を及ぼすものと考えられる。しかしながら、現在の科学的知見ではこれらの影響要因が及ぼす注目種・群集への影響を、すべて定量的に把握することは多くの場合難しいと考えられる。実際には、その時点で活用し得る科学的知見や生態系項目についてどの程度重点をおいて環境影響評価を行うべきかの検討を踏まえて、重要と考えられる影響について調査・予測・評価を行うことになると考えられる。したがって、どの部分の影響を重点的に評価すべきかをよく検討し、その選定理由を明確にすることが特に重要である。
重点的に評価すべき項目が選定されたら、その予測のために必要となる調査・予測項目と手法の検討を行う。調査項目としては、注目種・群集の生息状況、生活史、生息場所、種間関係等があるが(前年度中間報告書参照)、予測・評価すべき内容に応じて、どの程度までの調査が求められるのかを考慮し、適切に選択する必要がある。
注目種・群集に関するこれらの調査項目の中には、対象とする種によっては調査方法が確立されていない場合や調査方法としては確立されていても調査に長年月を要するために現実的でないものもある。そのため、調査項目の選定にあたっては調査対象となる生物種の生態的な特性を十分考慮する必要がある。また、調査地点・期間・時期・回数などを決定する際にも、調査対象とする生物種の生活史や生態的な特性を踏まえ、適切に設定することが必要である。なお、このような調査内容を決定する際には事後調査も考慮する必要がある。
検討の際に重要と考えられる視点は次の通りである。
- 事業による影響によって注目種・群集の生息場所が消失・減少することで、注目種・群集にどのような影響を与えるのか。
- 事業実施に伴う環境要素(地形・地質、水環境など)の変化がどの程度注目種・群集に影響を及ぼすのか。
- 注目種・群集への影響が生じた場合、他の生物(生態系)にどのような影響を及ぼすのか。
また、注目種の生息場所に関する好適性の区分を行うことは、複雑な生態的な側面を生息場所という土地の空間的な広がりとして把握しその変化を定性的または定量的に予測評価できることから、注目種への影響や環境保全のための配慮について検討していくためのひとつの有効な方法であろう。
図I-1-6 注目種・群集の調査から予測の流れ