生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
生物多様性分野の環境影響評価技術(II) 生態系アセスメントの進め方について(平成12年8月)
3-4 陸域生態系への影響予測
(1)影響予測の基本的な考え方
予測を行う際には影響要因や影響内容に応じた適切な手法で行うこととなるが、基本的な留意点として以下の事項があげられる。
- 科学的・技術的に可能な範囲でできる限り定量的な予測を行う。
- 予測の不確実性の程度について明確にする。
- 類似事例や科学的な知見の引用は重要であるが、対象事業の影響に当てはめる場合には種や環境条件によって地域的な差がある可能性があり、引用したデータについてはその背景を十分考慮する。
- 生物種・群集の変化に関する定量的な予測は直接改変による消失などの場合を除き、難しい場合が多いが、生物の生理的・生態的な特性を十分に検討し、調査で得られたデータに基づいた客観的な予測を行う。
- 事業による環境の消失・縮小に伴う影響だけではなく、新たに創出された環境により生じる移入種の侵入・都市型生物の増加などによる影響も考慮する。
- 予測にあたっては事業実施区域や調査地域を一律に考えるだけではなく生態系のまとまりを考慮し、小流域単位で様々な予測結果をとりまとめるなど予測評価のための空間単位を考慮することも大切である。
- 生態系への影響は工事中は影響が大きくても工事後には植生の回復などにより影響が緩和される場合もあり、逆に長期的に時間とともに大きな影響が現れる場合もある。このように影響が時間とともに変化する場合があることを考慮する必要がある。
【GISの活用について】
調査及び予測の作業にあたっては各種調査結果をデータ化し、GIS(地理情報システム)により解析を行うことで効率的な作業を行うことができる。特に、環境影響評価においては複数の主題図間のオーバーレイ機能や面積計算などの数値処理等により、類型区分の作成の他、調査地点の選定、調査・予測における複数案の影響の比較検討などの解析や種々の図面の作成などに利用することが可能である。
(2)予測手法
1)基盤環境と生物群集の関係による生態系への影響予測手法
基盤環境及び植生に影響を及ぼす要因を整理し、基盤環境と生物群集の関係の調査・整理の結果を踏まえた上で、事業の影響要因が基盤環境と生物群集、及びその関係に与える影響を概括的に幅広く予測する。この際、生物群集の生息場所が変化する可能性を、類似の事例や既存の知見を参考に検討する必要がある。また、基盤環境や人為影響の変化により植生が時間的に変化し、生物の生息場所に影響を与えることにも留意する必要がある。
これらの作業を通じて、生態系の垂直・水平構造の変化を把握し、それによる生態系への影響を予測する。
なお、この基盤環境と生物群集の関係に基づく影響の予測のみによっては生息地の分断や生活史の上で重要な生息場所の消失、複数の環境を利用する動物に対する影響など、十分には予測できない事柄も多いと考えられる。このような影響については注目種・群集の調査により詳細な影響の予測を行う。
2)注目種・群集による生態系への影響予測手法
注目種・群集による生態系への影響予測はまず事業による影響要因により、注目種・群集に直接的・間接的にどのような影響が及ぶのかを予測することから始まる。
予測は、主に注目種・群集の生息場所への影響から注目種・群集の生息に与える影響について、上記1)の検討内容も踏まえ類似の事例や既存の知見を参考に行う。その際、種間関係の変化(捕食者の増加、帰化種等による在来種の圧迫、餌種の変化など)による注目種・群集に対する影響の可能性や程度も類似事例や既存の知見などから検討することが必要である。
これにより、注目種・群集が指標している生態系の構造や機能の変化を把握し、それによる生態系への影響を予測することになる。
上記1)、2)において、予測すべき基盤環境、植生、動植物種及び注目種・群集への主な影響としては以下のものがあり、これらの予測項目に対して適切な予測手法を用いることが必要である。
- 植生の伐採や地形の改変などの事業の直接改変に伴う生息場所の消失、縮小、分断、 断片化による影響
- 水質汚濁や地下水位の変化等の環境要素の変化に伴う生息場所の消失、縮小、質の劣 化による影響
- 事業により新たに創出される環境に伴う生息場所の変化による影響
- 供用後の施設利用に伴う生息場所の変化による影響
- 人間の立ち入り等に伴う生息場所の攪乱による影響 など
(3)予測地域
予測地域は生態系への影響を予測するための適切な範囲とする。具体的には、調査結果を踏まえ事業による影響が及ぶ範囲を対象とするとともに、影響の程度・内容や対象の特性に応じて周辺の地域も含める必要がある。注目種・群集の予測地域は注目種・群集が事業による影響を受ける範囲を対象とするとともに、影響を予測するために、場合によっては事業実施区域及びその周辺にみられる個体群全体が含まれる地理的範囲などを対象として予測することも必要である。
(4)予測対象時期
予測の対象時期は影響の大きさを的確に把握できる時期とし、対象とする基盤環境、植生、動植物種及び注目種・群集の特性を踏まえ、影響の大きさを的確に把握できる時期に設定することが必要である。工事後には植生の回復などにより影響が緩和される場合もあり、逆に時間とともに影響が拡大する場合もあると考えられる。このため、工事及び施設の存在・供用の影響を予測する時期については一時点だけを予測するのではなく、可能な限り時間的な影響の変化が捉えられるように予測の時期を設定する。また、季節による影響の程度の変化についても考慮する必要がある。
環境影響評価は複数の事業計画案や複数の環境保全措置(影響の回避・最小化などの効果)の検討を踏まえて行うこととなる。したがって、スコーピングの段階で複数の事業計画案や環境保全措置について検討されている場合には複数の事業計画案の影響や環境保全措置(例えば事業予定地の変更など)による効果を予測するための情報収集も折り込んで調査・予測・評価を計画することが必要である。また、調査・予測・評価は一連の作業で一体的に行われるものであり、その過程で環境保全措置の検討にとどまらず事業計画へのフィードバックも繰り返し行われることとなる。
予測・評価の実施段階では複数の事業計画案や環境保全措置のケースごとに予測・評価を行い、必要であれば、方法書に記載しなかった新たな調査・予測手法を取り入れるなど柔軟な対応が望まれる。新たな調査・予測手法を取り入れた場合には準備書にその検討過程について記載することも必要である。
予測・評価の結果を準備書に記載する際には影響の予測結果、複数の環境保全措置の効果比較、最も影響が少ないと予測される事業計画案などに対する事業者の見解や判断を整理して述べることとなる。
環境保全措置と調査・予測・評価の関係は、図I-1-7に示したようになる。
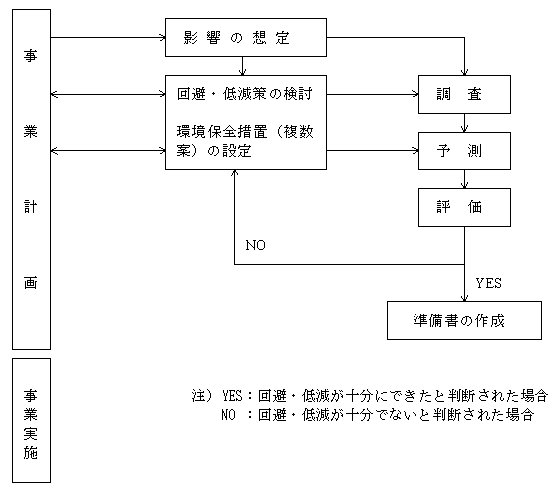
図I-1-7 環境保全措置と調査・予測・評価の関係