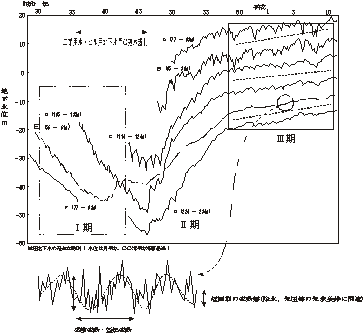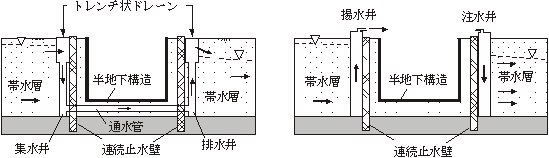平成14年度第1回検討会
資料 5
2章
2-2 水環境(地下水等)
地下水等については、環境保全措置、評価及び事後調査を行う上で、留意すべき事項を中心に、個々の作業イメージを具体化できるよう整理した。
また中でも、環境保全措置の立案の手順・環境保全措置の内容は、半地下道路事業に係る地下水流動阻害の場合については、一般的な影響の概要や実際の予測対策事例について、[1]保全措置の対象、[2]保全方針設定のための基礎的情報の考え方、[3]目標設定の考え方及び[4]保全措置の内容の順に述べた(ケーススタディ2~5)。
【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方
【ケーススタディ2】保全措置の対象
【ケーススタディ3】保全方針設定のための基礎的情報の例
【ケーススタディ4】目標設定の考え方
【ケーススタディ5】保全措置の内容
【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証
【ケーススタディ7】客観的な効果の評価
【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)
【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)
【ケーススタディ1】早期段階における環境保全への配慮の考え方
● テーマ
総論中に示された「早期段階での環境保全への配慮」の具体例として、環境影響評価前の事業計画立案時において、環境保全策及びその検討経緯について、方法書に明記することが望ましい。
スコーピング、環境影響評価実施以前の事業計画立案時において、環境保全への配慮として、問題点、目標、保全技術を取り入れた対策及びその検討経緯について、方法書に記載し、以後の調査・施工計画に資することとする。検討事例を示す。
● 方法書記載例【地下鉄事業の例】
工事による地下水の地表面湧出、街路樹等植生の根腐れ、井戸涸渇等の環境諸要素の保全を目的に、上流から下流に地下水を通す工法を選定し、周辺環境への影響を小さくするよう配慮する。
● 方法書記載例【造成事業の例】
丘陵地を造成し宅地化するにあたり、事業地には従来の表面排水システムに変わり、雨水浸透方式等の環境保全技術を取り入れた工法を採用し、開発による地下水環境へ影響を小さくするよう配慮する。
【ケーススタディ2】保全措置の対象
● テーマ
保全措置の対象を選定するにあたって、地下水が水循環系の一部であり、水の特性・機能(循環、変動、地盤構成要素、物質運搬者)を十分に考慮する必要がある。つまり、地下水の主な供給源は降水や地表水(河川、表流水等)であり、それらが浸透または帯水する涵養域や流出部にあたる河川・湖沼・海洋、湧水での水収支バランスが保全されるか否かを考慮しながら事業を進めなければならない。
事業者は事業(以下の事例は都市部における半地下道路事業)による環境要素の変化を想定し、特に重要と考えられる要素については、情報の収集・整理及び事業との関係を十分に把握しておくことが望ましい。保全措置の対象の選定例を示す。
【道路事業:半地下道路工事の例】
半地下道路事業(掘割構造)における地下水流動阻害の場合を例(図2-2-1)に、想定される環境保全上の問題(事象)を示し、この場合の環境要素(左欄)と実際の影響内容をとりまとめる(表2-2-1)。
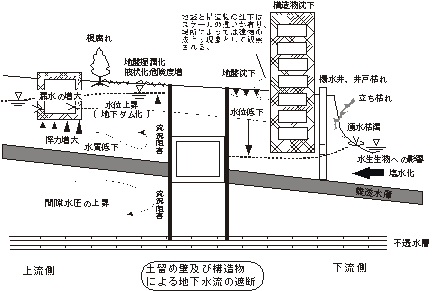
図2-2-1 半地下道路事業による地下水流動阻害とその環境保全上の問題(概念図)
|
上流側 |
下流側 | |
| 地下水位 |
水位(水頭)上昇 |
水位(水頭)の低下 |
| 地下水利用 |
- |
井戸涸れ 湧水涸渇 |
| 地盤環境 |
地盤の湿潤化液状化危険度の増大 |
地盤沈下・酸化等 |
| 地下水質 |
滞留による水質低下 |
塩水化 |
| 生態系 |
根腐れによる樹木の被害地盤内生物への影響 |
樹木の立ち涸れ水生生物への影響 |
| 構造物 |
浮力増大地下漏水量増大 |
間隙水圧低下による沈下 |
注) 実害に至るか否かは地下水位変動の程度や地盤条件による。
【ケーススタディ3】保全方針設定のための基礎的情報の例
● テーマ
環境保全方針の検討には、その前提条件となる[事業特性]、[地域特性]の十分な把握が不可欠である。つまり、事業において想定される環境影響の出現に密接な関係をもつ環境要素とこれに関わる地域特性の整理・検討が特に重要となる。
ある事業が周辺環境に及ぼす影響は広範で、その保全対象も多岐にわたるが、ここでは半地下道路事業に伴う周辺環境への影響の中から、地下水位について取り上げ、基礎的情報としての地下水位(都市部における被圧地下水)の変動の事例における考え方の例を示す。
【自然条件・地域特性情報としての被圧地下水位】
地下水位は不圧地下水と被圧地下水に大別されるが、下図に示す通り、都市部の被圧地下水は、全体的な傾向は概ね調和しているものの、地域ごとに水位や変動幅に差があり、事業にあたっては対象地域の地下水変動が過去、現在及び将来的にどのような変化が見込まれるか等、十分な検討が必要である。
|
|
Ⅰ期:揚水による水位低下期 |
|
図2-2-2 地域特性としての地下水位情報(被圧地下水位の変動傾向の例) |
|
図2-2-2では、都市部における長期的観測データとその短期変動の状況について、事業対象地に近接するE地区の地下水位変動例を示すとともに、その特性の概略を以下に示す。
・E地区の被圧地下水位は規制以前では断続的な水位低下期が、規制後は急激な水位回復期を経て、現在は穏やかな水位上昇期にある。(この資料は、自然現象としての水位変動と地域特性を示す変動の両者の性質を合わせ持つ)
・現在の変動傾向は、短期的(1年以内)には気象条件に強く影響を受け、中長期的には事業対象域を含む涵養域・流出域全体の水収支や社会的情勢の変化等に左右されていると考えられる(不確実性)。
【ケーススタディ4】目標設定の考え方
● テーマ
事業対象地における地下水環境の健全性を知る手段の一つとして、地下水位は最も簡便な指標と考える。しかし、その変動が自然要因によるものか、人為的要因の作用によるものかを精度良く判別することは容易ではない。
地下水位の変動を指標とし、地下水環境保全のための目標設定を行う場合の例を示す。
【地下水位変動に対する目標設定の例】
半地下道路事業において地下水流動を一時に遮断させるような場合、地下水位は急激な変化を示し、供用後も以前の水準から大きく変化する場合が少なくない。特に、事業前段階における地下水位の特性を精度良く把握していない場合、供用後に周辺環境に及ぼす影響が大きいことが予想されることから、事前に十分な検討が必要となる。
以下、図2-2-1に示した都市部の地下水位(E地区)が事業によって将来的にどのように変わるかを予測し、目標を設定した例を示す。
・既往調査及び文献調査から水位変動の周期性を確認し、実測でも調和的な変動傾向や変動幅を確認した。
・基本統計値(最大、最小、平均及び変動率等)を考慮し、将来の地下水位を想定(複数)した。
・事業による水位変化はシミュレーションによる。
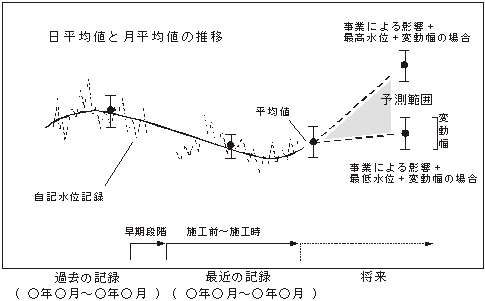
図2-2-3 事業化における地下水位の変動目標の設定
【ケーススタディ5】保全措置の内容
● テーマ
事業者は、事業計画立案時及び環境影響評価の結果を受け、事業による周辺環境への影響を「回避・低減」あるいは避けられない影響については「代償」する措置をとることとなる。
ここでは、半地下道路事業における保全措置の事例として、復水工法を採用し、地下水流動阻害に起因する水位変動を低減させた例を示す。
● 評価書記載例
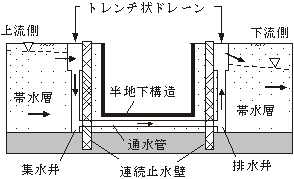 |
山留工で透水層を遮断するため、連続止水壁に加えトレンチ状ドレーンを路線の両側に設置し、この間を通水管で繋ぐ。この方法より上下流両側での水位の変化が小さく、地下水の流向や水量の安定確保が見込まれる。 |
|
図2-2-4 復水工法採用による地下水流動阻害の低減の例
|
|
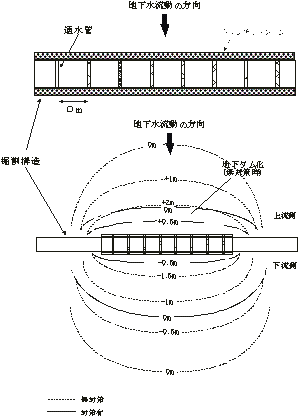 |
図2-2-5(上)に施工平面図を示す。 |
|
図2-2-5 保全措置(施工)の平面図及び低減範囲 |
|
【ケーススタディ6】環境保全措置の妥当性の検証
● テーマ環境影響評価段階において、環境保全措置の検討経緯を並列的に記載し、その妥当性を検証した例を示す。
ここでは、半地下道路事業における地下水流動阻害(水位や流向の変化)を低減させるため、複数案の比較、実現性等による環境保全措置の選定の妥当性を例示する。
● 評価書記載例
【複数案検討の例】
対象事業が地下水環境及び利水環境に及ぼす影響を低減するための最適な環境保全措置を選定するため、以下の2案を比較検討する。
|
保全措置A案 |
保全措置B案 |
|
|
|
|
図2-2-6 複数の保全措置案における検討事例 |
|
原案に対し、2つの保全措置(A、B案)について、効果の可能性、実行可能性及び改善効果等からの比較検討した事例を示す。
|
対策内容及び環境 |
掘割構造(原案) |
ドレーン+通水管 (A案) |
揚水井+注水井 (B案) |
|
地下水流動阻害・対策効果 |
連壁によって上流側の地下水を上昇させ、路線の両側に沿って設置したドレーン溝から連続的に上流側地下水を取水する。○m置きに集水井と通水管で地下水を下流側へ送水する。通水管径:φ○mm |
揚水井を○m置きに掘削し、地下水を取水する。 揚水深度:○m 掘削径:φ○mm 仕上げ径:φ○mm 地下水は下流側の注水井を通じて地中に還元する。 |
|
|
○ |
△ | ||
|
知見の不十分さがあるが効果の可能性として考えられる事項 |
・必要水量の○%が確保でき、他の方法と併用することで効果が期待される。 ・上流側地下水位・流量の変動によっては集水効果が低下する。 ・将来にわたって効果が持続するか不明(目詰まり等) |
・必要水量の○%が確保でき、他の方法と併用することで効果が期待される。 ・上流側地下水位・流量の変動によっては集水効果が低下する。 ・将来にわたって効果が持続するか不明(目詰まり等) |
|
| 実行可能性 |
・技術的には十分 |
・技術的には十分 |
|
|
○ |
△ | ||
|
効果を見込んだ場合の本事業による地下水流動阻害等の改善効果 |
・確保水量○/min |
・確保水量○/min |
|
|
○ |
△ | ||
| 評価判定 |
地下水流動阻害を回避・低減するための対策が必要。 |
水量確保の確率が高く、上流側、下流側に対して面的な改善効果が大きい。 |
水量確保、地下水流動阻害の改善効果は井戸の周辺を中心に改善される可能性がある |
|
× |
○ |
△ |
【ケーススタディ7】客観的な効果の評価
● テーマ
環境保全措置の結果を客観的に評価するには、環境要素、もしくはその関連事象が定量的に計測・観測されることが前提となる。
地下水環境においても、既に環境基準や条例による基準が設定されている場合はその基準が評価に用いられる。しかし、実際には事業による地下水環境への影響が出現する場合でも、その事象の多くに明確な基準値がないため、環境影響の程度を客観的に評価することが困難となっている。
このような基準をもたない環境要素に対し、その要素が本来のあるべき姿(または事業化以前の状態)が基本となり、これを基準(ベースライン)として環境影響を考えることができる。
ただし、前述したように、環境要素は地域特性をもち、かつ、その要素自身も固有の変化を示す場合(図2-2-1の地下水位の変遷等)があることに留意して目標を設定し、評価の基準として活用すべきである。
「保全方針設定のための基礎的情報の例」で取り上げた地下水位について、半地下道路事業で採用した保全措置の客観的評価の例を示す。
● 評価書記載例
【半地下道路事業で用いた保全措置の効果(地下水位変動の低減)の例】
図2-2-7には、事業により発生する地下水流動阻害に対して、既往調査や施工前の観測及びシミュレーションにより、保全措置(復水工法)の効果を検討した事例を示す。
保全目標:地下ダム化による上流側の水位上昇を現況+○m以下に、下流側の水位低下を-○m以下に抑える。既存井戸の利水環境を変えない。
影響予測:復水対策なし → 上流側で現況+○mを越える水位上昇が予測され、下流側では最大○mの水位低下が見込まれた。
復水対策あり → 上・下流側共に目標の範囲内に水位変化が予測されるが、下流側ではやや水位の上昇が見込まれた。
評 価:地下水位は現況と調和的な文応を示すことから、地下水流動阻害による影響は低減されること、利水環境への影響がないことが各々予測され、対策の効果が高いことが判明した。
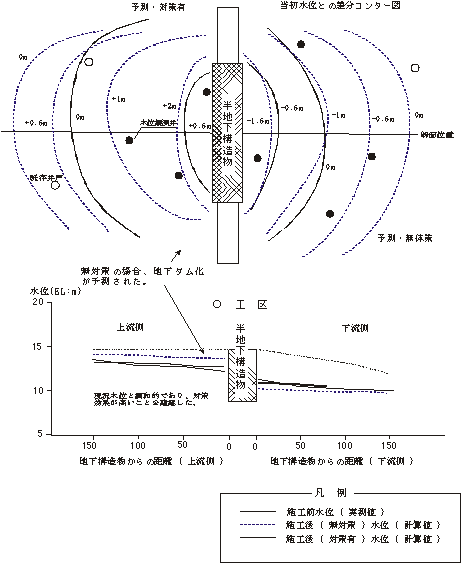
図2-2-7 道路事業における保全措置の効果
【ケーススタディ8】事後調査(調査実施案)
● テーマ
環境影響評価及び環境保全措置の採用に基づく開発行為により、供用された施設(やその機能)は、長期にわたって水環境の中で周辺の環境諸要素に影響を与えることとなる。
このような新たな関係がその地域環境において健全か否かを確認するため、あるいは初期の予測や保全効果が妥当かどうかを把握するため、環境保全の観点から事後調査は重要である。ここでは前述した半地下道路事業における事後調査の事例を示す。
● 評価書記載例
保全措置の妥当性の検証「保全措置の複数案検討の例」で示したケースにおける事後調査の実施案の例を示す。
本ケース(保全措置B案)では、揚水井と注水性を用いた復水工法によって、安定した流量が確保され、流動地下水の保全に寄与する効果が見込まれた。しかし、実際に揚水による周辺環境への影響は不明であり、事後調査によって、環境項目の監視が必要であった。
|
調査項目及 |
<地下水位> |
| 調査範囲 |
<地下水位> |
|
調査実施時期 |
○調査実施時期 |
| 調査方法 |
事前調査時の方法を踏襲する。 |
|
調査結果の取扱い |
公表 |
|
不測の場合 |
不測の状況にあった場合は、原因調査や緊急調査を実施し、かつ、有識者による検討会を設置し、その原因による影響を回避、低減する環境保全措置を計画・実施する。・・・・・・ |
| 実施体制 |
事業者。ただし、周辺環境の状況については地方公共団体の関連部局の公表資料を参照する。 |
【ケーススタディ9】事後調査(事後調査報告)
● テーマ
事後調査報告の例を示す。
● 記載例
|
調査項目 |
流況・水位・水質 | 関連する環境要素 | 周辺環境の状況 |
|
環境保全措置 |
・水質的に問題となる変化は認められない。 ・路線上流側での水位上昇は予測範囲内であった。 ・これまで灌漑期には慢性的な水不足であったが、揚水により十分な水量が確保され、余水が路線南側一帯に供されている。 |
・事業地周辺の井戸の水位変動は予測の範囲にあり、変動による環境影響は認められない。 ・揚水により南側農地の井戸では若干の地下水位の上昇が見られたが余水は河川等に戻されている。 |
・予測対象範囲周辺域での地下水位及び水質の状況は経年変動及び降雨時の短周期的な変動が見られるものの、悪化の傾向は認められない。 ・上記範囲での地盤及び植生に関わる変状は認められない。 |
| 追加的措置 |
特になし。 |
特になし。 | 特になし。 |
| 今後の対応 | ・中長期的に保全対象の推移を見守る。 |
・関連する環境要素の推移を見守る。 |
・周辺環境の推移を見守る。 |
|
今後の事後 |
・実施された保全措置の中長期的な効果を確認するための継続調査を行う。
|
・関連する環境諸要素は、既存データを活用し、保全対象の変化に関わらず定期的な監視を行う。 |
・周辺環境に関わる情報の整理を行う。
|