平成14年度第1回検討会
資料 5
1章
1-2 騒音・振動・低周波音
1)調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査の基本的な考え方
(1)調査・予測・評価、環境保全措置の検討及び事後調査のあり方
環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておく必要がある。特に、「評価」の視点を明確にすることは、環境影響評価の適切な実施において重要であり、このためには、環境影響評価の実際の作業の流れと逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めることが重要となる。
これは、環境影響評価法における「評価」が、事業者による環境影響の回避・低減への努力内容を見解としてまとめ、明らかにすることによる相対的な評価手法を基本とするためである。これが、「環境影響の回避・低減に係る評価」であり、環境保全措置の選定の妥当性を検証した上で事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断するものである。また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」も合わせて行われるが、環境保全措置の効果を考慮した予測結果と、環境基準及びその他の環境の保全の観点から定められた基準又は目標との整合が図られているか否かについて検討するものである。
このように、環境保全措置の検討は、「評価」を行う上で重要な位置をしめており、評価手法の検討を行う段階で、環境保全措置(案)についても検討することが必要である。この段階で環境保全措置(案)の検討を実施し、「評価手法→予測手法→調査手法」の順に検討を行うことで、環境影響評価を行うことは、調査不足や不適切な予測手法の選定等の手戻り等の発生を防ぐことが可能となり、また、環境保全措置の妥当性、具体性及び客観性に関する調査の必要性の有無を判断することも可能となる。
また、事後調査については、環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか否か、予測した対象事業による影響が予測範囲内であるかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。したがって、環境保全措置の検討等に合わせて、事後調査の手法の検討も必要に応じて検討することが望ましい。これは、事後調査における調査項目、調査方法等が未検討のままでは、事後調査におけるモニタリング実施地点を配慮して予測地点及び調査地点を設定するか否か等を判断することは困難であり、事後調査手法の検討は環境影響評価の効率的かつ効果的な実施の上で重要となってくる。
(2)調査・予測・評価と環境保全措置及び事後調査の関係(全体の流れ)
事業計画の立案から、スコーピング、環境影響評価(調査、予測、評価)を踏まえ、事後調査の実施に至るまでの作業の流れとこれらの作業における環境保全措置との関係は図1に示すとおりである。
[1]事業計画立案時における環境保全への配慮
事業計画の立案時においては、事業計画の一部として検討される環境保全への配慮がある。これは、大きな視野で検討される内容で、事業者の環境保全に対する姿勢、考え方等が示されることとなる。騒音・振動分野における事業計画の立案時に計画の一部として検討される環境保全への配慮としては、騒音・振動発生源の配置計画、騒音の影響を特に配慮すべき住居密集地、学校、病院等をコントロールポイントとして考慮した事業位置選定(工場立地位置選定、道路線形計画)等がある。
[2]スコーピング段階における環境保全への配慮の明示
スコーピング段階においては、対象事業の事業特性及び地域特性を把握した上で環境影響評価項目を選定し、それぞれの項目毎に調査・予測・評価手法を選定することとなる。騒音・振動に係る評価の項目は、該当する基準があるものは原則としてそれを選定し、また、基準がないものは対象とする騒音・振動を適切かつ効果的に評価ができるものを、背景を明確にしたうえで選定することが最も重要である。そのためには、事業概要として事業の必要性等について客観的に整理するとともに、事業規模、位置だけでなく、対象事業の実施により周辺環境に影響を与えると考えられる具体的な施設及び行為の計画の有無並びにそれらに対する環境保全への配慮の有無を、可能な限り示す必要がある。このとき、環境保全への配慮の検討経緯も併せて記載することが望ましい。通常これらの検討は、事業計画立案時に実施されている内容ではあるが、方法書では複数案からある一つの案が選定された検討経緯の記載は省略されている場合が多い。事業計画立案時における事業者の環境保全への配慮及びその検討経緯を可能な限り方法書に記載することにより、事業者のスコーピング作業における考え方が住民に対してより確実に伝達可能となり、理解が得られるものと考えられる。このことは、住民等から、より早期の段階で要点を得た意見の把握が可能となるため、効率的な環境影響評価手続きを進めるために重要なことである。
[3]環境影響評価実施段階での環境保全措置の立案
環境影響評価実施段階においては、事業計画の進捗に合わせて手法、効果及び妥当性等を踏まえてより具体的な環境保全措置を検討することとなり、その内容については複数案の比較検討等によりその検討経緯を明らかにできるよう整理し、準備書・評価書においてわかり易く記載する必要がある。
環境影響評価実施段階で検討される騒音分野の環境保全措置は、遮音壁の嵩上げ、低騒音舗装の採用等がある。
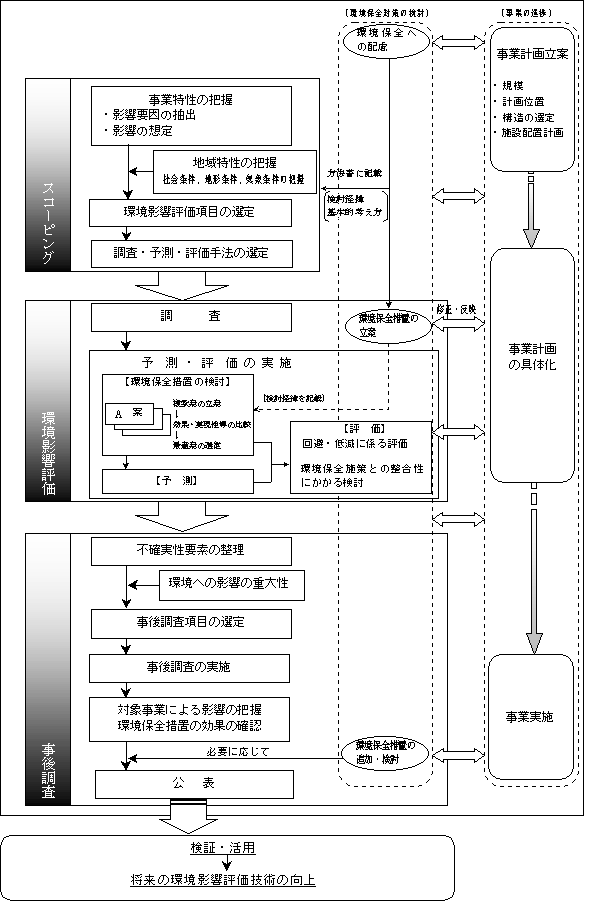
図1 環境影響評価と環境保全措置及び事後調査の関係(全体の流れ)
[4]環境保全措置を考慮した予測・評価の実施
環境影響評価法における評価の考え方として、「環境影響の回避・低減に係る評価」及び「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」がある。
「環境影響の回避・低減に係る評価」の実施においては、事業計画立案段階から環境影響評価実施段階における幅広い環境保全対策を対象とし、複数案の比較により妥当性を検証した上で事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断する。もし、検討した環境保全措置で回避・低減が十分にされていない場合には、事業計画案について必要な見直しを行い、環境影響が回避または低減するための最善の環境保全措置がとられていると評価されるまで検討を繰り返す必要がある。
また、「国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討」については、これら環境保全対策の効果を考慮し、予測に反映させて得られた結果と、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点から定められた選定項目に関する基準又は目標との整合性が図られているか否かについて検討する。
[5]予測及び環境保全措置の不確実性要素と事後調査の関係
事後調査については、環境影響評価により検討された環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか、予測した対象事業による影響が予測結果の範囲内であるかを把握すると共に、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討等を実施することを目的とする。
事後調査の対象となる項目は、調査・予測・評価の流れの中で考えられる不確実性を補う等の観点から選定されるものである。環境影響評価にあたっては、調査、予測から評価に至る過程で常に不確実性要素があることを念頭に置く必要がある。
特に予測や環境保全措置の効果等においては、その内容に不確実性要素を伴うことが多く、予測の不確実性要素には、予測の前提となる現状及び将来の自然的変動・社会的変動・人的変動、現状の把握にあたっての測定誤差及び予測モデルのそのものの限界やパラメータ・原単位等に内在する不確実性等のさまざまなレベルのものがある。例えば、道路交通騒音の予測の予測条件の一つである交通量については、それ自体が将来の道路整備計画を踏まえた推計を含む予測条件であり、将来の道路整備状況(想定シナリオ)は、将来の社会的変化に左右される不確実性を持つものである。また、環境保全措置の不確実性要素としては、その知見の不十分さが挙げられる。
これらの不確実性要素を整理し、その程度及びそれに伴う環境への影響の重大性に応じて事後調査の実施を検討する必要がある。
なお、環境影響評価の段階で想定した前提条件に大きな変更が確認された場合等、現実に合わせて条件を変更し、再予測を実施するとともに、この再予測結果と事後調査結果とを比較することにより、予測の手法の不確実性及び環境保全措置の効果についての検証が可能となる。
[6]事業実施後の対応
事業実施後においては、環境影響評価書で公表した事後調査実施内容に基づき工事中及び供用時の事後調査を実施することとなる。事後調査の結果、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、環境保全措置の追加・再検討をすることとなり、これらの検討内容は、事後調査結果と合わせて調査実施後できる限り早い段階で、適切な場所において公表する必要がある。
なお、環境影響評価の段階で想定した前提条件に大きな変更が確認された場合等は、変更の内容に応じて条件を変更し、再予測を実施するとともに、この再予測結果と事後調査結果とを比較することにより、予測の手法の不確実性及び環境保全措置の効果についての検証が可能となる。
2)環境保全措置
|
環境保全措置は、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響について、事業者により実行可能な範囲で、当該影響を回避し、又は低減すること及び当該影響に係る各種の環境保全の観点からの基準又は目標の達成に努めることを目的として検討されるものとする。 |
(基本的事項 第三項一(2))
(1)環境保全措置の考え方
環境保全措置とは、調査、予測及び評価を行う過程において事業者が実行可能な範囲で対象事業の実施による影響を回避又は低減することを目的として検討する環境保全対策である。環境保全措置は事業計画の中に反映される内容であるため、環境影響評価の中で最も重要であり、事業計画の進捗に応じてできる限り具体的に検討し、整理されることが必要である。
環境保全対策は、事業計画の立案から事業計画の進捗に応じて適切かつ具体的に実施されるものである。このうち環境保全への配慮は、事業計画の立案時に計画の一部として検討されるもので、事業者の環境保全に対する姿勢、考え方等が示されることとなる。これに対し、環境保全措置の立案及び追加検討については、調査、予測及び評価の過程と共に事業計画の進捗に応じて、手法、効果及び妥当性等を踏まえてより具体的に対策の内容が示されるものである。
また、環境保全措置の概念には、環境影響を回避する措置から避けられない影響を代償する措置までも含まれている。環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響を回避し、又は低減することを優先するものとし、これらの検討を踏まえ、回避又は低減効果が不可能であると判断された場合には、必要に応じ代償措置の検討を行う。
環境影響評価法における回避、低減及び代償とは、NEPAによるミティゲーションの概念と同様であり、各々の考え方は表2の内容として捉えることができる。
表2 環境影響評価法における回避、低減及び代償の考え方
| 区分 | 内 容 | NEPAによるミティゲーションの概念 |
| 回避 |
行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。重大な影響が予測される環境要素から影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。 【例】 施設立地位置の変更 等 |
回避(Avoidance) |
| 低減 |
行為(環境影響要因となる事業行為)の実施の程度または規模を制限することにより、また、発生した影響を何らかの手段で軽減または消失させることにより、影響を最小化するための措置である。 【例】 工事工程の変更、防音壁の設置 等 |
最小化(Minimization) |
| 修正(Rectifying) | ||
|
軽減/消失 (Reduction/Elimination) |
||
| 代償 |
行為(環境影響要因となる事業行為)の実施により損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出すること等により、環境の保全の観点からの価値を代償することを意味している。 |
代償(Compensation) |
しかし、実際に行う環境保全措置の効果が環境への影響を回避したのか低減したのかを厳密に区分することは困難である。工事用車両ルートの変更を実施する場合を例に挙げると、住居密集地域等の影響を受けやすい地域からの位置関係により、迂回した程度により低減効果となる場合もあれば回避として捉えられる場合もある。
回避と低減の概念は視点及び影響の低減の程度によって異なるものである。実施する環境保全措置が回避であるのか低減であるのかの区別は重要ではなく、環境保全措置は、あくまで環境への影響がどの程度低減されたかにより検討を行うものである。
また、騒音のように環境の質そのものに変化をもたらす場合は、同様の環境質を創出するという代償の考え方を実行することは現実的に困難である。そのため、騒音分野における環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響をいかに回避・低減するかが重要となる。
なお、環境影響評価においては、いわゆる「補償」に類する措置は、環境保全措置としては扱わない。
(2)環境保全措置立案の手順
[1]環境保全方針の設定
環境保全方針の設定は、環境への配慮をどのような視点で実施するのかを明らかにするために行うものであり、事業特性や地域特性を勘案して適切に設定する必要がある。具体的には、環境保全措置を実施する対象、環境保全の目標、環境保全措置の内容等を明らかにすることとなる。騒音分野においては、環境基準・規制基準等が設定されている場合が多く、基準の達成も環境保全方針の一つと考えることができるが、事業特性や地域特性を勘案した結果、基準の達成以外の環境保全方針を設定することが必要となる場合は十分に考えられる。また、地域の環境基本計画等により地域特性に配慮した目標や配慮の方針等が示されている場合には、十分に配慮する必要がある。
環境保全措置を実施する対象としては、住宅密集地域、学校、病院といった具体的な施設や、将来これらの施設が立地する地域全体を対象とする場合等が考えられる。
環境保全の目標としては、環境の状況に係る定量的な目標の設定や、実行可能な範囲での最大限の環境保全措置の実施といった保全措置に係る目標の設定等が考えられる。
環境保全方針の設定に考慮すべき地域特性としては、特に静穏を要すると考えられる施設や住宅密集地域の存在、現在の環境の状況等が考えられる。また、考慮すべき事業特性としては、騒音等の発生特性(時間、頻度等)、工事期間や施工方法等の工事計画等が考えられる。例えば工事期間については、ダム工事のように工事期間が10~20年に及び長期間に渡って環境に影響を及ぼす場合には、1~2年程度で終わる工事より相対的に厳しい環境保全方針の設定を行う場合等が考えられる。こういった地域特性や事業特性を考慮して設定した環境保全方針に従って環境保全措置を検討することとなる。
[2]事業計画の段階に応じた環境保全措置の検討
環境保全措置の立案においては、事業計画の熟度に合わせた検討が必要である。これは、ほぼ確定されてしまった計画においては適切な環境保全措置の立案が困難となる場合が生じるためであり、事業計画の早期段階から環境保全措置の方針を整理し、内容・手法については事業計画の熟度に合わせて具体化していくことにより、適切な環境保全措置の実施が可能となる。
[3]環境保全措置の複数案検討と検討経緯の整理
環境保全措置の立案までの検討段階においては、騒音低減効果や実現可能性を考慮して複数案が検討されることとなる。実際の作業の中では事業の実施による環境への負荷をより効率的に削減し、実現性の高い環境保全措置から優先的に選択し予測・評価を繰り返すことになる。
実行可能な範囲でより良い技術を取り入れるためには、優先的に選択した手段が環境保全方針に沿った結果であっても、効果及び実現性において最適であるという判断はできないため、内容の異なる複数の環境保全措置を並行的に比較検討することとなる。環境影響評価法においては、この複数案の比較検討のプロセスを評価の中で明らかにすることとしているため、検討経緯、検討結果については準備書・評価書において可能な限り具体的に記載する必要がある。
騒音分野では、騒音や振動の基準を達成するべく防音壁の設置等の環境保全措置を実施する場合がある。このような場合には、今後の評価や事後調査の検討が効果的に実施できるように、検討の経緯、前提条件等の考え方を明らかにすることが重要となる。
[4]他の環境要素への影響の確認
環境保全措置の検討にあたっては、他の環境要素への影響についても考慮する必要がある。例えば、騒音の影響を回避・低減するために設置した防音壁が、日照阻害や景観に影響を及ぼすような場合等が考えられる。そのような場合には、他の環境要素へ及ぼす影響も十分に考慮し、透光型防音壁を設置する等の環境保全措置を検討することが重要である。
(3)環境保全措置の内容
[1]事業者により実行可能な範囲で行われる環境保全措置
環境保全措置とは、事業者の実行可能な範囲内で行われるものであり、たとえ想定している環境保全措置が事業計画の変更に係わるものであっても、技術面、コスト面、現実性及び具体性といった観点において十分に見合うものであれば、その環境保全措置を実行することが考えられる。
なお、事業計画に係る大幅な変更を実施する際には時系列に沿って検討経緯を明確にし、住民が理解しやすい様に整理することが重要である。
[2]環境保全措置の事例
騒音分野における保全対策は、1)発生源対策、2)伝搬経路における対策、3)受音点、受振点における対策の大きく3つに分類できる。環境影響評価においては、事業者の実行可能な範囲で事業の実施による環境影響を回避・低減するために、事業実施区域内で行う発生源対策と伝搬経路における対策で環境影響を回避・低減することが基本となる。
また、環境保全措置を実施者の立場で分類すると、事業者が実施する対策と事業者以外の者が主に実施する対策に分類される。環境影響評価においては、環境保全措置は事業者により実行可能な範囲内において検討されるべきものである。しかし、実際には、行政や当該施設の管理者が実行する環境保全措置等があり、環境影響の一層の回避・低減のためには、必要に応じてこれらを活用することも効果的な場合がある。例1に行政の実行する施策(環境保全措置)による効果を見込む例を示す。
【例 環境保全措置】
|
事業者以外の者が実施する環境保全措置の事例~ 行政の実施する自動車の単体規制の効果を見込む事例 |
|
将来交通による道路交通騒音を予測する場合に用いられるASJ Model 1998では、以下のように将来交通のパワーレベルに施策の効果が盛り込まれている。 「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」(平成4年中央公害対策審議会中間答申)及び「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)」(平成7年中央環境審議会答申)には、将来の目標となる自動車騒音低減に関する許容限度設定目標値が明らかにされており、ASJ Model 1998のパワーレベル式はその目標値が達成されるものとして設定されている。 平成4年及び平成7年の答申の後、自動車騒音低減に係る技術開発が進み、平成12年2月に改正された「自動車騒音の大きさの許容限度」により、答申で示された全ての車種に対して騒音規制が強化されることとなった。 ○ 通常のパワーレベル式(定常走行時) 大型車:LWA= 53.2 + 30log10V 小型車:LWA= 46.7 + 30log10V ○ 施策の効果を反映させたパワーレベル式(定常走行時) 大型車:LWA= 52.3 + 30log10V 小型車:LWA= 45.3 + 30log10V 答申 ・平成4年中央公害対策審議会中間答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について」 ・平成7年中央環境審議会答申「今後の自動車騒音低減対策のあり方について(自動車単体対策関係)」 答申に対応する施策とその効果 ・騒音規制法に基づく「自動車騒音の大きさの許容限度」の改正が行われ、新たに販売される自動車から発生する騒音が従来よりも低減されることとなる。
|
表3は騒音分野における環境保全措置の例を環境影響要因に対応させて示したものである。環境保全措置については、事業者の実行可能な範囲内で最大限実施するものであるが、必要に応じて事業者以外の者への環境保全措置の要請等を検討することも望まれる。
また、環境保全措置には、道路整備事業における「交通規制等による対応」や飛行場整備事業における「低騒音型機材の導入」のように、環境保全措置の実施主体が事業者以外になる場合もあるため、環境保全措置の検討を行う際には、その保全措置の実施主体についてあらかじめ明確にしておく必要がある。
表3 騒音分野における環境保全措置の例
| 環境影響要因 | 発生源に対する環境保全措置 |
伝搬経路における 環境保全措置 |
|
| 供用時 | 自動車の走行 |
低騒音舗装の設置 舗装の維持・管理 ジョイント部の改良 自動車の単体規制 道路網の整備による対策 交通規制等による対応 |
防音壁の設置 環境施設帯の設置 緩衝建築物の設置 |
| 列車の走行 |
ロングレール・重量レールの敷設 レール継目の管理と改良 車両と軌道の整備 適切な運行管理 構造物の重量化 車両の軽量化 バラストマット |
防音壁の設置 吸音材の設置 |
|
| 航空機の運航 |
低騒音型機材の導入 飛行経路の遵守 騒音を低減する運行方法 |
防音堤の設置 | |
| 工場の稼働 |
低騒音・振動型設備の採用 適切な配置計画 稼働時間の限定 |
防音壁の設置 防振溝の設置 |
|
| 工事中 |
建設機械の 稼働 |
低騒音型建設機械の採用 工事工程の平準化 工事期間、時間帯の限定 |
仮囲いの設置 |
|
工事用車両の 走行 |
交通法規の遵守 適切な走行ルートの選定 走行時間帯の限定 |
- |
|
|
【留意事項】事業者以外が行う環境保全措置 事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合においては、事業計画と事業者以外の者が実施する対策等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの対策の予算措置等の具体化の目途が立っていること等を客観的資料に基づき明らかにする必要がある。 |
|
【留意事項】防音工事の考え方 道路交通騒音や航空機騒音に係る騒音対策の一つとして、受音側での防音工事を実施する場合がある。防音工事自体は法的にも位置づけられており、否定されるものではないが、環境影響評価における環境保全措置の検討に際しては、事業による環境への影響を実行可能な範囲で回避・低減することが優先されるものである。そのため、環境影響評価においては、事業実施区域内で行う発生源対策と伝搬経路における対策により環境影響を回避・低減することが基本となる。 |
(4)環境保全措置の妥当性の検証
|
環境保全措置の検討に当たっては、環境保全措置についての複数案の比較検討、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を通じて、講じようとする環境保全措置の妥当性を検証し、これらの検討の経過を明らかにできるよう整理すること。 |
(基本的事項 第三項二(5))
環境保全措置の妥当性の検証は、複数案の比較検討及び実行可能なよりよい技術が取り入れられているか否かの検討により行うことが基本となる。
複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を対象とし、それぞれのもつ効果、不確実性及び他の環境要素への影響等を総合的に比較検討することである。
より良い技術が取り入れられているか否かの判断をするためには、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。この際、採用することとした環境保全措置の効果が不確実である、または不明であると判断された場合には、慎重な対応が必要となり、その不確実性の程度についても明らかにするとともに、事後調査により環境保全措置の効果や影響を確認することが必要となることも考えられる。
環境保全措置の採用の判断は、上記の妥当性の検証結果をふまえて行われる必要があり、その検証結果及びその結果に至るまでの経緯については、準備書・評価書においてできる限り具体的に明らかにする必要がある。
3)評価
|
ア 環境影響の回避・低減に係る評価 建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。 イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討 評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。 ウ その他の留意事項 評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。 |
(基本的事項 第二項五(3))
環境基準等の基準又は目標が設定されている項目については、上記ア及びイの評価を併用することとなる。従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われてきた。環境影響評価法に基づく環境影響評価では、アの視点による評価が前提となる。事業の実施による環境影響をゼロにすることはできないが、環境影響をいかに低減した計画となっているか、またそのためにどこまで検討を重ね、配慮してきたかが理解できる内容の環境影響評価が望まれる。特に、在来鉄道振動や低周波音といった基準の無い項目や、特に影響を受けやすい施設への影響等については、環境影響評価において事業者による積極的な配慮が求められるものである。
また、環境基準は環境保全上維持されることが望ましい基準として定められる行政上の目標となるべきものであり、幅広い行政の施策によって達成を目指すものである。それに対し、規制基準は、環境基準達成に向けて講じられる諸施策と考えられる。このような背景を理解した上で、事業による環境影響を適切に評価する必要がある。
(1)回避・低減に係る評価
[1]回避・低減に係る評価の基本的な考え方
回避・低減に係る評価は、環境影響の回避・低減のための事業者の努力を明らかにするとともに、取り入れた環境保全対策について、客観的にその効果、技術の妥当性が明確にされているかどうかを検討することによって、その環境保全対策により事業による環境影響が回避・低減されているかどうかを判断する。
ここでいう、環境保全対策とは事業計画の立案から調査、予測及び評価までの過程の中で検討された幅広い環境保全対策が該当する。これらの効果の客観性、妥当性を示す手法として、環境保全対策の検討を時系列に沿って対比する、最良の技術か否かを判断できる資料を明示する等が考えられる。
[2]基準又は目標がある場合の回避・低減に係る評価
基準又は目標があり、環境保全措置の実施によりその基準又は目標が達成される場合には、ある一定の水準で環境が保全されることとなる。その水準が環境の保全の視点から十分に妥当であると考えられる場合には、その妥当性を明らかにして、当該環境保全措置の実施について評価することとなる。
一方、基準又は目標があり、実行可能な範囲で最大限の環境保全措置を実施した場合においても、その基準又は目標が達成されない場合には、まず実行可能な最大限の環境保全措置を実施した旨と現時点で達成できない理由を明らかにすることともに、将来における達成への努力、すなわち、事後調査等の実施や新技術の積極的導入といったものが評価の重要な視点となる。
[3]基準又は目標がない場合の回避・低減に係る評価
基準又は目標がない場合には、回避・低減に係る評価のみを実施することとなる。評価にあたっては、事業者がどのような観点に基づいて環境保全措置を検討したのか明らかにすることが重要である。また、定量的に予測した場合には、予測結果を他事例や閾値と比較する等により、客観的で分かりやすい表現を用いた評価が望まれる。
(2)基準又は目標との整合に係る評価
[1]基準又は目標との整合に係る評価の基本的な考え方
騒音・振動分野については、環境基準等の基準又は目標が設定されている環境要素を予測・評価する場合が多いため、従来の環境影響評価においては、基準との整合についての視点による評価が実施されてきた。そのため、既に現状の騒音の状況が環境基準を達成していない地域で事業を実施する場合であっても、環境基準との整合を図ることが環境影響評価において最も重要な事項として取り扱われてきたことは否めない。
現状において基準又は目標が達成されていない状況においては、事業者が実行可能な範囲での環境保全対策による基準又は目標の達成は困難であることが容易に想定される。この基準又は目標との整合に係る評価においては、従来の考え方を払拭し、基準との整合が図られない場合は、それを明らかにすることが最も重要であることを認識する必要がある。そして、その結果を踏まえて、前述の回避・低減に係る評価を実施していくことが必要である。
また、地域の環境基本計画等により、地域特性に配慮した目標が示されている場合は、この目標の設定の背景等を踏まえ、その整合性に十分に配慮した評価を実施することが必要である。
[2]評価と事後調査の関係
基準値又は目標値との整合を検討した結果は、一般的に「達成している」、「達成していない」と表現されることが多いが、更に踏み込むと、「現況で達成していないため、達成できない」、「最大限の環境保全措置を行ったが、達成していない」、「基準を達成するまで環境保全措置を実施したため、達成している」、「達成すると予測されるが、予測の不確実性を考慮すると、達成しない場合も考えられる」等、様々な背景が存在する。「基準を達成するまで環境保全措置を実施することとしたため、達成している」場合や、「達成すると予測されるが、予測の不確実性を考慮すると、達成しない場合も考えられる」場合等には事後調査の実施を検討する必要があると考えられる。
|
【留意事項】一時的な影響に対する考え方 騒音等は、他の環境要素とは異なり、影響が環境中に残留しないことから、影響等が一時的になることがある。その場合、影響の頻度や継続時間、発生時間帯等を考慮した評価の視点も重要であり、発破作業において使用する薬量と回数の関係や、建設作業において使用する建設機械の大型化と工期の短縮の関係など、柔軟な検討が望まれる。 |
|
選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果にかかる知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとともに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできるようにすること。 なお、事後調査を行なう場合においては、次に掲げる事項に留意すること。 ア 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行う項目の特性、地域特性等に応じて適切な内容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。 イ 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な限り環境への影響の少ない事後調査の手法が選定され、採用されるものとすること。 ウ 事後調査において、地方公共団体等が行なう環境モニタリング等を活用する場合、当該対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかな場合等においては他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容について明らかにできるようにすること。 |
(基本的事項 第三項二(6))
(1)事後調査の考え方
[1]事後調査の基本的な考え方
環境影響評価の結果は当該事業の許認可等に反映されるため、環境保全措置等の実行性は担保されることとなる。しかし、不確実性の大きい予測結果に基づいた環境保全措置、あるいは効果にかかる知見が不十分な環境保全措置では必ずしも環境影響を予測したとおりに回避・低減できるとは限らない。事後調査は、事業の実施前に行う環境影響評価において、予測及び評価の不確実性等を補う等の観点で位置づけられており、事後調査を実施することにより、1)環境影響評価により検討した環境保全措置が十分に機能し効果を示しているか、2)予測した対象事業による影響が予測範囲内であるかを把握すると共に、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、3)環境保全措置の追加・再検討等をすることを目的とする。
騒音・振動分野においては、対象事業から発生する騒音・振動に基準値が定められ、供用時に基準値の達成の確認を調査する場合があるが、環境影響評価における事後調査は、調査だけでなく、必要に応じて環境保全措置の追加検討等を行う場合もあることに留意する必要がある。
[2]事後調査の必要性の検討
事後調査の必要性の検討は、環境影響評価の結果における予測の不確実性の程度、環境保全措置の効果に係る知見の不十分さを把握することに始まる。環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に不確実性があることに留意する必要がある。また、事業による影響の程度に応じて事業特性及び地域特性を勘案した環境保全措置を実施することとなるが、その効果についての知見が十分であるものばかりではない。従って、予測の不確実性の程度、環境保全措置の知見の程度から起因する予測結果への影響の程度の大きさから「予測の不確実性が大きい場合」及び「知見が不十分な環境保全措置を講ずる場合」と判断される場合等においては、環境への影響の重大性に応じ、事後調査によって事業実施後の環境の状況を把握する必要性について検討することとなる。
事後調査を実施する場合においては、より効果的な調査内容とするために、予測結果に大きな影響を及ぼす項目を整理し、また、事後調査の結果と環境影響評価の結果との比較検討が可能なものを調査すべき情報として選定することに留意する必要がある。
(ア)不確実性と影響の重大性
事後調査は、事業の実施前に行う環境影響評価において、調査、予測及び評価の不確実性を補う等の観点から位置付けられており、予測の不確実性と環境影響の重大性を把握し、検討することは事後調査の検討にあたって最も重要な事項となる。
不確実性には予測条件に起因する不確実性や予測方法に起因する不確実性、効果にかかる知見が不十分な環境保全措置に起因する不確実性等がある。これらの不確実性は既存の知見や類似事例等を有効に活用し、極力排除されることが望ましいが、道路事業における将来交通量や走行速度、飛行場整備事業における航空機の機種・飛行経路といった事業者によって完全に管理できないものが存在することにも留意する必要がある。
影響の重大性は、騒音レベルや振動レベルといった定量的な数値のみならず、地域特性や事業特性を勘案して総合的に検討されるべきものであり、基準値と単純に比較して判断されるものでないことに留意する必要がある。
[3]地方公共団体等が行う環境モニタリング等の活用
環境基準が定められている道路交通騒音や航空機騒音等では、地方公共団体がモニタリングを行い、モニタリング結果に基づいて必要な施策・対策を検討するといったシステムが構築されている。環境影響評価は事業者の責任の下で行われるものであるが、地方公共団体等が行う環境モニタリング等を活用できる場合にその活用が否定されるものではなく、必要に応じて効果的かつ効率的な対応を行うことが望ましい。
(2)事後調査の方法
事後調査では環境影響評価で予測・評価した環境の状況の変化の程度を把握することが求められることから、事後調査の対象、地点、時期及び手法については、原則として予測を行った対象、地点、時期及び手法と同様とすることが基本となる。ただし、将来的に土地利用の変化及び調査手法の改良等がある場合には、調査地点や調査手法の変更等、適宜柔軟な対応が望まれる。
事後調査を実施するにあたっては、対象事業による騒音・振動・低周波音の状況を把握することはもちろんであるが、予測結果との差が生じた場合の原因となる事項、例えば周辺道路の整備状況、交通量、環境保全措置の効果等も併せて確認する必要がある。
また、現在実施段階の事業の中には環境監視を目的とし、事業者により自主的にモニタリングが実施され、地域住民に対して公表されているケースも多く、対象事業の実施による環境への影響の程度の把握及び環境保全措置の効果の程度を把握するための調査手法として、これらモニタリングについても積極的に活用していく必要がある。
同様に、公共機関や自治体などの事業者以外が実施している環境調査結果(騒音観測結果、苦情調査、交通センサス等)の利用が可能なものについては、有効に活用することが望ましい。例えば、事業実施直後の事後調査については、事業者により詳細な調査を実施し、著しい影響が生じないことを確認した後においては、モニタリングを活用し、長期的で効率的な事後調査を行うことが考えられる。
(3)環境保全措置の追加検討
事後調査の結果、予測結果を上回る著しい環境影響が確認された場合には、必要に応じて環境保全措置の追加・再検討を実施することとなる。予測及び評価の不確実性等を補う事後調査の観点から、事後調査結果に応じて追加的な環境保全措置の検討をすることは、事後調査の中で最も重要な事項である。また、追加的な環境保全措置を検討する可能性がある場合には、その実施が可能となるような計画としておくことが当然必要である。
また、騒音・振動分野では供用時に環境保全措置を追加実施することが他の分野に比べると比較的容易であるが、飛行場の設置や鉄道(地下鉄)の新設といった事業では、供用時に環境保全措置の追加実施が困難であり、事業実施前までの対策検討が非常に重要であることは言うまでもない。
また、環境保全措置の追加検討においては、防音壁の嵩上げといった物理的な措置のみならず、関係機関との連携による円滑な交通流の確保やモニタリングの充実といった多岐にわたる措置の中から効果的・効率的なものを検討し、採用することが重要である。
(4)公 表
事後調査を実施するにあたっては、1)事後調査を行うこととした理由、2)事後調査の項目及び手法、3)環境影響が著しいことが明らかとなった場合の対応の方針及び4) 公表の時期について整理し、可能な限り準備書・評価書において明らかにする必要がある。
実際の事後調査の結果については、調査実施後できる限り早い段階で、適切な時期及び場所において公表する必要がある。このとき前述する追加的な環境保全措置の検討を実施した場合には併せて公表することが望ましい。
(5)事後調査結果の活用
環境影響評価における事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測技術の向上及び環境保全措置の効果を客観的かつ定量的に示す指標として利用が可能であり、将来の環境影響評価技術の向上に大きく貢献することができる。特に、予測結果と事後調査結果に大きな相違が生じた場合は、その原因を究明することにより今後の環境保全措置に係る知見の向上に役立つものと考えられる。そのような観点から、事後調査の結果は広く公開され、また、積極的に整理、解析及び活用されることが重要である。そのためには、一事業者の努力のみでは負担が大きく、情報の収集には限界があるため、国や自治体等が積極的に取り組んでいくことが望ましい。