平成13年度第1回 騒音分科会
騒音分科会騒音分野における調査・予測・評価の進め方
(2)影響予測
予測とは事業の実施による環境影響を適切に評価できるように、対象地域における騒音、振動、低周波音の状態に生ずる変化を明らかにすることである。
冒頭で述べたとおり、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めた場合には、予測を行う段階においては予測の手法は具体化していることとなるが、改めて調査の結果を勘案するとともに、予測及び評価に関する最新の知見の把握に努める必要があり、その結果、必要に応じて予測及び評価手法の見直しを行う場合も考えられる。また、単独の発生源からの影響だけでなく、地域特性や事業特性によっては、複数の発生源からの騒音の影響について予測及び評価を行う必要が生じることも考えられる。
予測手法の選定にあたって、基本的にはその時点で最新の知見を基に、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測の結果には常に不確実性があることに留意する必要がある。予測の不確実性については、評価に際して考慮するだけでなく、不確実性の状況に応じ、事後調査の実施について検討する必要がある。
予測にあたっては、対象とする発生源、評価量(LAeq、LA5等)、評価の観点、予測の不確実性等を明らかにする必要がある。
なお、将来的な予測の不確実性の低減に資するためには、予測方法や予測条件の研究、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。
[1]予測項目の考え方
項目の選定については、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と地域特性から抽出された環境の変化による影響をうける環境要素との関係を厳密に検討する必要がある。その場合、評価量(表1-2-2~3)による予測が基本となるが、法令等に基づく評価量以外の予測*7についても、必要に応じて検討することが望ましい。また、同時に複数の発生源が存在する場合には、複合騒音の予測を検討することが望ましい。この場合、個別の発生源からの騒音を合成して複合騒音を予測するためには、技術的に合成が可能な評価量である等価騒音レベル(LAeq)による予測を行うものとする。 また、地方公共団体において環境基本計画等の環境保全施策が示されている場合には、当該施策との整合性を評価するために必要となる予測項目を選定する必要がある。
|
【留意事項/事例】
|
[2]予測手法の考え方
予測手法は、伝搬理論計算式、経験的回帰式、模型実験、類似事例の参照、その他適切な手法から対象事業の種類等を勘案して選定することとなる。騒音・振動については、学会等により各種発生源(自動車、鉄道、航空機、工場・事業所等)に対応した汎用性の高い予測式が提案されているが、これらの予測手法を用いる場合においても、予測式を単に適用するのではなく、予測式の適用条件、予測の不確実性等を十分に考慮する必要があり、その結果として、複数の予測手法を併用する場合も考えられる。また、予測項目の等価騒音レベル(物理量)、時間率騒音レベル(統計量)や騒音レベルの最大値(統計量)等の技術的な性格を認識し、必要に応じて予測の不確実性を明らかにするなどの対応が必要である。
予測等に用いる技術手法については、既往の技術マニュアルや評価書等を参考にするばかりでなく、以下に示すような環境影響評価技術に関する図書資料や、学会の論文等、あるいは海外の予測手法(米国EPAの手法等)を参照することが必要である。なお、海外の手法を用いる場合には、我が国とは異なる気象・地形条件等に合わせて作成されたモデルであることに十分留意する必要がある。
・環境アセスメントの技術 (社)環境情報科学センター
・環境影響評価技術シート
・地方自治体の環境影響評価技術指針(ア) 予測の不確実性
予測の不確実性の原因には、予測条件の不確実性、計算に用いるパラメータ等の不確実性、予測式の不確実性等のさまざまなものがあるが、これらの不確実要因が予測結果に与える影響を常に考慮し、予測結果の記述にあたってはその不確実性についても言及するとともに、単一の前提条件、予測手法による単一の結果に固執することなく、必要な場合には複数の予測条件や予測手法*8による結果を併記するなどの柔軟性が求められる。特に、交通量に代表される交通条件*9のように、それ自体が想定を含む予測条件については、その妥当性や不確実性を十分明らかにして示す必要がある。
なお、以前の環境基準の評価量であったLA50等の時間率騒音レベルは統計値であるため、技術的には合成や予測はできない。しかしながら、時間率騒音レベルでの予測の必要性や実用上は問題が少ないことから使用されていたものであり、これも予測の不確実性の一つとして考えることができる。
|
【留意事項/事例】
|
(イ) 手法の重点化・簡略化*10
環境影響評価の対象とすべき要素について、地域特性の把握の結果、環境上劣悪な地域が存在する場合や、あるいは、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合等については、手法の重点化を、一方、類似事業の事例などから判断して環境影響が極めて小さい場合等については手法の簡略化を検討する。手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、予測地点、予測期間・時期等の増減等も含めて検討する。 なお、国又は地方公共団体の環境保全施策として定量的な基準が示されている場合には、基準と比較して評価できるよう、手法の簡略化を行う際には留意する必要がある。
|
【留意事項/事例】
|
[3]予測条件の考え方
予測の元となる原単位等の予測条件は、既往の環境影響評価に用いられた資料を参考とすることのみならず、新たなデータの有無を確認し、必要に応じてこれらを取り入れることが必要であり、必要により複数の予測条件に基づく予測結果を併記する場合も考えられる。特に建設機械のパワーレベル等の原単位については、新しい建設機械の開発等により、常に変化するものであることを念頭に置く必要がある。
また、事例の引用又は解析による予測を行う場合には、伝搬特性や周波数特性など、これらの予測条件に該当する条件の類似性を、不確実性を考慮しつつ、極力明らかにする必要がある。*11
|
【留意事項/事例】
|
(ア) 原単位の検討
騒音、振動の予測の基本となる原単位(パワーレベル、基準点振動レベル等)については、「実測により設定された原単位」と「施策の目標から設定した原単位」に大きく分けられる。また、パワーレベル、基準点振動レベルなどの原単位は、どのような条件下で設定されたものか、予測及び評価指標との整合性は確認しておかなくてはならない。*12
「実測により設定された原単位」を用いる場合には、測定条件や類似性を明らかにする必要がある。しかし、予測と全く同一の条件での測定は、現実として不可能であることから、その場合は、不確実性を明らかにする必要がある。
「施策の目標から設定した原単位」については、施策の実現可能性の検討が必要であり、実現性が確実でない場合*13には不確実性があるものとして明らかにする必要がある。
また、道路を走行する自動車については、2車種(大型車・小型車)に分類して予測する場合が多いが、工事用車両の大型ダンプトラックやトレーラー等を利用する場合には、通常の大型車の原単位ではなく、より現実に即した原単位の設定に留意する必要がある。
|
【留意事項/事例】
|
(イ) 伝搬特性
騒音の伝搬特性を決定する要因は、距離以外にも、気象条件、建物による遮音、地表面の性状等の様々なものがあり、近年では、空気による音響吸収、障害物による回折効果、地表面における反射等の影響を計算する方法が確立されている。これらの伝搬特性を必ずしも全て予測に網羅する必要はないが、伝搬過程全体の精度を考慮して、必要と考えられる要因は取り込んでいく必要がある。
振動については、騒音のように様々な伝搬特性を計算する方法が確立されていないため、特定の発生源に対し、複数の予測式が提案されていることが多い。その場合は、計算式を類似事例に当てはめて比較照合する等により、予測式の適用性を明らかにする必要がある。特に、地中が振動源となる道路のトンネル部や地下鉄については、供用時における環境保全対策の実施が困難である場合が想定されるため、伝搬特性の不確実性については吟味する必要がある。
(ウ) 周波数特性
騒音、振動、低周波音はいずれも様々な周波数の空気振動及び地盤振動であり、吸音や回折等を検討する場合には周波数特性を検討する必要がある。特に、吸音材を用いた環境の保全のための措置を実施する場合や、空気振動及び地盤振動が数百m~数㎞も伝搬する場合には、周波数特性を考慮する必要がある。
(エ) その他
(a) 将来交通量
将来交通量の予測方法としては、OD表に基づいた配分モデルにより推計する方法や現況交通量の経年変化から推定する方法等があり、表1-2-4に示す事業特性や地域特性を勘案し、適切な方法を設定する必要がある。 推計にあたっては、将来における交通ネットワークの構築については慎重に検討する必要があり、道路や鉄道の新設・改良の計画のみならず、実施中の事業についても、進捗に留意し、より妥当性のある交通ネットワークの設定に努める必要がある。また、将来のある時点で交通ネットワークが大きく変化する場合の将来交通量の設定に際しては、十分に検討する必要があり、考え方の一例を図1-2-3に示す。
表1-2-4 将来交通量に関連する事業特性及び地域特性
| 事業特性 | 工事計画 道路設置計画 設計交通量(道路事業の場合) |
| 地域特性 | 新規の幹線道路や鉄道の開通予定 道路の新設や改良の状況 周辺地域における大規模開発 地域における交通量の経年変化・経時変化 |
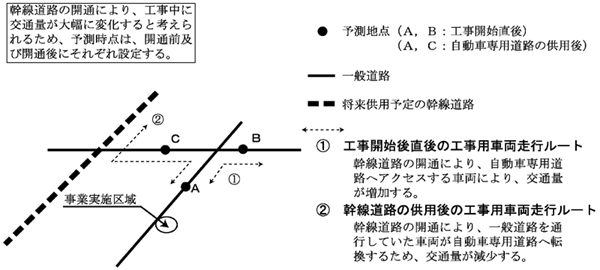
図1-2-3 道路が新設されることにより将来交通量が変化する場合の考え方(例)
(b) 走行速度
自動車の走行速度については、道路管理者により規制速度が設定される場合がある。しかし、その規制速度はアセス実施時点では明らかにはならないことから、予測条件となる走行速度は法定速度として道路交通騒音・振動を予測する場合が多い。しかし、市街地においては、実際の規制速度が法定速度よりも小さく設定されることが多く、その差は予測条件の不確実性として明らかにすることが望ましい。
実際の環境影響評価手続きにおいて、「現在の道路では規制速度以上で車両が走行しており、騒音上問題である」といった意見が住民から指摘される場合もあり、速度の設定については、事業者の立場を明らかにしながら、現実的な予測条件を設定することが肝要である。
(c) 家屋による減衰及び増幅*14
騒音の環境基準は、会話影響及び睡眠影響の防止の観点から基準値を定めており、窓を開けた状態を考慮して屋外での基準値を定めている。しかし、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる場合には、屋内へ透過する騒音に係る基準により評価することも可能であり、その場合には家屋による減衰効果を設定する必要がある。家屋による減衰量は個々の家屋により差異があるため、現地踏査や既存資料調査を十分に行い設定する必要がある。
振動については、家屋により減衰及び増幅するが場合あり、特に屋外を予測地点とし、感覚閾値で評価する場合には、家屋による振動の増幅効果により、家屋内で感覚閾値を上回る可能性があることを考慮して検討する必要がある。
【留意事項/事例】
- *14 家屋による振動の増幅を考慮した事例(p.1-2-33参照)
・家屋による振動の増幅を考慮して振動の保全目標値を設定した事例
[4]予測地域の考え方
予測地域は、原則として事業の実施により騒音、振動、低周波音がの一定のレベル以上変化する範囲を含む地域とする必要があり、一般的には調査地域に包含される。この範囲は事業の規模や内容によって変化するものであり、予測の不確実性や地域特性に配慮する必要があり、安全サイドの考え方から広めにとることになる。また、調査を実施した結果から予測する必要がないと判断された地域がある場合には、調査地域から予測地域を絞りこむことができる。
工場や鉄道等の発生源の場合は、発生源の条件等の把握が容易であることから、一般的な予測式によって試算して範囲を設定することも可能である。また、自動車等の移動発生源の場合は、影響は比較的周辺に限られることから、道路沿道の数十mから数百mの範囲が予測地域の目安とされる。また、騒音に係る環境基準において、「一般地域」、「道路に面する地域」、「幹線交通を担う道路に近接する空間」が定められているので、予測地域の設定にあたっては、その考え方を参考とすることが可能である。
予測地点については、調査地点と同様に環境の状況の変化を重点的に把握する場合に設定するものであり、定点での評価を必要としない場合には必ずしも予測地点の設定を必要としないが、調査地点における「(イ)特に影響を受けるおそれのある地点」、「(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点」、「(カ)法令等により定められた地点」のある場合には、これらの地点を予測地点とすることが考えられる。また、予測地点の設定・選定に際しては、事後調査や環境監視計画等にも配慮することが望ましい。
また、騒音の予測地点における鉛直方向の高さは通常1.2mで設定されるケースが多いが、周辺に高層建築物が存在しているような場合には、生活実態に対応して高さ方向を考慮に入れた地点の設定*15を検討する必要がある。
【留意事項/事例】
- *15 高さ方向を考慮に入れた地点の設定(p.1-2-33参照)
騒音に係る環境基準において、個別の建物等を単位として評価する場合、「個別の住居等が影響を受ける騒音レベルによることを基本とし、住居等の用に供される建物の影響を受けやすい面によって評価する」ものとされており、中高層建築物等が存在する場合には、高さ方向を考慮に入れた地点の設定を検討する必要がある。[5]予測時期の考え方
予測時期は事業の実施に伴う発生源の活動を時系列的に検討して決定するが、大きくは、事業の工事中と供用時に二分される。
(ア) 工事中
工事中については、工事計画全体にわたって時系列的に工事量の変化、工事区域の変化等を把握するとともに、建設機械の稼働に係る予測については、予測地点に最も近い位置で建設機械が稼働する時期、もしくは、発生する騒音・振動レベルが最も大きい工種を行う時期を予測時期とし、工事用車両の走行に係る予測については、工事用車両の走行台数が最も多くなる時期を予測時期とする。
また、工事期間が非常に長い場合や、図1-2-3に示したように工事中に工事用車両走行ルートの変更が考えられる場合には、工事の中間的な時期における予測の実施についても検討する。(イ) 供用後
供用時については、事業の供用後において施設の稼働や車両の走行等が定常状態となる時期とする。
また、事業が長期にわたって段階的に実施される場合や中間段階において環境の状況が大きく変化する場合には、それらの経年変化を把握し、適切な時期に予測を行う。(ウ) その他
廃棄物の最終処分場の建設等は工事期間と供用期間が重複することが想定される。このような場合においては、工事の実施及び施設の供用の両面から環境への影響を勘案し、少なくとも影響が最も大きいと考えられる時点を検討し、予測時点として設定する。