平成13年度第1回 騒音分科会
騒音分科会騒音分野における調査・予測・評価の進め方
2)騒音・振動・低周波音の環境影響評価の方法
(1)騒音・振動・低周波音の調査
調査の目的は、地域特性の把握における調査(既存資料の収集整理又は現地踏査等)では明らかにされなかった情報を収集して、対象地域の現況をより詳細に把握するとともに、予測・評価において必要な情報を取得することにある。地域特性の把握において収集整理した騒音、振動、低周波音の状況や地盤の状況等には、地域的な偏りや調査地点の観測点密度の問題があり、事業実施区域及びその周辺における状況を詳細に把握する必要がある。
また、予測・評価において必要な情報を取得するための調査としては、地盤卓越振動数等の予測条件の設定や、現況と比較して評価を行う場合に必要となる現況の騒音・振動レベルの把握等が考えられる。
特定発生源からの騒音・振動が予測・評価項目の場合、把握した現況の騒音・振動レベルが予測・評価において何ら活用されていない場合があるが、調査に際しては、調査の目的を常に認識し、例えば、建設作業騒音の評価において現況と比較するのであれば、環境騒音としてLAeqだけでなく、最大値やLA5についても調査する等、効果的な調査を実施することが重要である。
なお、既存資料調査の結果を予測・評価に利用できる場合もあるが、その場合は、既存資料調査の調査方法や調査の目的等を精査し、利用の妥当性を十分に検討する必要がある。また、調査計画の立案段階及び調査の実施中においても、効果的かつ効率的な手法を検討する必要があることは前述したとおりである。
[1]調査項目の検討
調査項目は、騒音、振動、低周波音の状況、地表面の状況、地盤の状況等が挙げられるが、事業の特性及び規模並びに地域の特性を勘案し、事業の実施による騒音、振動、低周波音の影響を適切に把握し得るよう十分に配慮し、予測・評価を行うために必要なものを選定する。
項目の選定においては、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と地域特性から抽出された環境の変化による影響を受ける環境要素との関係を厳密に検討する必要がある。影響要因と環境要素を把握する上で考慮すべき事項は以下のとおりである。なお、地域特性の検討に際しては、法令に定められた基準値等の達成の可否のみでなく、法令や基準値の考え方*1についても配慮して検討する必要があることは言うまでもない。
|
事業特性
|
発生する騒音、振動、低周波音の発生特性(時間、頻度等) 伝搬の過程 発生源の種類・位置 等 |
|
地域特性
|
騒音の環境基準達成状況 環境基本計画等の騒音・振動・低周波音に係る目標値の達成状況 騒音規制法、振動規制法に規定する指定地域 等 |
また、同時に、予測・評価の方法についても詳細に検討し、予測・評価において必要な情報を取得するため、表1-2-1に示すような調査の実施についても検討する必要がある。
表1-2-1 予測・評価において必要な情報を取得するため調査例
|
調査項目(例)
|
必要となる理由(例) |
|
類似事例における騒音レベル
|
パワーレベルの設定のため |
|
交 通 量
|
将来交通量の推計のため |
|
地盤卓越振動数
|
道路交通振動の予測条件 |
|
現況の騒音レベル
|
現況からの変化の程度で評価するため |
地域によっては、既に騒音の発生源があり、調査の結果、既に環境の状況が悪化していることが判明した場合には、複合騒音の影響*2を検討するための必要な調査の実施の検討が生じることも考えられる。
|
【留意事項/事例】
|
[2]調査手法の考え方
調査手法に関しては、前述したように「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要があり、評価の対象及び方法を明確にした上で、様々な予測手法の適用条件を考慮し、その予測のために必要な調査手法を検討することが必要である。特に、騒音、振動に係る評価量は表1-2-2~3に示すとおり発生源の種別により異なるため留意しなくてはならない。また、基準が定められていない複合騒音や在来鉄道振動等については、発生特性等を考慮して、適切に設定することが必要である。 なお、調査は現地調査及び既存資料調査に限られるものではなく、騒音に係る環境基準の改定により、実測のみならず推計により把握する方法*3についても合理的に活用することが望ましい。
|
【留意事項/事例】
|
表1-2-2 騒音に係る基準値等の評価量
|
基準等 種別 |
環境基準 | 規制基準(要請限度) | 指針指針条例等 | 備考 | |
| 環境騒音(道路交通騒音) |
L Aeq
|
|
|
|
|
|
L Aeq
|
|
|
|||
| 鉄道騒音 | 新幹線 |
L AP
|
|
|
|
| 在来線 |
|
|
L Aeq
|
指針
|
|
| 航空機騒音 | 大規模飛行場 |
WECPNL
|
|
|
|
| 小規模飛行場 |
|
|
L den
|
暫定指針
|
|
| 工場・事業場騒音 |
|
LA5他
|
|
|
|
| 建設作業騒音 |
|
LA5他
|
|
|
|
| 深夜営業騒音、拡声器等 |
|
|
LA5他
|
条例
|
|
表1-2-3 振動に係る基準値等の評価量
基準等
種別
規制基準(要請限度) 指針指針条例等 備考 道路交通振動 鉄道振動 新幹線 在来線 工場・事業場振動 建設作業振動
(ア) 手法の重点化・簡略化*4
環境影響評価の対象とすべき要素について、地域特性の把握の結果、環境上劣悪な地域が存在する等、あるいは、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある等について勘案し、手法の重点化や簡略化を検討する。なお、手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、調査地点、調査期間・時期等の増減等も含めて検討する。
【留意事項・事例】
・*4 手法に関する重点化・簡略化
重点化(重点的かつ詳細に実施する)又は簡略化(簡略化した手法で効率的に案施する)を適用するかとうかを検討する要素としては、以下のようなものが考えられる。 〔手法の重点化を検討する要素〕
[1]想定される環境への影響が著しい場合
[2]環境影響を受けやすい地域又は対象が存在する場合
・埋立地なと軟弱地盤の場合で振動の影響を受けやすい地域
・学校、病院、住居が集合している地域、その他の人の健康の保護又は生活環境の保全についての配慮が特に必異な施設又は地域
[3]環境の保全の観点から法令等により指定された地域又は対象が存在する場合
・幹線道路の沿道の整備に関する法律(昭和55年法律第34号)第5条第1項の規定により指定された沿道整備道路・既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合
・環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準であって、騒音に係るものが確保されていない地域
・騒音規制法(昭和43年法律第98号)第17条第1項に規定する限度を超えている地域
・振動規制法(昭和51年法律第64号)第16条第1項に規定する限度を超えている地域・地域特性、事業特性から標準手法では調査が技術的に困難と思われる場合・地形、地盤特性から複雑な伝搬特性を有する地域
・高さ方向や面的な現況把握が必要な地域(留意事項*3参照)
・事業者が保全上特に重視したものがある場合・地域特性
[6]事業特性、ならぴに事業における環境保全上の方針等に照らして、事業者が特に環境保全上重要だと判断したものがある場合
〔手法の簡略化を検討する要素〕
[7]環境への影響の程度が極めて小さいことが明らかな場合
・類似事業の事例などから、環境への影響が極めて小さいことが立証できる場合
・影響を受ける地域又は対象が相当期間存在しないことが明らかな場合
・騒音、振動、低周波音により影響を受ける住居、施設等が影響範囲内に現在およぴ将来にわたって存在しないことが明らかな場合
[9]実際の事例や既存の文献等に示された事例により標準手法を用いなくても影響の程度が明らかな場合
・類似事業における実測例等から影響の程度が推定可能な場合
[3]調査地域の考え方
調査地域は、調査対象とする騒音、振動、低周波音の特性や事業内容、地形及び土地利用等の地域の特性等を踏まえ、事業の実施による影響が最大となる地点を含む範囲とする必要があり、環境影響を受けやすい地域の存在等を考慮しなくてはならない。 一般的には、事業実施区域や道路端からの距離で設定する場合が多く、事業の実施により騒音レベル、振動レベル、低周波音圧レベルが一定以上変化する範囲を含む地域を、事業特性や騒音、振動、低周波音の伝搬特性等を考慮し調査地域として設定する。また、伝搬距離が長い等の理由により、一定以上変化する範囲の不確実性が大きい場合には安全サイドの考え方から広めに設定することも考えられる。
なお、工事用車両の走行の影響を検討する場合に、建設発生土の再利用場所が明らかであれば、必然的に事業実施区域から再利用場所までの工事用車両の効率的な走行ルートは限定され、事業実施区域から再利用場所までの全ての道路で道路交通騒音・振動レベルが一定以上変化する場合も想定されるが、その場合の調査地域としては、事業の実施による影響が最大となる地点を含む範囲として、図1-2-2のように、主要幹線道路までとする方法や、主要幹線道路沿道の特に影響を受けやすい地域までとする方法などが考えられる。
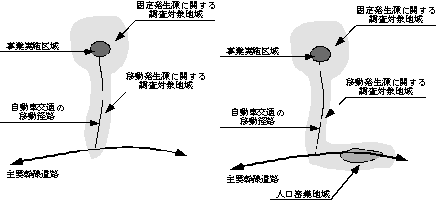
図1-2-2 移動発生源を対象とする場合の調査地域(例)
[4]調査地点の考え方
騒音、振動、低周波音の調査は一般に定点において行われるため、調査地点を設定することとなる。調査地点の設定にあたっては以下のような項目に配慮するとともに、実際に現地踏査を行い、測定に際しての安全性や、近傍の特定発生源の影響が少ないことを確認する必要がある。また、選定にあたっては、予測・評価地点と極力一致するように選定することで、現況からの環境の変化を分かりやすく表現することが可能となる。 なお、事後調査を行うことが想定される場合には、その地点における事後調査の実施可能性についても検討することが望ましい。
また、「騒音に係る環境基準について」(平成10年9月30日)において、幹線道路に近接する空間における基準値や、個別の住居等において騒音の影響を受けやすい面の窓を主として閉めた生活が営まれていると認められる場合の室内基準等が定められている。そのため、騒音に係る環境基準に準拠した調査を行う場合は、これらの考え方に十分留意して適切な調査地点を設定する必要がある。*5
- (ア) 地域を代表する地点
- 環境騒音・振動など、調査対象地域の騒音・振動の代表的な状況を知るための地点として調査地点を設定する場合には、地域特性を勘案して地域の代表性があると考えられる地点とし、近隣の特定発生源による影響が少ない箇所を選定する。
- (イ) 特に影響を受けるおそれのある地点
- 事業による影響が特に大きいと予想される地点(工事用車両走行ルート、高層住宅、主要道路との交差部、インターチェンジ等)は、事業特性等から特に影響を受けるおそれのある地点を設定する。 特に、幹線道路等の発生源の近傍に中・高層住宅が存在する場合には、高さ方向の調査地点の選定を検討する。
- (ウ) 特に保全すべき対象等の存在する地点
- 医療施設、文教施設など特に保全すべき対象等の存在する地点を予測地点として設定する場合、道路など他の発生源の影響により、(ア)の地域を代表する地点とは異なる状況が予想される場合には、これらの地点を調査地点として選定する。
- (エ) 既に環境が著しく悪化している地点
- 道路・鉄道等の特定発生源による影響を受けて、既に騒音・振動及び低周波音の状況が悪化していると考えられる地点を選定する。
- (オ) 特定発生源からの影響を把握できる地点
- 類似の事例による騒音測定結果を踏まえて予測を行う場合、事業内容や施設規模の類似性とともに発生源からの伝搬状況等も十分に確認した上で特定騒音・振動及び低周波音の状況を把握できる地点を選定する。
- (カ) 法令等により定められた地点
- 鉄道騒音や鉄道振動等は法令等による原則的な調査地点の規定があるため、基準又は目標との整合に係る評価を行う場合や事後調査を行うことが想定される場合には、法令により規定された地点を選定する。
例) 新幹線鉄道騒音 ………… 軌道中心線より25m及び50mの地点 在来鉄道騒音 ………… 近接側軌道中心から12.5mの地点 工場・事業場騒音・振動 ………… 敷地境界
【留意事項/事例】
- *5 環境基準における調査地点の考え方「騒音に係る環境基準」においては、一般地域、道路に面する地域でそれぞれ調査地点を選定する考え方が異なるため留意する必要がある。
・一般地城- 調査地域の騒音を代表すると恩われる地点とし、特定の音源の局所的な影響を受けず、地域における平均的な騒音レペルを評価できると考えられる地点して設定する。従って、必ずしも住居等の建物の周囲にある地点である必要はなく、例えば空き地であっても、当該地域の騒音を代表すると思われる地点であれぼ選定して差し支えない。
・道路に面する地域- 測定地点の選定にあたっては、評価区間内の住居等の分布を考慮し、道路に最も近い住居等の位竈とみなせる場所の騒音(道路近傍騒音)が測定できる地点を選定することとする。また、背後地における測定結果をもって距離減衰補正等を行う場合は、評価範囲内の背後地にある住居等の位置に相当する場所の騒音(背後地騒音)が測定できる地点を選定することが望ましい。道路近傍騒音の測定場所については将来の住居等の立地の可能性も考慮する。
(「騒音に係る環境基準の評価マニュアル」(平成12年4月環境庁)より抜粋)[5]調査期間、時期の考え方
調査期間や調査時期は、調査の目的を達成できるように、適切かつ効率的な期間・時期を設定する必要がある。
鉄道や航空機のような運行計画が存在するものや、工場のように、発生源の稼働を人為的に制御できるものについては、それらを事前に把握し、調査期間・時期を設定し、効率的かつ効果的な調査を行うことが可能である。
道路交通騒音は、不特定多数の車両の運行が騒音の発生源となるため、道路の利用特性等を事前に把握し、季節、曜日、時間帯の変動等を十分に考慮したうえで、調査期間・時期を設定する*6必要がある。
【留意事項/事例】
- *6 道路の利用特性を考盧した調査時期の設定(p.1・2・26参照)
環境基準では騒音は1年間を通じて平均的な状況を呈する目を選定するものとされており、道路交通騒音であれば、一般的には平日の24時間を調査時期・期間とする場合が多い。しかしながら、道路の主な利用目的が観光等の場合は、対象となる施設や行為の特性に応じて調査を行う季節、曜日、時間帯を設定することが望ましい。