平成13年度第1回陸水域分科会
資料3-2ダム
2. ケーススタディ -河口堰を例として-
《環境影響評価の実施段階》
3-4 基盤環境と生物群集の関係の調査
(1) 物理化学的な環境要素(基盤環境)の変化
1) 調査・予測の流れ
調査・予測のフローを図-3.8に示す。
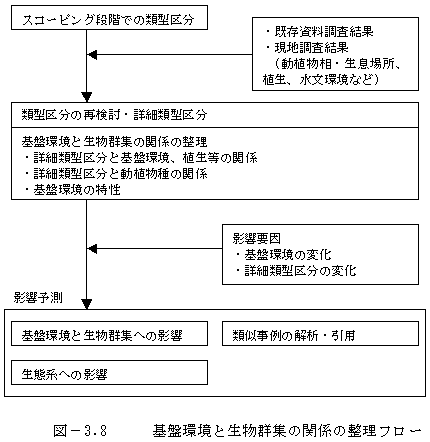
2) 類型区分
[1]類型区分の再検討
スコーピング段階における類型区分をもとに、「植物」、「地形・地質」等の現地調査結果(地形分類図、植生図等)、既存資料、現地調査結果、他項目での調査結果を踏まえて類型区分の再検討を行った。再検討した類型区分を表-3.7(PDFファイル12k)と図-3.9に示す。
なお、類型区分には、特に河川形態(瀬、淵の状況)、河川勾配、河床材料(底質)、生物群集の確認状況等に基づいて行った。
[2]各区分の生態系特徴
それぞれの類型区分における生態系の特徴について再整理を行った。
(a)類型区分Ⅰ
類型区分Ⅰに表現される山地渓流型河川は、山地の谷部にみられ、周辺は森林に覆われている。川幅は狭く、河川敷はなく、流路際まで山の斜面が迫っている。河川形態はAaⅠ型で、階段状の小滝が多い。河床材料は岩盤や巨石、人頭大の礫、ところにより砂利等が多くみられ、また、流倒木や落ち葉の溜まりがみられる。河岸にはミズナラ、サワグルミ等の群落が発達し、河川は完全に樹木に覆われている。両生類ではハコネサンショウウオ、魚類ではイワナが確認され、また、産卵場ともなっている。
(b)類型区分Ⅱ
類型区分Ⅱに表現される山地渓流型河川は、谷を流れる山地の渓流であり、河川沿いに平坦部はほとんどなく、山地の斜面が迫っている。河川形態はAaⅡ型であり、所々に小滝があり、早瀬と淵が多く、流入支流との合流点付近には中州や河原がみられる。河床はこぶし大から人頭大の礫が目立ち、粗砂等の細粒分も多い。また、直径2mを超えるような巨石もみられる。河岸にはミズナラ等の群落が発達し、河川の上空を完全に覆っている。両生類ではハコネサンショウウオ、アズマヒキガエル、魚類ではイワナ、ヤマメが確認され、また、流入する沢等は産卵場ともなっている。
(c)類型区分Ⅲ
類型区分Ⅲに表現される中間渓流型河川は、山間部の谷間から平野に移るあいだの地域であり、河川形態は主にAa-Bb移行型である。川幅が広く、平瀬や早瀬、中州や河原がみられる。河床には砂利や粗砂の細粒分や人頭大の礫の浮石がみられる。上流と比較して河床勾配は緩く、流路が広い。両生類ではイモリ、カジカガエル、魚類ではイワナ、アユ、アブラハヤ、オイカワが生息しており、これらの種の産卵場ともなっている。
(d)類型区分Ⅳ
類型区分Ⅳに表現される中流河川は、河床勾配は比較的緩く、川沿いには低地がみられる。流路の上空は完全に開けており、広い間隔で平瀬や早瀬が連続している。鳥類ではカワセミ、キセキレイなど、両生類ではイモリ、カジカガエルなどがみられ、魚類ではアブラハヤ、オイカワ、ヨシノボリ、カマツカなど種類が多い。水生植物ではバイカモ、コカナダモの生育する水域も認められた。
(e)類型区分Ⅴ
類型区分Ⅴに表現される止水域は、既存のダムの貯水池であり、湖岸には水位変動による裸地がみられ、陸域と水域は分断されている。鳥類ではオシドリ、マガモ等がみられ、魚類ではウグイ、ワカサギ、サクラマス等が生息している。
3) 類型を構成する環境要素
先に示した類型区分(Ⅰ~Ⅴ)を生物の生息場所としての視点からさらに細かく環境要素で分けることにより、各類型をより詳細に把握することができる。
類型区分を構成する環境要素の視点としては、早瀬、平瀬、淵、サイドプール、水生植物群落、石礫の河原、短茎草本群落、ヨシ群落、崖、高木の樹冠など、魚類、両生類、大型甲殻類、鳥類、昆虫類などの生活史の一時期、あるいは一生の生活場所となる範囲とする。
また、河川内ついては、早瀬、平瀬、淵等に区分したうえで、さらにそれぞれの河床材料の種類と状態で分けることもできる。河床材料の種類とは、巨石、礫、砂(粗砂、細砂等)、泥(シルト、粘土)などであり、河床材料の状態とは、浮き石(1層、2層)、はまり石等をさす。
なお、さらに細かく生息場所を区分する場合の視点としては、河床の石礫の表面、間、裏面、水中の植物体表面、河床の砂中等があげられる。
これらの視点から類型区分をさらに生物の生息場所という視点で細かく分けることにより、より詳細に生物への影響が把握できると考えられる。
なお、現在の予測手法ではこれらの瀬・淵構造や河床材料がダムの存在・供用に伴い非存在・非供用時に比べて定量的にどの程度変化するかまでの予測はできない。しかしながら、予測レベルに調査レベルを合わせるとすると、大枠のみの調査となり、現況把握のレベルにも到達しないといえる。よって、ここでは、現況における生物と場の状況の把握に務める。
なお、瀬・淵の位置や河床材料の状況等は、1回の洪水で変化してしまうことから、現況を調査区域全体にわたってあまりにも詳細な調査を実施する必要はなく、例えば、類型区分Ⅱを代表するポイント、区間の数カ所において調査を実施し、大まかな状況(瀬、淵の割合等)を把握する程度とする。
これらの類型区分を構成する環境要素とそれぞれの要素で確認された動植物種の対応を表-3.8(PDFファイル15k)に示す。
4) 影響要因、影響内容の検討
ダムの存在・供用時の影響は、地形改変及び施設の設置、貯水池の存在、河水の取水である。これらの事業による環境への影響フローを図-3.10(PDFファイル15k)に示す。
(2) 基盤環境と生物群集の関係による生態系への影響予測
動植物の「生息場所」に対する事業の実施による影響を予測するという観点から、「生息場所」を成立させている基盤環境(物理的要素)の変化について予測を行った。また、それらの基盤環境に生息・生育する種についての変化についても予測を行った。
1) 事業実施による基盤環境ごとの面積変化
[1]予測手法
各類型への影響についてはダムの堤体位置、貯水予定地等の改変区域と類型区分図との重ね合わせにより、各類型ごとの改変区間の距離等から影響の内容・程度について把握した。
[2]予測結果
改変予定区域と類型区分図とを重ね合わせた結果、直接的な改変の影響を受ける区間及び距離を表-3.9に示す。
事業の実施に伴い、区分Ⅲに相当する河川6㎞、及び区分Ⅳに相当する河川7㎞が貯水予定地と重なり、消失する。
区分Ⅲにはイモリ、カジカガエル、イワナ、アユ、アブラハヤ、オイカワ、水生昆虫類ではヒゲナガカワトビケラ、ウルマーシマトビケラ等が生息しており、それらの種の産卵場所ともなっている。また、区分Ⅳにはアブラハヤ、ヨシノボリ、カマツカ等の種がみら、水生植物の生育も認められた。
これらの渓流域を代表する種が生息・生育する基盤環境のうち20~40%が消失することにより、そこに生息・生育する種の個体数等も減少するものと考えられる。
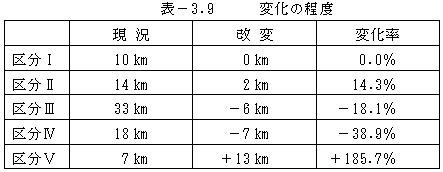
2) 流量・水温・水質の変化
当該ダム事業は、水力発電を兼ねたものであることから、下流河川の一部においては減水区間が生じる(流量の減少)。また、ダムからの放流水は、低水温である可能性が高く(水温の低下)、さらに貯水池で滞留することにより植物プランクトンが増殖し、放流水質の変化が懸念される(水質悪化)。よって、下流河川において流量及び水温・水質について予測を行った。これらの基盤環境は、下流河川における生物に大きな影響を及ぼすおそれがある。
[1]予測手法
流量は予定されるダムの運用方針、水力発電状況等を用い、過去の類似事例等を参考に予測した。また、水温・水質に関しては、水環境における予測結果を用いた。
[2]予測結果
減水区間の流量は現況の○m3/sから供用後には○m3/sになると予測される。減水区間の流量の減少に伴い、過去の類似事例より早瀬が○%程度減少し、平瀬が○%程度増加すると予測された。これにより、現地調査結果等から早瀬を好んで生息する○○○や○○○の個体数は減少し、平瀬を好んで生息する○○○や○○○の個体数は増加すると考えられる。
また、貯水池からの放流水により、夏季における3-5℃程度の水温低下、および貯水池内における植物プランクトンの増殖によるBODの○mg/l程度の増加が予測される。これに伴い、下流河川に生息する○○や○○等の種の成長速度や繁殖等に影響が出るおそれがある。なお、イワナへの影響については、後述の「注目種・群集に関する調査・予測」に示す。
3) 河床材料の変化
ダムの供用に伴い、下流河川への土砂供給量の減少、後述する氾濫頻度の減少等によって下流河川の河床材料が変化すると考えられる。河床は水生昆虫類の生息空間であるとともに、魚類等の産卵場所になることから、これらの生物種への影響が懸念される。
[1]予測手法
既存資料、類似事例、ダムの運用方針等からダム下流に流下する土砂供給量を予測し、下流河川の河床材料の変化を予測した。
[2]予測結果
ダムが供用することにより、ダム堤体より下流河川への土砂供給が減少する。それにより、粒径の小さい砂礫の供給がなくなり、また、現在存在する砂礫は掃流され、粗粒化する可能性が高いと予測される。また、ダム直下においては、土砂供給がなく氾濫頻度が減少することにより、礫間が埋まり河床が硬化するいわゆるアーマー化現象が起きると考えられる。
これらの事象が生じることにより、河床に生息する水生昆虫類のうち砂礫質を好む○○○等の個体数は河床の粗粒化に伴い減少し、また、粒径の大きな河床を好む○○等の個体数は増加すると考えられる。
4) 下流河川の氾濫頻度の減少
ダムの供用に伴い、下流河川においては○m3/s程度の中小洪水の発生頻度が減少する。それにより下流河川への土砂供給量の減少、河畔の冠水頻度の減少等の影響が考えられ、下流河川の河床、河畔等に生息・生育する種に影響を及ぼすおそれがある。
[1]予測手法
代表的な予測地点において、既存資料や現地調査結果等から河川横断面、河床勾配、粗度係数、また、過去の洪水時の流量等を求め、マニングの平均流速公式に基づいた式を用いて、ダムの供用前後洪水確率毎の水位を求める。
[2]予測結果
洪水確率毎の水位の予測結果を表-3.10、図-3.11(PDFファイル17k)に示す。
断面A、Bともに洪水時の水位は大きく低下すると予測された。これにより、中小洪水時において冠水する河畔に生育する植物等は次第に安定立地を好む種の侵入を受け、植物の構成が変化すると考えられる。
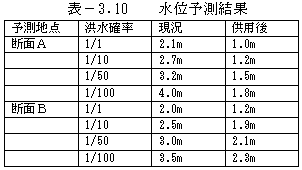
3-5 注目種・群集に関する調査・予測
ここでは、スコーピングにおいて注目種・群集として抽出されたヤマセミ(上位性)、イワナ(典型性)、オオバヤナギ林(典型性)の3種についての調査・予測作業例を示す。
(1) ヤマセミ(上位性)
1) 予測する影響の内容
ダム事業によるヤマセミへの影響フローを図-3.12に示す。
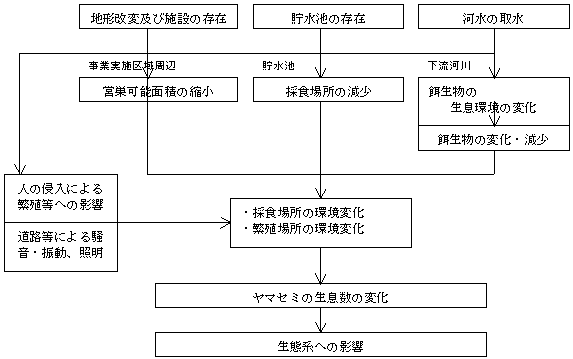
図-3.12 ダムの存在・供用が注目種(ヤマセミ)に及ぼす影響フロー
これらのヤマセミへの影響のうち、ここでは生息環境の変化程度、繁殖への影響について検討する。
2) 調査・予測手法の検討
[1]調査・予測手法検討の流れ
調査・予測手法検討の流れを図-3.13に示す。
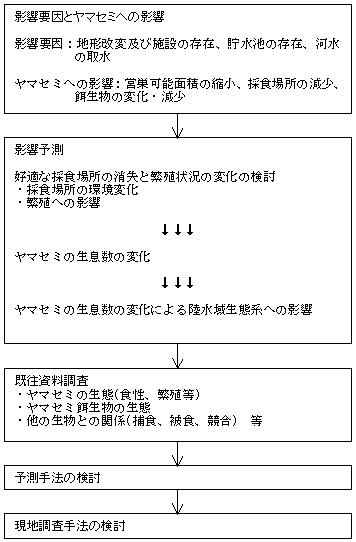
[2]予測手法検討
事業実施に伴うヤマセミの好適な生息場所の消失の程度と繁殖への影響については、以下の2つの予測手法を用いて検討する。
(好適環境に関する予測)
好適な採食場所の変化に注目し、変化する面積の相対的変化量を影響予測の材料とする。
→好適性区分の面積変化量により影響予測する。
(繁殖への影響予測)
個別つがいを単位として、事業実施区域と行動圏の位置的な関係から存続の可能性を判断する。ただし、行動圏の外郭が明らかでない場合、推定行動圏(繁殖のためのコアの部分として、ここでは1km幅とする)を設定する。
→存続可能つがい数により影響予測する。
[3]現地調査手法の検討
予測手法の検討結果をもとに検討した現地調査手法を表-3.11に示す。
| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 |
| 環境利用に関する調査 | ヤマセミの個体を追跡しながら情報をとるタイムマッピング法により行う。単位時間ごと(3~5分)に個体の位置・行動及び環境を記載する。 また、餌場に適した生息場所を踏査し、個体の行動を確認する。 調査時期は、繁殖期、夏季、秋季、冬季とする。 調査場所は、事業実施区域及びその周辺地域とする。 |
| 餌生物に関する調査 | 餌生物の確認は、双眼鏡等を用い、目視観察により行う。また、ヤマセミが吐き出したペリット(不消化物)を観察し、餌生物の種類・割合等を推測する。 調査時期は、繁殖期、夏季、秋季、冬季とする。 調査場所は、事業実施区域及びその周辺地域とする。 |
| 生息状況に関する調査 | ヤマセミの出現しそうな川沿いを踏査し、さえずり、実個体等を確認する。 繁殖つがいの数やテリトリーの分布状況はテリトリーマッピング法により行う。 調査時期は、繁殖期とする。 調査場所は、事業実施区域及びその周辺地域とする。 |
なお、繁殖期に調査を実施する際にはヤマセミの繁殖行動に影響を与えないよう十分に注意する必要がある。
3) 調査結果・予測結果の概要
[1]調査結果の概要
調査対象地域内におけるヤマセミの繁殖つがい数は6つがいであった。いずれのつがいも川沿いの土の崖に営巣していた。このうち、2つがいは貯水予定地に位置していた。営巣場所を中心とした活動範囲を図-3.14に示す。
好適な場所に関する調査では、営巣場所としては土質の崖等が、また、餌場としては樹木の枝が水面を覆うような環境で淵となっている場所が好適であると判断された。
採食状況と営巣地に関する調査から、ヤマセミの繁殖好適エリアを把握した。
また、餌として利用されていた生物は、5~20㎝程度のイワナ、ヤマメ、ウグイ等の魚類が大半であった。
[2]予測結果の概要
(a)個体の繁殖存続に関連する影響予測結果の概要
(好適環境に関する予測)
事業実施区域及びその周辺地域における河川沿いのエリアをヤマセミの営巣場所としての視点からみた好適さの程度と餌場としての視点からみた好適さの程度で区分した。また、事業によるそれらの消失割合を把握した。その結果を表-3.12に示す。
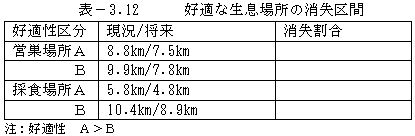
これらより、営巣場所として好適な環境の○%と餌場として好適な環境の○%が事業により消失することになり、これによりヤマセミへの影響が懸念される。
(繁殖への影響予測)
事業実施区域内に行動圏をもつ2つがいについては、生息場所の消失の影響を受けるといえる。
なお、湛水時期が繁殖期以外であれば、湛水により巣が消失しても周辺の類似した環境に移動することも考えられるものの、不確実を伴うことから、工事中、供用後に事後調査を行い、影響を確認する必要がある。
(b)生態系への影響予測結果
ヤマセミは渓流における食物連鎖の上位に位置する種であることから、本種が事業影響を受けることで、ヤマセミと捕食-被補食関係にある種 及びそれらの種に関連した種々の生物に影響が及ぶと推測される。
つまり、ヤマセミの餌生物であるイワナ、ヤマメ等の魚類への捕食圧が変化し、それらの魚種構成や個体数にも影響があると考えられ、ひいては渓流域生態系への影響が懸念される。
さらに、ヤマセミと同様な環境に営巣する種、同様な生物を餌とする種などについても同様の影響があると考えられる。
(2) イワナ(典型性)
1) 予測する影響の内容
ダムの供用に伴うイワナへの影響フローを図-3.15に示す。
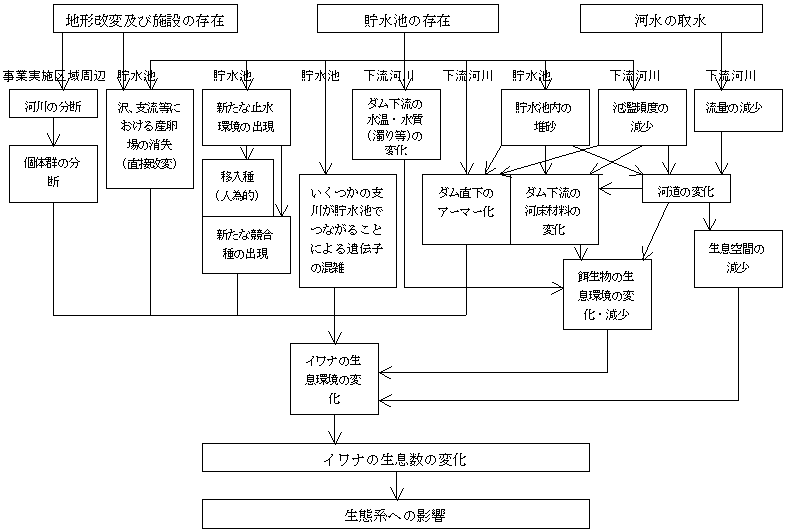
図-3.15 ダムの存在・供用が注目種(イワナ)に及ぼす影響フロー
これらのイワナへの影響のうち、ここでは生息場所の変化、水温・水質の変化、産卵場所の変化について検討する。
2) 調査・予測手法の検討
[1]調査・予測手法検討の流れ
調査・予測手法の流れを図-3.16に示す。
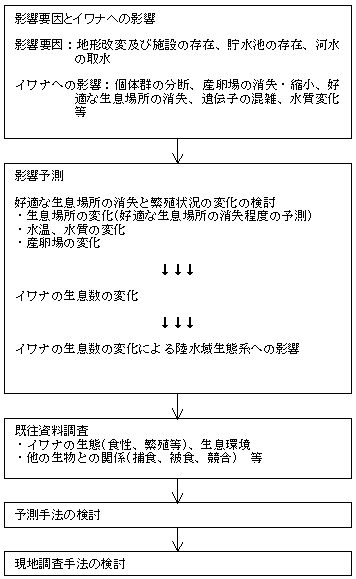
図-3.16 調査・予測手法検討の流れ
[2]予測手法の検討
事業に伴う生息場所の変化、水温・水質の変化、産卵場の変化について予測を行う。
(生息場所の変化)
イワナの成長段階ごとに利用する河川環境を整理し、事業実施により変化する河川環境についてイワナが利用可能かどうかを予測する。
(水温・水質の変化)
ダム放流水の水温変化の予測結果をふまえ、既存文献等より事業実施後の水環境においてイワナが生息可能かどうかを予測する。
(産卵場の変化)
ダム下流側の河床材料の予測結果等より、イワナの産卵場としての適所と改変区域とを比較し、消失する場を予測する。
[3]現地調査手法の検討
予測手法の検討結果をもとに検討した現地調査手法を表-3.13に示す。
| 調査項目 | 調査内容 |
| 生息状況に関する調査 | イワナの現存量を把握するため、投網や網の設置等によりイワナを捕獲し、体長等を測定したのち、成長段階ごとの利用環境の状況、生息密度の高い場所等を把握する。 調査時期は春季、夏季、秋季、冬季とする。 調査範囲は、事業実施区域及びその周辺区域とする。 |
| 生息環境に関する調査 | 河川形態、流況、水温、水質、河床材料、河畔の植生を調査し、イワナの生息環境を把握する。 調査時期は春季、夏季、秋季、冬季とする。 調査範囲は、事業実施区域及びその周辺区域とする。 |
| 産卵場の調査 | イワナの産卵に適した砂礫質の河床材料のエリアを把握する。 また、イワナの卵や稚魚の採集を行い、実際に産卵が行われている場所を確認する。 調査時期はイワナの産卵時期とする。 調査範囲は、事業実施区域及びその周辺区域とする。 |
3) 調査結果・予測結果の概要
[1]調査結果の概要
現地調査結果により、調査地域周辺河川にはイワナが広く分布していることが明らかとなった。特に、○○支川との合流箇所や、○○沢の付近は生息密度が高かった。
イワナの生息環境は成長段階ごとに異なる。成長段階ごとの河川の利用環境を表-3.12に示す。
調査時期の水温は2.1℃~20.3℃、pH6.5~8.5、DO7.4~9.8mg/l、BOD0.5mg/l未満~2.0mg/lであった。
河床材料は場所により異なるが、砂礫、岩盤等がみられた。また、砂礫の区域で産卵場がいくつか確認された。
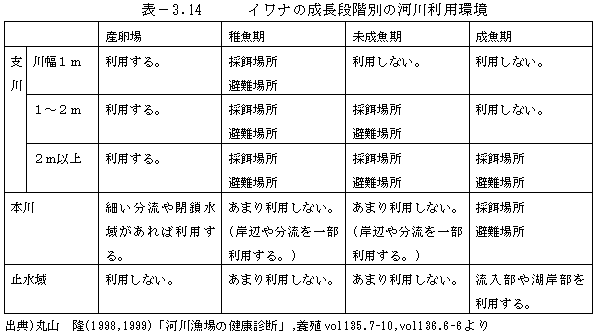
[2]予測結果の概要
(a)個体の繁殖存続に関連する影響予測結果の概要
(生息場所の変化)
稚魚、未成魚の生息環境や産卵場には、川幅の狭い河川が利用され、成魚の生息環境としては川幅の広い河川が利用される。ダム湖内は稚魚、未成魚の生息環境や産卵場には利用されないが、成魚はダム流入部や湖岸を利用する。よって、ダム湖周辺のイワナの存続には稚魚、未成魚の生息環境や産卵場である川幅の狭い流入河川等が残存することが重要であるといえる。
(水温・水質の変化)
イワナの水温に対する生息適正条件は18℃以下であり、20℃以上では摂食できなくなるとされている。水環境の予測結果を用いると、ダムの供用に伴い、ダム直下の水温は夏季に2~5℃程度低下すると予測され、その他の時期はダム供用前と同様であると予測された。イワナは冷水域に生息する種であることから、この程度の水温の低下は影響を受けないと考えられるものの、魚の成長や成熟が進む夏季の水温が低下することにより、成長や成熟が多少抑制される可能性もある。なお、産卵期、稚魚の生育期における水温の低下はみられないことから、おおむねイワナの生息への影響はないと考えられる。
水環境において予測されたダム下流の水質は、夏季のある時点においてBODが0.5上昇し、2.5mg/lになるものの、その他の時期はダム供用前とほとんど変化がみられないと予測された。一般の魚類ではBODが5mg/lでも普通に生育できるものの、イワナ等の冷水域に生育する種は有機汚濁が進むと伝染性疾患にかかりやすくなるとされている。サケ、マス、アユではBOD2mg/lが自然繁殖の条件であり、3mg/l以下が生育の条件である。よって、水質予測結果の2.5mg/lは生育の条件を下回っているものの、自然繁殖は難しくなる値であるといえる。しかしながら、水質悪化の時期は繁殖時期でないことから、イワナへの影響は大きくはないと考えられるものの、何らかの影響は注意して観察すべきであるといえる。
(産卵場の変化)
現地調査において、流入支川ではイワナの稚魚、未成魚やイワナのものと考えられる産卵場が確認できた。これらのうち一部はダムの供用により消失するエリアであることから、ダムの供用によりイワナの産卵場は影響を受けると考えられる。しかしながら、ダム貯水区域の上流側や下流側の支流には同様な産卵場が確認されていることから、対象河川におけるイワナは存続を続けられるといえる。
(b)生態系への影響予測結果
本種の生息密度の高いエリアや産卵場となるエリアの一部が消失することにより、また、ダム下流河川の水質悪化に伴い、イワナの生息数に何らかの影響が出ると予測された。その結果、イワナを餌とする生物、イワナの餌となる生物、又はイワナと同様な生活を送る生物に影響が出ると予測される。さらに、イワナと同様の場所で生活を送るイワナの餌生物についても影響がでることから、さらにイワナの減少が考えられる。
(3) オオバヤナギ林(典型性)
1) 予測する影響の内容
ダムの供用に伴うオオバヤナギ林への影響フローを図-3.17に示す。
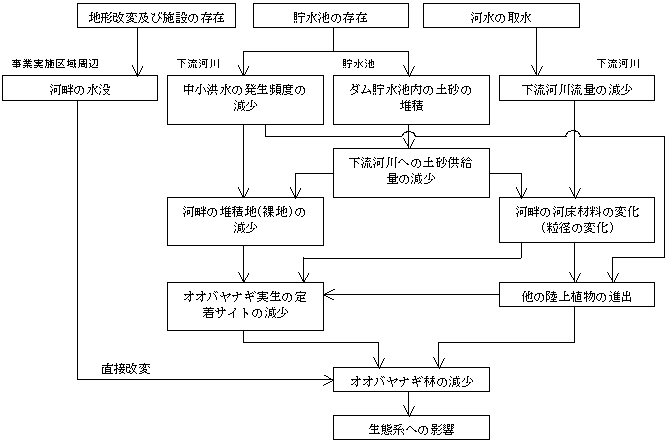
図-3.17 ダムの存在・供用が注目種(オオバヤナギ林)に及ぼす影響フロー
これらのオオバヤナギ林への影響のうち、ここでは中小洪水の発生頻度の減少及び貯水池における堆砂に伴う下流河川の河畔地形の変化について検討する。
2) 調査・予測手法の検討
[1]調査・予測手法検討の流れ
調査・予測手法の流れを図-3.18に示す。
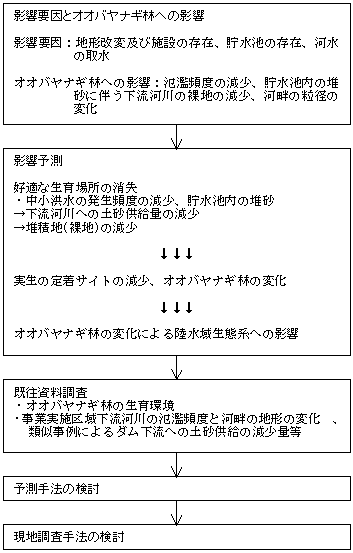
図-3.18 調査・予測手法検討の流れ
[2]予測手法の検討
オオバヤナギ林はオオバヤナギ、ヤマハンノキ、オノエヤナギ等で構成される河川上流部の河畔に成立する河畔林であり、砂礫質の土壌を好む。
洪水により、オオバヤナギ林の生育地は破壊される一方で、新たな堆積地(裸地)ができることにより、オオバヤナギ林の更新が可能になる。(オオバヤナギ等の実生は裸地に定着し、オオバヤナギ林の林床では育たない。)つまり、洪水の作用により、河畔にさまざまな林齢のオオバヤナギ林が生育することとなり、様々な環境の創出につながっているといえる。
よって、ダムの供用によって中小洪水の発生頻度が減少し、また、ダム貯水池内の堆砂により下流河川への土砂供給量が減少することにより、新たな堆積地(裸地)の減少につながり、ひいてはオオバヤナギ林の衰退につながる。
よって、ダムの供用に起因する下流河川の中小洪水の発生頻度の変化、土砂供給量の変化に伴う河畔地形(堆積地)の変化について予測を行う。
事業実施区域下流河川の河畔地形及び植生の推移については、過去の空中写真及び現地調査結果から整理する。また、過去の洪水の履歴を整理し、ダム供用後の環境を予測する。
なお、基盤環境の影響予測において整理した下流河川の洪水時の水位変化、及び既存ダムにおける土砂堆積量の類似事例を整理し、ダム供用後の下流河川環境の予測のための資料とする。
[3]現地調査手法の検討
予測手法の検討結果をもとに検討した現地調査手法を表-3.15に示す。
| 調査項目 | 調査内容 |
| 生育状況に関する調査 | オオバヤナギ林の生育状況を把握するため、オオバヤナギ林の生育場所を現地踏査より確認し、年輪解析、空中写真の判読により林齢等を把握する。 調査時期は夏季とする。 調査範囲は、事業実施区域下流河川とする。 |
| 生息環境に関する調査 | 河川形態、流況、水温、水質、河床材料、河畔の植生を調査し、オオバヤナギ林の生育環境を把握する。 調査時期は通年とする。 調査範囲は、事業実施区域及びその周辺区域とする。 |
| 洪水頻度、河道の変化の把握 | 航空写真や既存資料から近傍観測所における過去からの洪水の履歴(日最大流量)、河道内の地形、植生の変遷等を把握する。 |
3) 調査結果・予測結果の概要
[1]調査結果の概要
河道内の地形及び植生の変遷及び過年度の洪水の頻度とその規模を図-3.19に示す。
洪水の頻度と地形、植生の変遷を併せてみると、洪水の発生頻度の低い期間では、草本群落の減少、木本群落の増加がみられ、また、発生頻度の高い期間では草本群落の増加、木本群落の減少がみられた。
また、近傍のダムにおける堆砂量を整理したところ、表-3.16のとおりとなり、これらの堆砂により、下流河川への土砂供給量が減少していると考えられる。
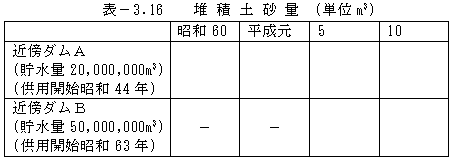
現地調査結果によると、オオバヤナギ林は河畔の砂礫地に点在しており、その林齢は林分ごとにさまざまであった。林分の多くは数十cm程度の水位上昇によって冠水する場に位置しており、構成種はオオバヤナギのほか、ヤマハンノキ、オノエヤナギ、サワグルミ等の生育がみられた。オオバヤナギ林の林齢解析、及び過去の空中写真判読により、オオバヤナギ林の定着年、及び生育基盤となっている砂州の成立時期が推定された。また、過去の空中写真判読により、昭和53年及び平成7年の500m3/s以上の洪水後にはオオバヤナギ林の消失がみられた。その後、裸地化した砂州には数年後に再びオオバヤナギ林の定着が確認され、当該地でのオオバヤナギ林の更新には、この程度の洪水による撹乱が必要であることが推察された。
[2]予測結果の概要
(a)オオバヤナギ林生育環境の予測結果
洪水頻度と裸地形成の関係、ダム貯水池内の堆砂による下流河川への土砂供給量の変化、洪水時の水位変化予測計算等より、下流河川のオオバヤナギ林は以下のとおり変化すると予想される。
・土砂供給量の減少によってオオバヤナギ林面積は河川水に浸食され、徐々に面積が減少する。また、中小洪水の発生頻度が減少により、生育地の安定化が進むため、ミズナラ、オオカメノキなど周辺の山腹斜面の安定立地に見られる種がオオバヤナギ林内に増加し、次第に優占度を増してゆくと考えられる。
・稚樹が生育可能な河畔の裸地は、中小洪水発生頻度の減少、土砂供給量の低下に伴い、新たに形成されにくくなる。その結果、新たなオオバヤナギ林は成立しにくくなる。
・なお、中小洪水の発生頻度は、事業実施により減少すると考えられるものの、その程度の予測は現段階ではむずかしく、生育地の安定化による種構成の変化、裸地の形成状況等に不確実性が伴う。よって、事後調査の必要があるといえる。
(b)生態系への影響予測結果
河畔のオオバヤナギ林が老齢化により衰退し、また、新たなオオバヤナギ林が育ちにくくなることによって、日射遮断効果、落葉・落下昆虫類の供給、倒木の供給が減少し、ひいては渓流全体の生態系に影響を与えると考えられる。また、オオバヤナギ林に代表される渓畔林、河畔林は同様な裸地や砂礫地を好むことから、渓流域全体に対する影響が考えられる。それぞれの効果について以下に詳細に述べる。
◇日射遮断:樹冠による日射の遮断により、夏期においても渓流の水温を低温に保つ。このため、渓流内の石礫に付着する藻類の繁殖は押さえられ、夏季においても安定した低温環境が保たれる。こうした効果は、冷水を好むイワナ、ヤマメ等の渓流魚にとってはきわめて重要である。
◇落葉・落下昆虫供給:水辺林の樹冠による日射遮断が卓越する山地渓流では、水生植物による光合成量は小さく、エネルギーの大部分を渓流外で生産される有機物に頼らねばならない。このエネルギーのほとんどが秋に水辺林から落とされる落葉である。渓流内に入った落葉は可溶性物質が溶け出した後、微生物が付着し、最終的には水生昆虫により摂食されて分解される。落葉速度は渓畔に見られる種の方が一般には高く、コナラ属(ミズナラなど)、ブナ属(ブナ、イヌブナなど)の葉は分解されにくい。オオバヤナギ林(渓畔・水辺の種を主体とした森林)である事が、エネルギーを供給する機能のうえでは重要と考えられる。
◇倒木供給:倒流木は渓流の微地形を形成し、環境の多様性を高めるとともに渓流内の物質の移動に重要な役割を果たす。倒流木によりできる淵、その陰にできる暗い場所などは魚類の生息場として重要な要素である。
◇生息場所としての機能:陸上の動物、鳥類、昆虫類等にとっての生息場所、繁殖場所となっている。
◇その他:流量を多様化し、瀬、淵構造の形成につながることや、栄養塩吸収により過剰な水質汚濁を防ぐ効果、また土砂の捕捉の効果により安定した河川環境の維持につながる。
また、オオバヤナギ林と同様に河畔の裸地や河原等の環境に生息・生育する種として、河川中流域の砂礫地を好むカワラハンミョウ、カワラサイコ、カワラヨモギ等があげられる。対象河川では、中・下流域に流下するまでにはいくつかの支川が流れ込むことから、洪水時の水位低下、土砂供給量の減少はオオバヤナギ林が確認された位置ほどではないといえる。しかしながら、将来、各支川にそれぞれ何らかの洪水調節施設ができた場合、これらの種にも影響が及ぶと考えられ、ひいては生物多様性への影響、生態系への影響が懸念される。
戻る