平成13年度第1回陸水域分科会
資料3-1河口堰
2-5 注目種・群集に関する調査・予測
ここでは、スコーピングにおいて注目種・群集として抽出されたミサゴ(上位性)、ヤマトシジミ(典型性)、アユ(典型性)、トビハゼ(特殊性)の4種についての調査・予測作業例を示す。
(1) ミサゴ(上位性)
上位性の代表種であるミサゴは、主に沿岸付近や周辺の山間部などで繁殖を行い、通常河川内では繁殖活動は行わない。そこで、本ケーススタディでは、河川内をミサゴの餌場と考え、事業による餌場の変化と、変化による影響予測を行うこととした。
1) 予測する影響の内容
本事業がミサゴに及ぼす影響フローは図-2.12に示すとおりである。
堰の存在によって、汽水域が中央部で上・下流に分断され、上流側には湛水域が出現し、下流側には塩分などの環境要因が変化することなどによって、ミサゴの狩り場及び餌生物が変化すると考えられる。これらの変化によって行動圏や捕獲する餌の変化など、ミサゴへの影響が想定される。
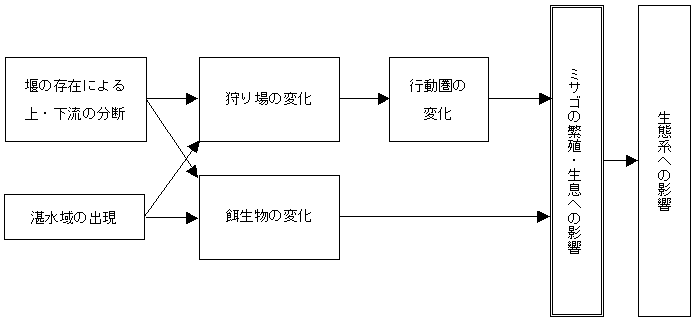
図-2.12 堰及び護岸(存在)が注目種(ミサゴ)に及ぼす影響フロー
2) 調査・予測手法の検討
[1] 調査・予測手法検討の流れ
ミサゴへの影響について、調査・予測の流れを図-2.13に示す。事業による影響は、餌生物の変化、狩り場の環境変化などによる影響などがあげられる。このような影響を把握するために、生息状況調査を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の変化と、繁殖の存続の可能性を検討し、事業による影響を予測する。また、ミサゴへの影響予測結果を基に、生態系への影響について検討する。
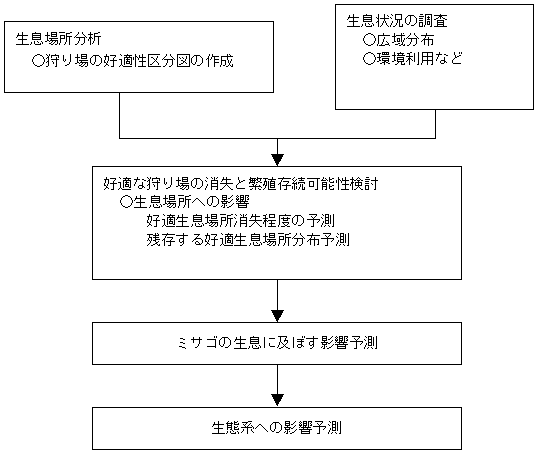
| 注)ミサゴは通常河川内ではなく、沿岸付近や周辺の山間部で繁殖する。河川の環境変化による繁殖への影響は想定されないことから、ここでは繁殖についての調査は行わないこととする。 |
図-2.13 ミサゴの調査・予測の流れ
[2] 予測手法検討
堰や護岸の存在によるミサゴの影響予測手法の内容を表-2.14に示す。
ここでは、堰や護岸の存在による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を設定した。
| 影響 要因 |
想定される影響と予測手法 | ||
| 狩 り 場 の 変 化 |
想定される影響 | ・ミサゴの狩り場に堰や護岸が設置されることにより、ミサゴの行動圏や摂餌行動に影響が及ぶと考えられる。 | |
| 予測手法 | 分布・餌場 | ・ミサゴの行動圏や探餌・摂餌行動については、現地調査地域における分布状況と行動パターンから主要な利用環境を把握し、環境の変化からミサゴへの影響を予測する。 | |
| 餌 生 物 の 変 化 |
想定される影響 | ・堰の存在による上・下流の分断、湛水区域の存在や河床勾配の変化によって、水質の変化、地形・水深変化、底質変化が考えられることから、ミサゴの餌生物が変化すると想定される。 | |
| 予測手法 | 餌 | ・ミサゴの餌生物の変化については、現地調査地域でミサゴが捕獲した餌の調査、それら餌生物の分布状況を調査し、予測される河川環境の変化によって想定される餌生物への影響から、ミサゴへの影響を予測する。 | |
[3] 現地調査手法の検討
予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表-2.15に示す。
| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 | ||
| ミ サ ゴ の 分 布 状 況 |
・ミサゴの分布状況 ・行動パターン・環境条件 |
調査項目の設定根拠 | ・ミサゴの狩り場に堰や護岸が設置されることにより、ミサゴの行動圏や摂餌行動に影響が及ぶと考えられるため、ミサゴの分布状況と探餌・摂餌などの行動パターン等を調査し、主要な利用環境を把握し、環境の変化による影響を予測する。 |
| 調査地点 | ・河口~河口から20km及びその周辺3kmの区間。 | ||
| 調査時期 | ・月1回、4日間の観察を1年間行う。 ・環境条件の調査は、ミサゴが探餌・摂餌などの行動を行った場所についてその都度行う。 |
||
| 調査方法 | ・周辺を見通せる地点に調査員を配置し、ミサゴの確認位置、個体数、行動パターン、雌雄、年齢、個体の特徴等を観察、記録する。また、調査範囲における摂餌行動、餌の捕獲位置、餌の採餌位置を記録する。 ・環境条件の項目は、水深、透明度、水面の静穏度合いなどとし、目視によって確認、記録する。 |
||
| 餌 生 物 の 変 化 |
・捕獲した餌 ・餌生物の分布 |
調査項目の設定根拠 | ・堰の存在による上・下流の分断や湛水区域の存在によって環境要因が変化し、ミサゴの餌生物が変化すると想定されるため、ミサゴの捕獲した餌を調査し、次にそれら餌生物の分布状況を調査し、予測される河川環境の変化によって想定される餌生物への影響を把握する。 |
| 調査地点 | ・ミサゴの分布状況調査と同様とする。 ・餌生物の分布については分布状況調査範囲に調査地点を設定する。 |
||
| 調査時期 | ・月1回、4日間の観察を1年間行う。 ・餌生物調査については4季調査(各1回)とする。 |
||
| 調査方法 | ・分布状況調査時に餌の捕獲をした個体について、目視による餌の大きさと種類を観察、記録する。 ・餌生物の分布調査は、投網を用いて試料を採集し、個体数、湿重量などを測定する。 |
||
3) 調査結果・予測結果の概要
[1] 現地調査内容
分布状況調査は4月から翌年3月まで月1回、合計12回実施した。観察は1回の調査について4日間行った。調査地点は河口~20kmまでの範囲とその周辺3kmの区間に15地点設定した。調査方法は、周辺を見通せる地点に調査員を1~2名配置し、ミサゴの位置の確認、個体数、行動パターン、雌雄、年齢、個体の特徴等を観察、記録した。また、摂餌行動、餌の捕獲位置、餌の採餌位置の記録も行った。なお、環境条件項目については、摂餌を行った場所について、目視で水深、透明度、水面の静穏度合いなどを観察、記録した。
餌生物の変化の調査は、分布状況調査時に餌の捕獲をした個体について、目視によって餌の大きさと種類を観察、記録した。また、餌生物の分布については、分布状況調査範囲に調査地点を50地点設定し、5、8、11、2月に合計4回行った。調査は投網を用いて試料を採集し、個体数、湿重量などの測定を行った。
[2] 調査結果及び考察
(a) ミサゴの分布状況
現地調査の結果、生息個体数は6~10羽で、最も多く観察されたのは1月であった。
分布状況についてみると、ミサゴは調査範囲内の河川を広く利用しており、特に汽水域から河口域にかけて多く観察された。
採餌行動は河口から海上部で多くみられ、摂餌がみられた場所の多くは水面が静穏な場所であった。
(b) 餌生物の変化
現地調査の結果、ミサゴはボラ、コイ、フナを主に捕食していた。
以上の結果により確認された、ミサゴの生息状況の概要を表-2.16に示す。
| 項 目 | 調 査 結 果 |
| 分布状況 | 河口~20kmに広く分布。 |
| 観察頻度の高い範囲 | 汽水域から河口域にかけて多く観察された。 |
| 個体数 | 調査期間中に6~10個体を確認。 |
| 雌雄 | 雌雄比は調査期間を通じてほぼ1:1であった。 |
| 年齢 | |
| 採餌・摂餌行動 | 採餌行動は河口から海上部で多くみられ、摂餌がみられた場所の多くは水面が静穏な場所であった。 |
| 餌生物 | 主にボラ、コイ、フナを捕食。 |
[3] 予測結果
予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果は表-2.17のとおりである。
・狩り場の変化によるミサゴへの影響
・餌生物の変化によるミサゴへの影響
・調査範囲を狩り場として利用するミサゴ個体群への影響
| 項 目 | 予 測 結 果 | |
| ◎狩り場の変化によるミサゴへの影響 | 影響要因 | ・狩り場の変化 |
| 想定される影響 | ・ミサゴの狩り場に堰や護岸が設置されることにより、ミサゴの行動圏や摂餌行動に影響が及ぶ。 | |
| 予測内容 | ・ミサゴの行動圏や探餌・摂餌行動については、現地調査地域における分布状況と行動パターンから主要な利用環境を把握し、環境の変化からミサゴへの影響を予測した。 | |
| 予測結果 | ・ミサゴは水面の静穏な河口周辺(河口~2km付近まで)を主な採餌場所としており、河口から5km地点に設置される堰の影響は大きくないと考えられる。また、湛水区域の出現や堰下流域など、水面の静穏な範囲が増加することが考えられることからも、堰の存在による狩り場の変化の影響はミサゴにとって大きなマイナスにはならないと予測された。 | |
| ◎餌生物の変化によるミサゴへの影響 | 影響要因 | ・餌生物の変化 |
| 想定される影響 | ・堰の存在による上・下流の分断、湛水区域の存在や河床勾配の変化によって、水質の変化、地形・水深変化、底質変化が考えられることから、ミサゴの餌生物が変化すると想定される。 | |
| 予測内容 | ・ミサゴの餌生物の変化については、現地調査地域でミサゴが捕獲した餌の調査、それら餌生物の分布状況を調査し、予測される河川環境の変化によって想定される餌生物への影響から、ミサゴへの影響を予測した。 | |
| 予測結果 | ・ミサゴの主要餌生物であるボラ、コイ、フナについて、分布状況の変化について予測を行った結果、ボラは堰下に滞留すること、またコイ及びフナは湛水域で増加する可能性が示された。この結果から、堰の存在による影響は、ミサゴの餌場としては大きなマイナスにはならないと予測された。 | |
| ◎調査範囲 を狩り場とし て利用する ミサゴ個体群へ の影響 | 予測結果 | ・狩り場や餌生物の変化がミサゴへ与える影響は大きくないものと予測されたこと、また、本種の主要な分布域は海岸であることからも、本地域のミサゴ個体群への影響は小さいと考えられる。 |
(2) ヤマトシジミ(典型性)
1) 予測する影響の内容
本事業がヤマトシジミに及ぼす影響フローは図-2.14に示すとおりである。
堰の存在によって、5kmから10kmの区間の汽水域は淡水域になることにより、ヤマトシジミの生息場所の大部分が消失する。これは直接的改変によるものである。また、堰より下流側に生息している個体に対しては、堰下流側の河床高が変化すれば、生息する水深面積が変化する可能性があり、これにより現存量が変化することが考えられる。また、取水により堰下流域は塩分が高くなることから、生息面積の変化につながる。さらに、ヤマトシジミは濾過食者であることから、餌料環境の変化を通したヤマトシジミへの影響も考えられる。
また、ヤマトシジミが持つ機能については、ヤマトシジミは上記のとおり水中の懸濁有機物(珪藻類や渦鞭毛藻類などの植物プランクトンやワムシ類などの小型動物プランクトン)を濾過して飼料とすることから、水質浄化機能が考えられる。
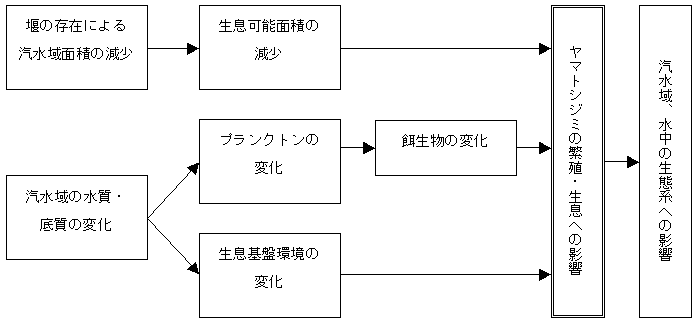
図-2.14 堰及び護岸(存在)が注目種(ヤマトシジミ)に及ぼす影響フロー
2) 調査・予測手法の検討
[1] 調査・予測手法検討の流れ
ヤマトシジミへの影響について、調査・予測の流れを図-2.15に示す。事業による影響は、生息面積の減少、生息場所の環境変化などによる生息・繁殖場所の減少などがあげられる。このような影響を把握するために、生息状況調査と生息場所の環境分析を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の変化と、個体群の変化の可能性を検討し、事業による影響を予測する。また、ヤマトシジミへの影響予測結果を基に、生態系への影響について検討する。
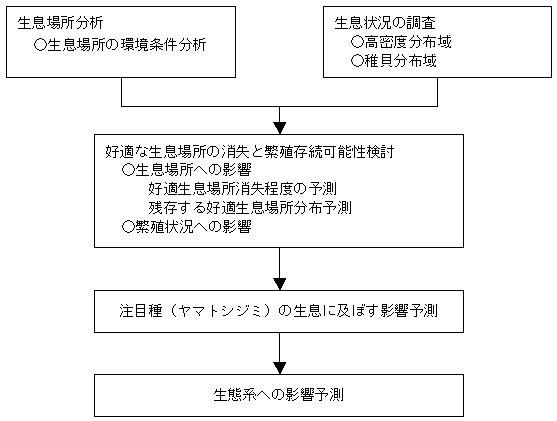
図-2.15 ヤマトシジミの調査・予測の流れ
[2] 予測手法検討
堰や護岸の存在によるヤマトシジミの影響予測手法の内容を表-2.18に示す。
ここでは、堰や護岸の存在による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を設定した。
| 影響 要因 |
想定される影響と予測手法 | ||
| 湛水による生息空間の消滅 | 湛水による生息空間の消滅 | ・堰や護岸の存在によりヤマトシジミの生息場が消失するため、ヤマトシジミの生息(個体数)に影響が及ぶと考えられる。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・ヤマトシジミの個体群の変化については、現地調査地域の生息個体と汽水から淡水に変化する予定地の生息個体の関係から減少率を予測する。 | |
| 定性的予測 | ・ヤマトシジミの個体群の変化による生態系への影響については、ヤマトシジミの個体群の減少率を基に、主に食物連鎖の関係から予測する。 | ||
| 下流部の生息環境の変化 | 想定される影響 | ・湛水区域の存在や河床勾配の変化によって、塩分を含めた水質の変化、地形・水深変化、底質変化が考えられることから、ヤマトシジミの生息環境が変化すると想定される。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・ヤマトシジミの個体群の変化については、既往資料等による生活史の主要な段階における生息状況、ヤマトシジミの生理・生態特性等と数値モデル等による生息環境に関する項目の予測結果から、生息環境の変化に伴うヤマトシジミの個体群への影響を予測する。ヤマトシジミへの影響予測は主に水質、底質、地形変化とヤマトシジミの生理特性の関係を重視する。 | |
| 定性的予測 | ・ヤマトシジミの個体群の変化による生態系の変化については、主に食物連鎖の関係から予測する。 | ||
[3] 現地調査手法の検討
予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表-2.19に示す。
ヤマトシジミは、幼生期の一時期浮遊生活とするが、これ以外は大きな移動を行わずに底生生活を送るので、調査項目としては、底生生活期の分布状況と生息環境を把握する。また、本種は漁獲や放流も行われているので、漁業実態についても整理する。
| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 | ||
| ヤマトシジミの分布状況 | ・ヤマトシジミの個体数と大きさ、重量 | 調査項目の設定根拠 | ・堰による淡水化によりヤマトシジミの生息場が一部消失するため、分布状況と個体数等を調査し、生息場の消失によるヤマトシジミの個体数の減少率を把握する。 |
| 調査地点 | ・汽水域全域に調査地点を設定する。鉛直的には干潟上部から最深部までを網羅するように配置する。 | ||
| 調査時期 | ・高水温期に1回調査する。ただし、2ヶ年の調査を行う。 | ||
| 調査方法 | ・採泥器、枠取り法(深さ10cm程度)により定量的に採取し、測定を行う。 | ||
| 生息環境 | ・水深 ・水温 ・塩分 ・水質 |
調査項目の設定根拠 | ・堰や護岸の建設(存在)によりヤマトシジミの生息域が減少し、また、ヤマトシジミの生息場である干潟周辺は河床勾配の変化、これに伴う底質の変化や、湛水区域の存在に伴う水質の変化が生じると想定されることから、ヤマトシジミの生息環境を把握する。 |
| 調査地点 | ・ヤマトシジミの分布状況の調査と同様とする(水深、底質条件)。 ・水質については、水質等の数値予測のために別途調査地点を数地点設置する(水質調査地点で補完する)。 |
||
| 調査時期 | ・ヤマトシジミの分布状況の調査と同様とする。 | ||
| 調査方法 | ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成、有機物含有量、硫化物等、水質の調査項目としては、COD、DO、SS、クロロフィルa、塩分等とする。 ・計器によるDO、塩分等の連続観測を行う。 |
||
| 漁獲・放流、漁獲量の実態 | ・漁獲量 ・放流場所と放流量 ・漁場分布等 |
調査項目の設定根拠 | ・汽水域の干潟は、春季から初夏にかけて潮干狩り場として利用されており、また、漁業活動も盛んである。そのため、放流が行われており、現地調査に際しては、放流状況について把握する。 |
| 調査地点 | ・現地調査地域全域とする。 | ||
| 調査方法 | ・漁業協同組合資料、聞き取り、標本船、抜き取り調査等により把握する。 | ||
3) 調査結果・予測結果の概要
[1] 現地調査内容
調査は8月と10月に実施した。
地点は河口~10kmまでの範囲に20測線、各5地点、計100地点を設定し、生息環境として水温、水深、水質(直上水の塩分、DO、間隙水の塩分)、底質(強熱減量、全硫化物、酸化還元電位、粒度組成)の調査を実施し、分布調査として、ヤマトシジミ生息密度、殻付き湿重量、殻長組成を調査した。また、漁業協同組合に聞き取りを実施し、シジミ放流実態、漁獲実態、主要漁場を調査した。
[2] 調査結果及び考察
(a) ヤマトシジミの放流と漁場
聞きとり調査によると、シジミの放流は河口から10km地点から下流にむけおよそ5kmの範囲である。
主要なシジミ漁場は、河口から7km、5kmの左岸付近および2kmの右岸付近の3水域であり、分布調査の結果とおおむね対応していた。これら主要漁場の環境条件についてみると、いずれも浅い感潮域で、底質も有機物量が少ない砂質底であった。
(b) ヤマトシジミの分布状況
分布調査によると、ヤマトシジミは10km地点から河口部付近までの広い範囲に生息していることが明らかになった。高密度生息域は、汽水域の中の比較的上流側に多く、7km付近左岸、2kmの右岸などであった。多く生息している場所は、地形的に土砂が堆積しやすく、干潟的環境が形成されているところであった。また、 稚貝と成貝の分布場所をみると流程方向では両者に大きな違いはみられなかったが、稚貝はヨシ原のある干潟に多く、成貝はその前面の干潟よりやや深い所に多かった。
(c) ヤマトシジミと環境との関連
調査結果から、ヤマトシジミの生息密度と環境条件との関係は、以下のように想定された。
・生息する地盤高は干潟下部から浅所に限られ、ほぼA.P.-1mより浅い所に多い。
・硫化物は0.2mg/g以下で、酸化状態にある所に多い。
・泥分が少なく砂質から砂礫質の所に多い。
以上の結果により確認された、ヤマトシジミの生息状況の概要を表-2.20に示す。
| 項 目 | 調 査 結 果 | |
| 放流場所 | 10km地点から下流側4kmの区間 | |
| 主要な漁場 | 河口から7km、5kmの左岸付近および2kmの右岸付近の3水域 | |
| 流程分布 | 河口付近から10km地点までの広い範囲に分布する。 | |
| 生息密度の高い分布域 | 7km付近左岸、2kmの右岸など、干潟的環境となっている場所である。また、これらの場所は主要漁場とほぼ一致していた。 | |
| 環 境 条 件 と 生 息 密 度 |
地盤高 | 潮間帯下部~浅場(A.P.-3m~+1m)で生息密度が高かった。 |
| 底質粒度 | 砂質および砂礫質に多い傾向がみられたが、泥分が多い所にも生息密度が高いことがあった。 | |
| 強熱減量 | 1%程度の所に多い傾向がみられた。 | |
| 硫化物 | 0.2mg/g以下の所に多い傾向がみられた。 | |
| TOC | 8mg/g以下の所に多い傾向がみられた。 | |
[3] 予測結果
予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果は表-2.21のとおりである。
・ヤマトシジミの個体群の変化
・ヤマトシジミの個体群の変化による生態系への影響
堰の存在により想定されるヤマトシジミ個体群の変化の主な要因は、堰上流部の湛水化による生息場の消失と堰下流部の生息環境の変化である。
堰の存在による生息場の消失によって、移動性がほとんどないヤマトシジミの生息に及ぼす影響は大きいと考えられることから、消失区域(汽水域が淡水になる区域)のヤマトシジミの個体数が、汽水域全体に生息している総個体数と比較してどのくらいの割合を占めるのかに焦点を絞り、ヤマトシジミの個体群の変化として定量的に予測した。
また、堰や低水護岸の存在により、ヤマトシジミの生息環境の流況、水質及び底質等が変化する可能性がある。ヤマトシジミの生息環境が変化する場合、生息しているヤマトシジミに対する影響は大きいと考えられることから、ヤマトシジミの生息環境である流況、水質及び底質の変化が現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化はヤマトシジミの生理的・生態的特性を勘案してヤマトシジミの生息にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、ヤマトシジミの個体群の変化として定性的に予測した。
ヤマトシジミの個体群の変化による生態系への影響は、上記で示したヤマトシジミの個体群の変化の予測結果を基に、ヤマトシジミの個体数の変化が生態系の食物連鎖の中でどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、生態系への影響として定性的に予測した。
| 項 目 | 予 測 結 果 | ||
| ◎ヤマトシジミの個体群の変化 | 直接的な変化 | 影響要因 | ・生息空間の消滅 |
| 想定される影響 | ・堰の存在による上流側の淡水化や地形の改変によるヤマトシジミの生息場の消失 | ||
| 予測内容 | ・調査地域内の生息個体数と消失区域内の生息個体数の関係から減少率を予測する(定量的予測)。 ・調査地域内に生息しているヤマトシジミの生息個体数は、詳細類型区分ごとに個体数を平均し、その平均値に各類型区分の面積を乗ずることにより求めた。 |
||
| 予測結果 | ・堰の存在や地形の改変によりⅠ-2、Ⅰ-3類型のヤマトシジミの生息場は約○○ha消失することから、その消失面積に生息するヤマトシジミの現存個体数○○×107個体程度は影響を受ける(減少する)と考えられる。 ・調査地域内に生息しているヤマトシジミの全現存個体数は○○×107個体程度であることから、堰の存在による減少率は約○%となる。そのうちⅠ-2、Ⅰ-3類型内における減少率は、現存個体数が○○×107個体程度であることから、約○○%となる。 |
||
| 間接的な変化 | 影響要因 | ・堰や護岸の存在による間接的な生息空間の変化 | |
| 想定される影響 | ・堰や護岸の存在によるヤマトシジミの生息環境の変化 | ||
| 予測内容 | ・ヤマトシジミの生息状況、生理的・生態的特性等と生息環境(水質、底質等)の予測結果との関係から予測する(定性的予測)。 | ||
| 予測結果 | ・堰下の水質に関しては、COD、SS及び栄養塩はともに堰の影響により現状と比較してやや高く(CODの増加量 0.1mg/l、SSの増加量 0.5mg/l、T-Nの増加量 0.50mg/l、T-Pの増加量 0.005mg/l)なる水域が生じる。 ・平水時に湛水区域で沈降した底泥が出水時に流出し、堰下流域で堆積することにより、河口付近まで底質の変化が予測される。 ・ヤマトシジミの生理的・生態的特性を考慮すると、堰下流域における底質の変化に伴いヤマトシジミの生息(個体群)に影響が生ずる可能性があると考えられる。 |
||
| ◎ヤマトシジミの個体群の変化による生態系への影響 | 影響要因 | ・生息空間の消滅・堰の存在 | |
| 想定される影響 | ・堰の存在によるヤマトシジミの個体群の変化に伴う生態系への影響 | ||
| 予測内容 | ・ヤマトシジミの個体群の変化による生態系への影響について主に食物連鎖の関係から予測する(定性的予測)。 | ||
| 予測結果 | ・ヤマトシジミの個体群の変化の予測結果から、堰の存在によりヤマトシジミの生息場が消失すること及び堰下流側における底質の変化に伴い生息に影響が生ずる可能性もあることから、その個体群は減少すると予測される。 ・ヤマトシジミと同様な環境を生息場所とするゴカイ類、小型甲殻類等の底生動物にも同様な影響が生じ、その結果、ヤマトシジミやゴカイ類を含む底生動物を餌とするシギ・チドリ類や潜水ガモ類等の鳥類の餌資源量が減少することにより、鳥類の生息状況に影響を及ぼす可能性がある。 ・ヤマトシジミの採餌(濾過)による水質浄化機能、ゴカイの採餌(有機物摂取)による底質浄化機能に影響を及ぼす可能性がある。 |
||
(1) アユ(典型性)
典型性の代表種であるアユについては、連続性の分断における影響をみるため、本ケーススタディでは降下仔アユに的を絞り、調査および影響予測を行うこととした。
1) 予測する影響の内容
本事業が降下仔アユに及ぼす影響フローは図-2.16に示すとおりである。
5km地点に堰を建設することによって、堰の上流側には湛水域が出現し、また河川は上流と下流に分断されることになり、河川水の流下時間が延びることが想定される。孵化直後の仔アユは抗流性が極めて小さく、その降下時間は河川における水の流下時間と大きく変わらないと考えられることから、堰の存在によって仔アユの降下時間が延長する可能性が考えられる。
また、堰からの取水によって、その取水中に仔アユが迷入し、降下する仔アユの現存量が変化することも考えられる。
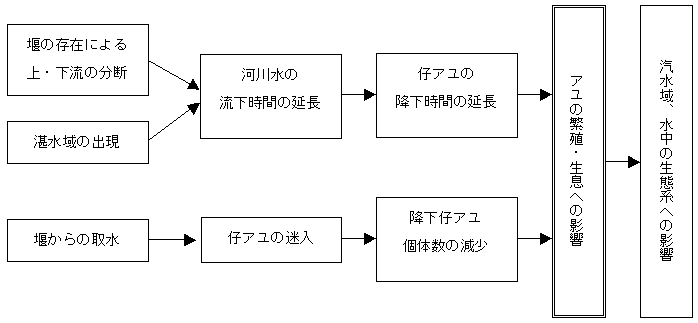
図-2.16 堰及び護岸(存在)が注目種(降下仔アユ)に及ぼす影響フロー
2) 調査・予測手法の検討
[1] 調査・予測手法検討の流れ
降下仔アユへの影響について、調査・予測の流れを図-2.17に示す。事業による影響は、河川の分断、湛水区域の出現などによる河川水の流下時間の変化に伴う仔アユ降下時間の変化及び堰からの取水による仔アユの迷入があげられる。流下時間の変化についての影響を把握するために、仔アユの分布状況および降下時間の調査を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、河川水の流下時間の変化を推定し、それに伴う仔アユへの影響について検討、予測を行う。また、取水による影響ついては、河川流量と計画取水量を比較し、取水中へ迷入する仔アユの量を予測する。これらの仔アユへの影響予測結果を基に、生態系への影響についても検討する。
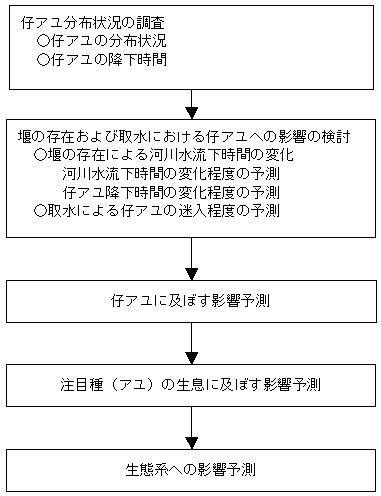
図-2.17 仔アユの調査・予測の流れ
[2] 予測手法検討
堰の存在による降下仔アユの影響予測手法の内容を表-2.22に示す。
ここでは、堰の設置および取水による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を設定した。
| 影響 要因 | 想定される影響と予測手法 | ||
| 堰の設置による河川水流下時間の変化 | 想定される影響 | ・河川の分断、湛水区域の出現などによって河川水の流下時間が変化し、それに伴って仔アユの降下に影響が及ぶと考えられる。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・河川流量および湛水容量等から河川水流下時間を試算し、仔アユの降下時間の変化量を推定する。また、現地調査地域における仔アユの分布状況、孵化後の発生状況から、降下時間の変化が仔アユに及ぼす影響を予測する。 | |
| 定性的予測 | ・仔アユの降下量の変化によるアユの個体群および生態系への影響については、定量的予測の結果を基に予測する。 | ||
| 堰からの取水 | 想定される影響 | ・堰からの取水によって、取水中に仔アユが迷入し、降下仔アユの個体数が減少することが考えられる。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・取水中に迷入する仔アユの個体数については、河川流量と取水量の比較から予測する。 | |
| 定性的予測 | ・仔アユの降下量の変化によるアユの個体群および生態系への影響については、定量的予測の結果を基に予測する。 | ||
[3] 現地調査手法の検討
予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表-2.23に示す。
なお、調査期間中の流量データについては、連続観測地点の結果を用いて整理する。
| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 | ||
| 仔アユの分布状況 | ・個体数 ・全長 ・日齢 ・卵黄長 ・現地観測 (水温、流速、水深) |
調査項目の設定根拠 | ・堰の存在による河川水の流下時間の変化によって、仔アユの降下に影響が及ぶと考えられるため、仔アユの分布および降下状況を調査し、降下時間の変化が仔アユに及ぼす影響を把握する。 |
| 調査地点 | ・当該河川におけるアユの産卵場所の最下流部、汽水域の最上流部、堰の設置地点にそれぞれ調査地点を設定する。 | ||
| 調査時期 | ・当該河川におけるアユの産卵盛期である10月下旬~11月にかけて週1回調査する。採集は仔アユの降下が多いとされる日没から日出までの間に2時間ピッチで行う。 | ||
| 調査方法 | ・船外機による直線曳網(MTDネット使用、船速0.5m/sで10分間曳網)。 | ||
3) 調査結果・予測結果の概要
[1] 現地調査内容
調査は10月下旬~11月の期間に週1回のペースで合計6回実施した。
調査地点は、既存調査でアユの産卵場とされている範囲の最下流部(河口から18kmの地点)、汽水域の最上流部(河口から10km)、堰の設置予定場所(河口から5km)に測線を設置し、測線毎に右岸、中央(流心部)、左岸の3地点、計15地点を設定し、上下2層で仔アユの採集および現地観測を行った。採集した仔アユは個体数、全長、日齢、卵黄長の分析を行った。
また、河口から10kmにある流量連続観測地点にいて、調査期間中の河川流量の整理を行った。
[2] 調査結果及び考察
(a) 仔アユの分布状況
調査結果から、調査地域の10月下旬~11月おける仔アユの分布状況は、以下のように想定された。
・孵化した仔アユが汽水域に到達するまでの日数は、流量50m3/秒で孵化後1.5~2.0日、流量20m3/秒で孵化後約3日(年平均日流量は60m3/秒)である。
・仔アユの卵黄吸収は孵化から約6日で終了する。
・降下仔アユの出現量は時期的にみると11月中旬に多く、時間帯では20~0時にかけて多い。
・河川横断方向の分布についてみると、仔アユは流速の緩やかなところに多い。
以上の結果により確認された、降下仔アユの分布状況の概要を表-2.24に示す。
| 項 目 | 調 査 結 果 |
| 仔アユの密度分布 | ・密度は11月中旬の調査で最も高かった。 ・出現量の多い時間帯は20時~0時の期間であった。 ・河川横断方向の分布は、流速の緩い地点で多い傾向がみられた。 |
| 日齢組成 | ・流量50m3/秒では、産卵場最下流部で0~1日齢、汽水域上流部で1~2日齢、堰の設置地点では2~3日齢のモードがみられた。 |
| 卵黄吸収 | ・仔アユの日齢および卵黄長の調査から、アユの卵黄吸収は約6日で終了すると考えられた。 |
(b) 堰設置時における河川水の流下時間の試算
設置される堰の総貯水容量は5,800千m3であり、取水量は最大で20m3/秒である。堰からの流量を10.0m3/秒、取水量を15.0m3/秒と仮定すると、湛水区間の出現によって河川水の流下時間は64.4時間、日数にして2.7日延長すると試算された。
[3] 予測結果
予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果は表-2.25のとおりである。
・降下仔アユ個体数の変化
・降下仔アユ個体数の変化によるアユ個体群および生態系への影響
| 項 目 | 予 測 結 果 | |
| ◎降下仔アユ個体数の変化 | 影響要因 | ・堰の存在および堰からの取水 |
| 想定される影響 | ・河川の分断、湛水区域の出現などによって河川水の流下時間が変化し、仔アユの降下に影響する。・堰からの取水による仔アユの迷入によって、降下仔アユの個体数が変化する。 | |
| 予測内容 | ・河川流量および湛水容量等から河川水流下時間を試算し、仔アユの降下時間の変化量を推定する。また、現地調査地域における仔アユの分布状況、孵化後の発生状況から、降下時間の変化が仔アユに及ぼす影響を予測する(定量的予測)。・取水中に迷入する仔アユの個体数を河川流量と取水量の比較から予測する(定量的予測)。 | |
| 予測結果 | ・堰設置後、仔アユが汽水域に到達するまでの日数は、流量50m3/秒では孵化後約4~5日、流量20m3/秒では孵化後約6日と予測された。流量が20m3/秒を下回ると、仔アユは卵黄吸収前に汽水域まで到達できないと考えられる。・堰からの流量を10.0m3/秒、取水量を15.0m3/秒と仮定すると、堰設置後、仔アユの降下量は全体の40%程度に減少すると考えられる。 | |
| ◎降下仔アユ個体数の変化によるアユ個体群および生態系への影響 | 影響要因 | ・堰の存在および堰からの取水 |
| 想定される影響 | ・降下仔アユの個体数が変化することに伴い、アユ個体群および生態系に影響が及ぶ。 | |
| 予測内容 | ・仔アユの降下量の変化によるアユの個体群および生態系への影響については、定量的予測の結果を基に予測する(定性的予測)。 | |
| 予測結果 | ・降下仔アユの個体数が減少すると予測されたことから、堰の存在および堰からの取水によって、アユ個体群も減少すると予測される。・アユと同様に河川を降下する生物にも同様な影響が生じ、その結果、河川の生態系にも影響が出ると考えられる。 | |
(4) トビハゼ(特殊性)
1) 予測する影響の内容
本事業がトビハゼに及ぼす影響フローは図-2.18に示すとおりである。
トビハゼの生息する泥干潟は、そのほとんどが堰を設置する直接改変区域にあたっており、堰の設置によってトビハゼの生息域の大部分が消失する。また、直接改変区域外の干潟に生息している個体群についても、堰の設置によって生息基盤環境が変化する可能性があることから、現存量が変化することが考えられる。
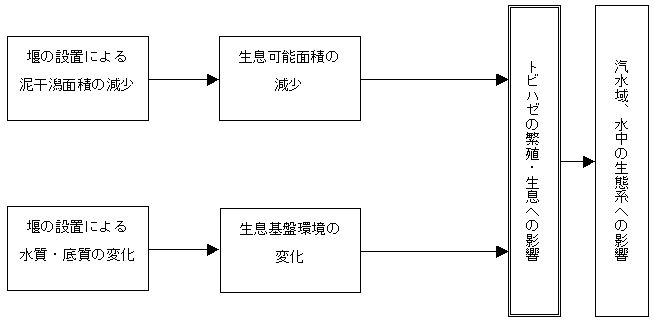
図-2.18 堰及び護岸(存在)が注目種(トビハゼ)に及ぼす影響フロー
2) 調査・予測手法の検討
[1] 調査・予測手法検討の流れ
トビハゼへの影響について、調査・予測の流れを図-2.19に示す。事業による影響は、生息面積の減少、生息場所の環境変化などによる生息・繁殖場所の減少などがあげられる。このような影響を把握するために、生息状況調査と生息場所の環境分析を行う。そして、これらの調査結果と事業計画との関係から、好適な生息場所の変化と、繁殖の存続の可能性を検討し、事業による影響を予測する。また、トビハゼへの影響予測結果を基に、生態系への影響について検討する。
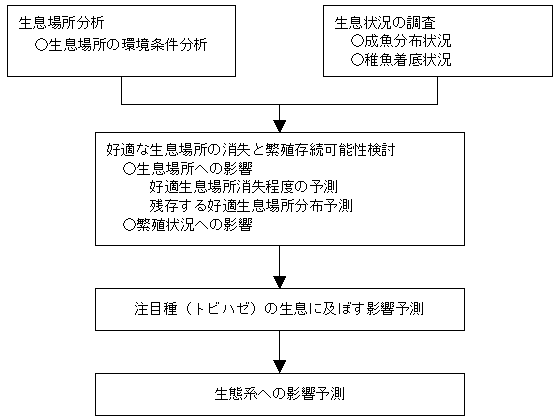
図-2.19 トビハゼの調査・予測の流れ
[2] 予測手法検討
堰や護岸の存在によるトビハゼの影響予測手法の内容を表-2.26に示す。
ここでは、堰や護岸の存在による影響要因と想定される影響及び予測項目を考慮し、予測手法を設定した。
| 影響 要因 | 想定される影響と予測手法 | ||
| 堰の設置による生息空間の消滅 | 想定される影響 | ・堰の設置によりトビハゼの生息場が消失するため、トビハゼの生息(個体数)に影響が及ぶと考えられる。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・トビハゼの個体群の変化については、現地調査地域の分布状況と消滅する泥干潟面積の関係から減少率を予測する。 | |
| 定性的予測 | ・トビハゼの個体群の変化による生態系への影響については、トビハゼの個体群の減少率を基に、主に食物連鎖の関係から予測する。 | ||
| 下流部の生息環境の変化 | 想定される影響 | ・堰の設置によって、水質の変化、地形・水深変化、底質変化が考えられることから、トビハゼの生息する泥干潟環境が変化すると想定される。 | |
| 予測手法 | 定量的予測 | ・トビハゼの個体群の変化については、既往資料等による生活史の主要な段階における生息状況、トビハゼの生理・生態特性等と生息環境に関する項目の予測結果から、生息環境の変化に伴うトビハゼの個体群への影響を予測する。トビハゼの影響予測は主に地形変化、水質、底質とトビハゼの生理特性の関係を重視する。 | |
| 定性的予測 | ・トビハゼの個体群の変化による生態系の変化については、主に食物連鎖の関係から予測する。 | ||
[3] 現地調査手法の検討
予測手法の検討結果を基に、現地調査手法を検討した結果を表-2.27に示す。
トビハゼは、孵化後、仔魚期に浮遊生活をするが、これ以外は大きな移動を行わずに底生生活を送るので、調査項目としては、底生生活期の分布状況と生息環境を把握する。
| 調査項目 | 調査項目の設定根拠と調査内容 | ||
| トビハゼの分布状況 | ・トビハゼの個体数と大きさ、重量 | 調査項目の設定根拠 | ・堰による直接改変で、トビハゼの生息場が消失するため、分布状況と個体数等を調査し、生息場の消失によるトビハゼの個体数の減少率を把握する。 |
| 調査地点 | ・トビハゼの生育する泥干潟のある汽水域中流部から河口域に調査地点を設定する。 | ||
| 調査時期 | ・トビハゼの活動期である4~10月に3回調査する。 | ||
| 調査方法 | ・干潟を見通せる地点に調査員を配置し、トビハゼの確認位置、個体数、行動、雌雄、年齢、個体の特徴等を観察、記録する。 | ||
| 生息環境 | ・水深 ・水温 ・塩分 ・水質 |
調査項目の設定根拠 | ・堰の設置によりトビハゼの生息域が減少する。また、トビハゼの生息場である泥干潟は、堰の存在による流量・水質・底質の変化、湛水区域の存在に伴う様々な変化によって、底質環境が変化すると想定されるため、トビハゼの生息環境を把握する。 |
| 調査地点 | ・トビハゼの分布状況の調査と同様とする(地形測量、底質条件)。 | ||
| 調査時期 | ・トビハゼの分布状況の調査と同様とする。 | ||
| 調査方法 | ・採泥器、採水器により試料を採取し、分析する。 ・底質の調査項目としては、粒度組成、有機物含有量、硫化物等、水質の調査項目としては、COD、DO、SS、クロロフィルa、塩分等とする。 ・この他トビハゼの生息環境要因と考えられる項目を記録する。 |
||
3) 調査結果・予測結果の概要
[1] 現地調査内容
調査は5、8、10月に実施した。
河口~10kmまでの範囲の干潟を中心とした移行帯全域を踏査し、調査員2名によってトビハゼの目視観察を行った。分布を確認した干潟において、確認位置、個体数、行動パターン、雌雄の別、大きさを記録した。なお、観察には倍率20倍程度の望遠鏡を用いた。
生息環境調査としてはトビハゼの分布確認地点において、水温、地形測量、水質(直上水の塩分、DO、間隙水の塩分)、底質(強熱減量、全硫化物、酸化還元電位、粒度組成)の調査を実施した。
[1] 調査結果及び考察
(a) トビハゼの分布状況
分布調査によると、トビハゼは汽水域中流部(河口から5km地点)付近に存在する泥干潟に生息しており、当該河川では限られた範囲のみに生息していることが明らかになった。生息場所は、地形的に土砂が堆積しやすく、泥質の干潟的環境が形成されているところであった。
(b) トビハゼと環境との関連
調査結果から、トビハゼの生息密度と環境条件との関係は、以下のように想定された。
・生息する地盤高は干潟部に限られ、A.P.-1m以浅に分布。
・底質は泥分の多いところに生息。
・
以上の結果により確認された、トビハゼの生息状況の概要を表-2.28に示す。
| 項 目 | 調 査 結 果 | |
| 流程分布 | 汽水域中流部(河口から5km地点)付近に一部ある泥干潟に分布する。 | |
| 生息密度の高い分布域 | 泥質の干潟的環境となっている場所。 | |
| 環境条件と生息密度 | 地盤高 | 干潟域(A.P.-3m~-1m)にのみ生息。 |
| 底質粒度 | 泥分の多い所に生息。 | |
| 水質 | ||
| 干潟周辺の流況 | ||
[3] 予測結果
予測結果については、下記に示す項目について検討した。予測結果は表-2.29のとおりである。
・トビハゼの個体群の変化
・トビハゼの個体群の変化による生態系への影響
堰の存在により想定されるトビハゼ個体群の変化の主な要因は、堰設置の直接改変による生息場の消失及び堰の存在に伴う様々な変化による生息場や生息環境の変化である。
堰設置の直接改変による生息場の消失によって、泥干潟という限られた環境にのみ生息するトビハゼの生息に及ぼす影響は大きいと考えられる。このことから、消失区域のトビハゼの個体数が、当該河川全体に生息している総個体数と比較してどのくらいの割合を占めるのかに焦点を絞り、トビハゼの個体群の変化として定量的に予測した。
また、堰の存在により、直接改変区域外のトビハゼの生息環境についても、底質等が変化する可能性がある。トビハゼは前述したとおり泥干潟という限られた環境にのみ生息するため、その生息環境が変化した場合、トビハゼへの影響は大きいものと考えられる。そのため、トビハゼの生息環境である泥干潟の底質及び周辺の流況、水質等の変化が現状と比較してどのくらいの変化があるか、また、その変化がトビハゼの生息にどの程度影響を及ぼすかに焦点を絞り、トビハゼの個体群の変化として定性的に予測した。
トビハゼの個体群の変化による生態系への影響は、上記で示した個体群の変化の予測結果を基に、トビハゼの個体数の変化が特殊性の観点からみた生態系にどのような影響を及ぼすかに焦点を絞り、生態系への影響として定性的に予測した。
| 項 目 | 予 測 結 果 | ||
| ◎トビハゼの個体群の変化 | 直接的な変化 | 影響要因 | ・生息空間の消滅 |
| 想定される影響 | ・堰設置の直接改変による生息場の消失及び堰の存在に伴う様々な変化による生息場や生息環境の変化 | ||
| 予測内容 | ・調査地域内の生息個体数と消失区域内の生息個体数の関係から減少率を予測する(定量的予測)。 ・調査地域内に生息しているトビハゼの生息個体数は、分布調査におけるトビハゼの生息密度に泥干潟の面積を乗ずることにより求めた。 |
||
| 予測結果 | ・堰設置による直接改変によってトビハゼの生息場は約○○ha消失することから、その消失面積に生息するトビハゼの現存個体数○○×107個体程度は影響を受ける(減少する)と考えられる。 ・調査地域内に生息しているトビハゼの全現存個体数は○○×107個体程度であることから、堰の存在による減少率は約○%となる。 |
||
| 間接的な変化 | 影響要因 | ・堰の設置による生息空間の消滅及び堰の存在による生息空間の間接的な変化 | |
| 想定される影響 | ・堰の設置及び存在によるトビハゼの生息環境の変化 | ||
| 予測内容 | ・トビハゼの生息状況、生理的・生態的特性等と生息環境(底質、流況水質等)の予測結果との関係から予測する(定性的予測)。 | ||
| 予測結果 | ・底質の変化 ・流況の変化 ・トビハゼの生理的・生態的特性を考慮すると、生息場である泥干潟の環境条件の変化に伴いトビハゼの生息(個体群)に影響が生ずる可能性があると考えられる。 |
||
| ◎トビハゼの個体群の変化による生態系への影響 | 影響要因 | ・生息空間の消滅・堰の存在 | |
| 想定される影響 | ・生息空間の消滅及び堰の存在によるトビハゼの個体群の変化に伴う生態系への影響 | ||
| 予測内容 | ・トビハゼの個体群の変化による生態系への影響について主に食物連鎖の関係から予測する(定性的予測)。 | ||
| 予測結果 | ・トビハゼの個体群の変化の予測結果から、堰の設置及び存在によりトビハゼの生息場が消失すること及び堰下流側における流況、底質等の変化に伴い生息場に変化が生ずる可能性があることから、その個体群は減少すると予測される。 ・トビハゼと同様に泥干潟を生息場所とするゴカイ類、小型甲殻類等の底生動物にも同様な影響が生じ、その結果、トビハゼが生息する汽水域泥干潟の生態系に影響が出る。 ・調査地域に成立している生態系の中で、局所的に成立している汽水域泥干潟の生態系がほとんど消滅する可能性がある。 |
||