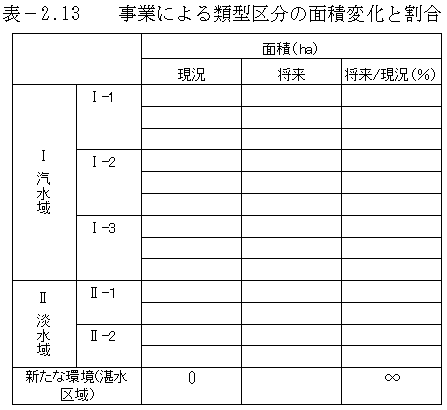平成13年度第1回陸水域分科会
資料3-1河口堰
2. ケーススタディ -河口堰を例として-
《環境影響評価の実施段階》
2-4 基盤環境と生物群集の関係の調査
(1) 物理化学的な環境要素(基盤環境)の変化
1) 調査・予測の流れ
予測のフローを図-2.9に示す。
各類型区分の変化について、改変区域と類型区分との重ね合わせにより、各類型ごとの変化面積、変化の内容と程度について把握した。
基盤環境と生物群集の関係や類似事例の引用により、基盤環境と生物群集への影響をおおよそ整理し、生態系の影響を概略把握した。
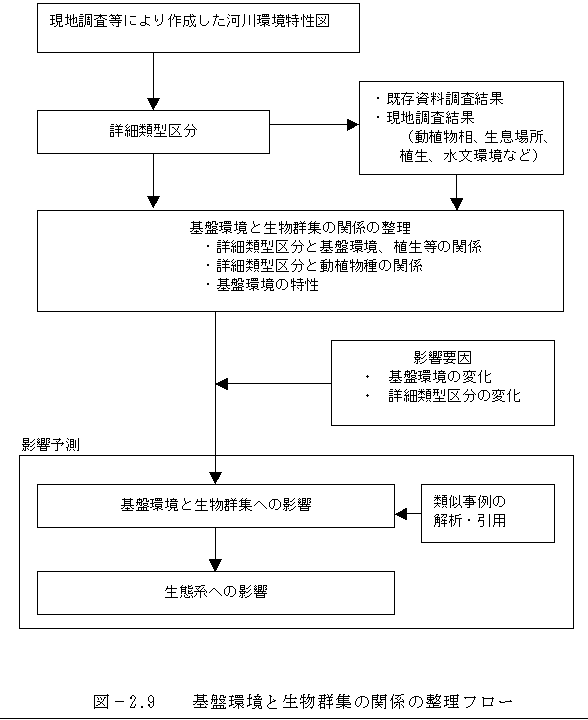
2) 詳細類型区分
[1] 類型区分の再検討
ここでは、環境影響評価の実施段階で把握した基盤環境や生物の特性を利用して、スコーピング段階で行った類型区分を再検討し、より詳細な類型区分を行った。
類型区分と基盤環境、生物の解析結果を整理し図-2.10(pdfファイル28k)に示す。
解析結果では、底生動物や魚類、水鳥など水環境との結びつきが強い生物では、縦断方向の区分が比較的明確であった。そこで、環境条件と生物群集のまとまりとして、縦断方向の分布で認識できるものを整理すると、基盤環境、水域生物および一部の陸域生物ともに、河口から10km地点の下流側と上流側、つまり汽水域と淡水域で大別できることが明らかとなった。調査地域は基本的にはこの2つの生態系から成立しているといえる。
河川の基盤環境や水生生物群集からさらにもう少し細かいスケールでまとまりを検討してみると、汽水域では、河口~4km(Ⅰ-1類型)、4~7km(Ⅰ-2類型)、7~10
km(Ⅰ-3類型)の3つ、淡水域では、10~14
km(Ⅱ-1類型)、14~20 km(Ⅱ-2類型)の2つに区分するのが妥当と考えられる。
この区分は、底質の粒径分布や水質の塩分条件など生息基盤条件ともほぼ整合するものであり、この5つの区分を類型区分とした。
[2] 各区分の生態系の特徴
上記の類型区分の結果を踏まえて、それぞれの類型区分の生態系の特徴を再整理した。ここでは各区分ごとに特徴的な生息種などについても整理した。
(a) 河口から4kmまで(類型区分Ⅰ-1)
河口に近く広大な干潟のある汽水域。
最も高塩分であり、川幅が広く外海からの波浪の影響も強くうけ、内湾的な環境である。
広大な砂干潟や一部泥干潟があり、大規模なヨシ原や塩沼地植生もみられる。河床勾配はほとんどない。
水中の底生動物としては、環形動物のヤマトスピオや軟体動物のホトトギスガイを優占種とした群集、干潟(移行帯)周辺の底生動物としてはヤマトスピオ、ニホンドロクダムシを優占とした群集が形成され沿岸海域に生息する種類が多くみられる。魚類でもヒメハゼ、スジハゼ、シロギスなどの海産魚が多くみられ、魚類の餌生物としてはエビ目などの甲殻類が多く利用されている。また、広大な干潟は多数のシギ・チドリ類が採餌場として利用している。河川でよくみられる生物としては、広大な生育面積を有するヨシ、広い干潟を利用するシギ・チドリ類、砂泥質干潟に生息するヤマトオサガニ、泥干潟の泥上で活動するトビハゼ、水面のカワウやカモ類の集団などがあげられる。
(b) 4kmから7kmまで(類型区分Ⅰ-2)
河川内の汽水域。
汽水域の3つの区分のうち中間に位置し、塩分は、類型区分Ⅰ-1よりは低いが河床勾配はほとんどない。
河川の蛇行の水裏側には砂干潟が形成され、礫干潟も点在する。ノリ類が生育するほか、干潟周辺にはコアマモ群落がみられる。
水中の底生動物はⅠ-1類型と近似し、ヤマトスピオが第1優占種であるが、汽水性の環形動物であるゴカイも多く生息する。干潟ではゴカイやカワザンショウガイなど汽水性の種類を優占種とする底生動物群集が形成され、魚類ではヒイラギ、サッパなど海域から侵入してくる種が多く出現する。魚類の餌生物としては、小型甲殻類や環形動物(ゴカイ類)が多く利用されている。河川でよく目につく種としては、ゴカイ、ヤマトシジミ、イトメなどがあげられ、ここは典型的な汽水域生態系が形成されている。陸域は畑や人工草地など人工的な環境の占める割合が高い。
(c) 7kmから10 kmまで(類型区分Ⅰ-3)
礫干潟がみられる汽水域上流側
汽水域の類型区分のうち最も上流側に当たり、塩分としては汽水域の類型の中で最も低い。類型区分Ⅰ-1、Ⅰ-2よりも河床勾配がやや大きいため、底質の粒径がやや大きく、干潟も礫干潟が多く分布する。
底生動物としては、イトメやゴカイが多く、低塩分を反映して、イトミミズ類も生息している。魚類としては、マハゼやビリンゴなどの汽水性魚も多いが、コイやモツゴなど淡水性の種類も混在している。
本類型区分には、汽水性種と淡水性種が混在し、汽水から淡水への移行帯的な環境である。
(d) 10kmから14kmまで(類型区分Ⅱ-1)
比較的流れの緩やかな流水域。
淡水域の類型区分のうち下流側に当たり、流れは緩やかで、広い河原や淵があり、河床には礫が多いが、局所的に泥の堆積もみられる。
底生動物としては、淡水の流れの緩やかな環境に多くみられるイトミミズ類、ユスリカ類が多く、魚類としてはコイ、フナ、モツゴ、タナゴ類などが生育する。鳥類ではサギ類や冬季にはカモ類などもみられる。植生ではツルヨシが多くなり、ヤナギ林も出現する。
(e) 14kmから20kmまで(類型区分Ⅱ-2)
淡水域の類型区分のうち上流の流水域。
河川は蛇行し、瀬や淵、河原があり、河床は粒径10mmをこえる礫が多い。大きな淵はない。
底生動物はカゲロウ・カワゲラ・トビケラ類などの流水性の水生昆虫類が多く、このほかガガンボ類なども多く生息する。魚類ではオイカワやウグイが多く、カマツカやシマドジョウなども生息し、中流域の魚類群集になっている。植生は低水敷ではヤナギ林やツルヨシ群落が発達し、河原もみられる。鳥類ではカモ類などの水鳥はほとんどみられなくなり、アオサギやコサギなどのサギ類が多くなる。
[3] 詳細類型区分
これまでの調査結果を踏まえ、詳細類型区分について検討した。
調査区域の最も上流側の類型区分の底生動物群集は、早瀬、平瀬、淵、ワンドという環境条件としてのまとまりで認識された。一方、下流側の汽水域の各類型では、底生動物群集のまとまりは底質の粒度という条件で認識することができた。そこで、汽水域の区分としては、底質の粒度をとりあげて詳細類型区分とした(表-2.9)。
さらに、汽水域では地盤高や植生の有無によっても、底生動物群集が異なることがわかった。また、底質の分布は地盤高との関連がみられた。
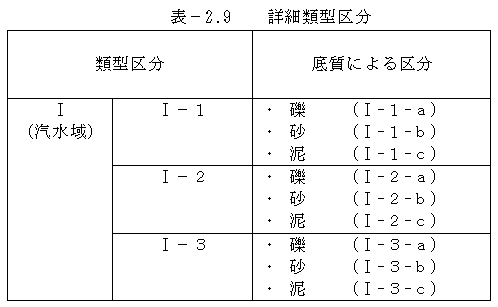
3) 基盤環境と生物群集の関係の整理
現地調査結果及び既存資料、ヒアリングによる情報も含め、調査結果に基づいて詳細類型区分と動植物種との対応関係を整理した(表-2.10PDFファイル7k)。その際、動物については、繁殖場所として利用しているかどうかについても整理して示した。
4) 影響要因、影響内容の検討
事業の実施に伴う環境影響の流れは表-2.11、環境の変化に伴う主要な生物への影響フローは図-2.11(pdfファイル13k)に示すとおりである。
存在・供用時の影響は、堰や護岸の存在による上・下流あるいは水中から陸上への連続性の分断、汽水域から淡水域への改変、砂洲の水没、流下仔魚の流下時間の延長などが考えられる。
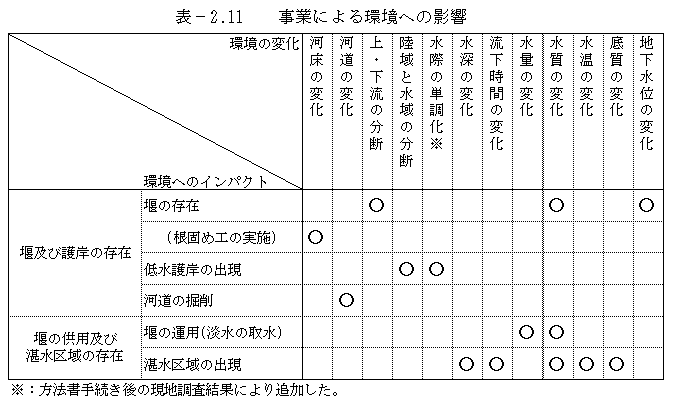
(2) 基盤環境と生物群集の関係の調査予測
1) 予測手法
各類型への影響については改変区域と詳細類型区分図との重ね合わせにより、類型ごとの改変面積、改変位置等から影響の内容・程度について把握した。
2) 基盤環境の予測結果
動植物の「生息場所」に対する事業の実施による影響を予測するという観点から、「生息場所」を成立させている物理化学的要素の変化について予測を行った。予測結果を以下に示す。
[1] 陸域と水域の分断
3.0~15.0 kmの区間において、低水護岸の設置に伴い陸域と水域の間の連続性が分断されると予測される。
[2] 河道の変化
(a) ワンド分布
低水護岸は、3.2~3.8kmの区間に分布する汽水域の小さな入り江を分断して設置されるため、この区間に分布するワンド○m2が消失すると予測される。
(b) 移行帯線の単調化
低水護岸の設置及び河道の掘削に伴い、3.0~15.0
kmの区間の移行帯線が現況の○mから○mに減少するため、移行帯線が単調化する。
[3] 上下流の分断
事業の実施に伴う堰本体の出現により、5.0km地点で河川が上・下流に分断される。
[4] 河床の変化
堰の設置に伴う床固めの実施により、堰地点において河床が○m2改変される。
[5] 流下時間の変化
堰は5.0km地点に設置され、約3.0kmの湛水区域が形成される。湛水区域の出現により、湛水区域上流端から堰までの水の流下時間が現況の○時間に対して○時間に長くなることが予測される。
[6] 河道内地形の変化
(a) 河道の掘削
3.0~9.0 kmの区間において河道水深2mまで掘削するため、掘削範囲の河道内地形が変化する。
(b) 湛水区域の出現
湛水区域の出現に伴う陸上部の水没と水深の増加により、河道内地形が変化する。
[7] 水質の変化
(a) 塩分の変化
事業の実施に伴い堰上流側の5.0~10.0km区間が汽水域から淡水域に変化する。
また、堰下流側では淡水の取水により塩分が上昇すると予測される。
(b) 水質の変化
湛水区域の出現による流下時間の変化に伴い水の滞留時間が変化することから、湛水区域における水質(BOD、クロロフィルa等)が変化すると考えられる。
予測の結果、湛水区域に流入してくる河川水のN、P濃度は堰運用後も変わらない濃度であることを前提とすると、水質は湛水区域では変化するが、その他の地点では事業実施後もほとんど変化しないと予測される。
湛水区域では、各水質項目とも値は増加するが、BOD75%値、DO年平均値は環境基準を満足する。水質の値が上昇する原因は滞留時間の増大が考えられる。
クロロフィルaについては、増加が予測されるものの現状を大きく逸脱するものではない。
なお、先に述べたとおり年平均値としてのDOは基準を満足するものの、湛水区域内の一部で夏季底層のDOが低下すると予測される。
[8] 底質の変化
堰は可動堰であるため出水時にはゲートを開放する。それに伴い湛水区域の底泥堆積物は下流にフラッシュアウトされると予測される。底泥の流出に伴い、現況における底質分布が変化することが考えられる。予測項目は、底生動物の生息状況と関係の大きいことが知られている粒度組成とした。なお、有機物量や硫化物等については、現況で粒度組成との相関がみられている。
(a) 湛水区域
5.0~8.0km区間は湛水区域となり流速が低下することから、粒度の細かい土砂が沈降することが考えられる。しかし、堰のゲート操作によって、沈降した土砂は堰下流側に流され、土砂の堆積は比較的小さいと考えられる。
(b) 堰下流域
堰下流域では、平水時に湛水区域で沈降した粒度の細かい底泥が出水時に出てくると考えられることから、底質が変化することが予測される。堰下流側の底質変化は、河口付近までと想定される。
以上のように、本事業による生息環境の変化としては、汽水域の減少、湛水区域の出現という基本的な変化以外にも、比較的多くの環境要因の変化が予測された。
生息・生育環境の変化から、どの影響内容がどの類型区分に現れるかをまとめて表-2.12に示す。
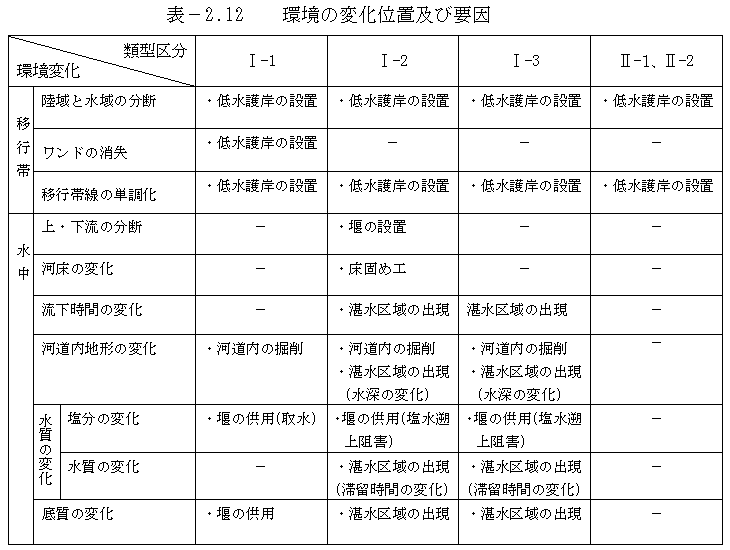
事業により変化する類型区分の面積を推定した。
この面積の推定に当たっては、以下を前提とした。
・ 類型の境界位置
・ 詳細類型区分については、横断面的な予測が必要である。
・ 汽水域と淡水域の境界は、5.0kmになるので、Ⅰ-3類型とⅡ-1類型の境界は10.0kmが5.0km地点になる。すなわち、5.0~10.0kmの範囲については、汽水域から淡水域(そのうち5.0~8.0kmの範囲は湛水区域)の環境になるとした。
・ 湛水区域の出現、湛水区域の環境条件。
・ 堰直下の低塩分域の環境条件。
・ 各詳細類型区分の環境の変化。
以上の結果、表-2.13に示すように、基本的には汽水域上流側であるⅠ-2、Ⅰ-3類型の面積の減少が大きく、堰の上流に現況にはない湛水区域という環境が新たにできることが予測された。