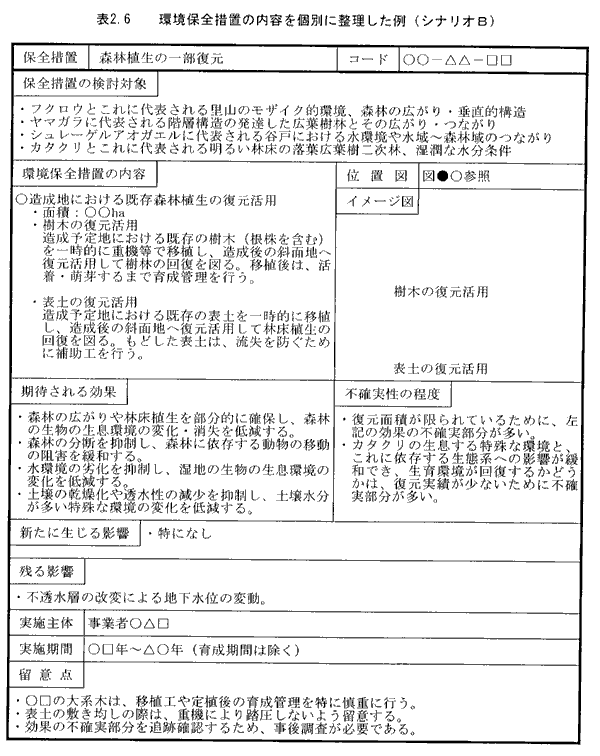平成13年度第1回陸域分科会
2.環境保全措置の検討
2.1 環境影響の整理から環境保全措置の検討に至る流れ
「調査・予測」では、造成工事や森林伐採などの影響要因による森林の消失・減少や水量の変化などの影響要素の変化を推定し、さらに、生物群集への影響を検討した。ここでは、注目種・群集を用いて、複雑な生態系への影響を把握する手法を例示した。注目種・群集としては、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどを選定した(表2.1参照)。 今回は、こういった環境影響の予測結果を整理したうえで、環境保全方針を設定し、さらに、保全方針にもとづく具体的な環境保全措置を検討した。 なお、本ケーススタディーでは、影響フローやマトリックス(図2.1、図2.2、表2.2、表2.3参照)、系統図、主題図等により内容を整理しながら検討を進めた。
表2.1 注目される生物種等の選定理由と生態系への影響予測
| 生態系の視点 と選定種 |
選定理由
|
生態系への影響予測
|
| 上位性 フクロウ | 行動圏が広く、森林を繁殖・休息の場、 狩り場として幅広く利用すると同時に、 草原や畑地も狩場として利用するため、 ランドスケープレベルでの植生改変、土地利用改変による影響を予測するのに適している。森林生態系の栄養段階の上位 に位置する種で、繁殖可能な場所が限定 されていること、狩りや休息のために高 樹齢で林内に空間がある高木林が必要なことから、森林の改変に敏感な種類である。里山に普通に生息する種で、調査は 比較的行いやすい。 | フクロウが影響を受けることで、捕食・被食 関係のある多くの種などに影響が及ぶ。また、 飛翔のための林内空間や繁殖のための大きな 樹洞などの好適な生息場所が縮小したり断片化することで、生息場所の質が低下し、事業 実施区域周辺の個体の存続に影響が及ぶ。林内空間を利用する他の森林性動物についても、森林が伐採されることで影響を受け、さ らに、森林性動物への影響は、これらの動物 が利用している植物や動物、競争関係にある動物へも影響をもたらし、地域の森林生態系 が影響を受ける可能性がある。 |
| 典型性 ヤマガラ | 繁殖のための小樹洞、採食のための昆虫類や木本の種子など、森林の多様な資源 を利用する森林性の種なので、里山の森 林生態系に典型的な種として、影響を把握するのに適している。また、森林が連続して存在することが必要なため、森林の断片化などの影響を受けやすく、森林の断片化による影響を把握するためにも適している。里山に普通に生息する鳥類で、個体数や採食行動の調査などの生態調査が比較的行いやすい。 | 落葉・常緑広葉樹林の階層構造や森林パッチの面積の変化などに強く影響を受ける森林性の生物種・群集に影響が及ぶ。森林の伐採等はヤマガラのみでなく、落葉・常緑広葉樹林に生活資源の多くを依存する他の生物種に対しても同様の影響を与える。また、森林伐採等による森林の小規模化・断片化や広大な裸地・草地の出現による都市型生物の侵入は捕食や営巣場所の占拠など、森林性鳥類の生息を圧迫する。 |
| 典型性 シュレーゲルアオガエル | 谷戸の水域と森林域とが連続した環境を必要とするため、森林や水田・湿地等の減少・消失及び、道路建設による水環境と森林環境の分断による影響を予測するのに適している。繁殖期には水域に依存し、非繁殖期には森林域への依存度が高いため、水域及び森林域が隣接していることが重要である。 | 水環境に一時依存する両生類や水生昆虫などの生物群集が影響を受ける。分断による影響は本種以外のカエル類のみならず、地表徘徊性の昆虫類などに広く影響を与える。地形等の改変によって谷戸の連結性が失われ、谷戸に依存する動物群の長期的な生息に影響が及 ぶ。 |
| 特殊性 カタクリ | 良好な生育には水分条件が重要であるため、谷戸における水環境の変化を予測するのに適している。分布南限付近にあたる事業対象地域において本種は高位台地 -落葉広葉樹林の類型の中でも特に、明 るい林床で、斜面下部の凹状地や沖積錘等の水分条件の豊かな立地にのみ生育している。このような特殊な環境の存在は本地域の種多様性を維持する上で重要であり、本種の保全を考えることは同様の立地に生育する多くの種の保全につなが る。 | 土壌水分が高く夏の地温が低いカタクリの生育地は一部消失する。直接的な生育地の消失をまぬがれる場所でも、谷戸の乾燥化が起こり生育環境が劣化する。森林の管理条件が変化すればアズマネザサ等が密生し、生育環境が劣化する。生育地の消失や生育環境の劣化は、本種と同様の立地に生育するイチリンソウなどの春植物の生育環境への影響も生じる。これらの春植物に影響が及ぶと、カタク リ等を密源植物として利用する訪花性昆虫類等にも影響が及ぶ。このような環境の変化はカタクリが生育する特殊な環境により維持される落葉広葉樹林の種多様性の低下を引き起 こす。 |
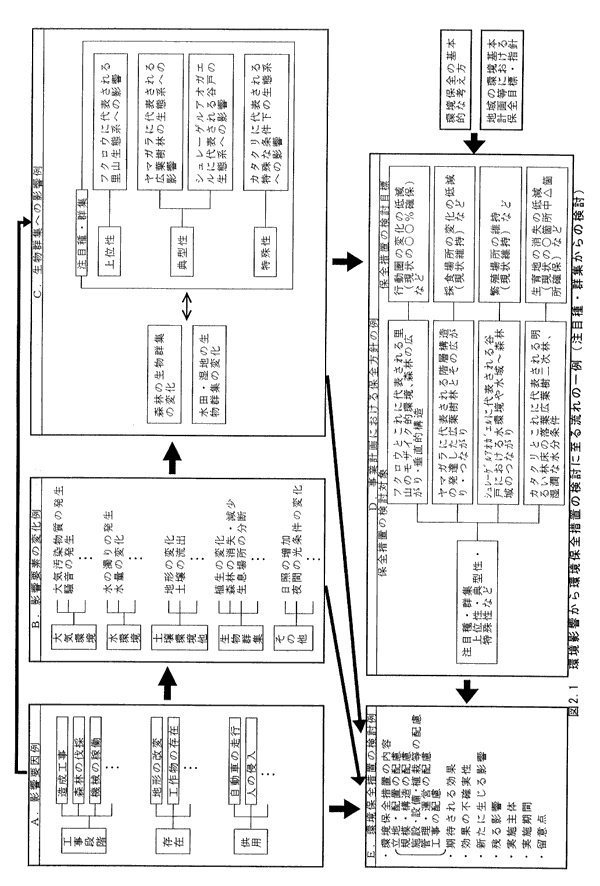
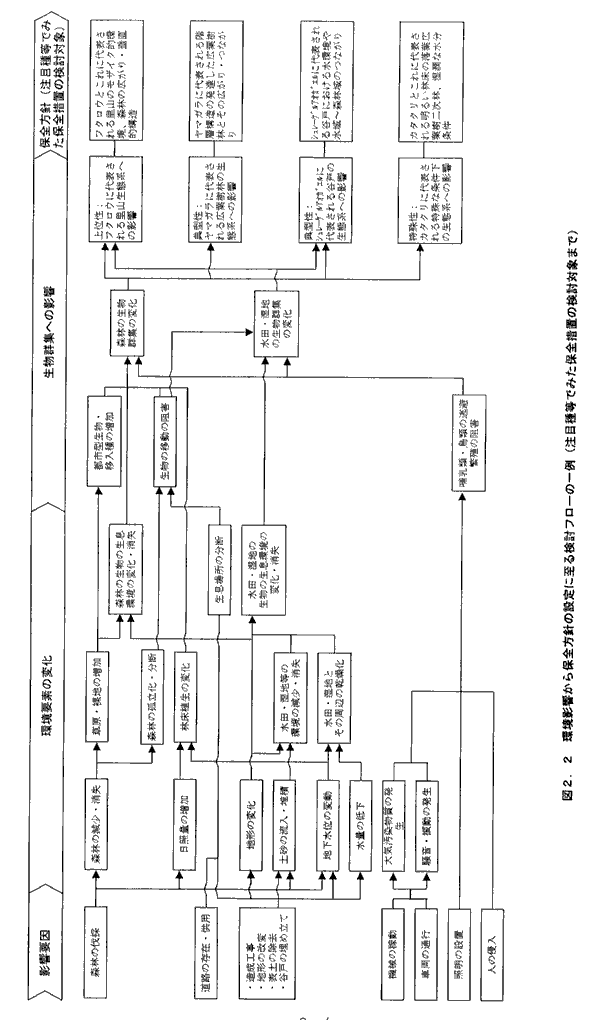
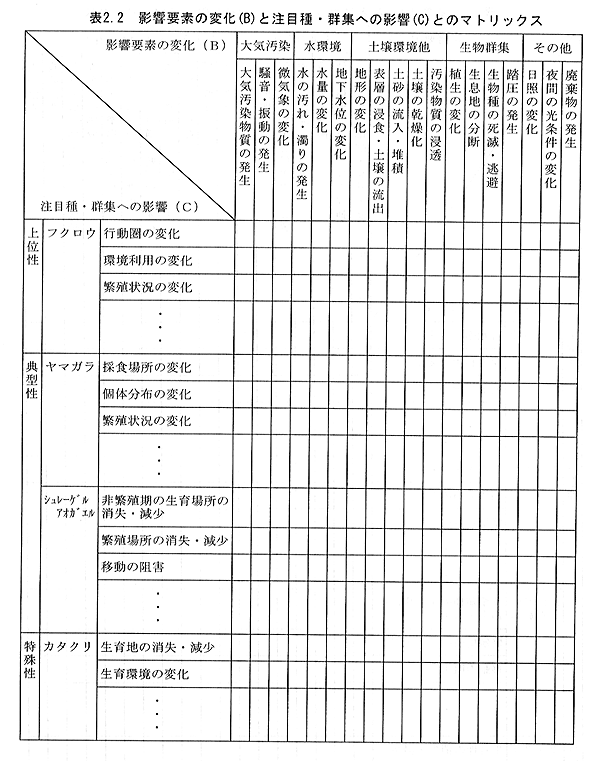
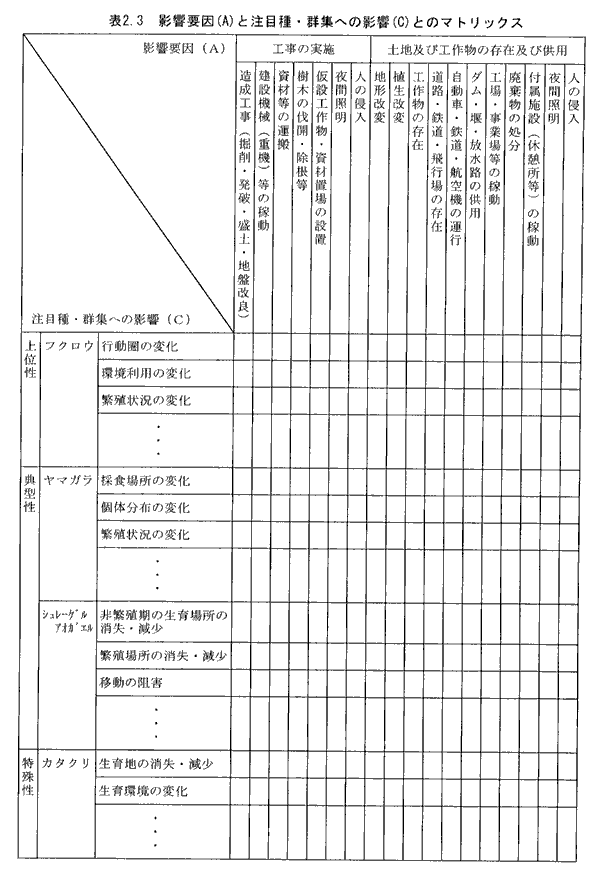
2.2 保全方針の検討
調査地域とその周辺は、平地~台地~丘陵地へとつながる谷戸の入り組んだ地形において、丘陵地のスギ・ヒノキ植林やクヌギ-コナラ群集、谷戸の水田・休耕田等が分布している。調査・予測では、フクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリなどの注目される生物種を選定し、これらの存在に代表される多様な里山の生態系が存在していることがわかった。
調査・予測で対象とした当初の事業計画1・2・3は、調査地域における里山の生態系に影響を与えることが予想された(表2.1、図2.5参照)。 事業計画1・2・3は、早期の基本計画段階にあたるため、今回は、失われつつある里山生態系への影響を回避・低減するために、調査地域における水源涵養域、地形、植生などの類型や注目種等の生育生息状況などを勘案した初期段階における環境保全措置の検討(基本計画の修正)から試みた。
まず、各注目種等の存在により代表される生態系への影響予測にもとづき、図2.3に示すような保全方針(保全措置の検討対象・検討目標)を設定した。
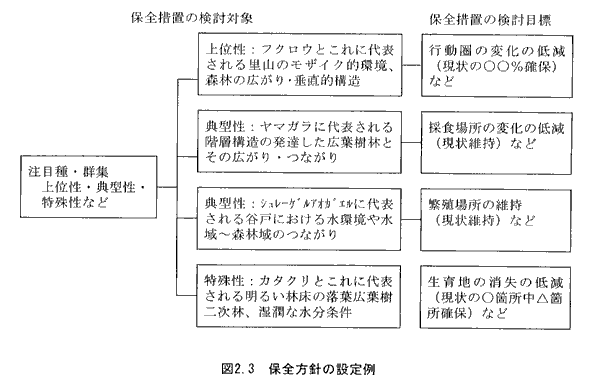
次に、保全方針にもとづく事業フレームを検討した。事業計画1・2・3のうち、調査地域における森林や谷戸などの生態系に対し最も影響の少ない計画として、事業計画3を選定した(詳細な比較評価は割愛する)。
さらに、事業計画に大きく関わる環境保全に向けての基本的な考え方として、事業計画3をより生態系に配慮する形で修正した、シナリオAとシナリオBのフレームを設定した(図2.4参照)。
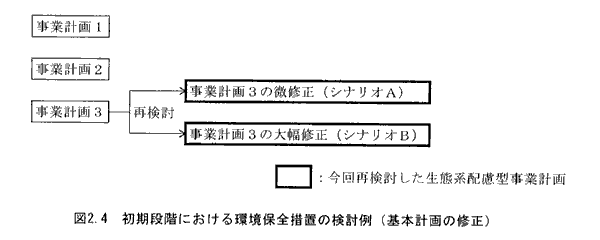
(1)シナリオA(図2.6参照)
○事業計画3を生態系配慮型に微修正。
○事業規模をほぼ維持し、道路のルートの変更や地形改変・道路構造の形式・形状の配慮、環境復元などを中心とした措置を検討。
○改変地(造成地、道路等)以外は、保全緑地として担保。特に、注目種であるフクロウ、ヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリの保全上重要な北側2流域(谷戸)のうち、1流域全体を保全エリアとして設定。
(2)シナリオB(図2.7参照)
○事業計画3を生態系配慮型に大幅修正。
○事業規模の縮小、道路のルート変更、環境復元などを中心とした措置を検討。
○改変地(造成地、道路等)以外は、保全緑地として担保。特に、注目種であるフクロウやヤマガラ、シュレーゲルアオガエル、カタクリの保全上重要な北側の2流域(谷戸)全体を保全エリアとして設定。
○事業実施区域中心部の1流域(谷戸)の谷頭にある源流部と、その上流に位置する集水域(斜面林)を保全緑地として担保。
なお、次項の環境保全措置の検討ではシナリオAとシナリオBのうち、事業計画3を大幅に修正した生態系配慮型計画「シナリオB」に関する検討事項を注目種別に示す。
2.3 環境保全措置の検討
(1)フクロウの場合(上位性)
フクロウの行動圏内には、里山のモザイク的環境に生息する多様な生物がみられ、フクロウはこれらの生物と捕食・被食関係をもち食物網を形成している。調査・予測では、事業計画1・2・3により、フクロウが影響を受けることで動物の生息状況が変化し、捕食・被食関係のある多くの種のみでなく、さらに関連した種々の生物に影響が及ぶことが推測された。
また、森林内で繁殖し生活の主要な部分を森林に依存するフクロウは、飛翔のための林内空間や繁殖のための大きな樹洞など、森林の垂直的構造などが重要な生息条件である。このような条件を満たす好適な生息場所が縮小したり断片化することで、生息場所の質が低下し、事業実施区域周辺の個体の存続に影響が及ぶことが予想された。同様に、林内空間を利用する他の森林性動物についても、森林が伐採されることで影響を受けることが予想された。さらに、森林性動物への影響は、これらの動物が利用している植物や動物、競争関係にある動物へも影響をもたらし、地域の森林生態系が影響を受ける可能性があることが予想された。
以上のような環境影響をふまえ、フクロウとその生息のための環境条件の維持に着目した保全措置の検討対象、さらに具体的な保全措置の検討目標を図2.8のように設定した。また、保全方針にもとづく保全措置を図2.9、図2.10のように設定した。
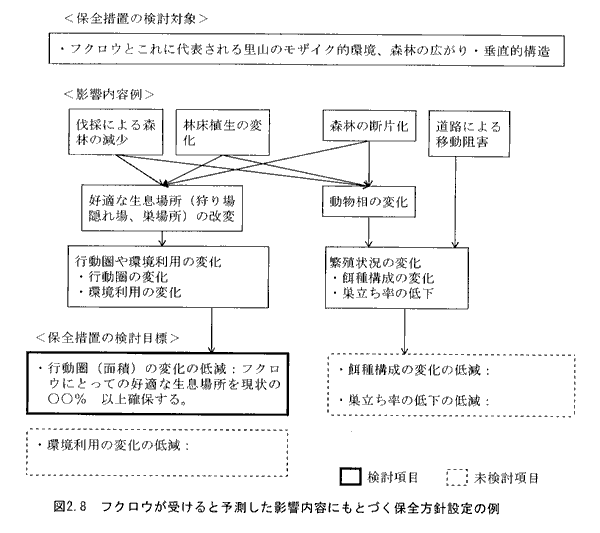
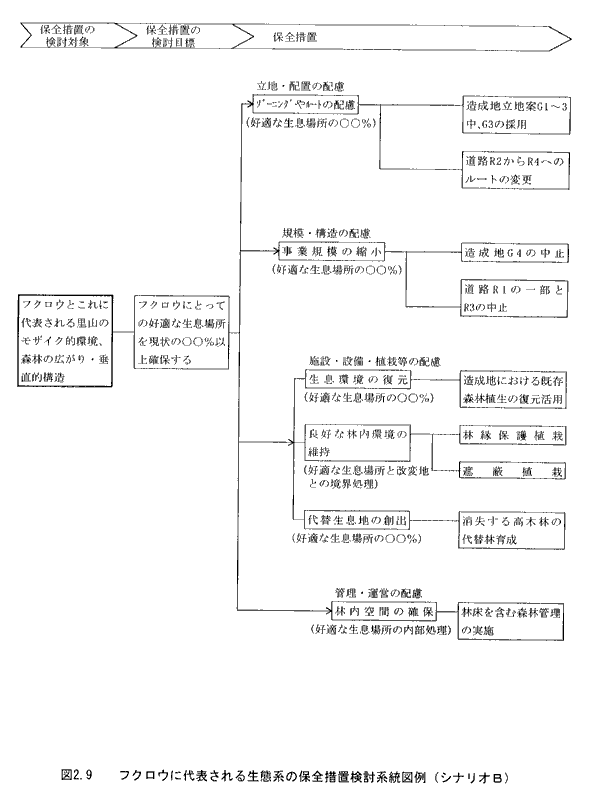
図 2.10 フクロウに代表される生態系の主な環境保全措置例(シナリオB)
(2)ヤマガラの場合(典型性)
調査・予測では、事業計画1・2・3が、ヤマガラのような落葉・常緑広葉樹林の階層構造や森林パッチの面積の変化などに強く影響を受ける森林性の生物種・群集に対して影響を及ぼすと推測された。
ヤマガラと同様に落葉・常緑広葉樹林を好むアオゲラなどの種は、採食場所や巣場所、要求する森林パッチの大きさなどの点で違いはあるが、いずれも森林で生産される昆虫類、種子、果実等を餌資源として利用し、広葉樹の枝葉や枯損木などを巣場所として利用している。森林の伐採等はヤマガラのみでなく、落葉・常緑広葉樹林に生活資源の多くを依存する他の生物種に対しても同様の影響を与えることが予想された。
また、森林伐採等による森林の小規模化・断片化や広大な裸地・草地の出現による都市型生物の侵入は捕食や営巣場所の占拠など、森林性鳥類の生息を圧迫することが予想された。
以上のような環境影響をふまえ、ヤマガラの生息のための環境条件の維持に着目した保全措置の検討対象、さらに具体的な保全措置の検討目標を図2.11のように設定した。また、保全方針にもとづく保全措置を図2.12、図2.13のように設定した。
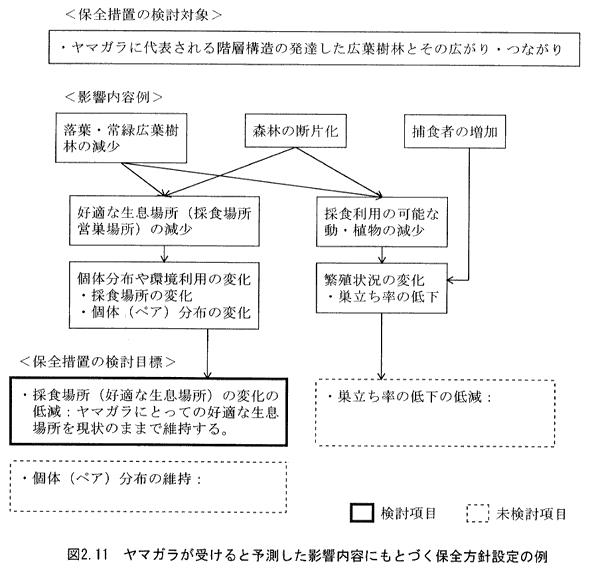
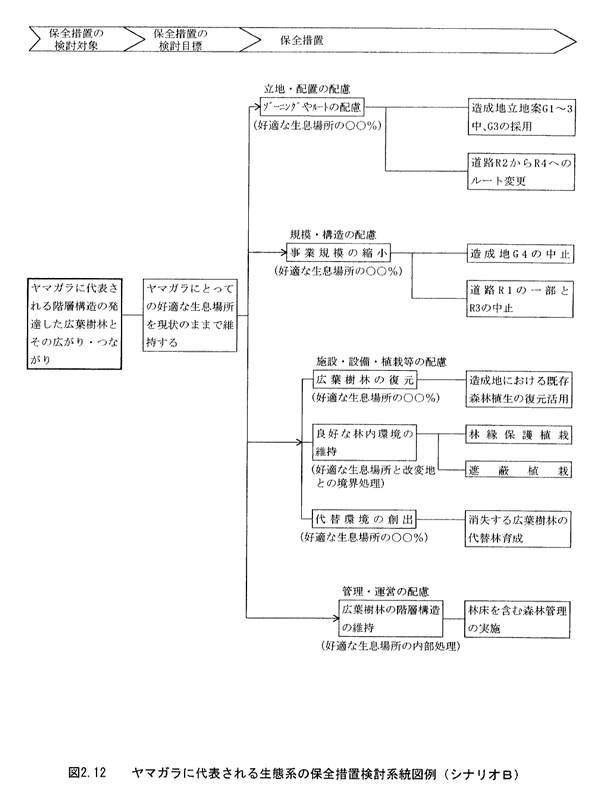
図2.13 ヤマガラに代表される生態系の主な環境保全措置例(シナリオB)
(3)シュレーゲルアオガエルの場合(典型性)
シュレーゲルアオガエルの生息密度の高い部分は、谷戸の良好な水環境が確保され、水域と森林域とが複合した環境及びその移行帯部分が動植物の生息にとって良好な環境となっていることを指標していると考えられる。調査・予測では、事業計画1・2・3が、このような環境に依存する両生類や水生昆虫などの生物群集に対して影響を与えると推測された。
分断による影響は本種以外のカエル類のみならず、地表徘徊性の昆虫類などに広く影響を与えるものと予測された。
ランドスケープレベルでの谷戸の連結性を確保することは、動物の移動や分散などが自然に行われることを示しており、地形等の改変によってこれが失われることにより、連続した谷戸に依存する動物群の長期的な生息に影響が及ぶものと予測された。
以上のような環境影響をふまえ、シュレーゲルアオガエルの生息のための環境条件の維持に着目した保全措置の検討対象、さらに具体的な保全措置の検討目標を図2.14のように設定した。また、保全方針にもとづく保全措置を図2.15、図2.16のように設定した。
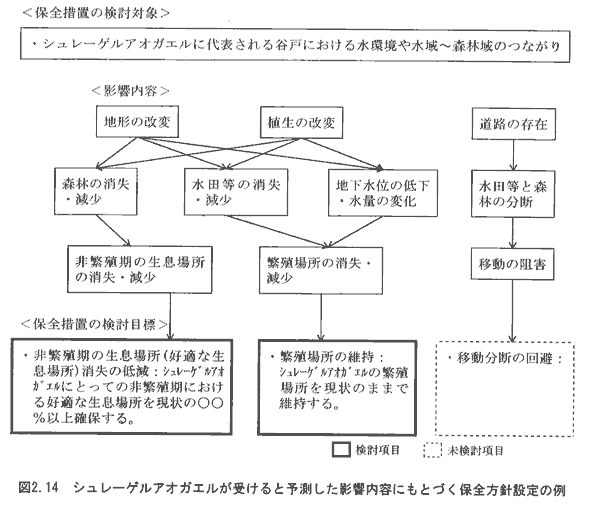
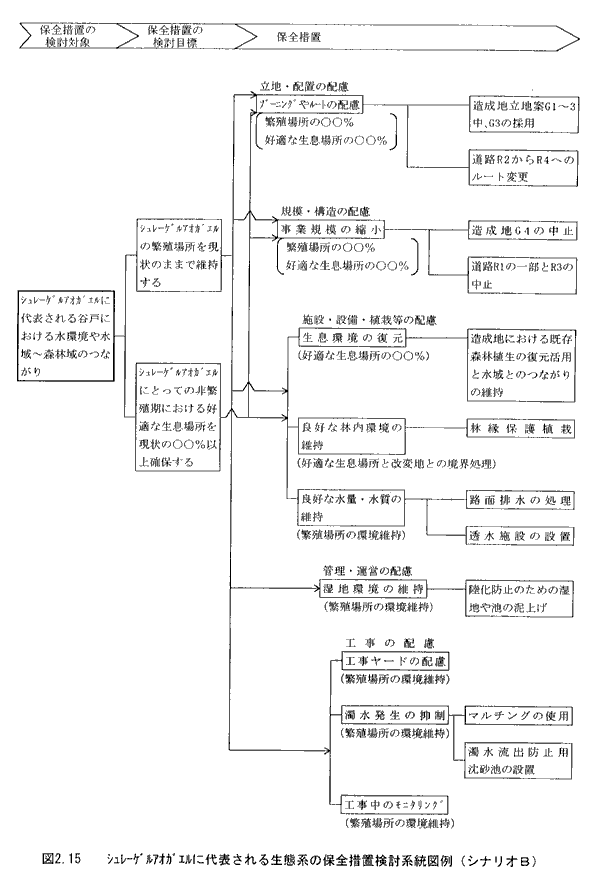
図2.16 シュレーゲルアオガエルに代表される生態系の主な環境保全措置例(シナリオB)
(4)カタクリの場合(特殊性)
調査地域のカタクリは、微妙な地形条件と水分条件のバランスのもとに生育している。調査・予測では、事業計画1・2・3により、土壌水分が高く夏の地温が低いカタクリの生育地は一部消失することが示された。また、直接的な生育地の消失をまぬがれる場所でも、谷戸の乾燥化が起こり、生育環境が劣化することが予測された。さらに、森林の管理条件が変化すればアズマネザサ等が密生し、生育環境が劣化することが考えられた。
カタクリの生育地の消失や生育環境の劣化は、本種と同様の立地に生育するイチリンソウ、エンゴサク類などの春植物の生育環境への影響も生じうることが予測された。これらの春植物に影響が及ぶと、カタクリ等を密源植物として利用する訪花性昆虫類等にも影響が及ぶ可能性がある。このような環境の変化はカタクリが生育する特殊な環境により維持される落葉広葉樹林の種多様性の低下を引き起こすことも示唆された。
以上のような環境影響をふまえ、カタクリとこれに関する特殊な環境条件に着目した保全措置の検討対象、さらに具体的な保全措置の検討目標を図2.17のように設定した。また、保全方針にもとづく保全措置を図2.18、図2.19のように設定した。
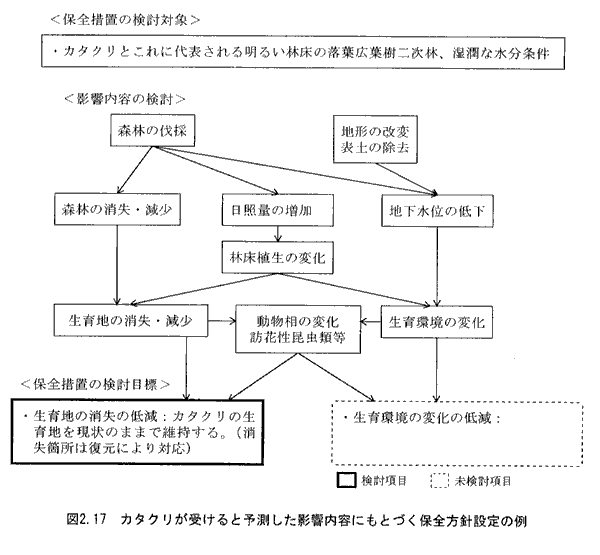
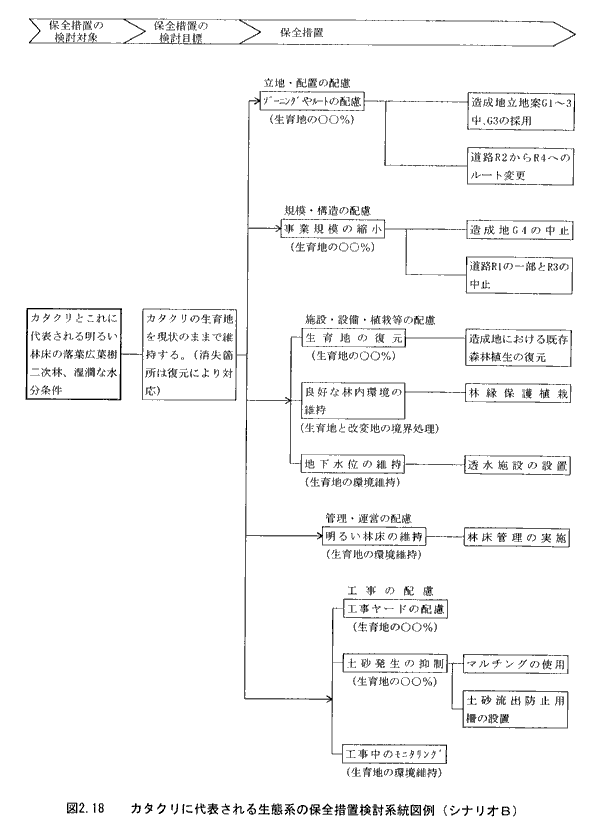
図2.19 カタクリに代表される生態系の主な環境保全代表例(シナリオB)
(5)生態系項目としての環境保全措置の検討
注目種等別にみた環境保全措置の検討結果にもとづき、対象事業実施区域における生態系項目としての環境保全措置を検討した。
まず、注目種別にみた主題図を整理・調整しながら、生態系の保全措置を検討した(図2.20参照)。次に、マトリックス表にて保全措置のもれがないようにチェックした(表2.4参照)。
図2.20 生態系項目としての環境保全措置の検討手順例(シナリオB)
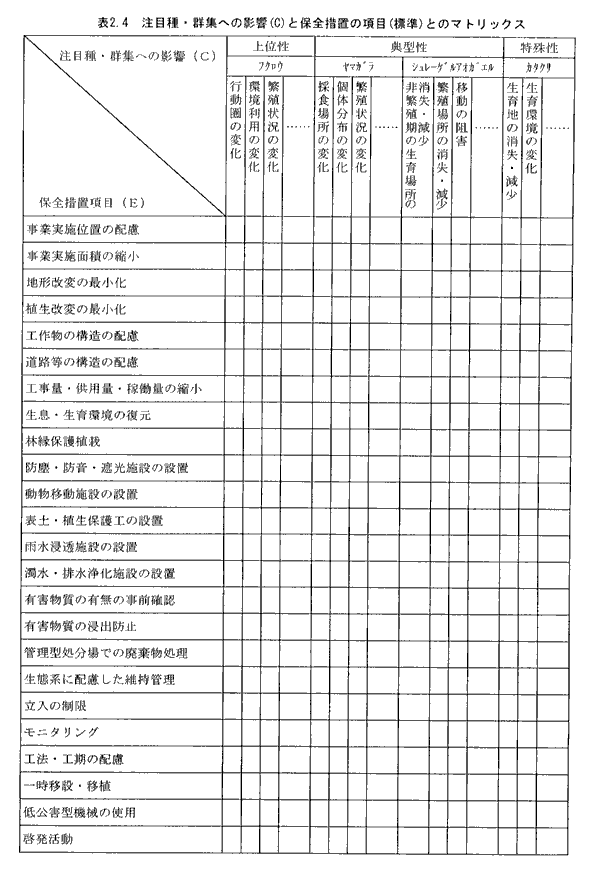
2.4 環境保全措置の妥当性の検証
複数案(シナリオAとシナリオB)の比較検討により、環境保全措置の効果、残る影響、不確実性等を確認し、保全措置の妥当性を検証した(表2.5参照)。
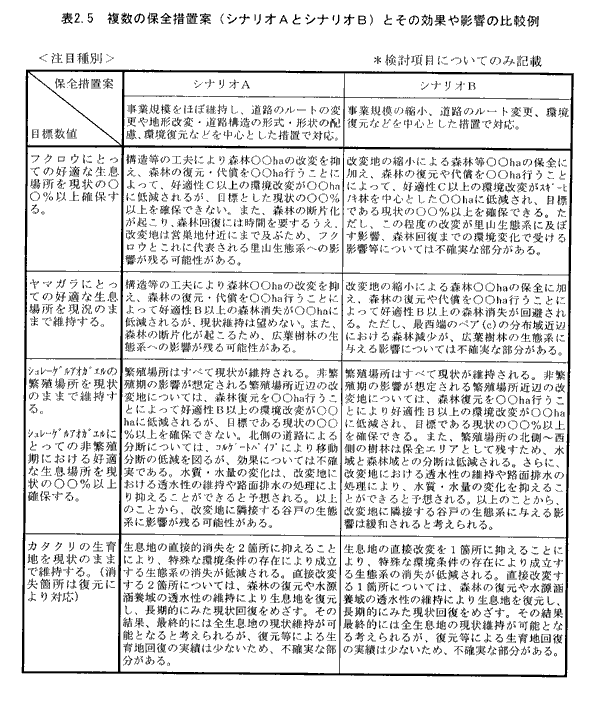
2.5 環境保全措置の実施案の選定
環境保全措置の妥当性の検証の結果にもとづき、妥当であると判断した保全措置(シナリオBを主体とした環境保全措置)の実施案を選定した(図2.21参照)。図中にある個別の環境保全措置(森林植生の復元等)については、一覧表にまとめた(表2.6参照)。