平成13年度 第1回海域分科会
これまでの検討内容(スコーピングおよび調査、予測の進め方)
(報告書の「はじめに」に記載予定)
図-1に示した検討の年次計画に基づき、平成10年度には生物の多様性分野の生態系項目に対するスコーピング手法を、平成11年度には環境影響評価の実施段階における調査・予測手法を検討し、平成12年度には環境保全措置・評価・事後調査の進め方を検討することとした。なお、陸水域に関する検討は、平成11年度と平成12年度の2ヶ年で行った。
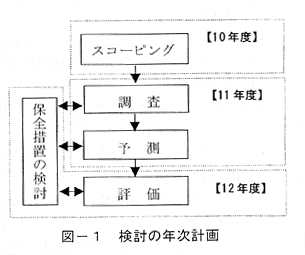
-10年度の検討内容
(平成11年6月 生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書「生物の多様性分野の環境影響評価技術(Ⅰ)」に取りまとめた)
図-1 検討の年次計画
○生態系項目におけるスコーピングの進め方
・生態系項目における環境影響評価の現状と課題を整理した上で、環境影響評価法において新たに導入されたスコーピング(環境影響評価の項目・手法の選定)段階に焦点を絞り、その目的や意義、実施手順について概説した。
(a)陸域生態系
・陸域生態系分野のスコーピングの考え方、検討手順、具体的な技術手法を示した。
・地域概況調査結果のとりまとめについては、陸域の類型区分、陸域生態系の構造と機能、注目種・群集の抽出手順、および調査・予測・評価手法の選定について概説した。
(b)海域生態系
・海域生態系分野のスコーピングの考え方、検討手順、具体的な技術手法を示した。
・地域概況調査結果のとりまとめについては、海域の類型区分、海域生態系の構造と機能、注目種の選定、把握すべき環境要素などを提示した。また、調査・予測・評価手法の選定、数値モデルの位置付けについても概説した。
-11年度の検討内容
( 平成12年8月 生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書「生物の多様性分野の環境影響評価技術(Ⅱ)」に取りまとめた)
○生態系項目における調査・予測手法
・生態系項目における環境影響評価の基本的な考え方、スコーピングから環境影響評価の実施段階への手順を示し、各生態系ごとに具体的な調査・予測手法について検討した。
(a)陸域生態系
・陸域生態系の特徴を整理した上で、地域概況調査から予測に至る一連の手順について基本的考え方を示した。
・実際の作業の参考となるように、里山地域の面的開発事業をケーススタディとして、具体的な作業例と留意点などを示した。特に、地域概況調査、類型区分、生態系の構造・機能、生態系への影響、注目種・群集の抽出、調査手法の選定、調査地域の設定について具体的な記載例を示した。
・環境影響評価の実施段階として、基盤環境と生物群集の関係の調査・予測と、注目種・群集の調査・予測について具体的に例示した。
(b)海域生態系 ・海域生態系の特徴を整理した上で、地域概況調査から予測に至る一連の手順について基本的考え方を示した。
・実際の作業の参考となるように、内湾における埋立地の存在をケーススタディとして、具体的な作業例と留意点などを示した。特に、地域概況調査結果、類型区分、生態系の構造、食物連鎖、注目種、生態系の機能などについて、具体的な記載例を示した。
・調査・予測手法の検討については、影響フロー図などによる検討手法を提示し、影響フロー図の検討から調査・予測手法の選定に至る流れを具体的に例示した。