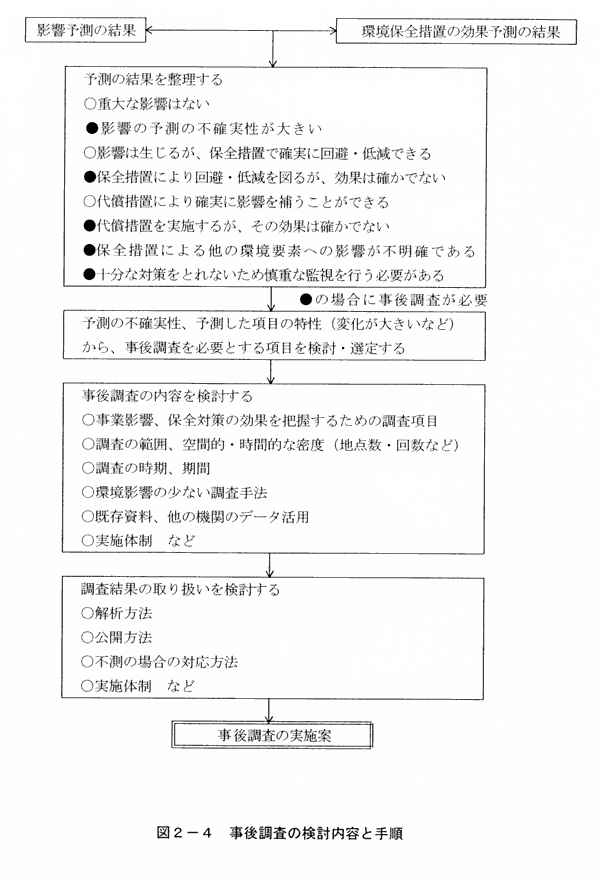平成13年度 第1回海域分科会
4 事後調査
選定項目に係る予測の不確実性が大きい場合、効果にかかる知見が不十分な環境保全 措置を講ずる場合等において、環境への影響の重大性に応じ、工事中及び供用後の環境 の状態等を把握するための調査(以下「事後調査」という。)の必要性を検討するとと もに、事後調査の項目及び手法の内容、事後調査の結果により環境影響が著しいことが 明らかとなった場合等の対応の方針、事後調査の結果を公表する旨等を明らかにできる ようにすること。
なお、事後調査を行なう場合においては、次に掲げる事項に留意すること。
ア 事後調査の項目及び手法については、事後調査の必要性、事後調査を行なう項目 の特性、地域特性等に応じて適切な内容とするとともに、事後調査の結果と環境影響評
価の結果との比較検討が可能なように設定されるものとすること。
イ 事後調査の実施そのものに伴う環境への影響を回避し、又は低減するため、可能な 限り環境への影響の少ない事後調査の手法が選定され、採用されるものとすること。
ウ 事後調査において、地方公共団体等が行なう環境モニタリング等を活用する場合、 当該対象事業に係る施設等が他の主体に引き継がれることが明らかな場合等においては
他の主体との協力又は他の主体への要請等の方法及び内容について明らかにできるよう にすること。(基本的事項第三、二、(6))
(1)事後調査の検討内容と手順
事後調査が必要な場合
予測および環境保全措置の検討結果において、事業による影響予測の不確実性が大きいと判断された場合、保全措置の効果または影響が不確実であると判断された場合、もしくは他の環境要素への影響が不明確であると判断された場合には、工事中および事業の供用後の環境の状態や保全措置による効果などに関し、事後調査を実施する必要がある。
事後調査の考え方
事後調査については、以下の点に留意しながら、図2-4に示した手順に従って調査内容および調査結果の取り扱いに関する方針を検討し、その結果を事後調査の実施案として一覧表などに整理し、準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。
・影響の時間的変化や保全措置の効果の出現までの時間を考慮し、調査時期を選定する必要がある。
・事業による影響と他の社会的変化などによるもとのとをできる限り区分できるよう、調査地点・対象・方法・手法を設定する必要がある。
・事後調査の過程において、環境保全措置の効果が不十分であることが確認された場合や、不測の影響が発生した場合には、その都度影響の内容や程度により柔軟に追加的な措置 を講じたり、技術的な進展を踏まえてより効果的な措置を検討する必要がある。
・大規模な工事が長期にわたるような場合には、適切な時期に事業の進捗に応じて得られた事後調査の結果を用いて、環境影響評価時点の予測・評価が適切であったかについて 検討を行うことも必要である。
・環境影響評価時点の予測の前提条件とした事業計画が、計画熟度の高まりに応じて変化した場合には、再予測を行うとともに必要に応じて追加的な措置の検討を行う必要がある。
なお、事後調査の結果は、追加的措置が発生する場合にはその方法など、必要がないと判断された場合にはその根拠などを含めて公表しなければならない。
陸域生態系における事後調査手法
陸域生態系に関する事後調査に関しては、次の点に留意する必要がある。
・陸域では、大気質、微気象、地下水などの環境変化が、生息・生育する生物種・群集の生息基盤に対して間接的、副次的に影響し、生物種・群集への影響が徐々現れる場合がある。また、植物種の成長や群落の遷移などへの影響も顕在化するまでに時間がかかる。これらを事後調査の対象とする場合は、影響程度を長期的な視点でも把握することを考慮し、想定される影響要因と環境要素及び影響内容に応じた調査項目や手法の選定、調査期間や頻度の設定、調査地点・範囲の検討が必要である。
・陸域の調査では一般的に対象とする「生態系」に立ち入って調査することが多いことや、動物種を捕獲してデータを取得することがあり、また、上位性の種では人の接近を忌避する種もあることから、調査圧がかからない手法を選択する必要がある。特に事後調査では繰り返し同じ対象を調査することが多いことから特に留意する必要がある。
陸水域生態系における事後調査手法
陸水域生態系に関する事後調査に関しては、次の点に留意する必要がある。
・陸水域生態系では水質や水量・流量、流速などは定量的に変化を把握できる要素であることから、生物そのものの動態を追跡する調査と併行して調査対象とする必要があるが、例えば河川における流速では、陸水域の生物にとって重要なのは、一般に流速として示される流心の流速ではなく河岸付近の流速であることなどを考慮し、事後調査対象を的確に把握できるように調査方法を検討する必要がある。
・また、水質や水量・流量、流速などは短時間で急激に変化することのある環境要素でもあり、各要素の特性を把握できるような調査頻度や継続的な追跡方法を考慮する必要がある。
・陸水域生態系では、事業による影響が時間の経過とともに生態系への影響が緩和される場合や反対に長期的に影響が累積してきて大きな影響が現れる場合と、自然の動態として稀に起こる基盤環境の大きな変化による影響を分けて捉えられるような項目や手法を検討する必要がある。
海域生態系における事後調査手法
海域生態系に関する事後調査に関しては、次の点に留意する必要がある。
・海域の生物は、海流のような大規模な環境要素に影響されるとともに、流れとともにあるいは成長に伴って移動するものが多い。そのため、陸域や陸水域の生態系に比べて年による変動が大きく、また季節変化の周期がはっきりしないことも多い。なかには長期的な変動を示すものもある。このようなことから、事後調査に当たっては長期的な視点が必要である。事後調査の対象とした注目種や生態系の現象がどの程度の時空間で変動するのかを既往知見などから想定し、事業影響や保全措置の効果を適切に評価できる調査期間と調査頻度および調査範囲の検討が重要である。
・海域における様々な現象は、そのほとんどが水面下でおこるため、調査データの代表性を検証することが重要である。そのためには、事後調査の当初はできるだけ多い調査点、調査頻度とし、調査の進捗に応じてデータの代表性を検証して調査点などを絞り込んでいくことも考えられる。
・海域では、波浪や塩分などが障害となって、船舶や自動測定機器による調査が行い難いという特徴がある。特に生物に関する調査は、採集器機によって採集するか潜水などにより観察するかのいずれかが主体となっており、魚群探知機のような特定の項目を除いては、自動測定機器による安全かつ連続した調査はほとんどできないのが実態である。したがって事後調査に関しては、調査の目的を踏まえた項目・手法などの十分な検討と絞込みが必要である。
(2)事後調査結果の公表・活用
事業着手後の適切の対処
事後調査の結果は、まずは、当該事業における追加的な環境保全措置などの適切な実施につなげることが基本である。
したがって、評価書もしくは修正評価書の段階で公表した事後調査実施案にしたがって、事業着手後に事後調査を実施し、その結果から追加的措置が必要と判断された場合には、その対処の方法などに関する事業者の見解を含めて公表しなければならない。
また、事後調査結果から、特段の追加的措置の必要性が認められず、予測したとおりの環境保全措置の効果が認められた場合にも、その根拠を含めて事後調査結果として公表することとなる。
事後調査の積極的な活用
事後調査結果は、適切な調査方法の確立、予測精度の向上、客観的・定量的保全目標の設定根拠の取得、保全措置の効果の検討に関する客観的情報の提供など、将来の環境影響評価技術の向上に資する貴重な情報でもあるので、積極的に整理・解析され、活用されることが重要である。そのためには、事後調査の結果を基礎的なデータを含めて広く公開し、活用に供するための仕組みを作っていくことが望まれる。