平成13年度 第1回海域分科会
2 環境保全措置
(1)環境保全措置の目的
環境保全措置の目的は、事業による生態系への影響を極力回避または低減するとともに、評価の対象とする地域において生態系保全に係る基準または目標*1が定められている場合にはそれらとの整合も図り、地域を特徴づける生態系が有する価値を保全し、機能の減少を限りなくゼロにすることにある。
*1基準又は目標とは、国または地方自治体が環境保全のために定めた計画(環境基準、環境基本計画、環境保全のための条例等)や生態系保全のために定めた指針等をいう。保全方針の検討に際しては、それらとの整合を図ることも重要である。なお、生態系に関する環境基準として特に定められたものはない
(2)環境保全措置の検討の流れ
環境保全措置の検討は、予測結果から得られた生態系の価値の変化状況に応じて、環境保全措置の必要性があると判断された場合に、図2-2および以下に示した流れにしたがって検討することとなる。
<環境保全措置の検討の流れ>
[1] 環境保全措置の保全方針(保全措置の検討対象、検討目標、検討手順・方針)を設定する。
[2] 存在・供用及び工事の実施による影響を回避・低減するため、事業の計画段階に応じた措置の内容を検討する。
[3] 検討された回避・低減措置については以下の手順で効果及び影響の検討を行い、その結果を整理することにより妥当性を検証する。
[3]-1 環境保全措置の効果をできる限り客観的に確認し、その結果、不確実性が残される場合にはその程度を明らかにする。
[3]-2 環境保全措置の実施に伴う他の環境要素への影響、あるいは、環境保全措置を講ずるにも関わらず存在する環境影響について検討する。
[4] 回避も低減もできずに残される影響を代償するための措置の内容を検討する。
[5] 検討された代償措置について、効果及び影響の検討を行い、その結果を整理すること により妥当性を検証する。
[6] [2]~[5]を繰り返し、最適な環境保全措置実施案を選定する。
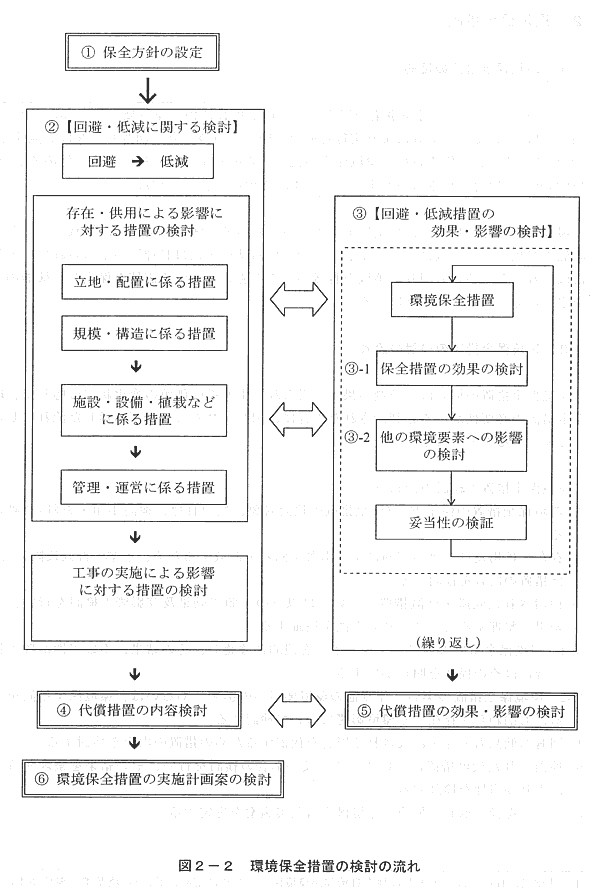
(3)保全方針の検討
1)保全方針検討の観点
保全方針検討の観点
保全方針の検討に当たっては、スコーピングおよび調査・予測のそれぞれの段階で把握される以下の観点を踏まえ、回避・低減措置または代償措置をどのように行うかを十分に検討する必要がある。
・環境保全の基本的考え方(スコーピング段階における検討の経緯を含む)
・事業特性(立地・配置、規模・構造、影響要因など)
・地域特性(地域の生態系の特性、環境保全措置を必要とする生態系の類型と注目種および生態系の重要な機能など)
・地域の環境基本計画や環境配慮指針などに生態系の保全に関連する目標や指針が示されている場合には、それらとの整合(ただし、生態系に関しては、環境基準のような特段の基準は定められていない)
・方法書手続きで寄せられた意見
・影響予測結果 など
生態系に関する環境保全措置の検討に当たっては、特に生態系の構造や機能などのどの部分、どの側面への影響を対象とした措置であるか、保全の対象を明確にする必要がある。事業特性と生態系の特性を勘案し、予測結果などから保全措置が必要と考えられる類型、影響を受けやすいと推定される注目種や生態系の機能については、重点的に環境保全措置を検討する。その際、地域特性(例えば沖縄と北海道)によっては、同じ影響(例えば水温上昇)でも保全の対象が異なる場合があることに留意する。
検討に当たっては、調査・予測段階までに検討した影響フロー図などを参考として、生態系に影響を及ぼすと考えられる事業の各段階における様々な影響要因と生物群集の変化を一覧表などに整理し、そのすべてについて環境保全措置を検討した上で、保全の対象を明確にすることが望ましい。
保全の対象が決まったら、次に、その保全の対象を完全に保全するのか、最小限の影響に留めるのかといった保全の目標を設定する。保全の目標の検討は、保全の対象の重要性、影響の内容や程度、保全技術の実行性などを踏まえて行う。
なお、対象地域の生態系に対し部分的な修復が必要であり、かつ可能な場合には、その実施についても検討されることが望ましい。
陸域生態系に係る保全方針検討の観点
陸域には、水平的、垂直的に多様な構造を持ち、基盤環境の違いや人為の関わり方の違いにより、それぞれ構成を異にした特有の構造・機能を有する生態系がみられる。また、対象とする地域には相互に関係した多様な生態系が複合して存在している。このため、陸域生態系の保全措置の検討に当たっては、特に以下の点に着目すべきである。
・基盤環境や生物群集が相互に関係し、まとまり、つながりを持って存在する場の維持
(特に里山などに見られるモザイク構造など、多様な生態系が複合して存在する状態の維持)
・生態系が持つ構造や機能の維持(特に生物の生育
・生息生育空間を形成する樹林などの階層構造や物質生産
・循環機能、基盤環境形成・維持機能などの維持)
・生態系保全に関する取り組みの実績や林床管理などの伝統的手法
・地理的、遺伝的な隔離により孤立した特徴ある生態系の維持
陸水域生態系における保全方針検討の観点
陸水域は、水域とその周辺の陸域および移行帯、水域で構成される一連の環境系の場であり、生物の生活の場という観点では、生活基盤への水の作用や陸域、海域とのつながりが重要であり、水の作用を通じた変動性と連続性が特性である。このような陸水域生態系に関する環境保全措置の検討に当たっては、特に以下の点に着目して検討することが重要である。
・陸域、移行帯、水域からなる場の維持
・河川・湖沼・湿原などの形態、開放的
・閉鎖的な系、安定・不安定な系などの個性的な面の維持
・洪水の発生、浸食と堆積、水量・水位、水質の変化など水の作用による変動で形成される構造や機能の多様性の維持
・物質の流下、生物の回遊、移行帯の存在など横断的、縦断的な連続性の維持
・生物の生息・生育空間の形成、基礎生産量の維持、生物群集の構成の維持、類型の構成の維持、健全な食物連鎖の維持
・地理的隔離などによって孤立した種や遺伝的に孤立した個体群を含む特徴ある生態系の維持
・河川などに見られる治水上行われていた生態系保全のための伝統的工法などの実績の取り込み
海域生態系における保全方針検討の観点
海域には、海底の基質、流れ、水深、河川水・外洋水の影響などによって、水平的・鉛直的に多様な類型(生態系)が存在している。それらの類型は流れや生物の移動などによって相互に関連し、複雑な海域生態系を構成している。このような海域生態系に関する環境保全措置の検討に当たっては、特に以下の点に着目して検討することが重要である。
・生物的機能、物質循環機能、環境形成・維持機能など様々な機能の維持
・場を形成している地形、基質及び藻場・サンゴ礁などを形成している生物群集の維持
・機能を維持するための基礎生産量の維持、生物群集の量と構成の維持、多様な類型の維持、健全な連鎖の維持など
・富栄養化・海水の停滞などによる赤潮・有毒プランクトンの大量発生、貧酸素水(青潮)の発生防止
・生活型、餌料、生息場所など生物の生活史の考慮
これらの作業を進めていく上では、例として表2-1(1)~(3)に示したものなどを参考として、事業による影響要因と想定される影響などを整理することが重要である。
・表2-1(1)事業段階別の環境影響要因と環境影響要素の変化(陸域)
・表2-1(2)各事業段階における環境影響要因と環境要素の変化(陸水域)
・表2-1(3)環境影響要因と環境要素の変化による生物への影響(海域)
2)保全措置の検討対象
保全措置の検討対象の選定
保全措置の検討対象は、上記1)に示した観点や、他の環境要素の評価や保全措置の検討状況なども考慮して、予測した項目の中から選定する。保全措置の検討対象の選定に当たっては、保全措置を実施する空間的な範囲や時間的な範囲について、十分に検討する必要がある。なお、環境保全措置が必要でないと判断された場合には、その理由を予測結果に基づきできる限り客観的に示す必要がある。
陸域生態系における保全措置の検討対象
陸域生態系は、多様な環境が有機的に集合した里地生態系などから、そこに含まれる比較的広い森林、草地などにおける生態系、湿地、ため池などにおける小規模な生態系まで様々なレベルでとらえることができる。そこで、地形や植生、土壌、水象などの組み合わせによってとらえられる空間単位(類型)や、生息・生育する注目種・群集、および、類型や注目種・群集から形成・維持される機能・構造などにより生態系を整理し、生息・生育の場や環境条件、さらには生物種・群集そのものを保全措置の検討対象としてとらえることが必要となる。
なお、地形・地質の状態によっては、地下を含む複雑な水循環がみられ局地的に独特の生態系が形成されている場合がある。こういった複雑な水環境下においては、地上部の環境要素の情報(例えば、分水嶺や相観的な植生)だけでは影響把握が難しい場合があることをふまえ、地下水の流動などに留意して保全措置の検討対象を設定する必要がある。
陸水域生態系における保全措置の検討対象
陸水域生態系は、河川では土砂の掃流、栄養分の供給などの物質生産・循環、水質形成・浄化、景観形成、生物の生育・生息空間の形成・維持など、湖沼などでは河川のもつ機能に加え、物質の貯留などの重要な機能があり、それらは生態系の健全性と密接に関連している。これらの機能を保全するためには、注目種によって指標される生物群集あるいは、機能を有する「まとまりを持った場」の保全が重要であり、生物群集と場の環境要素から構成される生態系がシステムとして健全に機能することに注目する必要がある。
具体的には、影響フローや影響要因と環境要素の変化の整理結果などを参考として、環境保全措置が必要と考えられる場としての類型や注目種・群集および構造・機能を選定し保全することで、生態系の保全を図る。例えば、典型性で指標される注目種・群集の保全にお当たっては、対象となる種の現存量、分布する類型、繁殖地、陸域と水域とのつながり、水質・水量などなど生育・生息に必要な環境条件などを保全措置の検討対象とする。
海域生態系における保全措置の検討対象
海域生態系では、生物資源の生産機能、物質循環機能、環境形成・維持機能、生物多様性の維持機能など、生態系が有する機能の保全が特に重要である。また、これらの機能を保全するためには、注目種によって指標される生物群集あるいは、機能を有する「まとまりを持った場」の保全が重要である。つまり、生物群集と場の環境要素から構成される生態系がシステムとして健全に機能することに注目する必要がある。
具体的には、影響フローや影響要因と環境要素の変化の整理結果などを参考として、環境保全措置が必要と考えられる類型や注目種・群集および機能を選定し保全することで、生態系の保全を図ることとなる。検討対象は様々なものが考えられるが、ごく一例として、以下のようなものが考えられる。
- ・生物資源の生産機能を保全するために、影響範囲内にある藻場を構成する注目種を検討対象とする。
・干潟が有する幼稚魚生育場としての機能を保全するために、干潟を生育の場とするカレイ類の幼稚魚を検討対象とする。
・干潟の水質浄化機能を保全するために、窒素・リン・CODの浄化力(年間浄化量など)を検討対象とする。
・ある注目種(例えばコブシメ)の産卵・育成場の機能を保全するために、一定範囲のサンゴ礁全体を検討対象とする。
・海域における種の多様性を保全するために、汽水域に生息するトビハゼを検討対象とする。 - ・その他
- ・注目種・群集の密度・現存量、分布面積、再生産量
・生物生産量・生産速度
・機能を有する場の面積、連続性
・浄化力・消波機能(波浪減衰率)のように直接的に測定できる機能
・産卵場として特殊な微地形(窪みや礫浜など)や底質(粒径など)が必要である、あるいは生息のために限られた条件(水温・塩分の範囲など)が必要であるというように、機能を有する場を形成している重要な環境要素
・種の多様性 など
3)保全措置の検討目標
具体的な目標の設定
保全すべき類型、注目種、生態系の機能などについて、影響の回避、低減もしくは代償のための方策を検討する上での目標の設定を行う。保全措置の検討目標の設定に当たっては、事後調査による効果の確認ができる具体的な目標として、保全措置の検討対象ごとに調査や予測結果を活用して、できるだけ数値などによる定量的な目標を設定することが望ましい。
また、目標の妥当性は、国または地方自治体が環境保全のために定めた計画や指針などとの整合性や、既存知見や研究例、保全措置検討の過程で得られたデータ(評価実験などの実施結果)などを用いて、できるだけ客観的に示すことが望ましい。
陸域生態系における保全措置の検討目標
陸域生態系では、例えば、注目種・群集の生息・生育にとって好適な条件にある樹林とその面積・連続性、注目種の繁殖場の面積や連続性などについて、現状以上に保つあるいは、最小限の影響にとどめるといったことなどが目標となる。
この他、陸域生態系の保全措置の検討目標となる項目としては、次のようなものが考えられる。
・注目種・群集の分布範囲、現存量、密度
・注目種等の餌種構成、餌量
・注目種等の繁殖率
・構成種の多様性・生態遷移の状況 など
特に陸域では人為の加わった二次的な自然環境が多いことから、二次的環境に成立する独特の生態系と、これに関連する人間活動や地域住民の意向、地域の環境保全の方向性などについて留意しながら、目標を検討する必要がある。
なお、陸域の生態系の影響を定量的に捉えることは困難なケースが多いが、対象とする生物の生態的特性、生態系の特性や広がりを踏まえ、できるだけ客観的なデータに基づく目標を設定することが重要である。
陸水域生態系における保全措置の検討目標
陸水域生態系では、移行帯(ヨシ帯、ヤナギ類などの河畔林)の面積・密度、水域への依存度が高い注目種の現存量、植物や底生動物の水質浄化量などを現状以上に保つあるいは、最小限の影響にとどめることなどが目標として考えられる。
その他、陸水域生態系の保全措置の検討目標となる項目としては、次のようなものが考えられる。
・注目種・群集の密度・現存量、分布面積、再生産量
・生物生産量・生産速度
・機能を有する場の面積、連続性
・浄化力のように測定できる機能
・魚類などの産卵場でみた場合、瀬や淵など河床形態、底質(粒径など)、水温、塩分などの条件など、機能を有する場を形成している重要な環境要素
・構成種・群集の多様性 など
また、保全措置の検討目標の設定に当たっては、以下に示すような留意点を踏まえて検討されることが望ましい。
・移行帯に生息する種や、生活史からある時期に水域に依存する種などが存在する場合は、水域と陸域の連続性を確保した生息・生育基盤の保全・維持が重要であること。
・陸水域生態系は、陸域生態系、海域生態系の双方と隣り合って関連しており特に相互の物質循環の面で重要な環境であることから、これらとの整合が必要であること。
・陸水域では洪水の頻度や規模が生態系の成立、維持に関係しており、これらの季節的な事象の発生が重要であること。
・特に河川では流量や水位の日変動、季節変動、年変動の維持が重要であること。
・湖沼では水温躍層が水生生物の分布に大きな影響を及ぼす場合があること。
・保全措置の検討対象とする生物が選好する水質が生活史の段階に応じて変化することがあること。
・河川では源流部から河口に至るまで地形、地質、土地利用などによりそれぞれの区間で固有の特性を持った生態系が形成されていること。
・遡上、降河する魚類、甲殻類や水生昆虫など水系のつながりを縦断的に利用する生物が存在すること。
・地理的隔離などによって孤立した種や遺伝的に孤立した個体群を含む生態系が存在する場合があること。
海域生態系における保全措置の検討目標
海域生態系に関する環境保全措置の検討目標の設定に当たって、特に留意すべき事項は次のとおりである。
・保全措置の検討対象を100%保全するという目標は理想的であり、かつ理解されやすい。しかし、影響を最小限にあるいは○%以内にとどめるといった場合には、その目標を達成することで生態系全体の保全が図られるか否かが重要な問題となる。そのような目標を設定する場合には、その目標を達成することで、どのようにして生態系の保全が図られるのかを明らかにすることが重要である。
・海域における現象はそのほとんどが海面下でおきるため、環境保全措置の効果や影響を把握することが難しい。環境保全措置の検討に当たっては、定量的・客観的に把握しやすい保全措置の検討対象・検討目標を念頭に検討することも必要である。
・海域においては、海流の変化や台風など、スケールの大きな自然要因が生態系を大きく変化させることがある。そのため、環境保全措置の目標の検討に際しては、自然要因による変化も考慮する必要がある。
4)保全措置の検討手順と方針
事業に伴う影響要因、影響の重大性、事業者としての実行可能性の判断、環境影響評価の実施時期などから、後述する「(4)環境保全措置の検討順位・検討内容(回避、低減、代償)」および「(5)事業計画の検討段階に応じた環境保全措置の検討」の考え方を参考として、先に設定した保全措置の検討対象に対する環境保全措置の検討手順と検討の方針を明らかにし、一覧表などに整理して示すことが望ましい。
(4)環境保全措置の検討順位・検討内容(回避、低減、代償)
1)検討の順位(図2-3)
環境保全措置の検討に当たっては、次の順位を遵守すべきである。
- 予測された保全の対象の状態や価値の変化が事業による影響であり、保全措置を検討する必要があると判断された場合には、その影響を「回避」し、また「低減」するための措置を優先して検討する。
- 回避、低減措置による効果が十分でないと判断された場合、もしくは不可避の理由により回避、低減措置の実行が不可能であると判断された場合に「代償措置」を検討する。
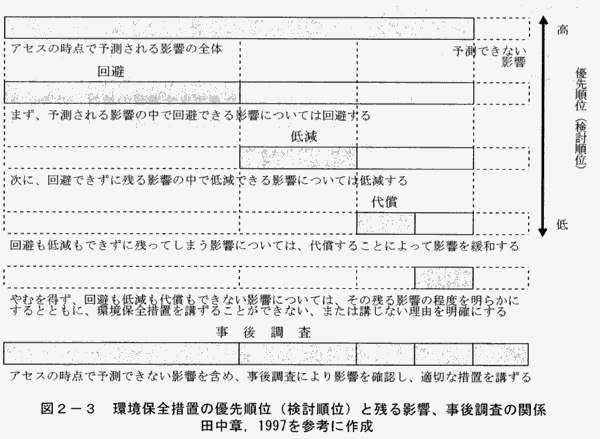
2)回避、低減、代償の区分と考え方
回避、低減、代償の考え方
生態系は、極めて多くの生物と環境要素の複雑な関係の上に成立していることから、事業による影響が何らかの形で生じる場合には、事業自体が中止されない限り厳密な意味での回避措置はない。また、全く同じ生態系を創出することは現実的にはできないため、厳密な意味での代償措置も存在しない。
しかし、調査・予測結果から生態系に何らかの影響があると予想される場合には、重大な影響を回避するための措置や、損なわれる対象や生態系のシステムを保全するための措置の検討は必要不可欠である。
検討の順位
環境保全措置の検討を回避、低減、代償の順に沿って検討することは、予測された影響を事業者が実行可能な範囲内で如何に小さくし得るかについて、より効果的な手法を目的に応じて合理的に選択していくための手段である。事業者は、先に設定した保全方針に従って最善の環境保全措置を検討し、事業による影響の低減を図っていく必要がある。
回避、低減、代償の内容
ここでいう回避、低減、代償とは以下に示す内容であるが、それらの間を厳密に区分できるものではない。
回避
行為(環境影響要因となる事業行為)の全体または一部を実行しないことによって影響を回避する(発生させない)こと。保全の対象となるものから影響要因を遠ざけることによって影響を発生させないことも回避といえる。具体的には、事業の中止、事業内容の変更(一部中止)、事業地やルートの変更などがある。つまり、影響要因またはそれによる生態系への影響を発現させない措置といえる。
低減
低減には、「最小化」、「修正」、「軽減/消失」といった環境保全措置が含まれる。最小化とは、行為の実施の程度または規模を制限することによって影響を最小化すること、修正とは、影響を受けた環境そのものを修復、再生または回復することにより影響を修正すること、軽減/消失とは、行為期間中、環境の保護および維持管理により、時間を経て生じる影響を軽減または消失させることである。要約すると、何らかの手段で影響要因または影響の発現を最小限に押えること、または、発現した影響を何らかの手段で修復する措置といえる。
代償
損なわれる環境要素と同種の環境要素を創出することなどにより、損なわれる環境要素の持つ環境保全の観点からの価値を代償するための措置である。つまり、消失するまたは影響を受ける環境(生態系)にみあう価値の場や機能を新たに創出して、全体としての影響を低減させることといえる。
3)代償措置の視点
-代償措置の困難性
生態系に関する代償措置を講ずる場合には、その技術的困難さを十分に踏まえた検討が必要である。微妙なバランスの上に成り立っている生態系や長い時間をかけて成立した生態系と同等の価値や機能を有する生態系を人為的に創出する事は著しく困難である。そのため、代償措置の効果に対する不確実性や代償達成までにかかる時間(消失と代償との時間差)、効果の正否に係る判断基準の不明確さなどを十分踏まえた検討が必要である。また、技術的困難さに留意しつつ、創出する環境要素の種類、内容、目標に達するまでの時間や管理体制について十分な検討を行うことが必要である。
代償措置により創出する環境要素の検討に当たっては、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、代償措置を講ずることによる環境影響についても把握する必要がある。
また、代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や代償措置を実施する場所によって、その効果が大きく異なることが多いことに留意が必要である。さらに、十分な検討を行ったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。
-代償措置の効果の検討
代償措置は、損なわれる環境と同種のものを影響の発生した場所の近くに創出することが基本的に望ましい。それができない場合には、事業により損なわれる環境、代償措置によって創出する環境および代償措置によって損なわれる環境の各々の価値を十分に検討し、最も効果的で影響の少ない措置を考える必要がある。また、代償措置の効果に確信が持てたとしても、環境の変化や生物相の変化を継続的に把握しながら、その変化状況に応じた追加的な措置や管理を行い、時間をかけて目標とする生態系の創出を進めていくといった考え方が重要である。
なお、代償措置を事業計画地外で行う場合は、その地域で定められた環境基本計画や環境配慮指針などの上位計画など環境保全施策や、他の事業計画との整合を保全措置の検討目標の設定段階で十分に図る必要がある。
-陸域における代償措置の考え方
陸域生態系において代償措置を実施する場合には、代償措置を実施する場所、創出する環境要素の種類、維持管理の有無などによって、その効果が大きく異なることが多い。多大な労力を費やし十分に代償したつもりでも、事業地周辺部の環境変化や外来種の侵入により代償効果が上がらなくなったり、管理体制が整わないため環境が維持できなくなったりすることがある。例えば、消失する貧栄養の湿地の代償として代替湿地を造成した場合、事業地周辺部の宅地化により水の富栄養化が起こり、堆積土砂の除去などの管理も不十分であると陸化の進行や帰化植物の侵入が起こり、貧栄養の湿地の持続が不可能な状態下におかれ、代償措置そのものが疑問視されるケースも想定される。
したがって、陸域における代償措置を検討する際には、周辺を含む環境の前提条件、空間的・時間的な環境変化、管理体制などを十分に考慮する必要がある。
-陸水域における代償措置の考え方
陸水域におけるダム事業を例に挙げると、通常河川で起こる洪水やレアイベントによる河川の攪乱はダム下流側では人為的な操作以外では起こらず、実際には河道が固定化(アーマー化)してしまい、多自然工法を導入した場合でも水位変動による攪乱が生じないため生息を想定していた生物が定着しないことが多くみらる。陸水域における代償措置では特に対象事業により損なわれる生態系と創出される生態系の構造や機能、環境要素、位置などの比較検討や、創出される生態系の長期的な安定性、持続性の検討が重要性である。また、代償措置の実施により、例えば外来種の侵入のように現況の生態系に悪影響を及ぼすことのないよう、創出する環境を十分に検討する必要がある。
代償措置により創出する環境要素の種類や場所によって効果が大きく異なることについては、例えば、堰あるいはハイダムに魚道を設置する場合、人工構造物であるために代償措置の効果そのものが問題視されることがある場合や、湖沼において埋立てに伴い水質浄化機能が減少することの代償として、事業地から遠く離れた場所にヨシ原を造成して浄化機能を保全するといった場合も同様である。
なお、陸水域では地理的隔離などによって孤立して分布する種や遺伝的に孤立した個体群を含む生態系や、事業地周辺でそこにしかない産卵場などを有する生態系に関する代償措置は、それらの生態系が存在する場や機能を完全に創出しなければ措置の効果は得られないが、現実的にそのような生態系を創出することは著しく困難であることから、これらは代償措置ではなくそもそも回避・低減を図るべき対象として認識しなければならない。
-海域における代償措置の考え方
海域生態系に関する代償措置を講ずる場合には、その技術的な困難さを十分踏まえた検討が必要である。特に、微妙なバランスの上に成り立っている生態系(例えば、漂砂・光条件・水温などの環境要素により成立するアマモ場や水温・光条件・流れなどの環境要素により成立するサンゴ礁など)、あるいは、事業地周辺において、そこにしかない産卵場・育成場などの機能を有する生態系に関する代償措置は、それらの生態系が機能するシステムを創出しなければ、代償措置としての効果は得られない。そのような価値、機能を有する生態系を創出することは現実的には著しく困難であり、最善を尽くして回避・低減を図らねばならない。
代償措置の検討に当たっては、損なわれる生態系の構造や機能、生物群集と物理化学的な環境要素の関係などに着目して、創出する環境要素の種類、位置、内容などを検討する。その際には、代償措置を実施する場所における現況の環境条件を考慮し、創出される生態系が長期的に安定して持続するように留意する必要がある。例えば、底質・波当たり・流れ・水中光量などの条件が悪く、もともとアマモ場が成立し得ない環境に藻場を造成しようとしても、なかなか成功しないように、その生態系が成立する環境条件を十分考慮することが不可欠である。また、代償措置の実施により現況の生態系に悪影響を及ぼすこと(例えば覆砂材の持込による外来種の侵入など)のないよう、十分留意しなければならない。
代償措置を実施する場合には、創出する環境要素の種類や場所によって、その効果が大きく異なることが多い。十分な検討を行ったとしても、予測された効果が得られない可能性もある。例えば、消失するアマモ場の代償として人工構造物によるガラモ場を造成するというような場合には、代償措置の効果そのものが問題視されることもある。内湾干潟の一部を埋立て、水質浄化機能を減少させることの代償として、事業地から遠く離れた場所に人工干潟を造成して湾全体の浄化機能を保全するといった場合も同様である。
なお、人工的に干潟造成を行う場合のように、人による利用形態(立ち入りの有無、漁業など)をどうするかといった検討が必要となる場合もある。
(5)事業計画の検討段階に応じた環境保全措置の検討
-計画段階に応じた複数案の検討
環境保全措置の検討に当たっては、事業計画の検討段階に対応して、それぞれいくつかの案を検討し、措置の実施による効果と環境への影響を繰り返し予測・評価して、影響の回避・低減が最も適切に行えるものを選択することが重要である。
検討内容としては、想定される影響要因の区分から、「存在・供用」の影響に対する環境保全措置と「工事」の影響に対する環境保全措置の検討が必要となる。
事業計画の検討段階については、「存在・供用」の影響に関わる計画の検討が先行して行われ、検討手順としては、立地・配置あるいは規模・構造、施設・設備・植栽など、管理・運営といった順に段階的に検討されるのが一般的である。
これに対し、「工事」の影響に関わる工事計画の検討は「存在・供用」の影響に関わる計画の検討がある程度進んだ段階で、これらの検討結果を計画条件として検討されるのが一般的である。このため環境保全措置の検討は、このような事業計画の検討段階に対応して段階的に検討していくことが必要であり、その検討過程を明らかにすることも重要である。
従来の環境影響評価においては、このような段階的検討手順を踏まず、あるいは検討の経緯を示すことなく、最終的に採用した環境保全措置のみを記載する場合が多く見られた。このため、合意形成を図るための情報としては極めて不十分なものとなり、かえって事業者に対する住民の不信感を醸成させる結果につながっていたケースもある。
このよう点を改善するためには、環境保全措置の検討過程や選定理由が準備書や評価書において明確に表現される必要がある。
-生態系分野における留意点
一般的に事業計画の進捗に伴い、事業計画の変更が可能な程度は徐々に小さくなることから、環境保全措置のうち立地、配置レベルにおける回避措置など計画変更の程度が大きくなる可能性のある措置については、できる限り事業計画の早い段階で検討する必要がある。
特に生態系分野では、まとまりを持った場を残す、または場相互の関係を保つといった立地・配置および規模・構造についての環境保全措置が最も重要である。したがって、事業における改変地と保全の対象となる場のおおよその位置関係などは、基本構想段階あるいは基本計画段階までに把握し、その段階から環境保全措置を念頭に置いた環境配慮の検討をはじめておく必要がある。
-計画段階に応じた環境保全措置の事例
計画段階に応じた、陸域、海域、陸水域における環境保全措置の事例を表2-2(1)~(3)に示した。表に示したものが保全措置のすべてではないが、事業の立地・配置、管理・運営、工事といった計画の段階に応じて、それぞれ必要な環境保全措置を検討することが重要である。
・表2-2(1)環境影響要因と一般的な環境保全措置の例(陸域)
・表2-2(2)各計画段階における環境影響要因と一般的な環境保全措置の例(陸水域)
・表2-2(3)事業の計画段階に応じた環境保全措置の例(海域)
(6)環境保全措置の妥当性の検証
-保全措置の効果と影響の検討
環境保全措置の妥当性の検証は、当該環境要素に関する効果とその他の環境要素に対する影響とを検討することによって行う。環境保全措置の採用の判断は妥当性の検証結果を示すことによって行われる必要がある。
-複数案の比較、より良い技術の取り入れの判断
環境保全措置の妥当性を検証するための手法には、早期の検討の経緯も含め、複数案を比較検討することや、より良い技術が取り入れられていることの判断を行うものなどがある。
複数案の比較は、予測された環境影響に対し、複数の環境保全措置を検討した上でそれぞれ効果の予測を行い、その結果を比較検討することにより、効果が適切かつ十分得られると判断された環境保全措置を採用するものである。環境保全措置の検討とその効果の予測は、最善の措置が講じられると判断されるまで、繰り返し行う。
より良い技術とは、高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術群をいう。ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄などに際して用いられた幅広い技術(ハード面のテクノロジー)、およびその運用管理など(ソフト面のテクニック)を指す。より良い技術が取り入れられているか否かの判断に当たっては、最新の研究成果や類似事例の参照、専門家による指導、必要に応じた予備的な試験の実施などにより、環境保全措置の効果をできる限り客観的に示す必要がある。
-より良い技術の取り入れ方
近年、自然の復元・回復のための取り組みや関連分野の研究成果など、様々な保全措置の事例が蓄積されつつある。中には、試行錯誤を繰り返しながらも、地域の住民の協力のもとに復活した伝統的技術もある。このような情報にアンテナを張りながら、対象とする生態系に対して適切な環境保全措置であると判断される技術に対しては、より良い技術として積極的に取り入れることが重要である。
一方において、従来の事業では、環境保全措置が行われていても事後調査が行われなかったり、調査が実施された場合でもその結果の詳細が公表され、活用されることはほとんどなかった。そのため、どのような措置が保全技術として効果的であるのか、情報が乏しいのが現状である。今後は、公的機関による技術開発の調査研究はもちろん、事業者においても事後調査の結果を広く公表し、より良い技術の向上を図ることが望ましい。また、長期的にみた保全措置の効果に不確実性がある場合や技術面で立ち後れている分野における取り組み、実験的な取り組みを行った場合や予備的な試験に関する情報は、早い段階で公開し、幅広い分野の専門家などからの意見をフィードバックすることが有効である。
既往事例や研究成果、専門家の意見などを保全措置に取り入れる場合には、限られた成果や意見だけでなく、広く情報や意見を収集する必要がある。専門家によっては、環境保全措置の効果に関する見解が異なることもあるが、多様な知見・意見を検討し、事後調査による検証を集積することで、より良い技術の獲得を目指すべきである。
今後の技術向上に当たっては、学際的調査研究、特に工学や物理・化学と生物の生理・生態を融合させた調査研究が必要であり、公的機関における実施が重要な緊急課題である。また、事業者においても、実施可能な範囲で保全措置に対する海生生物の応答を実験的に調査し、より良い技術を取り入れるといった積極的な対応が望まれる。
なお、海域において環境保全措置を検討する際には、保全措置と海生生物の生理・生態との関係を知ることが極めて重要である。海生生物の生理・生態に関して十分な知見があるとはいえないが、専門家へのヒアリングなども含めて、広く知見を収集することが重要である。
-他の環境要素への影響の確認
このような検討を行う際には、環境保全措置の実施による他の保全措置の検討対象への影響にも十分な配慮が必要である。特に、ある生物には良い効果をもたらすが、他の生物には悪影響となる場合もあるので、生物や環境要素の関連性についても十分な検討を行い、採用すべき環境保全措置を選択することが重要である。
-不確かな保全措置の事後調査
以上の検討の結果によっては、残される環境影響に対し更なる環境保全措置の検討が必要となる場合もある。
なお、特に技術的に確立されておらず効果や影響にかかる知見が十分に得られていない環境保全措置を採用する場合には、特に慎重な検討が必要である。そのような場合には、保全措置の効果や影響を事後調査により確認しながら進めることも必要である。
(7)環境保全措置の実施案
環境保全措置の検討に当たっては、次に掲げる事項を可能な限り具体的に明らかにで きるようにするものとすること。
ア 環境保全措置の効果及び必要に応じ不確実性の程度
イ 環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある環境影響
ウ 環境保全措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響
エ 環境保全措置の内容、実施期間、実施主体その他の環境保全措置の実施の方法
(基本的事項第三、二、(3))
準備書・評価書に記載する保全措置の内容
準備書・評価書には、当該生態系の保全方針や環境保全措置の検討過程、選定理由について記載する。また、環境保全措置の効果として措置を講じた場合と講じない場合の影響の程度に関する対比を明確にする。環境保全措置の効果や不確実性については、調査・予測段階で検討する影響の伝播経路を示した「影響フロー図」などを参考に、保全措置の検討対象となる生態系や種・群集と、それらを保全するために措置を講ずる影響要因や環境要素の関連の整理を通じて明らかにする。
採用した環境保全措置に関しては、それぞれ以下の点を一覧表などに整理し、環境保全措置の実施案として準備書、評価書においてできる限り具体的に記載する。
・採用した環境保全措置の内容、実施期間、実施方法、実施主体など
・採用した環境保全措置の効果に関する不確実性の程度
・採用した環境保全措置の実施に伴い生ずるおそれのある他の環境要素への影響
・採用した環境保全措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響
・環境保全措置の効果を追跡し、管理する方法と責任体制