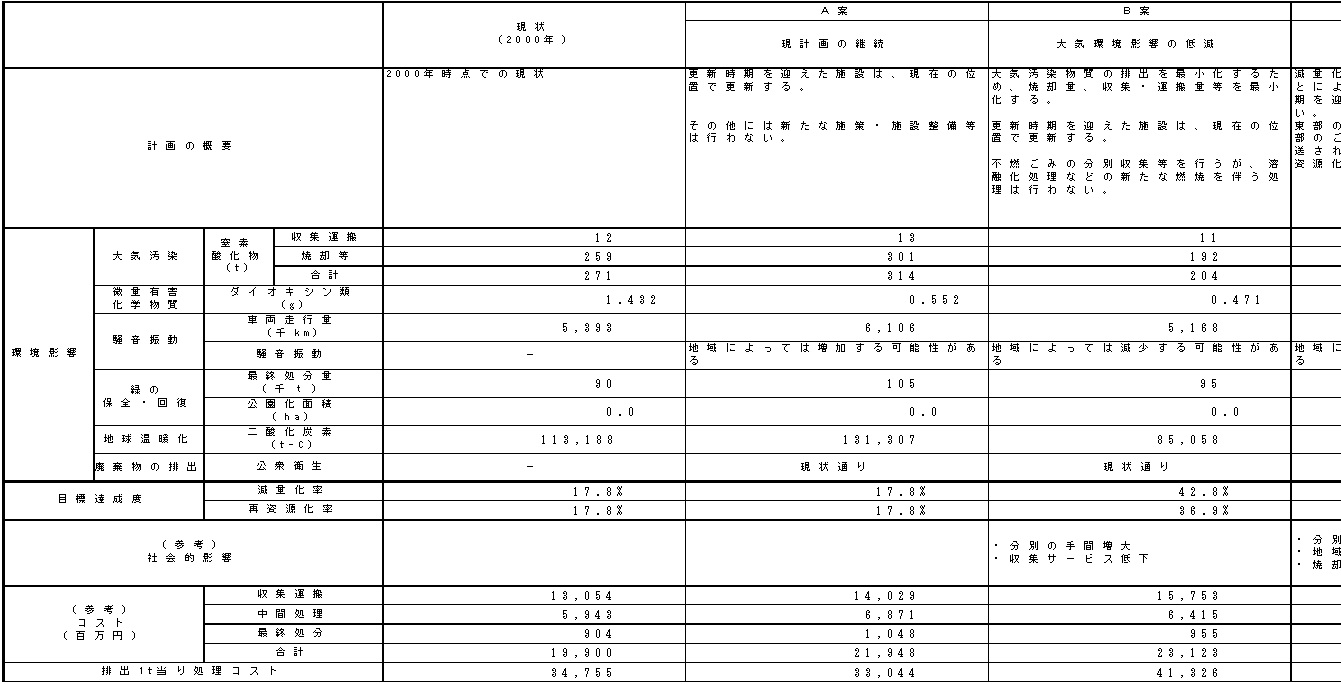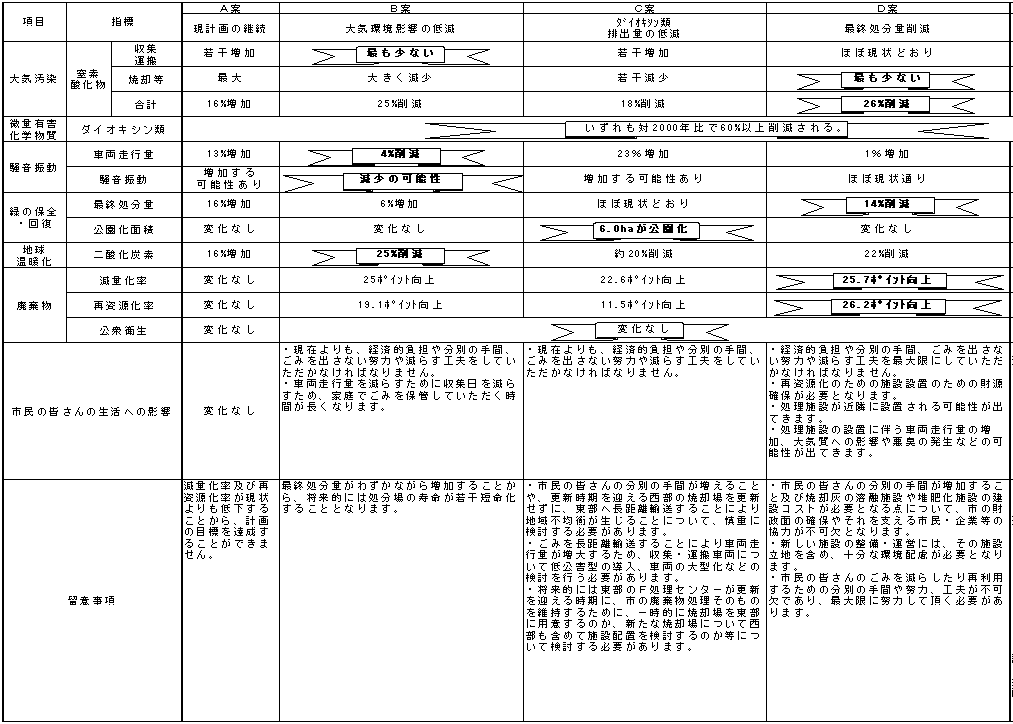一般廃棄物処理計画策定における 戦略的環境アセスメント試行ガイドライン
一般廃棄物処理計画策定における 戦略的環境アセスメント試行ガイドラインTOPへ戻る
IV.添付資料2
SEAケーススタディ
A市一般廃棄物処理計画
環境評価報告書(案)
A市○○局
|
目 次 |
|
| <概 要> | |
| 一般廃棄物処理計画とは? | IV-1 |
| 戦略的環境アセスメントの実施と本環境評価報告書(案)の位置づけ | IV-2 |
| 複数案の内容 | IV-3 |
| 複数案の比較結果 | IV-5 |
| 環境評価報告書(案)への意見募集 | IV-7 |
| 今後の予定 | IV-7 |
| <本 編> | |
| 一般廃棄物処理計画とは? | IV-9 |
| 戦略的環境アセスメントの実施と本環境評価報告書(案)の位置づけ | IV-10 |
| 市民参加 | IV-11 |
| 環境配慮計画書に係る意見等 | IV-16 |
| 環境面の課題に対する意見 | IV-16 |
| 複数案設定の方針に対する意見 | IV-17 |
| 調査・予測・評価の項目及び手法に関する意見 | IV-18 |
| 複数案の設定 | IV-20 |
| 調査・予測・評価の項目・指標及び手法 | IV-24 |
| 調査・予測・評価の項目の検討 | IV-24 |
| 調査・予測・評価の項目の検証 | IV-24 |
| 調査・予測・評価の指標の検討 | IV-25 |
| 環境影響の予測手法 | IV-26 |
| 影響の予測結果 | IV-28 |
| 評 価 | IV-29 |
| 複数案の比較 | IV-29 |
| 各環境項目の視点からの評価 | IV-31 |
| 各案比較による評価 | IV-32 |
| 今後の予定 | IV-38 |
| <資料編> | |
| 1. 環境配慮計画書の概要 | IV-41 |
|
1.1 一般廃棄物処理計画とは? |
IV-41 |
|
1.2 計画改定の必要性 |
IV-42 |
| IV-42 | |
|
1.4 環境配慮方針 |
IV-43 |
|
1.5 計画の目的 |
IV-43 |
|
1.6 複数案設定の方針 |
IV-44 |
|
1.7 環境配慮計画書への意見募集 |
IV-45 |
| 2. 市民参加 | IV-46 |
|
2.1 環境配慮計画書に係る市民参加 |
IV-46 |
| 3. 汚染物質排出量等の算出方法について | IV-51 |
|
3.1 収集量と収集効率 |
IV-51 |
| IV-52 | |
| IV-53 | |
|
3.4 溶融処理に伴う二酸化炭素排出量 |
IV-54 |
| IV-55 | |
<概 要>
ごみは毎日の生活の中で発生し続けています。ごみ問題は、市民の皆さんの生活の中で大きな問題であり、市でも様々な取り組みを行っていますが、市民の皆さんに身近な取り組みとして、ごみの収集や処理があります。これらのごみ処理については、市の一般廃棄物処理計画(以下処理計画といいます。)という計画の中で、全体の処理量や処理方法について将来の計画をたて、この処理計画に基づいて施設の整備や日々の収集・運搬や処理を行っています。
ごみの発生量や処理量は、どれくらい減量化や再資源化に取り組むかによって、その量が異なり、また処理の方法には焼却や埋立などがあります。処理計画では、減量化や再資源化のためにどのような具体的な施策を行うかを検討し、将来のごみの発生量や処理量を予測し、その処理方法や必要となる施設の数までを検討します。
処理計画で、市全体のごみの発生量や処理量の目標値、その処理方法と必要な施設の数までを決めた後には、必要となる個別の施設について、その立地や計画内容の検討が行われることになります。

⇒本編P.IV-9「一般廃棄物処理計画とは?」
戦略的環境アセスメントの実施と本環境評価報告書(案)の位置づけ
|
処理計画は、減量化や再資源化のための具体的な施策や、収集方法、中間処理等の施設建設の有無など、市民の皆さんの生活や市の環境に深く関連した事項を定めるものです。その内容には、市民の皆さんの手間や経済的な負担を伴うばかりでなく、環境への影響が考えられるものもあります。 |
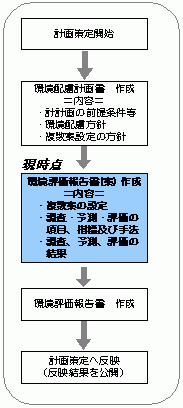 |
⇒本編P.IV-10「戦略環境アセスメントの実施と本環境評価報告書(案)の位置づけ」
環境配慮計画書で示した複数案設定の方針及び市民の皆さんから得られた意見等を踏まえ、2020(平成32年)年を目標達成年度とし、複数案として現計画の継続案を加えたA案、B案、C案、D案、E3案の5案を設定しました。
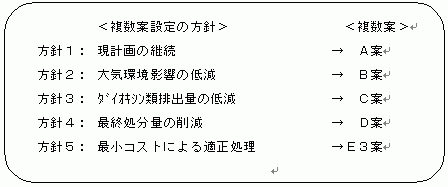
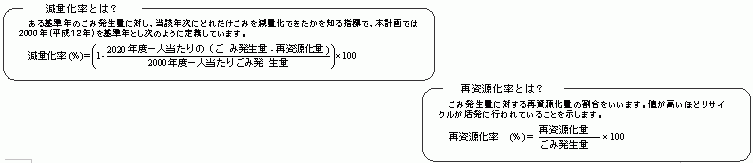
複数案の内容
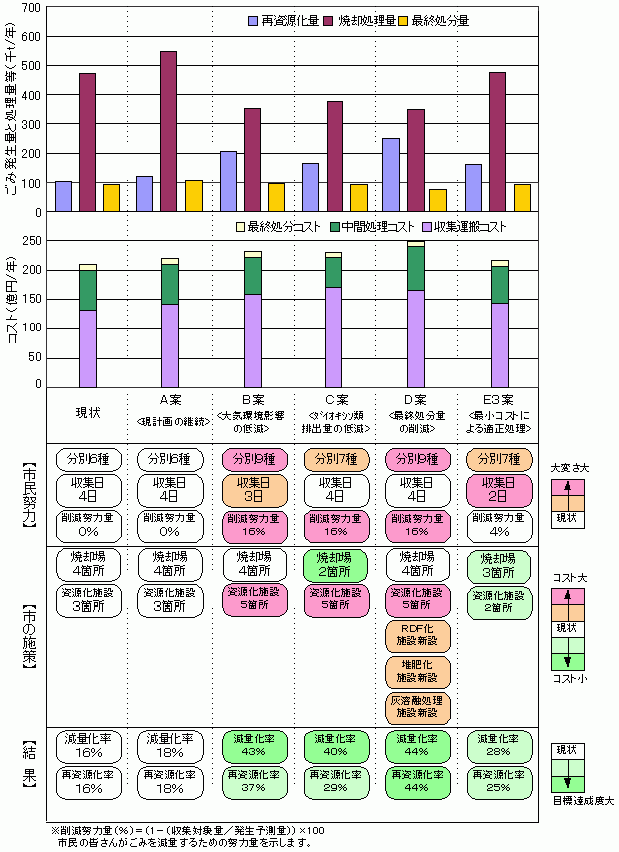
⇒本編P.IV-20「複数案の設定」
現状(2000年:平成12年現在)に対するA~E3案の比較結果は、次に示すとおりです。
A案を採用すると・・・
窒素酸化物排出量は、現状を大きく上回り、5つの案の中で最大となります。
騒音振動の影響は、地域によっては増加する可能性があります。
最終処分量は、現状より大きく増加し、5つの案の中で最大となります。
施設の削減に伴う公園化面積は確保できません。
二酸化炭素の排出量は5つの案の中で最大となり、現状を大きく上回ります。
廃棄物の減量化率は18%、再資源化率は18%となり、いずれも5つの案の中で最低となります。
B案を採用すると・・・
窒素酸化物排出量は、現状より大きく削減されます。
騒音振動の影響は、地域によっては減少する可能性があります。
最終処分量は、現状より増加し、A案に次いで大きくなります。
施設の削減に伴う公園化面積は確保できません。
二酸化炭素の排出量は、現状より大きく削減され、5つの案の中で最小となります。
廃棄物の減量化率は43%、再資源化率は37%となります。
C案を採用すると・・・
窒素酸化物排出量は、現状より大きく削減されます。
騒音振動の影響は、地域によっては増加する可能性があります。
最終処分量は、現状よりわずかに増加します。
施設の削減に伴う公園化面積は約6haとなり、5つの案の中で最大となります。
二酸化炭素の排出量は、現状より大きく削減されます。
廃棄物の減量化率は40%、再資源化率は29%となります。
D案を採用すると・・・
窒素酸化物排出量は、現状より大きく削減され、5つの案の中で最小となります。
騒音振動の影響は現状とほとんど変化しません。
最終処分量は、現状より大きく減少し、5つの案の中で最小となります。
施設の削減に伴う公園化面積は確保できません。
二酸化炭素の排出量は、現状より大きく削減されます。
廃棄物の減量化率は44%、再資源化率は44%となり、いずれも5つの案の中で最大となります。
E3案を採用すると・・・
窒素酸化物排出量は、現状より若干増加します。
騒音振動の影響は、地域によっては増加する可能性があります。
最終処分量は、現状よりわずかに増加します。
施設の削減に伴う公園化面積は約3.4haとなります。
二酸化炭素の排出量は、現状より大きく削減されます。
廃棄物の減量化率は28%、再資源化率は25%となります。
比較結果1 対2000年比の増加量及び増加率
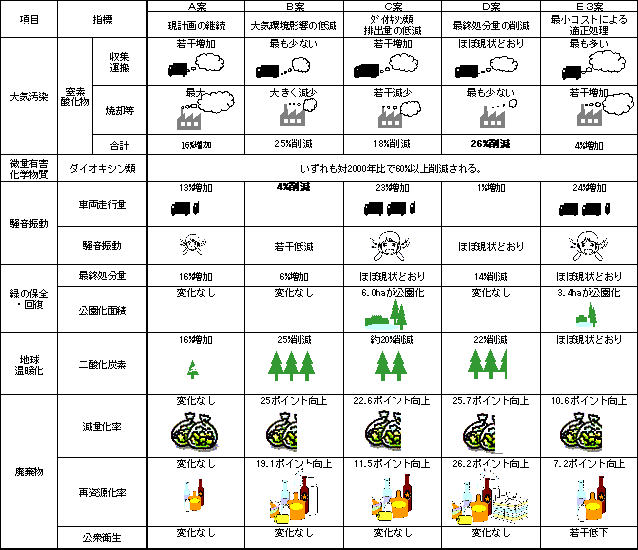
環境評価報告書(案)の内容について、計画の複数案に対する意見や、環境影響の検討の方法、その結果など、環境面からの幅広い意見を以下のとおり募集しています。
・ 環境評価報告書(案)の公開と意見募集
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)でお寄せ下さい。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
住所 A市○区○-○-○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
・ 意見交換会の実施
処理計画の複数案の内容や環境影響の検討方法に関して広く皆さんと意見を交換する場として、環境評価報告書(案)に係る意見交換会を、意見募集期間中に区民センター等において7回程度開催する予定です。
具体的な開催場所及び日時については、その内容が決定され次第、ホームページや市の広報に掲載します。
⇒本編P.IV-11「市民参加」
今後は、この複数案の比較検討結果に対して、広く市民の皆さんから意見を募り、最終的に環境評価報告書をとりまとめます。どのように今回の検討結果を反映したかについては、後日市から反映結果を公開します。
⇒本編P.IV-10「本環境評価報告書(案)の位置づけ」
A市一般廃棄物処理計画 環境評価報告書(案)に関する問いあわせ先:
A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
TEL:○○-○○○○-○○○○
FAX:○○-○○○○-○○○○
E-mail:iken.WMP@city.a-shi****.jp
<本 編>
ごみは毎日の生活の中で発生し続けています。ごみ問題は、市民の皆さんの生活の中で大きな問題であり、市でも様々な取り組みを行っていますが、市民の皆さんに身近な取り組みとして、ごみの収集や処理があります。これらのごみ処理については、市の一般廃棄物処理計画(以下処理計画といいます。)という計画の中で、全体の処理量や処理方法について将来の計画をたて、この処理計画に基づいて施設の整備や日々の収集・運搬や処理を行っています。
市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第六条により処理計画を定めるよう義務づけられており、一般廃棄物(以下、ごみと略します)の将来の発生量、分別の区分、処理施設の整備に関する事項等を定めることになっています。
ごみの発生量や処理量は、どれくらい減量化や再資源化に取り組むかによって、その量が異なり、また処理の方法には焼却や埋立などがあります。処理計画では、減量化や再資源化のためにどのような具体的な施策を行うかを検討し、将来のごみの発生量や処理量を予測し、その処理方法や必要となる施設の数までを検討します。
処理計画で、市全体のごみの発生量や処理量の目標値、その処理方法と必要な施設の数までを決めた後には、必要となる個別の施設について、その立地や計画内容の検討が行われることになります。
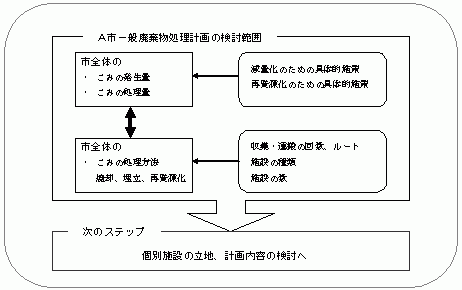
本環境評価報告書(案)の位置づけ
一般廃棄物処理計画(以下、処理計画といいます。)は、今後の一般廃棄物(以下、ごみといいます。)の減量化や処理(収集、運搬、中間処理、最終処分等)の基本的な内容を定めるものであり、市民の皆さんや企業による減量化の努力量や、焼却処理施設建設の有無など、市民の皆さんの生活や市の環境に深く関連した事項を定めるものです。大きくは、将来のごみ発生量、分別の区分、処理施設の整備に関する事項を定めることになっています。
処理計画の具体的な検討事項には、市民の皆さんの手間や経済的な負担を伴うばかりでなく、環境への影響が考えられるものもあります。このため、市では、本計画の策定にあたって戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment:SEA 以下、SEAといいます。)を実施することにより、環境影響のより少ない処理計画を目指すこととしました。
SEAとは、さまざまな計画の策定段階で環境への影響検討を行うことにより、より環境に配慮した計画づくりを進めようとするものです。
SEAでは、まず、処理計画の改定にあたり重視すべきこととして、環境配慮方針を策定します。処理計画は、この環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要がありますが、このような視点に沿って、処理計画が目指す具体的な方向性となる複数案設定の方針を策定します。
平成○年3月には、計画の背景や必要性、環境配慮方針や複数案設定の方針を示した「環境配慮計画書」を作成・公開し、広く市民の皆さんから意見を募集しました。
本環境評価報告書(案)は、環境配慮計画書に対する意見を踏まえながら、複数の計画案(以下、複数案といいます。)を策定し、それぞれの複数案ごとに環境への影響を予測・評価した結果をとりまとめたものです。
今後は、再び皆さんの意見を伺ってから、最終的な環境評価報告書を作成します。
このような過程を経て、環境負荷のより少ない、環境保全に配慮した計画づくりを進めていきます。
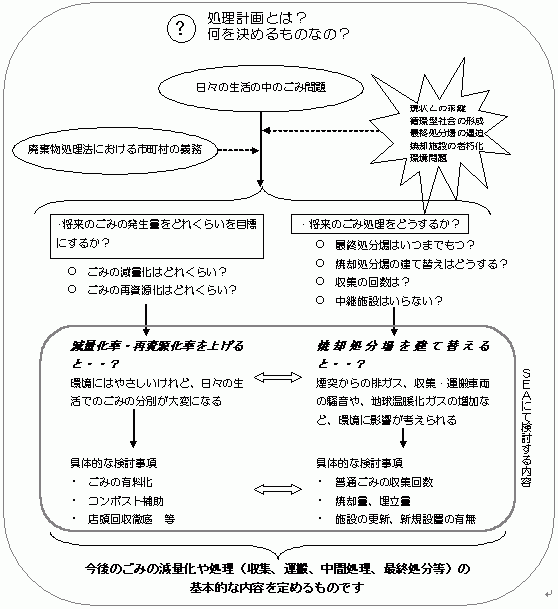
処理計画とSEAの関係
本SEAにおける市民参加の機会と方法等については、SEAの実施に先立つ計画に関するアンケート調査結果と専門家の意見を踏まえ、次に示すとおり実施しています。
市民参加の機会は、計画の策定開始から終わりまで、常時市のホームページ上の専用ページ及び専用ブースにおける情報公開を行うとともに、意見募集の窓口を開いています。また、計画策定開始段階では、ごみの処理全般についてのワークショップとヒアリングならびに環境配慮に関するアンケートを実施しました。意見の内容については、資料編に示しています。さらに、SEAの中で特に重要と考えられる、環境配慮計画書の段階では、計画書の公開、市の広報によるお知らせ、意見交換会の開催、文書での意見募集等を行いました。環境評価報告書(案)についても、同様に意見募集を行います。
⇒資料編「2.市民参加」
常設の情報公開の状況及び本環境評価報告書(案)について計画している市民参加の内容は以下のとおりです。
常設の情報公開について
・ 市のホームページ上の専用ページ設置
市のホームページ上に専用ページを常設し、情報公開及び意見募集を行っています。インターネットを通じた情報公開は、計画策定期間を通じて常に行っており、常に最新情報を掲載するとともに、意見募集の窓口を開いています。
情報公開ページ:http://www.city.a-shi***.jp/ippai03/index.html
(市のトップページからもリンクがあります)
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
また、次のページで、市民の皆さんから寄せられた意見に対する計画への反映結果についてご確認いただけます。
意見と反映結果:http://www.city-a-shi***.jp/ippai03/iken.html
・ リサイクルセンター専用ブース設置
Wリサイクルセンターの展示コーナーに、情報公開の専用ブースを設け、環境配慮計画書等の書類を常備するとともに、最新情報を公開しています。また、環境評価報告書(案)の意見募集期間中には、職員を配置し、相互の意見交換が可能な場を設けています。
設置場所:Wリサイクルセンター1F
住所:A市W区○○―○-○
TEL:○○-○○○○-○○○○
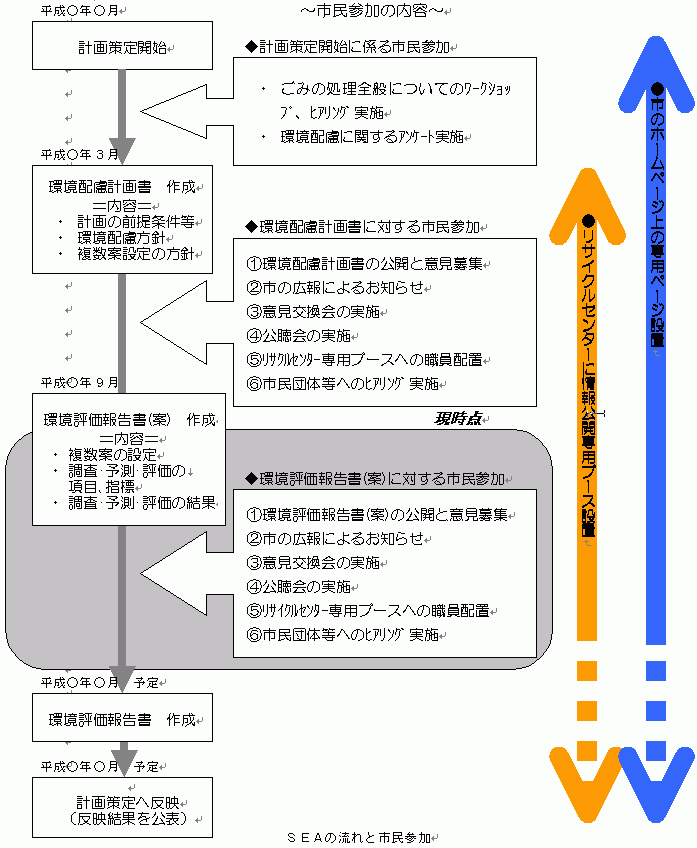
環境評価報告書(案)に係る市民参加
・ 環境評価報告書(案)の公開と意見募集
環境評価報告書(案)の内容について、計画の複数案に対する意見や、環境影響の検討の方法、その結果など、環境面からの幅広い意見を以下のとおり募集しています。
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)でお寄せ下さい。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
住所 A市○区○-○-○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
・ 市の広報によるお知らせ
環境評価報告書の公開やその概要等について、また意見募集についての情報は、市の広報にて既にお知らせしたとおりです。今後も意見交換会、公聴会等についての関連情報を市の広報にて随時お知らせしていきます。
・ 意見交換会の実施
処理計画の複数案の内容や環境影響の調査・予測・評価に関して広く皆さんと意見を交換する場として、環境評価報告書(案)に係る意見交換会を、意見募集期間中に区民センター等において7回程度開催する予定です。
具体的な開催場所及び日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。
・ 公聴会の実施
意見を述べる人の募集:平成○年○月○日~○月○日
公聴会の開催:平成○年○月
(開催場所及び詳細な日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。)
・ 市民団体へのヒアリング実施
環境評価報告書(案)の内容について、市民団体へヒアリングを行います。
対象とする団体は、平成○年度のA市「ごみ問題フォーラム」に参加した6団体に、環境配慮計画書に対して意見提出を行った2団体を加えた、以下の8団体を予定しています。
ヒアリング対象団体一覧
|
団体名 |
|
| 1 | A市ごみを考える市民の会 |
| 2 | 生ごみリサイクルの会 |
| 3 | A市消費者友の会 |
| 4 | 子どもと環境を考える会 |
| 5 | 生活ごみを考える女性の会 |
| 6 | 牛乳パックリサイクルの会 |
| 7 | A市の大気環境をよくする会 |
| 8 | エコフォーラム2000(A市支部) |
環境配慮計画書に対して得られた意見の概要とそれに対する反映結果は次に示すとおりです。
[1]ダイオキシン類は排出量"0"を目指すべきだ。
→ダイオキシン類の排出量を完全に"0"にするには、厳密には焼却量を"0"にする必要があり、現実的には大変困難です。これに対して、現在の施設においても大気中に排出されるダイオキシン類の濃度は、健康に害のない程度です。さらに、今回お示しする複数案はいずれも現在の60%以上ダイオキシン類が削減される計画となっています。しかしながら、市民の皆さんから、ダイオキシン類による影響を懸念する意見が多く寄せられていることから、ごみの発生抑制・再使用・再生利用に努め、ごみの焼却量そのものを可能な限り少なくした案も検討しております。その他、やむを得ず焼却するものについても、焼却施設等の徹底した運転管理により、ダイオキシン類が発生しないように努めます。
[2]沿道の大気汚染の問題は深刻だ。ごみの収集・運搬について地域をまたいで長距離運搬するなどの現状を改善してほしい。
→A市における沿道大気汚染は、ご指摘のとおり大変厳しい状況にあります。このような中、A市では西部のごみを東部へ長距離輸送を行っておりますが、将来的に西部の2つの焼却施設が更新時期を迎えると、その施設の更新の有無で、現在焼却しているごみの運搬を行うかどうかが決まります。そこで、沿道大気の環境改善に着目して、長距離運搬しない、つまり、焼却施設の地域バランスを考えながらそれぞれの施設を更新していくという案を検討しました。
[1]リサイクルのために、一生懸命ごみを分別して出しているが、分別していない人もいる。もっと啓発活動や分別できていない人への指導を徹底すべきではないのか。それにより焼却施設の更新や増設を減らす努力をすべきではないか。
→廃棄物行政全体の取り組みとして、ごみ処理の現状についての情報公開や啓発活動を積極的に行い、ごみの減量化や再資源化に対する理解を深めていただけるよう、より一層の努力をし、ごみを減らし、再資源化により取り組みやすい仕組みづくりに努めます。また、ごみの有料化により、お金を払わないとごみを出せない仕組みづくりをする案もあり、このような施策を通して、ごみを出すことについての市民の皆さん一人一人の意識を変えていければと考えています。
[2]老朽化施設の環境保全対策が適切に行われているのか、非常に心配だ。それらを新設施設に集約して、空き地を緑地にする等の案があってもよいのではないか。
→老朽化施設についても環境保全対策には万全を期しておりますが、更新を控えた複数の施設を、統合化して新たな施設を建設するという案も検討しております。また、施設の更新の際に、積極的な緑の回復を図ることを前提に、総合的に複数案の比較検討することとしました。さらに、今後具体的な個別施設の設置に係る計画に移る際に、重要課題として詳細検討を行います。
[3]普通ごみの収集を3日に減らした具体的な対策案があるが、もっと少ない1日とか2日でもよいのではないか。市民の痛みを伴うような極端な案もあってよいと思う。
→ごみ処理行政は、市民の皆さんの生活に直接的に大きく係わるものであり、また市民の皆さんの協力なくして目標を達成することのできないものでもあります。複数案設定の方針を実現するための具体的施策の中で、収集コストの低減のための対策として、普通ごみの収集を現在の週4日から3日に減らした対策案を示していましたが、市民の皆さんからのご提案により、さらに市民の皆さんの痛みを伴う案として一般ごみの収集日を週2日にする案を検討しました。
[4]分別収集がどんどん細かくなって、煩雑だ。何をどう分けて出せばいいか分からないからと、結局分別せずに出す人も居る。もっとシンプルな分別にできないか。
→本処理計画は、近年の循環型社会の推進のために、新たな再資源化目標の設定と再資源化推進のための施策を設定・展開することを目的の一つとして掲げています。したがって、現状よりもさらに分別収集を減らす案は、この処理計画そのものの目的に反することから、計画案へは反映しておりません。分別が煩雑で分からないというご意見については、より分かりやすい説明資料の配布や、地域センター等での説明会の実施など、市民の皆さんのご理解をいただける努力をしてまいります。
[5]レジ袋の有料化は効果があるのか。デポジット制や分別の徹底を行う案のほうが良いのではないか。また、事業系ごみについては、手数料等の増額の対策を入れた方が良いのではないか。
→レジ袋の有料化については、いままで無料だったものを有料化することで、ごみを減らすだけでなく、市民の皆さんのごみに対する意識を変えていきたいという狙いもあります。デポジット制や分別の徹底、事業系ごみの手数料等の増額についても、同様な考え方から、具体策として計画の複数案の中に反映しました。
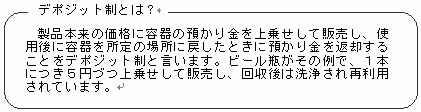
[1]廃棄物処理そのものが温室効果ガスなどの負荷を増やすことになるのではないか。LCAの観点を取り入れた評価が必要。 →ごみの発生段階から最終処分段階までの各段階それぞれで環境影響の調査・予測・評価の項目及び手法について検討しました。また、ごみの量そのものを減らす減量化・再資源化を最大限にするための具体的な対策として、コンポスト補助などを行うとともに、さらなる普及啓発活動に努めていきます。
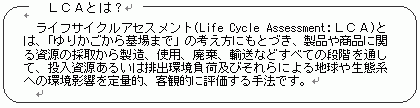
[2]環境にやさしい案であっても、コストが高すぎるというのでは、問題がある。そのあたりが上手く比較検討できるようにしてほしい。
→複数案の予測・評価の際に、コストも併せて比較しました。このコストの中には、施設の運営や維持管理に必要な経費も、減価償却費という形で盛り込んでおります。
[3]市内では、自動車交通による公害や渋滞、交通事故が深刻な問題となっている。市内を産業廃棄物を満載したダンプトラックが通過しており、この規制が必要ではないか。
→産業廃棄物については本処理計画の対象ではありませんが、産業廃棄物運搬車両への指導として、別途検討します。処理計画では、ごみ収集・運搬車両の述べ走行距離を、騒音、振動に関連する指標として選定しました。
[4]収集・運搬車がうるさい。それぞれの計画案でどの程度の道路交通騒音・振動になるのかをきちんと算定してほしい。
→本検討は環境基準との整合について厳密な検討をするものではなく、環境への全体的な負荷をとらえるものと位置づけています。道路交通騒音・振動は、自動車の走行量が多いほど値が高くなることは明らかですので、騒音・振動の値そのものを定量的に予測するのではなく、その指標として収集・運搬車両の述べ走行距離を用い、定性的な予測・評価を行いました。
[5]現状の計画のまま推移していった場合と、環境やコスト面で何がどう変わるのかがよく分からない。それを具体的に分かるようにしてほしい。
→本検討では、計画の内容について、現計画を継続した場合(現計画の継続案)と、環境配慮計画書で皆さんにお示しした複数案設定の方針ごとに、環境に対する影響やコストがどのように違うのかについて検討を行っています。その結果について、この評価報告書にて整理してありますので、ご覧いただきまして、またご意見をいただきたいと存じます。
⇒資料編「2.市民参加」
環境配慮計画書で示した複数案設定の方針及び市民の皆さんから得られた意見等を踏まえ、2020(平成32年)年を目標達成年度とし、現計画の継続案を加えたA案、B案、C案、D案、E3案の5案を設定しました。
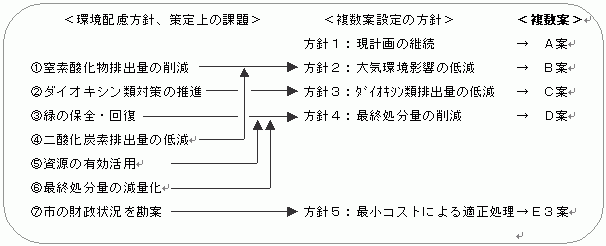
A案(現計画の継続)
新たな施策の追加、変更等は行わず、現行の処理計画(平成7年策定)に従った廃棄物処理を行う案です。そのため、老朽化し更新時期を迎える焼却施設(K焼却場、W焼却場)は、現在の位置で更新します。なお、同案では、改定計画の目的でもある環境基本計画に掲げた再資源化目標25%を満足できません。
B案(大気環境影響の低減)
A市の最大の環境上の課題である大気環境への影響を最小化するため、燃焼、溶融等の大気汚染物質を排出する可能性のある中間処理や、沿道大気環境の汚染に寄与する収集運搬車両の述べ走行距離をできるだけ少なくする案です。
中間処理量を削減し、ダイオキシン類の発生の原因となるプラスチック類の焼却量を減らすため、ごみは極力分別します。焼却灰についは、燃焼・再利用化せず最終処分場に埋立処分します。中間処理施設は、収集・運搬を効率化し車両走行量を削減するため、4箇所に設置することとし、更新時期を迎える焼却施設(K焼却場、W焼却場)は、原則として西部の現在位置で更新をします。
C案(ダイオキシン類排出量の低減)
焼却量を減らすとともに、少ない焼却場で連続的に処理することとします。そのため、減量化、再資源化に務め、対象期間内に更新時期を迎える2箇所の焼却施設(K焼却場、W焼却場)の更新を行わない案です。ごみ排出の抑制、分別収集の徹底により再資源化を行い、焼却対象となるごみを極力少なくします。また、新規中間処理施設を必要とする灰の溶融処理、生ゴミの堆肥化等は行いません。
更新時期を迎える2箇所の焼却施設(K焼却場、W焼却場)は更新せず廃止します。これにより現行4箇所の中間処理施設のうち、東部の2箇所のみが稼働することとなり、西部の廃棄物は東部へ移送して処理することとなります。ガラス、金属の再資源化を行うための再資源化施設、ごみの移送を効率的に行うための中継施設が必要となります。ごみ運搬車が長距離の移送をすることに伴い、市域の交通量が増大することが予想されます。
なお、C案では、本処理計画の対象期間外ではありますが、将来、東部の2箇所の焼却施設が更新時期を迎えた際には、処理の地域的不均衡是正をにらみ、施設建設位置の検討が必要となります。
D案(最終処分量の削減)
B案同様、ごみの減量化、分別を最大限に行った上で、さらに生ゴミの堆肥化、焼却灰の溶融処理による再資源化等も行い、最終処分量を最小化する案です。分別収集、堆肥化、溶融処理等にコストがかかり、また焼却や溶融、収集運搬により大気汚染物質の排出量が多くなります。
焼却施設は、B案同様、4箇所に分散し設置することとします。
E3案(最小コストによる適正処理)
E案は、処理コストをできるだけ低減する案です。一般ごみの収集回数を削減(週4日→3日)するほか、現状以上の分別収集はコストを増大させるため行わないこととします。また、更新時期を迎える2箇所の焼却施設(K焼却場、W焼却場)のうち1箇所を廃止し、処理を集中させることにより効率化を図ります。更新する1箇所の施設は、現在位置している西部において更新することとします。
ところが、このE案では再資源化率が環境基本計画に定める目標値(25%)を下回り、処理計画の目的を達成することができませんでした。そこで、E案を改良し、プラスチックの分別収集を行うことで分別収集率を向上させたE2案を新たに設定しました。さらに、環境配慮計画書に寄せられた、「もっと収集日を減らした、市民の痛みを伴う案があっても良いのではないか」との意見を踏まえ、一般ごみの収集回数を削減(週4日→2日)したE3案を設定しました。
なお、E3案では、本処理計画の対象期間外ではありますが、将来、東部の焼却施設が更新時期を迎えた際に、さらなる集中処理化を検討する可能性があります。
以上、A案、B案、C案、D案、E3案の5つを複数案としました。
これらの複数案について、実施する具体的な施策や、市民の皆さんの生活への影響の内容について詳細を次に示します。これらの具体的な施策や市民の皆さんの取り組み・努力によって、計画案が成り立つものと考えます。よって、減量化率・再資源化率が最も高いD案では、市民の皆さんの経費負担やごみを出さない、減らす努力量・難しさ及び分別の手間、煩雑さが最も大きくなります
設定した複数案の詳細
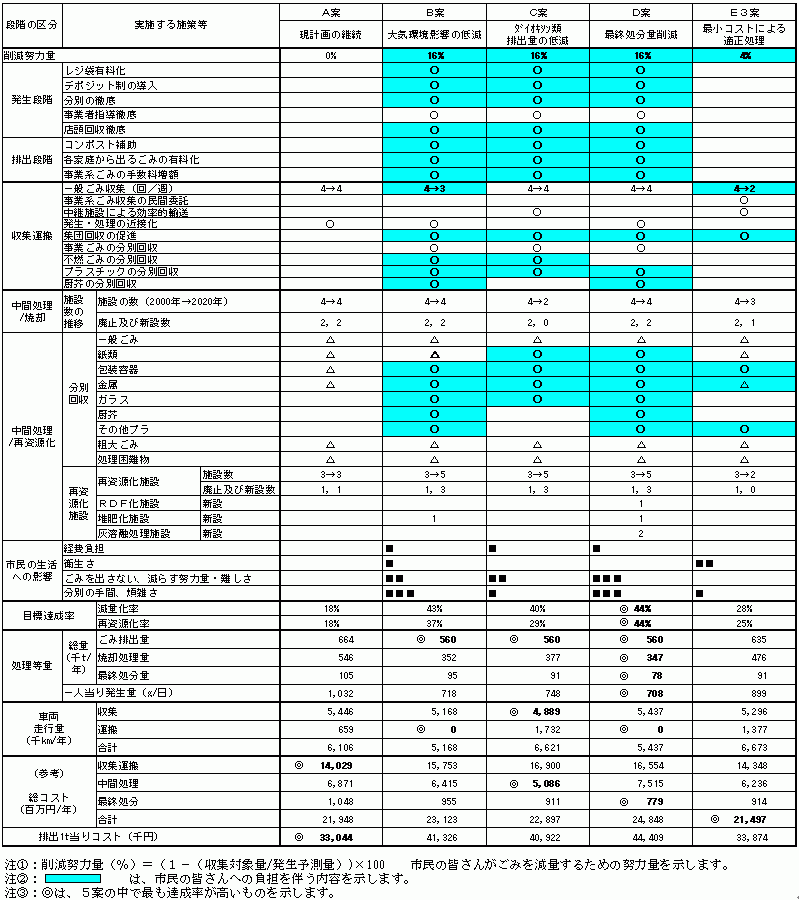
また、各複数案ごとの特徴を整理すると、次のとおりとなります。
設定した複数案の内容
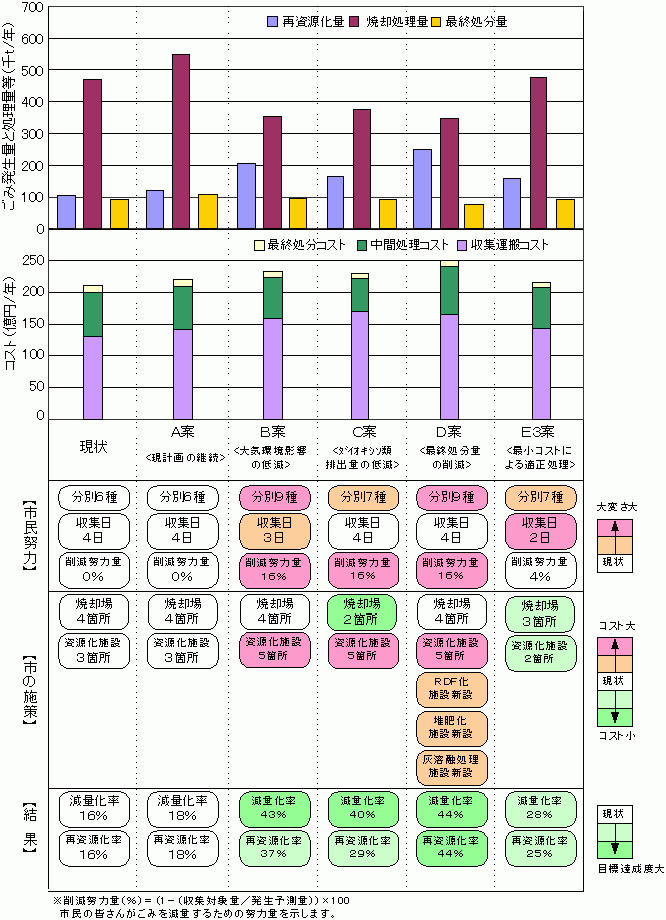
調査・予測・評価の項目は、環境配慮計画書の「環境配慮方針」に示した項目を基本とし、環境配慮計画書に寄せられた意見等を踏まえて以下の6項目としました。
|
[1] 大気汚染(窒素酸化物) |
[4] 緑の保全・回復 |
各複数案により、左記以外の項目に著しい影響を及ぼすことがないかどうかについて確認するため、複数案実施のための具体的対策、施設整備等がA市環境基本計画に示される環境要素へ、どのような影響を与えるのか検討しました。その結果、左記の6項目を指標とすることにより、関連の深い環境要素への影響を評価できることが確認されました。
複数案実施のための具体的対策等が環境に及ぼす影響
|
>段階の区分 |
>複数案実現のための具体的対策・施設整備等 |
A市環境基本計画における環境要素 |
||||||||||||||
| 健康な市民生活が営める安全なまち |
>うるおいとやすらぎのある快適なまち |
>地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち |
||||||||||||||
|
>大気 |
>水 |
>土 |
>化学物質 |
>騒音・振動 |
>建造物影響 |
>水辺 |
>緑 |
>生物 |
>都市アメニティ |
>都市気温 |
>資源・廃棄物 |
>地球環境 |
>エネルギー |
>水循環 |
||
| 発生段階 | レジ袋の有料化、デポジット制の導入 | + | ||||||||||||||
| 分別徹底のための啓発活動 | + | |||||||||||||||
| 事業者指導の徹底 | + | |||||||||||||||
| 店頭回収の徹底 | + | |||||||||||||||
| 排出段階 | コンポスト補助 | - | + | |||||||||||||
| ごみの有料化、事業系ごみの手数料増額 | + | |||||||||||||||
| 収集・運搬段階 | 普通ごみ収集を週2日へ | ++ | + | - | + | + | + | |||||||||
| 中継施設設置による効率的輸送 | ++ | +- | + | + | ||||||||||||
| 発生・処理の近接化(処理の不均衡是正) | ++ | + | + | |||||||||||||
| 事業ごみの分別収集 | + | ++ | ||||||||||||||
| プラスチックの分別収集 | + | ++ | + | |||||||||||||
| 生ごみの分別収集 | + | ++ | +- | |||||||||||||
| 中間処理段階 | RDF化による処理量削減 |
-- |
- | - | + | ++ | ++ | ++ | ||||||||
| 焼却処理施設の統合 | +- | + | + | +- | ||||||||||||
| K焼却場の更新 | + | + | + | + | + | + | + | ++ | ||||||||
| リサイクル等中間施設の建設 | - | + | - | - | + | + | ||||||||||
| 最終処分段階 | 焼却灰の溶融処理(減量化) | -- | - | - | ++ | + | + | - | - | |||||||
| 再資源化利用 | 焼却灰の有効利用 | + | ||||||||||||||
| 堆肥化施設の導入 | - | - | - | - | -- | - | + | - | ||||||||
| 項 目 | 大気汚染(窒素酸化物) | 微量有害化学物質 | 騒音・振動 | 緑の保全・回復 | 廃棄物の排出 | 地球温暖化(二酸化炭素) | 地球温暖化(二酸化炭素) | |||||||||
| 指 標 | NOx排出量 | ダイオキシン類排出量 車両走行量 | 最終処分量公園地化面積 | 減量化率再資 | 源化率公衆衛生の維持 | 二酸化炭素排出量 | 二酸化炭素排出量 | |||||||||
凡例:+ 好ましい影響、- 好ましくない影響、+- 好ましい影響と好ましくない影響の両方が考えられる場合
選定した各項目について環境影響を調査・予測・評価するための指標(以下、評価指標といいます。)は、環境配慮計画書に寄せられた意見等を参考に、次に示す通り設定しました。
評価指標
| 項目 | 評価指標 | 指標の選定理由 |
| 大気汚染 |
年間の窒素酸化物排出総量 |
A市では大気質の状態が良好とはいえず、特に自動車による窒素酸化物が課題とされているため。各案比較のために、窒素酸化物の年間の排出総量を指標とした。 |
|
>微量有害化学物質 |
年間のダイオキシン類の排出総量 |
焼却処理施設に関し、ダイオキシン類への住民の関心が非常に高いため。各案比較のために、年間の排出総量を指標とした。 |
| 騒音・振動 |
年間の車両走行量 |
道路交通騒音、振動についての市民からの苦情があるため。各案比較のために、道路交通騒音、振動の原因となる自動車走行の、年間の車両走行量を指標とした。 |
|
騒音・振動 |
道路交通騒音、振動についての市民からの苦情があるため。定量的な評価は処理施設の位置等が決まっていないため困難であるが、定性的な評価が可能であるため。 |
|
| 緑の保全・回復 |
最終処分量 |
A市は土地利用が高度に進んでおり、緑の保全・回復が課題であるため。 |
|
公園地化面積(施設跡地を公園利用する) |
処理計画自体に属地性がないため、最終処分量の削減及び廃止する施設の跡地の公園利用が緑の保全・回復に貢献できると考え、最終処分量と公園地化面積を指標とした。 |
|
| 地球温暖化 |
年間の二酸化炭素の排出総量 |
焼却場、収集・運搬車両などからの二酸化炭素の排出が考えられるため。各案比較のために、二酸化炭素の年間の排出総量を指標とした。 |
| 廃棄物の排出 |
減量化率、再資源化率 |
処理計画の目的との整合を図るため。 |
|
公衆衛生の維持 |
処理計画本来の目的との整合を図るため。定性的ながらも、専門家の意見をもとに予測が可能であるため。 |
検討の基本的な考え方
大気汚染、微量有害化学物質、地球温暖化に係る環境影響の検討は、既存資料をもとに、活動量に排出原単位等を乗じることにより、環境影響(排出量等)の総量を求める手法によりました。
騒音・振動に係る環境影響の検討は、その指標となる車両走行量を求める手法によりました。また、緑の保全・回復について
は、最終処分量を計画により求めるとともに、施設跡地を緑化するという前提のもとに、施設跡地の面積を指標としました。廃棄物の排出については、計画に基づき、廃棄物の減量化率等を求めました。
・ 大気汚染(窒素酸化物)
窒素酸化物(NOX)の排出総量の算出は、以下の手法によりました。
(固定発生源からのNOX排出量)=(廃棄物焼却量)×(固定源からの排出原単位)
固定源からの排出原単位:678.5g-NOx/焼却t(既往施設の実績による)
(収集車からのNOX排出量)=(収集車の走行距離)×(収集車からの排出原単位)}
収集車からの排出原単位:2.462g-NOx/km
(運搬車からのNOX排出量)=(運搬車の走行距離)×(運搬車からの排出原単位)
運搬車からの排出原単位=1.057g-NOx/km
収集車:ごみの収集、中間処理施設、集積場への運搬に使用する車両。
運搬車:処理施設間及び処理施設から最終処分場までの運搬に使用する車両。
・ 微量有害化学物質(ダイオキシン類)
ダイオキシン類の排出総量の算出は、以下の手法によりました。
(新設焼却施設からのダイオキシン類排出量)
=(焼却量)×(排出ガス量原単位)×(規制濃度)
(既設焼却施設からのダイオキシン類排出量)
=(焼却量)×(排出ガス量原単位)×(排出濃度実績値)
※
ただし、溶融施設からは、ダイオキシン類は排出されないと整理しました。
・ 騒音・振動
車両走行量は、ごみの収集量と車両走行量の実績から、収集量-収集効率関数を作成し、ごみの分別区分毎の走行量を求めました。(車両走行量は、収集車と運搬車の延べ走行距離です。)
騒音・振動については、車両走行量より、定性的に予測しました。
・ 緑の保全・回復
緑の保全については、最終処分量を計画より求めました。
緑の回復については、廃止する焼却施設の跡地が公園化されるものとして算出しました。
・ 地球温暖化
温室効果ガス(二酸化炭素:CO2)の排出総量の算出は、以下の手法によりました。
(焼却施設からのCO2排出量)=(廃棄物焼却量)×(焼却施設からの排出原単位)
焼却施設からの排出原単位:239.2kg-C/焼却t (環境省資料に基づく)
(収集車からのCO2排出量)=(収集車の走行距離)×(収集車からの排出原単位)
収集車からの排出原単位:126.5g-C/収集t
(運搬車からのCO2排出量)=(運搬車の走行距離)×(運搬車からの排出原単位)
運搬車からの排出原単位=66.9g-C/輸送t
その他、灰溶融施設からの二酸化炭素排出、堆肥化に伴うメタン発生について考慮しました。
・ 廃棄物の排出
減量化率、再資源化率については、計画における算出量によるものとしました。
公衆衛生の維持については、現状に対する衛生さの変化の度合いを、専門家の意見をもとに定性的に予測することとしました。
以上で使用した原単位については、資料編に示します。
⇒資料編「3.汚染物質排出量等の算出方法について」
影響の予測結果は、次に示すとおりです。
影響の予測結果
ここでは、複数案の比較結果を次の視点ごとにそれぞれ示します。
| [1] 対2000年(平成12年)比で増加するのか、減少するのかについて定性的な記述で示します。 | →比較結果1 |
| [2] 2000年(平成12年)を1.0とした時の比率をレーダーチャートで示します。 | →比較結果2 |
| [3] 市民の皆さんの生活への影響について示します。 | →比較結果3 |
比較結果1 対2000年比の増減について定性的に記述した比較
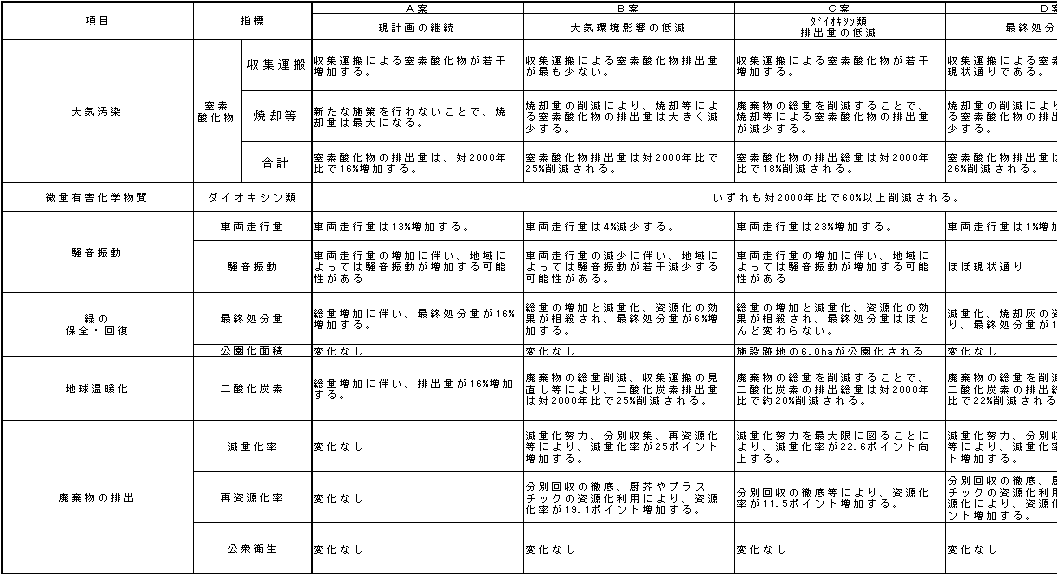
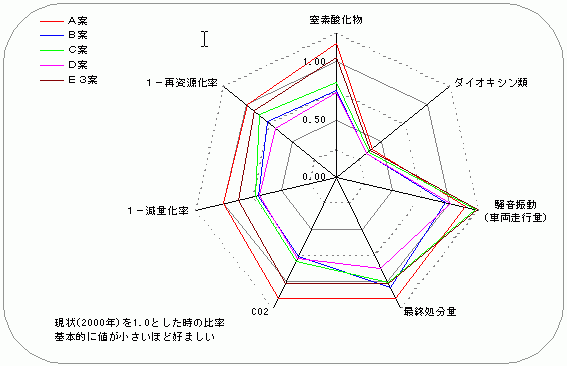
比較結果2 レーダーチャートによる比較
比較結果3 市民の皆さんの生活への影響についての比較
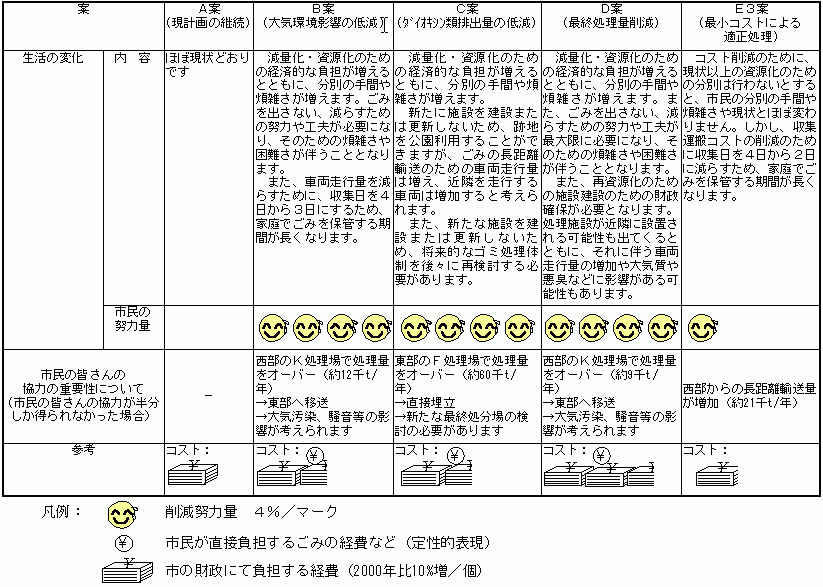
各環境項目からみて、それぞれどの案が最も環境負荷が小さいか、またそれぞれの案を採用する場合の留意点について、次の表に示します。
各案の比較結果と留意事項
A案:現計画の継続
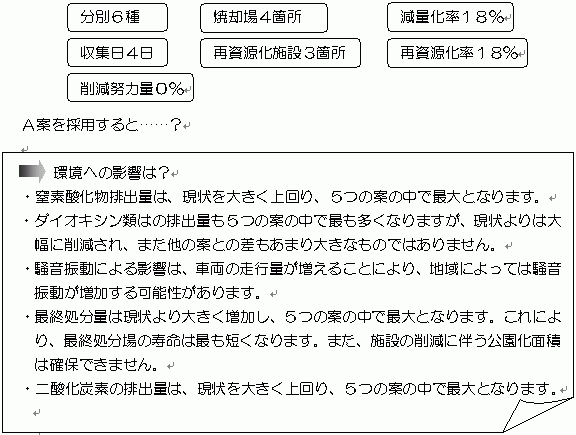
※ 留意事項
A案は、減量化率及び再資源化率が現状よりも低下することから、処理計画の目的を達成することができません。
※ 地域バランスは?
市内の焼却場の分布バランスは保たれます。
※ 市民の皆さんの生活への影響は?
ほぼ現状どおりと考えます。
※ コストは?
コストは現状に比べ10%増となり、5案の中で2番目に安い案となっています。
B案:大気環境影響の低減
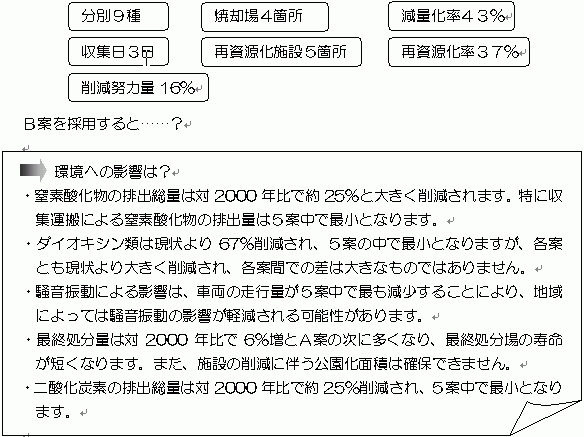
※ 留意事項
最終処分量がわずかながら増加することから、将来的には処分場の寿命が若干短命化することとなります。
※ 地域バランスは?
市内の焼却場の分布バランスは保たれます。
※ 市民の皆さんの生活への影響は?
・現在よりも、経済的負担や分別の手間、ごみを出さない努力や減らす工夫をしていただかなければなりません。
・車両走行量を減らすために収集日を減らすため、家庭でごみを保管していただく時間が長くなります。
※ 皆さんの協力の重要性について
・市民の皆さんの協力が予定の半分程度しか得られない場合、西部のK処理場での必要処理量が処理能力をオーバーします。
・K処理場の処理能力をオーバーする場合、市内の他の処理場(F処理場:東部)へごみの長距離輸送を行う可能性が出てきます。この場合、輸送の運搬車両による大気質への影響が考えられ、大気環境影響の低減というB案の方向性そのものが崩れることになります。
・ごみの長距離輸送を行わない場合は、直接埋立処分をする可能性があります。この場合、埋立量が増加することにより、最終処分場が若干短命化すると考えられます。
※ コストは?
コストは、対2000年比で16%増となり、5案の中で2番目に高くなっています。
C案:ダイオキシン類排出量の低減
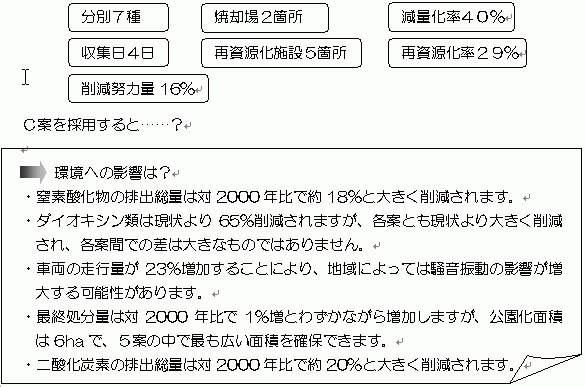
※ 留意事項
・市民の皆さんの分別の手間が増えることや、更新時期を迎える西部の焼却場を更新せずに、東部へ長距離輸送することにより地域不均衡が生じることについて、慎重に検討する必要があります。
・ごみを長距離輸送することにより車両走行量が増大するため、収集・運搬車両について低公害型の導入、車両の大型化などの検討を行う必要があります。
・将来的には東部のF処理センターが更新を迎える時期に、市の廃棄物処理そのものを維持するために、一時的に焼却場を東部に用意するのか、新たな焼却場について西部も含めて施設配置を検討するのか等について検討する必要があります。
※ 地域バランスは?
・更新時期を迎える焼却施設を更新しないことから、ごみを長距離輸送する必要が生じ、東西の地域不均衡が生じます。
※ 市民の皆さんの生活への影響は?
・現在よりも、経済的負担や分別の手間、ごみを出さない努力や減らす工夫をしていただかなければなりません。
※ 皆さんの協力の重要性について
・市民の皆さんの協力が半分程度しか得られない場合、東部のF処理場での必要処理量が処理能力をオーバーします。
・F処理場の処理能力をオーバーする場合、C案では西部の焼却場を廃止する予定であることから、市内では焼却処分できなくなります。対応策としては、最終処分場での埋立処分が考えられますが、数年短命化することになります。さらに、早急に次期候補地を検討する必要が出てきます。
※ コストは?
コストは、対2000年比で15%増となります。
D案:最終処分量の削減
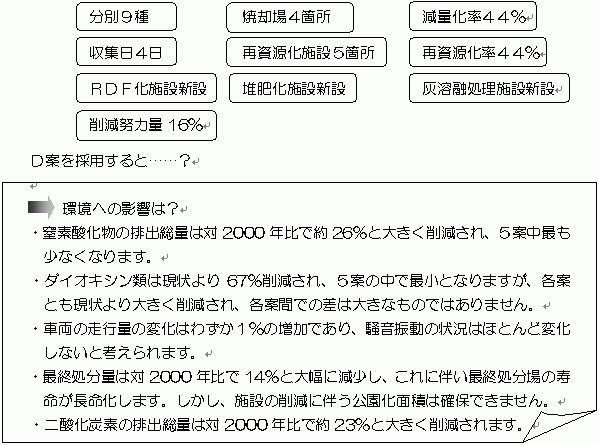
※ 留意事項
・市民の皆さんの分別の手間が増加すること及び焼却灰の溶融施設や堆肥化施設の建設コストが必要となる点について、市の財政面の確保やそれを支える市民・企業等の協力が不可欠となります。
・新しい施設の整備・運営には、その施設立地を含め、十分な環境配慮が必要となります。
・市民の皆さんのごみを減らしたり再利用するための分別の手間や努力、工夫が不可欠であり、最大限に努力して頂く必要があります。
※ 地域バランスは?
市内の焼却場の分布バランスは保たれます
※ 市民の皆さんの生活への影響は?
・経済的負担や分別の手間、ごみを出さない努力や減らす工夫を最大限にしていただかなければなりません。
・再資源化のための施設設置のための財源確保が必要となります。
・処理施設が近隣に設置される可能性が出てきます。
・処理施設の設置に伴う車両走行量の増加、大気質への影響や悪臭の発生などの可能性が出てきます。
※ 市民の皆さんの協力の重要性について
・市民の皆さんの協力が半分程度しか得られない場合、K処理場の処理量をオーバーします。
・K処理場の処理能力をオーバーする場合、市内の他の処理場(F処理場:東部)へごみの長距離輸送を行う可能性が出てきます。この場合、輸送の運搬車両による大気質への影響が考えられます。
・ごみの長距離輸送を行わない場合は、直接埋立処分をする可能性があります。この場合、最終処分量削減というD案の方向性そのものが崩れることになります。また、埋立量が増加することにより、最終処分場が若干短命化することになります。
※ コストは?
コストは、対2000年比で25%増と5案の中で最も高くなります。
E3案:最小コストによる適正処理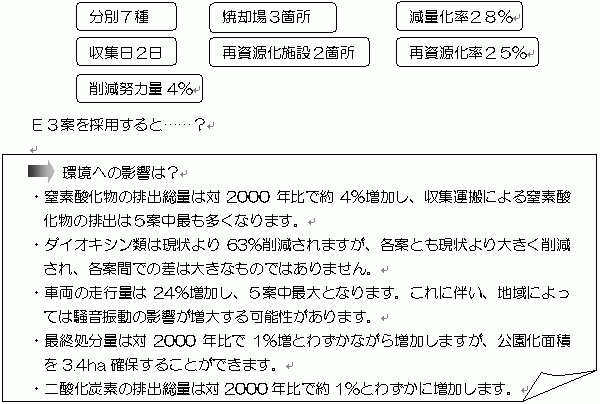
※ 留意事項
・コスト削減のために、更新時期を迎える2つの西部の焼却場を統合します。これにより、西部の一部のごみを東部に長距離輸送することとなり、地域不均衡が生じることについて慎重に検討する必要があります。
・統合する焼却場については、更新の時期に焼却量の見直しや他の焼却場との配置バランスを考慮した立地の検討を行う必要があります。
・普通ごみの収集日を4日から2日に減らすことに関して、収集サービスの質が下がること及びごみを家庭に数日間置いておくことにより衛生さが低下することについても、公衆衛生の観点からの検討や、対策を講じる必要があります。
・車両走行量が最大となることから、収集・運搬車両について低公害車の導入、車両の大型化などの検討を行う必要があります。
※ 地域バランスは?
更新時期を迎えた2つの焼却場の統合にあたって、他の焼却場との配置バランスを考慮した立地の検討を行う必要があります。
※ 市民の皆さんの生活への影響は?
・収集運搬コストの削3減のために収集日を減らすため、家庭でごみを保管していただく時間が長くなります。
・分別のための手間はほぼ現状どおりです。
※ 市民の皆さんの協力の重要性について
・市民の皆さんの協力が半分程度しか得られない場合、当初の計画で予定している西部から東部へのごみの長距離輸送量が若干増加します。
※ コストは?
コストは、対2000年比で8%増と、5案の中で最も安くなります。
今後は、この複数案の比較検討結果に対して、広く市民の皆さんから意見を募り、最終的に環境評価報告書をとりまとめます。どのように今回の検討結果を反映したかについては、後日市から反映結果を公開します。
A市一般廃棄物処理計画 環境評価報告書(案)に関する問いあわせ先:
A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
TEL:○○-○○○○-○○○○
FAX:○○-○○○○-○○○○
E-mail:iken.WMP@city.a-shi****.jp
<資料編>
1. 環境配慮計画書の概要1.1 一般廃棄物処理計画とは?
ごみは毎日の生活の中で発生し続けています。ごみ問題は、市民の皆さんの生活の中で大きな問題であり、市でも様々な取り組みを行っていますが、市民の皆さんに身近な取り組みとして、ごみの収集や処理があります。これらのごみ処理については、市の一般廃棄物処理計画(以下処理計画といいます。)という計画の中で、全体の処理量や処理方法について将来の計画をたて、この処理計画に基づいて施設の整備や日々の収集・運搬や処理を行っています。
ごみの発生量や処理量は、どれくらい減量化や再資源化に取り組むかによって、その量が異なり、また処理の方法には焼却や埋立などがあります。処理計画では、減量化や再資源化のためにどのような具体的な施策を行うかを検討し、将来のごみの発生量や処理量を予測し、その処理方法や必要となる施設の数までを検討します。
処理計画で、市全体のごみの発生量や処理量の目標値、その処理方法と必要な施設の数までを決めた後には、必要となる個別の施設について、その立地や計画内容の検討が行われることになります。
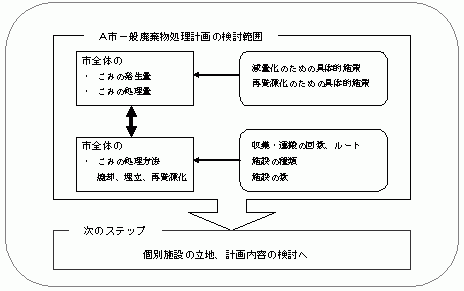
|
|
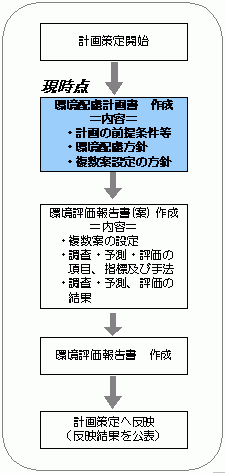 |
1.3 戦略的環境アセスメントの実施と環境配慮計画書の位置づけ
処理計画は、減量化や再資源化のための具体的な施策や、収集方法、中間処理等の施設建設の有無など、市民の皆さんの生活や市の環境に深く関連した事項を定めるものです。その内容には、市民の皆さんの手間や経済的な負担を伴うばかりでなく、環境への影響が考えられるものもあります。
このため、市では、処理計画の策定段階で、複数の計画案の環境への影響検討を行うことにより、環境負荷のより少ない環境保全に配慮した計画づくりを実施することとしました。この方法を戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment:SEA 以下、SEAといいます。)といいます。
SEAでは、まず、処理計画の改定にあたり重視すべきこととして、環境配慮方針を策定します。処理計画は、この環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要がありますが、このような視点に沿って、処理計画が目指す具体的な方向性となる複数案設定の方針を策定します。
環境配慮計画書は、計画の背景や必要性、環境配慮方針や複数案設定の方針について、市民の皆さんの理解を深めていただき、今後の環境影響検討についての意見を伺うために作成したものです。
今後は、皆さんからの意見を反映させながら複数案設定の方針に基づいて複数案の設定を行い、それぞれの複数案ごとに環境への影響を予測・評価します。これらの複数案や評価結果などを環境評価報告書(案)としてとりまとめ、再び皆さんの意見を伺います。これらを踏まえて最終的な環境評価報告書を作成します。
このような過程を経て、環境負荷のより少ない、環境保全に配慮した計画づくりを進めていきます。
環境配慮方針とは、処理計画を策定するにあたって特に環境保全上重視すべき事項を示すものです。処理計画はこの方針に沿ったものであることが求められています。
・ 窒素酸化物排出量の削減
・ ダイオキシン類対策の推進
・ 緑の保全・回復
・ 二酸化炭素排出量の削減
・ 資源の有効活用
計画策定上の課題及び環境配慮方針を踏まえた、計画の目的は以下のとおりです。
・ 2020年(平成32年)において、現処理計画がそのまま継続した場合における廃棄物の発生量の予測値(668.5千t/年)と比べ、発生量を極力低減すること。
・ 再資源化率について、環境基本計画の目標値(25%)を達成すること。
・ 排出削減や再資源化のための諸施策にもかかわらず発生する廃棄物が、適正に処理処分されること。
・ 老朽化施設の廃止又は更新が適切に図られること。
・ ダイオキシン類等の微量有害化学物質の排出が現状より抑制されること。
・ 最終処分場を極力延命化するため、最終処分量の削減が図られること。
・ 廃棄物処理の本来の目的である、公衆衛生の維持を図ること。
処理計画は、環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要があります。このような視点に沿って、どのような方向に計画が向かうべきであるのかという、処理計画が目指す具体的な方向性を、環境影響を評価する複数案の設定の方針としました。ここでは、環境配慮方針及び計画策定上の課題から、優先すべき事項を洗い出し、これらをまとめた上で、現計画を継続する方針を加え、複数案設定の5つの方針を策定しました。
今後、これらの方針ごとに、市民の皆さんの意見等を踏まえながら、複数案を作成していきます。
●現計画を継続します
現計画を改定することなく、そのまま継続させた場合についての案を作成します。
●大気環境影響をできるだけ低減します
窒素酸化物等の大気汚染対策が課題となっていることから、焼却及び廃棄物運搬に伴う大気汚染物質排出の低減を図ることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物の分別および減量化に着目します。さらに、沿道大気汚染対策として、廃棄物及び焼却灰の運搬に伴う車両交通量が減少するよう、焼却施設等の配置(ごみの排出と処理の市内バランス)に着目します。
地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物処理量の減量化に着目します。さらに、焼却施設等の配置により変化する廃棄物及び焼却灰の運搬に伴う車両交通量、収集の回数に着目します。
●ダイオキシン類排出量をできるだけ低減します
ダイオキシン類の排出を削減することが望ましいと考えます。廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出削減のため、廃棄物の分別および減量化に着目します。また、焼却施設の縮小を望む声があることから、計画期間内に廃止を迎える焼却施設については、新たに更新・新設しない案を検討します。緑の保全を望む声があることから、焼却施設等の跡地は、公園などの緑地として活用を図ります。
●最終処分量をできるだけ削減します
資源の有効活用については、市民の協力を最大限求めて分別、再資源化を追求する案と、再資源化施設を新たに建設し活用することで再資源化を追求する案を検討します。
最終処分場の新規建設を極力回避することが望ましいと考えます。そのため、分別回収の徹底や再資源化施設の有無等による最終処分量の増減に着目します。
●最小コストによる適正処理を図ります
市の財政状況を勘案し、コストに着目します。
1.7 環境配慮計画書への意見募集
環境配慮計画書の内容について、処理計画の複数案設定の方針、具体的施策、あるいは環境影響の検討の方法など、環境面からの幅広い意見を募集しています。
ここで皆さんから寄せられた意見を踏まえて、今後複数案を作成していく予定です。
・ 環境配慮計画書の公開と意見募集
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)でお寄せ下さい。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
住所 A市○区○-○-○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
・ 意見交換会の実施
処理計画の今後の方向性や環境影響評価に関して広く皆さんと意見を交換する場として、環境配慮計画書に係る意見交換会を、意見募集期間中に区民センター等において7回程度行う予定です。
具体的な開催場所及び日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。
2.1.1 環境配慮計画書の公開
・ 公開場所等
[1]市のホームページ上の専用ページ設置
市のホームページ上に専用ページを常設し、情報公開を行っている。インターネットを通じた情報公開は、計画策定期間を通じて常に行っており、常に最新情報を掲載するとともに、意見募集の窓口を開いている。
情報公開ページ:http://www.city.a-shi***.jp/ippai03/index.html
(市のトップページからもリンクあり)
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
また、次のページでは、市民から寄せられた意見に対する計画への反映結果について掲載し、随時更新を行っている。
意見と計画への反映結果掲載ページ:http://www.city-a-shi***.jp/ippai03/iken.html
<情報公開の内容>
平成○年○月 処理計画策定の開始のお知らせ~その根拠と必要性~
平成○年○月 環境審議会答申「今後の廃棄物行政のあり方について」 全文掲載
平成○年○月 環境配慮計画書 全文掲載
意見交換会、意見募集、公聴会等のスケジュール掲載
[2]リサイクルセンター専用ブース設置
Wリサイクルセンターの展示コーナーに、情報公開の専用ブースを設け、環境配慮計画書等の書類を常備するとともに、最新情報を公開した。また、環境配慮計画書の意見募集期間中には、要員を配置し、相互の意見交換が可能な場を設けた。
設置場所:Wリサイクルセンター1F
(A市W区○○―○-○)
[3]A市○○局廃棄物担当課執務室内
A市○○局の廃棄物担当課に環境配慮計画書等の書類を常備した。
・ 意見募集
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)とした。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
・ 寄せられた意見の概要
募集期間に寄せられた意見は58件であった。区別の意見数は表2-2及び表2-3に示すとおりである。
表 2-2 区別意見数
| 区 | FE区 | ME区 | M区 | MW区 | FW区 | 全市 |
| 意見数 | 11 | 10 | 9 | 16 | 12 | 58 |
表2-3 環境配慮計画書に係る意見提出状況
| 種類 | 数量(通) |
| 封書 | 7 |
| ハガキ | 21 |
| FAX | 18 |
| メール | 12 |
| 合計 | 58 |
寄せられた意見の概要は次のとおりである。
-環境保全上着目すべき事項について
・ダイオキシン類は排出量"0"を目指すべきだ。
・沿道の大気汚染の問題は深刻だ。ごみの収集・運搬について地域をまたいで長距離運搬している現状を改善してほしい。
-複数案設定の方針について
・老朽化施設の環境保全対策が適切に行われているのか、非常に心配だ。それらを新設施設に集約して、空き地を緑地にする等してもよいのではないか。
・普通ごみの収集を3日に減らす具体的な案があるが、もっと少ない1日とか2日でもよいのではないか。市民の痛みを伴うような極端な案もあってよいと思う。
・分別収集がどんどん細かくなって、煩雑だ。何をどう分けて出せばいいか分からないからと、結局分別せずに出す人も居る。もっとシンプルな分別にできないか。
-調査・予測・評価について
・環境にやさしい案であっても、コストが高すぎるというのでは、問題がある。そのあたりが上手く比較検討できるようにしてほしい。
・市内では、自動車交通による公害や渋滞、交通事故が深刻な問題になっている。市内を産業廃棄物を満載したダンプトラックが通過しており、この規制が必要ではないか。
・収集・運搬がうるさい。それぞれの計画案でどの程度の道路交通騒音・振動になるのかをきちんと算定してほしい。
・現状の計画のまま推移していった場合と、環境やコスト面で何がどう変わるのかがよく分からない。それを具体的に分かるようにしてほしい。
2.1.2 意見交換会
・ 意見交換会実施状況
環境配慮計画書に係る意見交換会の実施状況は表2-2に示すとおりである。
表 2-2 環境配慮計画書に係る意見交換会実施状況
| 開催場所 | 開催日時 | 参加者数 |
| FW区文化センター | 平成○年○月○日18時~20時 | 26名 |
| MW区区役所A会議室 | 平成○年○月○日16時~18時 | 27名 |
| M区文化センター | 平成○年○月○日18時~20時 | 21名 |
| ME区文化センター | 平成○年○月○日18時~20時 | 33名 |
| FE区文化センター | 平成○年○月○日18時~20時 | 25名 |
| A市情報プラザ | 平成○年○月○日18時~20時 | 18名 |
| MEプラザ別館 | 平成○年○月○日16時~18時 | 24名 |
・ 意見交換会で得られた意見と複数案への反映結果
意見交換会で得られた意見の概要と複数案への反映結果は次の通りである。
表 2-3 説明会で得られた意見の概要と複数案への反映結果
| 意見の概要 | 複数案への反映結果 |
|
もっとごみの減量化に取り組んで、施設の必要性そのものを見直すべき |
廃棄物行政全体の取り組みとして、ごみ処理の現状や啓発活動を積極的に行い、ごみの減量化や再資源化に対する理解を深めてもらう努力をし、減量化・再資源化率の向上に努める。また、その結果を処理計画や個別の施設計画へ随時反映させる。 |
|
収集日を少なくしてもいいので、環境への負担の少ない案を出してほしい。 |
普通ごみの収集日を週3日から週2日にした複数案を検討した。 |
|
ごみの分別が面倒くさい。もっと分別を簡素化してほしい。 |
本計画は、近年の循環型社会の推進のために、新たな資源化目標の設定と資源化推進のための施策を設定・展開することを目的の一つとして掲げている。分別収集を減らす案については、この方向性に反するため、今後も計画案へは反映しない。 |
2.1.3 公聴会
・ 公聴会実施状況
環境配慮計画書に係る公聴会の実施状況は下記のとおりである。
開催日時:平成○年○月○日 14時~16時
開催場所:A市市役所
出席者:市民A、市民B、市民C、市民Dら 計8人
・ 公聴会で得られた意見の概要
公聴会において、以下のような意見が市民から述べられた。
-複数案設定の方針について
・ リサイクルのために一生懸命ごみを分別して出しているが、中には分別していない人もいる。もっと啓発活動や分別できていない人への指導を徹底すべきではないのか。それにより焼却施設の更新や増設を減らす努力をすべきではないか。
・ レジ袋の有料化は効果があるのか。デポジット制や分別の徹底を行う案のほうが良いのではないか。また、事業系ごみについては、手数料等の増額の対策を入れた方が良いのではないか。
-影響評価について
・ 廃棄物処理そのものが温室効果ガスなどの負荷を増やすことになるのではないか。LCAの観点を取り入れた評価が必要。
2.1.4 市民団体ヒアリング
環境配慮計画書の内容について、以下の市民団体にヒアリングを行った。得られた意見の内容は、次のとおりである。
表2-4 ヒアリング対象団体一覧
| 団体名 | |
| 1 | A市ごみを考える市民の会 |
| 2 | 生ごみリサイクルの会 |
| 3 | A市消費者友の会 |
| 4 | 子どもと環境を考える会 |
| 5 | 生活ごみを考える女性の会 |
| 6 | 牛乳パックリサイクルの会 |
・リサイクルについて、もっと市民への啓発活動を行うべきである。
・資源ごみの集団回収をもっと促進してはどうか。
・生活ごみについては、家庭での減量化そのものに取り組むべきである。
・将来をごみで溢れた社会にしないために、今から積極的に減量化・再資源化に取り組むべきである。
一般に、廃棄物の減量化や分別により、1箇所1回当りの廃棄物収集量が減少すると、収集効率が低下し、収集単位量当り(t当り)の車両走行量やコストが増大する。
この変化は、以下に示すとおり推計した。
3.1.1 収集量と収集車走行距離
平成○年度のA市における、各収集区分毎の収集総量と収集単位量当りの車両走行距離を図3-1に示す。図の曲線より近似式を求め、分別された廃棄物の区分毎に、収集量当りの車両走行距離を推計した。近似式は以下の通りである。
走行距離=2×106/年間収集量+7.4
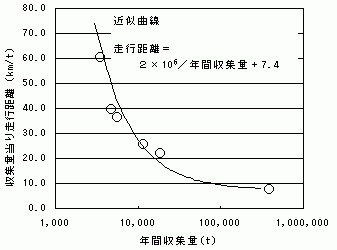
図3-1 廃棄物の年間収集量と収集量当りの車両走行距離
3.1.2 収集量と収集コスト
収集距離と同様、年間収集量と収集コストの近似式を求めた。近似式は以下の通りである。
収集コスト=1.2×106/(年間収集量)1/2
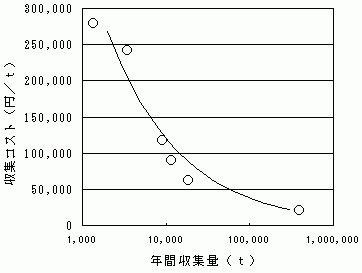
図3-2 廃棄物の年間収集量と収集量当りのコスト
3.2 収集運搬に係る汚染物質等排出原単位
収集運搬に係る窒素酸化物、二酸化炭素の排出原単位は、下記資料によった。
収集車からの窒素酸化物排出原単位:2.462g/km
収集車からの二酸化炭素排出原単位:126.5g/km
(東京都内自動車排出ガス量算出及び将来予測評価報告書 平成12年3月 における、平成12年の小型貨物車の10km/h走行時の原単位を用いた)
運搬車からの窒素酸化物排出原単位:1.057g/km
運搬車からの二酸化炭素排出原単位:66.9g/km
(東京都内自動車排出ガス量算出及び将来予測評価報告書 平成12年3月 における、平成12年の小型貨物車の30km/h走行時の原単位を用いた)
3.3 焼却処理による汚染物質等排出原単位
3.3.1 窒素酸化物
焼却施設からの窒素酸化物排出量は、既往施設における測定実績から、焼却量当りの排出量を求め、4施設の平均値である678.8g/焼却tを用いた。
表3-1 既往施設における窒素酸化物排出量
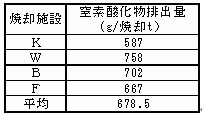
(資料:平成○年度 A市環境事業年報に基づく)
3.3.2 ダイオキシン類
焼却施設からのダイオキシン類排出濃度は、既往施設については、表3-2に示す、平成○年度における既往施設の測定値を用いた。また新規施設については、新規焼却施設に係る規制濃度である0.1 ng-TEQ/Nm3を用いた。
廃棄物焼却量当りの排出ガス量は、B焼却施設計画諸元資料より、4,832Nm3/焼却tとした。
表3-2 既往施設におけるダイオキシン類排出濃度
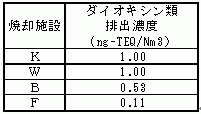
(資料:平成○年度 A市環境事業年報に基づく)
3.3.3 二酸化炭素
・ 廃棄物の焼却処理
廃棄物の焼却処理に伴う二酸化炭素排出原単位は、「平成○年 二酸化炭素排出量評価報告書 環境省」に示されたごみの焼却による二酸化炭素排出係数(バイオマス起源のものを含む)239.2kg-C/焼却tを用いた。
1996年のIPCCガイドラインの変更に伴い、バイオマス起源廃棄物の焼却に伴う二酸化炭素排出は排出量に含めないとされたことから、現在の排出係数は本報告書に示した値と大きく異なっているため、注意が必要である。
・ 施設稼働に伴う電力消費
焼却施設は稼働に伴い電力を消費するが、一方でK施設を除く新しい施設では、発電を行っている。このため、発電量と消費電力量の差し引きから、廃棄物焼却量当りの電力量を求め、二酸化炭素量に換算した。その結果、廃棄物焼却量当りの電力量は、発電量が消費電力量を上回るため、二酸化炭素排出量は-3.75kg-C/tとなった。なお、電力CO2原単位は、「温室効果ガス排出量算定方法に関する検討結果」(平成12年9月 環境庁)における、他人(一般電気事業者)から供給された電力の使用に伴う排出原単位によった。
この値は、焼却に伴う二酸化炭素排出量のわずか1.6%であるため、本報告書における二酸化炭素量の算出には用いていない。
表3-3 焼却施設稼働に伴う電力消費・発電量と二酸化炭素量
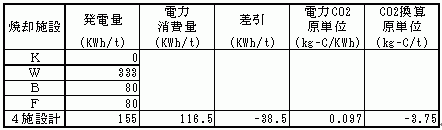
溶融処理を行う場合の処理方式は決まっていないが、ここでは電気による溶融を想定し、消費電力量を二酸化炭素排出量に換算する手法によった。溶融方式毎の電力消費量は、「最先端のごみ処理溶融技術」(日報企画販売)に記載された実績値を用いた。
表3-4 溶融施設稼働に伴う電力消費と二酸化炭素量
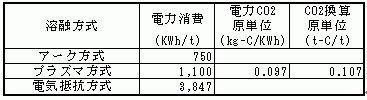
厨芥を堆肥化した場合については、堆肥から発生するCH6(メタン)を二酸化炭素量に換算し、推計に加えた。なお、堆肥の供給により化学肥料の使用量が削減が見込まれるものとし、化学肥料との差し引きを考慮した。
| 堆肥からのメタン発生量 | 19.9 kg-Ceq/t |
| 化学肥料削減による温室効果ガス排出量削減 | 9.0 kg-Ceq/t |
| 差し引き | 10.9 kg-Ceq/t |
(出典:食品残渣を対象とした循環・再資源化処理方式のライフサイクルアセスメント廃棄物学会論文集 Vol.12,No.5)