一般廃棄物処理計画策定における 戦略的環境アセスメント試行ガイドライン
一般廃棄物処理計画策定における 戦略的環境アセスメント試行ガイドラインTOPへ戻る
III.添付資料1
SEAケーススタディ
A市一般廃棄物処理計画 環境配慮計画書
平成○年3月
A市○○局
目 次
| <概 要> | ||
| 一般廃棄物処理計画とは? | III-2 | |
| 計画改定の必要性 | III-2 | |
| 戦略的環境アセスメントの実施と本環境配慮計画書の位置づけ | III-2 | |
| 環境配慮方針 | III-3 | |
| 計画の目的 | III-4 | |
| 複数案設定の方針 | III-4 | |
| 環境配慮計画書への意見募集 | III-5 | |
| 今後の予定 | III-6 | |
| <本 編> | ||
| 一般廃棄物処理計画とは? | III-9 | |
| 戦略的環境影響評価の実施と本環境配慮計画書の位置づけ | III-10 | |
| 市民参加 | III-11 | |
| 計画改定の必要性 | III-16 | |
| 計画改定の必要性 | III-16 | |
| 地域の特性(ごみ処理の現状) | III-18 | |
| 行財政の状況 | III-24 | |
| 処理計画の検討 | III-25 | |
| 環境配慮方針の策定 | III-28 | |
| 環境保全上着目すべき事項 | III-28 | |
| 環境配慮方針 | III-31 | |
| 計画の目的 | III-32 | |
| 複数案設定の方針 | III-33 | |
| 今後の予定 | III-38 | |
| <資料編> | ||
| 1. | 背景 | III-41 |
| 1.1 地域の特性 | III-41 | |
| 1.2 環境配慮方針 | III-48 | |
| 2. | 市民参加 | III-49 |
| 2.1 計画策定に係る情報公開等の経緯 | III-49 | |
| 2.2 一般廃棄物の処理全般に関する意見収集 | III-50 | |
| 2.3 環境配慮に関する市民アンケート | III-51 | |
<概 要>
ごみは毎日の生活の中で発生し続けています。ごみ問題は、市民の皆さんの生活の中で大きな問題であり、市でも様々な取り組みを行っていますが、市民の皆さんに身近な取り組みとして、ごみの収集や処理があります。これらのごみ処理については、市の一般廃棄物処理計画(以下処理計画といいます。)という計画の中で、全体の処理量や処理方法について将来の計画をたて、この処理計画に基づいて施設の整備や日々の収集・運搬や処理を行っています。
ごみの発生量や処理量は、どれくらい減量化や再資源化に取り組むかによって、その量が異なり、また処理の方法には焼却や埋立などがあります。処理計画では、減量化や再資源化のためにどのような具体的な施策を行うかを検討し、将来のごみの発生量や処理量を予測し、その処理方法や必要となる施設の数までを検討します。
処理計画で、市全体のごみの発生量や処理量の目標値、その処理方法と必要な施設の数までを決めた後には、必要となる個別の施設について、その立地や計画内容の検討が行われることになります。
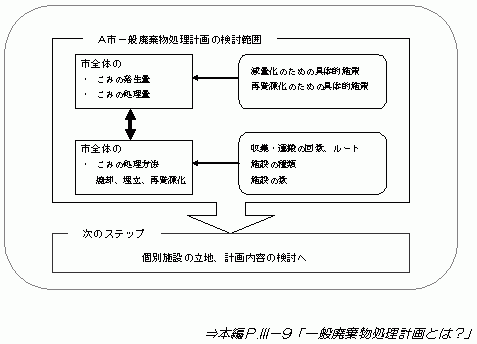
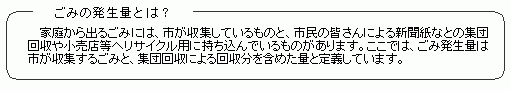
処理計画は、おおむね5年ごとに改定することになっており、A市では、平成2年に計画を策定し、平成7年に見直しを行いましたが、現在再度改定の時期を迎えています。
処理の現状を見ると、ごみ排出量の計画の値を実績の値が大きく下回っており、近年の傾向を踏まえた計画が求められているとともに、焼却施設の老朽化や最終処分場の逼迫などの課題を抱えています。また、財政面では廃棄物処理に必要な費用が市の年間の一般会計予算の約4%を占めており、コストの削減が急務となっています。
そのほか、環境問題の質が従来の特定汚染源の公害問題を中心とした環境問題からダイオキシン類などの微量有害化学物質や地球温暖化等の地球環境問題へと変化しているとともに、循環型社会を目指しリサイクル関連法が整備されるなど、廃棄物を取り巻く外部環境が大きく変化してきています。平成12年4月には容器包装リサイクル法が施行され、ガラスびんやペットボトルだけでなく、プラスチック製や紙製の容器包装についても分別収集が義務づけられ、さらに、平成15年3月には循環型社会形成推進基本計画が公開されるなど、新たな法令等が整備されてきています。今後は、環境負荷の小さい社会形成に向け、さらなる3R(発生抑制:リデュース、再使用:リユース、再生利用:リサイクル)の実践が重要です。
A市では、これらの法令等や社会のニーズに対応した処理計画の改定が求められています。
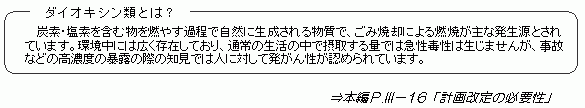
処理計画は、減量化や再資源化のための具体的な施策や、収集方法、中間処理等の施設建設の有無など、市民の皆さんの生活や市の環境に深く関連した事項を定めるものです。その内容には、市民の皆さんの手間や経済的な負担を伴うばかりでなく、環境への影響が考えられるものもあります。
このため、市では、処理計画の策定段階で、複数の計画案の環境への影響検討を行うことにより、環境負荷のより少ない環境保全に配慮した計画づくりを実施することとしました。この方法を戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment:SEA 以下、SEAといいます。)といいます。
|
SEAでは、まず、処理計画の改定にあたり重視すべきこととして、環境配慮方針を策定します。処理計画は、この環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要がありますが、このような視点に沿って、処理計画が目指す具体的な方向性となる複数案設定の方針を策定します。 |
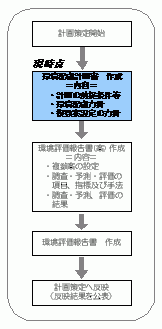 |
環境配慮方針とは、処理計画を策定するにあたって特に環境保全上重視すべき事項を示すものです。処理計画はこの方針に沿ったものであることが求められています。
- 窒素酸化物排出量の削減
- ダイオキシン類対策の推進
- 緑の保全・回復
- 二酸化炭素排出量の削減
- 資源の有効活用
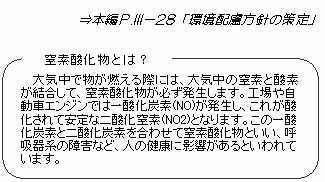
計画策定上の課題及び環境配慮方針を踏まえた、計画の目的は以下のとおりです。
- 2020年(平成32年)において、現処理計画がそのまま継続した場合における廃棄物の発生量の予測値(668.5千t/年)と比べ、発生量を極力低減すること。
- 再資源化率について、環境基本計画の目標値(25%)を達成すること。
- 排出削減や再資源化のための諸施策にもかかわらず発生する廃棄物が、適正に処理処分されること。
- 老朽化施設の廃止又は更新が適切に図られること。
- ダイオキシン類等の微量有害化学物質の排出が現状より抑制されること。
- 最終処分場を極力延命化するため、最終処分量の削減が図られること。
- 廃棄物処理の本来の目的である、公衆衛生の維持を図ること。
⇒本編P.III-32「計画の目的」
処理計画は、環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要があります。このような視点に沿って、どのような方向に計画が向かうべきであるのかという、処理計画が目指す具体的な方向性を、環境影響を評価する複数案の設定の方針としました。ここでは、環境配慮方針及び計画策定上の課題から、優先すべき事項を洗い出し、これらをまとめた上で、現計画を継続する方針を加え、複数案設定の5つの方針を策定しました。
今後、これらの方針ごとに、市民の皆さんの意見等を踏まえながら、複数案を作成していきます。
●現計画を継続します
現計画を改定することなく、そのまま継続させた場合についての案を作成します。
●大気環境影響をできるだけ低減します
窒素酸化物等の大気汚染対策が課題となっていることから、焼却及び廃棄物運搬に伴う大気汚染物質排出の低減を図ることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物の分別および減量化に着目します。さらに、沿道大気汚染対策として、廃棄物及び焼却灰の運搬に伴う車両交通量が減少するよう、焼却施設等の配置(ごみの排出と処理の市内バランス)に着目します。
地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物処理量の減量化に着目します。さらに、焼却施設等の配置により変化する廃棄物及び焼却灰の運搬に伴う車両交通量、収集の回数に着目します。
●ダイオキシン類排出量をできるだけ低減します
ダイオキシン類の排出を削減することが望ましいと考えます。廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出削減のため、廃棄物の分別および減量化に着目します。また、焼却施設の縮小を望む声があることから、計画期間内に廃止を迎える焼却施設については、新たに更新・新設しない案を検討します。緑の保全を望む声があることから、焼却施設等の跡地は、公園などの緑地として活用を図ります。
●最終処分量をできるだけ削減します
資源の有効活用については、市民の協力を最大限求めて分別、再資源化を追求する案と、再資源化施設を新たに建設し活用することで再資源化を追求する案を検討します。
最終処分場の新規建設を極力回避することが望ましいと考えます。そのため、分別回収の徹底や再資源化施設の有無等による最終処分量の増減に着目します。
●最小コストによる適正処理を図ります
市の財政状況を勘案し、コストに着目します。
⇒本編P.III-33「複数案設定の方針」
環境配慮計画書の内容について、処理計画の複数案設定の方針、具体的施策、あるいは環境影響の検討の方法など、環境面からの幅広い意見を募集しています。
ここで皆さんから寄せられた意見を踏まえて、今後複数案を作成していく予定です。
・ 環境配慮計画書の公開と意見募集
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)でお寄せ下さい。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
住所 A市○区○-○-○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
・ 意見交換会の実施
処理計画の今後の方向性や環境影響評価に関して広く皆さんと意見を交換する場として、環境配慮計画書に係る意見交換会を、意見募集期間中に区民センター等において7回程度行う予定です。
具体的な開催場所及び日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。
⇒本編P.III-11「市民参加」
複数案設定の方針の中には、市民の皆さんの経済的な負担や分別の手間が増えるものもあります。また、施設の更新・新設により環境への影響が懸念されるものもあります。今後、これらの複数案の方針ごとに市民の皆さんの意見等を踏まえながら複数案を作成していきます。さらに、それぞれの複数案について、どの程度の環境影響が考えられるのかを予測・評価し、複数案の比較検討を行った上で、環境影響のより少ない処理計画を目指していきます。
⇒本編P.III-10「戦略的環境アセスメントの実施と本環境配慮計画書の位置づけ」
A市一般廃棄物処理計画 環境配慮計画書に関する問いあわせ先:
A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
TEL:○○-○○○○-○○○○
FAX:○○-○○○○-○○○○
E-Mail:iken.WMP@city.a-shi****.jp
<本 編>
ごみは毎日の生活の中で発生し続けています。ごみ問題は、市民の皆さんの生活の中で大きな問題であり、市でも様々な取り組みを行っていますが、市民の皆さんに身近な取り組みとして、ごみの収集や処理があります。これらのごみ処理については、市の一般廃棄物処理計画(以下処理計画といいます。)という計画の中で、全体の処理量や処理方法について将来の計画をたて、この処理計画に基づいて施設の整備や日々の収集・運搬や処理を行っています。
市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第六条により処理計画を定めるよう義務づけられており、一般廃棄物(以下、ごみと略します)の将来の発生量、分別の区分、処理施設の整備に関する事項等を定めることになっています。
ごみの発生量や処理量は、どれくらい減量化や再資源化に取り組むかによって、その量が異なり、また処理の方法には焼却や埋立などがあります。処理計画では、減量化や再資源化のためにどのような具体的な施策を行うかを検討し、将来のごみの発生量や処理量を予測し、その処理方法や必要となる施設の数までを検討します。
処理計画で、市全体のごみの発生量や処理量の目標値、その処理方法と必要な施設の数までを決めた後には、必要となる個別の施設について、その立地や計画内容の検討が行われることになります。
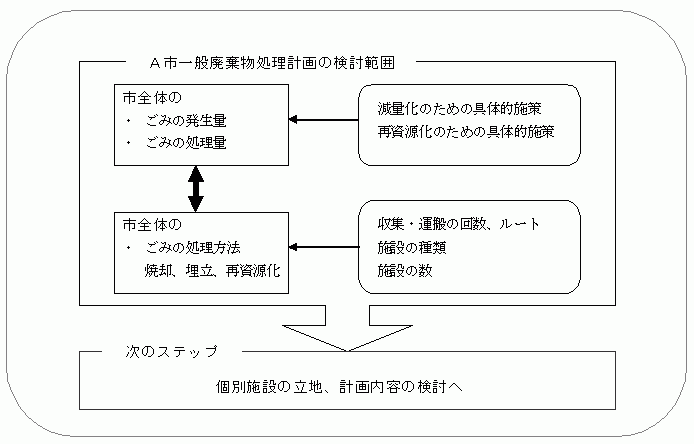
一般廃棄物処理計画(以下、処理計画といいます。)は、今後の一般廃棄物(以下、ごみといいます。)の減量化や処理(収集、運搬、中間処理、最終処分等)の基本的な内容を定めるものであり、市民の皆さんや企業による減量化の努力量や、焼却処理施設建設の有無など、市民の皆さんの生活や市の環境に深く関連した事項を定めるものです。大きくは、将来のごみ発生量、分別の区分、処理施設の整備に関する事項を定めることになっています。
処理計画の具体的な検討事項には、市民の皆さんの手間や経済的な負担を伴うばかりでなく、環境への影響が考えられるものもあります。このため、市では、本計画の策定にあたって戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment:SEA 以下、SEAといいます。)を実施することにより、環境影響のより少ない処理計画を目指すこととしました。
SEAとは、さまざまな計画の策定段階で環境への影響検討を行うことにより、より環境に配慮した計画づくりを進めようとするものです。
SEAでは、まず、処理計画の改定にあたり重視すべきこととして、環境配慮方針を策定します。処理計画は、この環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要がありますが、このような視点に沿って、処理計画が目指す具体的な方向性となる複数案設定の方針を策定します。
本環境配慮計画書は、計画の背景や必要性、環境配慮方針や複数案設定の方針について、市民の皆さんの理解を深めていただき、今後の環境影響検討についての意見を伺うために作成したものです。
今後は、皆さんからの意見を反映させながら複数案設定の方針に基づいて複数案の設定を行い、それぞれの複数案ごとに環境への影響を予測・評価します。これらの複数案や評価結果などを環境評価報告書(案)としてとりまとめ、再び皆さんの意見を伺います。これらを踏まえて最終的な環境評価報告書を作成します。
このような過程を経て、環境負荷のより少ない、環境保全に配慮した計画づくりを進めていきます。
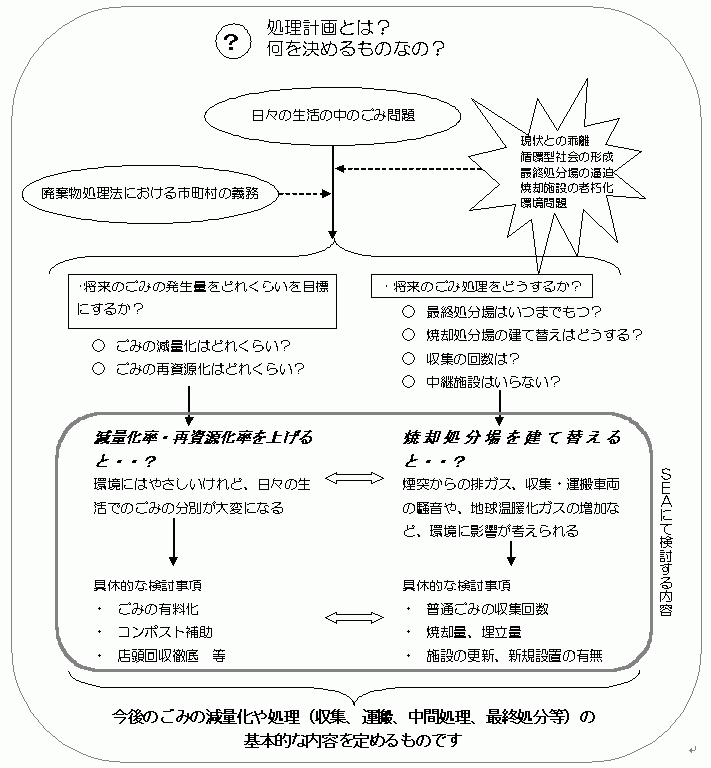
処理計画とSEAの関係
本SEAにおける市民参加の機会と方法等については、SEAの実施に先立つ処理計画全般に関するアンケート調査結果と専門家の意見を踏まえ、次に示すとおり実施することとしました。市民参加の機会は、処理計画の策定開始から終わりまで、常時市のホームページ上の専用ページ及び専用ブースにおける情報公開を行うとともに、意見募集の窓口を開いています。さらに、SEAの中で特に重要と考えられる、環境配慮計画書、環境評価報告書(案)の2つの段階では、計画書、報告書等の公開、市の広報によるお知らせ、意見交換会の開催、文書での意見募集等を行っていきます。
また、計画策定実施の告知時に、ごみの処理全般についてのワークショップとヒアリングならびに環境配慮に関するアンケートを実施しました。意見の内容については、資料編に示しています。
⇒資料編「2.市民参加」
常設の情報公開の状況及び本環境配慮計画書、環境評価報告書(案)について計画している市民参加の内容は以下のとおりです。
常設の情報公開について
市のホームページ上の専用ページ設置
市のホームページ上に専用ページを常設し、情報公開及び意見募集を行っています。インターネットを通じた情報公開は、計画策定期間を通じて常に行っており、常に最新情報を掲載するとともに、意見募集の窓口を開いています。
情報公開ページ:http://www.city.a-shi***.jp/ippai03/index.html
(市のトップページからもリンクがあります)
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
また、次のページで、市民の皆さんから寄せられた意見に対する計画への反映結果についてご確認いただけます。
意見と反映結果:http://www.city-a-shi***.jp/ippai03/iken.html
リサイクルセンター専用ブース設置
Wリサイクルセンターの展示コーナーに、情報公開の専用ブースを設け、環境配慮計画書等の書類を常備するとともに、最新情報を公開しています。また、環境配慮計画書や環境評価報告書(案)の意見募集期間中には、職員を配置し、相互の意見交換が可能な場を設けています。
設置場所:Wリサイクルセンター1F
住所:A市W区○○―○-○
TEL:○○-○○○○-○○○○
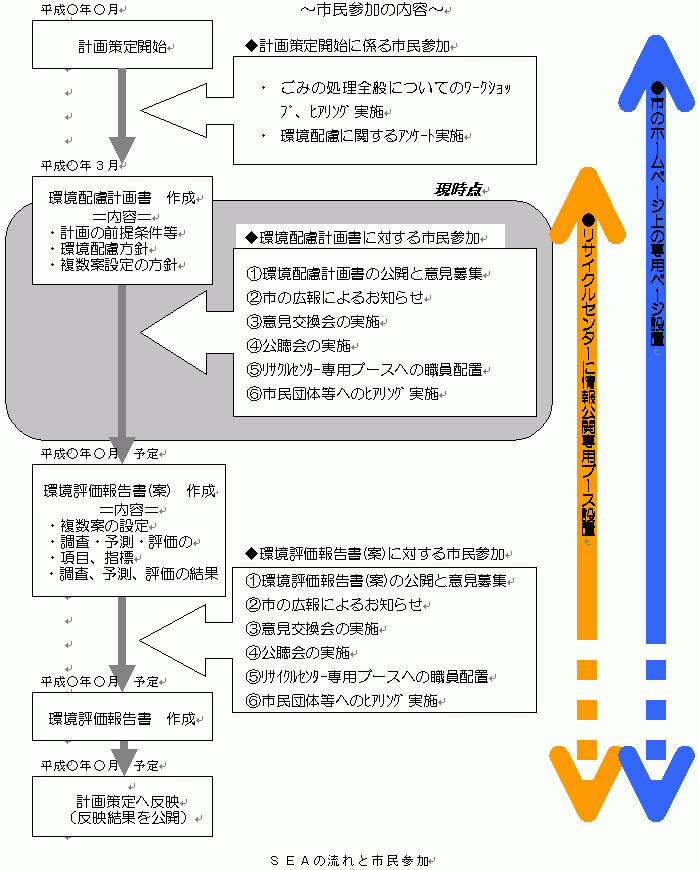
環境配慮計画書に係る市民参加
(1) 環境配慮計画書の公開と意見募集
環境配慮計画書の内容について、計画の複数案設定の方針、具体的施策、あるいは環境影響の検討の方法など、環境面からの幅広い意見を募集しています。
期間:平成○年○月○日~○月○日
募集方法:意見は、ハガキ、封書、FAX、メール、持参のいずれかの方法(文書)でお寄せ下さい。
提出先:A市 ○○局 廃棄物担当課 一般廃棄物処理計画SEA担当
住所 A市○区○-○-○○
FAX ○○-○○○○-○○○○
意見募集アドレス:iken.WMP@city.a-shi****.jp
(2) 市の広報によるお知らせ
環境配慮計画書の公開やその概要等について、また意見募集についての情報は、市の広報にて既にお知らせしたとおりです。今後も意見交換会、公聴会等についての関連情報を市の広報にて随時お知らせしていきます。
(3) 意見交換会の実施
処理計画の今後の方向性や調査・予測・評価に関して広く皆さんと意見を交換する場として、環境配慮計画書に係る意見交換会を、意見募集期間中に区民センター等において7回程度行う予定です。
具体的な開催場所及び日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。
(4) 公聴会の実施
意見を述べる人の募集:平成○年○月○日~○月○日
公聴会の開催:平成○年○月
(開催場所及び詳細な日時については、その内容が決定次第、ホームページや市の広報に掲載します。)
(5) 市民団体へのヒアリング実施
処理計画の今後の方向性や環境配慮計画書の内容について、市民団体へのヒアリングを行います。対象とする団体は、平成○年度のA市「ごみ問題フォーラム」に参加した以下の団体を予定しています。
ヒアリング対象団体一覧
|
|
団体名 |
| 1 | A市ごみを考える市民の会 |
| 2 | 生ごみリサイクルの会 |
| 3 | A市消費者友の会 |
| 4 | 子どもと環境を考える会 |
| 5 | 生活ごみを考える女性の会 |
| 6 | 牛乳パックリサイクルの会 |
環境評価報告書(案)に係る市民参加
今後、本環境配慮計画書に寄せられた意見を反映させながら複数案設定の方針に基づいて複数案の設定を行い、それぞれの複数案ごとに環境への影響を予測・評価します。これらの複数案や評価結果などを環境評価報告書(案)としてとりまとめ、再び皆さんの意見を伺います。これらを踏まえて最終的な環境評価報告書を作成します。
環境評価報告書(案)に係る市民参加は、次の方法で実施する予定です。詳細は、環境評価報告書(案)にて記載します。
・ 環境評価報告書(案)の公開及び意見募集
・ 市の広報によるお知らせ
・ 意見交換会の実施
・ 公聴会の実施
・ リサイクルセンター専用ブースへの職員配置
・ 市民団体へのヒアリング実施
処理計画の策定根拠
市町村は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」第6条により、処理計画の策定を義務づけられており、そのうちごみ処理に関する内容は以下の通りです。
(1) 計画内容
・ ごみの発生量と処理量の見込み
・ ごみの排出抑制のための方策
・ 分別収集するごみの種類・区分
・ ごみの適正な処理及び処理者
・ 処理施設の整備
・ その他の必要事項
(2) 計画期間など
・ 目標年次:10年から15年先
・ 改定 :おおむね5年ごと
処理計画策定の経緯
A市における処理計画の策定経緯は以下のとおりです。
(1) 平成2年計画
昭和○~○年の実績を踏まえ、平成2~17年までの処理計画を策定しました。最終処分場の確保が困難であることから、全量焼却を計画しました。
(2) 平成7年計画
平成○年段階で排出量が著しく増大したこと、廃棄物の組成が大きく変化したことなどから、平成2年計画を更新し、平成7~22年の計画を策定しました。排出量の増大を踏まえ、分別・再資源化による処理処分量の抑制を計画しました。
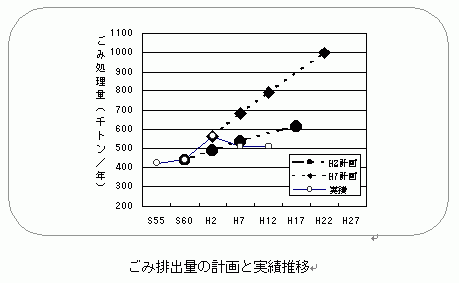
処理計画に求められていること
処理の現状を見ると、ごみ排出量の計画の値を実績の値が大きく下回っており、近年の傾向を踏まえた計画が求められています。
そのほか、従来の特定汚染源の公害問題を中心とした環境問題からダイオキシン類などの微量有害化学物質や地球温暖化等の地球環境問題へと環境問題の質が変化しているとともに、循環型社会を目指しリサイクル関連法が整備されるなど、廃棄物を取り巻く外部環境が大きく変化してきています。平成12年4月には容器包装リサイクル法が施行され、ガラスびんやペットボトルだけでなく、プラスチック製や紙製の容器包装についても分別収集が義務づけられ、さらに、平成15年3月には循環型社会形成推進基本計画が策定されるなど、新たな法令等が整備されてきています。今後は、環境負荷の小さい社会形成に向け、さらなる3R(発生抑制:リデュース、再使用:リユース、再生利用:リサイクル)の実践が重要です。
A市では、これらの法令や社会のニーズに対応した計画の改定が求められています。
現行処理計画、現状と要請事項
| 項目 |
現行処理計画 (H12年現在) |
現状 | 要請事項 |
| ごみ発生量 | 792千t | 572千t |
近年の傾向を踏まえた計画が必要 |
| 再資源化率 | 15% | 15.7% |
循環型社会をさらに推進するため、新たな目標設定が必要 |
| 外部環境 | 特になし |
・環境問題の質の変化(ダイオキシン類、温室効果ガス等) ・循環型社会形成推進基本法、循環型社会形成推進基本計画、リサイクル関連法等の制定 |
法整備を踏まえた排出量予測や施策整備が必要 |
ごみの排出量
一人当りのごみ排出量は平成元年まで増加傾向にあり、総排出量は平成元年に約570千t/年となり最大になりました。その後、集団回収が開始されたこと等により総排出量は減少し、平成12年には約500千t/年程度になりました。
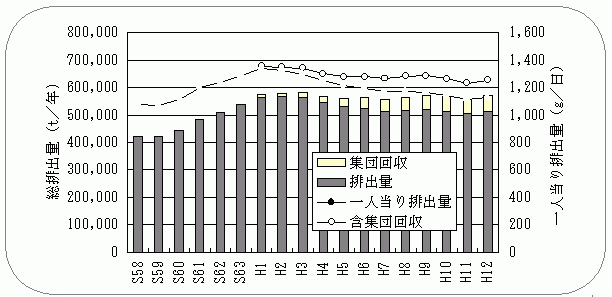
ごみ排出量の推移
ごみの組成
ごみの組成は水分が約52.3%、可燃分が約42.8%で、可燃分のうち紙類が約37.0%、厨芥類が約21.5%となっています。
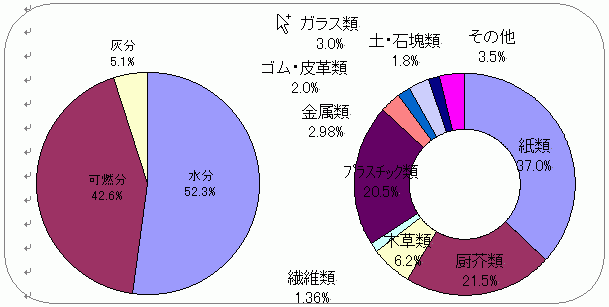
ごみの組成
ごみ処理フロー
A市においてごみは、市による収集、自己搬入、市民団体による回収の3つの方法により、収集されています。その中で、普通ごみと粗大ごみの中の可燃物及び事業系ごみについては焼却処理を行っています。その他、粗大ごみの金属類や雑金属類、空きびん、空き缶、古紙及びペットボトルについては再資源化を行っています。再資源化は、市の資源化と市民団体による回収分とを併せて、全体の約16%となっています。
なお、使用済み乾電池などの処理困難物については、市が回収し保管しています。
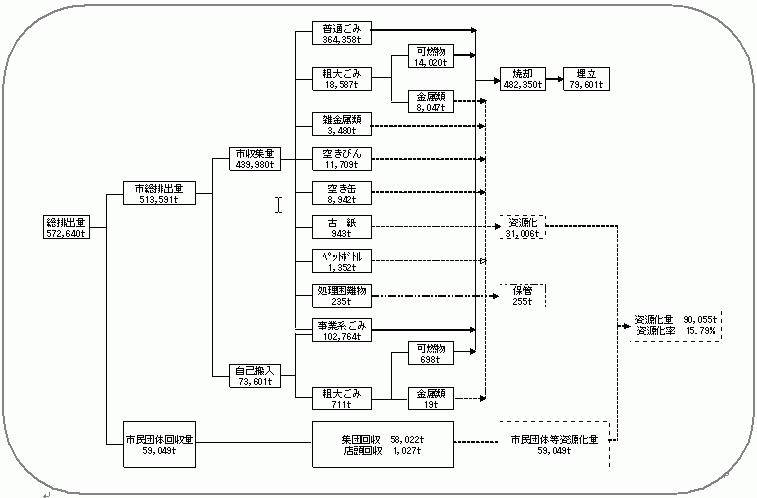
ごみ処理フロー(○年現在)
分別・収集・運搬
1) 分別・収集
・ 家庭系ごみ
普通ごみについては、土日、祭日、「資源ごみの日」を除く週4日収集となっています。
資源ごみは、地域ごとに週に1日「資源ごみの日」を設け、空き缶、空きびん、雑金属、ペットボトル、乾電池を収集しています。
粗大ごみは、地域ごとに曜日を指定して月2回収集しています。
・ 事業系ごみ
事業系ごみの排出量が日量30kg以下である事業者を対象とし、以下の有料処理を行っています。
・市に収集を委託する場合 26円/kg
・中間処理施設に直接搬入する場合 12円/kg
・許可業者に回収・処理を委託する場合 26円/kg(上限)
2) 運搬
A市はFW区、MW区、M区、ME区、FE区の5つの区域に分けることができます。焼却処分場は、M区を除く各区にありますが、西部のごみの一部及びM区のごみについては、東部へ運搬輸送し、処理を行っています。収集運搬量は、ごみ車で390千t/年、その他の分別車を含めた全体で約439千t/年になります。
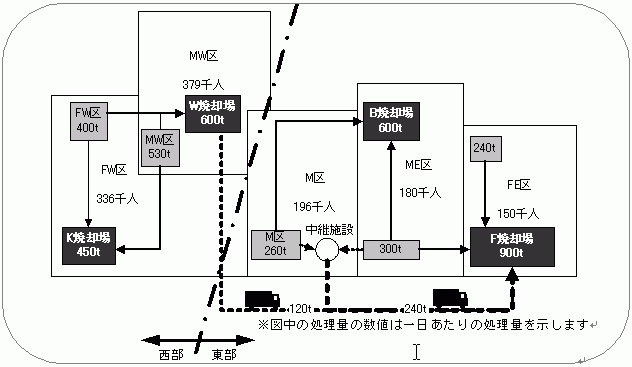
ごみの地域的処理の現状
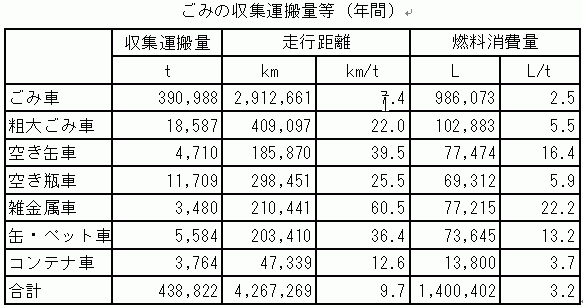
中間処理
1) 中間処理量
焼却量は、平成2年度が最大で、約560千t/年でした。その後、再資源化量の増加とともに、焼却量は減少し、平成13年には約489千t/年になっています。
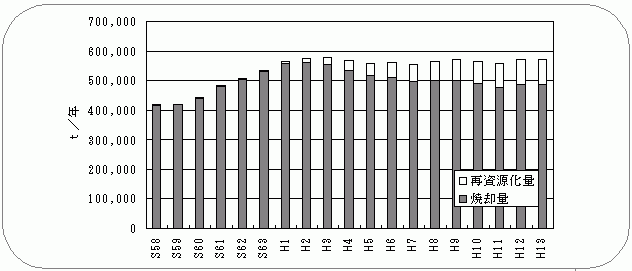
焼却量及び再資源化量の推移
2) 中間処理施設
再資源化処理施設
A市には、缶・瓶の再資源化施設がFE、B、Kの3箇所で、ペットボトルの再資源化施設がFE、Bの2箇所で稼働しています。また、粗大ごみ処理施設が、F、Wの2箇所で稼働しています。処理能力は、全体で缶が50t/日、瓶が75t/日、ペットボトルが9t/日、粗大ごみが100t/日となっています。
再資源化処理施設の概要
| 空き缶 | 空き瓶 | ペットボトル | 粗大ごみ | |
| FEリサイクルセンター | 20 t/日 | 45 t/日 | 7.5 t/日 | - |
| B再資源化処理施設 | 15 t/日 | 20 t/日 | 1.5 t/日 | - |
| K再資源化処理施設 | 15 t/日 | 10 t/日 | - | - |
| F粗大ごみ処理施設 | - | - | - | 50 t/日 |
| W粗大ごみ処理施設 | - | - | - | 50 t/日 |
| 合計 | 50 t/日 | 75 t/日 | 9 t/日 | 100 t/日 |
焼却施設
A市では、W、B、K、Fの4箇所で焼却施設が稼動しており、焼却能力の合計は2,550t/日となっています。これらの焼却施設のうち、K焼却場とW焼却場は施設の老朽化により、近年更新の予定です。
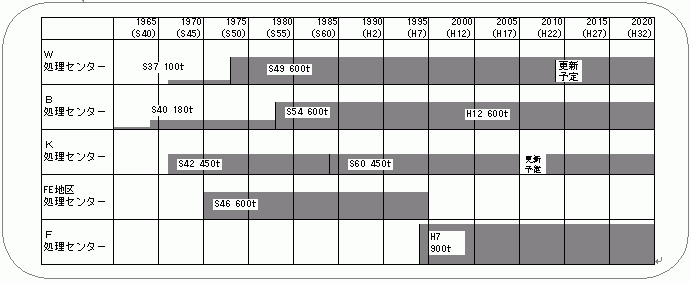
焼却施設の建設等推移
最終処分
最終処分場
市内の最終処分場は、F海面埋立処分場(第2期)1箇所であり、埋立容量は2,670,000m3です。平成7年計画の施策を続けると仮定した場合、最終処分場の使用可能年数は残り6年程度(平成12年現在)であり、非常に逼迫した状況です。
最終処分量
各焼却場からの焼却灰排出量は約73,000t/年(56,000m3/年)であり、この全量を埋立最終処分しています。
F埋立処分場は、一般廃棄物のほか、市水道局、市建設局からの産業廃棄物、及び民間の産業廃棄物の一部を受け入れており、年間の埋立量は約68,500m3となっています。
処理費用
A市のごみ処理費用は、約216億円/年で、ごみ1t当りの処理費用は約5万円となっています。また、ゴミ処理費用の内訳は、普通ごみが収集運搬に約81億5千万円/年、処理処分に約76億円/年、その他で収集運搬に約44億5千万円/年、処理処分に約14億円/年となっています。
ごみ処理費用の概要(年間)
| 項目 | 費用 |
| 1年間の処理費用 | 21,580百万円 |
| ごみ1t当り処理費用 | 49,177円 |
| 1世帯当り費用 | 39,736円 |
| 人口1人当り費用 | 17,265円 |
ごみ処理費用の内訳(年間)
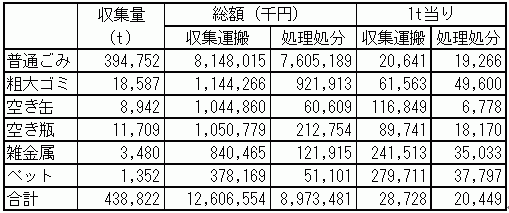
行財政の状況
A市は、平成○年度の歳出(5,411億円)が歳入(2,657億円)を2,754億円も上回っている状況であり、このままの行財政体質では、平成○年度以降にはさらに財政再建団体となる可能性に瀕している状況です。
この財政逼迫は、単に不況による一時的な税収減によるものではなく、過去からの制度疲労や少子高齢化社会の到来といった構造的な要因に基づいているものであり、現行の市民負担下では現行のサービス水準を維持することは不可能と判断されます。
このため、「行政体制の再整備」「公共公益施設・都市基盤の見直し」「市民サービスの再構築」を骨子とする行財政改革プランが平成○年に提示されています。
なお、平成○年度の事業決算原価によると、廃棄物の処理に係る費用は年間216億円に達しており、市の一般会計予算の約4%を占めており、コストの削減が急務となっています。
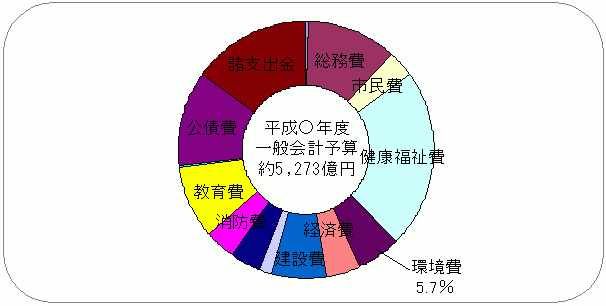
平成○年度一般会計予算
処理計画の前提条件
処理計画における前提条件として、ごみ排出量に大きく影響する要素として、処理方法、費用、人口、一人当りごみ排出量、産業の推移について、以下のとおりの前提条件を設定しました。
・ 廃棄物は市内処分を原則とします。
・ 現行に対して著しく処理費用が増大する計画でないこととします。
・ 人口推計
人口は、近年漸増しており、この傾向を踏まえて、2000年(平成12年)実績をもとに2020年(平成32年)までの人口推計を2000年比で116%の1,450千人と推計しました。
人口推計
| 年度 | 人口(千人) | 2000年比(%) |
| 2000(H12:実績) | 1,250 | 100.0 |
| 2010(H22) | 1,350 | 108.0 |
| 2020(H32) | 1,450 | 116.0 |
・ 一人当りごみ排出量予測
一人当りのごみ排出量は、平成○~○年の過去5年間の排出量がほぼ横ばいの状況であり、ごみ排出量に大きく影響する社会構造変化、産業構造変化や施策等が現時点では想定されないことから、過去5年間の平均値1,263g/人/日(集団回収量を含む)とします。
なお、この排出量には諸施策の実施や意識向上等に伴う減量化量は見込んでいません。
・ 現計画を継続した場合のごみ排出量予測
以上により、2020年(平成32年)のごみの排出量(集団回収量を含む)は、668,500t/年になると予測しました。
ごみ排出量予測
| 年度 | 人口(千人) | ごみ排出量(t/年) |
| 2000(H12:実績) | 1,250 | 572,640 |
| 2010(H22) | 1,350 | 622,400 |
| 2020(H32) | 1,450 | 668,500 |
ごみ処理に関する市民意見
処理計画に関する課題の洗い出しを目的とし、ごみの処理全般について市民の皆さんとのワークショップ及び市民団体へのヒアリングを行いました。
ワークショップの開催状況:市内2ヶ所、参加人数○名
ヒアリング実施状況:生ごみリサイクルの会、A市ごみを考える会
ごみ処理全般に関して得られた意見の概要は次のとおりです。開催状況等については、資料編に示します。
⇒資料編「2.市民参加」
・ 今後の廃棄物行政のあり方
ごみを処理するのではなく、ごみを出さない努力をするべきである。
市民参加の機会を増やし、市民の自主的な削減に向けた啓発活動を進めるべきである。
普通ごみを有料化し、市民が自発的にごみを減らすようにしてはどうか。
デポジット制度や、廃棄物税などの減量化に向けた制度を導入するべきである。
・ 処理費用の削減
処理コスト低減の努力を行うべきである。
民間処理との費用比較をし、より安価であれば民間委託を進めるべきである。
排出量の削減により、新たな焼却施設の建設費を削減すべきである。
・ 処理場、処分場
排出量が減れば、新たな焼却場はいらないのではないか。
現行の焼却場を廃止し、跡地を公共施設や公園にしてほしい。
既存焼却施設のダイオキシン類対策を進めてほしい。
最終処分場の建設により、貴重な緑地が失われたり、水源が汚染されたりしている。最終処分場の建設に反対する。
・ その他個別課題
不燃ごみの分別収集をしてほしい。
プラスチック、廃油、厨芥、剪定枝等のリサイクルを推進するべきである。
処理計画策定上の課題
・廃棄物の発生量が大きく変化していることから、近年の傾向を踏まえた処理計画が必要です。
・循環型社会をさらに推進するため、新たな再資源化目標の設定と再資源化推進のための施策が必要です。
・リサイクル関連法整備を踏まえ、対象廃棄物の排出量予測や施策整備が必要です。
・市内における廃棄物発生量と処理量の地域的な不均衡を補正する対策が必要です。
・最終処分場の容量逼迫に伴い、最終処分量のより一層の削減が必要です。
・平成16年頃にK焼却場が、平成20年頃にW焼却場がそれぞれ更新時期を迎えることから、これに対する対応が必要です。
・平成○年の一般会計予算では廃棄物関係が約4%を占めており、コストの削減が急務となっています。
地域概況
・ 自然的状況(環境の状況)
ア) 大気質
A市においては、環境基準が、光化学オキシダントについて全測定局未達成、幹線道路沿いの二酸化窒素、浮遊粒子状物質について一部未達成となっています。またA市の一部は「公害健康被害の補償等に関する法律」の第一種地域に指定されており、被認定患者数は60,000人を超えています。
工業地帯を持ち、また通過交通を含めた交通量の多い複数の幹線道路を持つ市の特徴として、大気環境に大きな課題があります。
イ) 騒音
A市では、道路交通に伴う騒音が大きな環境課題となっており、道路に面する地域及び近接空間の道路端の測定局の多くで環境基準が未達成の状況です。
ウ) 水質
A市内の河川のうち、G県との境となっているB川では環境基準A類型をほぼ達成していますが、その他のほとんどはいわゆる都市内河川であり、水質は良好ではありません。これらの河川水質は、昭和30年代の高度成長期には非常に水質が悪化し、その後、工業排水の改善や下水道の普及に伴い、昭和50年代には改善されましたが、まだ不十分な状況です。
・ 社会的特性
ア) 人口
A市の人口は、昭和30年代から40年代にかけて、工業地帯の発展とともに急増しました。その後急激な人口の伸びは見られませんが、人口は漸増を続けています。近年では、西部内陸地域における宅地開発に伴う人口増が多く、西部のMW区、FW区では人口が増加していますが、東部のME、FE区の人口はほぼ横這いの状況です。また高齢化も急速に進みつつあります。
イ) 産業
A市の産業は工業が主体です。工業製品出荷額は近年ほぼ横這いですが、事業所数及び従業員数は漸減の傾向にあります。
ウ) 土地利用
A市の東部は工業地帯となっており、また西部では宅地開発が進んでいることから、土地利用が著しく高度化しています。A市の緑被率は27.2%であり、特に東部において緑被率が低くなっています。
⇒資料編「1.1 地域の特性」
A市基本構想等の目標
「A市基本構想」(平成○年)を受けた「A市総合計画」(平成○年)では、5つの基本方針のうちの1つとして「快適環境都市づくり」をあげ、「地球環境にやさしい循環型のまちづくり」「地域の生活環境改善」を大きな目標として掲げています。
⇒資料編「1.1 地域の特性」
A市環境基本計画の理念
「A市環境基本計画」(平成○年)では、環境の現況や社会的状況を踏まえ、優先的に解決すべき緊急性の高い分野、特段の対応が求められる分野として、以下の7つを示しています。
1. 大気汚染の低減
2. 化学物質の環境リスクの低減
3. 緑の保全・回復
4. 地球温暖化防止対策の推進
5. 資源の有効活用による循環型地域社会の形成
6. 環境教育・環境学習の推進
7. 市民、事業者、市のパートナーシップの構築
⇒資料編「1.1 地域の特性」
A市全体計画における処理計画の位置づけ
処理計画は、A市の総合計画及び環境基本計画と以下に示すような関係にあり、市全体の都市づくりの方向性や将来の望ましい環境像に沿った処理計画が求められています。
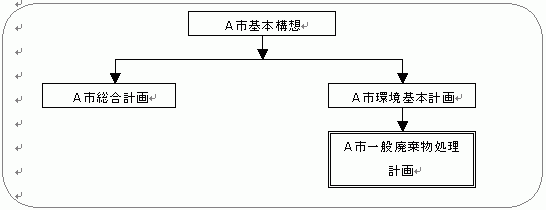
A市全体計画と処理計画との関係
環境配慮方針に関する市民意見
環境配慮方針とは、処理計画の改定にあたり、どのような環境面に配慮していくかという分野と考え方を示すものです。
環境配慮方針を策定する際の参考とするため、計画策定実施の告知時に環境配慮に関するアンケートを実施しました。その結果、以下のような意見が寄せられました。
・ 市全体の環境のあり方との関係
西部が緑が豊かで、東部に行くほど緑が少ないという環境の偏りを改善すべきである。
環境に係る市全体の環境方針等を踏まえた計画にしてほしい。
地球温暖化対策などを取り入れた地球にやさしい処理計画にすべきである。
・ 地域の生活環境保全
現状でも大気環境は良いとは言えないため、さらなる負荷は最小限に抑えるべきである。
既存施設のダイオキシン類対策を徹底してほしい。
・ その他
ごみの減量化・再資源化率の向上のために、分別の徹底指導や啓発活動を積極的に行うべきである。
⇒資料編「2.市民参加」
A市における地域概況、A市基本構想等の目標、環境基本計画の理念、A市全体計画における処理計画の位置づけ、環境配慮に対する市民意見から、処理計画を策定するにあたって環境保全に関して重視すべき事項として、以下の5つの事項を選定し、環境配慮方針としました。
1. 窒素酸化物排出量の削減
A市の大気質の状況は良好とは言えず、特に近年では、道路交通由来の窒素酸化物が大きな課題となっています。廃棄物処理にあたっては、焼却処分場などの固定発生源や収集・運搬に係る道路交通より大気汚染物質が排出されることから、特に課題となっている窒素酸化物の低減を重視すべき事項として選定しました。
2. ダイオキシン類対策の推進
A市内の焼却施設は、既設炉に係るダイオキシン類の排出基準(1ng-TEQ/m3)を既に満足していますが、市民の皆さんの関心が非常に高いことから、ダイオキシン類対策の推進を重視すべき事項として選定しました。
3. 緑の保全・回復
現在の一般廃棄物最終処分場の閉鎖後に新たに最終処分場を建設する場合には、A市は土地利用が高度に進んでいることから、宅地等の生活空間を避けると、残された貴重な緑地内に建設することとなります。また、次期最終処分場の建設はまだ具体化していませんが、現段階でも市民の関心が高くなっています。以上のことから、現最終処分場の延命化による緑の保全を、重視すべき事項として選定しました。
また、緑地に関連する内容として、既設焼却施設を廃止することによる跡地の公園化による緑の回復を、重視すべき事項として選定しました。
4. 二酸化炭素排出量の削減
二酸化炭素排出量の削減は、環境基本計画においても重点分野としてとりあげられており、基本構想においても「地球にやさしい循環型のまち」として掲げられていることから、重視すべき事項として選定しました。
5. 資源の有効活用
資源の有効活用は、処理計画の目的の一部でもあり、また、環境基本計画における重点分野としてあげられていることから、重視すべき事項として選定しました。
計画改定の必要性、地域の特性、計画の前提条件、ごみ処理に関する市民意見、処理計画策定上の課題及び環境配慮方針を踏まえ、計画の目的を以下のとおり設定しました。
1. 2020年(平成32年)において、現処理計画がそのまま継続した場合における、廃棄物の発生量の予測値(668千t/年)と比べ、発生量を極力低減すること。
2. 再資源化率について、環境基本計画の目標値(25%)を達成すること。
3. 排出削減や再資源化のための諸施策にもかかわらず発生する廃棄物が、適正に処理処分されること。
4. 老朽化施設の廃止又は更新が適切に図られること。
5. ダイオキシン類等の微量有害化学物質の排出が現状より抑制されること。
6. 最終処分場を極力延命化するため、最終処分量の削減が図られること。
7. 廃棄物処理の本来の目的である、公衆衛生の維持を図ること。
|
<用語解説> |
処理計画は、環境配慮方針を踏まえつつ、計画の目的を達成する必要があります。このような視点に沿って、どのような方向に計画が向かうべきであるかという、処理計画が目指す具体的な方向性を環境影響を評価する複数案の設定の方針としました。ここでは、環境配慮方針と計画策定上の課題から、優先すべき事項を洗い出し、これらをまとめた上で、現計画を継続する方針を加え、複数案設定の5つの方針を設定しました。
今後、これらの方針ごとに、市民の皆さんの意見等を踏まえながら、複数案を作成していきます。
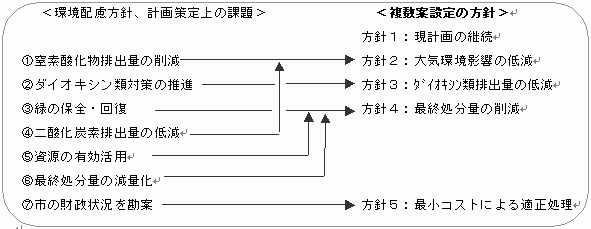 .
.
以下に、それぞれの複数案設定の方針ごとに、計画を策定する場合に着目すべきことやその実現のための具体的な施策を提示しました。さらに、これらの施策による市民の生活への影響の程度やコストについて付記しました。
<方針1:現計画の継続>
現行計画を改定することなく、そのまま継続させた場合についての案を作成します。
|
・ 環境の変化は? |
・ 毎日の生活はどう変わるか?
現状以上の分別や新たな施策を行わないことから、分別の手間や経済的な負担は現状と変わりません。
・ コストは?
更新時期を迎える焼却施設をその場で更新する計画であり、そのための財源確保が必要です。ごみの焼却量そのものが増加するため、収集運搬及び中間処理に要する費用が若干増加すると考えられます。その他、新たな施策は行わないことから、新規施設の建設等への費用は発生しません。
<方針2:大気環境影響の低減>
窒素酸化物等の大気汚染対策が課題となっていることから、焼却及び廃棄物の収集・運搬に伴う大気汚染物質排出の低減を図ることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物の分別および減量化に着目します。さらに、沿道大気汚染対策として、廃棄物及び焼却灰の収集・運搬に伴う車両交通量が減少するよう、廃棄物の減量化のほか、焼却施設等の配置(ごみの排出と処理の市内バランス)に着目します。
地球温暖化対策として、二酸化炭素の排出量を低減させることが望ましいと考えます。そのため、廃棄物処理量の減量化に着目します。さらに、焼却施設等の配置により変化する廃棄物及び焼却灰の運搬に伴う車両交通量、収集の回数に着目します。
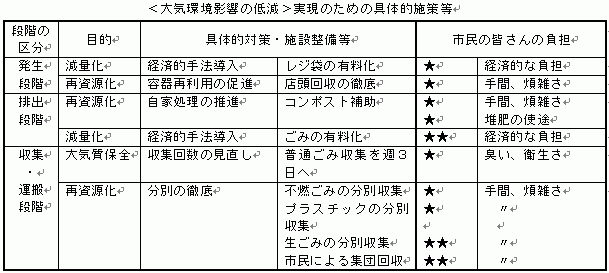
|
・ 環境の変化は? |
・ 毎日の生活はどう変わるか?
窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量の低減を図るため、ごみの焼却量そのものを減らす必要があり、減量化・再資源化のための経済的な負担や分別の手間や煩雑さが増え、ごみを出さない、再利用するための努力や工夫が必要になると考えます。また、車両走行量を減らすために、収集日を減らすことが考えられ、そのため家庭でごみを保管する期間が少々長くなる可能性があります。
・ コストは?
窒素酸化物及び二酸化炭素の排出量の低減を図るためには、ごみの収集車両の走行量を減らすことが考えられます。つまり、発生・処理の近接化が一つの手段となることから、更新時期を迎える焼却施設をその場で随時更新することが考えられ、そのための財源確保が必要になる可能性があります。また、収集日を減らすことにより、若干の収集運搬コストの低減が図られると考えます。
<方針3:ダイオキシン類排出量の低減>
ダイオキシン類の排出を削減することが望ましいと考えます。廃棄物の焼却に伴うダイオキシン類の排出削減のため、廃棄物の分別および減量化に着目します。また、焼却施設の縮小を望む声があることから、計画期間内に廃止時期を迎える焼却施設については、新たに更新・新設しない案を検討します。緑の回復を望む声があることから、焼却施設等の跡地は、公園などの緑地として活用を図ります。
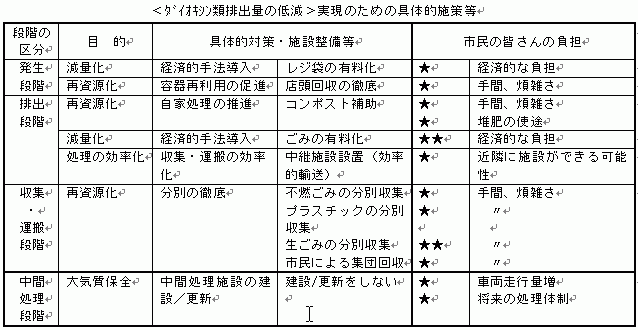
|
・ 環境の変化は? |
・
毎日の生活はどう変わるか?
ダイオキシン類の排出量削減のために、焼却するごみの量そのものを減らす必要があり、ごみの減量化・再資源化のための経済的な負担や分別の手間や煩雑さが増え、ごみを出さない、再利用するための努力や工夫が必要になると考えます。また、新たな施設を建設または更新しないため、将来的なごみ処理体制を後々に再検討する必要があると考えます。
・ コストは?
ダイオキシン類の排出量削減のために、新たに焼却施設を建設または更新しないとすると、焼却施設建設のための費用は発生しないが、焼却施設立地の現在の地域バランスが崩れ、ごみの長距離輸送のための中継施設を設けるための財源確保が必要になる可能性があります。また、ごみの収集・運搬費用が高くなる可能性があります。
<方針4:最終処分量の削減>
資源の有効活用については、市民の協力を最大限求めて分別、再資源化を追求する案と、再資源化施設を新たに建設し活用することで再資源化を追求する案を検討します。
最終処分場の新規建設を極力回避することが望ましいと考えます。そのため、分別回収の徹底や再資源化施設の有無等による最終処分量の増減に着目します。
<最終処分量の削減>実現のための具体的施策等
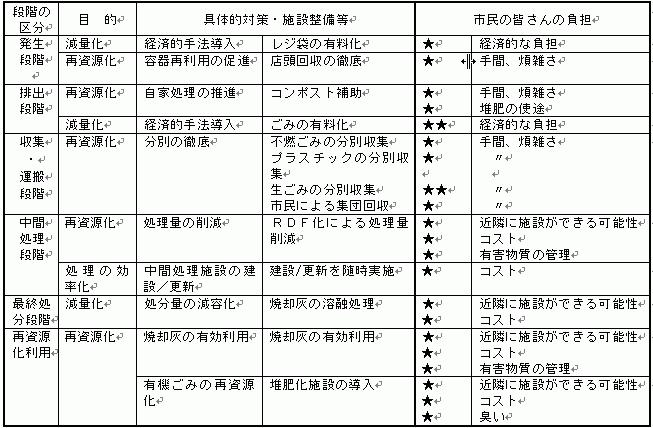
|
・
環境の変化は? |
・ 毎日の生活はどう変わるの?
減量化・再資源化のための経済的な負担や分別の手間や煩雑さが増え、ごみを出さない、再利用するための努力や工夫をしていただくことが必要になると考えます。さらに再資源化施設を新たに建設する必要があるため、施設が近隣に設置される可能性が生じると考えます。
・ コストは?
再資源化施設のための財源確保の必要が生じると考えられます。また、焼却灰等の運搬費用が増加すると考えられます。
<方策5:最小コストによる適正処理>
市の財政状況を勘案し、コストに着目します。
<最小コストによる適正処理>実現のための具体的施策等
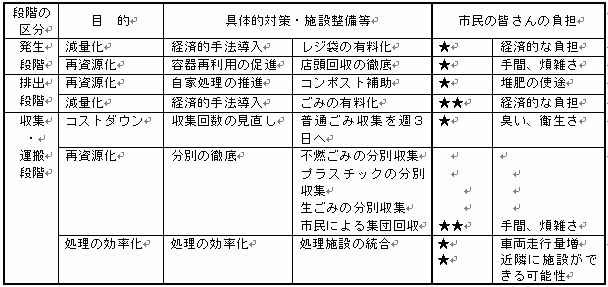
|
環境の変化は? |
・
毎日の生活はどう変わるの?
収集運搬コストや再資源化コスト削減のために、現状以上の分別は行わないとすると、市民の分別の手間や煩雑さや現状とほぼ変わりません。しかしながら、新たな焼却施設や埋立処分場を建設・更新しないとすると、ごみを減量化する必要があり、そのために多少の経済的負担を伴うこと、ごみを出さない努力や工夫を最大限図る必要があると考えられます。また、収集運搬コストの削減のために収集日を減らすことが考えられ、家庭でごみを保管する期間が少々長くなる可能性があります。
・ コストは?
更新を迎える2つの焼却施設を統合化することで、2つを更新するよりもコスト削減が図られるものと考えます。また、収集日を減らすことで、収集運搬コストの削減が可能になると考えます。
複数案設定の方針の中には、市民の皆さんの経済的な負担や分別の手間が増えるものもあります。また、施設の更新・新設により環境への影響が懸念されるものもあります。
今後、これらの複数案設定の方針ごとに市民の皆さんの意見等を踏まえながら複数案を作成していきます。さらに、それぞれの複数案について、どの程度の環境影響が考えられるのかを予測・評価し、複数案の比較検討を行った上で、環境影響のより少ない処理計画を目指していきます。
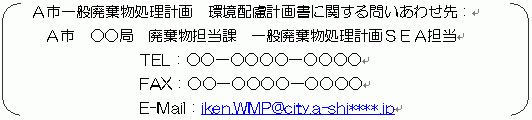
<資料編>
1.1.1 自然的状況(環境の状況)
(1) 環境基準の達成状況
ア) 大気質
A市では、一般環境大気測定局(9局)と自動車排出ガス測定局(9局)で大気汚染物質の濃度等を常時監視している。
平成12年度の環境基準の達成状況は以下に示すとおりであり、環境基準が、光化学オキシダントについて全測定局未達成、幹線道路沿いの二酸化窒素、浮遊粒子状物質について一部未達成となっている。
表1-1 大気質の環境基準達成状況(平成12年度)
| 内 容 | SO2* | NO2 | Ox | SPM* | CO |
| 一般環境局 | 9/9(100) | 9/9(100) | 0/9(0) | 9/9(100) | 3/3(100) |
| 自動車排出ガス局 | - | 4/9(44) | - | 2/9(22) | 8/8(100) |
注)表中の値は、達成局/測定局(%)として示す。
*:長期的評価(日平均値)について示す。 -:測定なし
出典:「平成13年度 ○○局事業概要-公害編-」A市、平成13年12月
イ) 水質
A市においては、公共用水域の健康項目及び生活環境項目について、市内河川21地点、海域13地点において測定を実施している。
平成12年度の環境基準の達成状況は、以下に示すとおりであり、河川のA目標水域の一部において環境基準が達成されていない。
表1-2 水質の環境基準達成状況(平成12年度)
| 対 象 | 項 目 | 達成状況 | |
| 河 川 | 健康項目 | 9/9(100) | |
| 生活環境項目 | A目標水域 | BOD:5/6(83)、COD:1/6(17) | |
| B目標水域 | BOD:3/3(100)、COD:3/3(100) | ||
| C目標水域 | BOD:3/3(100)、COD:3/3(100) | ||
| 海 域 | 健康項目 | B類型 | 3/3(100) |
| 生活環境項目 | C類型 | 10/10(100) | |
注)A目標水域:BOD、CODの目標値が5mg/L以下
B目標水域:BOD、CODの目標値が8mg/L以下
C目標水域:BOD、CODの目標値が10mg/L以下
出典:「平成13年度 ○○局事業概要-公害編-」A市、平成13年12月
ウ) 騒音
A市においては、自動車交通騒音の実態調査を20路線の30地点(道路端25地点と背後地(道路端から50mの範囲)5地点)において実施している。
平成12年度の環境基準の達成状況は以下に示すとおりであり、道路に面している地域(B地域)及び近接空間の道路端の測定局では、環境基準の達成率は低く、厳しい状況である。
表1-3 騒音の環境基準達成状況(平成12年度)
| 地域の類型 | 達成状況* | |
| 道路に面する地域(B地域) | 0/2(0) | |
| 幹線交通を担う道路に近接する空間 | 道路端 | 3/23(13) |
| 背後地 | 5/5(100) | |
|
合 計 |
8/30(27) | |
注)表中の値は、達成局/測定局(%)として示す。
*:全ての時間帯で環境基準を達成している測定局を対象とした。
出典:「平成13年度 ○○局事業概要-公害編-」A市、平成13年12月
(2) 公害の状況
A市は、FE区とME区が「公害健康被害の補償等に関する法律」の第一種地域に指定されている。A市における被認定者数の推移は以下に示すとおりである。
表1-4 公害病被認定者数
| 公害病認定患者数 |
1975 (S50) |
1980 (S55) |
1985 (S60) |
1988 (S63) |
2000 (H12) |
| A市 | 2,723 | 3,263 | 3,281 | 3,503 | 2,255 |
| B市 | 657 | 861 | 948 | 983 | 637 |
| 全 国 | 33,466 | 81,222 | 94,639 | 110,387 | 61,288 |
| A/全国(%) | 8.14 | 4.02 | 3.47 | 3.17 | 3.68 |
注)昭和63年3月1日をもって第一種地域の指定が解除され、
それ以降、新たな患者の認定は行われていない。
出典)「環境白書」環境省、昭和51年~平成13年
1.1.2 社会的特性
(1) 人口
A市における年齢階級別人口の推移は以下に示すとおりであり、若年層の減少、高齢者層の増加の傾向にある。
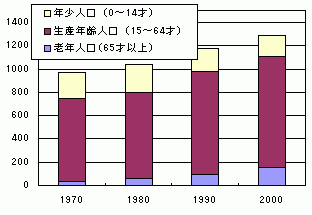
図1-1 年齢階級別人口の推移
(2) 産業
A市における産業大分類別事業所数の構成比は以下に示すとおりであり、製造業、卸売・小売業・飲食店が減少、サービス業が増加の傾向にある。
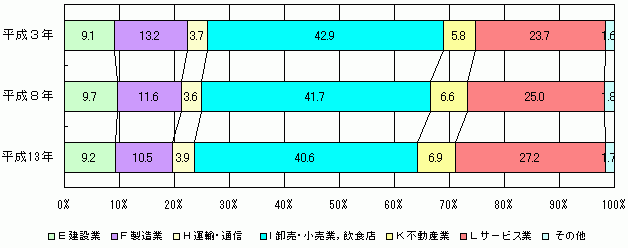
出典:「A市の事業所 平成13年」A市、平成14年5月
図1-2 産業大分類別事業所数の構成比
(3) 土地利用
A市全体の緑被率は、平成6年3月現在で27.2%であった。区別では、丘陵部から内陸部、臨海部にいくにしたがって緑被率が低くなっている。
表1-5 緑被率の状況
平成6年3月31日現在
|
内訳 (%) |
樹林地 | 農 地 | 公園緑地 | 緑化地 |
その他 (河川等) |
合 計 |
| FE区 | 0.3 | 3.9 | 5.3 | 7.0 | 5.4 | 21.9 |
| ME区 | 4.9 | 7.6 | 4.5 | 9.8 | 7.9 | 34.7 |
| M区 | 5.7 | 14.1 | 4.2 | 8.1 | 1.8 | 33.9 |
| MW区 | 5.4 | 8.0 | 5.6 | 11.0 | 5.6 | 35.6 |
| FW区 | 16.0 | 11.8 | 3.3 | 7.3 | 3.1 | 41.5 |
| 全市 | 4.7 | 6.2 | 3.7 | 7.9 | 4.7 | 27.2 |
注)市域面積:14,385ha
出典:「-A市緑の基本計画-A市緑の30プラン」A市、2010年3月
(4) 交通
A市における交通事故の状況は以下に示すとおりであり、G県の約12%の発生件数を占めている。
表1-6 交通事故の状況
平成12年度末現在
| 件 数 | 死亡者数 | 負傷者数 | |
| A市 | 8,361 | 38 | 9,889 |
| G県 | 69,097 | 324 | 84,452 |
1.1.3 A市基本構想等の目標
A市では、平成○年に「A市基本構想」を議決し、A市における基本目標、都市づくりの基本理念及び実現のための方向性等を示している。さらに、この議決を受け、A市は平成○年に「A市総合計画」を策定し、長期的な課題と実施計画を掲げ、5年ごとの見直しをしながら施策を実施している。
(1) 都市づくりの基本目標
A市基本構想では、都市づくりの基本目標を以下のとおり定めている。
|
~未来の都市づくりのために~ |
(2) A市新時代へ向けての基本方向
A市総合計画では、A市新時代へ向けての5つの基本方向を定めている。
|
~A市新時代へ~ |
1.1.4 A市環境基本計画の理念
A市では、平成○年に「A市環境基本計画」を定め、A市における「望ましい環境像」の達成のための施策を実施している。さらに、地球温暖化やダイオキシン類等の新たな環境問題、環境影響評価法や循環型社会形成推進基本法等の新たな国の施策に対応するために、平成○年には環境基本計画の改定を行っている。
(1) 望ましい環境像
A市環境基本計画では、望ましい環境像を以下のように定めている。
|
人と環境が共生する都市 ○健康な市民生活が営める安全なまち -産業公害の防止や都市生活型公害の改善、都市災害の防止に積極的に対応し、市民の健康と財産を守安全なまち- ○うるおいとやすらぎのある快適なまち -豊かな水と緑を保全し、歴史や文化を育み、良好な都市空間を創造する快適なまち- ○地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち -有限な資源やエネルギーを有効に活用し、再利用することなどにより、地球環境への配慮に地域から取り組む循環型のまち- |
(2) 望ましい環境像と環境要素との関連
A市では、三つの望ましい環境像の実現のために、各々の環境像に関連する環境要素を示し、それぞれに目標や施策を提示し、これを達成・推進していくこととしている。
表1-7 環境基本計画における環境像と関連する環境要素
| 環境像 | 環境要素 |
| 健康な市民生活が営める安全なまち | 大気 |
| 水 | |
| 土 | |
| 化学物質 | |
| 騒音・振動 | |
| 建造物影響 | |
| うるおいとやすらぎのある快適なまち | 水辺 |
| 緑 | |
| 生物 | |
| 都市アメニティ | |
| 都市気温 | |
| 地球環境にやさしい持続可能な循環型のまち | 地球環境 |
| 資源・廃棄物 | |
| エネルギー | |
| 水循環 |
(3) 環境要素に係る重点分野
環境基本計画では、A市の環境の現況や社会的状況を踏まえ、優先的に解決すべき緊急性の高い分野、特段の対応が求められる分野を5つ示している。
表1-8 環境基本計画における重点分野と重点目標
| 環境要素 | 重点分野 | 重点目標 |
|
大気 |
大気汚染の低減 |
2005年度から2010年までのできるだけ早期に、市内の自動車の窒素酸化物排出総量を対2000年度比で約70%削減、粒子状物質排出総量を対2000年度比で約70%削減し、固定発生源対策と併せ、二酸化窒素の対策目標値を市の全測定局で達成するとともに、浮遊粒子状物質の対策目標値を全ての一般局で達成することを目指す。 |
|
化学物質 |
化学物質の環境リスクの低減 |
2001年度を基準年度として2006年度までに市内のPRTR法対象事業所から排出される対象物質の総排出量を30%削減することを目指す。 |
|
緑 |
緑の保全・回復c |
2010年までに市域面積の30%に相当する緑の確保を目指す。(主なものとして、樹林地400ha、農地500ha、公園緑地1,000haの確保を目指す) |
|
地球環境 |
地球温暖化防止対策の推進 |
2010年における二酸化炭素等の排出量を1990年レベルに比べ6%削減することを目指す。 |
|
資源・廃棄物 |
資源の有効活用による循環型地域社会の形成 |
・ 2010年度における市民一人一日あたりのごみ排出量(事業系も含む)を2000年度に対し5%削減することを目指す。・ 2010年度におけるごみの再資源化率を25%とすることを目指す。・ 2010年度における産業廃棄物発生量を1999年度レベルに抑制・意地するとともに、再資源化率を51%とすることを目指す。 |
| - |
環境教育・環境学習の推進 |
環境教育・環境学習の場や機会の充実、人材育成等の基盤整備を目指す。 |
| - |
市民、事業者、市のパートナーシップの構築 |
市民、事業者、市の三者の多様な連携・交流を促す機会の創出や支援等を推進し、パートナーシップによる施策の展開を目指す。 |
環境保全上重視すべき事項として選定した5つの事項に関連する分野について、環境基本計画で示された重点目標及び指標は以下のとおりである。
(1) 大気汚染の低減(ディーゼル車を中心とした自動車排出ガスによる大気汚染の低減)
重点目標:2005年度から2010年までのできるだけ早期に、市内の自動車の窒素酸化物排出総量を1,010t(対2000年度比で約70%削減)、粒子状物質排出総量を172t(対2000年度比で約70%削減)とし、固定発生源対策と併せ、二酸化窒素の対策目標値を市の全測定局で達成するとともに、浮遊粒子状物質の対策目標値を全ての一般局で達成することを目指す。
固定発生源については、2005年から2010年までのできるだけ早期に窒素酸化物排出総量を9,330t(対2000年比で約12%削減)、粒子状物質排出総量を2,120tまで削減することを目指す。
指標:自動車の窒素酸化物排出総量、自動車の粒子状物質排出総量
二酸化窒素濃度(全測定局)、浮遊粒子状物質(全ての一般局)
(2) 化学物質の環境リスクの低減(ダイオキシン類等の微量有害化学物質による環境負荷の低減)
重点目標:2001年度を基準年度として2006年度までに市内のPRTR法対象事業所から排出される対象物質の総排出量を30%削減することを目指す。
指標:PRTR法対象物質の排出量
(3) 緑の保全・回復
重点目標:2010年度までに市域面積の30%に相当する緑の確保を目指す。
指標:市域面積に占める緑被面積の比率(水域を含めた緑被率)
(4) 地球温暖化防止対策の推進(二酸化炭素等の排出量の削減)
重点目標:2010年における二酸化炭素等の排出量を1990年レベルに比べ6%削減することを目指す。
指標:二酸化炭素等温室効果ガス排出量
(5) 資源の有効活用による循環型地域社会の形成
重点目標:・2010年度における市民一人一日あたりのごみ排出量(事業系も含む)を2000年度に対し5%削減することを目指す。
・2010年度における一般廃棄物の再資源化率を25%とすることを目指す。
・2010年度における産業廃棄物発生量を1999年度レベルに抑制・維持するとともに、再資源化率を51%とすることを目指す。
指標:市民一人一日あたりごみ排出量及び再資源化率
平成7年の処理計画策定以降、本処理計画の改定にあたっては、以下に示す経緯で情報公開及び意見収集を行ってきた。本環境配慮計画書の内容は、これらの経緯を踏まえて作成されたものである。
-平成7年度
平成7年○月 平成7年処理計画策定、公開
平成7年○月 平成7年度 市民アンケート実施
平成7年○月 「ごみ問題フォーラム」にて、平成7年処理計画の内容について報告
-平成○~○年度
○月 「環境局事業概要」にて、処理計画の実施状況について報告
○月 市民アンケート実施
○月 「ごみ問題フォーラム」にて、処理計画実施状況について報告
-平成○年度
平成○年○月 「平成○年度 ○○局事業概要」にて、処理計画の実施状況について報告
平成○年○月 平成○年度 市民アンケート実施
平成○年○月 「ごみ問題フォーラム」にて、処理計画実施状況について報告、改定の必要性について討議
-平成○年度
平成○年○月 市民討議(各区単位で計5回)
平成○年○月 平成○年度を目標に、処理計画改定の開始
・ 常設の情報公開の場として、市のホームページ上の専用ページ、Wリサイクルセンターに専用ブースを設置し、随時最新情報を掲載するとともに、意見募集の窓口を設けた。また、インターネットの専用ページでは、QA形式で寄せられた意見に対する反映結果を随時掲載している。
・ 処理計画に対するワークショップの開催、市民団体へのヒアリング実施
平成○年○月 環境審議会答申「21世紀における廃棄物行政のあり方について」の発表、パンフレットの一般配布
2.2.1 ワークショップの開催
(1) 目的
一般廃棄物の処理全般に関する課題の洗い出し及び問題意識の共通認識を図るため
(2) 開催状況
平成○年○月○日 18時~20時 於:M区区民センター 参加人数:○名
平成○年○月○日 14時~16時 於:A市市役所 参加人数:○名
(3) 募集方法
市の広報、インターネットによるお知らせ、町内会・市民団体等への出席依頼 等
(4) 議論の概要
-今後の廃棄物行政のあり方
ごみを処理するのではなく、ごみを出さない努力をするべきである。
市民参加の機会を増やし、市民の自主的な削減に向けた啓発活動を進めるべきである。
普通ごみを有料化し、市民が自発的にごみを減らすようにするべきである。
デポジット制度や、廃棄物税などの減量化に向けた制度を導入するべきである。
-処理費用の削減について
処理コスト低減の努力を行うべきである。
民間処理との費用比較をし、より安価であれば民間委託を進めるべきである。
排出量の削減により、新たな焼却施設の建設費を削減する。
-処理場、処分場について
排出量が減れば、新たな焼却場はいらないのではないか。
現行の焼却場を廃止し、跡地を公共施設や公園にしてほしい。
既存焼却施設のダイオキシン類対策を進めてほしい。
最終処分場の建設により、貴重な緑地が失われたり、水源が汚染されたりしている。最終処分場の建設に反対する。
-その他個別課題について
不燃ごみの分別収集をしてほしい。
プラスチック、廃油、厨芥、剪定枝等のリサイクルを推進するべきである。
2.2.2 市民団体へのヒアリング実施
(1) 目的
ごみの処理全般に関する課題の洗い出し及び問題意識の共通認識を図るため
(2) 対象団体
生ごみリサイクルの会(2名)、A市ごみを考える会(3名)
(3) 意見の概要
・各家庭のごみの減量化、再資源化についてもっと市が啓発活動を行うべきである。
・ごみの減量化、再資源化に貢献しても、その見返りがないと市民は自発的には取り組まない。よりインセンティブを与える手法が必要。
・地域センターなどでごみの減量化や再資源化のための講座を開くなど、地域に根付いた活動が必要ではないか。
・地域の商店街で店頭回収への協力を呼びかけるとか、ごみを出さない工夫をした商品を積極的にアピールするとか、販売者側の努力がもっと必要ではないか。
(1) 目的
処理計画の改定にあたり、処理計画においてどのような環境配慮を行うべきか、また考えられるかについて市民アンケートを行った。
(2) 調査期間
平成○年○月
(3) 募集方法
処理計画改定開始の告知は、インターネット上及び市の広報等を通じて行った。意見の募集は、ハガキ、FAX、メールのいずれも可とした。
(4) アンケート結果
環境配慮方針に関する意見として、69件の意見が寄せられた。区別の意見数は表2-1に示すとおりである。
表2-1 区別意見数
| 区 | FE区 | ME区 | M区 | MW区 | FW区 | 全市 |
| 意見数 | 22 | 17 | 16 | 6 | 8 | 69 |
(5) 意見の概要
環境配慮に関するアンケートの結果、以下のような意見が寄せられた。
-市全体の環境計画のあり方
西部が緑が豊かで、東部に行くほど緑が少ないという環境の偏りを改善すべきである。
環境に係る市全体の方針等を踏まえた計画にしてほしい。
地球温暖化対策などを取り入れた地球にやさしい処理計画にすべきである。
-地域の生活環境保全
現状でも大気環境は良いとは言えないため、さらなる負荷は最小限に抑えるべきである。
既存施設のダイオキシン類対策を徹底してほしい。
-その他
ごみの減量化・再資源化率の向上のために、分別の徹底指導や啓発活動を積極的に行うべきである。