平成13年度第1回環境負荷分科会
資料-2
1-2 温室効果ガス等の調査・予測・評価
1-2-1 スコーピングから環境影響評価の実施段階への手順
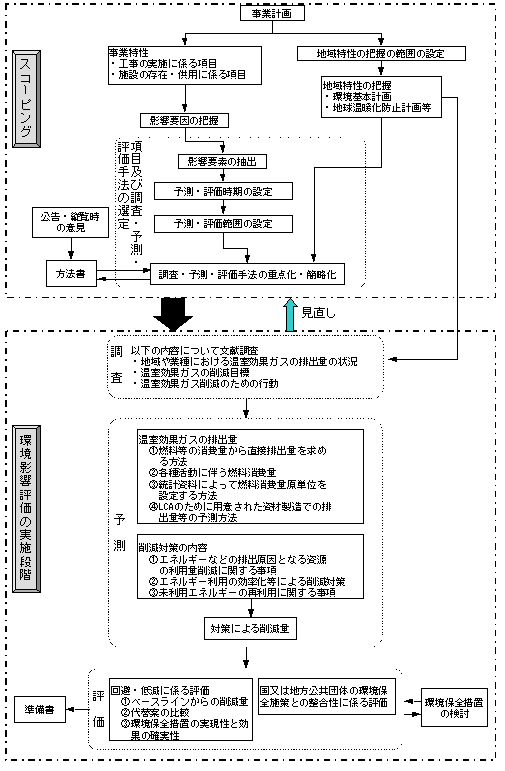
1-2-2 温室効果ガス等の予測・評価の基礎的事項
1)対象とする温室効果ガス等の分類
温室効果ガス等については本年度調査においては温室効果ガスを対象として行う。温室効果ガスの削減については国際的に1992年に「国連気候変動枠組み条約」が採択され、我が国も署名して1994年から発効している。この条約に基づき以下の6物質が、規制の対象として合意されており、我が国では「地球温暖化対策の推進に関する法律(以下「地球温暖化対策法」という。)第二条第3項」において対策の対象として定められている。これらの項目を環境要素の細目として以下に手法の整理を行う。
[1] 二酸化炭素(CO2)
[2] メタン(CH4)
[3] 一酸化二窒素(N2O)
[4] ハイドロフルオロカーボン(HFC)
[5] パーフルオロカーボン(PFC)
[6] 六フッ化硫黄(SF6)
なお、本年度の調査において[1]から[3]の3項目についての環境負荷量の定量化と、それによる評価について整理する。
2)事業における環境影響要因の整理
温室効果ガスの対象6物質の環境影響要因となる発生源との関連は表4-1にまとめるとおりである。
表4-1 「地球温暖化対策法」の対象の温室効果ガスの発生源
| 温室効果ガス | 地球温暖化係数 | 環境影響要因となる発生源の例 |
|---|---|---|
| 二酸化炭素 | 1 | 建設機械稼働、自動車・船舶・飛行機等の運行 発電所、工場での燃料の燃焼 等 |
| メタン | 21 | 燃料の燃焼廃棄物処分場、下水処理場 等 |
| 一酸化二窒素 | 310 | 燃料の燃焼、自動車・船舶・飛行機等の運行 廃棄物処分場、下水処理場 等 |
| HFC(ハイドロフルオロカーボン) | HFC-134a:1,300など | 工業製品の洗浄、発泡剤製造 等 |
| PFC(パーフルオロカーボン) | PFC-14:6,500など | 半導体工業、アルミニウム工業 等 |
| 六フッ化硫黄 | 23,900 | 半導体工業、軽金属工業 等 |
注)地球温暖化係数はIPCC(1995)による積分期間100年の値
表4-1中で、HFC、PFC及び六フッ化硫黄については特定の業種において使用されており、使用量が企業のノウハウに含まれる部分があるため一般的に負荷量の算定等において汎用的な手法を提示することが難しく、本報告書では、負荷量算定手法等の解説は行わないものとするが、該当する業種の誘致が想定される工業団地の造成等では、個別企業等の情報を可能な限り収集して負荷量の算定を行うものとする。
3)予測・評価の対象とする時期や行為の範囲等の考え方
予測・評価の対象となる時期又は領域の考え方としては次の3側面での区分設定の考え方がある。
[1] 事業段階の区分による設定
ア 建設段階
イ 供用(運用)段階
ウ 解体廃棄段階
[2] 負荷排出の当事者又は場所による区分
排出される段階と当事者にとっての区分(カッコ内に表示)を次のとおりである。
ア 消費資材の原料採取・製造・輸送段階(誘発負荷)
イ 事業者・施設利用者が行う行為の段階(直接負荷)
ウ 廃棄された物質(気体、液体、固体)の輸送・処理・処分段階(誘発負荷)
[3] 環境負荷量の表示
ア ピーク時の負荷量又は供用時における定常な状態を代表させて固定値として表示する方法。
イ 経時的に変化する量として計算し、算定対象とした事業段階の区分での積算値として表示する方法。
上記の区分に対して供用時の直接負荷については最低限算定の必要がある。その他の項目については、事業者が環境配慮として実施した内容を表示するためなどに範囲設定が必要な場合など、事業者の判断で可能な範囲で広げることが望ましい。
範囲設定について参考事例としては、「地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 平成11年8月 環境庁地球環境部環境保全課地球温暖化対策室」において対象範囲を明記しており、表4-2に示すとおりである。
検討対象範囲の取り方としては、表4-2に示す事項を標準的な項目として、事業者が他の要因(例えば、環境負荷の小さい原材料の採用など)によって環境配慮を行った場合などに、随時、検討対象範囲を広げることが考えられる。
また、負荷量の表示については、一般的に温室効果ガス等の負荷量削減に関する計画での目標値が、年間排出量で示されることが多いため、年間排出量の最大値の予測は必要であるが、比較評価を行う場合の範囲の設定によっては積算値が必要になる。
表4-2 二酸化炭素、メタン、一酸化二窒素の対象範囲とする行為の例
出典:地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 平成11年8月
環境庁地球環境部環境保全課地球温暖化対策室
| 物質 | 内容 |
|---|---|
| 二酸化炭素 | 燃料の使用に伴う排出 他人から供給された電気の使用に伴う排出 他人から供給された熱の使用に伴う排出 セメントの製造に伴う排出 生石灰、ソーダ石灰ガラス、鉄鋼の製造に伴う排出 アンモニアの製造に伴う排出 土地利用の変化に伴う排出 一般廃棄物の焼却に伴う排出 産業廃棄物の焼却に伴う排出 |
| メタン |
ボイラーにおける燃料の使用に伴う排出 ばい坑炉における燃料の使用に伴う排出 金属精錬用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 無機化学工業品用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 無機化学工業品用ペレット焼成炉における燃料使用に伴う排出 か焼炉における燃料の使用に伴う排出 金属溶解炉における燃料の使用に伴う排出 触媒再生塔における燃料の使用に伴う排出 セメント焼成炉における燃料の使用に伴う排出 その他の窯業製品焼成炉における燃料の使用に伴う排出 反応炉、直火炉における燃料の使用に伴う排出 セメント等乾燥炉における燃料の使用に伴う排出 その他乾燥炉における燃料の使用に伴う排出 電気炉(アーク炉)における燃料の使用に伴う排出 その他電気炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用溶鉱炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用溶解炉における燃料の使用に伴う排出 ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出 航空機(ジェット機)の飛行に伴う排出 自動車の走行に伴う排出 鉄道車両(ディーゼル機関車)の運行に伴う排出 船舶の航行に伴う排出 石炭掘採(坑内掘)からの排出 石炭掘採(露天掘)からの排出 原油採掘に伴う排出 原油の輸送に伴う排出 原油の貯蔵、精製工程における排出 天然ガス採掘に伴う排出 都市ガスの生産に伴う排出 製品(カーボンフラック等)製造に伴う排出 家畜の反すう等に伴う排出 家畜のふん尿処理等に伴う排出 水田からの排出 農業活動に伴う穀・わらの焼却による排出 土地利用の変化に伴う排出 廃棄物の埋立処分場からの排出 下水処理場における下水の処理に伴う排出 一般廃棄物の焼却に伴う排出 産業廃棄物の焼却に伴う排出 |
| 一酸化二窒素 | ボイラーにおける燃料の使用に伴う排出 ガス発生炉、ガス加熱炉における燃料の使用に伴う排出 ばい焼炉における燃料の使用に伴う排出 金属精錬用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 無機化学工業品用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 金属精錬用ペレット焼成炉における燃料の使用に伴う排出 無機化学工業品用ペレット焼成炉における燃料の使用に伴う排出 か焼炉における燃料の使用に伴う排出 金属溶解炉における燃料の使用に伴う排出 金属加熱炉における燃料の使用に伴う排出 石油加熱炉における燃料の使用に伴う排出 触媒再生塔における燃料の使用に伴う排出 セメント焼成炉における燃料の使用に伴う排出 その他の窯業製品焼成炉における燃料の使用に伴う排出 窯業製品溶解炉における燃料の使用に伴う排出 反応炉、直火炉における燃料の使用に伴う排出 セメント等乾燥炉における燃料の使用に伴う排出 その他乾燥炉における燃料の使用に伴う排出 電気炉(アーク炉)における燃料の使用に伴う排出 その他電気炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用焼結炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用溶鉱炉における燃料の使用に伴う排出 銅・鉛・亜鉛用溶解炉における燃料の使用に伴う排出 ガスタービンにおける燃料の使用に伴う排出 ディーゼル機関における燃料の使用に伴う排出 ガス機関又はガソリン機関における燃料の使用に伴う排出 自動車の走行に伴う排出 鉄道車両(ディーゼル機関車)の運行に伴う排出 船舶の航行に伴う排出 製品(アジビン酸等)製造に伴う排出 麻酔剤(笑気ガス)の使用に伴う排出 家畜のふん尿処理等に伴う排出 畑作での肥料の使用に伴う排出 農業活動に伴う穀・わらの焼却による排出 土地利用の変化に伴う排出 一般廃棄物の焼却に伴う排出 産業廃棄物の焼却に伴う排出 |
1-2-3 調査の手法
1)調査地域の設定
温室効果ガス等の調査地域の設定の考え方としては、「1-3 調査・予測・評価の考え方」に述べたように、環境の状態を把握するための地域設定の必要はない。調査は全体として環境負荷低減に寄与していることを検討するためのシステムを設定し、その範囲を調査範囲とすることができる。
この場合の範囲としては、温室効果ガス等の削減対策の計画がなされている地域の範囲とともに当該事業の業種の範囲(電気事業者全体など)などがそれに当たる。
2)調査
調査としては、地域範囲に関わる事項と、工業系や業務・商業系の開発であれば当該業種全体に関わる事項について既存文献資料に基づいて調査を行う。
(1)地域における温室効果ガス排出量の状況 [1] 物質別排出量
[2] 部門別(産業部門、民生部門、輸送部門など)排出量
(2)業種における温室効果ガス排出量の状況
[1] 物質別排出量
[2] 排出の原因となる活動等の状況の指標(燃料使用量、生産額など)
(3)温室効果ガス等の削減に係る計画等
[1] 地域における削減計画等
[2] 事業者団体又は事業者が定める削減計画等
(4)地域又は事業者が行っている温室効果ガス等削減のための行動等
[1] 地域冷暖房等の地域におけるエネルギー利用の効率化のための設備等整備状況
[2] エネルギーのカスケード利用、廃棄物のエネルギー利用などの設備等整備状況
1-2-4 予測の手法
1)予測事項
温室効果ガス等の予測としては表4-3にまとめる事項がある。
表4-3 温室効果ガス等における予測事項
| 予測事項 | 予測内容 |
|---|---|
| 温室効果ガス等の排出量 | 種類別排出量 |
| 二酸化炭素換算総排出量 | |
| 削減対策 | 対策の内容 |
| 対策の実施者 | |
| 対策の確実さ | |
| 削減対策による削減量 | 種類別排出量 |
| 二酸化炭素換算総排出量 |
2)温室効果ガス等の排出量
(1)二酸化炭素
人為的な二酸化炭素の排出は基本的に燃料等の燃焼や石灰の化学反応に伴うものであるが、二酸化炭素の排出量の予測としては、これら燃料や石灰の消費量から直接求める方法の他に、各種活動に伴う燃料消費量を求める方法、LCAのために用意された資材の製造での排出量等の予測の方法などがある。
[1] 燃料等の消費量から直接排出量を求める方法
この方法では基本的に(1)式により算定する。
(二酸化炭素の排出量)=Σ{(各種活動量)×(排出係数)}・・・・・(1)
この方法では、燃料に含まれる炭素分が燃焼により二酸化炭素に変化するとして排出係数が設定されている。また、石灰の化学反応による二酸化炭素も考え方は同様であり、セメントにおいてはCaCO3から化学反応によって放散されるCO2分をカウントする。
なお、平成11年4月に制定された「地球温暖化対策の推進に関する法律施行令」において、温室効果ガス排出量の算定に必要な活動区分毎の排出係数について、政令で制定することとされており、毎年度公表されている。このことより、予測に用いる排出係数の設定にあたっては、毎年度制定される排出係数に留意し、最新の値を用いるものとする。
[2] 各種活動に伴う燃料消費量
この方法では、基本的に(2)式により算定する。
(各種活動に伴う燃料消費量)=Σ{(各種活動量)×(燃料消費原単位)}・・・・・(2)
ア.自動車の燃料消費量
自動車毎や車種毎の平均として示される燃費が利用できる。
イ.建設機械の燃料消費量
建設機械は稼動時間当たりの燃料消費量が示されている。
建設機械の稼動時間については、国土交通省などが用意している建設工事の積算基準を利用すれば工事種別毎に算定することができる。積算基準の図書の事例としては下記がある。
・(財)建設物価調査会 建設工事標準歩掛 など
ウ.建築物での燃料消費量
建築物で使用する照明、空調等のエネルギーについては建築用途別延べ床面積当たりの原単位として、地域冷暖房の計画資料や下記の統計などの参考事例がある。
・建築物エネルギー消費量調査報告書 (社)日本ビルエネルギー統合管理技術協会
[3] 統計資料によって燃料消費量原単位を設定する方法
面開発事業において用地に進出する個別企業が決定されていない段階での燃料消費量は、進出が想定される業種などをもとに概数として予測することになる。このとき、その活動量として設定できるのは敷地面積程度の情報となる。この場合において統計資料に基づいて敷地面積当たりの原単位を作成する方法は、基本的に(3)式で行う。
(燃料消費量原単位)=(燃料消費に係わる各種統計データ)/(各種活動量)・・・・・(3)
なお、各種活動量においては、敷地面積、延べ床面積、製造品出荷額、従業員数等が考えられ、以下の図書が参考となる。
ア.業種別の敷地面積のデータ
・経済産業省 工業統計(用地、用水編)
イ.燃料消費量に関するデータ
・経済産業省 石油等消費構造統計表
[4] LCAのために用意された資材製造での排出量等の予測方法
事業者による直接の行為ではないが、消費する資材等の製造や廃棄物の処理・処分に関わる各種活動に伴って排出される環境負荷量をすべて把握して、環境負荷削減を検討しようとする手法としてライフサイクルアセスメント(LCA:Life
Cycle Assessment)がある。
この手法において、例えば製品では環境負荷量を算定するために原料の採取や加工・組立といった製造及び物資の輸送など、製品が消費者に届くまでの複数の過程における環境負荷を予め積算した環境負荷原単位が検討されており、基本的に(4)式により算定する。
(二酸化炭素の排出量)=Σ{(各種活動量)×(LCA用に用意された原単位)}・・・・・(4)
また、これらの原単位の例としては下記の事例がある。
・建築学会 建物のLCA(案)
・土木学会地球環境委員会LCA研究小委員会 建設業の環境パフォーマンス評価とライフサイクルアセスメント
・文部化学省金属材料技術研究所 予備的LCAのための4000品目の環境負荷(インターネット情報)
(2)メタン及び一酸化二窒素
メタン及び一酸化二窒素の排出量の算定は活動量に対して設定された排出係数を乗じる方法が採用されており、下記の図書が参考にできる。
・地球温暖化対策の推進に関する法律に基づく地方公共団体の事務及び事業に係る温室効果ガス総排出量算定方法ガイドライン 平成11年8月 環境庁地球環境部環境保全課地球温暖化対策室
なお、算定式については上述した二酸化炭素排出量の算定式と同様である。
(3)温室効果ガス総排出量の計算
温室効果ガスの総排出量は二酸化炭素の地球温暖化に寄与する程度を1とした地球温暖化係数(表4-1参照)に基づいて二酸化炭素換算量で表示される。その算定式は(5)式のとおりである。
(温室効果ガス総排出量)=Σ{(個別の温室効果ガス排出量)×(地球温暖化係数)}・・(5)
3)削減対策の内容
(1)検討事項
温室効果ガス等において環境負荷削減に関する検討事項としては下記の視点で行われる必要がある。
[1] エネルギーなどの排出原因となる資源の利用量の削減に関する事項
室内温度の適正化などによってエネルギーの消費量を抑えるなどの温室効果ガス等の発生原因となる資源や資材の消費を抑制する対策。
[2] エネルギー利用や供給の効率化等に関する事項
発電におけるコンバインドサイクルなどによる発電効率の向上策など、エネルギー転換設備や供給設備の改善などによる対策。
[3] 未利用エネルギーの活用に関する事項
コージェネレーションや河川水熱などの未利用エネルギーを利用して一次エネルギーの消費量を削減する対策。
(2)検討内容
温室効果ガス等では削減の努力が環境影響への回避・低減の評価において欠かせない事項であるとともに、その対策の実施及び効果の確実性が必ずしも確保されていない場合がある。そのため、対策そのものが予測の対象と考えることができる。記述する内容としては以下の事項が必要となる。
[1] 対策の内容
[2] 対策の効果(原単位等)及びその確実性
[3] 対策の実施者
[4] 実施の確実性
4)対策による削減量
前項でまとめた対策の効果に基づいて事業における対策による削減量及び設定したシステムでの総削減量を算定する。
1-2-5 評価の手法
1)回避・低減に係る評価
(1)評価事項
温室効果ガス等における環境影響の回避・低減に係る評価としては、代替案の比較及び削減量評価のために設定したベースラインとの比較によって、予測段階において提示した環境保全に関する措置を前提に次の事項について記述する。
[1] ベースラインからの削減量
対策又は事業を実施しない場合の既存施設又は全体システムからの排出量をベースラインとして、ベースラインからどの程度温室効果ガス等を削減しているか評価する。なお、温室効果ガス等におけるベースライン設定の考え方は後述する。
[2] 代替案の比較
事業計画において設定できる代替案の中で、採用案が最も温室効果ガス等の排出量が少ないかどうかを検証する。なお、代替案の設定の考え方は後述する。
[3] 環境保全措置の実現性と効果の確実性
事業によっては建設事業者と運用者が相違するようなケースある。この場合、方策を明示して実施の確実性を確保について記述する。 また、措置の内容によっては、効果の予測と実際のぶれがある場合や、新しい技術を導入する場合などは、その未確定さを記述するとともに、期待する効果ができない場合の代替案等の削減効果を確保する方策を記述する。
(2)温室効果ガス等におけるベースライン設定
[1] ベースライン設定に採用する原単位
温室効果ガス等の排出に関わるエネルギー消費の原単位は一般家庭の生活に係る原単位は現在でも上昇傾向にある。一方、製造業や輸送など産業部門の単位活動量当りの原単位は体勢的には減少傾向にある。
したがって、ベースラインを設定する場合には単純に現在の値を設定するのではなく、基準年を設定して、その年次における原単位を採用して排出量を算出することも考慮する。
[2] システム全体で評価する場合の検討範囲
システム全体で評価しようとする場合には、調査地域の設定で述べたように、地域的なものについては、国又は地方自治体の定めている計画等との整合性に係る評価で扱うこと場合などは、その行政区域範囲が検討範囲となる。その他のものとしては、当該事業における業種全体又は個別企業の範囲を全体システムとして設定することが考えられる。
例としては発電事業における電気事業者全体又は個別電力会社の範囲を全体システムとして設定する場合である。
(3)温室効果ガス等における代替案の設定
温室効果ガス等に関する代替案としては、次の事項で検討することができる。
[1] 計画の基本フレームに関する事項
計画の基本フレームに関しては事業の経済的要素など環境以外の要素との関連から設定が難しい場合がある。この場合には、当該基本フレームが環境以外の検討要素とどのように調整が図られているかを記述する。
[2] 資源・エネルギー消費の効率化を図る設備等の導入
[3] 未利用エネルギーなど廃棄されている資源・エネルギーの導入
[4] 原因物質の使用の抑制
2)国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る評価
国や地方自治体において定めている環境基本計画や地球温暖化対策等の計画において温室効果ガスの削減目標等が定められており、その値との整合性を評価する。
資料一覧へ戻る