平成13年度第1回陸水域分科会
資料2-3
3 陸水域生態系の環境影響評価の手法
3-1 陸水域生態系へ与える影響の整理
環境影響評価で対象とする地域の生態系の特性を把握するには、まず基盤となる環境を類型化し、まとまりを有する地域ごとに区分することが有効である。陸水域生態系の類型化については「自然環境のアセスメント技術(Ⅱ)」(環境庁,平成12年8月)に示されているが、陸水域生態系が陸水域を中心としてそれと連続する陸域で構成されていることから、陸域については陸域生態系で整理された考え方を適用するとともに、水域や移行帯については「水」やその作用に着目して類型区分する。その区分ごとの概要を把握した後に評価する上で重要な類型や生態系への影響を検討する。
陸水域における事業では、「陸域から水域へ」、あるいは「水域から陸域へ」という直接的な環境の変化をはじめとして、横断工作物の設置に伴い河川を縦断的に分断することによる遡上降河阻害、生物相の単純化など事業計画地周辺の類型でも様々な影響が予想されることから(図-2,3参照)、予測に際してはまずどの類型が影響を受けるかを明らかにする必要がある。
影響を受ける対象となる環境要素を明らかにするためには、従来から用いられることの多いマトリックス表による検討だけではなく、影響が類型や注目種・群集あるいは生態系の機能などにどのように伝わっていくかなど、影響要因と環境要素間の影響のネットワーク的な伝播経路を検討するとともに、影響フロー図等を用いてわかりやすく整理することが重要である。特に陸水域生態系では事業による影響以外に突発的に生ずる洪水などに伴う環境変動も整理しておく。また、陸水域生態系では、影響要因-環境要素間に水を介した影響の伝播があるものを主体に整理するとともに、作成したフロー図にもれがないように、マトリックス表も作成して、相互にチェックすることも必要である。
これらは、類型への影響、注目種・群集、生態系の重要な機能への影響のいずれについても、基本的には同様な形で用いることができる。このような手段で影響の検討結果を整理し、事業者が事業による影響をどのように捉えているかをわかりやすく示す。
なお、影響フロー図や影響マトリックス表等は様々な形式がある。フロー図のボックスの配置や線の引き方も作り手の考え方によって異なる。したがって、例示したものが標準的であるということではない。
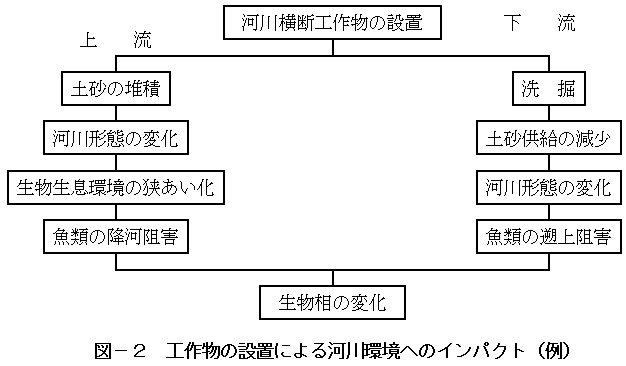
○河川工作物の設置により、上流域では堆砂により水生生物の生息環境が狭隘化し、底生動物や付着藻類の生息・生育条件を
大きく変化させ、魚道が付帯しない場合には魚類の降河行動への影響も大きい。
○下流域では上流の土砂が扞止されるため、ダムの直下に洗掘が起こり澪筋が定まらず魚類の遡上に大きな影響を及ぼす場合
もある。また、土砂の供給が減少するため、河床形態(瀬や淵の存在等)が変化し、底生動物相や付着藻類相にも変化が予想
される。
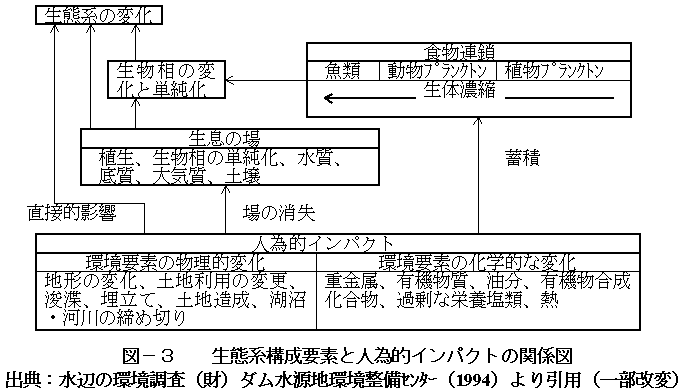
○調査で把握すべき事項を具体化するには、事業のインパクトとそのインパクトにより一般的に予想される影響を想定する必要 がある。陸水域に係わる事業について考えると、直接的影響として、植生の消失や動物の行動阻害等、物理的及び化学的変化 による「場の消失」として地形の改変や湛水による水環境の変化などが、蓄積として重金属などの汚染物質による生物への影 響等が想定できる。
3-2 調査、予測項目の選定
(1)調査、予測項目の選定
生態系への影響評価には、「基盤環境と生物群集に着目した影響評価」、「注目種・群集に関する影響評価」および「生態系の機能に関する影響評価」等がある。
これらの影響評価のための調査項目の選定にあたっては、まず前述のように注目種・群集や重要な機能に及ぶ影響要因を整理した影響フロー図を基に、注目種・群集や重要な機能など、生態系に及ぼすと想定される影響を検討する。
調査項目と予測項目は影響要因と影響を受ける環境要素の関連の中からその重要性に応じて選定する。対象とする項目やその手法は、着目した影響の流れについてその実態が把握でき、影響要因が時間的・空間的にどのように環境要素に作用するかを予測できるように設定する。
調査手法および予測手法の検討は、どのような事象が予測に適しているのか、そのために必要な調査はどのように設定すればよいかの順序でおこなう。検討にあたっては既往の手法の応用や組み合わせによる手法の検討に加えて、新しい科学的知見、技術による試みを積極的に活用する。特に水環境等に関する物理的、化学的影響については定量的に調査、予測する手法を活用することが必要であり、生態系の影響評価をできる限り科学的・定量的に行うことが重要である。
調査、予測の項目や手法の設定にあたっては、現在の科学的知見ではすべての環境要素とその相互関係を定量的に調査、予測することは困難であることから、定量的な調査や予測が可能なことと既往の知見等から定性的に予測することを分けて検討する。特に定量的な調査(測定等)が可能な対象であっても定量的な予測は不可能な場合があることに留意する。また、理論的には可能な調査でも長年月を要するため環境影響評価では現実的でないこともある。
重要なことは、影響評価を行う当事者がどのような視点で問題を検討し、どのような目的を持って調査、予測の手法を選定して実施したのかが明確に示されることである。調査、予測の項目や手法を選定した理由についてはわかりやすく明示することも必要である。 なお、表-1に示した各項目の検討に際しては環境保全措置との関係にも十分配慮することが必要である。
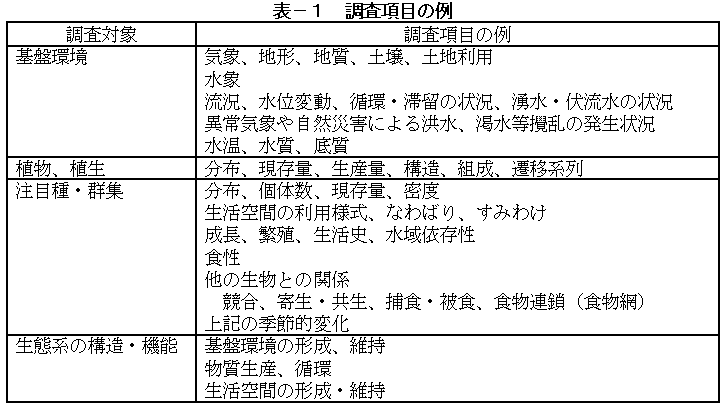
(2)基盤環境と生物群集に関する調査、予測項目
基盤環境と生物群集に関する調査は、「地域特性の把握」で捉えた生物種・群集の生息・生育基盤となる「水系」「地形」「植生」などの環境要素の分布状況と、それらを基盤とした動植物の生育・生息状況から、構成要素間の関係や生態系の構造を把握することが主体である。
対象項目は類型区分ごとの基盤環境の関連、生育・生息空間の存在状況、そこに成立する動植物群集およびその関連、動植物の種間関係、行動圏、生活史における水域の利用状況、特に繁殖の場の存在状況等とする。動植物群集の状況については「動物」「植物」項目の調査で明らかになる生息状況や生息環境等の基礎的情報も含めて整理する。これらの構成要素間の関連の特徴を明らかにするためには、生態系として把握する単位となる類型区分のスケールを的確に設定することが必要である。
対象とした生態系の構成要素に及ぼす事業による直接的・間接的な影響を想定し、構成要素間の関連から生態系への影響に対して概括的な予測を行う。
(3)注目種・群集に関する調査、予測項目
注目種・群集の選定は、事業による影響の検討により選定される評価する上で重要な類型区分に生息し、その影響を適切に把握できるものを対象とする。事業による影響を受けやすいと考えられる複数の生物群集の中で、上位性、典型性、特殊性の視点から、対象地域の生態系と事業による生態系の変化をよりよく表現できるような生物種・群集と、それらの生活環境、生活型、食性、繁殖状況、関連する生物の分布などを調査項目として選定する。
項目の検討の際には、事業実施に伴う環境要素(地形や水質・底質など)の変化と注目種・群集の生息状況の変化が影響として関連づけられること、および注目種・群集と相互に関係する生物種が明らかで、注目種・群集への影響が生じた場合、他の生物(生態系)への影響が予測できることに留意する。
なお、生活型や食性が同じような生物種・群集を多く選定すると、調査、予測、評価の作業が煩雑になるので、対象とする影響を最も的確に把握できる種・群集を選定することが効率的であると考えられる。
これらの種・群集について、「動物」「植物」項目の調査における生息状況や既存資料による生息環境等の基礎的情報も参考に、事業による影響要因が及ぼす直接的・間接的な影響を想定し、注目種・群集への影響に対して予測を行う。
| 【注目種・群集の選定にあたっての留意点】 ○陸水域生態系の場の成り立ちや、連続性、変動性、地理的隔離性などの特性へ事業が及ぼす影響を把握するという視点から、これらの特性を指標する注目種、群集を選定する。 ○河川では洪水の頻度や規模が生態系を形成する重要な要素のひとつであり、洪水によってもたらされる生態系の構造や機能の変化や、生物群集とその生活への影響という視点が必要である。すなわち河川ごとの特性はおもに洪水や水量・水位の日変動、季節変動によって形成され、生態系の基盤環境や生物相に影響を及ぼす。特に季節的な変動は河川の最も本質的な要素であることから、これらの視点にも留意して注目種・群集を選定する。 ○湖沼や湿原等の止水域にも河川水や地下水の流入・流出による流量・水位の変動のほか、洪水や異常気象に伴う波浪による攪乱や渇水による水位低下がある。特にこれらの影響を強く受ける移行帯に依存している生物種・群集に着目して注目種・群集を選定する必要がある。 |
(4)生態系の機能に関する調査、予測項目
生態系の機能については、水質や底質の形成・浄化といった環境形成・維持機能や、動植物の休息地、隠れ場、繁殖地、採餌地、移動経路といった生育・生息空間の形成・維持機能、物質生産・循環機能などを対象項目とする。
生態系の機能自体は構造に比べ捉えにくいことから、当該生態系でとくに重要な機能やそれを指標する基盤環境等の構成要素が明らかな場合に予測対象とする。
対象とした機能についてはそれを支える生態系の構造や、水質・底質、動植物等を構成要素を関連づけて整理する。なお、対象とした機能を指標する生物種・群集が見いだされる場合は「注目種・群集の調査」における典型性の視点から注目種・群集として取り上げて影響評価を行う。
生態系の機能に関する調査、予測についても他の調査と同様に影響フロー図に基づいて項目を検討する。影響フロー図には現時点で考えられる影響をほぼ網羅的に示す必要があるが、現在の科学的知見ではすべての項目と影響の流れを定量的に調査し、予測することは難しい場合が多いと考えられる。海域生態系では生態系の有する機能の仕組みを簡略化することで数値計算を可能にした数値モデルによる予測が用いられることがあり、陸水域でも海域と隣接した汽水域や水塊として捉えられる湖沼についてはこのような数値モデルの積極的な活用が求められる。
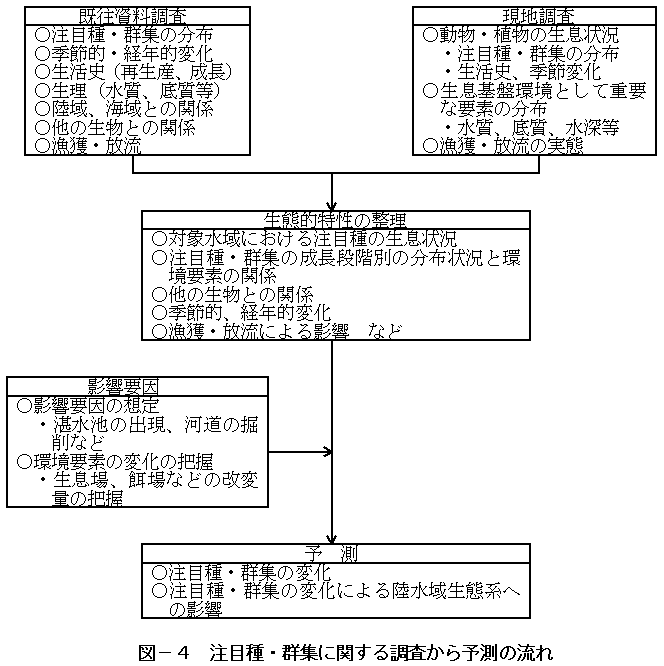
3-3 陸水域生態系の調査方法
(1)調査、予測地域の設定
調査、予測地域の設定にあたっては、事業による影響要因の及ぶ類型と基盤環境要素の分布、調査、予測の対象となる生物の生活史と利用する類型の分布などに十分留意して検討する。
特に陸水域に生息する生物は生活史の各段階で生息場所や餌資源量などが変化することが多いので、その全体が把握できるような調査地域を設定する。なお、渡りや回遊などで広範囲を移動する生物については、現地調査を詳細に実施する範囲と既存資料などにより広域に調査を実施する範囲に分けて検討することが効率的である。
予測地域は調査地域を基本とし、事業により対象となる類型、基盤環境要素や生物種・群集へ影響が及ぶ範囲を十分に網羅するよう設定する。一般的には、直接的影響は事業による改変区域、間接的影響は改変区域の周辺を基本として設定するが、陸水域生態系の場合は、水の流下や生物の遡上降河といった「構成要素の連続性」に着目し、直接的影響についても改変区域の上下流区間を含めた、より広い範囲で考えることを基本とする。
河川の分断による生物の移動阻害は、河川全体や海域生態系にも影響を与える可能性がある。特に対象河川の延長が長い場合は、調査地域よりも予測地域を広く設定する場合も考えられる。一方、湖沼の埋立て事業などにおける調査地域は、湖沼の規模により異なるが、生物種・群集を捉える調査の実施可能な範囲として、水深のある湖沼では湖棚まで、水深の浅い湖沼や漁業資源が存在する湖沼(シジミ、アサリ等が存在する汽水湖等)では湖沼全体など、地域を広く設定する場合が考えられる。
また、陸水域生態系では魚類など水域のみを移動経路としている生物種で、地史的な背景により流域ごとに個体群が隔離されていることがある。地理的に隔離された個体群が事業実施予定地に係る流域のみに分布が限定されることが明らかな場合は当該個体群を調査対象とするが、例えば隣接流域に交流のない個体群がいる場合の遺伝的関係や、事業により交流が阻害される場合の隣接流域の個体群の存続など、保全を考える上で事業対象流域以外の個体群についても考慮が必要な場合はこれらの流域も調査対象範囲とするべきであろう。
環境保全措置の検討後、事後調査を計画した場合に用いる地点(定点)として調査、予測地点の一部を確保する。事後調査のための調査地点は、直接改変を受けない地点など、同じ地点で将来的にも調査が行える場所とする。このためには調査、予測の着手段階で事後調査計画を検討しておく必要がある。
(2)調査時期の設定
調査対象となる注目種・群集について、植物では成長が活発な時期や開花・結実時期、動物では繁殖、渡り、移動、回遊や、変態等に伴う生息環境の違いなど、生活史における各段階の生息状況が把握できる時期・回数、また、基盤環境の季節変動が把握できる時期を含むよう調査時期を設定する。
河川では基盤環境の季節変動とともに年変動があり、調査対象とした年が必ずしも平年の状況を示していない可能性があることや、河床材料や河畔植生など動植物の生息生育基盤となる環境要素も変動することから、調査の対象期間は複数年設定することが望ましい。
(3)調査方法
生態系に関する影響予測は、基盤環境等の構成要素、注目種・群集、生態系の構造・機能などの事業による変化を予測することを通じて把握する。したがって、調査は環境要素の変化が生物にどのような変化を及ぼすかということをできるだけ定量的に把握するための情報を得ることが目的である。
なお、生態系の構成要素には定量的な調査が可能であっても、定量的な予測までは不可能であることも多いことに留意する必要がある。
1)基盤環境と生物群集の関係の調査
基盤環境と生物群集の調査では、類型区分ごとに生物種・群集の生育・生息環境となる基盤の分布とその場における生育・生息の制限要因の概要を明らかにする。
陸水域生態系では生育・生息環境を形成する水質、底質、地形・地質や植生などの基盤環境要素と、これらを基盤環境のまとまりから類型化される区分ごとに生物種・群集を調査し、基盤環境要素と生物群集の関係、階層性、捕食・被食関係など生物相互の関係を把握する。
調査は「水環境」、「地形・地質」、「動物」「植物」など他の環境影響評価項目の調査との関連で実施の順番、タイミングに留意する必要があるが、基盤環境要素に関係する調査は生態系の調査よりも先行していることが望ましい。
なお、調査の実施段階で生物種相に新たな情報が得られた場合や、逆に選定した注目種・群集の情報が得られなかった場合など、注目種・群集の見直しが必要となったときには、調査、予測等の手法を含めて見直しを行い、調査はその時点から必要な期間を実施する。
2)注目種・群集からみた生態系の調査
注目種・群集の調査では、生育・生息の制限要因を明らかにする必要があるため、生育・生息環境を形成する基盤環境要素と、捕食・被食関係などを通じて注目種・群集と関係する動植物種・群集の生態を調査する。
生物はその生活史に応じて生息場所や餌資源など選好する環境を変化させることが多い。したがって、調査範囲・地点などは注目種や注目種と深い関わりを持つ種の生活史を極力把握できるように設定する。種によっては特に繁殖期等の生活史のごく一時期のみ利用する場や、ごく小規模な場を失うことにより生存が危ぶまれるようなものもあることから、そのような時期や場を見落とすことなく把握できるように設定することが必要である。
手法の検討の際には、事業実施に伴う環境要素の変化と注目種・群集の生息状況の変化が把握できること、および注目種・群集と相互に関係する生物種の変化が把握できることに留意する。
なお、魚類等水域を移動経路とする生物種・群集の生息予測では、生息環境条件のほかに個体群の供給源として周辺の個体群との交流の状況を把握する必要がある。
3)生態系の機能に関する調査
生態系の機能に関する調査は、基盤環境要素や生息・生育空間の形成・維持、物質の生産・循環等に関係する構成要素の動態を把握する調査を主体に行う。基盤環境要素の多くは他の環境影響評価項目の対象となっているため、これらの調査、予測との連携を図る必要がある。
数値モデルによる予測を行う場合は、予測する項目に適した予測範囲・計算条件・パラメータなどを十分検討し、必要なデータが的確に得られるように調査計画を立てる必要がある。
数値モデルによって調査できる機能は現在の知見では生物生産、物質循環、浄化量などに限られており、他の多くの機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって調査を行うことが多い。その場合でも予測に用いるデータが極力客観的・定量的に示せるような調査計画を立案する。
3-4 陸水域生態系の影響予測
(1)影響予測の基本的な考え方
陸水域生態系の予測は、地形改変や水量、水質等の変化など基盤環境要素の直接的な影響と、基盤環境要素や相互関係を持つ動植物に徐々に現れる変化などの間接的な影響に分けて行う。
環境影響の予測を行う際には、対象とする影響要因-環境要素の関連を整理した上で行い、直接的な影響については、例えば水の有無、水量、水温の変化など生息生育に直接関わる基盤環境要素の改変の程度について可能な限り定量的に把握する。また、副次的であったり時間の経過により徐々に現れる間接的影響についても、できるだけ定量的に予測する必要があるが、既存事例や専門家の意見を参考とした定性的な予測も実施する。例えば、河川の特性である「浸食と堆積」については、環境影響評価では事業による浸食作用や堆積作用への影響との観点から、横断工作物の上流側での堆積、下流側での浸食や河床の固定化(粗粒化)等の直接的影響は把握が比較的容易であるが、より下流側では間接的影響が主体となり、水理学的な検討のほか既存事例をもとにした影響の検討も必要である。調査予測対象は底質や底生動物、河岸の移行帯の消長が考えられるが、浸食や堆積の特性をみて、対象範囲や時間軸を考慮した予測対象時期を設定することが必要である。
なお、予測に用いる手法の選定の際には、その選定理由、適用条件、範囲を明らかにし、以下の点に留意する必要がある。
[1]生態系の構造や機能のどの部分を対象とするのか、どの生物を対象とするのかを選定した理由とともに明確にする。
[2]科学的・技術的に可能な範囲で、できる限り定量的な予測を行う。特に流量・流速、水質等の物理的・化学的影響の程度については時間的空間的に定量的な予測を行う。
[3]生態系を構成する生物については定量的な予測の難しいことが多いが、必要に応じて定量化・モデル化を試みる。また、定量化が困難な場合でも、生物の生理的・生態的特性を十分検討し、感覚的な予測ではなく、データに基づいた客観的な予測を行う。
[4]湖沼等における物質生産や物質循環などの生態系の機能については、機能の仕組みを簡略化して数値計算を可能にしたモデルが開発されているものもある。それらのモデルを利用する場合には必要なパラメータを得て予測を行う。
[5]回遊魚の遡上行動・能力等の測定実験などの検討データが、予測に効果的な場合がある。必要に応じて実験的手法の検討を行う。
[6]結果の記載にあたっては図表を添付するなど、わかりやすい説明をするとともに、結果を出したプロセスの明示、予測の前提条件、パラメータ設定の根拠、データやモデルの精度と不確実性などを記述する。
(2)予測時期の設定
予測対象時期は、対象とする生態系それぞれで影響が最大となる時期として対象事業の工事中の代表的な時期、及び生態系が安定する時期として供用後一定期間経過した時期を基本として設定する。特に直接的影響については基盤環境の直接改変を行う工種の終了時や施工の完了時を予測時期とする。また、対象となる注目種・群集の生活史で、影響が最大に見積もられる季節も対象時期とする。なお、時間とともに影響が大きく変動することが予想される場合や、供用後を対象として陸水域特有の台風等による増水などにより稀に起こる基盤環境の変化(レアイベント)があることも踏まえて、可能な限り時間的な影響の変化が捉えられるように設定する必要がある。
また、環境保全措置を講じた場合は、それぞれの措置が効果を発揮することで生態系が安定すると想定される時期を対象とする。
(3)予測手法
陸水域生態系に関する構造・機能については確立された予測手法はないが、影響を受ける環境要素のうち物理・化学的環境要素の変化についてはできる限り定量的な予測を行う。定量的な予測手法は数値モデルを用いる手法のほか、簡易な手法による計算や既存事例による手法もある。
定量的な予測手法がある物理化学的環境要素の種類と予測モデルの概要については、「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会中間報告書(平成12年8月p267参照)」に示した。要素の種類では流れ、水質(SS,pH,BOD,COD,DO,N,P、塩分、水温等)などがある。
数値モデルや簡易な手法による計算で予測を行う場合には現況のデータやモデルのパラメータを現地調査、実験的手法、及び既存資料などによって取得する。その際には、できるだけ代表性のあるデータを取得することや正確な現況再現を行い、モデルとパラメータとの妥当性を検証することが重要である。また数値モデルによる予測を行う場合には予測する将来条件の検討も十分に行い、事業による影響が正確に反映されるようにパラメータを設定することも重要である。また、これらの予測の条件やパラメータなどの適切さと予測結果の妥当性・不確実性などについてはわかりやすく記述する必要がある。
1)基盤環境と生物群集の関係への影響予測
基盤環境と生物群集に関する予測は、基盤環境と生物群集の関係の調査結果から、事業の影響要因が基盤環境や生物群集、あるいはその関係に与える影響を概括的に幅広く予測する。基本的には事業により直接的な改変を受ける生態系の構成要素を明らかにする。特に繁殖の場が失われる生物群集について明らかにする。
また、生物群集の生息場所や構成要素が変化する可能性については類似事例や既存の知見を参考に検討する。
これらの検討を通じて、陸水域生態系の水平構造、縦断的・横断的な基盤環境の構造に対する影響の程度を定性的に予測する。
2)注目種・群集からみた生態系への影響予測
注目種・群集からみた生態系への影響予測は、事業の実施による「水環境」の変化を主体として、選定された注目種・群集等の生育・生息への影響を予測し、それらの結果を通じて生態系の構成要素・構造や、機能への影響を含めて予測する。
生態系への影響については、注目種・群集が、上位性、典型性、特殊性等のどの視点から生態系の特性を指標しているかを基本に、注目種・群集が選定された経緯や、影響の伝播経路などを参考に主に以下の観点から検討する。
[1]注目種・群集と同様の栄養段階や、生活史、生活形を持つ種・群集の変化
特に生活史、生活形の上で河川の遡上降河等の回遊や、陸域・水域双方を利用する動物種群の存在は陸水域生態系の連続性を表徴する重要な要素であるので特に留意する。
[2]注目種・群集と相互関係にある種・群集の変化、特に食物連鎖構造の変化
注目種・群集と捕食-被食、共生・寄生、競争、すみわけなどの種間関係にある種・群集についてその動態を予測する。たとえば河畔植生を典型性の注目種・群集として選定した場合、生産者としての観点から河畔植生に食物を依存する栄養段階の上位の種・群集への影響を予測する場合や、上位性として水域の捕食性の魚類を捉えたときに、予測される生息状況の変化によって食物連鎖構造の変化を検討する場合が考えられる。
[3]注目種・群集により形成される基盤環境の変化とそこに依存する種・群集の変化
たとえば植物や植物群落が生息空間を形成している場合、それらの場の変化とそこを生息の場とする種・群集への影響を予測する。
[4]注目種・群集が関わる生態系の機能の変化とその機能に関係する種・群集の変化
注目種・群集が水質、底質、土壌等の基盤環境の形成や維持に寄与している場合、それら機能の変化とそれに伴う構成要素の変化について予測する。
注目種・群集について影響を予測するには、影響をどのように捉えるかが重要である。しかし、現状では生物の生理・生態と環境要素との関連が解明されているものは少なく、環境要素の変化に対して起こる生物の変化を定量的に予測するのは、生物が消失するような影響が著しい場合を除くと困難なことが多いことや、環境要素の変化が注目種に及ぼす影響の程度も生物の成長や生活史の段階によって変化することもあるので、影響予測が定性的になり不確実性を伴うことが多いことに留意する必要がある。特に既存知見や研究成果を援用して影響を予測する際には、注目種の生理・生態特性やハビタットの利用特性が地域によって異なる場合があることにも留意する必要がある。
3)生態系の機能に関する影響予測
生態系の機能に関する予測は、主に事業の実施に伴う機能の向上や低下または変化について把握する。しかし、生態系の機能は様々な環境要素と生物が複雑に関係しており、多くの機能については、確立された予測手法はない。このため予測にあたっては機能に関連する生態系の構造として、基盤環境と生物群集の関連や、典型性の視点から指標される注目種・群集の予測結果、さらに他の環境影響評価項目の予測結果なども援用する必要がある。
前述のとおり数値モデルによって予測できる機能は今のところ生物生産、物質循環、浄化量などに限られており、他の多くの機能については定性的な手法、あるいは事例解析的な手法によって予測を行う。その場合でも予測結果の根拠は極力定量的に示すことが重要である。