SEA総合研究会報告書 中間報告書
戦略的環境アセスメントに関する国内外の取組と我が国における今後の展望について(平成11年7月)
第2節 戦略的環境アセスメントの今後の展開に向けた課題
(1)戦略的環境アセスメントのケーススタディの実施
環境庁が平成10年11月に開催した国際ワークショップにおいて、海外から参加した戦略的環境アセスメントに関する有識者や実務者が揃って強調したことは、「まず、始めてみることが重要である」ということである。戦略的環境アセスメントでは、その対象が事業アセスに比べて非常に広範であり、また、戦略的環境アセスメントでの結果は対象とする案件の意思決定過程において用いられる必要があるため、個々の案件の意思決定の手続に沿って実施することが必要である。このため、ケーススタディによる検証を行うことなく、詳細な手続を画一的に定めることは困難であり、まず、柔軟な形で取組を開始することが適当である。欧州共同体においても、まず、各加盟国において行われている戦略的環境アセスメントのケーススタディをとりまとめ、これを踏まえつつ、戦略的環境アセスメントに関する指令案の検討が行われている。我が国では、港湾計画などの一部の例外を除いては、政策・計画・プログラムについて、その環境影響を評価する取組事例は少なく、今後、ケーススタディを積み重ねていくことが必要である。
ケーススタディの対象としては、環境への影響をある程度具体的に評価することが可能であり、その結果を当該政策や計画に反映させることのできるもの、例えば、事業に枠組みを与える特定の地域の計画や個別事業の基本計画等が取り組み易いと考えられる。東京都においても、総合環境アセスメント制度の導入に当たり、事業アセスメントの対象事業を含む広域開発計画について試行を実施することにしている。
今後、国レベルでは、ケーススタディの対象となりやすい特に環境配慮が必要な特定の個別計画や、環境面での影響が明確になる環境セクターの計画などを対象として環境アセスメントを実施することが考えられる。地方公共団体でも東京都をはじめ、地域計画等に対する環境アセスメントを実施しようとの動きが見られる。このため、地方公共団体がケーススタディを行うに当たって参考となるよう、戦略的環境アセスメントの考え方や評価手法等をまとめた手引きを提供すること等により、その取組を支援することが必要である。
(2)我が国における政策や計画の策定プロセスの整理
図4-2-13 複合評価の考え方
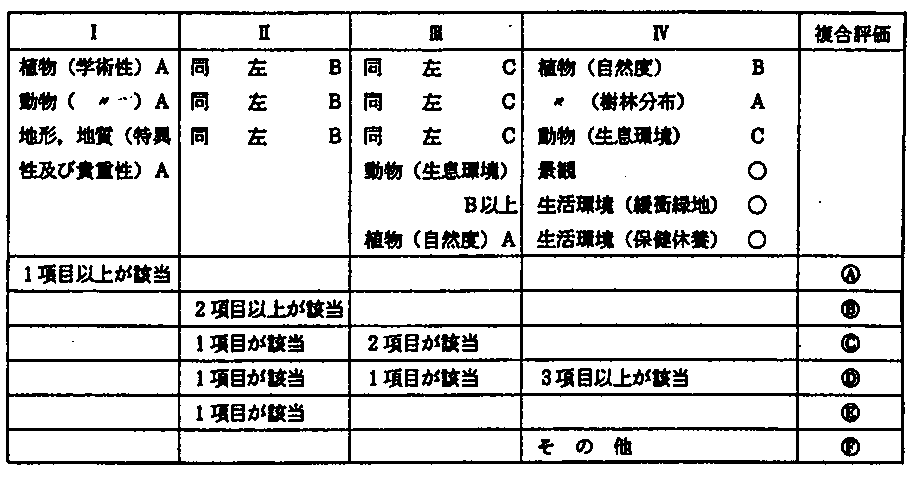
第1節でも見たように、戦略的環境アセスメントは、各案件の立案から決定に至るプロセスにおいて、環境面からの評価を行い、評価を行った結果を当該政策や計画に反映させていくものであり、評価を行うプロセスも、原則として、対象となる案件の策定プロセスに即したものとすることが重要である。
我が国では、国の取組の基本的な方向を定めた全国総合開発計画、経済計画、環境基本計画や土地利用計画、各地域のマスタープラン的な性格を有する都市計画や自然公園計画、水資源開発に関する計画、新幹線、空港、道路整備等の交通系の計画等の分野別の諸計画など、多数の政策や計画が策定されているが、これらは、法律に基づくものであるか否かといった法的性格や、財政的な裏付けの程度、事業や他の政策・計画等との関係の程度、将来の決定に及ぼす影響の程度等の政策や計画の抽象性・具体性、その策定に当たって調整が図られる行政機関や審議会・利害関係者との関係等の策定プロセスが極めて多様である。今後、戦略的環境アセスメントの制度化の検討を進めるに当たっては、それらの計画の策定プロセスを整理していくことが必要である。
特に、戦略的環境アセスメントでは、アカウンタビリティや透明性を確保することが必要であり、環境面からの評価が適切に行われるよう、評価の結果を文書にとりまとめ、環境部局や住民等からの意見が反映される機会が設けられることが望ましい。近年、審議会の公開、公共事業に対する費用対効果分析の導入や、規制の導入に当たってのパブリックコメントの導入等が急速に進んでいるほか、平成11年5月には情報公開法も成立したところであり、これらの最近の動向も踏まえつつ、諸政策・計画の策定プロセスを把握した上で検討を進めることが必要である。
(3)環境保全上のメリットを得られる戦略的環境アセスメントの対象の明確化
(2)の検討と併せて、戦略的環境アセスメントを行うことにより環境保全上メリットを得ることのできる政策や計画を具体的に明らかにしていくことも必要である。
この際、『政策』、『計画・プログラム』から『事業』へと連なる諸段階のうち、どの段階において、どのような環境要因について、どのような手続で環境アセスメントを行うことにより、所要の目標を達成することができるのかという観点からも、検討を行うことが必要である。原則的には、すべての段階で適用するということであるが、例えば、事業の実施段階と計画段階において環境アセスメントを行う場合には、計画段階のアセスメントで集められた情報を活用しないと同じ作業を繰り返すことにもなりかねず、先行評価を活用して、重複感をなくす必要がある。また、政策や計画の段階において環境アセスメントを実施することにより、事業の実施段階で行われる環境アセスメントが費用効果的に、かつ円滑に行われるという効果も期待される。実際に、オランダでは、従来は、水道会社がそれぞれ地区毎に水確保の仕方を検討し、事業段階での環境アセスメントを行っていたが、新たに国の中央レベルで戦略的環境アセスメントを実施することとなったため、事業段階で行われる環境アセスメントでは、大幅な時間と費用と労力が節約に繋がったという事例も報告されている。
また、環境配慮を行うことが効果的であっても、戦略的環境影響評価の適用を待たずとも、既に環境配慮を行う十分な仕組みが存在している場合もあり得るし、一方、環境配慮が行われていても、その項目等が十分ではない場合や、仕組みが透明性や信頼性等の観点から十分ではない場合等があり得る。このため、個々の『政策』や『計画・プログラム』が策定される過程で、環境配慮がどのような制度的仕組みで行われることとなっているのかを明らかにすることも必要である。
(4)環境政策手法の中での戦略的環境アセスメントの位置付けの整理
戦略的環境アセスメントの一つの大きな意義は、持続可能な経済社会の構築に向け、行政の意思決定メカニズムに環境への配慮を組み込むことであるが、そのための方策としては、既に様々な取組が行われている。
例えば、各種計画の策定に当たっては、環境基本計画との調整を図るため、計画の策定省庁は環境庁に対して協議を行っている事例がある。同様に、地方公共団体においても、環境管理計画や、環境基本条例に基づく環境基本計画が策定されているが、地方公共団体が策定する計画は、予め環境に脆弱な地域を示すことにより、開発を回避し、保全が図られるよう誘導する事例も見られるところである。また、中央環境審議会では、環境基本計画の進捗状況を事後的に点検しているが、これらも社会経済的な施策に環境への配慮を組み込む一つのインセンティブとなろう。各省庁や地方公共団体において、政策立案者自らが自己の政策を評価する政策評価の導入も積極的に進められており、これらの中でも環境への影響が併せて評価される事例も今後出てくるものと思われる。
このため、それぞれの政策ツールがどのような特徴やメリット・デメリットを有しているのかを明らかにし、それぞれの政策ツールの見取り図を描くことも必要である。このような作業を通じて、戦略的環境アセスメントの環境政策の中での位置付けも明確なものとなっていくものと思われる。
(5)制度化に向けた諸論点の整理
以上の課題を踏まえて、それぞれの政策や計画について整理を行うとともに、特に『政策』を対象とするのか、『計画・プログラム』を対象とするのかによってアプローチが異なることに留意しつつ、制度化に向けて、制度を構築する上での柱となる以下の論点について、整理を行っていくことが必要である。
- ○スコーピング
- ○評価
- -評価の実施主体
- -評価の視点
- -代替案の設定
- -調査・予測のための技術手法
- -バックグラウンドの状況の調査・予測、シナリオの作成
- -不確実性等の勘案
- ○公衆の関与
- -公衆の関与の位置づけ
- -公衆の関与の方法
- ○評価の結果の審査とプロセスの管理
- -審査の主体
- -第3者機関等の関与
- ○事業の公益性、社会経済的評価と環境面からの評価との関係
- ○評価後の手続
- ○国と地方公共団体との関係
- ○情報提供その他の基盤の整備