SEA総合研究会報告書 中間報告書
戦略的環境アセスメントに関する国内外の取組と我が国における今後の展望について(平成11年7月)
第2節 政策・計画段階での環境影響評価の実施事例
(1)広島空港の候補地選定
新広島空港は、中国・四国地方の拠点空港として、また、国際化の進展に対応できる国際空港として、1993年に開港したものである。同空港は、事業の実施段階において閣議決定要綱に基づく環境影響評価手続が行われているが、その前の立地選定の段階においても環境面からの検討が行われている。
新空港の開港は、従来使用されていた広島空港が市街地に隣接しているため周辺の環境対策には多くの経費、時間を要すること、また基本的に空港面積が狭く、施設面や機能面での制約や欠点がある一方で、21世紀において望ましい空港の規模としては、少なくとも2500mから3000mの滑走路長を持つ空港の整備が必要であることから、1980年度から2年間にわたる運輸省、県及び広島市の広島空港基本調査を経て、1982年の広島空港問題連絡会議において「ほかの適地に新空港の建設を志向すること、新空港候補地の選定は、気象調査及びアクセス検討の結果を踏まえ、行政で行うべき」との合意がなされたものである。
選定に当たっては、環境面を含めた諸条件を加味しながら代替案を設定し、それを必要に応じて検討を詳細なものとしながら、諸条件を加味して絞り込む作業が行われている。
まず、代替案を設定するため、[1]現空港の機能を代替可能であり、[2]建設条件、運行条件、環境条件が優れていること、[3]現空港から概ね40kmの範囲内にあることという新空港候補地の基本的条件から、国土数値情報、土地利用状況により条件の優れている地点を21ブロック選定し、地形による定性的評価の結果、29候補地が選定され、次いで、障害切土、空港整備土工量などの地形による定量的評価の結果から10箇所に、さらに、環境条件、空域条件、建設条件、アクセス条件に現地調査結果を加味して比較し、4候補地点に絞り込みが行われている。
表4-2-1 4候補地点の比較検討結果
| 区 分 | 洞 山 | 用 倉 | 江 田 島 | 大 奈 佐 美 | |
| 運航条件 | 気象 | 特に問題なし | 同 左 | 同 左 | 同 左 |
| 建設条件 | 空 域 | 特に問題なし | 同 左 | 同 左 | 精密進入側からの出発空域勾配が1/30 |
| 用地造成 | 障害切土なし |
同 左 切盛土量最小 |
障害切土大 切盛土量大 |
同 左 | |
| 最大盛土高 | 技術的な問題なし | 同 左 | 同 左 | 同 左 | |
| 環境条件 | 騒音 | 影 響小 | 影響小 | 影響大 | 影響大 |
| 景観文化財 | 問題なし | 同 左 | 古鷹山の切削の影響あり | 宮島への影響あり | |
| 地形改変 | 小 | 小 | 大 | 大 | |
| その他 | 保安林・用水池あり | 保安林・用水池あり、県立自然公園隣接 | 大量の残土処分用地を要す | 公有水面の埋立要す、潮流変化あり、瀬戸内海国立公園区域 | |
| その他 | 特になし | 開拓地あり | 特になし | アクセス道路の取付困難 | |
次いで、4候補地点毎に最適な案を設定した上で、表4-2-1のとおり、気象、造成方法、文化財その他の立地条件を加味して比較検討して2候補地点に絞りこんでいる。
さらに、既存空港を活用して沖出しする案と2候補地との比較が行われている。検討の結果、[1]既存空港は後背地に市街地が拡がるため、騒音の影響が大きく、建造物の大幅な移転が必要である、但しアクセスは良い、[2]空域条件が不良である、[3]瀬戸内海海域における広範囲の埋立が必要、かつ港湾機能と競合する、[4]広島市の経済・社会・文化活動等の発展への寄与はあるが、全県的な寄与度合いが低い、等の理由から、2候補地から選定することとなった。最終的には、表4-2-2のとおり、洞山、用倉の2候補地の詳細な検討が行われた結果、用倉が選定されることとなった。
表4-2-2 洞山と用倉の詳細比較の結果
- 運行条件(空域、障害物、精密進入、最低気象条件、予想就航率)
- 洞山は標高が120m高く、視程・雲高面で不利であり、就航率は用倉が高い。
- 建設条件(用地取得、用地造成、取付道路、滑走路延長可能性)
- 地質構造は洞山は岩が多く、起伏も大きい。地形改変は洞山が70ha多く、土工量は用倉の2倍となる。用倉は山陽自動車道からの取付道路の整備が容易であり、洞山は、用倉の3倍の距離が必要。
- 環境条件(騒音、周辺地域への影響)
- 地形改変量は用倉が少ない。騒音は大差なし。民家は用倉がやや多い。用倉は県立自然公園に隣接し、配慮が必要。
- 利便性(県内各都市からのアクセス)
- 広島市域からは大差なし。備後地域からは用倉有利。
- 地域開発(波及効果の可能性)
- 特に差はない。
広島空港の事例は、事業の構想段階での検討を行う際に、運行条件、建設条件等と同様に環境面からの検討も併せて行われた例である。総合評価の中に環境面からの評価も組み込まれ、代替案が設置され、その比較による評価が行われていること、飛行場の設置に当たって計画段階で考慮すべき環境項目として騒音や地形改変量、自然環境への影響に絞り込まれた上で検討されていること等は、評価手法として参考とすべき点は多い。
(2)横浜市青葉区における住民参加の道路づくり
横浜市では、市民と行政が協力して地域の課題を解決するパートナーシップ推進事業を進めており、地域の街づくりへの「市民の主体的な参加の推進」を提唱している。このような動きの中で、都市計画の分野でも、手続の中で説明会の開催や計画案の縦覧等の方法によって行ってきた従来の住民参加に加え、「構想段階から住民の意見を聞き、計画に反映させる」取組が行われている。
図4-2-1
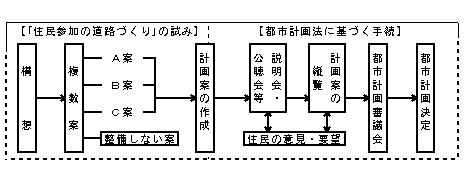
横浜市では、1998年度内に道路計画案の作成方針を決定するために、1992年から区民へのアンケート調査や意見交換会等を行ってきたが、1996年には、検討路線の沿線の自治体からの推薦者、住民からの公募、区内在住の学識経験者、市職員で構成される「住民参加の道路づくり委員会」を発足させ、住民意見の整理、整備する案と整備しない案のメリット、デメリットの検討、複数案の検討、環境調査の検討等を行っている。これと並行して、一般住民の参加の場として、意見交換会、シンポジウム、懇談会、公開学習会、ワークショップ等を開催している。これらの中で出された意見を踏まえ、横浜市では、道路のルートに関する複数案及び幅員・車線数の複数案を環境データ等とともにとりまとめている。
図4-2-2 恩田元石川線「住民参加の道路づくり」方針決定プロセス
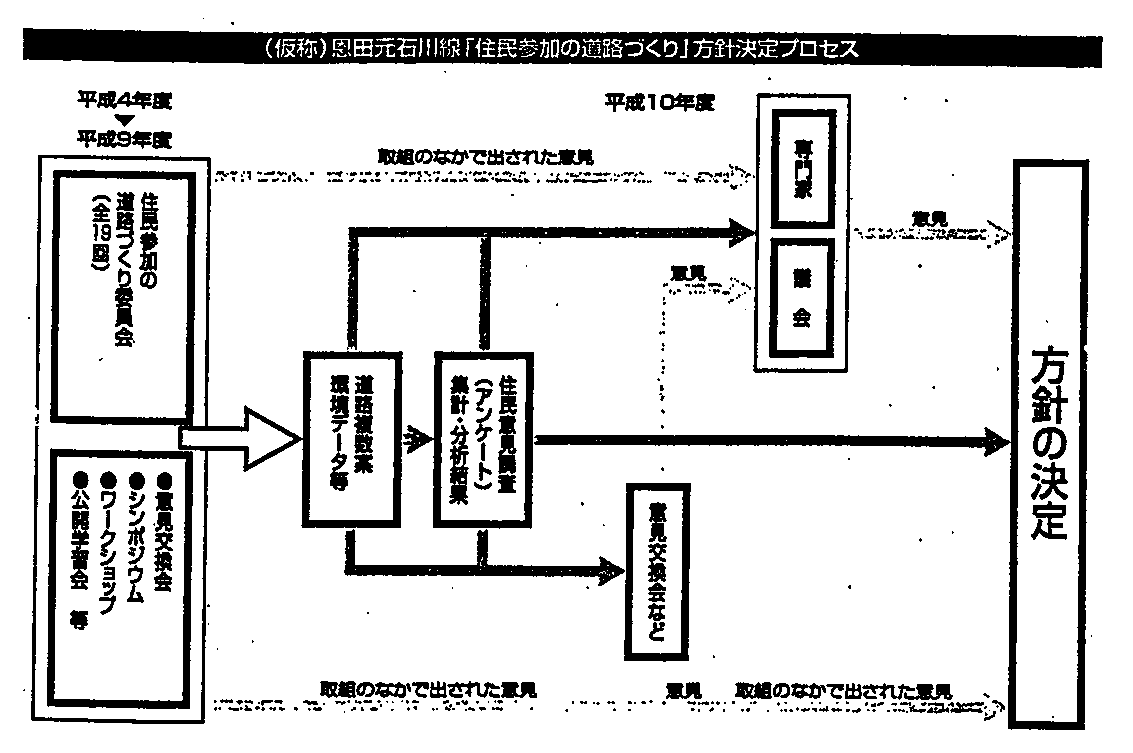
図4-2-3 複数案の内容
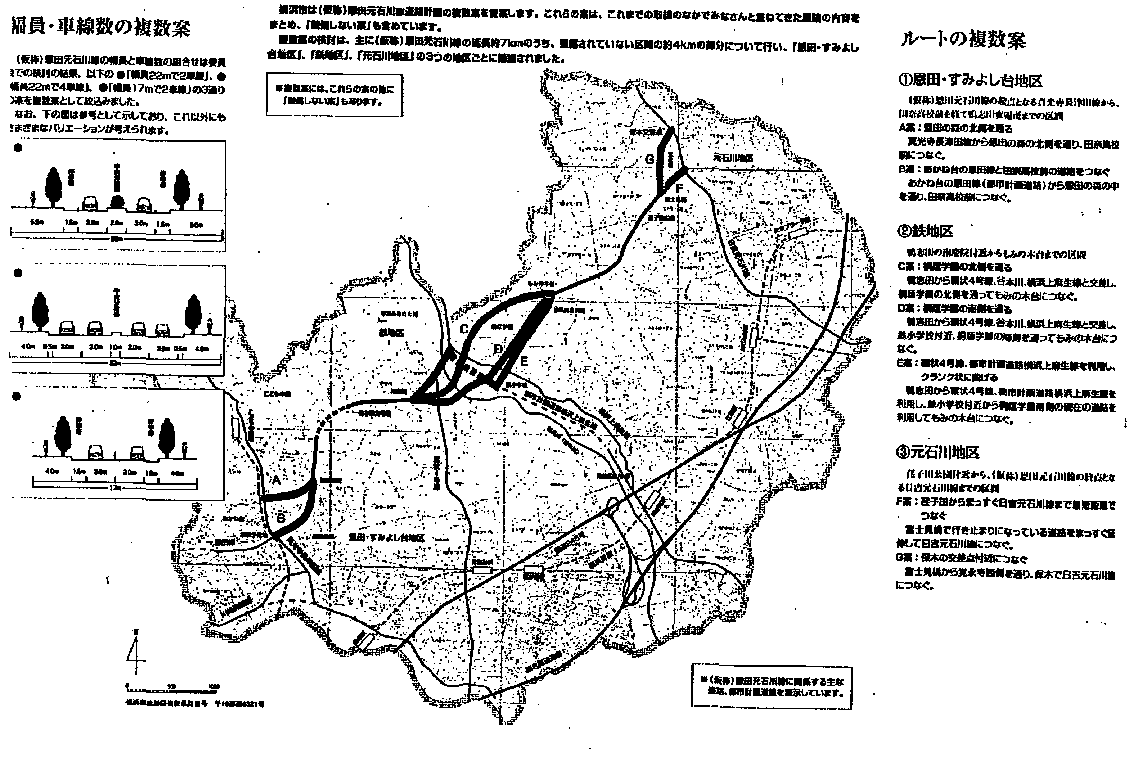
環境への影響については、図4-2-4及び図4-2-5のとおり、2車線で整備した場合、4車線で整備した場合及び整備しない場合等のそれぞれについて、予測される交通量に基づき、二酸化窒素濃度、騒音、振動の現況と予測・評価、各案による緑地の改変面積の予測・評価が行われている。このほか、利便性、安全性、快適性、空間機能、土地利用・文化財等の社会経済的な影響についても評価が行われている。
図4-2-4 交通量、大気、騒音、振動の現況と予測結果
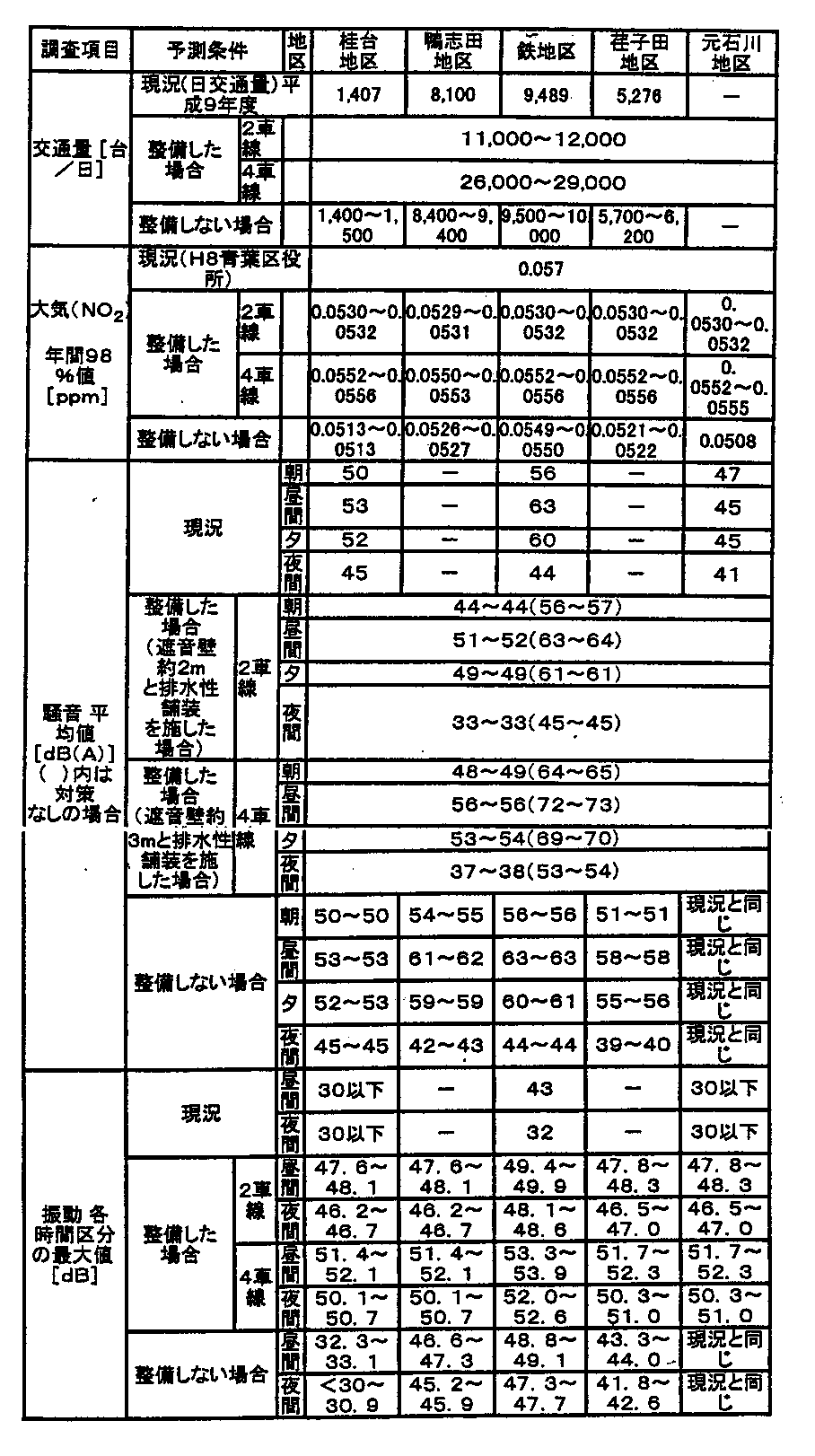
図4-2-5 緑地の改変面積の予測
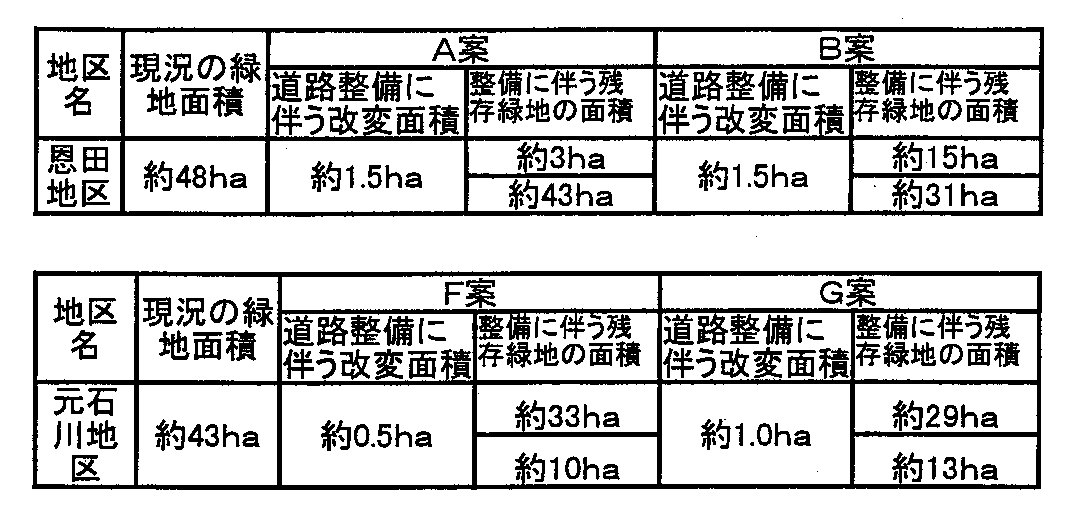
これらの結果を基に、道路の必要性、整備しない案も含めた道路の複数ルート方式、車線数及び幅員などに対し、区内約9万8千世帯の中から1万世帯を無作為抽出し、住民からのアンケート調査を行っている。最終的な方針は、住民意見調査の結果や議会、専門家の意見等も参考にして、市において決定されることとなっている。
(3)狛江市の一般廃棄物中間処理施設の建設
東京都狛江市では、ビン・缶の中間処理が1989年より市内の空き地で行われていたが、周辺住民の苦情により業務の継続が不能となり、市内に中間処理施設を立地する必要が生じることとなった。1991年に市が建設を予定していたビン・缶の中間処理施設が市民の強硬な反対により凍結されたことが契機となって、1991年より当該施設の立地選定の段階から市民の参加も得て検討が行われることとなり、その過程で環境への配慮が行われている。
中間処理施設の反対は隣接地の保育園の父母会が中心となって行われた。市民も施設の必要性は概ね理解していたが、市の当初示した施設案が住民にとっては突然のものであり、どこに立地するかで紛争が生じたものである。施設の必要性は一般市民にも概ね理解されており、リサイクル運動を続けてきた住民もあったため、事業の凍結後半年ほどで市民参加による計画づくりが行われることとなった。
91年12月には、市の要綱に基づいて、市民12名、専門家6名からなる「狛江市一般廃棄物処理機本計画策定委員会(通称、ごみ市民委員会)」が設置され、一般廃棄物を対象にごみ処理基本計画を作成し、ビン・缶の中間処理施設についても、この計画の中で用地の選定から検討されることとなった。委員会の事務局は市とコンサルタントが担当している。
ごみ市民委員会の設置後の約8ヶ月間で、ビン・缶の中間処理施設の用地の候補が絞り込まれている。ごみ市民委員会での検討は、市全体の一般廃棄物の処理問題についての議論から始められ、廃棄物の半減が具体的な目標として掲げられた上で、中間施設の立地の問題が検討された。市はまず公有地32ヶ所のリストを公開し、ごみ市民委員会において、その中からまず8ヶ所に候補地の絞り込み作業が行われている。この過程で、市民グループでは様々な形での自主活動が繰り広げられ、施設の必要性や設計条件等が整理された。その後、ごみ市民委員会は、さらに候補地を2ヶ所に絞り込んでいる。この2ヶ所は紛争の原因となった市の当初予定していた用地と、市役所1階の駐車場である。これら2地点を明記して中間報告がまとめられている。
図4-2-6 狛江ごみ中間処理施設建設計画の経緯と候補地点
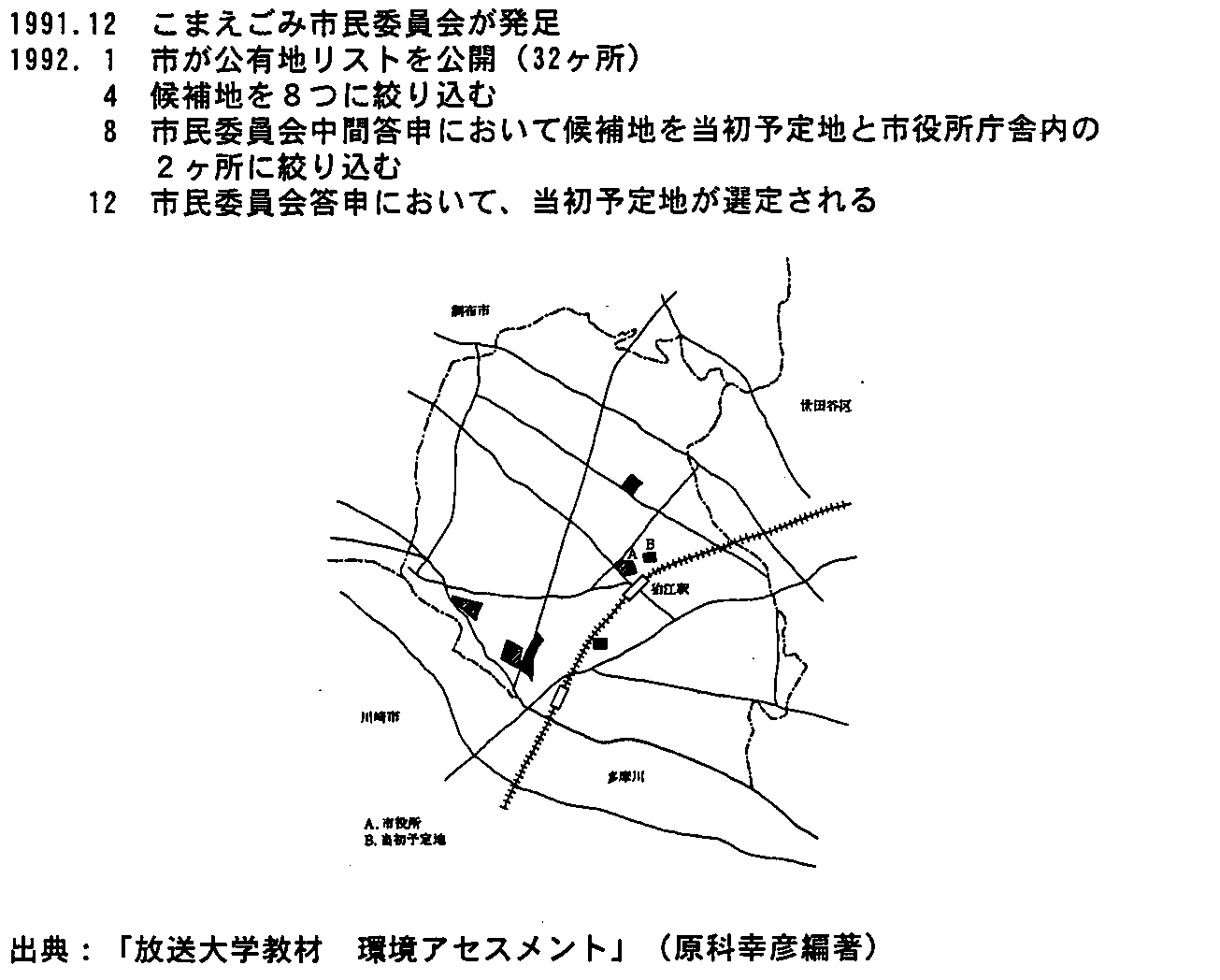
その後、2つの案についてさらに検討を深めるため、92年9月からは2ヶ所の立地候補地周辺の新たに5人の地元委員が加わった拡大ごみ市民委員会が設けられ、説明会やヒアリング等を行いながら、最終的な立地点選定作業が行われた。代替案の検討のため、両候補地の制約条件や騒音や悪臭等の環境対策の検討のための情報収集が行われた。最終的には、社会・経済面を含めた14項目にわたる評価表を作成して各委員が個別に評価し、両案の比較検討が行われた。図4-2-8は、拡大市民委員会の各委員が評価した結果を集計したものである。
評価表の14項目のうち、9項目が周辺環境や労働環境等へのマイナスの影響、3項目が市民のアピールや地域環境への貢献などプラスの影響である。比較評価を行った結果、当初予定地は、労働環境、作業の効率性、附帯設備の併設の可能性の3点で特に良く、騒音対策、悪臭対策、粉塵対策等でも明確に良好であった。市役所駐車場が特に良いのは市民へのアピール度だけである。建設コストに関しても当初予定地の方がやや良いという判断がなされた。最終的には市民委員会の場では結論が出せず、第3者の立場にある専門家委員に判断が任され、当初、市が計画していた地点に立地することとなった。その後、施設計画の中身についても、単にビン・缶の中間処理だけでなく、市民におるリサイクル活動の拠点となるよう機能が付加されるとともに、地域の周辺環境への影響を緩和するようデザインされている。
狛江市の事例では、立地選定の段階から市民参加と情報の公開が進められていることに特徴がある。廃棄物の処理施設は総論賛成、各論反対となる典型例であるが、計画の早期段階から市民が積極的に参加するプロセスが設けられたことによって市民の理解も得られ、比較的短期間で合意形成が図られている。今回の事例では、市民参加を進めるために相当程度の時間と費用がかけられているが、紛争がこじれた場合の時間や費用に比べればずっと少ないものと考えられる。
図4-2-7 ごみ市民委員会による検討手順の概要
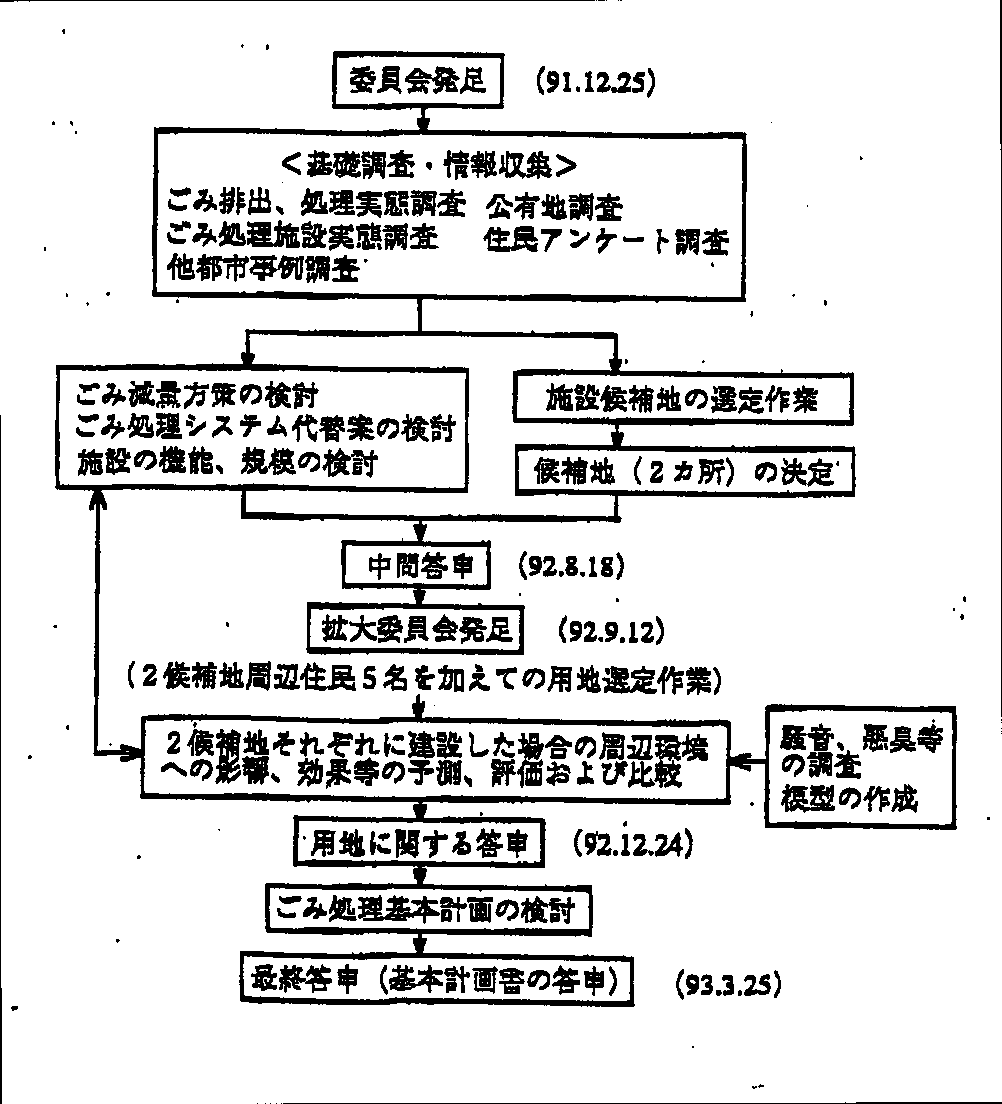
図4-2-8 用地選定のための2代替案の比較検討表
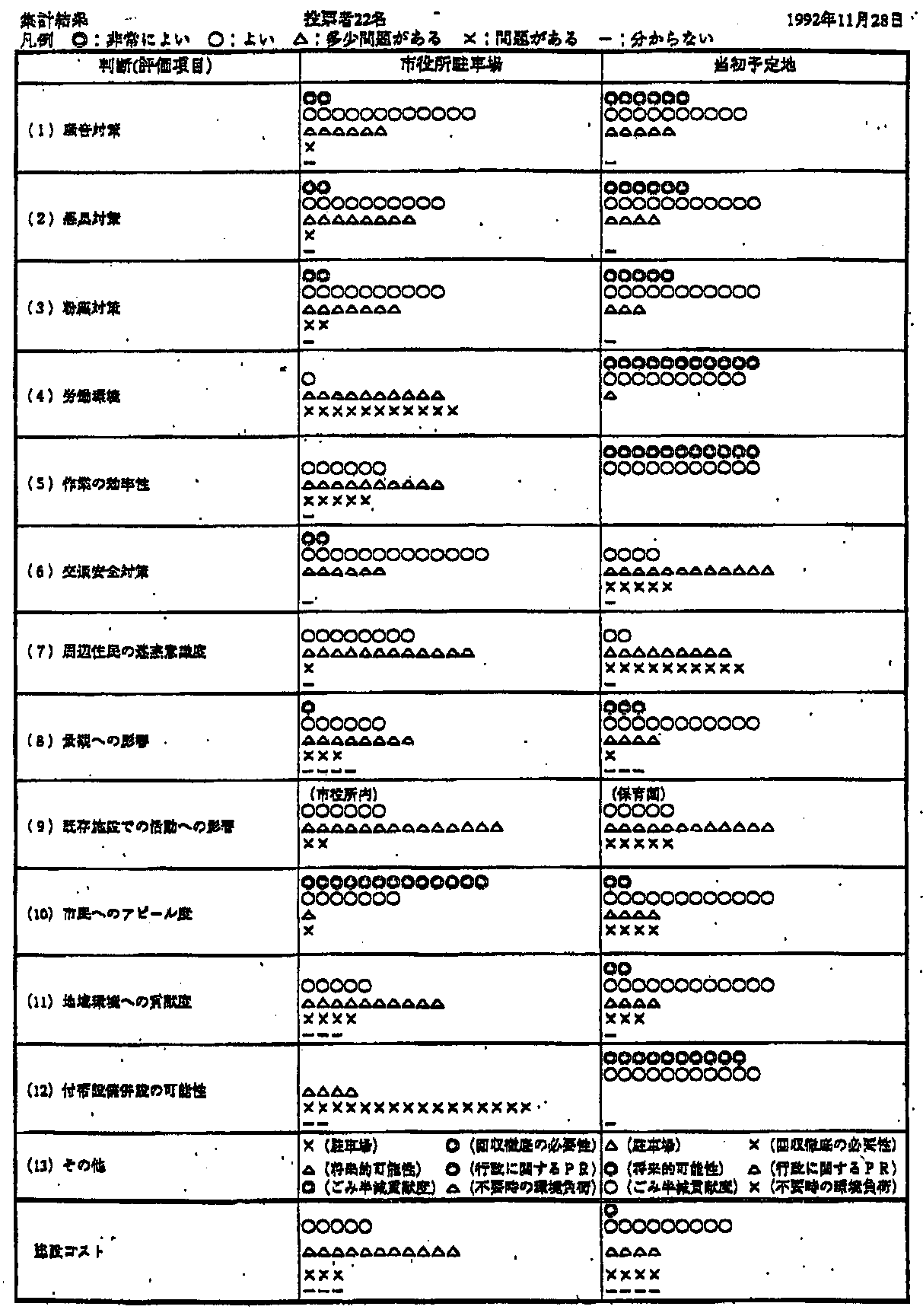
(4)むつ小川原開発基本計画と苫小牧東部大規模工業基地開発計画
昭和40年代末から昭和50年前後に計画された大規模な工業基地開発計画を含むむつ小川原開発や苫小牧東部開発に当たっては、それまでの生産に偏重した工業開発によって引き起こされた激甚な公害を背景に、開発計画の立案に際して、環境の保全を確保することが重視され、環境アセスメントが実施されている。
青森県のむつ小川原開発は、地域の主産業である農林水産業の振興を図りつつ、大規模工業を導入する大規模な地域開発である。昭和44年に策定された新全国総合開発計画に国家プロジェクトとして位置づけられた後、青森県において、開発の意義及び計画を明らかにした「むつ小川原開発基本計画」が、昭和47年及び50年の2次に渡って策定されている。同開発では、第2次基本計画の閣議口頭了解に際し、当該計画の中核をなす工業基地等における開発計画案に対して環境アセスメントが行われている。
開発計画案は、広範囲の地域にまたがる大規模な地域振興計画であり、具体的には、以下の事項が定められている。
図4-2-9 「むつ小川原開発計画第2次基本計画」の内容
- I 開発の基本方向
- II 地域開発計画
- 1 環境の保全(自然環境の保全、歴史的環境の保全、公害の防止)
- 2 産業の振興(農業、林業、水産業、工業、地場中小企業、観光)
- 3 基盤の整備(交通通信体系の整備、小川原湖総合開発、国土保全)
- 4 住民福祉の向上(都市整備、教育、労働福祉、社会福祉、保健医療等)
- III 工業基地計画
- 1 工業開発計画(工業立地計画、土地利用計画、公害防止計画)
- 2 施設計画 (港湾計画、道路計画、鉄道計画、水計画、新市街地計画)
- 3 開発スケジュール
- 4 工業開発に伴う住民対策(地権者対策、周辺地域対策)
図4-2-10 むつ小川原開発の工業配置計画概要図
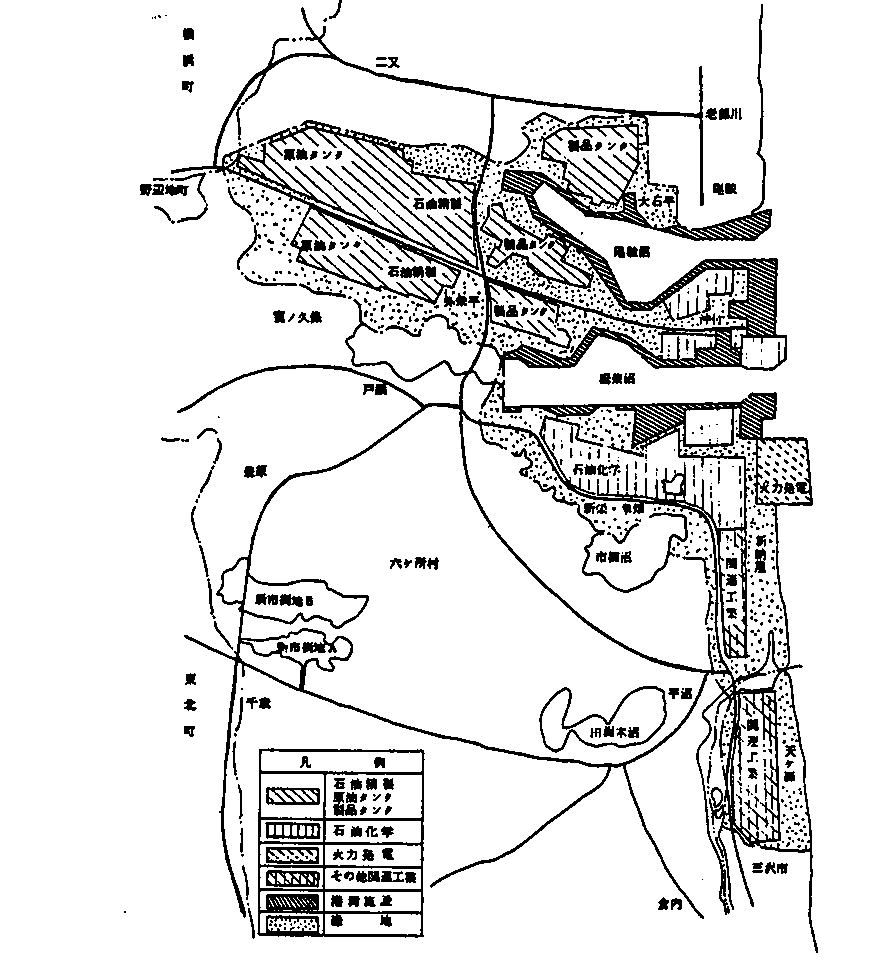
当該開発計画に対する評価項目としては、公害系では、大気、水質、廃棄物等が、自然系では、植物、動物が取り上げられている。開発計画に盛り込まれた個々の計画の内容、熟度等は様々であるが、大気、水質、廃棄物、騒音等の公害系の項目に係る環境影響の予測に当たっては、石油精製、石油化学、火力発電及び地域内の工場、事業所、一般家庭、自動車等に関し、計画に規定される活動規模等に基づいて試算が行われ、各項目に関して設定された環境保全目標に照らして評価が行われている。
自然環境に係る項目については、地域全体としては、各種調査結果に基づき、地域を10区分し、学術的価値、景観的価値、野外レクリエーション機能を有する自然環境の希少性、固有性、特異性に注目して保全目標が設定され、自然度の高い海岸線とその後背地、工業開発地区に隣接する学術的にも重要な植物群落等の保全が図られている。また、工業開発地区内では、自然的地形を活かし工場の分散配置を図ること及び緑地率を確保することに重点が置かれている。
北海道・苫小牧東部地域の開発は、昭和46年に策定された「苫小牧東部大規模工業基地開発基本計画」に基づき、三次に渡る段階計画に沿って各事業が推進されている。また、産業構造調整の進展など経済社会環境の変化を踏まえ、平成7年には、2020年代における開発の全体構想を明らかにした「苫小牧東部開発新計画」を策定し、今後はこの計画を効率的に推進するため、概ね10年後を目標とする新段階計画が平成9年3月に策定された。同開発についても、開発によって公害の発生等の事態を招くことのないよう、昭和40年代後半から北海道公害対策審議会の中間報告に基づき、また、昭和53年以降は北海道環境影響評価条例に基づく特定地域に係る環境アセスメントとして、環境面からの評価が行われている。
苫東第1段階開発計画に関して昭和50年にとりまとめられた「苫小牧東部大規模工業基地に係る環境保全について」では、公害系の項目については、計画に規定される活動規模等に基づく試算により予測を行い、環境保全目標に照らして評価を行う手法が用いられている。自然環境の保全については、立地段階で自然環境保全上重要性の高い地域の開発が避けられるよう、工業基地内の自然環境に関する綿密な調査が行われ、その結果に基づいて保全対象地域が設定されている。
保全対象地域の設定は、まず、[1]丘陵地と低地、尾根筋、沢などの顕著な地形界及び道路、水路等の工作物の設置状況、[2]樹林の性状、湿性植生、人為植生、海浜植生等の顕著な植生の変化から、基地内を22地区に細区分し、それぞれの地区について、植物の学術性、自然度、樹林分布、動物の学術性、生息環境、地形地質の特異性及び貴重性等の各項目について、図4-2-11の評価区分に基づいて評価が行われ、各地区の現況評価が図4-2-12の一覧表にとりまとめられている。次いで、各地区の現況評価の結果に基づき、図4-2-13の考え方に沿って複合評価を行うことにより、各地区をAからFまでにランク付けを行い、保全対象となる地域を抽出する。最後に、それぞれの主な保全対象に着目して現地調査、航空写真等により保全対象地域の区域が定められている。
図4-2-11 各項目に係る評価区分
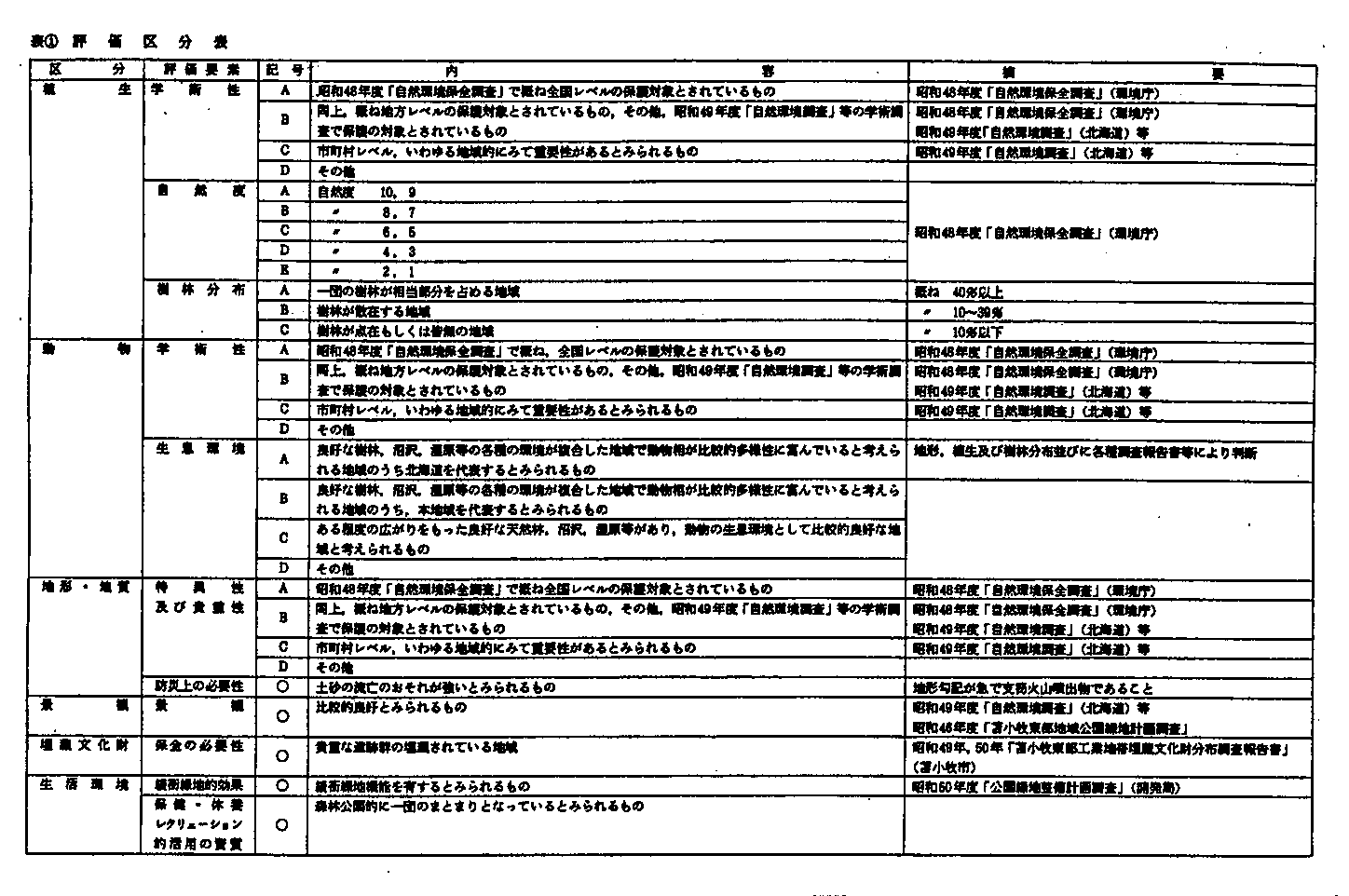
図4-2-12 苫東大規模工業基地計画の現況評価一覧表
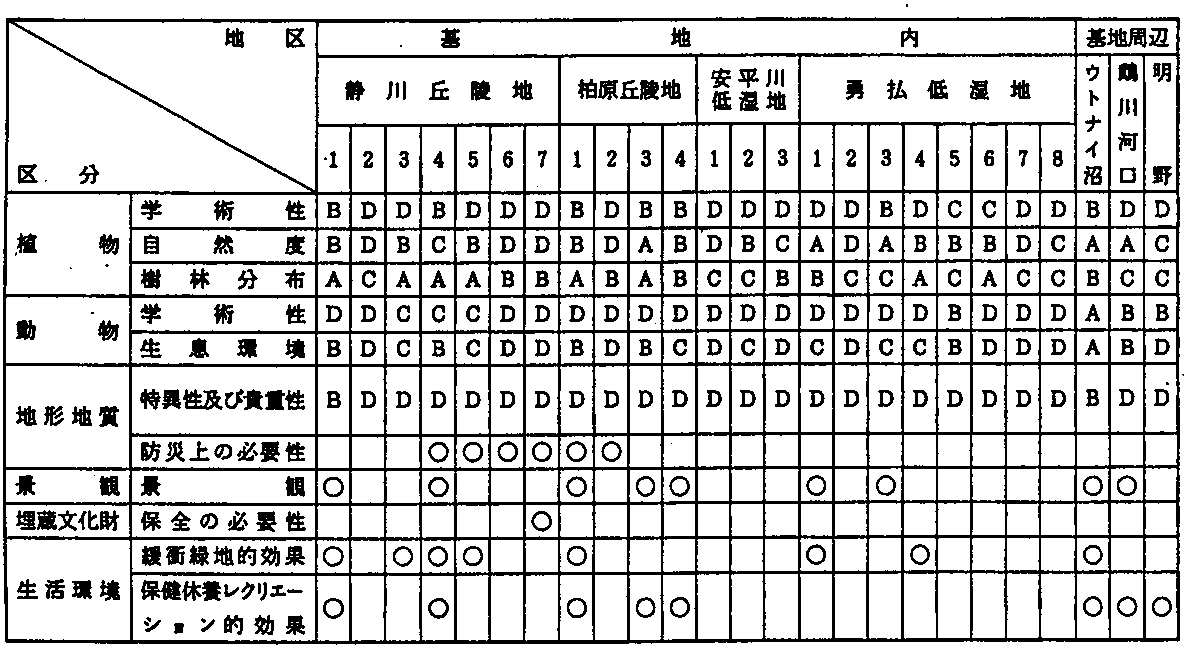
両地域開発に対する環境アセスメントは、環境面からの評価を明らかにした文書が作成され、住民等の意見聴取手続が行われるなど戦略的環境アセスメントの諸要素を満たすものであるが、当初は、計画案が策定された後にその影響を定量的に予測し、問題がない点を確認するために行われたために、その評価に当たっても、基本的には我が国での事業段階で行われる環境アセスメントと同様の手法が用いられ、代替案を設定して環境への負荷をできるだけ低減するものであることを明らかにするという視点が欠けている。
ただし、計画段階での環境アセスメントとして、事業段階での環境アセスメントでは評価することが困難な累積的な影響の評価が行われており、大気汚染や水質汚濁が進み、環境基準を超過するおそれがある場合には、個別の事業の実施段階での対策を促すことに用いられれば有効な手法となり得るものと考えられる。また、北海道の特定地域環境アセスメントで用いられた、構想段階で環境保全上脆弱な地域の開発が避けられるよう、保全地域を設定するとのアプローチは、構想段階での環境アセスメントの評価手法として参考になるものと考えられる。