SEA総合研究会報告書 中間報告書
戦略的環境アセスメントに関する国内外の取組と我が国における今後の展望について(平成11年7月)
第1章 戦略的環境アセスメントとは何か
(1)戦略的環境アセスメントの導入に向けた機運の高まり
環境アセスメントの創成期には、事業の実施段階でのアセスメントの取組と計画や政策に対するアセスメントの取組とが、並行して導入されている。例えば、世界で初めて環境アセスメント制度を導入したアメリカの国家環境政策法(NEPA)は、政策・計画・事業等を含んだ国家のあらゆる意思決定について、事前に環境への影響を評価することを連邦政府に義務付けるものとなっている。
我が国でも、NEPAの制定を受け、その3年後の1972年には「各種公共事業に係る環境保全対策について」の閣議了解が行われているが、これは各種公共事業の計画の立案、工事の実施等のそれぞれの段階において、環境保全上重大な支障をもたらすことのないよう、あらかじめ、必要に応じ、その環境に及ぼす影響の内容及び程度、環境破壊の防止策、代替案の比較検討等を含む調査研究を行い、所要の措置を講ずることを求めている。また、1973年には港湾法の改正により、港湾区域のマスタープランである港湾計画に環境アセスメントの実施が義務付けられ、1970年代半ばにはむつ小川原地域開発計画や苫小牧東部開発計画の立案に際して環境アセスメントが行われるなど、計画段階での環境アセスメントの取組も進められている。
しかし、その後、各地方公共団体の条例や1984年に廃案となった環境影響評価法案(旧法案)を受けて制定された閣議決定要綱では、事業の実施段階での環境アセスメント、いわゆる「事業アセス」のみが導入されることとなった。これは、[1]具体的な事業の諸元が明らかにされない段階では、環境影響の調査・予測に限界が生ずるため、効果的な環境アセスメントを行うためには、環境アセスメントの手続きが開始される前に、ある程度、具体的な事業の諸元が明確にされることが必要であること、また、[2]用地取得の前に事業計画を公表することとなる手続きを導入することは、事業内容によっては、用地の取得を困難とし、地価の上昇を招くなど、国土が狭隘な我が国においては、結果として事業の遂行を困難となると考えられたこと等が主な理由である。1993年に制定された環境基本法第20条を受けて1997年に制定された環境影響評価法でも、事業アセスについてスクリーニングやスコーピング手続による早期段階からの情報交流手続の導入等が図られるなどの改善が図られたが、従来より環境アセスメントが実施されていた港湾計画を除き、個別事業の上位の計画や政策に対するアセスメントの導入は、今後の検討課題として見送られた。
ただし、事業アセスから導入するというアプローチは、他の多くの先進諸国にも見られるものである。例えば、欧州諸国においても1985年に採択されたECの環境アセスメント指令により、まず、事業アセスから導入が図られており、また、アメリカの連邦政府のすべての意思決定を対象とするNEPAでも、制定当初は、事業アセスを中心に取組が行われている。
しかしながら、近年になり、事業アセスが進展する中で、その限界も強く認識されることとなった。すなわち、事業アセスでは、[1]経済社会活動の基盤となる環境の持続可能性の評価など社会経済活動に伴う環境への影響を総体として評価することができないこと、[2]個々の事業の活動単位が小規模な事業については、それらの総体としての影響が大規模な場合であっても、事業アセスにはなじまないため、その累積的な影響を検討することが困難であること、[3]異なる事業主体が実施する事業が集積する地域全体の環境の将来の姿を検討することに限界があることなどである。このため、国際的には、政策(policy)、計画(plan)、プログラム(program)を対象として、その環境面からの評価を行う「戦略的環境アセスメント(Strategic Environmental Assessment:SEA)」の導入の動きが見られる。
例えば、EU諸国では、1987年にはオランダにおいて土地利用計画等に対するアセスメントが導入され、91年にはイギリスにおいて各省庁が政策評価と併せて環境面からの配慮を行うための手引きが発行されている。さらに1993年には、欧州共同体が策定した「第5次環境行動計画-持続可能性に向けて」により、EU諸国の地域開発基金に当たる構造基金の適用を受ける各国の地域開発計画について事前に環境アセスメントを行うことが義務付けられている。また、同行動計画を受けて、1996年には加盟国に対して一定の計画及びプログラムについて環境アセスメントの実施を義務付ける指令案(SEA指令案)が提案され、現在、欧州議会、欧州理事会において検討が行われている。カナダでも、1990年に連邦政府機関が政策や計画を内閣に提案する場合には環境影響を評価した文書の添付が義務付けられている。
我が国でも、環境アセスメントの法制度化の検討の過程で、中央環境審議会は、上位計画・政策における環境配慮についても検討を行ったが、その答申「今後の環境影響評価制度の在り方について」(1997年2月)において、「現時点では、上位計画・政策における環境配慮をするための具体的な手続等の在り方を議論するにはなお検討を要する事項が多く、また、主要諸国においてもその取組が始められつつあるような状況にある。したがって、政府としてはできるところから取り組む努力をしつつ、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、今後具体的な検討を進めるべきである。」とされている。環境影響評価法案に対する国会の委員会(衆議院環境委員会及び参議院環境特別委員会)でも環境配慮の必要性が指摘され、「上位計画・政策における環境配慮を徹底するため、戦略的環境影響評価についての調査・研究を推進し、国際的動向や我が国での現状を踏まえて、制度化に向けて早急に具体的な検討を進めること」との附帯決議がなされている。このように、環境影響評価法には盛り込まれなかったものの、我が国においても戦略的環境アセスメントの制度化に向けた具体的な検討を早急に行うことが求められている。
地方公共団体でも、環境影響評価法の施行に向けて、多くの都道府県、政令指定都市で環境影響評価条例の制定が進んでいるが、その審議会や議会から、より早期の段階で環境配慮を行う仕組みの構築が求められており、一部の地方公共団体では、環境アセスメントの対象となる事業に対し、アセスメントを行う事前の段階で環境への配慮を義務付ける事例等も見られるところである。
(2)戦略的環境アセスメントとは何か
戦略的環境アセスメント(SEA)という概念は比較的新しいものであり、現在もその定義として様々なものが提案されているが、それらに共通する重要な要素は、[1]その対象が事業(project)ではなく、政策(policy)、計画(plan)、プログラム(program)の3つのPを対象とすること、[2]環境面からの評価を記載した文書を作成すべきこと、必要に応じて環境部局や公衆との協議を行うこと等の環境面からの評価を行うための体系的な手続を定めたものであることの2点である。一例を挙げれば、オランダ国土住宅環境省の報告書では、「SEAとは、提案された政策、計画、プログラムについて、それらの意思決定の初期の段階において、経済面、社会面で考慮されるのと同様に十分かつ明確に環境面での影響を評価する体系的な手続である。」と定義している。
諸外国において一般的に「戦略的環境アセスメント」と呼称されるのは、事業に先立つ、上位計画や政策等のいわば戦略的な意思決定を行うことのできる段階で行うためである。1994年の欧州委員会の報告書「戦略的環境アセスメントの方法論」では、「SEA」とは「戦略的な行為(Strategic
Actions)について環境影響を考慮すること」とされ、「戦略的な行為」とは「個別の建設事業より上位の段階でのすべての政府の行為を指す」と定義されている。
本研究会では、以上のような状況を踏まえ、事業アセス以外の、3つのP(政策、計画、プログラム)を対象とする環境アセスメントを広く視野に入れて検討を行うこととした。
ただし、諸外国の制度等でも「戦略的環境アセスメント」との用語は用いられておらず、その制度の対象に応じて「政策」「計画」「プログラム」等の用語が用いられることが一般的である。例えばEUの指令案は「計画及びプログラムの環境影響の評価に関する指令」とされている。今後、我が国でも、制度化を図るに当たっては、「戦略的環境アセスメント」の名称についても検討を行うことが必要である。
なお、政策、計画、プログラムの3つのPのそれぞれを厳密に定義することは、国や用い方によってもその範囲は異なることから困難であるし、また検討を行う上で必ずしも必要ではないが、その戦略的環境アセスメントの方法論やアプローチを検討する上では、図1-1のように、『計画』と『プログラム』には明確な差違を認めることは難しいが、『政策』より具体性が高いものとして、『政策』は、『計画・プログラム』よりも上位の抽象的なものに用いられるものという大まかな整理を行っておくことは有用である。
図1-1 『政策』『計画・プログラム』『事業』の関係
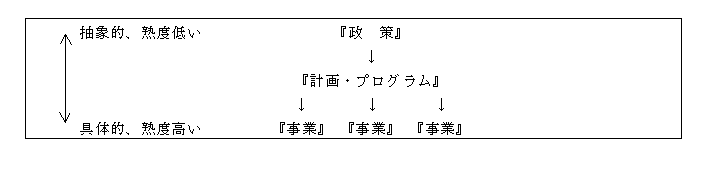
参考までに、諸外国における『政策、計画、プログラム』の定義の例を挙げれば、英国の政策評価における環境配慮のための指針である「政策評価と環境」では、「政策」とは「ある特定の分野においてポリシー自身が設定する目的を、政府が達成するための方法」と、「計画とプログラム」とは「政策に効果を与える活動の集まり」とされ、さらに「プログラム」とは「特定の地域において行われる個別の活動であるプロジェクトから構成されるものである場合がある」と説明している。また、1996年に環境アセスメントの有効性に関する国際研究の一環としてとりまとめられたオランダ住宅国土環境省の報告書「戦略的環境アセスメント」では、「政策」は「政府が現在若しくは将来遂行する行為の一般的な道筋、あるいは提案される全体的な方向で、それは政府の、一連の継続的な意思決定を導くもの」と、計画とプログラムはともに「政策目的を達成する手段を評価、選択して、事業や諸活動をいつ、どこで、どのように実施するかを明確にするもの」とであり、「計画」は「政策を詳細なものとし実行に移すための、目的を持ち将来に向けた戦略、あるいはデザインで、それはしばしば、調整された優先順位や選択肢、手段を伴う」ものと、「プログラム」は「政策を詳細なものとし実行に移すための、約束、提案、手段、活動から成る一貫性のある組織されたアジェンダ、あるいはスケジュールである。」とされている。
『政策』と『計画(・プログラム)』では、その熟度の違いから、『計画(・プログラム)』は、その内容がより具体的であり、財政的な裏付け、即地性、将来の事業の決定に及ぼす影響等が相対的に強いのに対して、『政策』は、より抽象的であるという特徴がある。
ただし、個々の制度やケーススタディに関しては、例えば「政策」が「政策評価」などのように『政策、計画、プログラム』を含めて用いられることもあるので、それぞれの用語が具体的に何を指し示しているのか注意が必要である。本報告書では、諸外国の制度や事例については、「policy」は「政策」と、「plan」は「計画」と、「program」は「プログラム」と便宜的に訳している。
(3)戦略的環境アセスメントの意義
戦略的環境アセスメントには、[1]社会の持続可能な発展を達成するために、政策の策定・実施に当たって環境への配慮を意思決定に統合するためのツールとしての意義と、また、[2]従来行われている事業の実施段階での環境アセスメントでは限界があるのでそれを補完するためのツールとしての意義がある。
前者の各種政策の策定・実施に当たって環境への配慮を求める考え方は、従前より自然環境の保全や公害の防止を未然に図るという観点から、国際的にも広く普及した考え方であり、我が国でも自然環境保全法や旧公害対策基本法にも規定されている。近年、環境問題は、地球環境問題や廃棄物問題をはじめとして事業者や国民の通常の活動に起因する環境負荷の集積の問題などが顕在化し、社会経済構造に根ざすものとなってきたために、通常の経済活動や日常生活に起因する環境への負荷を低減するための施策の必要性が高まっている。一方で、これらの社会経済活動の展開に対して影響を及ぼす国や地方公共団体の政策等は、その策定・実施の段階で、十分に環境への影響が考慮がなされていないことから、政策等の策定・実施に当たり環境配慮を求める動きが国際的に強まっている。
特に、地球環境問題の顕在化を背景に1992年にリオデジャネイロで開催された地球サミットでは、人間の与える負荷と地球環境の許容量を踏まえた保全を図り、社会の持続可能な発展を図っていくことの必要性から、この考え方が強く認識されることとなった。例えば、アジェンダ21には、「意思決定における環境と開発の統合」に関する章が設けられ、政策・計画・管理の各レベルにおける環境と開発の統合に関し、社会、経済的問題及び環境問題に関する配慮が十分に統合され、幅広く国民の参加が確保されるよう、意思決定システムを改善することが目標として掲げられている。また、生物の多様性に関する条約においても「生物の多様性に著しい悪影響を及ぼすおそれのある計画及び政策の環境への影響について十分な考慮が払われることを確保するため、適当な措置を導入すること」とされている。
我が国でも、1995年に制定された環境基本法では、国の施策に沿って広汎多岐にわたり社会経済活動が展開され、それに伴って生ずる影響もまた広汎にわたるため、その第19条に「国は、環境に影響を及ぼすと認められる施策を策定し、及び実施するに当たっては、環境の保全について配慮しなければならない」との規定が設けられているが、戦略的環境アセスメントは、そのための具体的なツールとなるものである。
一方、従来行われている事業アセスの限界としては、[1]個別事業の環境アセスメントでは、個々の規模が小さい事業の場合には全体として大きな負荷をもたらす場合であっても事業アセスの対象としてなじまないために、個々の事業の累積的な影響を検討することが困難であること、[2]複数の事業者が一定の地域において集中的に事業を行うことを計画している場合であっても、事業アセスでは個別の事業毎に評価が行われるために地域全体としての環境の将来像を検討することには限界があること、[3]通常、個別の開発事業の計画の立案に際しては、政策や上位の計画において、既にその一部が決定されているために、環境アセスメントを事業段階で行ったのでは、意思決定の段階として遅すぎ、有効な代替案の検討等が行えない、若しくは限定されたものとなってしまうこと等が指摘されている。
戦略的環境アセスメントは、政策や計画を対象に環境アセスメントを実施するものであるため、[1]小規模の開発事業による生態系への影響や交通系の事業による大気への影響等の累積的な影響についても、それらの事業に影響を及ぼす各地域の開発計画や関連する政策・計画等では評価することが可能であるように、政策・計画を対象とする環境アセスメントは、事業アセスよりも累積的な影響を評価する上ではるかに適しているし、[2]一定の地域において複数の事業者が集中的に事業を行う場合において、その地域の全体像への影響を評価することも、地域の総合的な開発計画や適切な計画の枠組みを設定すること等により可能でなる。また、[3]事業の熟度を高めるより早い段階で、広範かつ有効な代替案を検討することも、事業に枠組みを与える政策や計画について評価することによって十分可能となるものである。