大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書
大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)<環境影響評価の進め方>(平成13年9月)
大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術(II)TOPへ戻る
第1章 大気環境の環境影響評価の進め方
1-1 大気質・悪臭
(1)大気質・悪臭の特徴
大気質・悪臭は、大気そのものに乗って運ばれ、生体や、器物及び動植物に影響を生じる。人への影響・毒性等は物質によって異なるが、急性影響と慢性影響に大別され、状況に応じて急性、慢性両方の視点での検討が必要となる。
また、大気そのものに乗って移流・拡散するので、大気質・悪臭の影響はその発生源の形態、移流・拡散の場の状況、大気の動き(風向・風速)に大きく左右され、場合によっては、かなりの広範囲へ影響を及ぼすことが想定されるものである。
汚染の原因となる発生源の形態は、工場・事業場、換気塔等がそれに該当する固定発生源と、自動車・飛行機・船舶等が該当する移動発生源とに分けられる。発生源の形態により調査地域を考慮する必要があることは「(2) [3] 調査地域の考え方」で後述するとおりである。
なお、大気汚染物質には、大気中に排出された後、大気中で化学反応を生じ二次生成する物質も存在するため、調査・予測対象とする物質の性質を事前に把握しておく必要がある。
(2)調査・予測・評価のあり方
環境影響評価における調査・予測・評価を効果的かつ効率的に行うためには、環境影響評価の各プロセスにおいて行われる作業の目的を常に明確にしておく必要がある。環境影響評価における最終的な目的は「評価」であることから、実際の環境影響評価における作業の流れと逆に、「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要がある。特に手法の重点化、簡略化を行う場合には、従来の環境影響評価とは異なった調査が必要になったり、あるいは従来行われてきた調査が不必要になったりする場合がある。スコーピングは環境影響評価の調査・予測・評価の実施前だけでなく、実施中においても必要に応じて環境影響評価の項目・手法の見直しを行うものである。このスコーピングの基本的な考えを踏まえ、いかなる段階においても、効果的かつ効率的な手法の検討を実施することが重要である。
また、大気質に係る環境影響評価においては、評価対象を長期濃度とするのか短期濃度にするのか等によって予測手法が異なり、また、事業実施区域における地形条件、気象条件等によっても適用すべき予測手法や必要な条件が異なり、さらに調査手法も異なってくる。したがって、評価の対象を明確にした上で、事業実施区域の地域特性に合わせた予測手法を選定し、さらにそのために必要な調査手法を選定する必要がある。
ここでは、調査・予測・評価の各段階での基本的考え方を記し、各段階での個別の留意事項について、「3) 留意事項の解説と事例等」において解説を加える。
2)大気質・悪臭の環境影響評価の手法
(1)大気質・悪臭の調査
調査の目的は、地域特性の把握における調査(既存資料の収集整理又は現地踏査等)では明らかにならなかった情報を収集して、調査地域の現況をより詳細に把握するとともに、予測・評価において必要な情報を取得することにある。
地域特性の把握において収集整理した大気汚染物質や気象の観測点には、地域的な偏りや観測点密度により、事業実施区域及びその周辺における状況を正確に把握することが困難である場合がある。また、最新の情報が必要であるが、この情報の入手にある程度の時間が必要であり、利用できない場合もある。さらに、必要とする情報が測定されておらず、新たに必要な項目を測定しなければならないこともある。
また、調査計画の立案段階及び調査の実施中においても、効果的かつ効率的な手法を検討する必要があることは前述したとおりである。
[1]調査項目の検討
調査項目の検討においては、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と地域特性から抽出された環境要素との関係を厳密に検討する必要がある。事業特性及び地域特性の把握の上で考慮すべき事項は、以下に示すとおりである。
表1-1-1 事業特性及び地域特性の把握において考慮すべき事項
| 区分 | 考慮すべき事項 |
| 事業特性 | 大気汚染物質・悪臭物質の種類・量 発生の過程 発生源の種類・位置 等 |
| 地域特性 | 大気質の環境基準達成状況 環境基本計画等の大気汚染に係る目標値の達成状況 大気汚染防止法に規定する指定地域 自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量 の削減等に関する特別措置法に規定する特定地域 悪臭防止法における規制地域 等 |
表1-1-2に示すように大気質に係る環境要素は、大気汚染物質により区分されている。地域特性から環境要素を選定する場合には、標準項目以外の物質による大気質への影響の有無についても考慮する必要がある。特に、新たに有害物質として認知されるようになった物質や、法令等による規制物質ではないが住民等の関心の高い物質等にも留意する。
調査項目は、表1-1-3に示すように、主に環境要素として選定された大気汚染物質・悪臭物質の現況濃度等の状況及び気象の状況が挙げられるが、既存資料調査や現地踏査では十分でない情報を補完し、予測・評価を行うために必要な項目を選定することが重要である。
例えば事業の実施に伴い排出が想定される大気汚染物質の測定が、既存調査で十分に実施されていない場合には、現況を把握するとともに予測・評価において必要となるバックグラウンド濃度の設定等のために、その物質の測定が必要である。また、事業実施区域及びその周辺の拡散場が複雑地形であったり、都市域であるような場合には、地上気象以外に上層気象観測1-1)を含めて、予測のための拡散パラメータ等の条件を設定するための調査を実施する場合もある。さらに、予測モデルの再現性の検証には、現況の発生源の状況も必要に応じて調査する必要がある1-2)。特にバックグラウンド濃度の将来予測を広域大気拡散モデル等を用いて実施する場合には、発生源の状況把握は重要な調査事項となる。
表 1-1-2 主な大気汚染物質等
| 区分 | 大気汚染物質等 | ||
| 環境基準が設定されている物質 | 二酸化いおう、一酸化炭素、浮遊粒子状物質、光化学オキシダント、二酸化窒素、ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類 | ||
| 大気汚染防止法で定める物質等 | ばい煙 | いおう酸化物、ばいじん | |
| 有害物質 | カドミウム、カドミウム化合物、塩素、塩化水素、フッ素、フッ化水素、フッ化珪素、鉛、鉛化合物、窒素酸化物 | ||
| 特定物質 | アンモニア、フッ化水素、シアン化水素、一酸化炭素、ホルムアルデヒド、メタノール、硫化水素、燐化水素、塩化水素、二酸化窒素、アクロレイン、二酸化硫黄、塩素、二硫化炭素、ベンゼン、ピリジン、フェノール、硫酸(酸化硫黄を含む)、フッ化珪素、ホスゲン、二酸化セレン、クロルスルホン酸、黄燐、三塩化燐、臭素、ニッケルカルボニル、五塩化燐、メルカプタン | ||
| 有害大気汚染物質 | ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン、ダイオキシン類 | ||
| 一般粉じん | 一般粉じん(浮遊粒子状物質) | ||
| 特定粉じん | 特定粉じん(石綿) | ||
| 自動車排出ガス | 一酸化炭素、炭化水素、窒素酸化物、粒子状物質 | ||
表1-1-3 大気質・悪臭の環境影響評価における主な調査項目
| 調査項目 | 調査内容 | |
| 大気質の状況 | 環境要素として選定される大気汚染物質濃度 | |
| 悪臭の状況 | 悪臭物質濃度、臭気濃度、臭気指数 | |
| 気象の状況 | 地上風向・風速、上層風向・風速 | |
| 日射量、放射収支量 | ||
| 上層気温・湿度 | ||
| 発生源の状況 | 交通量 | 自動車 |
| 船舶 | ||
| 航空機 | ||
| 工場、事業場等の固定発生源 | ||
大気質の調査項目の検討においては、環境要素として選定された大気汚染物質が主要な検討要素となるが、その汚染物質の健康影響の関心の高まりと共に、現状の汚染物質に新たな課題等が生じるものもある。例えば、表1-1-2に示す浮遊粒子状物質の中でも、ディーゼル自動車等から排出されるディーゼル排気微粒子(DEP)1-3)や粒径が2.5μm以下の微小粒子状物質(PM2.5)については、その健康影響との関連が懸念されており、現在PM2.5の動態解明や計測についての調査・検討やPM2.5の曝露影響調査が進められている。
また、環境要素を大気汚染物質そのものでなく、発生現象として捉える場合もある。例えば、IPP注)等の小規模な火力発電事業における冷却塔からの排出ガスによる白煙化現象1-4)が挙げられる。このように大気汚染物質そのものによる環境影響ではなく、発生現象による環境影響を予測・評価する場合には、予測・評価を行うために必要な調査項目及び調査方法等について十分な検討が必要である。
注)「IPP」(Independent Power Producer:独立電気事業者)
発電所を建設・運営し、電力を卸売りする電力会社以外の事業者
【留意事項】
- 1-1) 上層気象観測(p.32~33参照)
上層気象観測は、事業に伴う排出源の位置が高い場合や周辺の拡散場が複雑である場合について実施を検討する。上層気象観測は、観測用の鉄塔や煙突等に測定器を固定して実施する場合と、気球や航空機あるいはその他の遠隔計測技術を利用して行う場合がある。混合層高度や大気逆転層の出現状況等の情報を得、予測条件に反映する。 - 1-2) 発生源の調査(p.34参照)
調査地域の全ての発生源を対象とした地域総合シミュレーションによるバックグラウンド濃度の設定や化学反応による二次生成過程を経る環境要素の予測、また予測モデルの再現性の検証を行うためには、現況の発生源の状況を調査する必要がある。 発生源の情報は地域総合シミュレーションを行う場合には不可欠な調査事項であるが、一事業者による情報の収集には限界がある。 - 1-3) ディーゼル排気微粒子(p.34参照)
ディーゼル排気微粒子(DEP)は、ディーゼルエンジン内の不完全燃焼が原因で発生する微粒子であり、沿道の浮遊粒子状物質(SPM)のかなりの部分を占めていると言われている。環境中のディーゼル排気微粒子の計測については、他の粒子状物質、ガス状物質等の大気汚染物質との区別が課題であり、その計測方法や曝露評価について現在研究が進められている。 - 1-4) 白煙化現象(p.34~35参照)
IPP等の小規模な火力発電所においては、循環水による冷却塔を用いた冷却方式が採用される場合が多いが、湿式冷却塔の排気は高温多湿であるため、排出ガスが白煙化する現象が起こり、視認障害等の問題が生じる可能性がある。計画地近傍に、高架道路、生活の場となる住宅地及び中高層建築物が存在する場合には検討が必要である。
[2]調査手法の考え方
調査手法に関しては、前述したように「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進める必要がある。これは、表1-1-4及び表1-1-5に示すように、評価の対象とする評価時間や考慮すべき現象に応じて、予測対象及び調査対象も異なり、予測手法及び調査手法の選定が大きく左右されることになるからである。したがって、評価の対象を明確にした上で、地形条件や気象条件等の地域特性に合わせた予測手法を検討し、その予測のために必要な調査手法を検討することが必要である。
なお、環境要素としての大気汚染物質濃度の測定に関しては、環境基準等に方法が定められているものなど、公定法が定められている場合が多いので、基本的にそれに準じるものとする。
表1-1-4 大気質予測における評価時間の考え方
| 評価の対象 | 予測対象 | 調査対象 |
| 長期濃度 | 長期予測(年平均値) | 異常年ではない1年間の年間を通した気象条件 |
| 短期濃度 | 短期予測(日平均値、1時間値) | 高濃度が想定される気象条件 |
表1-1-5 大気質予測において考慮すべき現象
| 区分 | 現象の特徴 | |
| 気象条件 | 逆転層 | 上空の逆転層により排煙の上方への拡散が制約され、地表面と上昇逆転層の間で高濃度が生じる。 |
| 海陸風 | 海陸風の交代時に一旦移送された汚染物質が吹き戻される、あるいは海陸風の交代時の凪により滞留した汚染物質がその後移送されて高濃度を生じる。 | |
| ダウンウォッシュダウンドラフト | 強風時に煙突や建物背後の渦領域に排煙が取り込まれ、排煙の上昇が妨げられるとともに渦領域での拡散が大きくなり、地上に高濃度を生じる。 | |
| フュミゲーション | 風速や大気の成層条件により、煙源の風下に高濃度の着地濃度が出現する。 | |
| 地形条件1-5) | 起伏等 | 高層ビル等の高所や、斜面に排煙が衝突する場合などは平坦地地上部と異なる濃度が発生する。 |
| 複雑地形 | 峡谷等の複雑地形により拡散場の条件が非一様・非定常条件となる。 | |
| 都市域 | ビル周辺では複雑な気流が発生する。 | |
| 道路構造 | 盛土・高架構造 | 道路構造による気流の変化が生じる。 |
| 掘削・トンネル | 汚染物質の排出が交通によって生じた気流の影響を受ける。 | |
| 時間条件 | 短期濃度 | 特殊気象条件下で短期的な高濃度が発生する他、発生源強度の変化する非定常煙源では短期濃度を検討する必要がある。 |
【留意事項】
- 1-5) 地形条件(複雑な拡散場)(p.36~39参照)
従来の環境影響評価においては、拡散場が複雑地形であるが、計算においては平坦地で用いられる正規プルーム・パフ式により予測計算が実施されている場合があり、この点について住民意見等において指摘されている場合がある。
拡散が地形の影響を受けるような状況の場合には、特に留意が必要である。
(ア)調査手法の重点化・簡略化1-6)
環境影響評価の対象とする項目について、地域特性の把握の結果、環境が著しく悪化した地域が存在する場合や、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合等については手法の重点化を、一方、類似事業の事例などから判断して環境影響が極めて小さいことが明らかな場合等については手法の簡略化を検討する。
なお、手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、調査地点、調査期間・時期等の増減等も含めて検討する1-7)。
【留意事項】
- 1-6) 手法の重点化・簡略化
重点化(重点的かつ詳細に実施する)又は簡略化(簡略化した手法で効率的に実施する)を適用するかどうかを検討する要素としては、以下のようなものが考えられる。
〔手法の重点化を検討する要素〕
[1]想定される環境への影響が著しい場合
[2]環境影響を受けやすい地域又は対象が存在する場合
・海陸風等の地域特有の気象条件により前線性逆転層等が発生しやすい地域
・盆地、ストリートキャニオンなど逆転層の発生により、大気汚染物質が滞留しやすい地形条件を有する地域
[3]環境の保全の観点から法令等により指定された地域又は対象が存在する場合
・大気汚染防止法(昭和43年法律第97号)第5条の2第1項に規定する指定地域
・自動車から排出される窒素酸化物の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(平成4年法律第70号)第6条第1項に規定する特定地域
・悪臭防止法(昭和46年法律第91号)第3条に規定する規制地域
[4]既に環境が著しく悪化し又はそのおそれが高い地域が存在する場合
・環境基本法(平成5年法律第91号)第16条第1項の規定により定められた環境上の条件についての基準であって、大気の汚染に係るものが確保されていない地域
[5]地域特性、事業特性から標準手法では予測が技術的に困難と思われる場合
・地形等の条件から複雑な風条件を有する地域
[6]事業者が環境保全上特に重視したものがある場合
・地域特性、事業特性、ならびに事業における環境保全上の方針等に照らして、事業者が特に環境保全上重要だと判断したものがある場合
〔手法の簡略化を検討する要素〕
[1]環境への影響が極めて小さいことが明らかな場合
・大気汚染物質の排出量や類似事業の事例などから、環境への影響が極めて小さいことが説明できる場合
[2]影響を受ける地域又は対象が相当期間存在しないことが明らかな場合
・大気汚染、悪臭により影響を受ける住居、施設等が影響範囲内に現在および将来にわたって存在しないことが明らかな場合には、影響を受ける地域や対象のない区域について詳細な予測計算等を行うことより、広域的な観点から汚染物質等の排出量により評価するなどの手法が考えられる。
[3]類似の事例により標準手法を用いなくても影響の程度が明らかな場合
・類似事業における実測例等から影響の程度が推定可能な場合
- 1-7) 調査手法の重点化(p.40参照)
既存の測定局等が事業実施区域周辺に存在せず、大気質の測定が行われておらず、事業計画から想定される影響が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合においては、調査手法の重点化として、環境要素となる大気質の調査を通年で実施することが考えられる。
[3]調査地域の考え方
調査地域は、調査対象とする大気汚染物質等の特性や事業内容、気象や地形、土地利用等の地域の特性及び保全対象施設(文教施設、医療施設及び住宅等)の配置等を踏まえ、事業の実施による影響が最大となる地点を含む範囲とする。
一般的には、事業の実施により大気汚染物質濃度があるレベル以上変化する範囲を含む地域とする必要があり、後述する予測地域を包含した範囲で設定すべきである。この範囲は事業の規模や内容並びに地域特性によって変化するものであり、予測の不確実性を考慮する必要があり、安全サイドの考え方から広めに設定することになる。
大気汚染物質の拡散特性から、発生源の種類ごとに概ねの影響範囲を設定することができ、影響範囲の目安は表1-1-6に示すとおりである。また、発生源が固定発生源や工事中の建設機械のように限定された地域における移動発生源の場合と、道路事業の場合の自動車交通やその他の事業の工事用車両のように周辺道路を走行する移動発生源である場合の調査地域の設定の考え方は図1-1-1のように考えられる。
表1-1-6 大気質に係る影響範囲の目安
| 煙源種類 | 最大着地濃度距離及び設定方法 | 対象範囲 | |
| ばい煙発生源(実煙突高さ) | 50m未満 50~150m150m以上 | 0.5km(20m) ~ 2km(100m) 2km ~ 9km(200m) 9km ~ 15km(500m) |
~ 4km ~18km ~30km |
| 自動車 船 舶 航空機 |
- ばい煙発生源の50m未満に準ずる1,000mへ上昇するまでの水平距離 |
~ 2km ~ 4km ~10km |
|
| 粉じん発生源 炭化水素発生源 群小発生源 工事中 |
ばい煙発生源の50m未満に準ずる | ~ 4km | |
注)( )内は対応する有効煙突高さを示す
(社)環境情報科学センター(1999)を一部修正
図1-1-1 発生源の性質毎の調査地域の設定方法
[4]調査地点の考え方
大気質・悪臭の調査は定点において行われることが多いため、調査地点を設定することとなる。現地調査を実施する場合の調査地点は以下のような項目を考慮して設定する。
また、地域の特性に係る既存資料調査の結果を予測・評価に利用できる場合もあるが、その場合は、既存の測定地点の代表性の確認が必要である。代表性の確認を行うためには、「(ア)地域を代表する地点」での現地調査を実施し、既存の測定地点での測定結果と対比することなどが必要である。
なお、昨今では大気質調査の簡易測定法における計測の精度も高くなっており、大気汚染物質の面的な広がりを把握1-8)する場合は公定法を含めて、簡易測定法の併用も考慮していくことが望ましい。
(ア)地域を代表する地点
バックグラウンド濃度の設定など、調査地域の大気質の代表的な状況を知るための地点として調査地点を設定する場合には、近隣の発生源による影響が少なく、気象条件の安定した箇所を選定する。
(イ)特に影響を受けるおそれのある地点
事業による影響が特に大きいと予想される地点(最大着地濃度の予想される地点、敷地境界など)は、事業特性や類似事例からおおまかな地点を予想して設定する。なお、設定した地点には、他の発生源等の影響が少ないことを確認する必要がある。
(ウ)特に保全すべき対象等の存在する地点
医療施設、文教施設等の特に保全すべき対象等の存在する地点を予測地点として設定する場合に、道路など他の発生源の影響により、「(ア)の地域の代表地点」とは異なる状況が予想される場合には、これらの地点を調査地点として選定する。
大気汚染物質排出源周辺に高層建築物が存在し、住民の生活等に供されているような場合には、鉛直方向の調査地点の設定1-9)も検討する。
(エ)既に環境が著しく悪化している地点
道路、固定発生源などの他の発生源による影響を受けて、既に大気質の状況が悪化していると考えられる地点を選定する。
(オ)現在汚染等が進行しつつある場所
近隣の別発生源により現在汚染が進行しつつあると考えられる箇所などは、当該事業による影響とその他の影響を区分するため、事業実施前の状況を把握する。
【留意事項】
- 1-8) 大気質の面的把握(p.41~42参照)
大気質の現地調査は、定点で行われることが多いが、事業の実施に伴う大気汚染物質の面的広がりを把握するには、簡易測定法による地点密度の高い調査と公定法による自動計測での測定とを併用して実施することの検討も必要である。
既存の工場に隣接して新たな工場を設置するなどの際に、既存の工場からの汚染物質の空間的広がりを把握する場合に有用であると考える。また、事後調査においても面的広がりの変化を把握することが可能である。 - 1-9) 鉛直方向の調査地点の設定(p.43~44参照)
事業の実施により影響を受ける環境要素の測定は、人が通常生活し呼吸する高さを考慮して地上1.5mでサンプリングされる。同様に、予測で設定する予測地点の高さも地上1.5mである場合が多い。しかし、排出源周辺に高層建築物が存在し、かつ保全すべき施設である場合には、予測地点高さを高所に設定する必要があり、そのため調査においても同様に高所での把握が必要である。
[5]調査期間・時期の考え方
大気質の状況は、その移流・拡散の場となる大気の状況により大きく左右される。調査時点の設定にあたっては気象条件や大気汚染物質濃度の季節変動等、大気の状況の変動を十分に考慮する必要がある。特に発生源からの大気汚染物質の排出は時刻、曜日、季節などによって異なるため、短期濃度、長期濃度など求める対象に応じて調査期間・時期を設定する1-10)。
現地調査において測定された短期間の情報については、測定年が異常年である場合など、その測定値の代表性を持たない場合もあり、測定値の代表性を確認するための検討が必要である1-11)。
また、地域特性に係る既存資料調査の結果を予測・評価に用いる場合は、既存測定点の代表性を確認する必要がある。例えば、既存の測定地点の配置や周辺状況が調査地域と異なる可能性がある場合等には、現地調査において4季あるいは2期(非暖房期・暖房期)に1週間から1カ月間程度のサンプリング測定を行うなどの検討も必要である。
【留意事項】
- 1-10) 予測対象(短期濃度、長期濃度)を考慮した調査内容(p.45~48参照)
一般的に大気質の予測では年平均値を予測する長期予測を基本とする。この場合の気象条件としては、代表性を持つ通年の気象データを予測条件とする。また、短期濃度を対象とする場合には、逆転層の発生が多くなる冬季等、高濃度の発生が想定される気象状況を把握できる調査が必要である。通常、短期予測のみを実施することはないため、長期予測に用いる通年の気象観測結果等を利用して短期濃度予測の条件整理を行う。また、ダウンウォッシュやダウンドラフト、大気逆転層の形成等の短期高濃度の出現が想定されるような状況が発生し得る場合には、別途検討が必要となる。 - 1-11) 既存資料調査と現地調査結果の対照(p.49~51参照)
現地調査において得られた調査結果はその代表性の確認のため、長期間の既存データによる調査年の妥当性の検討(異常年検定)や、調査期間中の現地調査結果と既設の測定局における測定データとを比較し、経日変化や期間変化の類似性等を確認することからデータの検証を行う。
(2)影響予測
予測とは事業の実施による環境影響を適切に評価できるように、対象地域における大気質の状態に生ずる変化を明らかにすることである。「評価手法の検討→予測手法の検討→調査手法の検討」の順に検討を進めた場合には、予測を行う段階においては予測の手法は具体化していることとなるが、改めて調査の結果を勘案するとともに、予測及び評価に関する最新の知見の把握に努める必要があり、その結果、必要に応じて予測及び評価手法の見直しを行う場合も考えられる。
予測手法の選定にあたっては、基本的にはその時点での最新の知見を基に、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に計算上発生する誤差と予測手法や予測条件等に起因する不確実性があることに留意する必要がある。誤差については精度検定等により回避が可能であるものもあるが、予測の不確実性については、評価における考慮も必要であるとともに、不確実性の状況に応じて、事後調査の実施について検討する必要がある。
なお、将来的な予測の不確実性の低減に資するために、予測手法や予測条件の研究、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。
[1]予測項目の考え方
項目の選定は、対象事業の事業特性から抽出された影響要因と地域特性から抽出された環境要素との関係を厳密に検討して行う。
なお、環境要素のなかには、現状において予測手法が確立されていないもの、発生源情報の蓄積が不十分なもの、予測技術の更なる研究が必要なものなど1-12)が存在するが、最新の知見等を勘案して予測項目を検討する必要がある。
【留意事項】
- 1-12) 予測手法に検討を要する環境要素(p.52~54参照)
近年問題となっているダイオキシンやその他の環境ホルモン等の微量化学物質の中には、発生機構や生成過程が未解明な物質が存在する。しかし、これらの物質の中には、住民等の関心の高い物質もあり、環境要素として留意する必要がある。その場合は、事例の調査結果に基づいた予測手法の検討が考えられる。
浮遊粒子状物質や光化学オキシダントの生成は化学反応を伴うものであり、予測モデルにおけるパラメータの設定等において、必要となる発生源情報等のデータの入手に制約がある。
また、有害大気汚染物質のベンゼン等においては、概ね予測手法は確立されているが、その発生源情報については、今後の蓄積が必要である。
[2]予測手法の考え方
予測においては、発生源の種類、大気汚染物質の種類、地形条件、周辺の事物の条件、評価の方法等により、適用できる予測手法が異なる。従って予測手法の選定にあたっては、既往の環境影響評価における事例で用いられている手法を参考とするだけでなく、さまざまな予測手法の適用範囲を十分に検討した上で手法を選定し、選定したモデル等が当該事業に適用できるように調整を行う必要も生じる場合がある。なお、モデル等に調整を加えた場合には、その内容及び理由を明確に示すことが必要である。
また、予測手法によって予測結果が異なることが当然予想されるため、必要に応じて複数の予測手法の活用1-13)についても考慮する。
現状において、予測手法が確立されていない環境要素も存在する。最新の知見を把握するために、技術手法については以下に示すような環境影響評価技術に関する図書資料や、学会の論文等、あるいは海外の予測手法(米国EPAの手法等)を参照することも必要である。なお、海外の手法を用いる場合には、我が国とは異なる気象・地形条件等に合わせて作成されたモデルであることに十分留意する必要がある。
- 「環境アセスメントの技術」(平成11年8月 (社)環境情報科学センター)
- 技術シート(本中間報告書 第5章)
- 地方自治体の環境影響評価技術指針
【留意事項】
・ 1-13) 複数の予測手法の活用
複数の予測手法を活用することで、各予測手法の持つ不確実性について留意することができ、環境影響の最も大きくなる場合の把握も可能となる。
図1-1-2 複数の予測手法による結果提示のイメージ
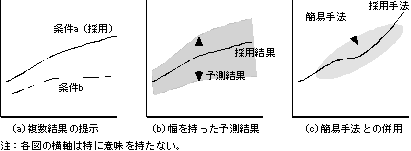
(ア)予測の不確実性
環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確からしい結果を定量的に導き出す手法を選定することが望ましいが、予測には常に誤差並びに不確実性があることに留意する必要がある。
予測の不確実性には、予測の前提となる現状の自然的・人為的変動、現状の把握にあたっての測定誤差及び予測モデルのそのものの限界やパラメータ・原単位等に内在する不確実性等の手法の不確実性がある。
測定誤差とは、精度の検証等によって回避できるものであり、例えば選定した気象条件等に含まれる誤差の場合には、異常年検定等の長期間の気象条件との比較から、その誤差を推定することが可能である。
一方、予測モデル、パラメータ等に内在する不確実性や、現象の理解度等に起因する不確実性については、単一の前提条件、予測手法による単一の結果に固執することなく、必要な場合には複数の予測条件や予測手法による結果を併記するなどの柔軟な対応を行うことを考慮する必要がある。特に、交通量に代表される交通条件1-14)のように、それ自体が推計を含む予測条件については、統計的に推測することができる。
例えば、環境影響評価に用いられる将来交通量は、道路整備計画を踏まえて設定した目標対象年の道路ネットワークとOD表を用いた交通量配分シミュレーションによる設定や、現状交通量に道路整備計画等から得られる伸び率を用いて設定されることが多い。このような場合、道路整備計画における道路ネットワーク等の整備の確実性の観点から、設定される将来交通量の精度が問題視される場合がある。これは道路整備計画から推計のベースとなるネットワークや伸び率を設定しているからである。一つの推計交通量を固定化することなく、想定されうる幾つかの推計交通量を予測条件にするなど、幅のある推計交通量による予測結果の併記も検討することが重要である。また、設定したネットワーク等を予測条件として明示することも必要である。
【留意事項】
- 1-14) 交通条件における予測の不確実性(p.55~58参照)
交通に関する予測条件だけでも交通量、時間変動率、大型車混入率等の種々の指標があり、それらが個々に不確実性を含むと考えられるものである。
交通計画の分野においては、種々のモデルによる詳細な交通量の推計手法が存在するが、環境影響評価において予測に用いられてきた推計交通は日ベースの計画交通量であることが多い。推計手法としては、「OD表をベースとした交通量配分シミュレーションによる方法」、「現状における交通量または走行量に伸び率を乗ずる方法」等が主に用いられているが、いずれも将来の道路整備計画を踏まえて目標推計年の道路ネットワークや交通量の伸び率が推計されており、そこに予測の不確実性が存在することを認識する必要がある。
また、時間変動率や大型車混入率は、周辺の既存道路等の調査結果を準用して設定されている。それぞれが、不確実性を発生させる要因となることに留意が必要である。
(イ)予測手法の重点化・簡略化
環境影響評価の対象とすべき要素について、地域特性の把握の結果、環境の著しく悪化した地域が存在する場合や、事業計画から想定される影響要因が一般的な事業内容に比べ著しい環境影響を及ぼすおそれがある場合等については手法の重点化を、一方、類似事業の事例などから判断して環境影響が極めて小さい場合等については手法の簡略化を検討する。手法の重点化においては、複数の予測手法の併用による方法が挙げられる1-15)。また、大気汚染物質排出量に関して、類似事例や周辺事例との比較により影響を予測することは簡略化の一つと考えられる1-16)。
なお、手法の重点化・簡略化は、技術的に高度な手法や簡易な手法を用いることだけを対象とするのではなく、予測地点、予測期間・時期等の増減等も含めて検討する。
【留意事項】
- 1-15) 複数の予測手法の併用(手法の重点化)
特異な気象条件や複雑地形においてプルームモデルを適用する場合は拡散パラメータ等の設定により、予測結果が大きく変動する。したがって、ダウンウォッシュ、ダウンドラフトや複雑地形等における予測では、模型実験や三次元シミュレーションによる方法で影響の有無を確認し、また、その予測結果からプルームモデルのチューニング(拡散パラメータの補正等)を行うことで、複数の環境保全措置の比較検討をプルームモデルにより行うことも可能となる。 - 1-16) 大気汚染物質排出量の把握による予測(手法の簡略化)
周辺に同様の事例がある場合には、拡散場の条件は同様と考え、拡散理論式による予測は行わず、当該事業の環境保全措置を加味した大気汚染物質排出量の把握により予測する。この様な予測手法は、事例と環境保全措置を勘案して行うものであり、手法の簡略化と考えられる。
ただし、事業の主要な評価項目については、安易な簡略化は環境影響評価への取り組み姿勢そのものが問われることにもなるので留意が必要である。
[3]予測条件の考え方
予測条件は、予測項目、予測手法に応じて必要となる項目について、事業特性及び地域特性を考慮して設定することとなる。
既往の環境影響評価において、一般的に用いられるプルーム式及びパフ式による予測を行う場合の主な予測条件は、表1-1-7に示すとおりである。「[2] (ア)予測の不確実性」において示したように、これらの予測条件の設定においては、予測の不確実性の原因になるものもあり、設定においては留意が必要である。
(ア)発生源条件
固定発生源の排出源条件のうち、発電所や工場等の大規模発生源については、事業特性から設定されるものであり、類似施設の状況や施設の稼働条件等を踏まえること及び事業者の管理下で運用されることから比較的不確実性が小さいと考えられる。
一方、移動発生源のうち、自動車に関しては、国や一部の地方自治体において将来年次別速度別車種別の排出係数1-17)が設定されており、予測においては、この排出係数、交通量及び車種構成から排出強度が設定される。排出係数については、排出ガス量の許容限度に関する中央環境審議会の答申による単体規制の目標値に基づいて設定されているものであり、適用されている単体規制の内容を明確にする必要がある。また、排出強度は、この排出係数と交通量、車種構成、速度等とから算出されるが、これらの交通条件が排出強度を大きく変化させる要因となることに留意すべきである。しかし、排出係数は大型車及び小型車の2車種分類で適用することが多く、大型のダンプトラックやトレーラー等の割合が高い場合には、排出強度を過小に見積もる可能性がある。現状において、これらの大型車に適用できる排出係数の設定は難しい面もあるが、予測に用いた排出係数と実際の車種構成との整合性にも留意が必要である。
走行速度については、法定速度や設計速度に基づいて設定する場合が多いが、予測地域の類似路線での実測速度を用いる等、予測地域や計画路線の道路特性等を反映した設定が必要である。
(イ)気象条件
気象条件については、地域的な代表性や設定した測定年に誤差が含まれる場合が想定されるため、広範囲や長期間の観測データとの対比等により時空間の両面からの誤差の推定・検証が必要である。
(ウ)拡散パラメータ
拡散パラメータに関しても、一般的にPasquill-Giffordの拡散パラメータが用いられるが、この拡散パラメータは平坦な草地における地上発生源からの拡散実験によって作成されたものである。高煙源の拡散や都市域のような粗度の大きな地域に適用する場合には、Pasquillの安定度分類と実際の安定度との対応について留意する必要があるように、煙源条件に見合った適切なパラメータの検討及び選定が必要となる。
(エ)バックグラウンド濃度
将来の大気汚染物質濃度を予測する場合には、予測の対象とする大気汚染物質の将来のバックグラウンド濃度の設定が必要である。一般にバックグラウンド濃度は予測対象地域において一律に設定されることが多いが、大規模な固定発生源や面発生源のように予測地域が広範囲(数kmから数10km)に及ぶ場合や計画路線が大気質の状況が異なる複数の地域をまたがって計画される場合には、バックグラウンド濃度を一律に設定するのではなく、地域毎に設定することが必要である。
表1-1-7 拡散予測における予測条件
| 予測条件 | 固定発生源の場合 | 移動発生源の場合 | |
| 排出源条件 | 排出量 | ・排出条件:ばい煙発生施設等の計画諸元、稼働計画等に基づく燃料使用量、排出濃度、排出ガス量、排出温度 等 ・排出強度の時間変動 |
・排出条件:交通量(自動車、船舶、航空機)、移動速度、排出係数、大型車混入率、重量構成 等 ・排出強度の時間変動 |
| 排出位置 | ・排出源の位置 | ・道路の位置 ・航路 ・飛行経路 等 |
|
| 排出高さ等 | ・排出源の実高さ ・有効煙突高1-18) |
・道路構造(路面高さ、遮音壁高さ 等) ・船舶の煙突高さ、飛行高度 等 |
|
| 気象条件 | ・風向・風速 ・Pasquill大気安定度 |
・風向・風速 ・Pasquill大気安定度 |
|
| 拡散パラメータ1-19) | ・Pasquill-Gifford図 ・Turner図 ・Briggsの拡散幅 ・OMLやAERMOD等による不安定時の拡散幅 |
・Pasquill-Gifford図、Turner図を基に設定されたパラメータ ・上記図を参考に沿道の実測結果から設定されたパラメータ |
|
| バックグラウンド濃度 | ・一般環境の大気汚染物質濃度 | ・予測・評価対象とする発生源の影響を受けない状況の大気汚染物質濃度 | |
【留意事項】
- 1-17) 排出係数(p.58参照)
大気汚染物質排出量算出の原単位となる自動車等からの大気汚染物質の排出係数は、排出ガス規制年別・燃料別の排出係数原単位と車種構成比及び平均半積載重量(貨物車類のみ)から設定されている。社会状況等の変化に伴い、想定したガソリン車・ディーゼル車の車種構成比や年式別の車両構成比の変動により、将来年次の設定値が外れる可能性がある。そのため、文献・資料等の排出係数を用いる際には、算定の前提となる諸設定が、予測地域や路線へ適用できるものかどうか考慮する必要がある。 - 1-18) 有効煙突高さ(p.59~60参照)
大気汚染物質を含む排出ガスが、排出される環境大気より高温であったり、排出ガスが上方向に速度を持っている場合には、排出されたプルームは実排出口高さ(H0)よりも上昇してから移流・拡散される。その上昇分(ΔH)を実排出口高さに加えたものを有効煙突高さ(He)という。上昇分(ΔH)の算出は、種々の算定式があるが、事業特性、排出形態等を考慮に入れて、妥当な算定式を採用する必要がある。 - 1-19) 拡散パラメータ(p.60~61参照)
地形が平坦でない場合や上層の拡散場においては、Smithの地表面粗度を考慮した粗度補正の方法に基づくPasquill-Giffordの拡散場パラメータや、電力中央研究所が国内の火力発電所を対象とした拡散実験結果により最大着地濃度と有効煙突高さの関係から設定した拡散パラメータ等がある。また、不安定時の拡散パラメータには、混合層構造を考慮したOML、AERMODモデルで使用されている拡散幅がある。自動車が発生源となる場合は、道路近傍における拡散実験等をもとに、自動車の走行による攪拌混合を初期拡散幅として考慮し、道路近傍における安定度と拡散パラメータとの関係が明確でないことを根拠とした安定度によらないパラメータが利用されている。
[4]予測地域の考え方
予測地域は、原則として事業の実施により大気汚染物質濃度があるレベル以上変化する範囲を含む地域とする。この範囲は事業の規模や内容によって変化するものであり、予測の不確実性や地域特性を考慮する必要があり、安全サイドの考え方から広めに設定することになる。調査地域、調査地点の考え方と同様に、固定発生源の場合と、自動車等の移動発生源の場合には、影響の範囲が異なるため予測地域・予測地点の考え方も異なる。
発電所や清掃工場等の固定発生源の場合は、排出条件の設定を施設の稼働条件により行うことが多く、予測条件の想定がある程度可能であることから、代表的な気象条件及び煙源条件を用いて、一般的な拡散式(プルーム式)によって試算し、最大着地濃度が出現する地点を把握し、この地点を十分に含む範囲を予測地域の目安とする。
自動車等の移動発生源の場合は、影響は比較的周辺に限られることから、道路沿道の数百mから数kmの範囲が予測地域の目安とされる。このように、大気汚染物質の拡散特性から、発生源の種類毎に概ねの影響範囲の目安を設定することができ、その目安は表1-1-6に示したとおりである。
また、既存の類似施設からの大気汚染物質の排出量と事業特性から想定される大気汚染物質の排出量との比較により、固定発生源からの予測を行う場合には、特に予測地域を定めないことも考えられる。
予測地点については、調査地点と同様に環境の状況の変化を重点的に把握する場合に設定するものであり、定点での評価を必要としない場合には必ずしも予測地点の設定を必要としないが、「(1) [4] 調査地点の考え方」における「(イ) 特に影響を受けるおそれのある地点」や、「(ウ) 特に保全すべき対象等の存在する地点」のある場合には、これらの地点を予測地点とすることが考えられる。また、予測地点の設定・選定に際しては、事後調査や環境監視計画等にも配慮するのが望ましい。
なお、予測地点における鉛直方向の高さは通常1.5mで設定されるケースが多いが、道路沿道やばい煙発生施設周辺に高層建築物が存在しているような場合には、利用形態に対応して鉛直方向を考慮に入れた地点の設定が必要な場合がある。
[5]予測時期の考え方
予測時期は、事業の実施に伴う発生源の活動を時系列的に検討して決定するが、大きくは、事業の工事中と供用後に二分される。
(ア)工事中
工事中については、工事計画全体にわたって時系列的に工事量の変化、工事区域の変化等を把握し、工事全体からの大気汚染物質排出量が最も大きくなる時期(あるいは負荷の大きい建設機械の稼働台数が最も多くなる時期)とする(図1-1-3
(イ)参照)。
なお、工事期間が非常に長い場合や、工事中に工事用車両走行ルートの変更が考えられる場合には、工事の中間的な時期における予測の実施についても検討する。
長期予測の場合には年平均値を予測するため、以下のような予測時期の設定が考えられる。
- 連続する12ヶ月の建設機械稼働台数が最大となる一年間
- 連続する12ヶ月の建設機械からの大気汚染物質排出量が最大となる一年間
短期予測の場合も、大気汚染物質排出量が多い時期という考え方は同様で、以下のような設定が考えられる。
- 一日の建設機械の稼働台数の総計が最大となる時期
- 一日の建設機械からの汚染物質排出量が最大となる時期
(イ)供用後
供用後については、施設の稼働や車両の走行が定常状態となる時期とする(図1-1-3 (イ)参照)。
また、事業が長期にわたって段階的に実施される場合や中間段階において環境の状況が大きく変化する場合には、それらの経年変化を把握し、負荷が最大となる部分供用時等の適切な時期に予測を行う(図1-1-3 (ニ)参照)。
最終的な供用時ではなく、途中段階で負荷が大きくなる場合には以下のようなものが挙げられる。
- 発電所等における施設の更新計画に際して、新規施設の部分的稼働による影響と既存施設の影響とが同時期に発生し、その程度が最終的な定常状態よりも大きくなる場合
- 計画道路の段階供用に伴い、中間供用時における交通量が全面供用時における交通量より大きくなる時期がある場合
(ウ)その他
事業によっては工事期間と供用期間が重複する場合が想定される。このような場合においては、工事の実施にかかる予測の時期は、工事の実施による負荷と供用による負荷の合計が最大になる時点とする(図1-1-3 (ロ)参照)。
また、環境への影響が最大になる時点は、必ずしも負荷量が最大になる時点ではなく、例えば工事期間中に特に保全すべき施設等が新たに出現する場合などは、これらの周辺環境の状況を勘案して予測時点を設定する(図1-1-3 (ハ)参照)。
上記のように、段階供用を行う事業に関しては、複数の予測時期を設定する場合がある。さらに、個々の予測時期に挟まれた期間に排出ガス規制が導入されることなどの予測条件を変化させる要因が明らかな場合には、それらを考慮して、予測時期毎に予測条件の設定を行う。
予測対象時期の考え方
(3)評価の考え方
環境影響評価における最終的な目的は評価であることから、評価の段階において手戻りが生じないためにも環境影響評価は、「評価→予測→調査」といった一連の流れに沿って検討し、作業が進められる。
環境影響評価法における評価の考え方は、大きく以下のア、イの2種類があり、これらのうちアの視点からの評価は必ず行う必要があり、またイに示される基準又は目標等のある場合には、イの視点からの評価についても必ず行う必要がある。
ア及びイの評価を行う場合には、イの基準等との整合が図られた上でさらにアの回避低減の措置が十分であるかどうかを検討し、双方の評価をあわせて総合的に評価することになる。アの視点からの評価は、回避低減の措置における「複数案の比較」、「実行可能なより良い技術の導入」に係る検討結果や効果等を明確にすることが重要となってくる。特に、イの基準等との整合が図られない場合には、それを明らかにするこ
とが重要であり、その上でアの回避低減の措置の検討を明確に示していく必要がある。
なお、回避・低減の措置等に係る環境保全措置の効果に関する知見の向上に資するために、事後調査・環境監視結果の蓄積及びその解析等を進めていく必要がある。
ア 環境影響の回避・低減に係る評価
建造物の構造・配置の在り方、環境保全設備、工事の方法等を含む幅広い環境保全対策を対象として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討すること、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討すること等の方法により、対象事業の実施により選定項目に係る環境要素に及ぶおそれのある影響が、回避され、又は低減されているものであるか否かについて評価されるものとすること。なお、これらの評価は、事業者により実行可能な範囲内で行われるものとすること。
イ 国又は地方公共団体の環境保全施策との整合性に係る検討
評価を行うに当たって、環境基準、環境基本計画その他の国又は地方公共団体による環境の保全の観点からの施策によって、選定項目に係る環境要素に関する基準又は目標が示されている場合は、当該基準等の達成状況、環境基本計画等の目標又は計画の内容等と調査及び予測の結果との整合性が図られているか否かについて検討されるものとすること。
ウ その他の留意事項
評価に当たって事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、当該措置等の内容を明らかにできるように整理されるものとすること。
(基本的事項 第二項五(3))
環境基準等の基準又は目標が設定されている大気質については、上記ア及びイの評価を併用することとなる。従来の環境影響評価においては、一般的にはイの視点のみによる評価が行われてきた。環境影響評価法に基づく環境影響評価では、アの視点による評価が前提となる。事業の実施による環境影響をゼロにすることはできないが、環境影響をいかに低減した計画となっているか、またそのためにどこまで検討を重ね、配慮してきたかが理解できる内容の環境影響評価が望まれる。
また、環境基準は環境保全上維持されることが望ましい基準として定められる行政上の目標となるべきものであり、環境汚染防止上の規制値とは概念上異なる。環境基準は幅広い行政の施策によって達成を目指すものである。それに対し、排出基準や総量規制は、環境基準達成に向けて講じられる諸施策と考えられる。このような背景を理解した上で、事業による環境影響を適切に評価する必要がある。
[1]回避・低減に係る評価
回避・低減に係る評価は、事業者による環境影響の回避・低減への努力・配慮を明らかにし、評価するものであり、その手法の例として、複数の案を時系列に沿って若しくは並行的に比較検討する方法や、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かについて検討する方法が基本的事項に挙げられている。また、現況よりも環境を悪化させないことで評価する方法等も考えられる。
回避・低減に係る評価において最も留意すべき点は、現状において環境基準を達成していない地域など、イの視点における基準等との整合が図られない場合1-20)において、アの視点からより一層の回避・低減の措置を検討した上で、双方の評価を併せて総合的に評価する場合の考え方についてである。
このような場合においては、基準等の整合が図られない内容を明らかにし、回避・低減の措置による事業の実施に伴う付加分の低減の程度(低減率等)、現状の大気質状況の変化の程度等から、その回避・低減の措置に関して実行可能なより良い技術が取り入れられている否かを検討し評価を行う1-21)。
[2]基準又は目標との整合に係る評価
大気質については、環境基準等の基準又は目標が設定されている環境要素を予測・評価項目とする場合が多いため、従来の環境影響評価においては、一般的に基準との整合についての視点による評価が実施されてきた。そのため、既に現状の大気質の状況が環境基準を達成していない地域での事業の場合、この基準との整合を図ることが環境影響評価において絶対として取り扱われてきたことは否めない。
現状において基準が達成されていない状況においては、事業者が実行可能な範囲での環境保全措置による基準の達成は困難であることが容易に想定される。この基準又は目標との整合に係る評価においては、従来の考え方を払拭し、基準との整合が図られない場合は、それを明らかにすることが最も重要であることを認識する必要がある。そして、その結果を踏まえて、前述の回避・低減に係る評価を実施していくことが必要である。
この基準との整合において環境影響評価の重要課題として取り上げられてきたものが、将来濃度の予測並びに基準との整合に必要となるバックグラウンド濃度の設定である。
(ア)大気質に係る評価とバックグラウンド濃度の関係
従来の環境影響評価においては、基準又は目標の達成に関する評価において、将来濃度を予測する上での最も重要なバックグラウンド濃度を小さく見込んだことによる問題等が環境影響評価の課題として取り上げられてきた。
事業実施による大気汚染物質の将来濃度は、設定した将来のバックグラウンド濃度に事業実施による付加分を上乗せして算出される。従って、バックグラウンド濃度は事業実施後の将来濃度を予測する上で、その結果を大きく左右するものである。
前述した課題は、このバックグラウンド濃度に地方自治体等が公表した大気質濃度の将来低減目標値(将来目標達成型)がそのまま採用されるケースが多々見受けられ、その低減施策実行の確実性に不透明さや不確実性が内在する点である1-22)。これは、削減計画による環境基準の達成状況に依然として十分な改善が見られないことなどにも起因するものである。
しかし、ここで留意すべき点は、将来低減目標値は環境基準の達成に向けた種々の削減施策の実施の結果であり、この目標値自体を問題視するものではなく、環境影響評価におけるバックグラウンド濃度としてこの目標値を採用する場合に、目標値の設定背景等を十分に考慮する必要があるということである。
このような課題の対応案としては、国や自治体等の公的機関において、現状の発生源の状況が将来にわたってそのまま推移した場合の将来予測値(現状推移型)の推計が考えられる。現状の大気汚染の状況を改善すべく削減施策の実行を前提条件とした将来濃度の推計のみならず、「[1] 排出源の状況が現状推移した場合」、「[2] 現時点で実施の確実性の高い施策のみ実行された場合」等の幅を持った将来濃度の予測を行い、この幅の中でバックグランド濃度を設定することの検討・公表も必要と考える。これらの検討については、今後の大きな課題であると考える。
なお、現状推移型のバックグラウンド濃度の設定においては、予測地域における代表的な一般環境大気測定局における5~10年間の過年度データの経年変化を把握し、その平均値で設定することも一手法として利用されている。
(イ)バックグラウンド濃度に対する個別事業の付加分の捉え方
本来、バックグラウンド濃度と個別事業の実施による付加分とは双方向の関係があるものである。設定された将来のバックグラウンド濃度を一個別事業が用いて環境影響評価を行う場合、そのバックグラウンド濃度には、影響の及ぶ地域での他事業の付加分が反映されている必要がある。さらに、環境影響評価手続き後には、その事業の付加分もバックグラウンド濃度に反映していく必要がある。しかし、従来の環境影響評価においては、複数の個別事業が同一のバックグラウンド濃度を用いており、双方向でなく一方向の関係しか見ることができない。
このような双方向の関係が確立されていない中で、個別事業の環境影響評価において将来濃度の予測を行い基準との整合性を評価する場合においては、どうしても単一のバックグラウンド濃度を各事業が用いることによる問題が生じる。この原因は、「バックグラウンド濃度+他事業付加分+新たな事業付加分」といった他事業の影響を将来予測に反映できない点にある。
この問題を解決する方法としては、まず、将来大気質の地域総合シミュレーションシステムの構築が考えられる。これは、国や各地方自治体等を中心とした公的機関によって定期的にバックグラウンド濃度の推計及び見直しを実施するシステムである。このようなシステムによって、バックグラウンド濃度と個別事業による付加濃度との双方向の関係を組み込んだシミュレーションができれば、「基準又は目標との整合性に係る評価」が可能となると考えられる。
しかしながら、このような地域総合シミュレーションシステムが構築されていない現状において、事業者が双方向の関係を組み込んだ将来大気質を予測することは困難である。そこで、「基準又は目標との整合性に係る評価」の一環として「回避・低減に係る評価」の考え方を導入した評価を行うことも考えられる。それは、基準又は目標とされる将来のバックグラウンド濃度については公表されているものを用い、事業者はそれに対する事業による付加濃度の割合を妥当性に十分留意しながら予測して、この付加濃度の割合を低減するための環境保全措置を実行可能な範囲で実施しているか否かを評価するものである。
[3]その他の留意事項
事業者以外が行う環境保全措置の効果を見込む場合1-23)においては、事業計画と事業者以外の者が実施する環境保全措置等の内容・効果・実施時期がよく整合していることや、これらの予算措置等の具体化の目途が立っていることを客観的資料に基づき明らかにする必要がある。
【留意事項】
- 1-20) 基準等の整合が図られない場合における回避・低減に係る評価(p.61~63参照)
地域特性の調査及び現地調査の結果から、事業実施区域及びその周辺における大気質の状況が環境基準を満足していない場合、そのような地域において事業を実施する場合の予測・評価においては、下記の内容について十分な検討が必要である。
・既存調査結果と現地調査結果との対比による地域の大気質の状況の把握
・将来におけるバックグラウンド濃度の設定
・回避・低減措置の効果の把握 - 1-21) 実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討(p.64参照)
実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討においては、客観的にその評価の妥当性を判断するために、事業の実施に伴い導入可能な技術にはどのようなものがあり、当該事業において採用したものは何なのかの情報を明示する必要がある。また、それらの技術による効果を可能な限り定量的に示すと供に、採用できなかった技術がある場合には、その理由を明確に提示することも必要と考えられる。 - 1-22) 将来低減目標値のバックグラウンド濃度への適用(p.65~66参照)
大気質の削減計画や低減目標値を将来のバックグラウンド濃度の設定に適用した例は多い。しかし、削減計画は社会状況の変化により想定どおりにならない場合も考えられるため、削減計画の内容及びスケジュール、現状の大気汚染の状況または改善状況等を勘案し、削減計画に基づく将来濃度と経年的な推移から推定される将来濃度から幅のある将来のバックグラウンド濃度の設定を行うことも必要である。 - 1-23) 事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合(p.66~67参照)
事業者以外が行う環境保全措置等の効果を見込む場合には、その環境保全措置の具体化の目途がついていることについて明らかにする必要がある。
事業者が同じであれば、事業実施区域近傍の対象事業以外の事業において環境保全措置を実施しその効果を加味することも可能である。
また、対象事業以外の事業による環境保全措置の効果が高い確度で見込まれる場合や、環境影響を総合的に予測・評価できる場合には、複数の事業による複合的なメリットが生じることが考えられる。例えば、道路事業において、複数の道路整備により結果的に道路網が整備される場合には、交通流の円滑化に伴う排出強度の減少等による環境面へのプラスの効果が生じる場合がある。それらのプラスの効果も加味して評価を実施することも検討する。
なお、複数の事業による複合的な影響は必ずしもメリットのみを生み出すものではなく、前述の例の場合、交通量の増加による環境面へのデメリットが生じる場合がある。この点にも十分に留意が必要である。