“実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き
7 実行可能なより良い技術”検討にあたって参考とした国内の制度
1)東京都による自発的な創意工夫による取り組みの制度化
《概要》 東京都における公害防止条例改正にあたっての基本的な方向を提言する環境審議会答申では、自発的な創意工夫による取り組みを通して環境負荷を低減させる誘導的な手法を制度化すべきと提言しており、“実行可能なより良い技術”的なものとなると考えられる。 また、答申ではこの誘導的手法について「環境影響評価手続きの対象となる大規模建築物(延べ床面積10万㎡かつ高さ100m以上)については、同手続きに委ねることとする。」としており、事業者にとって環境影響評価手続の中で同様な観点からの検討が必要となる方向にある。 《参考となるポイント》 ◇自発的な創意工夫による“より良い取り組み”を制度化するとともに、その取り組みの水準を指導や助言などの行政との協議プロセスを経ることにより、“実行可能なより良い”水準へと引き上げていく仕掛け ◇制度化の対象は、製造工場などに限らず流通・消費・廃棄など環境への影響をもたらすすべてを対象とすべきと提言しており、環境への影響をもたらす発生源をより広範に捉える姿勢 ◇東京都の環境影響評価制度において“実行可能なより良い技術”の導入についての評価が必要としていること |
[1]公害防止条例の改正にあたっての環境審議会答申
東京都では、昭和44年制定の公害防止条例の改正を検討中であり、その改正方向を示すものとして環境審議会より答申が出されている。
同答申では、地球環境対策としての温室効果ガスの排出抑制を具体的に促進させる規定がないという状況を踏まえ、環境負荷の低減化に係る措置として、次の2つの方策を提言している。
| - | 全ての事業者に対して自主的な環境負荷の低減のための努力義務を課す方策 |
| (温室効果ガスの抑制、エネルギー使用の抑制・合理化、リサイクルの促進、環境に配慮した物品調達、自動車使用の抑制・合理化など) | |
| - | 施設を建設する建築主に対して環境負荷を低減する努力義務を課す方策 |
| (省エネルギー・省資源、水循環、廃棄物の抑制、周辺環境への配慮など) |
同答申では、環境の危機に対応できる先駆的な仕組みを導入すること、これまでの規制的手法に加えて誘導的手法も配慮することが重要であるとし、条例改正の基本的な考え方として
「事業活動や都市づくりに環境配慮を重視した仕組みの導入」、具体的には、「事業活動に対しては、自発的な創意工夫によって計画的に環境負荷を低減させるような誘導的な手法が効果的かつ現実的であり、行政の支援のもとに、これら環境負荷の低減に向けた総合的な管理又は配慮を求めることを制度化すべきである。また、施設建設にあたっては、環境負荷の少ない土地利用に留意しながら、省エネルギー、水循環や緑化などを計画段階から配慮させることを制度化すべきである」と提言している。
具体的には、事業者に関しては「環境負荷低減計画書」を作成・提出し、取り組み内容を自ら都民に公表するすること、施設を建設する建築主に「環境配慮施設計画書」を作成・提出することを提言している。
[2]協議プロセスを通じたBAT的な水準の達成
環境審議会答申が提言する仕組みは、事業者に計画書の作成を求めるとともに、その記載内容について東京都と協議することを求めている。協議の場では、東京都は事業者に対して、事業者による創意工夫をベースとして、さらに環境への負荷を軽減するような取り組みを要請することが想定される。このような協議プロセスを経る結果、計画書が掲げる取り組みの水準は“実行可能なより良い技術”の導入により達成されるBAT的な水準となると考えられる。
[3]環境審議会答申にみるその他の特徴
環境審議会答申では、BAT的な水準へと引き上げようとする仕組みの導入に加えて、次のような点が特徴としてあげられる。
(1)制度化の対象
同答申では、制度化の対象としては産業分類の製造業を中心に、流通・消費・廃棄、さらには自動車利用者などの需要者も含めた公害の発生するおそれのある施設や機器を設置する事業場すべてを対象とすべきとしている。
(2)環境影響評価手続の中で同様な観点からの検討が必要となる方向
答申では、「環境影響評価手続きの対象となる大規模建築物(延べ床面積10万㎡かつ高さ100m以上)については、同手続に委ねることとする。」としており、事業者にとって環境影響評価手続の中で同様な観点からの検討が必要となる方向にある。
図表-31 環境審議会答申が提言する仕組み
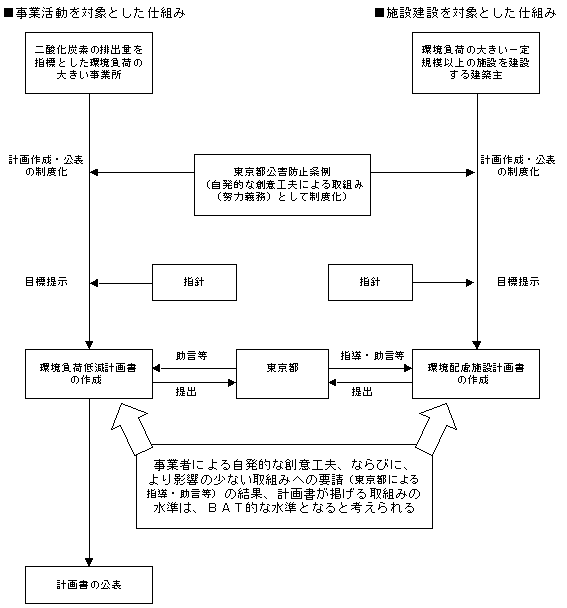
出典:東京都環境審議会「東京都公害防止条例の改正について(答申)」、平成12年3月より作成
2)神戸市における事前配慮指針
| 《概要》 神戸市では、計画の可能な限り早期の段階において環境の保全・創造の観点から十分な事前配慮を環境影響評価に先立って行うために、事前配慮指針を策定した。 《参考となるポイント》 ◇事前配慮事項の抽出においても事業計画の内容及び地域特性に応じて検討すること ◇事業計画の特性や熟度に応じて検討可能な事前配慮事項の内容は異なることから、事業者が該当する事前配慮項目について、どの段階で検討するかを明らかにすることが重要 ◇市は事業者に事前配慮を求める代わりに、必要な情報の整備と公開を進める |
[1]事前配慮指針の位置づけ
土地の形状の変更、工作物の新設等の事業の実施に際しては、当該計画の構想・立案段階といった可能な限り早期の段階において、事業計画の特性等を踏まえた上で環境の保全・創造の観点から十分な事前配慮を行うことにより、事業計画全体をより環境に配慮したものとしていくことが重要である。
そこで、神戸市においては、環境影響評価条例の対象とする事業等に対して、「事前配慮」を行うことを定めている。
事前配慮指針は、自然環境の保全やより望ましい快適な環境の創造などに関して事前に配慮すべき事項を指針として示すものである。事業者に対して、適切な環境配慮を事業計画の中に取り入れることを求めることにより環境への影響を可能な限り低減していくしくみづくりが必要であること、事前配慮に関する事項を示すことにより事業者が行う環境への配慮の理解促進が期待できることから、神戸市環境影響評価等に関する条例に基づき、事前配慮指針が策定されている。
また、神戸市では、平成8年3月に策定された神戸市環境保全計画においては、健全で快適な環境の確保のために、市長、事業者及び市民が配慮すべき指針(環境配慮指針)を定めることとしている。事前配慮指針は、この環境配慮指針の一部を構成するものとしても位置づけられる。
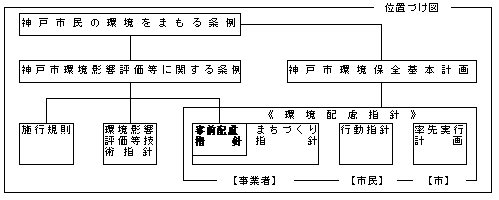
[2]事前配慮事項の内容と手順
事前配慮事項は、自然環境の保全や生活環境の保全、快適環境の保全・創造、地球環境保全への貢献について、事業者が配慮すべき事項を記している。市では、事業の種類と地域の区分を考慮して、各事前配慮項目を行う地域・事業の組み合わせを示している。但し、この組み合わせはあくまで例示であり、事業計画の特性等に応じて幅広く柔軟に検討するものとされている。
事前配慮を行う主体は事業者である。事前配慮の手順等は、次のように定められている。
| (1) | 事業者は、既存資料等によって、事業計画地及びその周辺地域の概況を調査する。また、必要に応じ現地調査を行う。 |
| (2) | 事業計画内容と概況調査により把握した地域特性を勘案のうえ、本指針に基づき事前配慮事項を抽出する。 |
| (3) | (2)で抽出した事前配慮事項を検討し、[1]早期段階において事業計画に取り入れる事項、[2]事業計画の熟度に応じて検討していく事項、[3]事業計画の内容・特性等から配慮できない事項、に整理する。 |
| (4) | [1]早期段階において事業計画に取り入れる事項及び[2]事業計画の熟度に応じて検討していく事項については、それらの内容を実施計画書に記述する。なお、計画の熟度に応じ検討した結果については、適宜事業計画に反映する。 |
| (5) | (1)から(4)の検討の経過については、環境の保全のための措置を講ずることとするに至った検討の状況として、評価書案及び評価書に記述する。 |
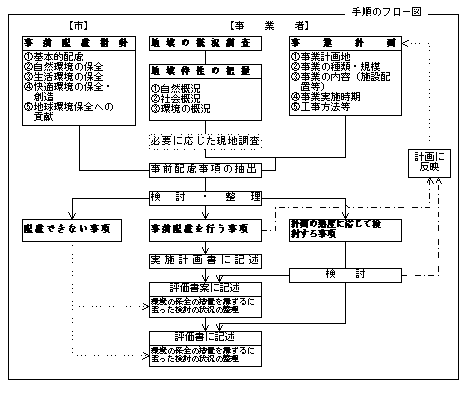
(事前配慮項目例)
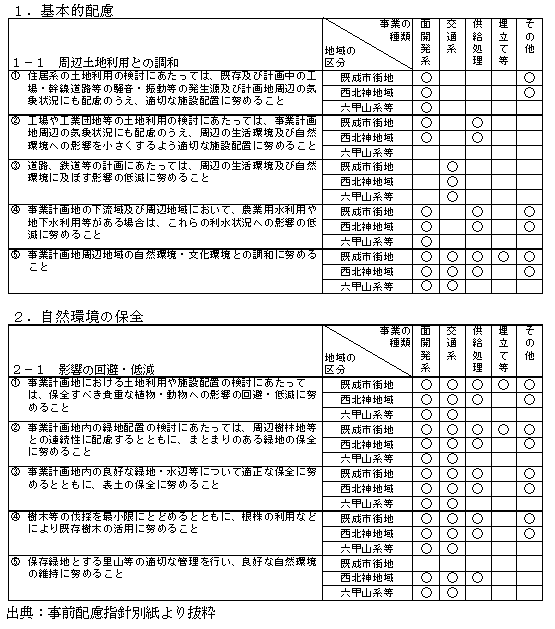
[3]神戸市の役割
神戸市は、事業者に事前配慮を求めるかわりに、市としても「自然環境等に関するデータベースの整備及び維持管理、調査手法の研究等、事業者の事前配慮に必要な体制を整備の上、環境に関する情報の提供など積極的な支援に努めていくものとする」(事前配慮指針より抜粋)と定めている。
神戸市では、事前配慮指針の作成において、できるだけ事業者自身で検討・工夫を行うことができ、弾力的に運用できるものとすることを心掛けたとのことである。