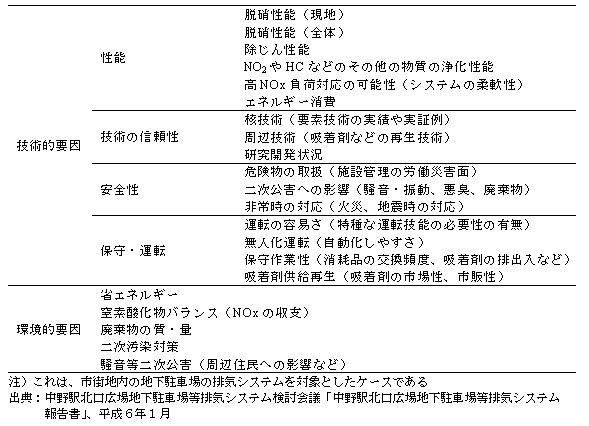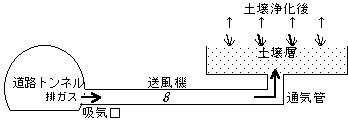“実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き
5 事例にみる“実行可能なより良い技術”検討の考え方
1)火力発電所の新増設での事例
|
||||||||||||||||||
近年の火力発電所における大気汚染物質の排出状況をみると、大気汚染防止法や地方公共団体の条例が定める排出基準を大幅に下回る状況となっており、実行可能なより良い技術が導入されて成功をおさめた分野の1つであると考えられる。
そこでここでは、これまでの火力発電所での環境保全対策を例に
“実行可能なより良い技術”導入と導入についての評価の考え方を示す。
なお、ここで紹介する火力発電所の例も環境影響評価法の新たな評価の考え方に対応していないことから、実行可能なより良い技術の導入方法についてさらに改善が必要である。
[1]火力発電所における環境影響評価の考え方
───国内最高水準の設備の導入により達成できる水準を排出レベルとする───
火力発電所の新増設には、新規立地の場合と既存発電所の更新(スクラップ&ビルド)により総発電能力を増強する場合とがある。
これまでのところ電力会社による火力発電所での大気汚染物質の排出レベルの決定にあたっては、新規立地の場合には、国内での既存および計画中の施設の動向を踏まえ、最高水準の設備を導入することで達成できる水準を排出レベルとしている。
また、スクラップ&ビルドの場合には、計画地内に立地する既存施設も含めた全体での排出量が増加しない程度の水準を排出レベルとしている。この場合でも、その排出レベルを達成しながら必要な出力を確保するためには、国内の最高水準の技術や設備を導入することが必要となる。なお、新設立地の場合において、計画地内に限らず同一県内の他の既存施設を含めた全体で排出量が増加しない程度の水準という考え方を採用した例もある。
図表- 5 排出レベル設定の考え方
| 新設立地の場合 | 国内最高水準の設備を導入することにより達成できる水準を排出レベルとする |
| 既存施設の更新 | 計画地内に立地する既存施設も含めた全体での排出量が増加しない程度の水準を排出レベルとする 実際には国内最高水準の設備の導入が必要) |
上記のような最新の設備を導入するという考え方、あるいは、計画地内外の他の施設も含めた全体で排出量を増加させないという考え方に従って排出レベルが設定されてきた結果、現在での火力発電所からの大気汚染物質の排出状況は、大気汚染防止法や地方公共団体の条例が定める排出基準を大幅に下回る状況となるに至っている。(図表-6 参照)
新規立地あるいはスクラップ&ビルドの場合とも、常に最高水準の設備を導入することが必要とされてきている状況をみると、これまでの電力会社による火力発電所が導入してきた技術は、“より良い技術”であったとみなされる。
図表- 6 LNG火力発電所での排出状況の例(窒素酸化物)
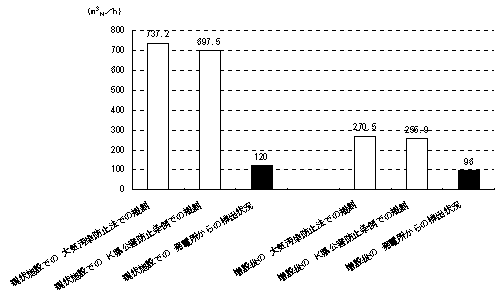
|
───これからの考え方:方法書手続の活用とベスト追求型への転換───
環境影響評価法においては、これまでの目標クリア型からベスト追求型の考え方となった。このため、火力発電所における環境影響評価でも、今後は、現状非悪化であること等の目標を達成できるかどうかだけで評価するのではなく、回避・低減の達成の程度を評価することになる。
よって、今後は火力発電所においてもこの新たな評価の考え方に基づき“実行可能なより良い技術”の導入についての評価を行うことが重要になるといえる。
また、スコーピングの考え方が導入され、方法書手続が設けられたことにより、早期段階から事業内容を示し、住民等の意見を聞くことも可能になった。よって、今後はこの手続を活用することで、より効果的な“実行可能なより良い技術”の導入を図ることが重要である。
───各段階における環境保全対策───
火力発電所での大気汚染防止に向けた環境保全対策は、燃料対策、燃焼方法の改善、排ガス対策、運用対策の4つに区分(図表-7 参照)されるが、実行可能なより良い技術”の導入についての検討にあたっては、まず、この環境保全対策別に検討する必要がある。
図表- 7 発電所での排ガス対策
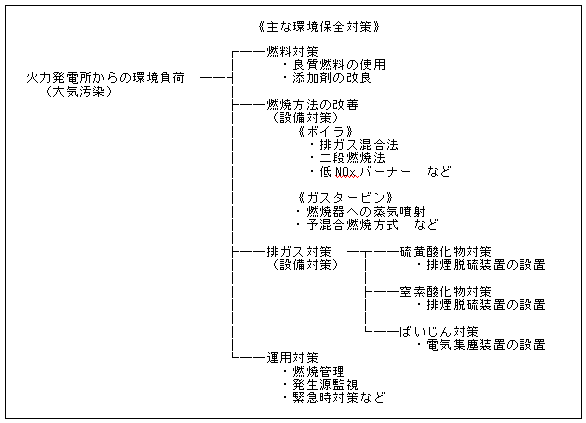
───燃料対策も含めた幅広い検討が必要───
火力発電所には、石炭火力発電所、石油火力発電所、LNG火力発電所などがあるが、使用する燃料により必要となる環境保全対策は異なる。種類別の大気汚染防止対策をみると、例えばLNG火力発電所では、硫黄酸化物や煤じんが発生しないため窒素酸化物対策が中心となる。石炭火力発電所では、硫黄酸化物及び窒素酸化物対策に加えて煤じん対策や貯炭場より飛散する粉じん対策が必要となる。(図表-8 参照)
図表- 8 火力発電所の種類別にみた大気汚染防止対策
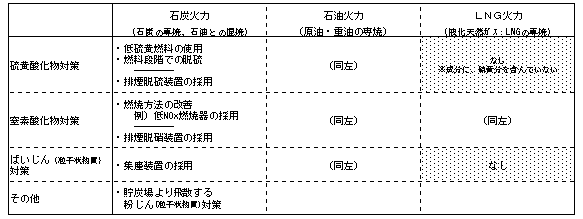
環境への影響面からみると、火力発電所の中ではその使用燃料の特徴によりLNG火力発電所が最も負荷が少ないと考えられるが、日本国内には化石燃料が限られ、資源を海外からの輸入に大きく依存するという状況では、LNG火力発電所の立地のみを進めることは困難といえる。また、火力発電所等の立地には地元調整および建設に相当の年数が必要とされることから、長期的な観点から電源開発が行われており、概ね10年先を見通した供給計画に従い、発電所の種類や規模が具体化されている。このような状況のため、計画熟度が高くなるアセス着手の段階では、燃料については計画の変更に関する柔軟性に乏しい。一方、従来から火力発電所での環境影響評価における大気汚染防止対策の具体化に際しての中心的事項は、硫黄酸化物や窒素酸化物などの排出レベルであり、これは大気汚染物質の煙突出口排出量であって、ボイラ等から出る排ガスを脱硫装置あるいは脱硝装置等で処理した後に、最終的に煙突より大気に放出される段階での排出量である。このため、従来から燃焼方法の改善及び排ガス対策を中心に環境保全対策が検討されてきている。
しかしながら、ベスト追求に向けた検討においては、燃料の選択およびその質や燃焼方法などの事業計画の早期段階で決定される事項も含めたより幅広い範囲での検討が必要とされる。火力発電所の場合には、環境影響評価の段階において、例えば目指すべきベストな水準の達成に向けた良質な燃料の導入などを検討する必要性もある。(図表-9 参照)
なお、新しい環境影響評価制度においては、スコーピングが導入されたことから、ある程度早い段階で手続が開始できるため、この活用も重要である。
図表- 9 環境影響の回避・低減検討の検討段階
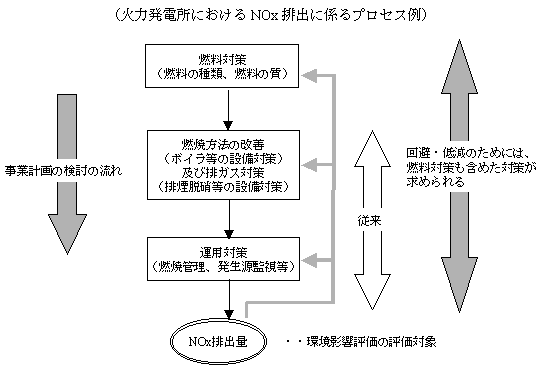
[2]火力発電所の事例から見る“実行可能なより良い技術”の考え方
───燃料対策が焦点となった事例───
発電所の計画の根幹に関わる部分のひとつとして燃料計画がある。近年、燃料の多様化と燃料価格の点から発電等の燃料として超高粘度である減圧蒸留残渣油やオリマルジョン(歴青質混合物とも呼ばれる、南米・ベネズエラのオリノコ川流域で産出される天然タールに水と界面活性剤(水と油をなじませる物質)を加えて乳液化(エマルジョン化)した重質油エマルジョン燃料)が利用され始めた。これらの燃料は、重油に比べ、成分中の硫黄分、窒素分及び灰分が高く、燃焼時には極めて高度な環境負荷低減対策が必要とされるものである。
また、平成7年12月に施行された改正電気事業法により、許可を受けない非電気事業者でも入札制度を通して自由に発電事業に参入できる卸供給発電が可能となり、独立発電事業者(IPP;Independent Power Producer)により減圧蒸留残渣油を燃料として使用する火力発電所が多数計画されている。これらの計画は環境影響評価手続を行っていく過程において、その事業による環境負荷の大きさが問題となり、当初事業者が想定していたものよりもより高水準の環境負荷低減対策が求められ、やむなく計画を中止としたケースも生じている。
このような高水準の環境負荷低減対策が必要と考えられる計画に対して、今回の検討対象である“実行可能なより良い技術”の考え方に沿った取り組みを求める環境庁長官意見が出されている。(図表-10 参照)
このようなケースからは、これからの環境影響評価では、燃料の選択のような事業計画の根幹に関わる部分は環境への影響に大きく関与しており、この段階から“実行可能なより良い技術”の考え方に即した検討を行っておくことが必要であるといえる。
図表-10 環境影響評価に係わる環境庁長官意見
| 事業名 (所在地) |
意見箇所 | 最新の技術等の導入を促す意見内容 |
事業の背景 |
| 御坊第二発電所 (和歌山県) |
燃焼技術・排出ガス処理技術 燃料対策 |
環境負荷が少なく、十分な信頼性を有する燃焼技術・排出ガス処理技術の積極的導入、維持管理の徹底等、大気汚染物質の一層の排出抑制に努力すること。・・・(中略)・・・環境影響の小さい界面活性剤を用いたオリマルジョンの開発を促進し、その採用を図ること(平成9年7月、環境庁長官) | 当該発電所の燃料として使用が予定されているオリマルジョンについては、重油に比べ、成分中の硫黄分、窒素分及び灰分が高く、燃焼時には極めて高度な環境負荷低減対策が必要とされるため |
| 川崎火力1・2号系列 (川崎市) |
燃焼技術・排出ガス処理技術 | 環境負荷の少ない燃焼技術・排出ガス処理技術について、最新の技術の開発・普及状況を踏まえ、積極的な導入に努めること(平成10年3月、環境庁長官) | 周辺地域は、二酸化窒素濃度が環境基準を超過しているとともに、大気汚染防止法に基づく固定発生源に係る窒素酸化物総量規制地域であり、大気環境への負荷を極力低減する必要があるため |
| 神鋼神戸発電所計画 (神戸市) |
燃焼技術・排出ガス処理技術 燃料対策 |
硫黄酸化物について、硫黄分の少ない炭種選定や最新の排出ガス処理技術の導入等により、既設製鉄所を含めた低減対策を講じ、年間総排出量が現状程度となるよう可能な限りその抑制に努めること(平成10年10月、環境庁長官) | 立地予定地の周辺地域は、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が達成されておらず、大気汚染防止法の硫黄酸化物に係る総量規制地域に指定され、かつ、公害健康被害の補償等に関する法律の旧第一種地域であることから、事業の実施に際しては、既設製鉄所の対策も含めて大気環境への負荷低減対策を推進する必要があるため |
| 川鉄千葉クリーンパワーステーション計画 (千葉市) |
燃焼技術・排出ガス処理技術 | 新設発電所において、最新の燃焼技術及び排出ガス処理対策を導入するとともに、既設コンバインド発電所においても排出ガス処理対策を講じ、これら発電所からの排出ガスの厳格な管理を行うことにより、両発電所からの窒素酸化物年間排出量の合計を、事業者が既に計画しているとおり200t未満とすること。(平成11年5月、環境庁長官) | 周辺地域は、二酸化窒素濃度が環境基準を超過しているとともに、大気汚染防止法に基づく固定発生源に係る窒素酸化物総量規制地域であり、大気環境への負荷を極力低減する必要があるため |
| 東亜石油エネルギー供給施設 (川崎市) |
燃焼技術・排出ガス処理技術 燃料対策 |
発電用燃料について、高カロリーガスに係る硫黄分除去技術の導入及び低カロリーガスに係る脱硫装置の操業技術の改善等により、より一層の性状改善を図ること。併せて、技術開発動向を踏まえつつ最新の燃焼技術を導入する等の対策により、ばい煙排出量のさらなる低減を図ること(平成12年2月、環境庁長官) | 計画地周辺地域においては、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準を達成しておらず、大気汚染防止法の窒素酸化物及び硫黄酸化物に係る総量規制地域及び自動車NOx法の特定地域に指定されており、大気環境への負荷を可能な限り低減する必要があるため |
| 出典:環境庁資料より作成 |
───環境保全対策による波及的な影響も考慮する必要がある───
石炭火力発電所の場合、二段燃焼などのNOx排出量を抑制する燃焼方法と脱硝装置の併用によって環境負荷の低減が図られてきている。現在使用されている低NOx燃焼方法ではNOxの低減により逆に灰中に残存する未燃分が増加し、石炭種によっては石炭灰をセメント等へ有効利用できず、最終埋立処分場への埋立処分が必要となる問題点が生じている。このように、窒素酸化物の発生量と石炭灰のリサイクルとはトレードオフの関係にある。(このような状況に対して電力会社等では石炭灰の有効利用率を増加させる燃焼方法について研究開発を進めているところである。)
このように、発電所における大気汚染防止対策について、例えば運転条件の変更や燃焼方法の改善も含めて環境保全対策を検討する場合には、マイナス面での影響が生じる場合も考えられる。これからの環境影響評価での環境保全対策の検討にあたっては、環境要素間のトレードオフに留意し、波及的な影響を考慮しながら全体的に負荷の軽減を行う必要がある。
───早期段階から環境への事前配慮を検討していた事例───
この事例は、製鉄所に併設される卸供給発電事業である。発電出力140万kWの石炭火力発電所計画であり、当該地域内で初めての本格的な発電所計画である。同計画にあたり事業者は、発電所計画地点及びその周辺地域の環境と調和を図り、より良い事業計画とする観点から地方公共団体の指導を受けて環境への事前配慮を行っている。大気汚染の防止に向けては、1.発電所においては、大気汚染物質除去装置の設置等により、排出濃度を可能な限り低減し、大気汚染物質の発生を抑制すること。2.石炭や石炭灰の貯蔵、搬送設備を密閉構造とし、粉じんの飛散を防止すること、3.既設製鉄所においても、都市ガスへの燃料転換、1,2号焼結炉の廃止等により大気汚染物質の発生量を低減させ、周辺地域の環境濃度への寄与の低減を図ることが事前配慮事項とされていた。このうち2.および3.の配慮事項は、環境への影響をより低減させることを主眼として、その環境保全対策の範囲をより広範囲に検討している。このケースからは、早期段階からより広範な環境への影響を検討することが必要であることが言える。
一般に、発電所などの大規模な構造物の場合、計画立案、環境影響評価、認可、そして建設には数年~十年近くを要する状況にある。このため、計画立案段階では最新の技術であったが、準備書・評価書の手続の段階では、より環境保全の効果の高い技術が実用化されているケースも考えられる。同計画は、最新技術が環境影響評価を進める中で変化したケースである。
同計画は、電力の需要地に近接することから送電による損出がほとんど無くエネルギーの有効活用という面では大きな利点を有している。一方、環境への影響面からみると同計画は、1.政令指定都市の中心市街地に隣接して発電所を設置する計画であること、2.工場や港湾施設などの高密度な土地利用がなされており、幹線道路や鉄道が集中する東西交通の要衝であること、3.計画地を含めた臨海部周辺の環境の現状は大気汚染防止法の硫黄酸化物に係る総量規制地域に指定され、かつ、公害健康被害の補償等に関する法律の旧第一種地域であるとともに、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が達成されていない等依然として厳しい状況にあること、等特段の環境保全上の配慮が必要とされている地域である。
このケースでは、特段の環境保全上の配慮が必要とされている地域特性を鑑み、当初の行政との事前調整の段階から環境への負荷をより一層低減できる技術を導入することを盛り込んだ事業計画であった。当初の段階では、横浜市に立地する発電所に導入される技術が最も環境への負荷を抑えられる技術であったため、その技術を導入するという計画内容であった。その後環境影響評価の手続が進み、評価書を審査する段階で新たに愛知県に計画された発電所に導入される技術がより環境への影響を抑えた技術であることが判明した。このようなより一層環境への負荷を低減できる技術が実用化されようとしている状況に対して、評価書を審査する審査会では、特段の環境保全上の配慮が必要とされている地域特性を最重要視し、より最新の技術の導入を求めることを答申している。
このケースからは、1.より環境保全効果の高い技術を求める姿勢が事業者に求められること、2.反面、開発途上の技術に関する事前の情報収集が不充分だったことにより軌道修正が必要になったことから、これからの環境影響評価では、開発中の技術も含めて最新の技術動向を継続的に把握するとともに、中長期的な観点から導入技術を選択することが必要であること、3.地域特性によって求められる技術水準が変化すること、特に今回のように特段の環境保全上の配慮が必要とされる地域である場合、導入が必要な技術の水準は極めて高くなり、「実行可能性」についても事業者にとっては厳しく捉えられる必要があることなどが言える。
2)道路事業におけるトンネル脱硝での事例
| 《概要》 道路事業では、道路トンネル出口や換気坑周辺で生じる高濃度な大気汚染が問題となっている。このような問題に対して、自動車より生じる低濃度の窒素酸化物を除去する技術(トンネル脱硝技術)の開発が進められている。このトンネル脱硝技術は、既に開発段階を経て、より良い技術を経済性等を加味して比較検討し、“実行可能なより良い技術”を絞り込んでいく段階に達している。
|
||||||||
これまでの環境アセスメントについての環境庁長官や知事等の意見をみると、今回の検討対象である“実行可能なより良い技術”の考え方に沿った取り組みを求める意見が道路、空港、発電所において出されている。(図表-11 参照)
その中での最初のケースは平成2年に国の閣議決定要綱に基づくアセス制度により、環境庁長官が東京都の地下首都高速道路建設計画(中央環状新宿線:青葉台-南長崎、8.7km、図表-12 参照)について、窒素酸化物の除去装置(脱硝装置)を設置するよう建設省に対して意見書を提出した事業である。このケースでは、地下高速道路に脱硝装置を取り付けないと道路区間内の2ヶ所のインターチェンジ部で二酸化窒素の環境基準0.04~0.06ppmを超えるとする予測が評価書内に記載されていた。同様な意見書は、首都圏での東京湾横断道路建設事業や川崎縦貫道路事業についても提出されている。
そこでここでは、個別のアセス事例ではないものの、道路トンネルでの窒素酸化物対策(トンネル脱硝技術)を通じて
“実行可能なより良い技術”導入の考え方を検討する。
図表-11 環境影響評価に係わる環境庁長官及び知事等意見
| 施設 形態 |
事業名 | 意見箇所 | 最新の技術等の導入を促す意見内容 | 事業の背景 |
| 道路 | 東京湾横断道路(1区間) | 窒素酸化物 | 事業の実施にあたっては、換気等において汚染物質の除去に努める等環境保全に最善を尽くす必要がある(昭和62年7月、環境庁長官) | 計画されている地域では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が達成されていないため |
| 都市高速道路中央環状新宿線(1区間) | 窒素酸化物(トンネル脱硝) | 脱硝装置の技術的可能性について調査・研究を進め、その成果を踏まえて換気塔における脱硝装置等汚染物質の除去装置の導入を図るほか、必要に応じトンネル坑口部において覆蓋を設置する等環境保全目標の達成が図られるよう最善を尽くす必要がある(平成2年8月、環境庁長官) | 計画されている地域では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が達成されていないため | |
| 川崎縦貫道路(1区間) | 窒素酸化物(トンネル脱硝) | 本事業における脱硝装置の技術的可能性について調査・研究を進め、その成果を踏まえて換気塔における脱硝装置等汚染物質の除去装置の導入を図る等環境基準の達成が図られるよう当該道路の事業においても最善を尽くす必要がある(平成2年8月、環境庁長官) | 計画されている地域では、二酸化窒素及び浮遊粒子状物質に係る環境基準が達成されていないため | |
| 東京外かく環状道路(松戸市~市川市間) | 窒素酸化物 | 窒素酸化物対策に係る最新技術の知見を収集し、事業の実施に際して道路構造上の対応も含め具体的な対策を講じること(平成8年9月、千葉県) | 大気汚染等による環境問題が顕在化している地域であるとともに、計画道路が二酸化窒素濃度の高い地域を通過するため | |
| 都市計画道路尾道三次線 | 全般 | 環境保全対策は、的確に履行するとともに、最新の技術・工法等を積極的に採用し、環境保全に努めること(平成8年11月、広島県) | ||
| 徳島東部都市計画道路1・3・2号阿南鳴門線 | 工事車両 | 工事中においては、・・・(中略)・・・周辺への影響の少ない工法や低公害型機種を可能な限り採用する等、適切な保全対策を講じること(平成9年1月、徳島県) | 工事中の周辺民家、動植物の生息・生育環境への配慮が求められるため | |
| さがみ縦貫道路事業(愛川町中津~城山町川尻) | 騒音 | 騒音対策の検討にあたっては、・・・(中略)・・・最新の技術の導入についても積極的に検討すること(平成9年5月、神奈川県) | 道路周辺は比較的住居が多い地区であるとともに、学校が立地しているため | |
| 空港 | 広島空港拡張整備事業 | 全般 | 環境保全対策は、的確に履行するとともに、最新の技術・工法等を積極的に採用し、環境保全に努めること(平成8年1月、広島県) | 空港拡張による航空機騒音等の影響が広範囲に及ぶこと、また、関係住民からこれらに関する意見が多数寄せられているため |
| 出典:環境庁資料より作成 |
図表-12 中央環状新宿線計画の概要
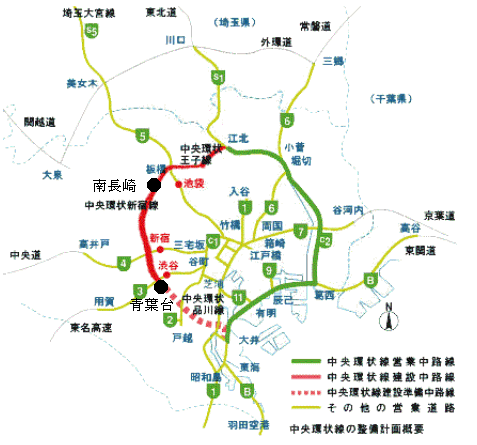
出典:首都高速道路公団資料 |
[1]トンネル脱硝技術のこれまでの流れと現状
───トンネル脱硝が焦点となった背景:煤塵、CO対策ではカバーしきれないNOxや新たな物質───
これまでの道路トンネルの設計にあたっては、煤塵および一酸化炭素(CO)を対象とした設計基準(図表-13 参照)が設けられ、この基準を満たすトンネルが設計されてきている。
図表-13 道路トンネルでの換気設計
| 煤塵の設計濃度 | COの設計濃度 | |||
| 設計速度 | 100m透過率 | 質量濃度 | 容積濃度 | 質量濃度 |
| 80km/h以上 | 50% | 1~3mg/m3 | 100ppm | 116.4mg/m3 |
| 60km/h以下 | 40% | |||
| 出典:(社)日本道路協会「道路トンネル技術基準・同解説(換気編)」、昭和60年12月 |
道路トンネル内でのガソリン車・ディーゼル車での所要換気量(図表-14 参照)は、ディーゼル車からの煤塵が最も量的に多い。このため、道路トンネル内での排ガス対策は、煤塵対策が中心となり電気集塵機の導入が進んでいる。
一方、煤塵やCOに加えて道路トンネル出口付近や排気口での窒素酸化物(NOx)の濃度が大きな問題となる。NOx対策をトンネル内での所要換気量でみると、NOxは、煤塵に比べるとその必要量は少ないものの、ディーゼル車ではCOを上回る量が必要とされる。しかしながらこれまでのところ、煤塵は電気集塵法による除去が可能であるが、NOxに対しては有効な除去対策がとられていない状況にある。
図表-14 車種別にみた道路トンネルにおける排ガスの所要換気量
| 車種 | 対象物質 | 換気のための |
所要換気量 |
| ガソリン 乗用車 |
CO NOx |
100ppm 25ppm |
23 m3/km/台 10 |
| ディーゼル 大型トラック |
CO NOx 煤塵 |
100ppm 25ppm 40% |
55m3/km/台 136 1250 |
出典: |
水谷他「道路トンネル内のNOx低減技術に関する基礎的実験」(土木技術資料)、昭和59年 |
道路トンネル内からの汚染空気は、常温、低濃度(最大でも3~5ppm)、大風量、粉塵や各種物質の混在という特徴を有するとともに、また処理空間に制限があるなどの理由から数秒以内に処理することが望まれるが、その処理は技術的に難しい状況にあり、現在、窒素酸化物の除去に向けた低濃度脱硝技術の開発が行われている。
大都市中心部における多くの自動車排出ガス測定局では、環境基準が未達成であり、都市部の窒素酸化物等のバックグラウンド濃度値が極めて高くなっている。このため、低濃度脱硝技術の開発は、道路事業にとって不可欠な技術になりつつある。
また、道路トンネルでの大気汚染は、走行する車両の性状により大きく左右される。ディーゼル車の排ガス中には、ガソリン車に比べて排出量が多いアルデヒド類などの未規制の臭気刺激性物質が含まれており、臭いや眼、鼻、のどへの刺激等の不快感が生じるため、電気集塵機で処理した空気の再利用を3回以内とする設計基準が設けられているが、空気を再利用することにより二次公害として排気坑やトンネル出口周辺で局所的に高濃度な大気汚染が問題となる。
近年では、ディーゼル車への排ガス規制が新たに適用される方向にあるが、その段階にはまた新たな物質への対応が必要とされることも予想される。
───地下駐車場や交差点でも問題化───
同様な問題は、道路トンネルでの換気により排ガスが集中するトンネル出口や換気抗口及び換気塔に限らず、地下駐車場などの閉鎖空間や都市内幹線道路沿いやその交差点でも発生している。
大都市中心部では、数多くの地下道路、地下駐車場が建設されてきている。業務機能や交通量の集中が進みつつある中、これらはますます増える方向にある。
(→中野区の例:後述)
───トンネル脱硝技術は、経済性評価の段階に達している───
平成2年の環境庁の地下首都高速道路建設計画に対する脱硝装置の設置を求める建設省への意見書を受ける形で、平成3~6年度にかけて(財)先端建設技術センターが公募により低濃度脱硝装置の技術水準についてのフィールド実験が行われた。さらに、平成9~11年には、引き続き建設省等によりパイロットスケール実験を行った。現在、建設省ではより効率的なシステムの実現に向けて、民間との研究を推進中である。研究にあたっての基本的な条件としては、1. 既存の実証実験での大気汚染物質の除去性能を上回ること、2. スペース、エネルギー、コスト、維持管理等の他の要件とのバランスを満たし、できるだけ高率で除去すること、などが掲げられている。
これまでの10年にもおよぶ研究プロセスや建設省における今後の開発方向をみると、トンネル脱硝技術は既に開発段階を経て、より良い技術を経済性も加味して比較検討し、“実行可能なより良い技術”を絞り込んでいく、ほぼ実用の段階に達している。現在、トンネル脱硝装置開発のきっかけとなった中央環状新宿線の工事が平成15~18年完成を目標に進んでおり、トンネル脱硝装置導入の具体化は進んでいないものの開発のスケジュールは充分間に合ったと言える。
図表-15 トンネル脱硝装置に関わる流れ
| 昭和63年12月 | 環境庁が「窒素酸化物対策の新たな中期展望」を公表 この中で、交差点、都市部道路トンネルの出口、換気坑口付近等を具体的な高濃度汚染対策地域とした局所的な大気汚染浄化装置の技術的可能性の調査研究の必要性を指摘する |
||||||||||
| 平成元年12月 | 中央公害対策審議会が、自動車からの排出量規制対策の限界を指摘するとともに、局所的な高濃度汚染の発生、環境基準達成が困難であることを予測し、早急な対策の検討の必要性を指摘する | ||||||||||
| 平成2年8月 | 環境庁は、国の閣議決定要綱に基づく環境アセスメント制度により、東京都の地下首都高速道路建設計画(中央環状新宿線:青葉台-南長崎、8.7km)について、建設省に対して脱硝装置を設置するよう意見書を提出する | ||||||||||
| 平成4~6年度 | 上記意見を受ける形で、(財)先端建設技術センターが公募し、民間企業6社・グループによる脱硝装置の自主実験(フィールド実験)が行われる(場所:首都高速道路湾岸線東京港トンネルの大井換気所及び13号換気所) | ||||||||||
| 平成6年5月 | フィールド実験の検討成果を中間報告としてとりまとめる 技術開発の課題として下記を指摘する |
||||||||||
|
|||||||||||
| 平成9~11年 | 建設省、日本道路公団、首都高速道路公団、阪神高速道路公団によりパイロットスケール実験が行われる(場所:首都高速道路湾岸線空港北トンネルの京浜島換気所) | ||||||||||
| 平成11年8月 | 建設省がパイロットスケール実験に続く新たな実験計画を公募 | ||||||||||
[2]トンネル脱硝技術の検討過程に見る“実行可能なより良い技術”の検討の考え方
───技術の抽出・評価・選定というプロセスが考えられる───
これまで行われてきた低濃度脱硝技術の実証実験を参考とすると、“実行可能なより良い技術”の検討にあたっては、まず技術面から
“より良い技術”を抽出し、次にこれらを実行可能性の面から検討して、“実行可能なより良い技術”として選定していく検討プロセスが考えられる。(図表-16 参照)
その検討対象となる技術の技術革新の進展は早いのが特徴であり、より広範に技術を収集・評価することが必要である。
なお、トンネル脱硝技術の検討過程には見られないが、今後は諸外国の例に見られるように、住民等やNGO等の関係者に広く公開された検討を進める必要がある。
───光触媒方式、土壌浄化方式などの新技術も具体化されつつある───
また近年、従来のトンネル脱硝技術である機械式に加えて、光触媒方式、土壌浄化方式なども導入され始めようとしており、これら新しい技術も含めた“実行可能なより良い技術”の具体化が求められる。(図表-17 参照)
このように検討すべき技術の範囲は、必ずしも当初想定した範囲に限られるものではないことに留意する必要がある。
図表-16 トンネル脱硝技術の検討の流れ
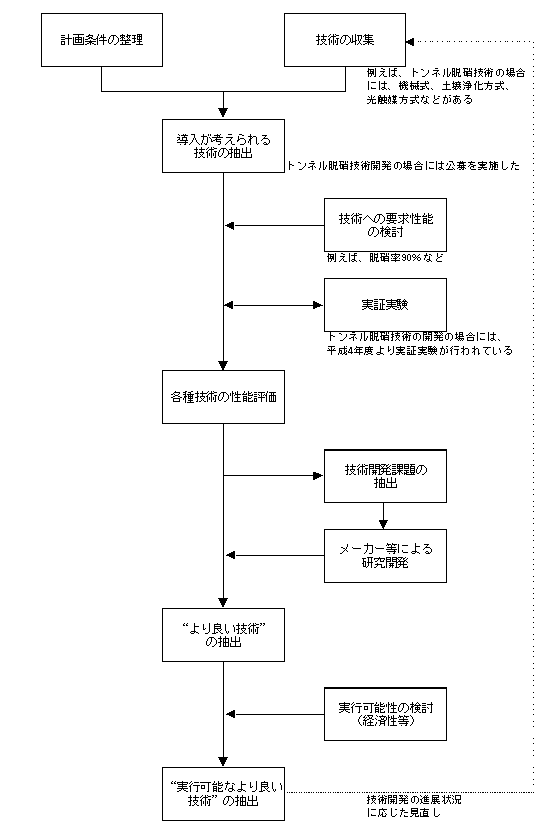
図表-17 窒素酸化物対策
方式 |
概要 |
||||||||||||||
| 機械式 |
|
||||||||||||||
| 光触媒方式 |
|
||||||||||||||
| 土壌浄化方式 |
|
||||||||||||||
図表 システムの概要
|
|||||||||||||||
─事業特性や地域特性に応じてケースバイケースで“実行可能なより良い技術”を検討─
道路トンネルは、その総延長、地理的位置、換気方式、交通量、通行する車両特性等の事業特性や気象、地形等の地域特性により形状は大きく異なる。例えば、道路トンネルでの換気方式は、地域特性、トンネルの延長、走行車両の特性に応じて多様な形態が考案・選択されている。(図表-18 参照)
このため“実行可能なより良い技術”の導入を行うにあたっては、これらの特性に応じてケースバイケースで行う必要がある。
図表-18 道路トンネルでの換気方式
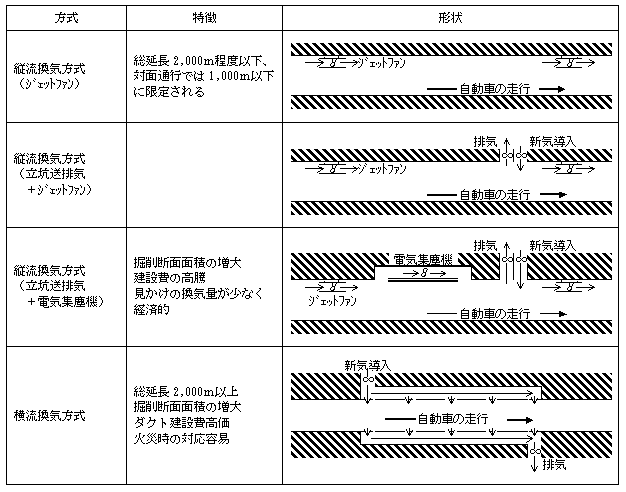
───ライフサイクル全体から見た経済性の検討を行った事例───
“より良い技術”が複数選定された後には、実行可能性を検討することとなる。
下表は、製鉄所や発電所に採用されてきた排煙脱硫装置の技術を応用した低濃度トンネル脱硝装置のプロトタイプを経済性の面から比較した例である。“実行可能なより良い技術”の検討にあたっては、このような特定の目標を達成するために導入が考えられる“より良い技術”を多数抽出し、経済性をはじめとする実行可能性からの比較も加味して導入が可能と見込める“実行可能なより良い技術”を絞り込む検討プロセスが考えられる。(図表-19 参照)
なお、これからの環境影響評価では、より良い技術の経済性検討にあたって、初期投資をはじめとして、消耗品に要する費用、維持管理費用やエネルギー費用に加えて廃棄物処理等の廃棄段階の費用も含める等、ライフサイクルから捉えることも必要である。
図表-19 トンネル脱硝装置の経済性比較の試算例(平成3年)
(処理規模:30万m3/h)
項目 |
乾式吸着- 活性炭 |
乾式吸着 -活性炭 |
乾式吸収法 | 乾式吸着 -分解法 |
電子線 照射法 |
|
| 概要 | 活性炭処理したゼオライトで吸着濃縮してアンモニア脱硝法で還元する | 活性炭で酸化吸着し、周期的に脱着・濃縮して触媒接触還元反応により分解する | 亜塩素酸塩あるいはカリ塩・粉末活性炭をセメント剤でハニカム成型したものに吸着させ還元または分解する | ゼオライト系吸着剤で濃縮してゼオライト系触媒で熱分解する | アンモニアを添加して電子線を照射し、固体粉末や硝酸ミストにして電気集塵機で補集 | |
| 電力(千kWh | 3.6 | 1.2 | 0.9 | 8.8 | 2.1 | |
| 運転費 (千円/h) |
電力費 吸着・吸収剤 その他消耗品排水産廃処理 |
54 |
18 |
13.5 148 7.8 3.7 |
131.94 未検討 未検討 未検討 |
30.75 27 8.4 1.6 |
| 合計 | 136.1 | ─── | 173 | ─── | 67.75 | |
| 設備 | 設備費 | 100億円程度 以下 | 不明 | |||
| 容積 | 7万m | 2万m3 | 39,200m3 | 117,000m3 | 100,485m3 | |
| 寸法 (L×W×H m) |
40×70×25 | 50×50×8 | 50×56×14 | 130×60×15 | 87×55×21 | |
出典:内藤「自動車排ガス対策としての道路トンネル換気ガス脱硫装置の実用化動向」(公害と対策)、平成3年 |
───安全性、技術の信頼性などより多面的な視点からの検討を行った事例───
東京都中野区がJR中野駅北口に予定している地下駐車場計画では、平成5~6年度にかけて排気システムに関する検討会を設け導入すべき技術の検討を行っている。そこでは、トンネル内の排気システムを評価するにあたって、環境保全上の性能や技術の信頼性、安全性などの技術的要因、省エネルギーなどの環境的要因などから比較評価している。(図表-20 参照)
このようなケースからは、これからの環境影響評価では、技術そのものの評価に加えて技術を取り巻く社会的な条件、例えば、安全性、保守・運転の容易さ等を加味したより多面的な視点からの検討を行うことも考えられる。
なお、これら様々な視点を取り入れるに際して、その妥当性や技術の環境保全に関する性能との関係について十分に検討し、客観的に整理する必要がある。
図表-20 排気システムの評価項目