“実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き
4 “実行可能なより良い技術”の導入方法
1)全体の検討への反映
《ポイント》
|
環境影響評価と“実行可能なより良い技術”との関わりを考えると、環境影響の「評価」及び環境保全措置の検討の局面で “実行可能なより良い技術”の観点からの検討が必要と考えられるが、その検討のためには方法書検討の段階や事後の段階での対応も重要である。
図表- 3 環境影響評価と“実行可能なより良い技術”との関わり
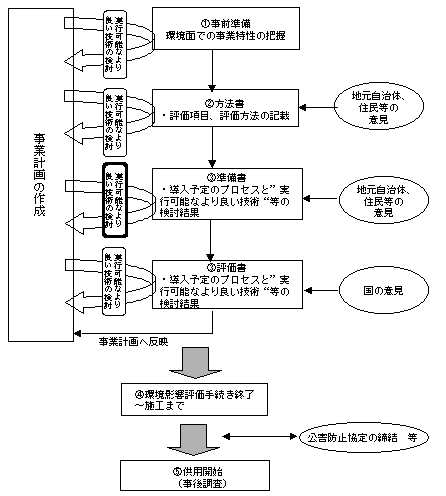
(注)それぞれの段階における“実行可能なより良い技術”の検討手順は、次項に示す。
[1]事前の段階
事業全体の環境影響の回避・低減を行うには、事業工程の出口対策等にとどまらず、事業の全工程において環境影響を評価・検討することが非常に有効である。
しかし、事業計画の熟度がある程度高まった準備書等の段階で事業計画の根幹を変更することは、事業計画の大幅な見直しが必要となって事業を進める上での負担が大きい。
従って事業者には、環境影響評価に着手する以前の事業計画を検討する段階であらかじめ“実行可能なより良い技術”の考え方を取り入れ、地元の地方公共団体等との意見交換等を行いながら地域の特性を取り入れた効果的な環境保全対策を計画に組み込むことが必要である。
[2]方法書の段階
方法書は地域住民等に対して事業計画を最初に公表する書類であることが多い。方法書の中で“実行可能なより良い技術”の観点からの検討の考え方やここまでの経緯等を示すことは、地方公共団体や地域住民に対して情報の透明性を担保し説明力を高めるとともに、この検討の方法の妥当性について早い段階で意見交換を行うことが可能となる。
また、検討の考え方等のみならず、具体的な導入案をこの段階で示すことも有効である。特に計画熟度の低い段階で定まるものについてはこのような対応が可能であり、定まっていないものでもこの段階での複数の導入候補案や具体的な方向性は示すことが可能である。これは事業者の手戻りやさらなる費用負担を避けるために、また報告の公開の観点からも必要である。
従って事業者は、方法書において“実行可能なより良い技術”の観点からの検討の考え方やここまでの経緯、具体的導入案を明記することが必要である。反面、この段階で示されない導入案は準備書や評価書以降の段階でも柔軟に変更が可能になるものに限られることになる。
[3]準備書及び評価書の段階
準備書及び評価書の段階で“実行可能なより良い技術”の観点からの検討について記載するということは、まさに評価と環境保全措置の検討について記載することに他ならず、ここでの検討が“実行可能なより良い技術の導入についての評価”の中心となる。
従って、事業者は環境影響の評価及び環境保全措置の検討において、“実行可能なより良い技術”に関して行った検討の経緯(上記[1]及び[2]における検討を含む)、検討手順、具体的な検討方法、検討対象となった技術、採用しようとしている技術とその理由、評価書公告後に計画熟度が上がり更なる検討が必要となる場合等の方針や考え方(下記[4]、[5]に係る方針)等について、準備書及び評価書に明記することが必要である。
なお、この段階の詳細な手順については2)“実行可能なより良い技術”の検討手順 に記載する。
[4]環境影響評価手続終了後から施工までの段階
環境影響評価の実施段階に不明確だった点が明らかになったり、計画熟度が上がることなどにより、環境保全対策の検討が可能になることがある。また
“より良い技術”も科学技術の進展により変化するものである。
このため、特に環境影響評価手続の終了後から施工までの期間が長い事業においては、環境保全対策の詳細について施工の段階で改めて整理する必要がある。
なお、このような検討については予めその方針を評価書に記載しておくことが求められる。
[5]供用開始後の段階
環境影響評価書に記された事後調査の実施や供用に関する事業者と地元の地方公共団体、住民との間に締結される環境保全協定等により、供用後も事業者は環境影響のさらなる回避・低減に努めることになる。このとき事業者には供用後も“より良い技術”の導入可能性の検討等を行うことが望まれる。
なお、このような検討については予めその方針を評価書に記載しておくことが望まれる。
2)“実行可能なより良い技術”の検討手順
“実行可能なより良い技術”の検討は事前から供用開始後まで全ての段階を対象とするが、この中で最も重要な検討段階となるのは実際に事業者として事業についての評価を公表する準備書の作成段階であるといえる。
実行可能なより良い技術の具体的な検討方法については、基本的な検討手順として図表―4の流れが考えられる。この流れは図表―3に示したフロー図における準備書~評価書段階での「実行可能なより良い技術の検討」に対応するものである。なお、検討手順の流れは事前調整の段階も含め環境影響評価の全ての段階に概ね共通であるが、手続の内容に応じて若干の修正が必要である。
図表- 4 “実行可能なより良い技術”の基本的な検討手順
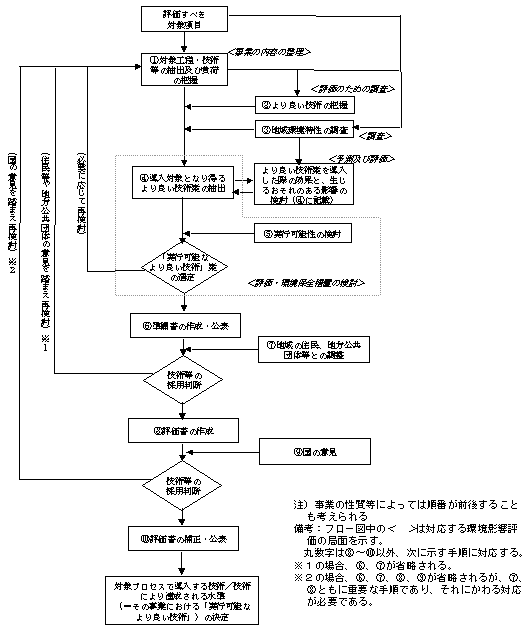
手順1:対象とする工程とその技術の抽出及びそれぞれに関する環境負荷の把握
<事業の内容の整理(一部予測)>
| ● | 事業全体の工程を明らかにし、その中で着目する環境要素に関して影響を及ぼす工程を抽出する。ここでいう「工程」には発電所における燃焼方式等のまさに事業工程そのもののや排ガス、排水対策といった出口(end-of?pipe)に関する工程、土木工事における工法や工事工程、さらに設備面だけではなく管理・運用に関する局面等、幅広く様々なものを含む。 |
| ● | 抽出した工程における環境負荷の量を把握し、事業全体の工程との関係を踏まえ、優先すべきものを明らかにしながら対策技術を想定する。 |
|
||||||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 言うまでもなく、環境影響評価法の対象は、環境基本法で言うところの環境全般であるから、既存の法規制の対象に限らず、環境への影響を被ると考えられる環境要素全般についても検討対象となる。例えば、大気汚染防止分野であれば、温暖化物質や内分泌攪乱物質等が考えられる。 |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 環境影響を及ぼす工程は、排ガス、排水対策といった出口に関する工程だけではなく、事業工程そのものにも含まれる。従って、“実行可能なより良い技術”は事業工程全体を広く捉えて検討することが必要である。 |
| (例) | |
| ・ | EUやオランダでは、対象産業別にBREF(BAT参照文書)等の文書を作成し、対象となる設備・工程を幅広く示している(→欧米の事例1)、4)) |
| ポイント[3]; | |
| ・ | 1つの工程を変更することによる他の工程への影響や、1つの環境要素の保全対策による他の環境要素への影響など、1工程、1環境要素のみに着目すると副次的な影響を見落とす可能性がある。従って、対象とする工程とその技術の抽出は、工程毎の検討と同時に事業全体の像を意識して行う必要がある。 |
| ポイント[4]; | |
| ・ | 環境影響評価法においては、事業計画の変更に伴い再手続となることがある。評価書の公告前であれば環境保全措置のための変更は可能となっているが、特に評価書公告以降の場合は変更がありうる工程に関する変更の手続について事前に把握しておくこと。 |
| ・ | 事業計画の変更に関する手続については、方法書以降評価書の公告までの段階に関しては環境影響評価法施行令第9条、評価書の公告以降着手までの段階については同第13条に記されている。 |
・手順2:より良い技術の把握 <評価のための調査※>
| ● | 当該事業で対策が必要となる技術・プロセス等についてのより良い技術の情報を幅広く把握する。 |
| ● | 技術情報の具体的な収集方法として、下記の方法が考えられる。 |
| ・ | 過去の同種事業や同様な環境負荷を生じる事業、同種の工程を持つ事業の環境影響評価書等(条例等に基づくものや手続中、手続準備中のものや手続中、手続準備中のものも含む) |
| ・ | 現在進行中の同種の事業に関する技術の採用状況等の事例調査 |
| ・ | 業界団体等を通じての技術情報の交換 |
| ・ | 学術文献調査、専門家ヒアリング |
| ・ | メーカー等関係者ヒアリング |
| ・ | 地方公共団体ヒアリング |
|
||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 手順1で示したように、環境負荷の回避・低減には、従来重視された出口管理の技術だけではなく事業全体の工程を対象として検討することが重要である。従って技術の情報についても、出口における環境管理技術だけに特定せず、全ての工程に係る技術や、操業等の運用管理の面の技術についても対象として幅広く把握することが必要である。 |
| ・ | また、技術情報の収集範囲は、国内の同種の工程をもつ事業を中心としながらも、国外や異種の事業等にも幅広く目を向ける必要がある。 |
| ・ | さらに、これらの情報収集を効果的に行うため、業界団体を活用することや行政の協力を得ることも望ましい。 |
| (例) | |
| ・ | 我が国の各電力会社においては、電気事業者連合会を通じて発電所の技術に関する技術交流を行ってきた |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 大規模事業等においては、環境影響評価を行ってから事業開始までが長期にわたるため、その間に技術が進歩することがある。また、環境影響評価の実施段階では実証実験中や研究開発中の技術であっても、事業開始時期までには実用化される可能性がある。従って、施工段階で、改めて最新技術の導入を検討することも視野において、広く技術情報を収集し、環境影響評価を実施することが必要である。 |
| (例) | |
| ・ | 道路の脱硝装置に係る技術開発はある事業への環境庁長官意見を契機に始まり、その事業の着工の段階では様々な方式が具体化されている(→道路事業におけるトンネル脱硝での事例) |
※評価のための調査: |
通常の調査は地域の特性を把握することを目的とするが、評価における回避・低減の程度を客観的に把握するために、評価や環境保全措置の検討に先立ち予め判断の材料となるべき条件等を調査することが時として必要である。そのような調査を、ここでは「評価のための調査」と表記している。 なお、この調査の結果等の準備書・評価書における記載については、各項目毎の調査の項か、もしくは環境保全措置の項に記載することとなる。 |
手順3:地域環境特性の調査 <調査>
| ● | 事業を計画する地域の環境特性について把握する。重点を置くべき調査項目を以下に示す。 |
| ・ | 評価項目(例:「道路の供用により生じるNOx」)に関する環境要素(例の場合、NOx)について、地域の現況 |
| ・ | 評価項目に関する環境影響の回避・低減と強く関連する環境要素(例の場合、SPMなど)について地域の現況 |
| ・ | 評価項目に関する環境要素について、保全対策をとった場合に影響の生じるおそれのある環境要素について地域の現況 |
| ・ | 事業地を含む地域における、同様な事業や同様な負荷を発生する発生源の分布と状況(導入されている技術や環境負荷の削減目標等も含む) |
| ・ | 事業地とその周辺に存在する被影響対象の分布と状況(例えば、希少な動植物や病院、学校など) |
| ・ | 環境影響の予測や、実行可能なより良い技術の効果を検討する上で重要な環境要素の状況(例えば、地形や気象等) |
| ● | 地域環境計画等を参照し、地域環境に関する政策的目標を把握する。 |
|
||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 技術の特性により、その技術が最も効果を発揮する条件があり、それゆえ地域の条件に応じて、最も適当な技術は異なる。また、地域の環境や社会の要求により、求められる環境のレベルは異なり、従って導入すべき技術の性能にも差が生じる。よって、これらを踏まえた技術の選定が重要であり、それを客観的に検討するために必要なデータを入手することが調査に求められる。 |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 地域住民の求める地域環境の将来像は、通常地域環境計画等にとりまとめられているが、このような行政文書のみならず、地域住民の生の声を聞くことや、紛争事例を把握すること、また地域環境保全の長期的経緯等を把握すること等により、地域で求められる技術について幅広く検討すること。 |
手順4:導入対象となりうる「より良い技術」案の選定 <予測及び評価>
| ● | 導入対象となりうる「より良い技術」の導入が事業全体として環境影響の回避・低減に極力努めたものとなりうるか、その環境保全上の性能・効果について検証し、順位付けを行う。<評価> |
| ● | その検証に際し、事業の実施による地域の環境変化をできるだけ定量的に予測するとともに、“実行可能なより良い技術”の導入の結果として、地域の環境の状況変化がどの程度抑えられるか予測する。<予測> |
| ● | 地域の環境基本計画や地域環境管理計画といった地域の計画等を満たしているか否かについても確認する。<評価> |
|
||||||||||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 検討の必要上、各工程毎の検討を行うものの、評価は全体として行われるものであり、事業の影響、対策のそれぞれの全体像に留意しつつ検討してとりまとめる。 |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 事業の特性のみならず、地域の特性が技術選定において最も重要なファクターの1つである。これは、実行可能なより良い技術の選定だけでなく、環境影響評価全てにおいて一貫している。 |
| ・ | 米国における大気汚染防止分野では、地域の環境基準達成状況に応じて、異なる排出目標を設定している(→欧米の事例5)) |
| ポイント[3]; | |
| ・ | まずコストなどの実行可能性を考えずに、性能効果の面からの検討を優先して行うことによって「より良い技術」の抽出もれなく行うことができる。 |
| ポイント[4]; | |
| ・ | 環境影響評価の予測手法選定においては、基本的にはその時点で最新の技術を用い、最も確かな結果をできる限り定量的に導き出す手法を選定することが必要であり、この原則は実行可能なより良い技術の選定の際にも変わらない。しかし、その一方で、予測には常に不確実性があることに留意し、記述にあたっては不確実性を明らかにし、またパラメーター等についても予め明らかにする必要がある。これらの点の他、予測に関する一般的留意事項は全てこの手順4に当てはまるので留意すること。 |
| (例) | |
| ・ | 予測における留意点は、環境庁 大気・水・環境負荷分野の環境影響評価技術検討会中間報告書(平成11年度)に整理されている |
| ポイント[5]; | |
| それぞれの技術の性能やそれに関する予測の結果から、その技術の導入による効果を検討し、達成可能な定量的目標を明らかにして比較する。準備書として公開し意見を聞くことを考えると、性能だけを表記するのではなく導入の効果を明確にすることがわかりやすく重要である。 | |
| (例) | |
| ・ | イギリスにおけるBATNEECにおいては、許可手続の際に個別の事業ごとに目標排出基準を設ける(→欧米の事例2)) |
| ポイント[6]; | |
| ・ | 実行可能なより良い技術の導入効果を検討する時期については、環境影響の最も大きな時点やいわゆる定常期について予測する、あるいはライフサイクル全体を予測するなどの考え方があり、環境要素や環境影響の特性、最終的な評価のあり方を念頭に置きながら、最も適した時点・手法を検討する必要がある。 |
手順5:実行可能性の検討 <評価>
| ● | “実行可能なより良い技術”の定義を基に、事業全体に着目し、検討している環境要素以外の要素との関係を踏まえながら、「より良い技術」が採用可能であるかを検討する。(3、1)に示した定義を参照) |
| 要素例; | |
| ○ | 科学的知見 |
| ○ | 施工性 |
| ○ | 経済性 |
| ○ | その他 |
| ―安全性 | |
| ―保守・運転管理の容易さ など | |
|
||||||||||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 必ずしも、コスト面等で実行できないことを理由により良い技術を採用しないでよいのではなく、あくまで環境面での必要性と実行可能性との関係で客観的な検討を行うことが必要である。 |
| (例) | |
| ・ | 米国における大気汚染防止分野では、事業所の特性に応じて排出基準が設定されている。具体的には、大規模な事業所に関しては、小規模な事業所に比べて厳しい水準が排出基準として適用されている(→欧米の事例5)) |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 環境影響評価の対象事業は、着工まで長い時間を必要とする。それゆえ、その時間を利用することにより、現在実現が不可能な環境保全対策について、実行可能なものとすることができる。よって、環境影響評価の上でも、将来を見越した環境保全対策が必要である。 |
| (例) | |
| ・ | 道路の脱硝装置に係る技術開発はある事業への環境庁長官意見を契機に始まり、その事業の着工の段階では様々な方式が具体化されている(→道路事業におけるトンネル脱硝での事例) |
| ポイント[3]; | |
| ・ | 施工性の観点から実行不可能とは、事業及び地域の特性から技術的に実行不可能なことを言う。一般的には実行可能でありながら特定の要件が課題となることから、この課題については、より客観的な説明が必要となるとともに、それを理由とすることは限定的に行われる必要がある。 |
| ポイント[4]; | |
| ・ | まず考えるべき条件は、地域環境保全のための諸条件であり、経済性については、これらが検討された後に検討されるべきものである。経済性は、地域の特性や地域の求める環境保全の達成目標、さらには排出物質の有害性等により相対的に検討されるものであり、必ずしも一定の基準が存在するのではない。また、経済性については、事業のライフサイクル全体で考えることが必要である。 |
| (例) | |
| ・ | イギリスでは、技術を評価する際に、「過大なコスト負担なく(Not entailing excessive cost)」という評価の考え方が示されているが、これはコストと環境面での必要性とのバランスの考え方を含んでいる(→欧米の事例2)) |
| ポイント[5]; | |
| 科学的知見、施工性、経済性の他に安全性や保守・運転管理の容易さなどが検討された例がある。実行可能性を規定する要素は限定されるものではないが、それを環境影響の回避、低減より優先させることの妥当性については十分な客観的説明が必要である。 | |
| (例) | |
| ・ | 地下駐車場設置に関する検討では、排気システムの評価項目として、性能、技術の信頼性、安全性、保守・運転といった技術的要因、省エネルギー、窒素酸化物等といった環境的要因を挙げている(→中野駅北口広場地下駐車場における排気システムでの事例) |
| ポイント[6]; | |
| ・ | 環境要素によっては1つの環境要素の環境影響を回避・低減することにより、他の環境要素への環境影響が大きくなることがあり得る(例えば、燃焼によるNOxと廃棄物となる未燃分のそれぞれの排出量の関係等)。従って、地域環境特性を十分に考慮し、事業の影響を受ける他の環境要素との関係を踏まえて、優先すべき環境要素を検討し、また、事業による環境影響を全体として回避・低減するような技術の導入を検討することが必要である。 |
手順6:準備書への記載
| ● | “実行可能なより良い技術”の検討方法、検討内容、検討結果について、「調査」「予測」「評価」及び「環境保全のための措置」の項目として準備書に記載する。記載内容としては、下記の事項が考えられる。 |
| (記載内容例と考えられる記載の場([ ]内)) | |
| ―検討対象とする項目と検討手順(フロー図等)[項目・手法] | |
| ―対象とする工程とその技術の抽出及び環境負荷の把握[事業の内容、予測] | |
| ―より良い技術の把握方法及び把握結果[環境保全措置] | |
| ―環境特性の把握方法及び把握結果[調査] | |
| ―「より良い技術」案について、その性能、効果についての検討方法及び検討結果[予測] | |
| ―「より良い技術」案について、その検討の考え方、結果、経緯、選択した理由[評価] | |
| ―実行可能性の検討の考え方、検討方法、検討結果[評価] | |
| ―長期的な環境保全措置、今後の検討方針(評価書公告後に計画熟度が上がる場合の方針や考え方等)[環境保全措置、事後調査] | |
| ● | 記載の仕方については、法等の規定に則って個別の項目について記載する。この際“実行可能なより良い技術”の導入の趣旨がわかりやすく記載されていることが重要である。 |
|
||||||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | これまでの環境影響評価制度においては、導入技術や達成水準等に関する設定根拠が明確に示されていなかった。新たな環境影響評価制度では、事業者と住民等、地方公共団体、国とのコミュニケーションが重要であることから、事業者には、事前段階での実行可能なより良い技術導入に関する検討経緯、方法書作成過程での検討経緯、方法書に対する地方公共団体や住民から出された意見及び意見が準備書にどのように反映されたか等に関して客観的な情報を提供することが求められる。 |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 実行可能なより良い技術とされたものが妥当かどうかについては、客観的に説明されなければならない。そのため、例として上に示したような記載内容について具体的かつ客観的に記載する必要がある。 |
| ・ | 特に技術等に関しては記載が専門的になるが、準備書の読み手となる全ての対象にとって理解しやすい記載とすることが重要である。 |
| ポイント[3]; | |
| ・ | 実行可能かどうかの事業者の判断についても、住民等に対してその考え方等を明らかに示し、コミュニケーションを行う必要がある。特に、実行可能な範囲や限界について事業者の考え方を明確に示す必要がある。 |
| ポイント[4]; | |
| ・ | 環境影響評価実施段階には計画熟度が高まっておらず、環境保全対策の検討詳細が行えない項目については、環境影響評価手続終了後に改めて環境保全措置等の検討を行うこととなる。事業者は、このような項目について事前に明らかにし、その対応方針について地方公共団体や住民等に示しておくことが必要である。 |
手順7:住民等、地方公共団体等とのコミュニケーション
| ● | 準備書に対する地方公共団体や住民等の意見及び住民説明会や公聴会・審議会等での意見を尊重し、計画に反映させる。 |
| ● | 住民や地方公共団体から出された意見が“実行可能なより良い技術”に関連し、これを見直すことによってより適切な技術を導入できる可能性がある場合には、改めて“実行可能なより良い技術”を検討する。 |
|
||||||
| 《解説》 | |
ポイント[1]; |
|
| ・ | 事業が社会的に認知され、円滑な事業開始や供用を行うためには、住民や地方公共団体等、地域に受け入れられることが重要であり、そのためには、できるだけ早い段階から関係者とコミュニケーションすることが必要である。 |
| ・ | また、環境影響評価の開始後に大幅な事業変更となる事態を避けるという観点からも、早い段階からのコミュニケーションが重要である。 |
| ・ | 必ずしも環境影響評価法や条例において手続として定められているものだけでなく、任意の説明会、ヒアリングやアンケート等を活用しながら、住民や地方公共団体等と濃密なコミュニケーションを行うこと。 |
| ポイント[2]; | |
| ・ | 環境影響評価は事業計画に環境配慮を組み込んでいく過程を広く公開するしくみであるともいえる。よって、様々な主体の意見と事業者の見解については公開が必要である。 |
| (例([1][2]共通)) | |
| ・ | 東京都では、事業者の環境負荷低減制度の中で、都の指導が位置づけられている(→国内事例1)) |
| ・ | イギリスでは、許認可の手続において公衆からの意見が目標排出基準の決定に考慮されている(→欧米の事例2)) |
| ・ | ドイツでは、許認可手続において地方の主務省庁が(排出基準よりも厳しい)技術水準の適用を事業者に求めるとともに、技術水準の決定に際し、住民や産業界の意見を聞くこととされている(→欧米の事例3)) |
| ・ | オランダでは、住民が企業や行政の判断に対して、訴訟を起こすことが可能となっている(→欧米の事例4)) |
| ・ | アメリカでは、排出基準は産業界、州政府、住民及びその他の利害関係者からの意見聴取を行うことによる「インフォーマル・ルールメーキング」の手続によって決定される(→欧米の事例5)) |