“実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き
3 “実行可能なより良い技術”の考え方
1)“実行可能なより良い技術”の意味
本章では、2、2)で位置づけられている“実行可能なより良い技術”をより具体的に理解するため、環境影響評価法についての従来からの議論も踏まえ、また諸外国における定義を踏まえながら、環境影響評価における下記の用語の定義を行った。
なお、水質保全や大気保全等の分野においても、近年実行可能なより良い技術導入に関する検討がなされているが、ここでの定義はこの報告書に限定したものであり、他分野においては別途に検討されるべきものである。
「実行可能な」: |
|
| ・ | 事業者にとって実行可能な範囲とは、事業の目的や効果との関係性、環境保全措置の効果の程度、他の環境影響評価項目への影響の程度や事業者の責任の及ぶ範囲を踏まえながら、総合的に検討されるものと考えられる。ある意味で、回避・低減に関する評価とは、この「実行可能」性を事業者の努力によってどこまで広げられるか、それが環境保全上十分であるかどうかを評価するものであるとも言える。 |
| ・ | 基本的事項の策定の際の議論においては、「実行可能な」とは、事業者にとって科学的知見、施工性、経済性等の観点から実行可能であることを指すとされている。なお、諸外国では主に「科学的、技術的な側面」から実行可能性が優先的に検討されるとともに、さらに経済性についても検討が加えられる場合が多い。 |
| ・ | 科学的知見の面から実行可能であることとは、すでに実用段階にあるか若しくは施工時点など近い将来実用化される見通しであることを指し、施工性の面から実行不可能であることととは、科学的知見の観点から実行可能であるが、個別事業ごとの特性や地域の特性により技術的に適用が不可能であることを指す。 施工性の観点から個別の事業で実行不可能であっても一般的には実行可能であるといえることから、実行不可能とする理由については十分な吟味とその改善のための努力も問われるところである。従って施工性の面から実行不可能と述べることは限定的に行われるべきであり(例えば「用地がない」等は理由とならない。)、客観的な説明もより必要となる。 |
| ・ | 経済性の面から実行可能であることとは、環境保全対策の必要性や地域特性などを鑑み、その技術を適用することが過大な費用負担を必要としないことを指すが、例えば、有害な排出物を排出する際に、通常より高額の対策が必要になるのは当然であり、「過大」であるかどうかは、その対策の必要性によって相対的かつ個別に定まるものである。事業者の持つ「予算」や事業の採算性に規定されるものではない。 |
「より良い」: |
|
| 高水準な環境保全を達成するために最も効果的なことを指す。ただし、必ずしも最善の1つとは限らず、ある程度の幅を持つ一定の水準を指す。 この「幅」や「一定の水準」は事業の行われる地域の特性によって変わりうる。地域特性により求められるレベルが高ければ、最善の1つに限ることもある。 |
|
「技術」: |
|
| ここでいう技術とは、事業の計画、設計、建設、維持、操業、運用、管理、廃棄に際して用いられた幅広い技術、つまりハード面の「テクノロジー(technology=科学技術・工業技術)」及び運用管理等のソフトの面の「テクニック(technique=技法・手法)」を指す。なお、技術に関して設計から廃棄までの広範囲でとらえているのは、環境影響評価における評価が事業に係る建設や存在・供用の結果としてもたらされる環境影響を対象としているものの、これを回避・低減するためにはより広い範囲での対策が必要なためである。 | |
「より良い技術」: |
|
| 高水準な環境保全を達成するのに最も効果的な技術を指す。必ずしも最善の1つの技術とは限らず、最善の水準に達した技術群を指す。 「より良い技術」から「実行可能な」技術を選ぶのであり、「実行可能な技術」から「より良い」技術を選ぶのではない。環境保全の面からできるだけ優れた技術を幅広い範囲から選ぶことが重要である。 |
|
2)“実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討”の意味
環境影響評価においては、事業者は環境影響の回避・低減に係る評価及び環境保全措置の検討を行うにあたって、複数の案の比較検討や実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討等を実施し、事業者の考えの妥当性を検証しなければならない。
この際に求められることは客観的で定量的な評価・検討であり、実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討は、特に設備や工法に関する技術に大きく依存するケースについて有効な評価手法となると考えられる。
実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かは、事業全体で評価されるものである。しかし、実際には、まず事業内容を各工程に分解し、工程毎の環境負荷物質の発生状況を把握して対策を検討する。その上でこの分解された各工程の環境負荷と対策を整理し、優先するべきものを明らかにしつつ事業計画全体を見直す。そして全工程から発生する環境負荷が全体として可能な限り回避・低減されているかどうかを検討することとなる。
例えば、火力発電所の場合、窒素酸化物排出にあたっての回避・低減対策には下図の燃料対策、燃焼方法の改善および排ガス対策、そして運用対策が挙げられるが、燃焼方法の改善と排ガス対策は一体として検討されるものであり、出口(end-of-pipe)対策である排ガス対策のみの検討では不十分である。また、燃焼方法は、燃料によって左右されるものであり、施設により運用対策も決まることから、全体を見渡した検討が必要である。
図表-2 環境影響の回避・低減検討の検討段階
(火力発電所におけるNOx排出に係るプロセス例)
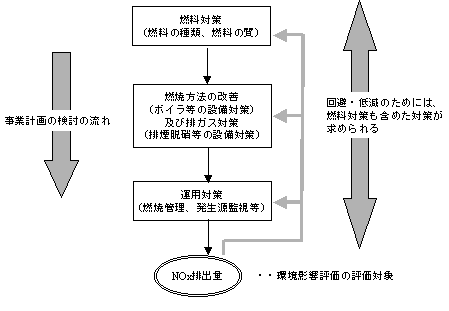
具体的な検討としては、導入しようとする技術とその類似技術についての開発状況などを調査し、地域の環境特性や事業の特性を踏まえながら、技術的に環境保全の面から最も優れた性能を持つ技術(複数の場合もある)を選ぶ。そして、科学的知見の観点等からその技術の実行可能性を検討し、住民等や地方公共団体等の意見を聞いてこれらの検討の妥当性を検証することになる。
これらの検討のプロセスは従来からも一部の事業で行われてきたが、その内容は一般にほとんど公開されなかった。「実行可能なより良い技術が取り入れられているか否かの検討」とは、この技術選定のプロセス(過去の経緯を含む)と技術の導入効果、そしてそれらに対する事業者の考え方を明らかにすることで客観的な評価を行うものである。