“実行可能なより良い技術”の検討による評価手法の手引き
2 “実行可能なより良い技術”の導入目的
1)環境影響評価制度への“実行可能なより良い技術”の考え方の導入経緯
従来の環境影響評価制度(閣議アセス等)は、環境基準等を環境保全のための目標として設定し、この目標を達成するか否かという点を重視して評価しており、いわば「目標クリア型」の環境影響評価であった。この方法では、評価の視点が固定的な基準や目標の達成に限定され、対象地域の実情を鑑みてより一層の環境配慮を追求していくための取り組みが不十分であること、また、自然環境などの分野では明確な基準を設定しにくい項目があること、等の問題が指摘されてきた。
そこで、環境影響評価法では環境影響の緩和、いわゆるミティゲーションの考え方を導入し、環境基準等の達成だけでなく、環境影響を実行可能な範囲で回避・低減しているか否かについて事業者自らの見解をとりまとめることによって評価を行う、いわば「ベスト追求型」の評価を導入することとした。この際、事業者の実行可能な範囲で環境影響を回避・低減しているか否かを評価する際に用いられる手法として例示されたもののひとつが、「実行可能なより良い技術が導入されているか否かを検討する」(以下、「実行可能なより良い技術の導入についての評価」とする。)という手法である。
図表- 1 評価の考え方の変化
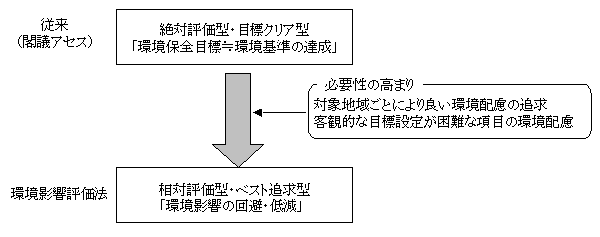
| 技術指針等に係る基本的事項における“実行可能なより良い技術”に関する記載 環境影響評価法の技術指針等に係る基本的事項の中では、“実行可能なより良い技術”は以下のように定められている。 第二 環境影響評価項目等選定指針に関する基本的事項 五 調査、予測及び評価の手法の選定に関する事項 (3) 評価の手法の選定にあたっての留意事項 ア 環境影響の回避・低減に係る評価
第三 環境保全措置指針に係る基本的事項 二 環境保全措置の検討にあたっての留意事項
|
2)“実行可能なより良い技術”の導入の目的とメリット
事業実施にあたって“実行可能なより良い技術”の考え方の導入の主な目的を以下に示す。
“実行可能なより良い技術”を事業実施にあたって検討することは、技術指針に定められた手続としてだけでなく、事業者にとってメリットがあると考えられる。
|
【理由】 |
「環境影響の回避・低減に係る評価」の手法として、最もわかりやすく望ましい手法は複数案の比較検討である。しかし、必ずしも全ての評価でこの手法を採用できるとは限らず、また効果的でない場合(例えば技術的に優劣が明確な場合など)も多い。このように複数案の比較検討ができない場合、従来は定性的な評価が行われ、ともすれば事業者による主観的な評価となっていた。今後の環境影響評価においては、より客観的な評価が重視されることから、このような場合には実行可能なより良い技術の導入についての評価が有効である。 |
|
【理由】 |
環境影響評価法においては事業者と環境保全の見地からの意見を有する者(以下「住民等」)、地方公共団体、国とのコミュニケーションが重要である。特に評価については回避・低減に係る評価となったことから、事業者はその評価の内容を客観的に説明することが必要である。また、そのためには、実行可能なより良い技術の導入についての評価、その経緯及び想定される効果等の明記が有効となる。 |
|
【理由】 |
事業計画は環境影響評価の実施より相当早くから段階的に作成されており、環境影響評価手続が行われる時点では、実際には事業計画の熟度がある程度高まっている。このため、方法書等の公表により住民等からより良い案が提案され計画を見直すことになると、事業者にとっては時間、費用を想定以上に要することがある。従って、あらかじめ実行可能なより良い技術の考え方を踏まえて事業計画を検討することにより、導入の必然性が高い環境保全対策を早い段階から事業計画に組みこむことが可能となるとともに、事業者における手戻りやさらなる費用・時間の負担を避けることができる。 |