平成12年度第2回 騒音分科会
資料6
課題の整理とアセス事例調
~これまでに挙げられた課題・留意点に対する解決策・対応案~
1. 工事中の複合騒音
▼課 題
多くの事業で標準手法においては、「工事用車両の走行」及び「建設機械の稼働」が工事中の影響要因として選定されているが、場所によっては、これらの影響が同時に生じることとなる。しかし、評価指標が異なること等から、複合騒音として予測・評価を行った事例はない。
▼対応の方針
工事中の複合騒音が問題となる仮想のケースを設定し、調査・予測・評価方法や保全措置を例示する。
▼ケーススタディ
| Case:工事区域が2箇所に分かれており、別の区域で発生した工事用車両がもう一つの工事区域の近傍を通過する。 | ||||||
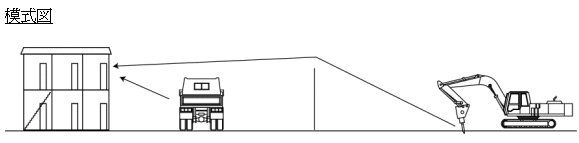 |
||||||
調査・予測・評価(案)
|
▼調査・予測・評価の留意事項として記載する内容(報告書記載案)
複合騒音が問題となるケース(例示)
工事区域、工事用車両の走行ルートと保全対象施設の位置によっては、工事用車両と建設機械の稼働による複合騒音の検討が必要な場合が考えられる。
複合騒音の予測・評価手法(例示)
ケーススタディの例示
2. 供用時の複合騒音
▼課 題
騒音に関する環境基準や規制基準は、個別の特定発生源を対象としているが、実際には特定騒音が同時に聞こえるため、複合騒音を予測・評価を求められる場合がある。
▼対応の方針
事業者の違いや各発生源からの騒音の特性等により、調査・予測・評価方法が異なるものと考えられることから、調査・予測・評価方法の留意点を整理して、一般化したものを示す。
▼課題に対する解決策・対応策
・問題となるケースと留意点の整理
[1]標準的なケース(現在、道路(鉄道)がある地域に鉄道(道路)が新設される)
・将来の予測方法を考慮して現況調査を実施する。
|
||||
・等価騒音レベルで予測する場合、発生源の特性等を考慮して評価時間を設定する必要がある。
|
||||
・基準がないため、評価は回避・低減が基本となるが、事業者の違いによる実現可能性に配慮する必要がある。
|
[2]特種なケース
◆
事業に合わせて、現在の道路(鉄道)に対しても改良が行われるケース
([1]の留意事項が参考となる)
◆ いずれも新設されるケース
・同時に都市計画される場合、「都市計画においては個別の案件毎に手続きが実施される」(「面整備事業環境影響評価技術マニュアル」H11.11 監修 建設省都市局都市計画課)こととなるが、「条例等による環境影響評価の必要性、都市計画として定めるに当たっての必要性等の観点からの検討を経て、適切な方法での対応」(同マニュアル)がなされているかどうかの検討が必要である。
例1) (いずれの事業についても環境基準を達成しているが、)同時に都市計画される事業との複合騒音を回避・低減するために、必要に応じて遮音壁の嵩上げや透水性舗装の実施を行う。
▼調査・予測・評価の留意事項として記載する内容(報告書記載案)
複合騒音が問題となるケース(例示)
既に道路・鉄道等の騒音発生源が存在している地域に、新たに道路等を計画するケースでは、複合騒音が問題となることが考えられる。
調査の留意事項
現況の騒音を把握する場合、事業により高架構造物等の遮蔽物が出現する場合や、道路の車線位置が移動する場合等が考えられるため、予測を踏まえ発生源からの寄与を明らかにする必要がある。
保全措置の考え方(例示)
事業者による実施可能な保全措置を明確にした上で、各発生源からの寄与を考慮して保全措置を検討する必要がある。
3. 道路交通振動
▼課 題
道路交通振動に関する基準として要請限度があり、環境アセスメントにおいて、この値を下回ることをもって評価しているケースが多い。しかしながら、要請限度は、「公安委員会に措置要請できる振動レベルの大きさ」であることから、道路交通騒音での環境基準のように、要請限度よりも厳しい水準が本来の目標となるべきと考えられる。
▼対応の方針
要請限度以外の評価の事例、考え方を例示する。
▼道路交通振動の評価事例(特定工等の規制基準による評価事例)
「調布都市計画道路3・2・6号調布保谷線、三鷹都市計画道路3・3・6号調布保谷線(調布市富士見町~三鷹市野崎間)建設事業 環境影響評価書」(平成9年2月 東京都)
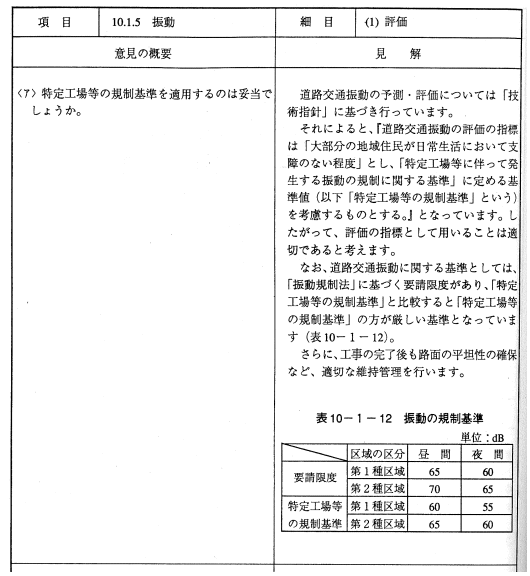
▼調査・予測・評価の留意事項として記載する内容(例)
評価の考え方(例示)
要請限度以外の評価指標・評価の考え方を例示する。
4. 鉄道振動
▼課 題
鉄道振動(普通鉄道及び軌道)については、振動の調査・予測・評価手法が確立していない。
▼対応の方針
既存の事例で採用されている手法を整理し、得られる知見を示す。
▼課題に対する解決策・対応案の提示
・既存の事例(概略)
| 事業名 | 横浜市4号線 (日吉~中山) |
大阪8号線 (井高野~今里) |
常磐新線 (守谷~伊奈・谷和原) |
| 調査 | 既存の地下鉄を対象として新幹線の調査方法を準用 | 既存の地下鉄を対象として新幹線の調査方法を準用 | (なし) |
| 予測 | 地下部:営団式を補正地上部:事例の引用 | 地下部:営団式を補正 地上部:(なし) |
地下部:(なし) 地上部:伝搬理論式 |
| 評価 | ・建議※(65dB) ・回避・低減 |
・閾値(55dB) ・回避・低減 |
・65dB (横浜等の他事例、気象庁震度階を参考に設定) |
| 保全対策 | 不確実性を考慮して60dB(A)以上と予測される区間について 防振枕木を実施 |
必要に応じて防振枕木等の防新対策を実施 | ロングレールの設置 軌道パッド敷設 |
| 備考 | 市条例より法に移行 地上及び地下を走行 |
市条例より法に移行 地下のみを走行 |
茨城県要綱アセス 地上のみを走行 |
| ※「鉄道公害の防止策について(建議)」(昭和49年横浜市公害対策審議会) |
・調査について
2事例は「緊急を要する新幹線鉄道振動対策」に定める測定方法に準じて振動レベルの調査を実施している。しかしながら、新幹線と在来鉄道の違いを考慮して、列車種別(快速、普通等)、車両形式、走行時間帯(朝・夕のピーク時に徐行運転する場合がある)等を明らかにする必要性が考えられる。
・予測について
予測の基本モデルについて大きな差はないものの、それぞれ独自の補正等を行っている。
・評価について
大阪が55dBに対し、横浜・常磐新線は65dBとしている。これには、55dBでは、地上部及び土被りの浅い地下部での達成が困難であることが背景にあるものとも考えられる。
また、東京都環境影響評価技術指針では、「緊急を要する新幹線鉄道振動対策」に定める指針(70dB)又は「特定工場等に係る振動の規制基準」(55~65dB)とされている。
▼調査・予測・評価の留意事項として記載する内容(例)
調査の考え方
現時点では「緊急を要する新幹線鉄道振動対策」の調査方法を採用せざるを得ないが、調査にあたっては、列車種別、車両形式、走行時間帯等を明らかにする必要がある。
予測手法(技術シート)
各事業者により様々な予測手法があるため、それぞれ整理を行い、技術シートに示す。
評価の考え方(例示)
事業特性や地域特性により、定量的な評価指標が異なる場合も考えられる。また、定量的に予測しているものの統一的な評価指標がないため、客観的な判断(比較評価)が困難である。いずれの事業についても現計画よりも一層の回避・低減の措置を表明している。
5.低周波音
低周波については、広くアセス事例を整理・検討するほか、以下の国レベルの動向等を整理し、技術シートに取りまとめる。
・低周波音調査マニュアルの策定
・本年度中の調査を目処に、全国90箇所で実態調査を実施
6.「予測・評価結果」と「事後調査結果」との比較検討
既存の環境影響評価における予測結果と事後調査結果の比較等を行い、これらの以外の課題の抽出・問題点の整理等を行う。(資料6-3参照)
資料6-1 建設工事騒音の伝搬計算方法の基本的考え方
資料6-2 技術シート
資料6-3 事例整理