平成12年度 第3回検討会
資料 3
自然との触れ合い分野の環境保全措置
(ケーススタディー)
1.景 観
影響要因 |
存在・供用(土地の改変、工作物の存在) |
現計画に対する予測の結果、『眺望景観』における固有価値(自然性)及び固有価値(郷土性)、『囲繞景観』における固有価値(自然性)の価値の低下が予測されたことから、『眺望景観』の「規模・構造」、『囲繞景観』の「立地・配置」及び「デザイン・修景、設備」に関する保全措置を講じた修正案を作成、現計画と比較。 |
|
1.保全措置
1.1 保全方針の設定
1)保全措置検討の観点
| ・ | 事業地は、市街地縁辺の丘陵緑地に位置し、周辺からは地域の眺望のシンボルとなる△△山へと連続する緑に覆われた山腹として眺められる存在として広く親しまれていることから、事業実施に起因するこうした眺望景観の変化の低減に努めることとする。 |
| ・ | また、事業実施区域は、地域でも自然性の高い樹林や地域住民に親しまれる渓谷景観等を有していることから、事業実施に起因する自然性の高い囲繞景観の変化の低減に努めることとする。 |
2)保全対象と目標の設定
| <眺望景観> | <囲繞景観> | |
保 |
・事業実施に伴い、主要な眺望点からの△△山を中心とする眺望視野のほぼ中央に構造物が出現し、△△山へのスカイラインの連続性の一部分断、視野内の人工物の占有率の増加等による価値の変化が予測されたことから、保全措置の必要性があると判断。 ・上記を踏まえ、複数視点場の中で最も大きな価値変化が予測された「○○ヶ丘」における普遍価値の「自然性」、固有価値の「郷土性」を保全対象とする。 |
・事業による直接改変区域に係る一部の景観区においては、景観区の自然性の高さを規定すると考えられる樹林の改変や構造物の出現等による価値の変化が予測されたことから、保全措置の必要性があると判断。 ・上記を踏まえ、特に発達した樹林の大規模な改変が予測された「○○川中流区」における普遍価値の「自然性」を保全対象とする。 |
保 |
<普遍価値(自然性)> ・人工物の視野占有率の低減を図る。 ・具体的には、「人工物の視野占有率が3~4%を越えるとプラス評価が得られなくなる」という既往知見*に基づき、人工物の視野占有率を3%以下に低減する。 <固有価値(郷土性)> ・構造物によるスカイライン分断を回避する。 |
<普遍価値(自然性)> ・景観区内の樹高の高い樹林の直接改変量を低減する。 ・構造物の出現による景観区内の眺めの変化を低減する。 |
*:「国立公園集団施設地区の景観評価に関する研究」(1979 樋口忠彦・田口勤・長坂富雄)
3)保全措置の検討内容
表-1 保全措置の検討内容
| 立地・配置 | 規模・構造 | デザイン・修景、設備 | |
| 眺 望 景 観 |
(現計画に対する予測結果では、構造物の立地・配置に起因する価値の変化が認められなかったことから、検討の対象としない) | 保全目標で掲げた指標は、いずれも出現する構造物の規模・構造により操作しうる内容であることから、存在・供用時における構造物の高さの低減、構造の変更を検討する。 | (視点場からの構造物の視認距離は中景以上であり、デザイン・修景等の変更による影響低減効果は少ないと考えられるため、囲繞景観において検討) |
| 囲 繞 景 観 |
保全目標で掲げた指標のうち、樹林の改変量については、直接改変域の配置変更により操作しうる内容であることから、「○○川中流区」内の樹高の高い樹林域の直接改変を避けた配置を検討する。 | (規模・構造については、眺望景観の保全措置内容を優先することとし、検討の対象としない) | 保全目標で掲げた指標のうち、景観区内の眺めの変化については、構造物の規模・構造が「眺望景観」の回避・低減措置で規定されることから、修景緑化の実施及び構造物の色彩の変更を検討する。 |
![]()
1.2 保全措置の検討及び妥当性の検証
1)回避・低減措置
(1)立地・配置(囲繞景観)
[1] 具体的措置の検討
| ・ | 現計画に対する予測において、特に景観区内の固有価値(自然性)の変化が予測された「○○川中流景観区」を対象として、固有価値(自然性)の物理指標として用いた「植生単位の平均樹高」の変化を低減するための具体的措置として、同景観区内の樹高の高いエリアの直接改変を避け、当該景観区及びその隣接景観区(いずれも事業実施区域内)の他の樹高の低いエリアに変更した修正案を検討した。 |
| ・ | 具体的には、「○○川中流区」北東部の改変を中止し、これを南東に隣接する「中部斜面混交林区」及び「集落北部混交林区」内の比較的樹高の低い二次林域に振り分けることによって修正案を作成した。 |
[2] 効果・影響の検討
a.「景観」要素に関する効果の検討
| ・ | 現計画と修正案(次頁図-1参照)それぞれについて、事業実施後の景観区内の樹高について得点化し、それを比較した。 |
| ・ | 検討結果は次頁表-2のとおりであるが、「○○川中流区」の樹高に関する得点は、現計画が249点であるのに対し、修正案では334点となる。また、「中部斜面混交林区」、「集落北部混交林区」については、変更に伴い増大する直接改変域はランク4または3であることから、隣接する景観区との合計点も現計画の1,187点に対し、1,194点となる。このため、保全措置による効果は確認されたと判断した。 |
b.その他環境要素に対する影響の検討
| ・ | 修正案について、景観以外の環境要素への影響の程度を検証した結果、修正案において改変量が増加した景観区は、「野鳥観察活動」にとって重要な活動区と重複しており、「触れ合い活動の場」への影響が極めて大きいことが確認された。 |
| ・ | 「野鳥観察」は、当該地域にとって高い普遍価値、固有価値を有する重要な活動であり、活動の存続の必要性は極めて高いものであることから、ここでは「触れ合い活動の場」おいて検討された修正案(修正Ⅱ案、図-1参照)を採用することとした。 |
| ・ | なお、修正Ⅱ案に対する「景観」に関する効果の検討結果は表-2のとおりであり、修正案よりは劣るものの、現計画と比較して、影響の若干の回避低減効果が認められた。しかし、修正Ⅱ案の採用により影響が残ることから、代償措置の検討を行うこととした。 |
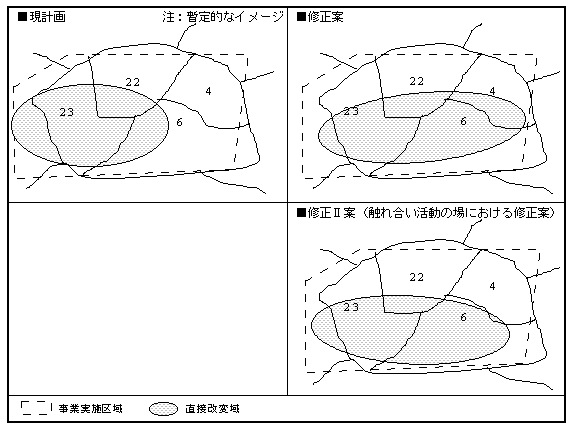
図-1 現計画及び「立地・配置」に関する修正案における直接改変域
表-2 現計画及び「立地・配置」に関する修正案の改変後の樹高に関する得点
* ランク5(平均樹高20m以上)、4(同15~19m)、3(同10~14m)、2(同5~9m)、1(同4m以下) |
景観区№ |
現計画 |
修正案 |
修正 |
|||||||||||
ランク* |
合 |
ランク* |
合 |
合 |
||||||||||
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
|||||
4 |
中部斜面混交林区 |
45% |
17% |
18% |
0% |
20% |
100% |
42% |
12% |
6% |
0% |
40% |
100% |
377 |
225 |
68 |
54 |
0 |
20 |
367 |
210 |
48 |
18 |
0 |
40 |
316 |
|||
6 |
集落北部混交林区 |
18% |
35% |
4% |
2% |
41% |
100% |
18% |
28% |
2% |
0% |
52% |
100% |
258 |
90 |
140 |
12 |
4 |
41 |
287 |
90 |
112 |
6 |
0 |
52 |
260 |
|||
22 |
○○池区 |
16% |
38% |
2% |
2% |
42% |
100% |
16% |
38% |
2% |
2% |
42% |
100% |
280 |
80 |
152 |
6 |
4 |
42 |
284 |
80 |
152 |
6 |
4 |
42 |
284 |
|||
23 |
○○川中流区 |
13% |
19% |
18% |
4% |
46% |
100% |
32% |
22% |
18% |
4% |
24% |
100% |
275 |
65 |
76 |
54 |
8 |
46 |
249 |
160 |
88 |
54 |
8 |
24 |
334 |
|||
合 計 |
1,187 |
合 計 |
1,194 |
1,190 |
||||||||||
(2)規模・構造(眺望景観)
[1] 具体的措置の検討
| ・ | 現計画に対する予測において特に眺望景観の固有価値と普遍価値の大きな変化が予測された「○○ヶ丘」を代表視点として、固有価値(自然性)、普遍価値(郷土性)の物理指標として用いた「60°視野内の人工物の占有率」、「△△山周辺のスカイラインの連続性」の変化を低減するための措置として、構造物の規模・構造を変更した修正案を検討した。 |
| ・ | 具体的には、構造物の高さを事業計画で規定される床面積を確保できる範囲内で低くするほか、一部地下構造化することが可能なものについて、地下式とした修正案を作成した。 |
[2] 効果・影響の検討
a.「景観」要素に関する効果の検討
| ・ | 現計画と修正案それぞれの予測画像を作成し、先に述べた物理指標の状態を比較することによって効果の検討を行った。 |
| ・ | 検討の結果は図-2のとおりであり、現計画におけるスカイラインの分断が回避されるとともに、人工物の見えの大きさも2.1%と3%を下回ることから、保全措置の実施による効果が確認されたと判断した。 |
| ・ | ただし、検討は予測画像を用いて行ったものであり、保全措置の効果が期待通り発揮されるか否かに不確実性が残る。このため、事後調査により効果の確認を行うこととする。 |
b.その他環境要素に対する影響の検討
| ・ | 修正案について、景観以外の環境要素への影響の程度を検証した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、修正案を採用することとした。 |
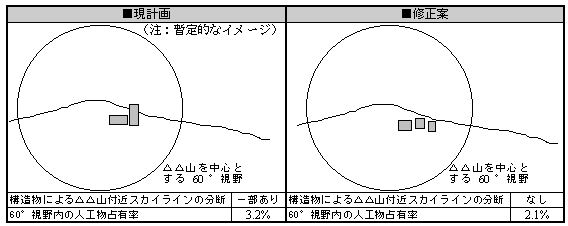
図-2 現計画及び「規模・構造」に関する修正案の予測画像と把握指標
(3)デザイン・修景、設備(囲繞景観)
[1] 具体的措置の検討
| ・ | 現計画に対する予測において、造成面と構造物の出現により、景観区内の眺めの状況が特に大きく変化する予測された「○○川中流景観区」を対象として、変化を低減するための措置として、修景緑化及び構造物の色彩を変更した修正案を検討した。 | |
| ・ | 具体的には、修景緑化として造成面及び構造物周辺に周辺の残置樹林との調和に配慮した高木を中心とする植栽*を施す、また、構造物の色彩については、現計画で白色系としていたものを暗茶系色に変更することによった。 | |
*: |
構造物の遮蔽と周辺景観や残置森林との調和を勘案し、常緑・落葉高木の混植とするほか、歩道等からの樹林内の林床の見通しの確保を考慮した上で、常緑の中低木を植栽する。なお、「触れ合い活動の場」における保全措置内容にも留意し、野鳥誘因効果のある樹木も採用する。 | |
[2] 効果・影響の検討
a.「景観」要素に関する効果の検討
| ・ | 現計画と修正案それぞれについて、景観区内を代表する眺望利用地点である「○○台」を視点とした予測画像(図-3)を作成、これを用いて被験者に対する視知覚心理学的手法による評価実験を実施することによって効果の検討を行った。 |
| ・ | 実験の結果、被験者30名中26名から現計画より修正案の方が普遍価値(自然性)に関する価値の低下が緩和されるとの評価結果が得られたことから、保全措置の実施による効果が確認されたと判断し、修正案を採用することとした。 |
| ・ | ただし、修景植栽については、予測画像に表現したものが、植栽後5年を経過した状態のものであり、効果の不確実性が残る。また、構造物の色彩についても、予測画像を用いて行った検討であることから、保全措置の実施により期待する効果が発揮されるか否かに不確実性が残る。このため、事後調査の実施により、効果の確認を行うこととする。 |
b.その他環境要素に対する影響の検討
| ・ | 修正案について、景観以外の環境要素への影響の程度を検討した結果、特に大きな影響は確認されなかったことから、修正案を採用することとした。 |
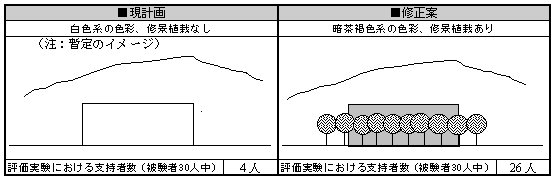
図-3 現計画及び「デザイン・修景、設備」に関する修正案の予測画像と把握指標
2)代償措置
[1] 具体的措置の検討
| ・ | 「触れ合い活動の場」の影響の回避・低減を重視したことにより、十分な影響の回避・低減を行うことができなかった「囲繞景観」の普遍価値(自然性)については、特に直接改変による影響が大きいと予測された「○○川中流区」内を対象として代償措置を行う。 |
| ・ | 具体的措置としては、「○○川中流区」内の残置森林のうち、現状において価値認識の低いランク2~3の樹林への高木類の植栽及び植生管理を実施し、直接改変により喪失される「ランク4~5」と同等の樹林を復元する。 |
[2] 効果・影響の検討
| ・ | 代償措置実施前後での「○○川中流区」の普遍価値(自然性)に係る指標(得点)の変化は、次頁の表-3のとおりであり、代償措置実施前の275点から311点に上昇する結果が得られたことから、代償措置の実施による効果が確認されたと判断し、これを採用することとした。 |
| ・ | ただし、代償措置の効果は、植栽計画に基づく机上算定によるものであり、効果の不確実性が残る。このため、事後調査の実施により効果の確認を行うこととする。また、植栽実施後の管理を要するものであることから、あわせて事業者による継続的な管理を行うこととする。 |
表-3 代償措置(喪失樹林の復元)による囲繞景観の普遍価値(自然性)の指標の変化
景観区№ |
代償措置実施前 |
代償措置実施後 |
|||||||||||
ランク* |
合 |
ランク* |
合 |
||||||||||
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
5 |
4 |
3 |
2 |
1 |
||||
23 |
○○川中流区 |
21% |
17% |
17% |
6% |
39% |
100% |
33% |
23% |
5% |
0% |
39% |
100% |
105 |
68 |
51 |
12 |
39 |
275 |
165 |
92 |
15 |
0 |
39 |
311 |
||
* ランク5(平均樹高20m以上)、4(同15~19m)、3(同10~14m)、2(同5~9m)、1(同4m以下) |
![]()
1.3 環境保全措置の実施案
表-3 「景観」に係る環境保全措置の実施案
措置の区分 |
回避・低減措置 |
代償措置 |
||
内容 |
直接改変区域の配置変更 | 構造物の規模・構造変更 | 構造物周囲の修景緑化、暗茶系の色彩の採用 | 残地森林への高木植栽 |
実施期間 |
造成工事時 | 構造物建設工事時 | 構造物建設工事時 | 工事期間中 |
実施方法 |
造成計画の変更 | 建築計画の変更 | 建築計画の変更及び植栽の実施 | 植栽計画の立案及び植栽の実施 |
実施主体 |
事業者 | 事業者 | 事業者 | 事業者 |
措置の不確実性の程度 |
特になし | 保全措置の実施による効果の程度(構造物の視認性) | 保全措置の実施による効果の程度(修景植栽、色彩変更による効果) | 保全措置の実施による効果の程度(植栽による効果) |
措置の実施に伴い生じるおそれのある環境影響 |
「触れ合い活動の場」のうち、野鳥観察の場の改変 | 特になし | 特になし | 特になし |
措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 |
「触れ合い活動の場」の影響の回避・低減を重視した修正Ⅱ案の採用による囲繞景観の自然性低下 | 主要視点場からの構造物の視認 | 景観区内の眺めの状態の変化 | 景観区内の普遍価値(自然性)の低下 |
![]()
2.評 価
| ・ | 現計画及び修正案の価値の認識項目の変化は下表のとおりであり、修正案では、構造物の規模・構造の変更によるによる△△山周辺のスカイラインの切断は概ね回避されるほか、デザイン・修景の変更による囲繞景観の普遍価値(自然性)の変化も低減効果が認められた。 |
| ・ | 一方、「触れ合い活動の場」における保全措置を優先したために、影響の回避・低減不十分であった囲繞景観の普遍価値(自然性)についても、代償措置による影響緩和効果が認められた。 |
| ・ | このため、事業の実施による眺望の変化影響は、講じた措置により、事業者の実行可能な範囲内で概ね回避・低減が図られたものと評価した(次頁表-4参照)。 |
表-4 「景観」に関する評価(総括)
現計画 |
修正案 |
||
回 |
立地・配置 |
・○○川中流区における囲繞景観の普遍価値(自然性)を表す指標である樹高に関する得点は249点。 | (「触れ合い活動の場」の保全措置を優先し、修正Ⅱ案を採用、影響の回避・低減が不十分であったため、代償措置を検討) |
規模・構造 |
・構造物により、△△山周辺のスカイラインの一部が分断。 | ・構造物による△△山周辺のスカイラインの分断は生じない。 | |
| ・○○ヶ丘からの眺望視野内の人工物占有率約3% | ・○○ヶ丘からの眺望における人工物占有率約2% | ||
デザイン・修景、設備 |
・評価実験において4人が支持。 | ・評価実験において26人が支持。 | |
代償措置 |
・代償措置の実施により、○○川中流区における囲繞景観の普遍価値(自然性)を表す指標である樹高に関する得点は、275点から311点に上昇 | ||
![]()
3.事後調査
表-5 事後調査の実施案
調査項目 |
構造物の規模・構造変更による保全措置の効果の確認 | 構造物の色彩変更による保全措置の効果の確認 | 修景植栽の実施による保全措置効果の確認 | 残置樹林への植栽(代償措置)による保全措置効果の確認 |
調査範囲 |
○○ヶ丘からの眺望 | ○○川中流区内(○○台)の眺望 | ○○川中流区内植栽実施個所 | |
実施時期 |
供用開始年次 | 供用開始年次 | 供用開始から5ヶ年間程度 | |
調査密度 |
1回/季 | 1回/季 | 4季各1回/年 | 1回/年 |
調査手法 |
○○ヶ丘からの撮影した眺望写真と予測画像の比較による効果の検証に用いた指標値の状態を検証 | ○○台から撮影した写真を用いた被験者による視知覚心理学的評価実験により効果の程度を検証 | 植栽の活着・生育状況の確認、○○台から撮影した写真と予測画像との比較により効果の程度を検証 | 植栽の活着・生育状況の確認 |
調査結果の取扱 |
インターネットによる調査結果の公表 | |||
不測の場合の対処方法 |
修景植栽の追加による構造物視認量の軽減 | 構造物の壁面補修に合わせた色彩の再変更 | 植生管理(施肥等)、補植(樹種の見直し含む) | 植生管理(除間伐、施肥等)、補植 |
実施体制 |
事業者 | 事業者 | 事業者 | 事業者 |