平成13年度第1回陸水域分科会
資料3-2ダム
2. ケーススタディ -多目的ダムを例として-
3-0 事業計画の想定
ケーススタディにおいて対象とする事業は、本州太平洋側に流下する仮想河川の上流部に位置する仮想の多目的ダム(洪水調節、かんがい、発電)の新設事業とする。
仮想の事業計画の概要は以下のとおりである。平面図等を図-3.1に示す。
湛水面積 :330ha 総貯水容量 :101,000,000m³ ダムの形式 :ロックフィルダム 堤 高 :105m 発電最大出力 :30,000kw
3-1 地域特性の把握
(1) 地域概況調査
既存資料調査、概略踏査及び専門家等へのヒアリングを行い、「動物」「植物」「地形・地質」等といった生態系に密接に関連する項目を中心とした情報を収集、解析することにより対象地域における生態系の概況を把握した。
(2) 全国的・広域的な視点からみた対象地域を含む河川の特性
事業の対象となる河川は、フォッサマグナの東側に位置し、本州太平洋側に流下する○○川の支川にあたり、○○県南西部の○○山地に位置する○○岳(標高1,300m)にその源を発し、○○川、○○川と合流したのちに、○○市で○○川に合流する、流路延長は150km、流域面積は900km2の河川である(図-3.2)。
対象地域周辺は、標高900~1,100mに位置し、冷温帯気候の夏緑広葉樹林帯(ブナクラス域)にある。
対象地域は環境庁による「生物多様性保全のための国土区分(試案)」では「本州中北部太平洋側区域」に属している。
対象とするダム建設予定位置の上流には○○ダム、下流には○○ダムが既に存在する。
対象地域の広域的な環境特性を把握するために、広域図を作成した(図-3.3)。
事業実施区域及びその周辺は、低地から山地の地形を呈し、低地では水田が、山地ではスギ・ヒノキ・サワラ植林がそれぞれ優占する。一部、ヤマツツジ-アカマツ群落、クリ-ミズナラ群落及びコナラ群落などもみられる。下流の低地は広く田園景観を、上流の山地は各河川沿いの谷底平野を中心に里的な景観を示している。
広域図作成に用いた資料を以下に示す。
・地形図
・航空写真
・植生図
・土地利用図 等
| 広域図は、広域的なレベルでの地形、植生、水系等の状況を概観するものであり、特に、対象地域の生態系の自然的特性や周辺との連続性などの点について把握した。広域図の作成範囲は事業実施区域周辺を含む範囲とし、海域又は本川との合流箇所や主な支川との合流箇所までを目安として各事業で検討することが望ましい。 |
(3) 陸水域生態系の類型区分
河川域における動植物の生息・生育環境は、河川形態、河床勾配、河床材料(底質)、河畔の植生、周辺の土地利用状況や河岸の地形、水質等と密接な関係があり、これらにより河川域における動植物の生息・生育環境としての機能が異なっていると考えられる。
事業実施区域周辺地域の生態系の特性を把握するため、基盤となる環境を類型化し、まとまりを有する地域ごとに区分した(類型区分)。
なお、類型区分を行う際に把握すべき情報として、主に河川形態(瀬・淵の状況)、河床材料(底質)、河岸の植生、周辺土地利用状況、河川内に設置された構造物の位置等の基礎情報や概況調査結果や生物の確認状況等に着目し、それらの情報を図又は表を用いて整理し、総合的に判断することにより類型区分を行った。
類型に区分する範囲は、事業実施区域及びその周辺の環境特性を把握できる範囲や、事業により影響を受けるおそれのある範囲とした。また、調査地域を設定するための資料とすることも念頭に置いて設定した。
本河川域における環境類型区分は、A~Dの4つの環境に区分できた(表-3.1、図-3.4)。
3-2 事業による影響
ダム(水力発電所)事業による環境影響評価の影響要因は以下のとおりである。
・地形改変および施設の存在(堤体の存在、護岸の存在、河道の改変等)
・貯水池の存在
・河水の取水
(いずれもダムの存在・供用時)
なお、原石山や付帯道路の建設等も影響要因に考えられるが、これらは陸域の改変であることから、本陸水域の検討の対象外とする。
これらの影響要因により、調査地域周辺の物理化学的環境に変化を与えることが考えられる。また、物理化学的環境によって動植物の生息・生育環境が成立していることから、物理化学的環境の変化は、調査地域周辺の動植物の生息・生育状況に影響を与えることが考えられる。
事業の実施により想定される環境要素の変化を表-3.2に示す。
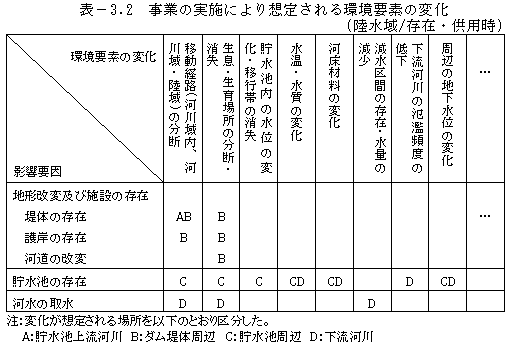
3-3 環境影響評価の項目及び調査・予測・評価手法の選定
(1) 重要な類型区分の選定
生態系への影響をとらえるに当たり、3-2で整理した影響要因が具体的に類型区分された地域や、概況調査で明らかとなった環境に対してどのような影響を与えるのかを検討した。
重要な類型の選定に当たっては、以下の観点から選定した。
[1] 事業により一部または全部が消失する(または他の類型に置き換わる)類型を評価対象とする。
[2] 事業による影響が及ぶと想定される範囲(影響予測範囲)に含まれる類型とする。
上記のような基準で選定すると、重要な類型区分は以下のとおりである。
4つの類型のうち、ダム事業による改変の程度を検討すると、区分Bの一部区間が貯水池となることから、重要な環境類型区分であると判断できる(上記[1])。
また、区分Cの一部が貯水池になること(上記[1])、事業実施区域下流側では、河水の取水が行われることにより流量が減少すると予想されることから、重要な環境類型区分であると判断できる(上記[2])。なお、この区分Cの近傍には湿原があり、ミズバショウ、ザゼンソウ等の好湿性種の生育等が確認されている。
(2) 対象とする生態系の構造の概略検討
対象とする調査地域は前述のように、「区分B」、および「区分C」である。そこで、区分ごとに生物の採餌場としての機能について、基盤環境ごとの主な生物種を整理し、生態系の構造を想定した。
また、生態系の構造は、環境との関係だけでなく生物要素間の関係も重要な側面である。
生物要素間の関係には、種内関係、種間関係があり、種内関係には雌雄の関係、親子の関係、同年齢間の関係等、種間関係には「食う-食われる」の関係(食物連鎖)、種間競合、共生、寄生等がある。
ここでは最も知見が多い食物連鎖について整理した。
調査地域に生息する動物各種の食性及び餌場を既存の文献、現地踏査等の情報から整理し、それに基づき調査地域における生物要素間の相互作用として食物連鎖の骨格的な構造を想定した(図-3.5)。
なお、当該事業実施区域及びその周辺に成立する生態系の持つ機能については、河畔林の日射遮断機能(渓流部の水温上昇を防ぐ)、水中への栄養分(落葉・落下昆虫類)供給機能や、また、同じく河畔林や河床等では動物の生息場所としての機能、繁殖場所としての機能等を有するが、本ケーススタディではそれぞれの機能の変化予測という視点でなく、基盤環境の変化予測、注目種の変化予測等の中で把握することとする。
(3) 重点を置いて評価すべき生態系への影響の整理
事業によるインパクトによって生物の基盤環境要素のどの部分がどのように変化し、それによってどのような生物群集がどのような影響を受けるかという影響フローを図-3.6(PDFファイル15k)に示す。
(4) 注目種・群集の選定
注目種・群集は、生態系の上位性、典型性、特殊性の観点を考慮して選定した。
1) 上位性
上位性については、以下の観点から検討を行った。
○生態系を形成する生物群集において栄養段階の上位に位置する種・群集
○生態系の撹乱や環境変動などの影響を受けやすい種・群集
○対象となる陸水域のスケールに応じた種・群集
○陸水域生態系への依存性の高い種・群集
その他、調査の難易度、生物量の多さ等についても踏まえ、生態系の上位性に該当する種を取り上げ整理した(表-3.3)。
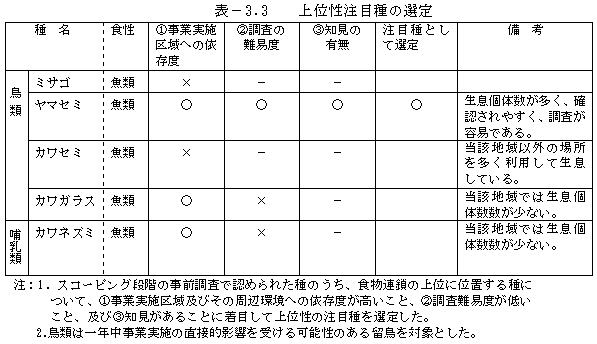
この結果、生態系の上位に位置する種のうち、ミサゴ、ヤマセミ、カワセミ、カワガラス、カワネズミが注目種の候補として挙がったが、このうち、最も事業区域への依存度や調査の難易度等からヤマセミを上位性の注目種とした。
この種は、当該地域の河川環境を広く利用しており、かつ、魚類、両生類、昆虫類を餌とする等、生態系の上位に位置するものである。
2) 典型性
典型性については、以下の観点から検討を行った。
○事業の実施に伴う生息・生育環境の変化が著しく、かつ、その影響が大きいと想定される種・群集
○地域の連続性を保持する上で重要な種・群集
○事業実施に伴い河川の変動性が損なわれることにより影響を受けるおそれのある種・群集
○重要な機能的役割を有する種・群集
○生物の多様性を特徴づける種・群集
○生物間の相互作用や生態系の機能に重要な役割を担う種・群集
○地理的に隔離された水域を指標する種・群集
○一時期であっても生態系に重要な位置を占める種・群集(渡り鳥等)
○調査すべき情報(生態、生息、生育状況等)が得やすい種・群集
スコーピング段階で生息・生育の確認された種・群集のうち、事業による影響を受けると考えられる種について、先に示した典型性観点を用いて注目種としての抽出を行った。種・群集の抽出を表-3.4に示す。
その結果、魚類ではイワナ、ヤマメ、両生類ではカジカガエル、水生昆虫類ではヒゲナガカワトビケラ、ウルマーシマトビケラ、河畔の植物ではオオバヤナギ林を典型性注目種・群集とした。これらの種が事業により受けるおそれのある影響は以下のとおりである。
イワナ・ヤマメ:事業により生育域が分断され、また、止水域の出現で生息環境に変化が生じるおそれがある。
カジカガエル:事業実施(貯水池周辺の裸地化、減水区間の流量の低下等)に伴う移行帯の消失により、産卵場への移動が困難になるおそれがある。
ヒゲナガカワトビケラ、ウルマーシマトビケラ:ダム下流河川の河床材料の変化によって生息空間である河床の礫間が減少するおそれがある。
オオバヤナギ林:中小洪水の発生頻度の低下に伴い、実生が定着できる裸地が減少するおそれがある。
なお、これらの種に関する現地調査は比較的容易であり、既存文献等の知見も比較的多いといえる。
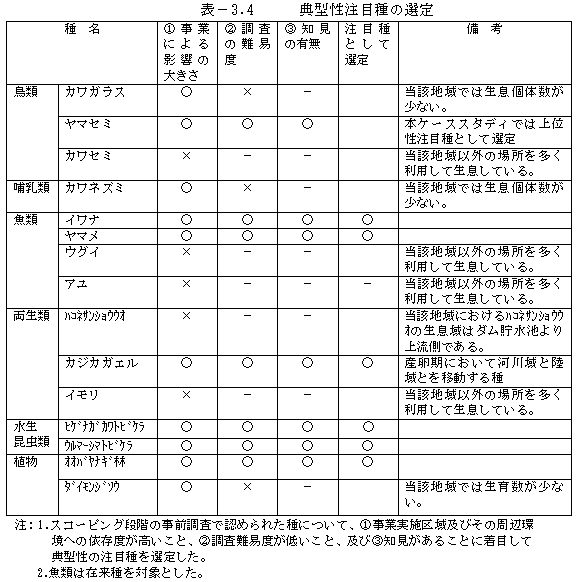
3) 特殊性
特殊性については、特殊な環境や対象地域において占有面積が比較的小規模で周囲にはみられない環境やそこに生息する種・群集を選定する。
本調査地域内の区分Dの近傍に湿地が存在する。そこにはミズバショウやザゼンソウが確認されている。この湿地は事業実施により地下水位の変化を受け、水位が上昇するおそれがあることから、この湿地に生育する種のうち、調査の容易さ等を勘案してミズバショウを対象とした。
4) 選定された注目種・群集
1)~3)をまとめると表-3.5に示すとおりである。
これらの注目種、群集の一般的な生活史、生息環境を表-3.6に示す(一例としてヤマセミ)。
(5) 調査・予測・評価手法の選定
調査・予測・評価手法の選定に際しては、これまでの作業結果をふまえて検討した手法を方法書にとりまとめるとともに、公告・縦覧時の方法書に対する意見を適切に反映させ、方法書に記述した手法を見直す必要がある。手法の選定に際しては、地域特性を考慮し、対象地域の生態系に対する影響を捉える上で最も適切な方法を選定する。
本ケーススタディで検討した手法については、後述の3-4、3-5の中で解説する。
(6) 調査・予測地域の設定
1) 調査地域
事業実施区域は、谷や尾根が連続し、谷戸が入り組んだ山地の環境である。そのため、調査地域を設定する際には、事業実施による影響範囲に加えて、その範囲を含む尾根や谷などの地形的な要素を勘案した。調査地域を図-3.7に示す。
2) 注目種・群集の調査対象地域
また、注目種・群集の調査対象地域は、調査地域を基本として、行動圏の大きさ、生活史、個体群の分布などの個別の種の生態的特性に応じてそれぞれ適宜設定した。