平成13年度 第1回海域分科会
第2部 第1章 総論
目次
| 1 | 対象とする地域と事業の想定 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- 1 | |
| 2 | 環境保全措置検討の観点 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- 3 | |
| 3 | 環境保全措置 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- 5 | |
| 3-1 | 保全方針の設定 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- 5 | |
| 3-2 | 環境保全措置の検討と妥当性の検証 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2- 6 | |
| 3-3 | 環境保全措置の実施案 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-10 | |
| 4 | 評価 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-11 | |
| 5 | 事後調査 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-12 | |
| 5-1 | 事後調査実施案 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-12 | |
| 5-2 | 事後調査報告 | ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ | 2-13 | |
1 対象とする地域と事業の想定
海域生態系の環境保全措置のケーススタディは、「生物の多様性分野の環境影響評価技術検討会の中間報告書 生物の多様性分野の環境影響評価技術(Ⅱ)-生態系アセスメントの進め方について-(平成12年8月、生物多様性分野の環境影響評価技術検討会)」(以下、平成12年報告書と示す)であげた調査・予測のケーススタディを用いる。
対象とする地域と事業の想定は以下のとおりとする。
[1]本州太平洋沿岸中部の比較的大きな内湾(図1)
[2]事業内容
・公有水面埋立(100ha)
・上物施設は道路用地、宅地、緑地(公園)、マリーナ
[3]基本条件
・上物施設による海域への環境影響はないものとする
・建設資材、埋立資材等からの溶出等による影響はないものとする
・環境保全措置のケーススタディは、調査・予測のケーススタディと同様に土地及び工作物の存在(埋立地の存在)とする
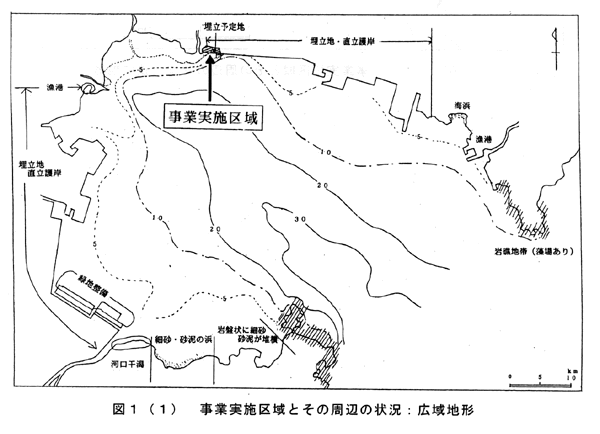
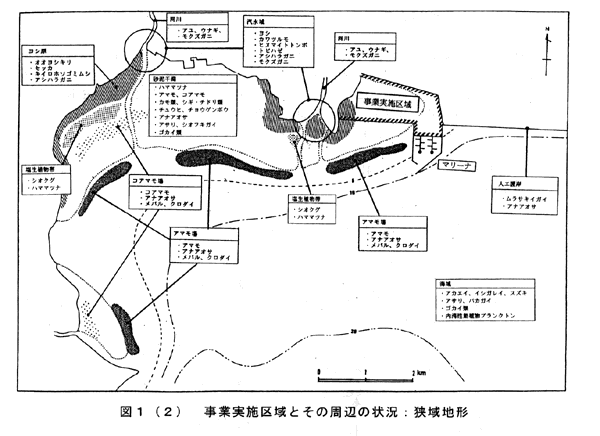
2 環境保全措置検討の観点
スコーピング段階の情報では、事業実施区域は本州太平洋沿岸中部の比較的大きな内湾に位置しており、その周辺には河口干潟が広がっており、また、沿岸域は水深5~10mの浅海域であり、その性状は砂泥質である。さらに、事業実施区域周辺の干潟前面にはアマモ場が分布している。生物についてみると、干潟にはアサリ等の貝類が多く生息し、水鳥・水辺の鳥の渡来地となっている。また、干潟には塩生植生帯があり、その背後にはヨシ原が分布しており、鳥類の繁殖地として利用される他、昆虫類も多くみられる。
以上のように事業実施区域及びその周辺は「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系」と位置付けられる。また、海域の類型としては、ヨシ原、干潟(海域・汽水域)、コアマモ場、アマモ場、人工護岸、砂泥底域に区分される。
本事業において、上記のような周辺環境を踏まえると、「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系の保全」を環境保全上の基本的な考え方とし、事業計画の立案を行った。
なお、平成12年報告書において、事業における環境影響評価の対象として選定した注目種はアサリ、イシガレイ、アマモ、ヨシ、アシハラガニ、シギ・チドリ類、バカガイ、トビハゼであり、重要な機能は生物的な機能、「場」としての機能、環境形成・維持の機能、物質循環機能、緩衝機能であった。平成12年報告書では注目種であるアサリ、イシガレイ、アマモ、重要な機能としてはアマモ場がもつ「場」としての機能(仔稚魚の育成場等)と干潟がもつ物質循環機能(水質の浄化)を調査・予測のケーススタディの対象とした。環境保全措置のケーススタディにおいても平成12年の検討を受け、表1に示す注目種及び重要な機能について検討を行うこととする。
立案した事業計画に対する影響予測は、まず、表1に示す注目種と重要な機能に対する影響を予測した。次に、注目種や重要な機能への影響の予測結果から導き出される海域生態系への影響について予測を行ったが、その結果、主に以下のような影響が生じると予測された。このように事業により生態系へ影響を及ぼすおそれがあると予測されたことから、環境保全措置を講じた修正案を作成、現計画との比較を行う。
表1 注目種及び重要な機能とその指標となる項目
|
注目種及び重要な機能
|
指 標 と な る 項 目
|
| アサリ :注目種(典型性) |
アサリの個体群の変化 |
| イシガレイ :注目種(上位性) |
イシガレイの卵、仔稚魚の分布範囲と幼魚及び成魚 の生息範囲 |
| アマモ(場) :注目種(典型性) 重要な機能(仔稚魚の育成場等) |
アマモ場に対する影響範囲 |
| 干潟 :重要な機能(物質循環機能) |
干潟の消失面積 |
<予測結果の概要>
アサリ
・アサリの個体群の変化による生態系への影響は、生息環境への影響は少ないものの、埋立(存在)によりアサリの生息場が消失することから、その個体群は減少する可能性がある。 ・アサリと同様に砂泥質の干潟を生息場所とする底生生物にも同様な影響が生じ、その結果、アサリを含む底生生物を餌とするシギ・チドリ類等の鳥類の餌資源が減少することにより、鳥類の生息状況に影響を及ぼす可能性がある。
イシガレイ
・イシガレイは調査地域全域を産卵場や育成場として利用しており、生息環境への影響は少ないものの、埋立(存在)により卵や仔稚魚の分布範囲や幼魚や成魚の生息範囲が消失する。イシガレイは移動性であるため、定量的な判断はできないものの生息範囲が消失することから、その個体群は影響を受けると考えられる。
・イシガレイと同様に、餌となる底生生物等にも同様な影響が生じると考えられることから、餌生物の減少によりイシガレイの生息個体数が減少する可能性がある。また、食物連鎖の上位に位置するイシガレイが減少することにより、調査海域の食物連鎖に影響を及ぼす可能性がある。
アマモ場
・アマモの生育については予測結果より、アマモの生育環境要素である水質、底質には影響を及ぼすことはないと考えられるものの、埋立予定地近傍のアマモ場で重要な生育環境要素である流速が変化するため生育に影響を及ぼす可能性がある。
・影響を受ける可能性がある埋立予定地近傍のアマモ場の生育株数は、調査地域内のアマモの総生育株数の約22%を占めている。アマモ場に依存する生物(仔稚魚等)の個体数は、主に生育株数に左右されると考えられることから、アマモ場の生育変化がそこに依存する生物である、メバルやクロダイなどの仔稚魚や葉上動物に影響を与える可能性がある。
干潟
・埋立(存在)で消失する干潟の総窒素の浄化量は、消失面積と浄化量から25kgN/日と算出された。これは、埋立予定地及びその前面の干潟の全浄化量の42%に該当する。
3 環境保全措置
3-1 保全方針の設定
「3.環境保全措置検討の観点」で述べた基本的な考え方や予測結果を踏まえ、保全対象と目標を表2のとおり設定した。なお、環境保全措置の検討にあたっては、環境への影響を回避し、又は低減することが優先されるが、今回のケーススタディでは干潟に対して代償措置として検討を行った。
保全対象は、事業実施区域及びその周辺が「干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系」として位置付けられることから、この生態系が保全対象となる。次に、保全目標であるが、事業実施区域及びその周辺の生態系への影響を評価するために、様々な観点から注目種と重要な機能を選定を行い、それらの項目を指標として生態系への影響予測を行ったことから、保全目標は注目種及び重要な機能に対するものとなる。注目種及び重要な機能に対する環境保全措置の保全方針は表3に示すとおりである。
表2 環境保全措置の保全対象と保全目標
|
保全対象
|
保全対象を保全するための指標となる項目
|
保全目標
|
| 干潟とアマモ場の存在する内湾砂泥底海域の生態系 | アサリ | アサリの個体群(生息域)に対して代償を図る |
| イシガレイ | イシガレイの生息域に対して低減及び代償を図る | |
| アマモ場 | アマモ場の生育域に対して回避を図る | |
| 干潟 | 消失する干潟に対して代償を図る |
表3 注目種及び重要な機能に対する環境保全措置の保全方針
| 注目種及び重要な機能 | 保全方針 |
| アサリ | アサリは移動能力が乏しいことから、個体群を保全するためには生息 場を保全・確保する必要がある。埋立(存在)により生息場が一部消 失することから、事業計画の軽微な変更として事業実施区域の縮小(埋 立面積の縮小)及び新たな生息場の創出(人工干潟)を検討する。 |
| イシガレイ | 埋立(存在)により、イシガレイの産卵場や育成場等の分布範囲や生 息範囲が一部消失することから、事業計画の軽微な変更として事業実 施区域の縮小(埋立面積の縮小)及び新たな産卵場や育成場等(人工 干潟)の創出を検討する。 |
| アマモ場 | 埋立(存在)により、アマモ場の生育環境(流速)に影響を及ぼす可 能性があることから、事業計画の軽微な変更として事業実施区域の縮小を検討する。 |
| 干潟 | 埋立(存在)により干潟が消失することから、事業計画の軽微な変更 として事業実施区域の縮小(埋立面積の縮小)及び新たな干潟の創出 (人工干潟)を検討する。 |
3-2 環境保全措置の検討と妥当性の検証
「4-1 保全方針の設定」であげた注目種及び重要な機能に対する環境保全措置の保全方針に基づき、現計画に対し環境保全のための軽微な変更を行う。その修正案は以下のとおりである。
修正案1(埋立面積:100ha→70ha)
アマモ場への影響を回避するために、既設護岸の延長上から海域に突出しないように、埋立面積を縮小し、マリーナを掘り込みにする。
また、アサリ、イシガレイの生息域への影響を代償するため、消失する干潟に対する代償のために事業実施区域の西の海域に人工干潟(約70ha)を造成する(図2参照)。
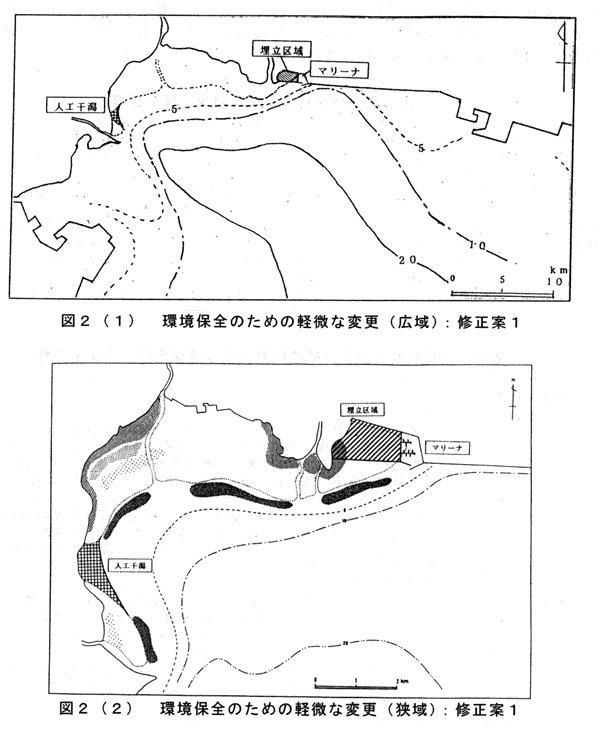
修正案2(埋立面積:100ha→70ha)
アマモ場への影響を回避するために、既設護岸の延長上から海域に突出しないように、埋立面積を縮小し、マリーナを掘り込みにする。
また、アサリ、イシガレイの生息域への影響を代償するため、消失する干潟に対する代償のために事業実施区域の東の人工護岸前面に人工干潟(約70ha)を造成する(図3参照)。
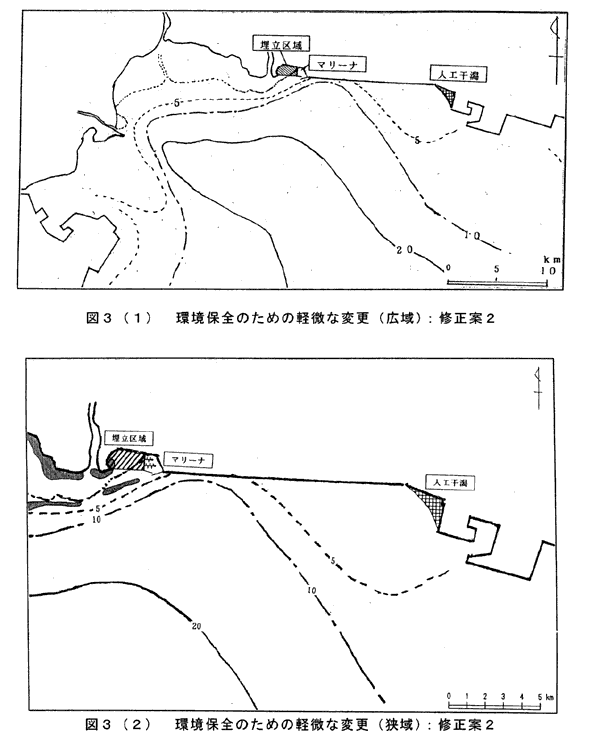
現計画と修正案1、修正案2について、調査対象地域の状況と注目種及び重要な機能に及ぼす影響について、環境保全措置の効果及び影響について比較検討した。検討結果は表4に示すとおりである。
検討の結果、修正案1と修正案2を比較し、生態系への影響を考慮すると、以下のような理由から修正案2を採用することとした。
人工干潟について
修正案では、埋立予定地近傍に消失する干潟と同規模の人工干潟を造成する措置を行う。造成する人工干潟は、粒度組成や干潟の勾配等について最新の研究結果や調査結果及び学識者
等による検討会を実施することより、消失する干潟と同程度の状況(場としての機能や物質循環機能)になるよう計画し、造成する。
修正案1と2との相違は、人工干潟の造成位置であり、修正案1では自然海岸の前面、修正案2では人工護岸の前面である。修正案1の造成区域は、現在まで工作物の建設等が行われていない。修正案2は過去干潟が存在していたところを埋め立てし、現在に至った自然状態の区域である。
これらの状況を踏まえると、自然海岸前面に造成する修正案1は、内湾の中で残り少ない自然海岸を消失することとなる。また、造成する区域周辺の干潟は、過去からその地形は維持しており、安定した自然環境を形成している。ここに、人為的な干潟造成を行うことは、周辺の干潟の地形等に影響を及ぼす可能性があると考えられる。
一方、人工護岸前面は浅海域であり、注目種のイシガレイの育成場となっている可能性はあるが、干潟の創出は産卵場と干潟の汀線付近での育成場を確保することができる。また、人工干潟は過去に失われた干潟を復元し、多様な生物の生息場の創出、物質循環機能の向上、さらには海岸線から隔絶された周辺後背地の人々に対し、親水エリアを提供することもできる。従って、修正案2を採用することとした。
4 注目種及び重要な機能に関する現計画と修正案との比較
| 注目種及び重要な機能 | 現計画 | 修正案1 | 修正案2 |
| アサリ | アサリの生息場である干潟等の消失(約70ha)により、調査地域内の全現存個体数の約5%(36×107個体程度)減少する可能性がある。 | 【代償】 干潟等の消失面積の変更はない。消失するアサリの生息域に対する環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 |
【代償】 干潟等の消失面積の変更はない。消失するアサリの生息域に対する環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 |
イシガレイ |
イシガレイの産卵場や育成場等の分布範囲や生息範囲が一部消失により、調査地域内での卵の分布範囲は約5%(約21ha)、仔稚魚の分布範囲は約7%(約27ha)が消失する。 | 【低減】 現計画に比べ、イシガレイの産卵場や育成場等の消失する分布範囲や生息範囲への影響はやや低減される。 【代償】 消失するイシガレイのに対する産卵場や育成場等の消失する分布範囲や生息範囲環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 |
【低減】 現計画に比べ、イシガレイの産卵場や育成場等の消失する分布範囲や生息範囲への影響ははやや低減される。 【代償】 消失するイシガレイのに対する産卵場や育成場等の消失する分布範囲や生息範囲環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 |
| アマモ(場) |
アマモの生育環境の重要な要素である流動(流速)が変化するため、埋立予定地近傍のアマモの生育に影響を与える可能性がある。 | 【回避】 マリーナを掘り込み型にすることで、流動(流速)の変化が現状と変化がないようにする。 |
【回避】 マリーナを掘り込み型にすることで、流動(流速)の変化が現状と変化がないようにする。 |
| 干潟 |
埋立(存在)で消失する干潟の全窒素の浄化量は25kgN/日である。 | 【代償】 干潟等の消失面積の変更はない。消失する干潟の物質循環機能に対する環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 ただし、人工干潟を造成する箇所は、自然海岸前面である。 |
【代償】 干潟等の消失面積の変更はない。消失する干潟の物質循環機能に対する環境保全措置として、埋立予定地の近傍に人工干潟(約70ha)を消失する干潟と同程度の状況になるように造成する。 ただし、人工干潟を造成する箇所は、人工護岸前面である。 |
3-3 環境保全措置の実施案
環境保全措置の実施案(修正案2)は表5に示すとおりである。
表5 環境保全措置の実施案
| 措置の分類 | 回避・低減の措置 | 代償措置 |
| 内容 | 事業実施区域の変更(埋立面積を縮小し、マリーナを掘り込み型に する) | 埋立予定地近傍に人工干潟を造成 |
| 実施方法 | 事業計画の軽微な変更 | 人工干潟の造成計画の立案及び実施 |
| 実施主体 | 事業者 | 事業者 |
| 措置の不確実性の程度 | 特になし | 環境保全措置の実施による効果の程度(人工干潟の造成による効果) |
| 措置の実施に伴 い生じるおそれのある環境影響 | 特になし | 人工干潟の造成に伴う浅海域の消失 |
| 措置を講ずるにもかかわらず存在する環境影響 | 特になし | 特になし |
4 評価
現計画と修正案2との比較を含めた評価は以下のとおりとなる。
- スコーピング段階で収集された情報に基づき設定した保全方針を踏まえ、現計画に対する予測の結果、注目種としてあげたアサリ(典型性)、イシガレイ(上位性)については生息域の消失により個体群が減少する可能性があること、注目種及び重要な機能としてあげたアマモ(場)については流速が変化することにより生息域に影響が及ぶと考え られること、重要な機能を有する干潟については干潟の消失により浄化量(窒素換算)が減少することが予測されたことから、環境保全措置を講じた修正案を検討した。
- 事業実施区域の縮小する(マリーナを掘り込み型する)ことで、現況と比較して流動(流速)がほとんど変化しないことから、アマモ場への影響はほとんどないと判断した。また、イシガレイの産卵場や育成場等の分布範囲や生息範囲の消失面積が減少することか ら、イシガレイへの影響は低減することができると判断した。
- アサリとイシガレイへの影響及び消失する干潟に対する代償措置である人工干潟の造成にあたっては、消失する干潟の粒度組成や造成場所の流動や波浪等を踏まえ、最新の研究結果や調査結果及び学識者等による検討会を実施することより、消失する干潟と同程度の状況(場としての機能や物質循環機能)になるよう計画し、実施する。
5 事後調査
5-1 事後調査実施案
事後調査の実施案は表6に示すとおりである。
表6 事後調査の実施案
| 環境保全措置の内容 | 事業実施区域の変更(埋立面積を縮小し、マリーナを掘り込み型にする) | 埋立予定地近傍に人工干潟を造成 |
| 調査項目及び調査内容 | 調査地域内の状況
|
造成した人工干潟とその周辺の状況
|
| 調査範囲 | 調査地域内全域(現地調査と同様) | 造成した人工干潟とその周辺 |
| 調査実施時期 |
|
|
| 調査方法 | 現地調査の方法と同様とする。 | |
| 調査結果の取り扱い | 調査結果の公開及びインターネットによる公表 | |
| 不測の場合の対処方法 | 不測の状況になった原因を調査し、その原因による影響を回避、低減(場合によっては代償)する環境保全措置を計画・実施する。 | |
| 実施体制 | 事業者 | 事業者 |
5-2 事後調査報告
事後調査報告例は表7に示すとおりである。
表7(1) 事後調査報告(埋立地存在後○年目)例
| 環境保全措置の内容 | 事業実施区域の変更(埋立面積を縮小し、マリーナを掘り込み型にする) | ||
| 調査項目 | 水質、底質、流動、波浪 | アマモ場の生育状況 | アマモ場での仔稚魚の出現状況 |
| 効果の確認 | 水質について、存在前 から存在後○年間、COD は4mg/l前後、SSは5mg/l前後、T-Nは1.0mg/l 程度、T-Pは0.1mg/l程度と大きな変化が見られない。 底質について、残存干 潟や浅海域での粒度組 成は存在前と比較して 大きな変化はなく、埋 立地周辺において土砂 の堆積傾向は見られな かった。 流動について、干潟前 面の海域では、東から 西への流向が卓越して おり、流速も4cm/s前 後であり、存在前と大 きな変化は見られなか った。 | 生育環境の変化はな く、分布範囲もほとん ど変化していなかった。 しかし、平均被度は存 在前が約60%であった のに対し、存在後△年 目に約50%と低下した が、その後は60%前後 まで回復した。 | 存在前と同様に、存 在後○年間において、 仔稚魚で確認された種 はメバル、クロダイが 多く確認され、葉上生 物も小型甲殻類が多く 確認された。 |
| 追加措置 | 特になし | 特になし | 特になし |
| 今後の対応 | 特になし | この平均被度の低下 は、自然変動の範囲で あると考えられること から、今後の対応は不 要と判断した。 | 特になし |
| 今後の事後 | - | - | - |
表7(2) 事後調査報告(埋立地存在後5年目)例
| 環境保全措置 の内容 | 埋立予定地近傍に人工干潟を造成 | |
| 調査項目 | 粒度組成、勾配、流動、波浪、水質、 底質 | 底生生物、卵、仔稚魚、魚介類 |
| 効果の確認 | 人工干潟の粒度組成について、消 失する干潟と同様な粒度組成(砂分 80%、シルト・粘土分20%)で造 成した。造成後○年間の粒度組成は、 砂分70~80%、シルト・粘土分20 ~30%であり、人工干潟東側でシ ルト・粘土分が多くなってきたこと が確認された。 人工干潟の勾配について、造成後 ○年間において、勾配の変化もみら れなかった。 流動について、対象となる海域で は、東から南西への流向が卓越して おり、流速も4cm/s前後であり、存 在前と大きな変化は見られなかっ た。また、波浪についても同様に、 造成前と比較して大きな変化は認め られなかった。 水質について、存在前から存在後 ○年間、CODは4mg/l前後、SSは5 mg/l前後、T-Nは1.0mg/l程度、T-P は0.1mg/l程度と大きな変化が見ら れない。 底質について、人工干潟前面の底 質の粒度組成は、造成後○年間大き な変化を認められなかった。 | 注目種であるアサリについて、造 成後1年目は10個体/0.1m2であっ たが、年々増加し造成後○年目には 25個体/0.1m2まで増加したことが 認められた。底生生物についても同 様に出現種数、個体数とも年々増加 傾向はみられるものの、消失した干 潟の出現種数、個体数には及ばない ことが認められた。 注目種であるイシガレイについ て、造成した干潟前面を産卵場や育 成場として利用していることが認め られた。他の魚介類の卵や仔稚魚も 確認され、消失した干潟の前面同様、 多種の魚介類に利用されていること が認められた。干潟の浄化量もアサ リを含む底生生物が増加したため、 浄化量も年々増加したものの造成後 ○年目で16kgN/日であり、消失し た干潟(25kgN/日)の浄化量には及 ばないことが認められた。 |
| 追加措置 | 特になし | 特になし |
| 今後の対応と 事後調査計画 | 人工干潟の粒度組成等の安定性が確認されていないこと、生物の生息状 況及び浄化量が消失した干潟と同程度の状況まで回復していないことが 認められたことから、学識経験者による検討会を開き、今後の追加措置 を念頭に置き、生物多様な人工干潟(消失した干潟と同程度の状況)の 検討及び検討を踏まえた今後の事後調査計画の見直しを行う。 | |